 |
ナマズ腹口吸虫Parabucephalopsis
parasiluriの感染被害をうけたオイカワ (2007年1月,大阪府淀川) 本種による宇治川・淀川での魚病被害は1999年12月頃に始まり,翌年に原因は吸虫メタセルカリアの大量寄生によるものであることがわかりました(浦部 ほか,2001; Ogawa et al., 2004)。この魚病は現在までのところ宇治川・淀川のみで発生していますが,重篤さの程度は年によって異なり,ほとんど病魚が出ない年もあります。写真 はかなり重篤な魚で,目と尾びれに出血が見られます。この病気は直接魚を死に至らしめることはなく,後に回復する魚もいるようですが,重症魚では泳ぎ方 が弱々しくなり,タモなどで簡単に捕獲できます。 この寄生虫にはアユを除いてほとんどの魚が感染しますが,重症になるのはオイカワとコウライモロコの2種です(Ogawa, et al., 2004; Urabe, et al. 2007)。なお,人や哺乳類,鳥類には感染しません。 |
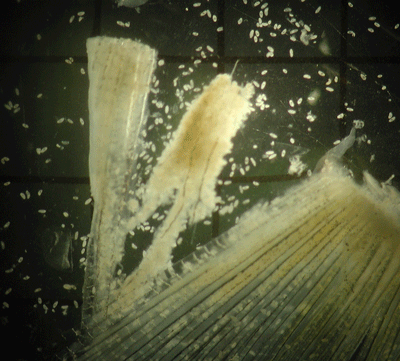 |
ナマズ腹口吸虫Parabucephalopsis
parasiluriの感染被害をうけたオイカワ (2007年1月,大阪府淀川:ホルマリン固定標本) 上段のような重症魚の尾を切ってみると,このような状態です。白い米粒のようなものが寄生虫で,多い場合には1個体のオイカワの尾に3000以上,全身 では10000近く寄生します。この密度の高さによって魚の体組織が損傷し,出血などを起こすようです。 魚の吸虫類で,宿主に病害性のある種は少ないのですが,腹口吸虫の仲間は,自然状態でも時々重篤感染を起こすことが知られています。 |
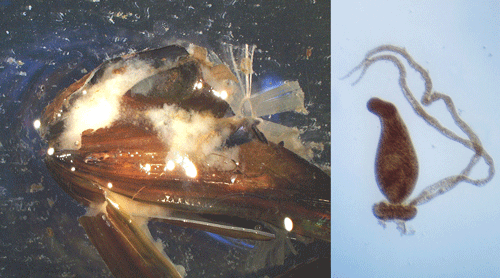 |
ナマズ腹口吸虫Parabucephalopsis
parasiluriのセルカリア (2000年11月,京都府宇治川:右,鉄ヘマトキシリン染色標本) この寄生虫の第一中間宿主は特定外来生物のカワヒバリガイで,おそらく宿主と共に持ち込まれたものと思われます。本種に限って言えば,終宿主はビワコオオ ナマズ1種だけなので,琵琶湖・淀川水系以外に広がる可能性は低いと言えますが,原産地には本種以外にもカワヒバリガイを中間宿主とする寄生虫が何種かい ます。それらが引き続き持ち込まれる可能性を防ぐため,カワヒバリガイの新たな移入には今後も注意を継続する必要があります。 |