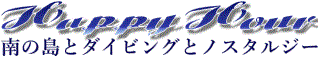Analogue record player
Technics SL-1600
 |
最初のステレオを買ってもらう前、足繁く通ったデパートの電気フロアの一角に展示されていたSL-1600、こんな感じだったでしょうか…。
 |
YOU-OZのプレーヤーより一段高級な感じ、何よりストロボライトの美しさにすっかり魅了されてしまいました。オーディオは見た目重視です。他の機器は「1977」で書いたとおり実機の音はおろか見た目の印象すらない状態で買ってしまいましたが、SL-1600だけはこの美しさの印象で購入しました。
 |
モーターのローターとターンテーブルが一体になった、D.D.(DirectDrive)方式の回転系、フルオートマチック機構、ジンバルサスペンション方式のユニバーサルトーンアーム等々テクニクスの技術がてんこ盛りです。
 |
モーターベース部、コイルが見えます。
 |
ターンテーブルと磁石が一体になっています。子どもの時に作ったモーターキットはコイルの方が回転しましたが、こちらは磁石の方が回転するんですね。
 |
使用前のセッティング、まずは針圧調整です。カートリッジを取り付けたらトーンアーム後方のウエイトを回して、アームが水平に釣り合う位置を探ります。次にメモリのリング部分だけを回して「0」に合わせます。その後、ウエイト全体を回して適正針圧の目盛りに合わせます。ちなみにメモリの単位は「g」です。この針圧も重め、軽めで音が変わりました。次は「アンチスケーティング」の調整です。レコードは回転して再生するので、そこに乗っているレコード針には遠心力で外側に引っ張る力がかかります。すると針の外側に力が偏ってしまい、左右の音が正しく再生されないので針の内外(音の左右)のバランスをとるために内側に引っ張る力をかけるために、針圧と同じ値にトーンアームベースにあるダイヤルの目盛りを合わせます。ちなみに手前にあるレバーは、針(トーンアーム)を上げ下げするためのものです。
 |
針圧調整が終わったらターンテーブルの回転の調整です。33/45回転を切り替え、それぞれのつまみを回して、東日本ならターンテーブル外周の50Hzのドットが止まって見えるように調整します。なので、ピッチを上げたり下げたりして再生することもできました。何度も言いますが、プリズム状にカットされたストロボライトが美しい~。
これで使用準備OKです。SL-1600の次に買ったQL-Y33Fではモーターがクオーツロックになったので回転数の調整は必要なくなりました。そしてCDになり針圧調整がレーザーの出力調整に…必要ありません。PCオーディオ、ネットワークオーディオになりディスクをセットすることすら必要なくなりました。これを便利になったというべきか…、昭和のおじさんにとっては「メカ」が感じられない、音の記録されている「物体」がない、音の出る仕組みが今ひとつ実感できなくなったのは、つまらないな~と感じてしまいます、音の良し悪しとは直接関係ないんですがね。
 |
SL-1600はフルオートメカを搭載しているので、真ん中のダイヤルをレコードの径に合わせてから下のレバーを「START」にすると、自動的にターンテーブルが回り出し針を正しいスタート位置に運んで下ろしてくれました。演奏が終わると自動的にトーンアームを元の位置に戻して、ターンテーブルが止まります。上のダイヤルは繰り返し再生用で、1~6&無限回数の設定ができました。もちろんマニュアルで好きな位置から再生することもできます。
 |
トーンアームの先にはレコードの溝に刻まれた振動を針で拾って電気信号に変えるカートリッジとそれを取り付けるシェルが付いてます。シェルとカートリッジは簡単に交換できるので、違うカートリッジやシェルに交換して音の違いを楽しむことができました。SL-1600には270Cというカートリッジが標準でついていました。音の振動を電気信号に変える方式はMM(moving magnet)とMC(moving coil)がありそれぞれ特徴がありましたが、270CはMM方式でした。写真左の緑色の部品を引っ張ると針が外れて交換ができます。右の写真はカートリッジからトーンアームに電気信号を送るリード線です。この細くて短いリード線を変えることで音が変わるといわれ、様々な製品が売られていました。つなぎ時も線をツイストさせると音がクリアーになるなんて話もあり、レコードプレーヤーだけでもいくらでもこだわることができました(ターンテーブルとレコード盤を密着させるための真空ポンプなんてものもあったなぁ~)。
 |
レコード針の材質はダイアモンドです。CDの音を拾うためのレーザーはルビーが使われています。ルビーよりダイアモンドの方が高価です。だからCDよりアナログレコードの方が音がいいんです、知らんけど。さて冗談はさておき、この針で塩ビでできたレコードの溝をこすりながら音を出すのですが、ダイアモンドでできた針がこすられて摩耗していきます。なので、一定の時間使用したら新しい針と交換しなければいけません。この先端についている針の形もマニアの心をくすぐる技術の進歩がありました。通常の針はとがった方から見て丸い形をしています。でもレコードの溝を掘るカッティングマシンの刃は薄い鋭角の形なので、細かい振動の溝の部分では丸い針が浮いてしまい正確なトレースができません。そこで針の形を楕円にすることでより刃で掘った溝に合うようにしたのが楕円針です。270Cは交換用に丸針と楕円針が選べ、楕円の方がお高くなっていました。ちなみに一つ上の写真の赤線は楕円針の印です(丸針は白色)。その後の製品では「ラインコンタクト針」という楕円の両先端をさらに少し飛び出た形にカットされた針が登場し、より溝の形に密着できるようになりました。それにしてもこんなに小さい針を楕円やそのさらに先端だけ飛び出した形に加工するなんてオーディオ技術に対する熱量を感じます。
SL-1600はQL-Y33Fの購入とともに引退しましたが、QL-Y33Fはかなり前に壊れて廃棄してしまい、今再びアナログレコードを聴くためにSL-1600を復活させようと考えています。
QL-Y33F
準備中