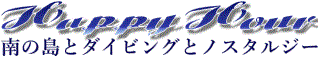1977
趣味のオーディオのはじまり
街の電気屋さん
子どもの頃、街には個人経営の電気屋さんがたくさんありました。基本的には特定のメーカーの看板を上げていて、そのメーカーの製品だけを売っていました。うちは、東京芝浦電気(TOSHIBA)と松下電器産業(National/Panasonic)のお店と付き合いがあって、家には両メーカーの製品が混在してありました。そして、各メーカーが「春の電気祭り」などと銘打って街の大きい会場を借りて、個人電気店が出店して、展示商談会を開くという恒例行事がありました。付き合いのある電気店から招待はがきが届き、来場記念品をもらいに、新しい電気製品を見に、ワクワクしながら出かけていきました。そう、あの頃は、定期的に行われる電気祭りは、まさにお祭りのようなイベントだったのです。
中学生になると「オーディオ」というものに興味が出てきて、電気祭りではオーディオ製品を目当てにいくようになりました。その頃は「音」ではなく「機械」としてのオーディオへの興味だったと思います。当時は、TOSHIBAはAUREX、NationalはTECHNICS、他のメーカーもオーディオ製品は独自のブランドネームがあって、子ども心にはそれがとてもかっこよく映っていました。そして、オーディオ(当時の認識はステレオ)は憧れの製品でした。
行動範囲が広がってくると、中心街にある百貨店/デパートが遊び場になり、いろいろなメーカーのオーディオ製品がいつでも見られることもあり、電気のフロアに入り浸っていました。テレビではいろいろなオーディオのCMが流れ、80年代のオーディオ全盛期に向けて活気のあるときでした。このとき「コンポ」という単語が耳につくようになり、「コンポって何だ?」となったわけです。
「コンポ」それは「立った、立った、コンポが立った、コンポのYOU-OZ~♪」というCMソングとともに私の頭に入ってきた単語でした。私の家にはありませんでしたが、お金持ちが買う当時の「ステレオ」は、レコードプレーヤー、レシーバー、スピーカーが一体の家具のようになったものでしたが、プレーヤー、アンプなどがそれぞれ独立した製品になっており、それらを同じメーカーの同じラインナップでそろえるのが「コンポ」?、よくわかりませんが、とにかくYOU-OZが気になり、デパートで(演出のために)やや薄暗いコーナーに展示されている実機、黒いパネルにメーター類の麦球のオレンジの光とプレーヤーの回転ピッチ調整のためのストロボライトがとてもきれいで、もうこれがほしい!となってしまいました。選択基準は「音」じゃないんです、「見た目」「イメージ」なんです。そして、そのメーカーはテクニクス、おー、ナショナルだ、近所の電気屋さんのメーカーだ、親に頼んで買ってもらおう!もちろん、あっけなく却下されました。
 |
1977
そこで交換条件です。高校受験を頑張って無事志望校に合格したらステレオを買ってもらう、という約束を母親と半ば無理矢理取り付けました。そして1977年、志望校に合格、無事入学しました。
「約束だから」と勝手にナショナルのお店に行って、デパートで手に入れたカタログからお目当てのアンプ、プレーヤーなどを指さしながら「これがほしいんだけど…」、そのときのおじさんの一言、「あー、それはもう売っていないな」、それはちょっと前のカタログでした。「今売っているのはこれだよ」最新のカタログを見せられました。ほしかったものと当然デザインが違っており(当時は見た目重視だったもので)、正直ちょっと迷いました。でもここで持ち帰ったら「待った」がかかるのは必至です。そのカタログから適当に注文してしまいました。世間知らずの少年です。音も聞かず、値段もあまり気にせず、勧められるままにいらなそうなものまで注文してしまいました。
レコードプレーヤー SL-1600(\49,800)、プリメインアンプ SU-7700(\45,800)、スピーカー SB-1770(\41,800×2)、チューナー ST-7300(\29,800)、カセットデッキ RS-670U(\89,800)、オーディオタイマー SH-4040(\20,000)、マイクミキシングアンプ SH-3035(\18,000)、オーディオパワーセレクター WZ9700(\17,500)、マイクロフォン RP-3540E(7,800)、それにヘッドホンやラックも合わせて40万円近く!その後おっちゃんが家に来て母親と話をしましたが、すでに息子が勝手に注文してしまったので強くもでられず、やっと1割負けさせるのが精一杯で、後でしこたま怒られたことはいうまでもありません。
ものがわかるようになってから、このときどのように交渉して買えばよかったのか、そして、当時小さい事務所に勤めていた母親の給料が、月10万少々だったことを知り、親のありがたみやお金の大切さを身にしみて感じ、今後高額商品を買うときはよーく考えてから買うことを心に刻みつけました。
そうして6畳の部屋に鎮座した我が家の初めてのコンポは横置き、今までの卓上レコードプレーヤーに比べれば格段にいい音になりました。お母さんに買ってもらったステレオで聞くのは、当時のアイドル歌謡、お母さん、ゴメンナサイm(__)m
かくして私のオーディオ趣味が始まりました。好きな歌手のレコードをお小遣いを貯めて買って聞きますが、そんなにお金がないのでFMエアチェックでカセットテープに録音して聞く、土曜日の半日授業が終わってダッシュで家に帰って「コーセー歌謡ベストテン」を聞く、NHK FMはよく昼にアイドルのアルバムを丸々流してくれる番組があったので、タイマーで録音する、そのうち歌謡曲以外の音楽にも興味が広がっていきました。そしてFMファンなどの雑誌からオーディオに関する知識も貯まっていきました。バブルに向けた、オーディオ全盛期の始まりでもありました。
オーディオタイマー SH-4040 オーディオパワーセレクター WZ9700 マイクミキシングアンプ SH-3035
他で紹介できない機器をここでちょっと書いておきます。
 |
まずはオーディオタイマー、FMエアチェックに活躍してくれ、目覚まし時計代わりにも使っていました。当時アナログ式とデジタル式があり、アナログ式の方がタイマーセットの方法が簡単で、融通が利いたらしいのですが、デジタルだと薄くなってラックに入れやすく、他の機器と合わせやすいのと表示部の緑色がきれいなのとでこれを選びました。1日1回、指定した時刻から1時間または2時間通電するといった機能でした。
今でも、このタイマーだけはAVラックに入って時刻表示だけしてくれています。給料の3ヶ月分もつぎ込んでバカ息子にステレオを買ってくれた母への感謝を忘れないように…。
 |
次はオーディオパワーセレクター(写真上)です。[LISTENINGのPHONOのMANUAL]のボタンを押すとプレーヤーとアンプの電源がワンタッチで入れられる、[RECORDINGのFM/AMのAUTO]のボタンでタイマーと連動して自動でチューナーとアンプの電源のON/OFFができる、[SLEEP]のボタンを使えば聞いているソースの電源がダイヤルで60分まで自由に指定した時間で切れる、といったものでした。
背面に各機器をつなぐコンセントの差し込み口があり、各機器の電源スイッチは入れっぱなしにしておくことで必要な機器に電気を供給するといった仕組みですが、クリーン電源でもパワーサプライでもなく、ただのスイッチャーです。つまり、このパワーセレクタの細い電源コード1本から各機器へ電気を供給(しかもタイマーも経由して)することになるので、電源やケーブルの沼にはまっているマニアには気が狂わんばかりの仕様となっております。
でも少年だった私には、この機能が、LEDの光がかっこよかったんです。この機械必要?と聞かれればたぶん…いえ、全く必要ありませんでした。でもほしかったんです、友達にも自慢できるし。お値段17,500円也、お母さん、ゴメンナサイm(__)m
もう一つはマイクミキシングアンプ(写真下)です。面白そうなのと、3台そろえるとアンプやチューナーと同じ高さになるので、ラックへの収まりがよくなるので買ってしまいました。お母さん、ゴメンナサイ。特徴?はエコーがかけられるのですが、中をのぞいてみるとバネが2本、それが震えることでエコーというかリバーブがかかる仕組みでした。「ウワン、ウワン~」といったアナログらしい味のあるエコーでした。結局、高校で始めたギターもすぐに挫折して、歌を録音するといった壮大な計画はあっけなく頓挫して、大学に入ってから音楽をやっている友達にあげてしまいました。とても喜んでいたよ…。