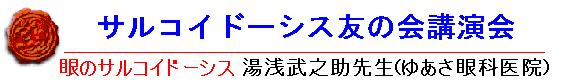
| ||||
| ||||
| サルコイドーシスによる眼に起こる変化 | ||||
|
1.基本的な変化
サルコイドーシスでは,約 2/3〜3/4 の人に眼の症状として, ぶどう膜炎や網膜静脈炎が出現します。多くは両眼に起こりますが, 一部には片眼だけの人もあります。ぶどう膜には肉芽腫ができて炎症が起こり, その部分のぶどう膜や網膜を破壊します。
炎症の程度がごく軽い人以外では,炎症の程度に応じて硝子体混濁が起こります。
このために視野に「ほこり」や「虫」のような黒いものが見えるほか,
混濁の程度が強いと,眼がかすみ,視力が低下します。
炎症が強かったり,長い間炎症が続くと、網膜のうちでもっとも視力のよい部分
である「黄斑」に浮腫(はれること) が起こり,浮腫が続くと黄斑が障害されて,
視力が回復しなくなります。
2.病気の経過
しかし,いつまでもこれらの炎症がなくならない場合(慢性)や,
薬をへらしたり中止したりすると,すぐに炎症が強くなる場合もあります。
ふだんは炎症がおさまっていても,数ヵ月に1回程度炎症が出現(再発)
することもあります。
治療が不十分であると, ぶどう膜に新しい肉芽腫が次々と出現して,
網膜の障害も拡大してゆきます。同時に,緑内障,白内障,網膜の障害など,
さまざまな合併症が起こり,視力が非常に低下し,ときには失明することもあります。
| ||||
| 壮年期から初老期のサルコイドーシス | ||||
|
最近とくに壮年期から初老期の人のサルコイドーシスが増加しています。
50歳から70歳ででは,女性の患者さんが多く,男性は女性の1/4〜1/5程度です。
通常は両眼に起こりますが, ときには眼の炎症の程度で左右差の大きい人や,
片眼は正常の人もあります。
眼底に, 直径 1mm以下の小さな斑点状の炎症のある部分(肉芽腫)
がたくさんできます。このような炎症のある部分は眼底のごく一部に限られている
人から, かなり広い範囲に及ぶ人まで, さまざまです。炎症のある範囲が広いほど
病気は重症で, 重症の人では早く強力な治療をしないと視力の回復が困難になります。
治療により, 炎症は徐々におさまって行きますが, 治療が不足すると次々に新しい
炎症病巣(えんしょう びょうそう, 肉芽腫のこと)が出現して眼底全体に分布し,
視力は非常に低下します。
一般に炎症は慢性で治療しても完治しない人が多く,数年にわたって
ぶどう膜炎が続くことも珍しくありません。虹彩や毛様体の炎症は軽いので,
眼圧が上がることは少ないようですが油断は禁物です。炎症が比較的軽く,
治療がよく効(き) いた場合には,治療によって数ヵ月から1年前後で炎症が
おさまってしまいます。
| ||||
| 緑内障には要注意 | ||||
|
眼のサルコイドーシスでは, 炎症が起こっていても ごく軽度の場合には,
その徴候が患者さんにはほとんど気づかれないことがあります。このような状態で
眼圧が上がってきても,眼圧が25〜30mmHg程度では「眼や頭が重い・痛い」
「見え方がおかしい」「少し見えにくい」などの異常を感ないことも多く,
知らぬ間に視野が欠けはじめて「緑内障」になっていることがあります。
緑内障と診断されてから, サルコイドーシスにかかっていることがわかることもあります。
したがって, いったんサルコイドーシスと診断されたら, 炎症が長期間
おさまっていることを医師が保証してくれる場合以外は, 症状に応じて一定の間隔
(1〜3ヵ月に1回程度)で眼科医の診察を受け, 眼圧を測定してもらうことが,
緑内障にならないための対策です。緑内障のために失われた視野は,
ふたたび取り戻すことができません。
| ||||
| サルコイドーシスと診断するには | ||||
|
1.からだの変化から
この病気では,肺門(気管支や太い血管が肺に出入りする部分, 肺の入口にあたり,胸の中央部で胸骨の後側にある)のリンパ節が腫(は)れて大きくなる ことが しばしばあり,胸部のレントゲン 撮影や,CT検査でこのような変化があることが わかれば,この病気の可能性が高くなります。
結核の診断に使用されるツベルクリン反応が陰性になりやすいのも,
この病気の特徴です。この病気では, 放射性同位元素の「ガリウム65」を体内に入れると,
これが異常のある肺やリンパ節に集まることも知られています。
血液中のアンギオテンシン変換酵素(ACE),リゾチーム(酵素の一種),
ガンマーグロブリン (細菌などを処理するための蛋白)の値が高くなっていると,
この病気が疑われます。
この病気の確定診断には,患者さんの体から異常のある組織(リンパ節, 肺, 皮膚など)
を少しだけ取ってきて,その組織を顕微鏡で観察し, サルコイドーシス特有の変化を
見つけることが必要です。また気管支や肺のなかを洗浄した液から細胞を集めて
診断を決定することもあります。
2.眼の変化から
| ||||
| 眼のサルコイドーシスに対する治療 | ||||
|
1.ステロイド薬の服用
ぶどう膜炎(虹彩毛様体炎)や網膜静脈炎が軽いときは,点眼薬だけで治療するのが普通です。 しかし眼底 (網膜, 脈絡膜) または視神経に炎症がある場合, 硝子体混濁が強く視力が低下している 場合,眼圧が高い場合などでは, 数ヵ月,ときには数年にわたるステロイド薬(プレドニン) の内服が必要です。
この薬を使用しないと,硝子体混濁が吸収されなくなったり,眼のなかで線維の増殖が
起こって網膜を障害したり,網膜の黄斑に浮腫が続くと網膜が障害されて視力が低下します。
また炎症が続くと緑内障が起こりやすくなるので,炎症があまり強くならないようにする
必要があります。炎症が軽くても,眼圧が上がる人はステロイド薬の内服が必要なことがあります。
プレドニンは治療開始後しばらく毎日内服して頂きますが,長期の服用が必要な場合には,
炎症が軽くなれば副作用を少なくするため1日おきに朝だけ内服します。
そのほか,炎症をおさえるために,比較的副作用の少ない薬を併用することがあります。
この病気では,一般にステロイド薬の内服による治療で 十分な効果が得られることが多く,
炎症が非常におさまりにくい人は少数です。約3か月くらい内服薬を使用すると,ぶどう膜炎は
かなり軽くなる人も多いのですが,炎症が慢性化していて薬をへらすと炎症がすぐに強くなる人や,
再発を繰り返す人も珍しくありません。
2.気長に通院・治療を
3.眼以外の症状と治療
からだの症状も次第に変化してゆきますので,特別な自覚症状はなくても1〜2年に
1回は体の検査(血液検査,レントゲン撮影など)を受けて,からだに新しい問題や
治療の副作用が起こっていないかどうかを調べておくのもよい方法です。
眼以外の異常が疑われるとき,または患者さんのご希望のあるときには,必要に応じて検査を行い,
また内科に紹介します。
| ||||
|
| ||||
|

