ホーム >
書評:『人生と陽明学』
この記事の最終更新日:2006年9月24日
| 人生と陽明学 | |
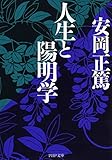 | 安岡 正篤 PHP研究所 2002-06 Amazonで詳しく見るby G-Tools 関連商品 論語に学ぶ 人間としての成長―東洋の古典から何をいかに学ぶか 活学としての東洋思想―人はいかに生きるべきか 人生の五計 困難な時代を生き抜く「しるべ」 日本の伝統精神―この国はいかに進むべきか |
日本の政財界に大きな影響を与えた陽明学者、安岡正篤の講話の中から、陽明学に関するものを集めたものです。特に陽明学が日本に伝来してからの、徳川時代、幕末の陽明学者の活躍に、強く心を惹かれました。
陽明学は「知行合一」の学問であり、孔子の教えの中でも、とりわけ自己修養を尊びます。
「大きなことを言うからといって、それがその人の本当の人物かというと、全くそうではない。言論・主張等というものはその人の真価・実質と関係なく、誰にも言えることであります。従ってそういうことよりも、自分の関係しておる、例えば、一つの家庭を治めるというようなことの方が、或いは己の身を修めるということの方が、はるかに難しいのであります。人間の真価はなんでもない小事に現われる。」(p138)
幕末の人の活躍を見ると、驚愕するものがありますが、そこには陽明学の教えが脈々と流れていると気づきました。
「当時の人はよく書を読んでいる。それも、人格を練る、識見を養うという様な立派な修養の書物ばかりである。われわれのような知識だとか、娯楽だとかの本ばかり読むのとは大変な違いである」(p142)
上記は安岡先生が聞いた牧野伸顕伯(大久保利通の次男)の言葉です。
陽明学的な観点からみた現代教育の問題点を、著者は鋭く指摘しています。
「人間をつくる、自己をつくるといことが、なんといっても学問・教育の一番根本的な意義でありますが、その学問・教育も、現代はやはり形は栄えておるようで、内容はだんだんとなくなって、単なる機械的知識技術に堕しつつある。(…)もっと誰にも分かる現象を申しますと、今日の一般学問・教育というものは、殆ど学校教育になって、自己教育とか家庭教育とかいうものがなくなってしまいました。人間の魂と魂が触れ合って、火花を散らすような個人教育・人間教育などというものがなくなってしまって、何千何万という厖大な学生を収容する大組織の学校をつくって……」
エリートのあいつぐ汚職、アンモラル、一般的不人気は、人間教育の欠如のためでしょう。