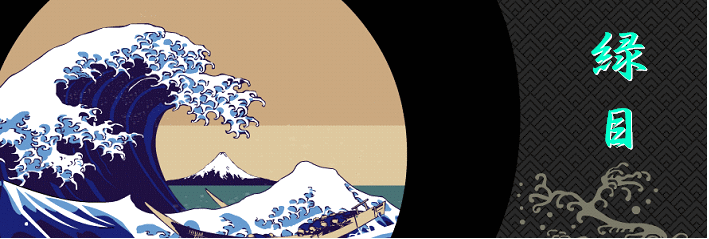
『緑目』 二00二年一月十二日 二00六年三月二十一日(改) 九谷 六口
|
空には細い三日月が懸かり、星が瞬いている。静かに凪いだ海面にいくつかの波が立ち、浜辺に向かって動き出した。
その男は、海から上がってきた。 体から滴り落ちる海水。髪の毛は長く伸ばし、頭の後ろで束ねている。痩せてはいるが、無駄の無い筋肉質な体。月明かりに照らされた姿は、全身バネのような感じである。七分袖の半被をまとい、革で出来た紐で腰を縛っている。太股までしかない股引を穿き、腕には手甲、脛には脚袢を着けている。彼は裸足だった。背中を見ると長い刀を背負っている。異様なのは目。緑色に輝いていた。 男は浜に上がると急に腰を曲げた。そして膝を付いたかと思うと、苦しそうに咳き込み、大量の海水を吐き出した。しばしの間じっとしていたが、スックと立ち上がり、二、三度大きな深呼吸をした。まだ濡れている体を月が照らした。 手甲も脚袢も白く光り、鮫皮でできていることが判る。鮫皮は、頭から尻尾の方に撫ぜると滑らかだが、逆に撫ぜると手の皮が剥けるほどささくれ立っている。この男は手首から肘の方に、足首から膝の方に順目が来るように着けていた。組み合った時、この腕や足を引けば相手を傷つけることができる。 浜に上がってきたのはこの男だけではなかった。辺りから幾つもの咳き込む声が聞こえてくる。月の光に浮かび上がった男たちは、総勢十五名。体付き、出で立ちを見れば、明らかに戦いを生業とする屈強な者たちであることが判る。しかし、中には深く傷ついたためか立ち上がることができない者もいた。 二人ほどが浜辺にうずくまり、じっとしていた。近くにいた者が声を掛けた。くぐもった甲高い声。二人は首を横に振った。刹那、声を掛けた者がこの男たちを斬り捨てた。二人が死んだ。男たちはこの二人を肩に担ぎ、陸の方に歩いていった。そして、深い穴を掘り、二人を埋めはじめた。別に手を合わせるでもなく、作業は淡々 |
(1)
|
と進められた。話し声は、全く聞こえない。埋葬し終わった彼らは、二人の刀を持ち、さらに陸地の奥へと消えていった。
浜辺から幾分奥まった処にある集落。四、五十人の民が長の周りに集っていた。長の名前は、モンダと言った。モンダが民に向かって叫んだ。 「皆の衆! どうしようもないのだ。判ってくれ! ダビル王は、倍の年貢を納めろと言っている。逆らう事はできん!」 「何を言っているだ! これ以上は無理だ! 今だって、ほとんどの作物を差し出しているではないか。我らは、何を食べればよいのだっ!」 「年貢を増やさないように頼む事はできる。だが、抵抗すればその場で殺される。他の者が逆らえば、その者も殺される。集落の民が減っていくだけだ。判ってくれ、何とか年貢を収めてくれ!」 多くの者が諦め顔でその場を去っていった。二人の男がモンダに言った。 「無理だっ! これ以上とられたら、我々は餓死する以外にない」 翌朝、一人の男の溺死体が浜に打ち上げられた。身を投げたのだ。そして、もう一人は、どこかへ逃げていった。 まだ、石器、土器しか知らない時代。 王と呼ばれる者が出現するまでは、ワノナ国は平和な国であった。集落ができ上がり、山の民、野の民、海の民が、それぞれの地域で採取した食べ物を物々交換することを覚え、野の民は、穀物や野菜を栽培することを覚えた時代である。 集落ごとに自然と長が決められた。民は長を慕い、判断がつかないことが起こると相談し解決していた。争いなどはなかった。 平和な時代が続き、食べ物などの採取、栽培の方法も改良されてくると、民の間に余裕が生まれてきた。中には、子供を沢山産み、血族を増やす者もでてきた。そして、このような家族は集落の中で |
(2)
|
も発言力を高めていった。家族の頭は、自らは働かず指示に徹するようになっていた。
今までの長は、合議制のような形で決められたが、血族集団の頭が集落の長に治まるようになった。このような長は、今までの長とは違っていた。物事を判断する場合、身内を優先した。当然、その判断に納得できず、不満を言う者も増えてきた。長にとり、不満を言う連中の存在は邪魔でしかなかった。しかし、彼らを大人しくさせるのは簡単であった。家族を引き連れ、殴りつければ済んだ。この方法を使えば誰もが黙ってしまった。 ある集落の長、ダビルは考えた。 ―― 何も、我が家族が働く必要などないのではないか。 ダビルは、体力のある者を集め出した。 「良いな、体力、腕力を付けろ。殴り合いに勝てるような体を作れ。自分で食べ物を採ったり作ったりせんでも良い。食い物は俺が与える。そのかわりに俺の言うことを聞けっ!」 石器は穀物を採ったり、魚や獣を獲ったり捌いたりするために作られたが、ダビルは、武器として使うことを思いついた。 ―― 簡単なことだ。民を脅せば食べ物を持ってくる。 ダビルの周りには、武器を持った集団ができ上がっていった。だが、ダビルは自分の集落を治めるだけでは満足できなくなっていた。 ―― もっと大勢を支配したい。 そこで、他の集落に兵隊を連れていった。ダビルたちよりも人数が多い集落もあったが、ダビルの兵隊に立ち向かう事はできなかった。人数は多いが、彼らは戦い方を知らないのだ。 ダビルは幾つもの集落を支配していった。海の集落、山の集落、野の集落。 立派な藁葺きの建物。ダビルの館の前に大勢の村人が平伏している。ダビルが両脇に武器を持った兵士を並べ、大きな石の上に立っ |
(3)
|
て叫んだ。
「良いな! これからは、俺をダビル王と呼べッ!」 ダビルは、幾つもの集落に自分の家族を長として赴任させた。しかし、幾つもある集落を支配する為には、家族だけでは人数が足りなかった。そこで兵隊の中で知恵が働く者を選び、集落の長として任じていった。それでも足りない場合、ダビルは一つ一つの集落に足を運び長を選んだ。自分に靡く長は、そのままその集落の長とした。靡かない場合は、自分の家族、または兵隊上がりの者を長として置いた。 そして、ダビルはワノナ国全体を支配していった。年貢の取り立ては厳しいものだった。 モンダの集落では自殺者、逃亡者が増えていた。ダビルにとり、モンダは使いやすい長であったが、このような状態を招いたモンダに罰を与える必要があった。さもなければ他の長に示しがつかない。だが、モンダは命じた通りの年貢を納めていた。さすがに殺す訳にはいかない。そこで、モンダをただの民に戻し、兵隊上がりの部下を長として置いた。 幾つもの集落で自殺者、逃亡者が出てきた。 ダビルは、実に不愉快であった。民の数は、年貢の量に関係する。そこで、お触れを出した。 『集落にある三家族を一つの組とする。組の中から一人でも自殺者、逃亡者が出た場合、三家族全員を殺す』 このお触れは効果があった。それ以後、自殺者、逃亡者はでなくなった。 さらに副産物があった。今まで親しかった家族同士の付き合いがなくなっていき、互いの行動を見張るようになったのだ。家族の中 |
(4)
|
にも同じような状況が生まれていた。そして、家族や集落のまとまりや和がなくなっていった。べら棒な年貢を納めるためには、他の家族と協力し合って働かなければならない。だが、それ以外の場においては、ほとんど会話がなくなっていった。
ダビルの思うが侭の世界ができ上がっていった。 緑目たちは、浜辺から一キロ程陸地に入った所に住処を作っていた。傍には川が流れ、この川は海へと続いている。彼らは黙々と作業を進めた。総勢十三名。逞しい体であるが、皆、寂しげな雰囲気を漂わせていた。 長老のマノリが言った。 「ついに我々だけになってしまった。この国に辿りついたが、我々の種族は此処で終わることになる」 「この国にも女性はいるようですが」 「詳しくは調べていないが、いくつかの集落があるようだ。しかし種族が違う。初めて見る種族だ」 「そうですね。子供ができるかるかどうか判りません。しかし、ミンティス帝国があのような形で無くなるとは考えてもいませんでした」 「もう言うな! 総て終わったことだ」 緑目たちは遠くを見るような目付きになった。 ミンティス帝国は、はるか大昔に一度、地殻変動により国土の八割ほどが海底に沈んだことがあった。しかし、この時の異変は急激なものではなく静かに進んだ。石で出来た建物の大半は海底に沈んだが、この種族は特殊な肺を持っていた。空気中から酸素を吸収することも、海水から酸素を吸収することもできた。地殻変動の後、生活の中心は海底になり、陸地に上がるのは、主に火を使う作業をする時、そして穀物の栽培の時だけだった。 |
(5)
|
帝国では平和な毎日が続いた。 山の中腹には果樹園が広がり、女達が果物を採った。海に通ずる平野には幾つのも建物が並び、中では鍛冶屋が刀を鍛え、他の建物では大きな魚を捌く者や魚介類を塩漬けにする者たちがいた。広場では、男たちが剣道や格闘などの訓練をした。
彼らは鉄を知っていた。石炭も石油も知っていた。それに煉瓦も作っていた。ほとんどの食料は海にある。魚貝類や海藻、そして動物性蛋白は、豊富なアザラシ、クジラからとった。 帝国だけを考えれば平和であったが、この帝国の冨を狙う国が幾つも存在し、彼らとの争いが絶えなかった。そのため、自衛を目的とした集団を持っていた。 だが、帝国の消滅は急激なものだった。突然に起こった大噴火と大地震が国土を粉々にしてしまった。逃げ惑う民を流れ出る溶岩が襲った。洞窟などに身を隠した民は、有毒なガスに襲われた。ほとんどの民は、この時に死んだ。わずかに生き延びた者たちは海に逃げた。だが、煮えたぎった海水が追い討ちを掛けた。 生き延びることができたのは、ワイナ国に辿り着いた者たちだけであった。 ある日、一人の緑目が川で砂鉄を採っていた。彼の名前はカマルと言った。この国に辿り着いた最初の男だ。 カマルは、考えても無駄なことと判りながらも、やはり帝国の事、死んだ家族の事が頭から離れなかった。この日も物思いに耽りながら作業をしていた。そのためか、五人の男が近づいてくるのに気が付かなかった。カマルが、ふと頭を上げると棒や石斧、石槍を持った男に囲まれていた。彼らは黒い目をしていた。何やらわめき散らしているのだが、全く理解できない言葉。異なる種族だ。カマルは、彼らの力量を知らない。黙って彼らを見つめる以外になかった。 すると、その中の一人がカマルの腕を掴んだ。カマルが、さっと |
(6)
|
腕を引いた。その男は、叫び声を上げて飛び上がった。彼の手の皮は剥け、血が噴き出した。もう一人が後ろから羽交い絞めを掛けた。カマルは、足で彼の脹脛を擦った。この男も叫び声を上げて飛び上び上がってしまった。足からは血が噴き出している。一人が石斧を振りかざし、カマルめがけて打ち下ろした。と同時に、カマルは背中の刀に手をやり、抜き打ちざま石斧の柄を切り落とした。彼らは奇妙な叫び声を上げながら逃げていった。
カマルは注意を怠ったことを恥じたが、お陰で彼らの力量を知ることができた。 この五人は逃げ帰ると、ダビルに報告した。 ダビルは、緑色をした目を持つ人間など聞きたことがなかった。驚きはしたが人数は少ないだろうと思った。大勢居るのであれば、既に耳に入っていてもよいからだ。多分、恐れる事はないだろう。しかし光る棒や触ると皮が剥けてしまう腕や足には興味があった。何なのだろう? ダビルは気になったが、いずれ滅ぼせば、事は済むと考えた。 カマルは、皆にこの国の男たちや武器などについて話した。皆、悪い予感がした。だが計画通り、砦の建設を進めることにした。 「姉ちゃん! また、あそこの女の子が王のところに連れて行かれたよっ。大抵の女の子は、そのうちにお腹が大きくなるんだ。姉ちゃんも気を付けないと連れて行かれるよ」 「私はね、そんなことになったら舌を噛んで死んじゃうわ」 「駄目だよっ! 死んじゃっ。姉ちゃんが死んだらおいら達も一緒に死ぬ!」 両親を失った四人兄弟。長姉の名はミミ、次姉はメメ、長男はテテ、末女はククと言った。この国では、家族毎に共通のものを対象に名前を付ける習慣があった。この家族は、身体の部分から名前を |
(7)
|
つけていた。
ミミは小声で話し始めた。 「大丈夫よ、死んだりしない。姉ちゃん、このままではいけないと思うの。みんな、良く聞いて。姉ちゃんはね、ある事に気が付いたの。お月さんなんだけど。お月さんて丸くなったり、細くなったり無くなったりするでしょ。不思議だったの。だから、その日数を石を置いて数えてみたの。そしたらね、その順番は決まってるの」 「何でそんなことをしたの?」 「此処にいては駄目。この集落を出るの」 「駄目だよ、そんなことしたら他の家族が殺されるっ!」 「テテ。ダビルは、そんなことはしない。私たち子供が逃げたからって、他の二家族を殺したりはしない。人手が無くなるから。精々、棒叩きくらいよ。大丈夫。次の次の夜は、お月さんが無くなるの。姉ちゃん決めたわ。いいわね、次の次の夜に、この集落を出るのよっ!」 皆、ミミの話にうなずいた。ミミは続けた。 「四人一緒だと気付かれる。だから一人一人で出て行くの。一番小さいククから出て行くの。そして、テテ、メメの順よ。まず川に行くの。川に着いたら川の流れを遡るの。小さいククは歩くのが遅いでしょう。だから川を遡っていくうちに順繰りに追いつくわ。そうすれば、皆一緒になれる。良いわね、判ったわね! みんな間違えないように明日、川の方向をちゃんと確かめておくのよ」 その夜がやってきた。ククは、おどおどしながら皆の顔を見た。 ミミが、きつい顔で言った。 「早く行きなさい。すぐに皆、一緒になれるんだから」 ククが出て行った。少し経ってからテテが。メメはミミを心配していた。最後になればなる程、周りに気付かれる危険性が高いからだ。 「姉ちゃん、一緒に出たほうが……」 |
(8)
|
「メメ。一人一人の方が安全よ。さっ、行きなさい」
メメが出て行った。ミミは、耳をそばだてたが気付かれている様子はなかった。ミミの番だ。そっと小屋を出て行った。 川まで辿りついた。 ―― 皆、きちんと歩いているだろうか。 しばらく行くと三人と一緒になった。 「さー、行きましょう」 しかし、ミミも何処に行けば良いのかは判らなかった。とにかく上流を目指した。何かあるのでは……。いや、上流までは、ダビルの勢力は伸びていないのではとの思いだけであった。 そろそろ夜が明ける。空の彼方が明るくなりだした。皆、くたくたであったが、休みなく歩いた。陽は高くなっていく。 今朝も、カマルが砂鉄を採るため川に来ていた。周囲に注意を払いながら砂鉄を採る。 ふと何かを感じた。何やら音がする。耳を澄ませると下流から足音が聞こえてきた。彼は草むらに身を隠し、音のする方を見た。トボトボと歩く四人の子供が見えた。カマルは静かに体を起こした。彼らもカマルに気が付いた。そして互いに見つめ合った。 子供たちに逃げる様子はない。カマルは、ゆっくりと近づいていった。彼らも、ゆっくりと近づいてきた。 ミミたちは、緑色の目に驚いた。だが逞しい体付きなのに、どことなく寂しさを漂わせているこの男を、多分優しい人だと思った。 カマルは、彼らが疲労しきっていることに気が付いた。一緒に付いて来いと手で合図して砦へと歩いた。振り向くと彼らも付いて来る。 カマルはは、なぜだか嬉しさが込み上げてきた。 子供たち四人は、何も話さずに男の後に付いて行った。 |
(9)
|
川から少し離れた所に大きなものが立っていた。四人は驚いた。このように長い丸太を縦に並べたものなど見たことがない。しかも、それを取り巻くように川が流れている。壁のような丸太のてっぺんを見ると、何ヶ所かに人が立っていた。彼らは、こちらを見ながら手を振った。こちら側の男も手を振った。すると丸太の一部が、ゆっくりと前に倒れ出した。そして、ちょうど川を跨いで止まった。皆は、その丸太の上を歩き中へと入っていった。
丸太で囲まれた内部は広い広場になっていた。そして幾つもの木で出来た四角いものが建っていた。広場の奥の方には、太くて長い丸い棒のようなものが立っている。その棒の先からは、煙がモクモクと立ち上がっていた。 大きな建物に手招きされた。中に入ると緑目が三人、板の前に座り何かを食べていた。板の傍には、石を丸く置いた囲炉裏があり火が燃えていた。その上には、半球の大きなお椀のようなものが掛かっている。何で燃えないんだろう? 四人は顔を見合わせた。 緑目たちが驚いたように四人を見つめた。連れてきた男が何やら喋った。聞いたこともないような言葉。それに、その声は甲高く、くぐもっていて聞き取りにくかった。いや、何を話しているのか全く判らない。緑目たちは、うなずいて四人を手招きし、座れと合図した。 不思議なことに四人は恐くはなかった。板の前に座ると緑目の一人が、木でできたお椀を持ち、中に食べ物を入れた。細い棒の先が丸くなっている小さな道具とお椀を渡し、食べろと合図した。四人は湯気の立つお椀を手にした。良い匂いがする。一口食べてみた。 ―― 美味しい! 四人が、初めて口にする味だ。 ―― こんな美味しいものがあるなんてっ! 四人は顔を見合わせ、ニコッと笑った。後は夢中で貪り喰った。 |
(10)
|
緑目たちも顔を綻ばせ見ていた。
緑目たちは塩の作り方を知っていた。海水を天日にさらし、その後、石炭を燃やして長時間煮る。四人が食べたものは魚介類と芋を煮たものだった。塩味が効いている。美味い訳である。 食べ終わると、四人はカマルに連れられ別の建物に案内された。中に入ると地面から少し高い所に竹で編んだ床があり、その上には茣蓙が敷いてあった。男が指を差した。四人は、寝ろと言っていると思った。横になったが、直ぐに深い眠りに入った。 緑目たちが集まっていた。マノリが言った。 「この国の子供たちだ。素直で良い子たちのようだ。多分、集落で辛い目に遭っていたのだろう。逃げてきたのだと思う。どうだろう此処に住んでもらっては」 カマルが頷いて言った。 「川で会った時、彼らは何かホッとした表情をした。私の目を見ても恐れる様子はなかった。不思議なことに私も親しみと言うか何か感ずるものがあった。言葉は通じないことは判っていた。そこで身振りで話してみたが、意思は完全に通じた。すでに、心は此処の住人になっているのではないか」 皆が頷いた。 「では彼らに話し……。いや、私とした事が何を言っている。言葉は通じなかったな」 マリノの言葉に皆が笑った。数ヶ月振りの笑いである。中には涙を流しながら笑っている者もいる。カマルが言った。 「通じるかどうか判らぬが、私が何とか伝えてみよう」 四人の到来は、緑目たちに、仄かな生きる喜びのようなものを与えたようだった。緑目たちは、久しぶりに心和む気持で夜を迎えることができた。 |
(11)
|
翌朝、カマルは彼らが寝ている小屋に行った。だが、彼らは居なかった。この砦から出ることはできないはずである。何処に行ったのだろう。
食事や話し合いをする集会場に行ってみた。彼らは床を掃除したり、お椀などを洗っていた。カマルは此処に居て良いなどと、あえて伝える必要がないと思った。 カマルに気付いた四人が寄ってきた。一番大きな女の子が何かを喋った。 「昨日は、ありがとう。食事もとても美味しかったし寝床も暖かく、グッスリ眠れました。仕事をしますから、ここに居させてください。お願いします」 四人が頭を下げた。カマルは何を言っているのか全く判らなかったが笑顔で頷いてしまった。それを見た四人は涙を流し抱き合って喜んでいる。カマルは、これで良いと思った。 四人は実に良く働いた。それに物覚えが早かった。女の子三人は、食事を作る事も布織りもすぐに覚えた。何の気なしに目をやれば掃除をしている。 男の子は、すぐに塩やお椀の作り方、煉瓦焼きを覚えた。しかも活き活きと働いた。休んで良いと手まねで言っても、何か教えろとでも言っているのか、皆が仕事をする様子をジッと見ている。カマルたちは、溶鉱炉や刀の作り方、それに火薬の作り方以外は何でも教えた。 二、三週間ほど経つと、彼らは一人前の仲間になっていた。 マノリが、皆を集めた。 「我々の帝国は崩壊した。戻る所はない。どうだろう、四人に言葉を教えてもらっては」 数ヶ月間、陸上で呼吸していたためか、彼らの声はくぐもりもなくなり、声音も低くなっていた。 |
(12)
|
「マノリ、その通りだ。我々は、この地に根を下ろし、生活していく以外にない。先に遭った連中は粗野な者たちだったが、子供たちを見ると、此処の種族にも我々と付き合える者が居るように思う。言葉だ。言葉を教えてもらおう」
この日から四人は忙しくなった。緑目は彼らを見つけると、鼻とか頭とかお腹を指差し、指で話せ、話せと身振りする。最初は面白がって教えていたが、相手は十三人である。さすがに疲れてしまう。 ミミがカマルに言った。 「十三人を二つの集団に分け、交互に言葉を教えた方が良いと思います。それに覚えるのも早いのでは……」 当然、まだ言葉は通じない。困ったようなカマルの顔を見て、ミミが地面に絵を描いた。一人の人間を描き、その周りに七人の人間を描く。もう一つの絵は一人と六人である。七人の一人を指差し、次にカマルを指差す。一人を指差し、次に自分を指差す。そして口に手を持っていき話す動作をした。カマルは怪訝な顔をしていたが、急に笑い出し、手を打って喜んだ。そして何度も頷いた。ミミの意思は、完全に通じた。 翌日から言葉の勉強が始まった。一つの集団は午前中、もう一つの集団は午後だ。 当初、大人が幼児のような話し方をするのを聞き、テテはゲラゲラと笑っていた。緑目たちは苦笑の連続であった。だが驚いたことに、一、二週間で必要な単語は覚えてしまった。 特にカマルの進歩は凄まじかった。三週間目に入ると、カマルは出来の悪い緑目に通訳のような立場でミミたちを補佐し始めた。所詮、単純な会話で用が足りる時代である。一ヶ月も経つと不自由のない日常会話ができるようになっていた。 緑目たちは、この国がどのような国なのかを知りたがった。四人は素直に事実を語った。話を聞き、緑目たちは顔を曇らせた。 |
(13)
|
そのようなある日、見張りの者が指笛を長く三度吹いた。非常事態だ。
見張りが大声で叫んだ。 「大勢の者たちが押し寄せてくるぞっ! 戦闘準備!」 四人はオロオロするばかりであった。だが、緑目たちの動きを見て驚いてしまった。 誰も指揮をしていない。しかし十三人は自分の役割を心得ているのか、各々が黙ったまま準備を始めたのだ。しかも、その俊敏な動作に驚いた。瞬く間に弓矢、刀、槍、松明、黒く丸い石のようなものが用意された。そして、彼らは配置についた。 押し寄せる者たちの叫び声は凄いものであった。かなりの人数のようだ。 テテは、恐る恐る砦の見張り台に登った。カマルは止めようかとも思ったが、押し寄せる者たちの力量は判っている。男の子だ、見ておいた方が良いだろう。 テテはビックリした。砦を幾重にも取り巻くほどの人数だ。これほどの人間を見るのは初めてである。彼らは、手斧、石槍、棒などを持ち、砦の周りにある水堀のそばまで来ていた。そして石を投げ始めた。砦にものすごい数の石が投げ込まれた。テテは心配になった。緑目は十三人しか居ない。これで防げるのだろうか。 緑目たちは、まず水堀に松明を投げ込んだ。テテは目を見張った。川が燃え出したのである。臭いのある川だと思っていたが、燃えているのである。川には石油が流されていたのだ。威勢の良い叫び声を上げて攻めてきた者たちは、この炎を見た途端、その声は悲鳴に変わった。そして、押し寄せる者たちの動きが止まった。 次に、緑目たちは、黒くて丸い石のようなものに松明の火を点けて彼らに放り投げた。、石は地面に落ちるとコロコロと転がっていった。テテは、ただの石だと思っていた。ところが石が凄まじい音 |
(14)
|
を立て、同時に火柱を上げた。テテは腰を抜かしてしまった。もっと驚いたのは押し寄せる者たちであった。ある者は空中に舞い上がり、また、ある者は体がバラバラになってしまった。
これだけで充分だった。緑目たちは弓矢を揃えていたが使う必要はなかった。押し寄せた大勢の者たちは蜘蛛の子を散らすように逃げていった。 テテは最後に残った者を見た。 そこに立っていたのは、真っ青な顔をしたダビルだった。そしてダビルは、後ろを振り返りながら必死で逃げていった。 後には、幾つもの死体が転がっていた。 しばらくして、緑目たちは砦の外に出て行った。そして死体を埋葬した。川は燃えていたが、大量の砂が撒かれ火は消えた。 ミミたちは食事の用意をしていた。テテは自分が見た光景を話した。姉たちは、聞きたくないようだった。大勢が死んだと話すと顔をしかめ、これ以上話さなくて良いと言った。 緑目の何人かがこの様子を見ていた。彼らは顔を見合わせ、誰とはなく優しい女の子たちだと呟いた。 ダビルは何が起こったのか理解できなかった。 川が燃えた。石が火を噴いた。眠れない日が続いた。毎晩、自分が燃える川に投げ込まれる夢を見た。部下たちは全く戦意を失っている。 ダビルは考えた。 ―― いずれ緑の目をした者たちが襲ってくるに違いない。このままでは遣られてしまう。どうすれば良いのだ。燃える川を渡る方法は? 黒い石は? いや、あの石で死ぬ者は諦めれば良い。こちらの方が人数が多い。何人死んでも構わない。川を渡り、あの丸太をよじ登り、中に入ることができれば、奴ら全員を殺せるはずだ。 |
(15)
|
ダビルは、総ての集落に声を掛け、長を集めた。
「緑色の目をした悪者が居る。我らを滅ぼそうとしている。我らが先に攻めないといけない」 先の争いに参加していない長たちは、王の言うことを信じた。皆は燃える川を渡る方法、丸太をよじ登る方法を話し合った。しかし、先の争いに参加した長たちは無言であった。まだ恐ろしさに体を震わせていた。ダビルは火を吹く石については話さなかった。参加した長たちも黙っていた。だが、思い出すだけでも身震いするほどの恐怖を感じていた。 ある長が言った。 「川を渡るには丸太を掛ければ良い。火は、濡れた毛皮を被れば良い。丸太をよじ登るには、細い丸太に足を掛けられる棒を刺したものを用意すれば良い」 準備が進んだ。王は、自分が支配する総ての人間を集めた。 マノリは皆の意見を聞いていた。 「彼らは、再び来るだろうか」 戦略面に優れた能力を持つムシカが口を開いた。 「必ず襲ってくる。砦の大きさなどから、我々の人数を見抜いていると思う。彼らの武器は気にすることはない。しかし、子供四人の話から想像するに、ダビルは犠牲者が何人出ても構わないと考える人間だと思う。人海戦術で来るはずだ。砦の中に入られるとまずいことになる。我々の体力がもたない」 「では、対策を講じなければならないが……」 ムシカは、彼らが考えるであろう砦に入り込む方法を述べた。その上で幾つかの作戦を話した。 その作戦の中には、堀の外側に溝を掘り落とし穴を作る事、梃子を利用して火薬ダマを遠くに飛ばすための機械を作る事、それに、 |
(16)
|
海藻を大量に用意する事などが含まれていた。
緑目たちは幾つかの集団に分かれて作業を開始した。テテは、カマルと共に機械を作ることになった。丸太を組み合わせた機械ができ上がった。火薬ダマを丸太の片方に乗せ、もう片方に大きな石を落として飛ばす機械だった。 落とし穴を掘る集団は、鉄でできた平らな道具を使っていた。足を使い道具を土に刺し土を持ち上げる。面白いように溝ができ上がっていった。溝の上には竹を組み合わせたものを掛け、その上に土が被せられた。 海藻を採る集団は、竹でできた駕籠を背負い海に潜っていった。彼らは何時間でも潜っていられる。海藻採りは瞬く間に終わった。 丸太の壁にも細工が施され、落とし穴の外側には、火薬を竹の筒に詰めたものが置かれた。 準備は整った。余った時間は、弓矢や火薬ダマ作りに費やされた。さらに持久戦を考え、魚介類、果物、穀物の採取が行われた。魚介類は、ミミたちにより塩漬けにされた。ミミやメメは、体こそまだ子供であったが考え方や行動は、りっぱな女性として成長していた。ククも姉たちの言うことを良く聞いた。 何日が経ったであろうか、彼らが攻めてくる騒々しい物音が聞こえてきた。どれ程の人数なのであろうか、土煙をモウモウと上げて走ってくる。 彼らはムシカが述べた通り、長い丸太を担いでいた。それに壁を登るためであろうか、梯子のようなものも担いでいる。だが、武器は前回と同じものであった。違いは毛皮を着ている者が何人も居ることだった。 ムシカが皆に言った。 「燃えた石油の上を渡るつもりだろう。毛皮には水をしみ込ませてあるはずだ。しかし恐れる事はない。手はず通りに動こう」 |
(17)
|
彼らの一陣が落とし穴の傍に来た。緑目たちは火矢を放った。竹筒の周りに撒いた火薬に火矢が刺さり、燃えあがった。と同時に竹筒が爆発した。彼らの何十人かが倒れた。彼らは怯んだ。彼らは、まだ弓矢を知らなかったし、幾つもの火が飛んで来たのである。
彼らは退いた。 彼らの後方に居る者たちが大声で叫んだ。 「何を遣っているのだっ! 進めっ! 進めっ!」 長たちであった。 第二陣が攻めてきた。かなりの人数である。緑目たちは機械を使って火薬ダマを放った。もの凄い数の火薬ダマである。第二陣は全滅した。 この時点で前の争いに参加していなかった長たちも、彼らは自分たちと異なり、遥かに優れた種族であることに気付きだしていた。だが、戦いを止めることはできなかった。ダビルと同じ考えに至ったからだ。今、彼らを滅ぼさないと、いずれ自分たちが滅ぼされてしまう。第三陣に号令する。進めっ! 第三陣には矢が放たれた。彼らの何十人かが矢に射抜かれた。しかし矢をかい潜って進む者もいた。だが、この者たちを待っていたのは落とし穴であった。溝の底には尖った杭が何本も立てられていた。大勢が犠牲になった。 第四陣は犠牲者の上を渡って来た。松明が掘に放り込まれた。燃える川である。毛皮をまとい丸太を抱えた一陣が進んできた。矢が放たれたが、毛皮に守られ倒れる者は少ない。堀に丸太が掛けられた。毛皮の者たちが渡ろうとした。しかし、丸太の上に落ちてきたものはヌルヌルとした海藻であった。果敢にも渡ろうとした者たちが燃える川に落ちていった。水中に潜れば火から逃れることはでき |
(18)
|
る。しかし呼吸ができない。顔を出せば火である。何人もが命を落とした。この時点で数百人いた彼らは、百人を割っていた。
丸太の上の海藻は、火に炙られ乾いていく。丸太を越える者が出てきた。彼らは梯子を持っている。上からは矢が放たれたが頭から被った毛皮が彼らを守った。梯子が掛けられた。何人もが梯子を登り始めた。梯子が彼らで鈴なりになったのを見計らい、緑目たちは壁の内側にある丸太を押し出した。丸太の先には、壁の外側にT字型のような形で丸太が付けられていた。この丸太が梯子を外側に押し出したのだ。鈴なりになっていた彼らは、梯子ごと燃える川に落ちていった。 残りの者は、長たちを含め四十人程になっていた。まだ人数的には勝っているが、戦いを止めた。 戦える者は総て集めている。これからは、この四十人で戦う以外にない。作戦を練った長が言った。 「彼らは、この囲いから出ることはできない。出てくれば我らに倒されることが判っているからだ。このまま見張っていれば、いずれ食べ物が無くなる。時間は掛かるが、それを待った方が良い」 何日もが過ぎが、緑色の目をした者たちの動きは一向にない。長たちは不思議がった。食べ物は無くなっているはずである。長い間、食べ物を置いておけば腐ってしまう。外に出て採取しなければ餓死してしまうはずだ。彼らは焦り出した。しかし囲いの中からは物音一つ聴こえてこない。既に餓死しているのではないだろうか。 燃えていた川の火が徐々に消えていった。 ある長が言った。 「川を渡ることができる。梯子も何本か残っている。今夜、皆で囲いの中に入ってみよう。仮に彼らが生きていたとしても我々の方が人数は多い。彼らに勝てるはずだ」 |
(19)
|
業を煮やしていたダビルは、実行することにした。
夜中、ダビルたちは静かに川を渡った。物音を立てないように梯子を掛ける。囲いの上に立ち、中を見た。誰も居ないようだ。彼らは次々と囲いの中に入っていった。最後にダビルも入った。 見たこともないような光景だった。整然と並ぶ建物。太い丸太のようなものが立っている。彼らは広場の真ん中に集まり、呆然としていた。ここの連中は、一体何者なのだろうか。 その時、急に辺りが明るくなった。松明だ。この松明は、布に石油を含ませたものだ。 気付くとダビルたちは、緑色の目をした者たちに囲まれていた。 マノリが言った。 「我々の力が判ったはずだ。戦いを止め、話し合おう。我々は、この地で平和に暮らしたいだけだ。あなた達と争うつもりはない。この近辺だけで良い。我々の土地として欲しい。これ以上死者を出すのは良くない。門を開ける。出て行ってくれぬか」 ダビルは驚いた。彼が自分たちと同じ言葉を話したのだ。 ―― 確かに奴らが襲ってきたことはない。しかし、このまま生かしておけば、いずれ権力を奪われる。 この考えがダビルの頭から離れるたことはない。ダビルは周りを見渡した。 ―― 十数人しか居ないではない。 ダビルが大声で叫んだ。 「やつらを殺せっ!」 彼らは、石斧や石槍、棒を振り回し始めた。 マノリが叫んだ。 「致し方ない、戦おうっ!」 所詮、彼らは対等に戦える敵ではなかった。人数が多いことだけが強みだったが、それが、彼らにとっては不幸なことであった。鍛えぬかれた緑目。しかも刀を持っている。緑目にとっては空しい戦いであった。 |
(20)
|
ダビル、一人が残った。
子供ら四人は固唾を呑んで彼らの遣り取りを見ていた。 「王、一人になったね。どうするんだろう」 テテが小声で呟いた。ミミが言った。 「マノリは正しい。ダビルもマノリの言うことを理解しているはず。心を入れ替えて……」 見れば、ダビルがマノリの傍に近寄った。 ダビルは、手ぶらだった。マノリは、ダビルが判ってくれたものと思った。その時、ダビルがマノリの手から刀を奪った。皆、身構えた。 しかし、ダビルが取った行動は、自分の喉を刀で切り裂くことだった。それは、一瞬の出来事だった。 数日後、何処からともなく大勢の人々が砦の周りに集まって来た。そして、緑目たちが死者を埋葬するのを手伝い始めた。緑目たちは、彼らの中に四人の子供たちと同じものを感じた。 カマルが、ミミに囁いた。 「優しい目をした人たちだ。ミミと同じ優しい良い人たちだ」 ミミは、応えた。 「そうよ。私たちはカマルたちと同じように、争いなんか好きじゃないの。楽しく仕事をして平和に幸せに暮らしたいのよ」 二人は見つめ合った。 緑目たちは、村人たちに塩や煉瓦の作り方などを教えた。 「マノリ、武器の作り方はどうしましょう」 カマルの問いに、マノリは答えられなかった。 「モンダに訊いてみよう」 マノリとカマルは、村の最長老であるモンダのところに行った。 「武器は持っていれば使いたくなるものです」 「では、教えない方が……」 |
(21)
|
「問題は使い方です。刀は魚を捌く時に便利です。鉄の作り方は知りたいデス。弓矢は獣を獲るときに使えます。それから火を噴く石ですが、畑を作るときに使えます。大きな岩があれば邪魔ですから。でも、武器は不要です」
雪が降り、そして、その雪が溶けだし草花が芽吹き、木々の若葉が風にそよいでいる。 村人たちが畑を耕したり山で果物を採ったりしている。緑目たちが獲ってきた魚を塩漬けにしたり天日に乾している村人もいる。 ワノナ国に平和な毎日が続いた。 月日は経ち、あの戦いの日から十数年が過ぎていた。 集落の中央には煉瓦で出来た大きな集会場があり、その前には大きな道がある。そして道の両脇には萱葺き屋根の木造の家々。 そんな家の前に、カマルと赤ん坊を抱いたミミが立っていた。そして傍には三人の子供が遊んでいる。子供たちの目は、茶色に輝いている。 遠くからメメとムシカが、手をつないで歩いて来た。ムシカが笑いながらカマルに言った。 「カマル、集落の長は大変か?」 「いや、閑なくらいだ。あれから十年経ったが、揉め事もないし、長などは要らんよ」 「村人が、是非と言ったんだ。皆、カマルを慕っている」 「心優しい人々だ。平和な日々が続いている。ところで、ムシカ、子供はまだか?」 ムシカが頭を掻くと、メメが言った。 「ミミが羨ましいわ。一人、頂戴よ!」 「駄目ですよ。早く作りなさい。ところでククは、キムカが好きなようだけど……。カマル、どう思う」 |
(22)
|
「おう、あの二人も一緒になるな。向こうの方が先に子供を作るんじゃないか」
ミミが膨れっ面で言った。 「兄さん! そんな意地悪、言わないで下さい。天国のマノリに言い付けますよ」 「言い付ける必要はない。マノリは、いつも我々を見守っている。マノリが残した言葉を忘れないようにしよう」 四人が、空を見上げた。 戦いが終わり、四年ほど経ったある日、集会場を大勢の村人たちが取り巻いていた。集会場の中では、マノリが竹で出来た寝台の上で体を半分おこして寝ていた。周りには緑目や村人たちが涙を流している。マノリが静かに語り出した。 「我々は、ミンティス帝国で幸せな暮らしをしていた。だが、不幸な経験をした。今、我々の種族は、ワノナ国の人々と共に幸せに暮らしている。この国の人々は、黒い目をしている。カマルや何人かの仲間たちは、この国の女性と一緒になった。産まれた子供の目の色は茶色だ。何世代かの後、此処は、茶色の目をした人たちの国になるだろう。そして、陸上だけの生活になるだろう。しかし、決して忘れてはいけない。我々が陸上でも海中でも生活できる種族であることを。そして、かつては、ミンティスという素晴らしい帝国を築いたことを。いつの日か、この国が海中に没することがあるかも知れない。その時こそ、我らの記憶や体を甦らせ、人々を助けるのだ。かならず……必ず、その時は、来る」 マノリは、幸せそうな顔を残して旅立った。 (了) インデックス・ページに戻る。 |
(23)