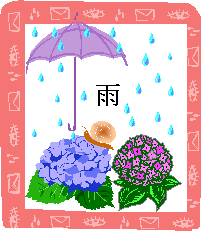 九谷 六口 九谷 六口 二00二年六月二十六日
|
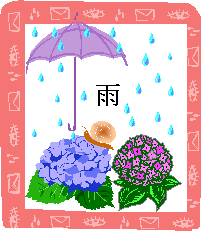 九谷 六口 九谷 六口 二00二年六月二十六日
|
|
「今日も、雨だわ」
加奈子は、窓際で頬杖をつきながらつぶやいた。 雨に濡れた庭を見るのは好き。地面は黒く光り、雨水が流れてい る。その流れに雨粒が落ち、ピチャピチャと 庭の 紫陽花は、ガク紫陽花。加奈子は、この花が好きだ。 ――そうよね…… 梅雨なんだもの。雨の日が多いのはあたりま えね。 見ると紫陽花の葉には、小さなカタツムリ。 「デンデン虫々、カタツムリー……」 小さな声で口ずさんでみる。 昼間なのに薄暗い庭。雨音しか聞えない。加奈子は、両方の手で 頬杖をつきカタツムリを見つめた。 「カタツムリちゃん、あなたも一人なの。私と同じ……。私ねー、 失恋しちゃったの……」 加奈子が最後に弘樹に会ったのは三年も前のこと。もう会えない と言うのに、弘樹への思いは日に日に強くなっていく。 加奈子は、絵を描くのが好きであった。子供の頃は自分から進ん で絵画教室に通うほどであり、高校時代には美術系のクラブに入っ ていたが、大学に入学した時には、どのクラブにするか決めていな |
|
かった。加奈子の油絵は展覧会などでいつも入選していたため、一
時は美術系の大學に進もうかと考えたこともあるが、自分の才能が どれほどのものであるかは判っていた。絵は趣味として続けようと 思っていた。 加奈子は、美術クラブで弘樹に出会った。 桜が咲き誇る季節、大學のキャンパスでは音楽クラブによる新入 生歓迎演奏会が開かれていた。グリー・クラブ、フォークソング、 オーケストラ、ジャズ、そして、クラシック・ギター。 加奈子は合唱は、あまり好きではない。器楽の方に興味を引かれ ていた。 ステージでは、司会者が熱心に話している。 「初心者の方でも大丈夫ですよ。先輩が優しく教えます」 ――クラシック・ギターか。一人でも楽しめるし合奏もできる。 小さい頃、テレビで見た映画が甦ってきた。禁じられた遊び。繊 細な曲。子供心にも弾けたら良いなと思ったことがある。 加奈子は、部室に行くことにした。 ギター倶楽部の看板が掛かっている。中では、何人かが弾いてい た。上手い人、下手な人。 「入部希望ですか」 一人が声を掛けてきた。 「いえ、まだ決めていません。でも、ギターって良いなと思って… …」 「君、ちょっと弾いてみる」 |
|
「触ったこともないんです」
「大丈夫だよ。さっ、ここに座って」 その部員は丁寧に持ち方などを教えてくれた。音が出た。思った ほど良い響きではない。何故かしら。加奈子は、急にギターを抱え ているのが嫌になってしまった。ギターは私に向いていないのかも 知れない。 「ありがとうございました」 「で、入部は……」 「考えてみます。その気になったら、また来ます」 その部員は、なーんだといった顔付きで加奈子を見た。 一つおいて隣が美術クラブの部室であった。絵具の臭いなどが廊 下にまで漏れている。見ると扉が開いていた。覗いてみた。ギター 倶楽部の部室に比べ、かなり広い。カンバスやイーゼルなどが散在 し、雑然としている。奥の方に、いかにも私は絵を描きますといっ た雰囲気の学生が居た。長髪に無精髭。うす汚れた服。加奈子の目 には、わざとらしい格好と映った。 加奈子に気がついたが、声を掛けようともしない。 「あのー、入部したいんですけど……」 「新入生か。そこに入部届けがあるでしょう。どうせハンコは持っ てないと思うから、拇印でいいよ。部費は、月千円。春、夏、冬の 休みには合宿をやる。その時は合宿費がいる。金額は、その時によ って違う」 「何曜日が部会なんですか」 「そんなものは別に決まっていない。ただ、モデルに来てもらって |
|
デッサンを遣る時は、皆が集まる。年に四回位かな。金が無いからね。ま、その時が部会だな」
「では、この部屋は適当に使って良いのですか」 「あー、構わないよ。あっ、忘れてた。年に二回、大學の図書館ロビーで展覧会をやる。参加、不参加は自由だ。ただ、余り下手な絵を出されるとクラブの評判が下がるからね。君も、そこいら辺を考えて決めればいい」 「判りました。では宜しく」 加奈子は部室を出てからつぶやいた。 ――何故、入部したいなんて言っちゃったのかしら…… 加奈子は判らなかった。 ――私って、適当なところがある。 広いキャンパスには木立も多く、点在する建物の周りを綺麗に手入れされた芝生が取り囲んでいる。キャンパスの中央には、大學のシンボルともいえる図書館がある。休み時間には、大勢の学生が芝生に座ったり寝転んだりしている。本を読む者、食事をす者など、まるで公園のような雰囲気である。 大學での毎日は、まさに自由であった。 一応、単位を取らなければならないため講義には出席している。文学部国文学科。加奈子は、別にどの学科でも良かった。どうせ就職して結婚。高校を出た時点で就職しても良かったが、後四年間ぐらい自由でいてもと思い試験を受けただけだった。加奈子の家は、 |
|
ごく普通の家庭。両親は五月蝿いことは言わず加奈子の自由にさせている。
この大學は国立総合大学。加奈子がここを受けると言った時にも両親は、あーそうかの一言。多分、学費が少なくて済むと考えただけだと思った。学費は親が出してくれる。 クラブには芸術学部の美術科学生が大勢いた。図書館での展覧会は、美術科の学生が作品を発表する場であったが、何年か前より他の学部の部員も一緒に展示するようになっていた。切っ掛けは、クラブの顧問教授が美術科の学生に刺激を与えるためだった。 加奈子は合宿には参加しなかった。先輩や同輩に強く言われたが費用が出せないんですと言い張って参加しなかった。クラブの雰囲気に溶け込めないのが理由であった。 加奈子は、人と一緒に何かをする事に醒めたところがあった。一旦、入り込むと夢中になるのだが、なかなか入り込もうとしない。部員たちは、皆から一歩ほど退いた所にいる加奈子に興味を持っていた。それに、加奈子は顔立ちもスタイルも良い。 展覧会は春と秋に開かれる。加奈子は、秋の展覧会に出展した。油でありながら日本画のように透明感のある風景画は注目を集めていた。 初めて部室に行った時に話をした学生がクラブの部長であった。彼は、美術科で日本画を専攻している四回生。加奈子を気に入ったのか絵が気に入ったのか、何かと声を掛けてくる。 |
|
いろいろなクラブがあるが、部長をやる学生は、一応、目立つ存在であった。この部長は加奈子の世話を良くやいてくれた。付き合ってくれと言う。ま、いいか付き合っても。
二人はキャンパスでも評判になった。部長は、加奈子とキャンパスを歩くのが嬉しいらしい。二人を羨ましがる学生も居たが、加奈子は、二、三ヶ月ほどで付き合うのを止めてしまった。感ずるものがないのだ。彼は絵について語るが、ほとんどが誰かの受け売り。日本画もただ綺麗に描こうとしただけのもの。 部員たちは、加奈子が退部するものと思っていた。しかし、加奈子は、彼を振ったからといってクラブを辞めるつもりもなかったし気まずいと感じる事もなかった。 一ヶ月ほど経つと彼の方が就職活動を理由にクラブを辞めた。部長は、三回生の女子学生がやることになった。 加奈子が二回生になった頃、加奈子はクラブに欠かせない存在になっていた。展覧会に出展した絵は、学内で評判になっていた。絵には名前と所属学科が添えられる。国文学科の学生か……。見る者は、絵を専門に描く学生の絵と比較してしまう。 展覧会は二週間開かれる。加奈子は、会期中に一度くらいは絵を見ておこうと図書館ロビーに行ってみた。 ラグビーのジャージを着た、背の高い学生が加奈子の絵を見ている。加奈子は邪魔になってはいけないと思い、少し離れていた。加 |
|
奈子がロビーに来てから、もう二十分以上経っているが、その学生は、まだ絵を見ている。加奈子は仕方なくロビーにあるソファーに腰をおろした。別に疲れている訳ではないが、眠ってしまったらしい。
ふと目を覚まし、ロビーを見渡してみた。その男は、まだ絵を見ている。時計を見ると、さらに三十分以上が経っている。加奈子はソファーから立ち上がり、その学生の側に立った。搬入の時はワサワサしていたが、こうやって落ち着いた雰囲気の中で自分の作品を見るのも楽しい。加奈子は無意識のうちに笑ったようだ。彼が、驚いたように加奈子を見た。 「今、笑った?」 「いえ、微笑んだのかも知れませんが……」 「何故?」 「何故って?」 「この絵を見て笑ったように見えたから」 「フフッ、そんな事ありませんよ。さっきから、ずーっとこの絵を見ていますね」 「この絵を描いた人は……」 「……どうなんですか」 「君には判らないかなー。この絵は綺麗だし明るい。でも、もの凄く寂しい。こんな風に感情を複雑に刺激する絵を見たことがない。描いた女性もこの絵のような人だと思うな。それに……感情移入をしていない。彼女には、醒めたところがあるんじゃないかな」 「絵に詳しいんですか」 |
|
「いや、詳しいとはいえないな。ただ、子供の頃から父に連れられて色々な絵を見せられた。父は、一枚一枚、説明してくれたよ」
「じゃー、お父さんは絵を描くんですか」 「画家を志したことはあったらしいけど…… 今は商社に勤めている」 「あのー、この絵を描いた人は、醒めていますか」 「多分ね」 「展覧会には、いつも」 「いや、一回生の時に来たことがある。気持ちは判るけど、どの絵も無理に描こうとしている。そういう絵って、なんだか見ていて痛ましさを感じちゃうんだ。今日来たのは、クラブのマネージャーが油なのに日本画のような絵が出ていると教えてくれたからなんだ。来て良かったよ。ところで、この絵、家に飾りたいけど……。売ってくれるのかなあ」 「先生に訊いてみたら」 「そうだね。いけねー、練習が始まる時間だっ。そうそう、君ってこの絵のように綺麗だよ。縁があったら、また会えると思うな。その時まで、じゃーね」 彼は走って行った。ロビーの連中は、顔をしかめて彼を見た。 「やーね、いくらラグビー部の顔だからって。ジャージ姿で見に来るなんて。それに、わざとらしいわよ、走っていくなんて」 「彼って目立ちたがり屋なのよ。付き合う女の子も目立つ子ばっかり」 「今は誰と付き合ってるの?」 |
|
「この前の、ほらっ、何とかピアノ・コンクールで三位に入った子よ。二人でキャンパスを歩く時なんか周りばかり気にしちゃって。見てくれる人がいないと機嫌が悪くなるんだって。二人ともよ」
「そういうのって、やーね」 そんな会話が、加奈子の耳に届いた。 ――醒めた感じ……そうかなー。 絵を見ながら加奈子はつぶやいた。 二日後、またロビーに行ってみた。 加奈子の絵には売約済みの小さな札が掛かっていた。あの人、買ったんだ。でも私、大學に売っても良いなんて言ったことない。 展覧会の担当教授に会いにいった。 「何だ、売っちゃいけなかったの。自分の絵が売れるなんて滅多にないことだよ。それに今までも、こういうことは何度かあった。いいだろう、売ってみたら」 「でも、先生、値段はどうしたんですか」 「彼は幾らでも良いって言ってたよ。君が決めればいい。最終日に来るから」 加奈子は、まー、良いかの気持ちになっていた。でも、幾らにすればいいの。 搬出の日が来た。加奈子はロビーに行った。彼はソファーに座っていた。周りをキョロキョロ見ている。加奈子は彼の前に立った。 |
|
「やー、君か。やっぱり、また会えると思っていたよ。あの絵、買っちゃったよ。描いた人を待ってるんだ」
「幾らで買うつもり」 「幾らでもいいんだ。親父に出させる」 加奈子は、からかうつもりで言ってみた。 「じゃー 五十万!」 「ハハハー、勝手に人の絵に値段を付けちゃ駄目だよ。でも五十だったら悪くないな。家に飾るのに相応しい絵だし……」 「では、五十万で売るわ」 「エッ! どう言うこと。まさか……描いたのは君」 「えー、描いたのは私」 彼は目を見開き、加奈子をじーっと見た。 支払いは、彼の家でと言う事になっていた。 「親父が直接渡したいって言うんだ。家に来てくれる? それに、絵を飾ったから見てもらいたいんだ」 豪華な邸宅だった。にこやかな笑顔満面の両親。 「絵は怖いね。画家の雰囲気が出てしまう。この絵の雰囲気は、貴女の雰囲気そのものだ。実に良い。息子の絵を見る目は確かだよ。それに女性を見る目も出来たかな。イヤーこれは失礼々々。わっ、ハッハー。さぁ、この封筒だ」 加奈子の父親は寡黙だが、この男は良く笑う。 「ありがとうございました」 加奈子は、封筒をそのままバッグに入れた。 |
|
「君っ、確かめなくていいのかい」
彼が言った。 「えっ、確かめるの? でも人の前でお札を勘定するなんて……」 「わっ、ハッハー。安心していい。ちゃんと入っている。可愛い女の子がお札を数えている図なんて綺麗じゃない」 父親は一人で満足そうな顔をしている。母親もニコニコ顔で付け加えた。 「加奈子さん、自分の家だと思って気軽に遊びに来てね。たまには女性同士の話がしたいわ」 キャンパスで二人の姿を見かけるようになった。 「あら、ラグビー部の彼、今度は、あの子にしたのね」 「前の子は止めちゃったのね。あの子、いつも自慢気な顔だったでしょう。気に食わなかったわ」 「アラ、貴女が気に食わなかったからって、関係ないんじゃない」 「それは、そうだけど……。でもね、今度の子、前は美術クラブの部長と付き合ってたのよ」 「あっ、あの子かー。結構、大人しそうだけど遣るわねー。大物食い。ねー、どっちが相手を振るか賭けない」 「面白いわね。あの子の絵、見たけど……浮ついてなかったわ。多分、芯はシッカリしていると思う。私は彼女の方に賭ける」 「何だ、それじゃー賭けにならないわ。私ねー、彼が振られた姿、見てみたいの。彼女を応援するわ」 「あたしたちも性質が悪いわね。別れるのを期待するなんて。あー |
|
ヤダヤダ」
キャンパスでは、加奈子の噂も囁かれていた。淀君。 この噂は二人の耳にも届いたが、目だちたがり屋の彼は、むしろ喜んでいた。加奈子は、そんな噂には耳をかさなかった。どうでもよい事だった。ラグビーの試合でも、何処に居ても加奈子は目立った。 酸っぱいような汗臭さが充満した部室。どうしても好きにはなれない臭い。たまには、ラグビーの部室にも顔を出すが、タオルを腰に巻いただけの部員たちも加奈子を受け入れていた。加奈子は、そんな姿を目にしても何も感じなかった。 二ヶ月ほどが経った。加奈子にとり、それなりに楽しい毎日だったが、気になることがあった。彼は何もしようとしないのだ。加奈子は、別に手を握ってもらいなどとは思っていないが、何か不自然さを感じていた。 ある日、部室を覗いてみた。誰もいないのかな……。耳を澄ますとヒソヒソ話が聞えてきた。そーっと中に入ってみた。隅の方に男が二人いた。一人は壁を背にしている。もう一人は……彼だ。彼は壁に左手をつき、右手で後輩の髪を撫ぜたり、頬を摩ったりしている。多分その男は後輩だろう。その男の右手を見た。彼の股間を撫ぜている。 ホモッ! 加奈子は、別に驚かなかった。成る程ね。そうだったんだ。静かに部室を出た。 |
|
加奈子が、一人でキャンパスを歩いている。
「あら、淀君だわ。ねぇ、聞いた。淀君、勝ったのよ」 「勝ったって?」 「知らないの? 別れたのよ、あの二人」 「やだー、勝負じゃないんだから勝ったなんて変よ」 「もう一月ほど経つわ。彼ったらしょんぼり一人で居るわよ。ラグビーも全然駄目なんだって。腑抜けみたい。可哀相ったらないわ。見ていて気の毒……」 「そんなに言うんだったら、付き合ってあげればイーじゃないッ」 「やだー。だって彼って、こっち系なんだって」 この学生は右手をツッパリ、指先を左の頬に持っていった。 「ウッ、ソー! それ本当ッ?」 「本当らしいわ。それらしきところを見た人がいるのよ。キャンパスの隅っこの方で……」 「気持ち悪ーい!」 「でも淀君って全く普段どおりね。別れた感じなんて全然しない」 「そこが、淀君たる所以よ」 加奈子の毎日に大きな変化はなかった。講義を受け、時間が空くと部室に行った。絵に集中している時は幸せだった。雑念などない空気のような時間。 ここ数ヶ月は一人で歩いているのに淀君の噂は消えていない。加奈子は、うしろ指をさされることはないが、常に複数の人間の視線を感じていた。しかし、別にそのような視線に煩わしさを覚える事 |
|
もなかった。
クラスに親しい友達はいない。だが、クラスの会合、例えば新年会や忘年会、休暇前の呑み会などには何度か参加していた。 当りさわりのない会話。クラスの男子学生は、とっくに加奈子のことを諦めていた。自分たちには付き合いきれない。淀君の噂がそうさせたのだろう。加奈子も気づいてはいたが、噂については否定も肯定もしなかった。そう思う人は、そう思っていれば……。私は構わない。 加奈子は、三回生になっていた。もうすぐ二十歳の加奈子は、ますます綺麗になっていた。 スケッチブックを小脇に抱え、長い髪を風になびかせながら、少し眩しそうな眼差しで歩く姿は、誰でもが振り返りたくなる雰囲気を持っていた。加奈子の歩幅は大きい。スカートの時など、スラッと伸びた足が爽やかなステップを踏む。 キャンパスの桜が薄いピンク色の霞を作り、新入生を迎える時期が来た。 加奈子は部室で絵を描いていた。ふと、視線を感じた。 入り口に色白でスマートな学生が立っていた。加奈子と目が合った。澄んだ潤んだ大きな目。加奈子は、一瞬、ドキッとした。ややもすると気取っているのではとも感じてしまう姿だ。 部室に入ってきた。新入生に決まっている。カンバスに目を戻し |
|
た。
「あのー、入部したいんですけど……」 優しそうな声だ。 「新入生ですか。そこに入部届けがあるでしょう。多分、ハンコは持ってないと思うから拇印でいいわ。部費は、月千円。春、夏、冬の休みには合宿をやります。その時は合宿費がいります。金額は、その時によって違いますけど……」 「部会は、何曜日ですか」 「別に決まっていないの」 加奈子は、話しながら何処かで聞いた話だなと思った。でも説明はしなくては。 「あのねー、年に二回、大學の図書館ロビーで展覧会をやるの。参加、不参加は自由だけど」 「僕は水彩なんですけど、構わないですか」 「別に、イイわよ。君、何学部?」 「経済の国際学科です」 「へー、頭良いんだ」 「父が、外交官なんです。だから……」 「だから?」 「一応、国際学科に入学しないと……。自分が、外交官に向いているかどうかは判らないんです。父が、そう言っても」 「そうなの。でも水彩が好きなんだ」 「大好きです」 急に活き々きと目を輝かせている。余程、絵を描くのが好きなんだと加奈子は思った。 |
|
「先輩ッ、描いてるんですか。見たいなー」
この新入生には気取りなどなかった。 「いいわよ」 新入生は、描き掛けの絵をジーッと見た。 「先輩っ、今度、僕の絵を見てください」 と言って部室を飛び出て行った。 変な子。加奈子はカンバスに向かった。しかし、彼の大きな目が頭の片隅に残った。 二日後だったと思う、その新入生が部室に入ってきた。 「先輩っ! 見てください」 三枚ほどの絵を持ってきた。空いているイーゼルに置いている。 加奈子は彼の絵を見た。描き方もきちんとした水彩画。でも、印象は違った。絵具を塗りたくってはいないのに部厚い感じを受ける絵だ。感覚的には油のような絵。彼から受ける柔和な印象と異なり力強さを感じさせる絵。惹かれるものがある。 「油みたいな絵ね」 「額縁に入れると油と間違える人がいるんです。水彩なのに」 「油で描いたことあるの」 「ありますよ。でも油だと絵筆が自由に動かないんです。水彩絵具の方が好きなんです」 「筆の動きか……。そうね、結構、気になるものかも知れないわ」 「先輩の絵は、油なのに日本画のような感じですね。岩絵具、使ったことあるんですか」 |
|
「あるわ。自分で色を作りたくて石を砕き粉にしたり、膠を溶いたり……。でも何か違うように思ったの。時間は掛かるし、それに疲れるしね。下手すると全く違った色が出たりする。描きたいのは絵。出したい色が出せれば、絵具は何でも良いと思ったの。私の場合は油で出せたの。描きたい絵が描ければ嬉しいわよね」
「先輩、僕の場合、それが水彩絵具だったんです」 「変ね。水彩絵具を使い油のような絵を描く人間と油を使った日本画のような絵を描く人間が此処にいる」 「先輩、これからもよろしくお願いします」 ペコリと頭を下げた。 弘樹は部室によく来た。部室に入ると加奈子の隣にイーゼルを置く。先輩、先輩と話し掛けてくる。加奈子は、気取ったり自分を飾ろうとする話を聞くのは嫌いだが、弘樹は自分の考え気持ちを素直に出してくる。会話も楽しい。話をしていると筆も滑らかに動いてくれる。見つめられると、ちょっと胸が鳴る。自然、二人で居る時間が多くなっていった。 「淀君、好みを変えたみたいね」 「どう言うこと?」 「見てごらんなさいよ。ほらっ。近頃、あの子と一緒が多いのよ」 「あら、ただの後輩じゃないの」 「二つ違い。でも、あんなに嬉しそうにニコニコしている淀君、見たことある。今までの彼氏と一緒の時なんか、絶対に笑ったりしなかったわよ」 |
|
「そう言われれば、そうね。好きになれば歳の差なんて……って事かしら」
「私は、そう思うわ。今度は、続くと思うな」 キャンパスでは、この二人の噂が広まっていった。 淀君とお小姓様。 弘樹の上背は百七十ほど。色白で、ほっそりとした姿は、見るからに文化系の雰囲気。加奈子の整った女としての体付きに比べ、まだ初々しい感じすら与える。 加奈子は、珍しく夏合宿に参加した。宿は川口湖畔の民宿。起床後の体操、朝食、そして部屋の掃除。広間で絵を描いたり、湖畔で写生したり……。昼食後も各部員は、自由に自分の時間を持つ。風呂に入り夕食。就寝までの時間は、気が合う者たちが酒を呑んだり焚き火をしたり……。 よく笑い、語るようになった加奈子の周りには、いつも部員たちが集まっていた。楽しい合宿。いつも一緒にいた二人だが、まだ先輩、後輩としての付き合い。 秋には文化祭が開かれる。キャンパスは緑を保つ常緑樹、紅葉した木々が秋を演出している。 文化祭は、各クラブの発表の場でもある。趣向を凝らした展示などが教室毎に展開されている。模擬店も多い。キャンパスのあちこちにテントを張り、大声で客を呼び込んでいる。 |
|
美術クラブは、毎年、焼鳥屋を出している。儲かれば部の運用に使う。
加奈子も、この模擬店には積極的に参加した。肉を切ったり串に刺したりする準備は時間が掛かるが楽しい。 弘樹にとっては初めての文化祭。先輩連中と串を刺したりしている。加奈子は弘樹が浮かない顔をしているのが気になっていた。 弘樹の両親は厳格に弘樹を育てた。外交官の父は、弘樹が受ける中学や高校、大學までを決めた。勉強の予定表にまで細かく口を挟んだ。世間体にも五月蝿い。見っともない真似はするな、友達にも気をつけろ、下らん奴らとは付き合うな。特に、女には注意しろ。下卑た女は男の一生を台無しにする。 弘樹は、加奈子に対する噂を耳にしていた。淀君。お節介な連中は、君は何番目だなどと指を折ってからかう。ラグビー部の彼を見たことがある。長身でガッシリした体。誰が見ても格好が良い男。でも、気が抜けたような雰囲気だった。 ――加奈子さんに振られると、あーなるんだ。 一人で居ると、やはり噂が気になってしまう。 しかし、二人で居る時には噂など全く忘れてしまう。偽りのない自分を出す事ができた。常に両親の目を気にしながら育った弘樹には、何でも話せる加奈子との会話は新鮮なものであった。弘樹は、加奈子を心から好いていた。 両親が文化祭に来ると言う。運良く仕事の休みが取れたと言う。 |
|
何が運良くだっ。弘樹は自分にとっては運悪くだと思った。加奈子さんを紹介すべきなのだろうか。焼鳥の準備をする弘樹の頭には両親のことしかなかった。
両親が来る事を加奈子に話せないまま模擬店はオープンした。 午後四時頃だったろうか、模擬店に両親が顔を出した。弘樹は心臓が止まるのではと思った。来る事は判っていたのに、何故、こんなに驚いてしまうのか、自分でも理解できなかった。両親はビールを注文しているようだ。女性の部員が、焼鳥は如何ですかと聞いている。大袈裟に手を横に振る父親。学生が作った焼鳥など食べられるかといった顔つきである。弘樹は、ゲンナリしてしまった。 父親が弘樹を手招きしている。行かなければ。案の定、こんな事やって何になるのかなどと言う。その時、声がした。 「弘樹ーッ! 手が空いているんなら、このビール運んでっ!」 弘樹は振り向いた。だが、父親の話は終わっていない。父との会話の途中で席を離れる事は出来ない。声は、加奈子の声だ。 「弘樹ーッ! もー仕方ないわねー」 加奈子がビールをお盆に乗せて、こっちに来た。弘樹の側に来ると人差し指で弘樹の頬をつついた。加奈子のいつものクセである。 「お待たせしました。ビールです。弘樹、焼鳥、焼いてちょうだいね。混んできたから」 加奈子は、その時凍りついたような雰囲気を感じた。弘樹の前に座る二人に目を遣った。加奈子が、このまま席を離れたとしても結果は同じだったのかも知れない。しかし、加奈子は弘樹に訊いた。 |
|
「こちらは?」
「僕の両親です」 「えっ!」 確かに加奈子は、えっ! と声を上げた。弘樹から聞いていなかった。両親が来るのなら言っておいてくれれば良かったのに……。 「美術クラブの者です。いつも、弘樹さんにはお世話になっています」 「……」 「今日は、どうぞ、ごゆっくり。では……」 加奈子は、この場から離れた。しかし、睨みつけるような二人の視線が頭から離れなかった。 いくら鈍い人間でも、二人が親しい事には勘付くはずだ。三人は固まっていた。 「弘樹っ! 今日は、早く家に帰って来い。いいな。話がある」 二人はビールにも手をつけず、金も払わずに席を立った。その後には、悄然とたたずむ弘樹が残った。 加奈子は、弘樹に何も言わなかった。起こってしまった事。世の中は、なるようにしかならない。それに大した事ではない。二人の態度には釈然としないものが残ったが、私には関係ない。 ――弘樹、今晩、どんな話をされるのだろう。ちょっと可哀想。 文化祭も今夜で終わりだ。キャンパスには大きなキャンプ・ファイヤーが炎を上げている。学生は、酒を呑み陽気に騒いでいる。 加奈子は、このような雰囲気の中にいるのは好きだった。別に隣 |
|
に誰かがいなくても良い。大きな炎を見ながら片手にはビール。騒がしい中にも静寂を感じる。
ふと見ると弘樹が隣に座っていた。気が付かなかった。 「加奈子さん……」 「弘樹、どうしたの。元気ないじゃない。呑んでないの」 「呑んでます。もうグデングデンです。世の中が終わったような気持ちです。あの炎を見ていると、飛び込みたくなるほどです。あーァ」 「馬鹿ねー、何言ってるの。どうしたのよ」 加奈子には判っていた。両親のことであろう。弘樹は、炎をじーっと見つめている。炎に照らされた弘樹の横顔を見た加奈子は、綺麗だと思った。この人は純粋な気持ちを持っている。 加奈子は、弘樹の肩に手を置いた。弘樹が振り向いた。炎を前に二人は初めて唇を合わせた。 翌日、加奈子は部室にいた。弘樹が入ってきた。加奈子は声を掛けようとしたが、弘樹は下を向いている。やはり、初めてだったんだ。火照った弘樹の唇が思い出される。 「どうしたの、挨拶もしないで」 弘樹は、普段と同じ雰囲気でいる加奈子を見た。 「ちょっと二日酔いなんです。それに……」 「それに、何?」 「加奈子さん、話があるんですが……」 「何? いいわよ、言って」 「外で話したいんですが……」 |
|
「世話がやけるのね。判ったわ」
二人は、いつもの喫茶店ではなく大学から離れた店に入った。 「何? 下向いてないで話して」 「実は……」 「何よ、ご両親の事でしょ」 「そ、そうなんです」 弘樹は、ボソボソと話し出した。 あの夜、家に帰ると両親が待ち受けていたらしい。居間で早速、詰問が始まったと言う。 あの女とは、どのような関係なのか。お前を呼びつけにして、年上じゃないか。頬をつついたり……何だ、あの下卑た態度は。 弘樹は、自分より二つ年上であること告げ、さらに、自分は、あの人が好きだとはっきりと言った。 言った途端、父親は立ち上がり弘樹の頬を打った。口やかましい両親だったが、手を上げた事はなかった。弘樹にとっては初めてのこと。それだけ、父親の怒りが大きい事が判ったという。 「絶対にあの女とは付き合うなッ!」 この一言を吐き捨てるように言うと父親は自分の部屋に戻った。 「で、弘樹はどうするの? 昨日のことなんか気にすることないのよ」 「……」 弘樹は、下を向いたままだった。 「ねー、はっきりしなさいよ。弘樹は嘘をつけない性質よね。私のことを好きだと言ってくれたのは嬉しいわ。でも、頬を打つほどお |
|
父さんは怒っているんでしょう。お母さんも同じ気持ちだと思う。親にそこまでされたら…… これから先、私と付き合っていくの辛いんじゃない」
「か、加奈子さんッ! そのように、第三者のように話すけど、僕のこと好きでも何でもないのですかっ」 弘樹にしては強い口調。加奈子は、ムキになっている弘樹を可愛いと思った。 「ふふ、好きよ。でも、絶対に付き合わなくちゃいけないってことではないわ。結婚する訳じゃないんだから」 「僕が言いたいのは結婚とかそういう事ではなく、好きなら一緒にいたいって願うのが普通じゃないかって言いたいんですよ」 「判るわ。でも、ご両親に隠れて私と付き合うなんて、弘樹にはできないでしょう。無理して付き合うなんて楽しくないんじゃない」 弘樹は黙ってしまった。 ――何故、自分はこうなんだろう。 加奈子は弘樹に強く言ったが、自分にも何かを言い聞かせているようだった。 この日、二人は、部室には戻らず家に帰った。 弘樹の澄んだ、どことなく寂しさを感じさせる大きな目がちらつく。しかし、加奈子は、弘樹のことを諦めようと思っていた。 ――少なくとも私は無理して付き合うのはイヤ。今なら別れられる。 弘樹は三日間、部室に来ていない。加奈子は、今まで通り絵に夢 |
|
中になっていた。加奈子が入り口を見ると弘樹が立っていた。
「どうしたの。中に入ったら」 加奈子には弘樹の顔つきが変わったように思えた。弘樹が近づいてきた。 「加奈子さん、僕は付き合うことにしたよ。親には内緒だけどね」 「大丈夫なの?」 「大丈夫。いつまでも親の顔色ばかり見ていちゃね」 弘樹は、確かに変わった。それに自分を主張するようになっていた。たまにだが、加奈ちゃんなどと呼ぶ。 二人の楽しい毎日が続いた。講義を受ける時以外は、ほとんど二人で過ごした。二人は外泊はしない。どんなに遅くなっても、その日の内には家に帰るようにした。 ある日、部室には何人かの部員がいた。二人もカンバスを前にしていた。ギター倶楽部の誰かが廊下でギターを弾いているようだ。音が聞こえてきた。 「弘樹、私ね、ギター部に入ろうとしたのよ」 「へー。何故、入部しなかったの」 「だって、変な音しか出せないんだもの」 「ちょっと、指見せてくれる」 加奈子は、両方の手を出した。 「右手だけでいいんだ」 弘樹は加奈子の指を持ち、見ている。 「加奈ちゃん、クラシック・ギターを弾く人は爪を伸ばすんだ」 |
|
弘樹は爪の長さ、磨き方などを丁寧に話した。弦に指頭を当て、滑らせるように爪で弦を弾く。爪弾くって言うでしょなどと嬉しそうだ。
加奈子は単純なことに気が付かなかった。弘樹は、自分の指を見せながら話していた。 「弘樹っ! 君、ギター弾くの?」 「僕はギターが大好きなんだ。中学の時に父親が買ってくれた。この事だけは父親に感謝している。いろんな弦楽器があるけど、自分の指で直接音を作る楽器はギターしかないんだ。弾く時は抱きかかえるようにする。愛しい人を抱くような感じかな。加奈子さん、ギターって不思議なんですよ。自分の心持ちとか気分によって弾く感じが変わる。もっと不思議なのは、いくらこっちが気分が良くてもギターの気分が悪い時がある。そんな時はいくら頑張っても駄目。まるで生きているようなんです」 「弘樹のギター聴きたいな。ギター倶楽部に行ってみようよ」 「良いのかなー。彼らギター貸してくれるかな」 「大丈夫よ、行こうよ」 部室に入ってきた二人を見て、ギター部の何人かが怪訝そうな顔をした。 「イヨー、ご両人! 我がギター倶楽部に何ぞご用でッ」 いつも女の子をからかっているチャカチャカ男が声を掛けた。ギター・アンサンブルでは、 「ちょっとギター、貸してくれる」 |
|
「これはこれは。して、女王様がお弾きになるので」
勘に触る男だ。 「違うわよ。彼が弾くの。ねー、どれか貸してよ」 この男は、チラッと弘樹の右手の指を見た。フムフムといった表情で一つのギター・ケースを持ってきた。 「これは倶楽部のギターだ。ケースにギター倶楽部のシールが貼ってある。シールがあるものは部の所有物。何本かあるけど、これが一番イイやつだ。これら以外は個人のものだから触らないように。皆、ギターを大切にしているからね」 ギターの話になると、チャカチャカさが消える。加奈子は、こいつも自分が好きなことになると真面目になるんだと少しは印象を良くした。 弘樹は、ケースからギターを出して眺めている。ギターを置き、楽譜が並ぶ棚の方に行った。何冊もあるギター曲集の中から一冊を取り出した。足台の高さを調整し、ギターを抱えてチューニングをしている。 結構、丁寧に音を合わせている。部室には六、七人いたが、皆、弘樹に注目している。チューニングをしているだけだが、シックリする。曲集をめくり、弾きだした。後で聞いたことだが十八世紀に書かれた典型的なギター・ソナタだという。 快活なテンポの速い曲。音が軽やかに飛びまわる。譜面をめくる時に演奏がちょっと中断した。チャカチャカ男が側にいた女の子に耳打ちした。彼女は弘樹の横に座わり、譜面をめくった。曲は流れていく。次の曲は、ゆったりとしたテンポ。音色も変わった。柔ら |
|
かいしっとりとした音。弘樹は、少しだが曲に合わせて体を動かしている。三つ目の曲は、一曲目よりもテンポが速い。良くも、あのように指が動くものだと加奈子は感心してしまう。大きな音、小さな音、硬い音、柔らかな音。最後は、六本の弦を親指でかき鳴らした。今までで一番大きな音……。
加奈子は、弘樹を素敵だと思った。この人は、自分の世界を持っている。 部室には拍手が起こった。チャカチャカ男も嬉しそうに手を叩いている。 「君、倶楽部に入らないか。セカンドの 「クラブを二つっていうのは無理ですよ。今は美術クラブが楽しいんだ」 「そうか。残念だなー。時間が出来たら、いつでも良いから遊びに来てよ。君なら歓迎する」 加奈子は、無我夢中で言った。 「弘樹、禁じられた遊び、弾いてっ!」 弘樹は躊躇っているようだ。ギター部の連中を見渡している。 「加奈子さん。その曲はね、ギターを持つとほとんどの人が弾く。だからじゃないけど、結構、弾き難いんだ」 加奈子は、じーっと弘樹を見ているだけだった。チャカチャカ男が言った。 「君の気持ちは判る。でも、僕も聴いてみたいな」 弘樹は弾きだした。 |
|
加奈子は、一つ一つの音が全く無抵抗に体の奥底に染み渡っていくような感じがした。転調した。スカッと明るい雰囲気。知らず知らずのうちに頬が緩むような気持ち。また、短調に戻る。加奈子は弘樹しか見えなかった。
二人は部室に戻った。加奈子は、多少、興奮気味だった。 「弘樹っ、君って凄いねー。驚いたわ。ねー、プロになりたいなんて考えたことないの」 「全くない。加奈子さん、僕は、自分には才能がないことを知っているから……。歌心ってやつがないんだ」 「だって、あんなに素敵に弾くじゃない。ギターっていいわね」 「高校の時だった。ギターが好きな友だちが三人集まったんだ。人と一緒にギターを弾くのは初めてだった。一人ずつ自分の好きな曲を弾くことにした。僕が最初だった。二人は、驚いていたよ。凄いってね。他の二人も弾いた。簡単な曲だった。でもね、今度は僕が驚いた。二人とも楽譜を見てない。暗譜しいてるんだ。僕は、音楽とは楽譜を見て弾くものだと思っていたからね。三重奏を遣ろうってことになった。僕が楽譜を持っていたので、その曲を弾くことにした。彼らにとっては初めての曲。また、驚いたんだ。彼ら、暗譜はできるけど初見が利かない。自分のパートを僕に弾いてくれって言う」 「弘樹、初見て何?」 「あー、そうか音楽を遣る人は皆知ってるけど。初めての楽譜を見て、すぐ弾くことなんだ。僕は難しい曲は無理だけど、大抵の曲に初見が利く。彼らは僕が弾くのを聴き、どんな曲かを知った上で楽 |
|
譜に向かった。でも、結局、三重奏は出来なかった」
加奈子は、懐かしそうに話す弘樹を見つめていた。 「やはり暗譜した方が良いに決まっている。練習したよ。初歩の初歩、ごく簡単な曲から覚えようとした。加奈子さん、僕は、自分が信じられなかったよ。譜面を閉じると曲も音符も、パーっと消えちゃうんだ。全く浮かんでこない。弾きなれた曲は指が覚えるとも聞いた。でも、指はじーっとしている。それが高校時代。今も思いつくとトライするけど結果は同じ。たまに彼らに会う。訊いてみたんだ、どうすれば暗譜できるのかってね。彼らは顔を見合わせ、一所懸命楽譜を見て、一所懸命練習する。そうすると自然と覚えられるが答えだった」 弘樹は、心なしか寂しそうな表情を見せた。 「加奈子さん、自然と覚えられるって聞いたときは悲しかったよ。僕には欠落したところがあるんじゃないかってね。ギターは大好きだ。でも、一人で楽しむものと決めたんだ。一生、続けると思うけど」 「弘樹っ、禁じられた遊びは、楽譜を見てなかったけど」 「ギターを持った人は、まず、禁じられた遊びを弾こうとする。僕は、そういうのって嫌だった。あの曲は、二、三年経ってから弾いてみた。加奈子さん、僕が楽譜なしで弾ける曲は、あの曲だけなんだ。たった一曲だけ。これも変な話だよね」 あんなに上手に綺麗に弾く。皆も感心していた。でも本人には諦めた部分がある。加奈子は、自分が美術系大學を諦めた頃を思い出した。自分の絵に対する周りからの評判は良かった。しかし、私には才能がないと思う。弘樹も音楽に対し才能がないと言う。自信を |
|
持つことは大切な事。
でも、自信を持てない二人。人間て難しい。 「弘樹、君の水彩画、結構素敵だけど、絵に対してはどう思っているの」 「ギターに対する気持ちと同じかな。絵心って考えると自分にはないと思うんだ。結局、自分の世界での楽しみ。今は、加奈子さんと一緒の世界かも知れないけど」 加奈子は、弘樹の頬をつついた。 三回生、最後の学期。二人は一年ほど付き合ったことになる。外泊はしないが、どちらからともなく求め合うようになっていた。 初めは、ぎこちなかった弘樹も、今は加奈子を幸せにさせる術を知っていた。 このような二人だったが、外泊以外にもう一つ暗黙の了解があった。加奈子の卒業とともに別れる。 この了解は、二人の結婚に対する考え方も影響していた。好きだからといって、それだけで結婚するものではない、いや、すべきではない。結婚は、経済的な面や社会的な面、将来計画…… これらに自信が持てなければするものではないとの考え方だ。二人は、どれ一つとして自信を持てるものはなかった。仮に結婚を考えたとしても、家族の了解、協力は絶対に得られない。 弘樹は、加奈子と付き合っていないことになっていた。当初、両親は弘樹を疑ったというが、弘樹は強い口調で否定を繰り返したらしい。一、二ヶ月経つと全く口にしなくなったという。弘樹の言う |
|
ことを信じたのだ。
しかし、加奈子は親に嘘をついている事を重荷に感じている弘樹を知っていた。 私が卒業したら別れれば良い。弘樹も同じ事を考えていた。二人とも、ある意味では自分たち二人の将来を諦めていた。 終わりのある付き合い。だが、この暗黙の了解は二人の楽しい毎日に影を落としてはいなかった。 最近、加奈子は、弘樹と同級生のクラブ員が気になっていた。その女の子は、いつも弘樹の近くにいたいようだった。二人が話していても、普通の同級生同士の雰囲気でしかないことは加奈子にも判る。弘樹も気の合う同級生として接しているようだ。加奈子がいても別に気遣う様子もなく、楽しそうに彼女と話しいている。 加奈子と弘樹が付き合っていることは周知の事実である。もし、彼女が弘樹に気があるのであれば、加奈子に対し何らかの形で態度に出るはずである。加奈子は、そのような態度を見たことはない。しかし、気になって仕方がないのである。 彼女は、早生まれだと言う。学年は同じでも歳は下になる。おっとりとしたお嬢様タイプ。言葉遣いや態度には、育ちの良さを感じさせるものがある。加奈子は、ふと彼女なら、あの両親は文句を言わないのではなどと考えてしまう。弘樹と二人の時に、弘樹が彼女のことを話題に出すことはない。加奈子が彼女の話をしても特別な反応はない。私って何を考えているのかしら。彼女の事ばかり意識しちゃって。 |
|
加奈子のゼミナールが長引いたことがあった。いつもなら部室にいる時間である。ゼミがやっと終わった。部室に顔を出すと弘樹と彼女、二人しかいなかった。何やら話し込んでいる。二人が加奈子に気付いた。
「加奈子さん」 二人は同時に声を出した。弘樹が、 「参ったなー、何も、二人同時に呼ばなくても良いのに……」 などと頭を掻きながら言う。そして二人して楽しそうに笑った。 加奈子は、その開けっ広げな二人を見ても何か胸騒ぎが起きてしまう。 「私のショルダー、その辺に置いてなかった?」 「ないですよ。加奈子さん、今日、ショルダー持ってたっけ」 「教室かしら。捜してみるわ。それから今日は家で用事があるの。私、その足で帰るわ。じゃーね」 嘘であった。加奈子は、何故、あんな嘘をついたのか歩きながら考えてみた。自分でも理解できない。しかし、二人を見た時、一瞬だが、私は邪魔なのではと感じたことは事実だった。何故、そんな事を……。二人には何もないはずと思いながらも感じる、この嫌な気持ち。 何をしていても彼女の事が頭から離れない。どうして弘樹は彼女に優しくするのと自問するたびにこみ上げてくる不愉快な気持ち。二人には何もないはず。 加奈子は、立ち止まった。 ――嫉妬。私は彼女に嫉妬している。 |
|
加奈子は、嫉妬という言葉を頭に浮かべた途端、息苦しさを感じた。息苦しさは、弘樹と二人の時も消えることはなかった。いつもと同じ弘樹であっても、彼女の事が頭から離れない。
加奈子は、四回生になる四月に美術クラブを辞めることにした。彼女がいるクラブから離れたかったのだ。就職活動を辞める理由にすれば良い。 加奈子は自分を卑怯だと思った。 弘樹に話した。 「弘樹、四月に入ったらクラブ辞めるわ」 「エッ! クラブを辞める!」 「そう、辞めるわ。就職活動もしなくちゃならないし……。それに大勢と居るのが煩わしくなったし」 「もう決めたの?」 「決めたわ」 「………」 弘樹は、信じられないといった顔で加奈子を見つめた。 「加奈子さんがいないクラブ……。寂しくなる。二人一緒の時間が少なくなるのかな」 「弘樹、二人の付き合いは、あと一年。弘樹もクラブを辞めるの。講義の時間以外は、二人きりになるの。いいでしょう」 弘樹は、一瞬、自分の耳を疑った。弘樹は加奈子が卒業してもクラブは続けるつもりでいた。思い出が残る部室の雰囲気は捨てたくないと思っていた。 長い時間、弘樹は黙っていた。加奈子も弘樹の気持ちは痛いほど |
|
判る。でも、自分の嫉妬心は消えない。加奈子も黙っていた。弘樹が嫌だと言ったらどうしよう。
「加奈子さん。考えてみれば、僕にとって、クラブ、イコール加奈子さんだったんだね。その加奈子さんがいないクラブにいても意味がないのかも知れない。判ったよ。一緒に辞めよう」 加奈子は、弘樹の顔をまともに見ることが出来なかった。私の顔は歪んでいるはず。 部員たちは、一様に目を見開き退部届けを見た。加奈子さんの退部の理由は判る。でも、何故、弘樹君まで。 弘樹は、はっきりと言った。加奈子さんがいないクラブは、僕にとって意味がないんです。部員たちは届けを受け取る以外になかった。 二人は、いつも一緒にいた。芝生に座り語り合う二人。雨が降れば、一つの傘に身を寄せ合い歩く二人。図書館で勉強をする二人。 もう、淀君とお小姓様などと噂する者はいなかった。むしろ暖かい目で見るものが増えていた。 「ねー、いいわね、あの二人。何か、いじらしいくらい」 「結婚するのかしら……。してもおかしくないわね。歳なんて関係ないわよね。あんなに仲良いんだもの。それに、彼。近頃、男らしくなったわね。私、思うの。私にも誰か現われないかって」 「無理よ。貴女は絶対に無理!」 |
|
「失礼ね! 貴女だって誰も居ないじゃない!」
「誰か、居ないかなー」 弘樹は親に車を買ってもらった。必修科目の単位は総て取っているし、それ以外の単位もかなり取った。成績も良い。両親は真面目に大学に通う弘樹を認めたのだった。 弘樹の家は、大學と加奈子の家のほぼ中間に位置していた。帰りは、まず加奈子を送り自分の家に戻るようになっていた。加奈子の家の近くには広い自然公園があった。無料駐車場もある。二人は、よく公園に行った。 公園には大きな木々があり、少し下ると細長い池がある。春は、桜吹雪。そして水面を埋める桜の花びら。夏には緑の葉を茂らせた木々が日陰を作り、騒々しいはずの蝉の声が耳に心地良い。 二人は、この公園で絵を描いたりギターを弾いたりした。夏は、公園にあるプールで、よく泳いだ。水から上がると見つめ合った。水に濡れ、太陽の光に輝く相手が眩しかった。 一日の予定は、すべて弘樹が決めた。加奈子は任せていれば楽しい一日を送ることができた。加奈子は幸せだった。 加奈子は外資系の商社に就職が決まった。父の口利きだった。 父が、こういう会社があるが行く気はあるかと聞いた。今まで、父は何事も加奈子の自由にさせていた。この様な事は初めてのことである。加奈子は、本腰を入れた就職活動をしていなかった。 |
|
親は見ていないようで見ていてくれた。加奈子は嬉しかった。弘樹のことは話していない。しかし、加奈子は両親が知っているような気持ちになっていた。
加奈子にとり、学生生活最後の正月が来た。子供じみているかとも思ったが、二人は、正月三日に和服で初詣をすることにした。 三日に和服を着ると母に伝えた。和服を着るのは、この四年間で初めてのことであった。 「加奈ちゃん。どうしたの和服なんて」 母はニコニコしながら聞いた。 「彼も和服だから……」 「まー、彼だって」 母は、それ以上何も言わなかった。始終、ニコニコしていた。 ――ふふ、親たちは知ってるな。 加奈子は何となく心弾む思いがした。 和服姿。二人は互いをジロジロ見ながら、結構、いけてるねーなどと笑いあった。神社は大勢の人で溢れていた。善男善女。そんな中にいることが二人には心地良かった。もうすぐ四月が来ると言うのに。 暗黙の了解が二人に重くのしかかって来ていた。 二月になった。弘樹が目を輝かせて加奈子のところに来た。 |
|
「加奈ちゃん、来月、伊豆に行こう。二泊三日の旅行」
エッ!、旅行? 加奈子はビックリした。加奈子は弘樹を信頼している。このような冗談を言う男ではない。しかし、喜びを隠しながら聞いた。 「弘樹、君、頭は大丈夫。二泊三日なんて……」 「苦労したんだ。細工は上々、仕上げをごろうじろってね。聞いてくれるかい。実はね、僕は高校の同級生と旅行するんだ。勿論、男だけどね。彼の家族も賛成してくれたんだ」 「弘樹、何言ってるの。ちゃんと説明してよ」 「まず彼に相談した。加奈ちゃんと旅行したいってね。彼は僕の両親とも親しい。と言うことは、どんな親かも知っている。彼と行く事にする。親にはそう話す。当然、親は、オーケーさ。しかし、彼の家族とも口裏を合わせておかなければならない。僕は、彼の両親とも親しい。そこで包み隠さず話したんだ。加奈ちゃんのことや親が反対していることをね。でも、最後に旅行くらいしたいって言ったんだ」 「大丈夫なの。判っちゃうんじゃない」 「子供として、親にまた嘘をつくことになる。でも、彼の家族は約束してくれたよ。青春にはそのような事があっても良いとね。加奈ちゃん、その時、僕は涙を流したらしいんだ。彼の家族も涙を溜めていた。でも妙な気分だったよ。彼の親の方が、僕を理解してくれてるんじゃないかとね」 「弘樹。行こうかっ!」 「行こうよ。絶対に!」 |
|
宿は民宿にした。予約は加奈子が担当。季節はずれであるため、すんなりと予約できた。一泊目は多々戸、二泊目は戸田。コースを決めるのは弘樹。ロード・マップに赤く線を入れていく。
二人は出発した。 伊豆とは言え、三月は寒いし、海の色も暗い。しかし、二人きりの車での旅。ただ二人で旅をしているだけで嬉しい。 多々戸の小さな入り江。夕暮れ時、二人は時間を忘れたように浜辺に座っていた。目の前に広がる海。聞こえるのは波の音だけ。民宿の親父さんが、湿っているかもしれないよとくれた線香花火に火をつけた。 シュパッ! シュパッ! と花が咲く。二人は、その花を黙って見つめていた。二人の頭の中はカラッポだった。 シュパッ! シュパッ! 暗い海を前に綺麗な花が咲く。一瞬の輝きを見せる花。 翌日は南伊豆を廻る。時間はたっぷりとある。所々で車を停め、海を景色を眺めた。二人の口数は少なくなっていった。重く重く暗黙の了解が覆い被さっていた。二人が考えている事は同じだった。 こんなに好きなのに……。 戸田に着いた頃から雨が降ってきた。民宿に荷物を置き、浜辺に出た。大した雨ではない。二人は、傘をささずに歩いた。黒く小さな湾。浜辺を歩いた。 晴れていれば夕日が沈む時刻。誰も居ない松林を抜け海の方に行 |
|
ってみた。黒く渦巻く雨雲。海も荒れている。時折、強く雨粒が落ちてくる。二人は、たたずんだまま荒れる海を眺めていた。辺りは暗く風も強い。何も話すことはなかった。ただ眺めていた。
黒い雲が空一面を覆っている。気付くと、はるか遠く、西の空の雲が動き出したようだ。すーっと雲が上がっていく。水平線と雲の間に切れ目ができた。 二人は、目を見張った。 その隙間から、半分ほど海に沈んだ太陽が顔を見せたのだ。一瞬のうちに夕日が足元に届いた。そして、今まで真っ黒だった雲が赤く染まっていく。 綺麗! 二人の手がきつく握られた。 加奈子は、このまま死んでも……と思った。 加奈子は、卒業式や謝恩会には出席しなかった。二人で居たかったのだ。すでに四月に入っている。入社式が近づいてきた。 加奈子も弘樹も暗黙の了解を口にできなかった。結婚は考えていない。でも、今すぐ別れなくても……。加奈子はそう思っていた。弘樹も同じだったと思う。 弘樹は、加奈子を入社式の会場まで車で送った。会場には大きな看板があった。昭和四十五年度入社式。何かが始まろうとする華やかな雰囲気。そのような中で弘樹の気持ちは沈んでいた。加奈子さんは自分と違う世界に入る。弘樹は辛かった。 入社式が終わると研修が待っている。泊り込みで一週間。弘樹に会う事はできない。離れている二人が連絡を取り合うのは容易では |
|
なかった。弘樹は加奈子の家に電話を入れることはできたが、加奈子には出来ない。ちょっと前までは大學に行けば二人は会えた。今は違う。もどかしい毎日だった。
研修開けの休みに二人は会った。一週間も離れていたのは初めての事だった。熱い思いが二人を包んだ。 休みの日に、二人は必ず会った。加奈子の会社は週休二日制だった。ウィークデイに会うと次に会う日を決めた。二、三日おきには会えていた。 しかし、弘樹の目に学生時代と違う加奈子が映りだしていた。 加奈子は、会社員に魅力など感じていなかった。どうせ決まった時間に出社し、決まった時間に帰宅する。たまに呑んでも上司、同僚の噂話だけ。出来れば楽をして給料を貰おうと考える人たち。 仕事に慣れてくると周りが見えてくる。 この会社では役職名をつけて名前を呼ばない。社長に対しても、さん付けで呼ぶ。皆、キビキビと体を動かしている。指示を受けたたからと言って、単に、はい判りましたではない。納得できるまで内容を確認する。一旦、納得すると皆、行動は早い。ダラダラした雰囲気はなかった。会議での議論、討論も激しい。最終結論はその仕事の責任者である者が決めるが結論を導き出すまで、参加者は、皆、同じ立場で話し合う。はっきりと賛成、反対の意見を言う。 時間に対する考え方も徹底していた。定時に仕事を始め定時に終わる。余程のことがない限り残業はしない。時間内に仕事を終わらせる風土がある。個々人が自己管理をきちんとしている。かと言って、冷たい雰囲気はない。時間内であっても其処ここで笑い声が起 |
|
こる。
加奈子は、このような雰囲気の中にいる自分が嬉しかった。新鮮な感覚に刺激を受けていた。皆と同じように仕事を進められる自分に早くなりたい。仕事の内容も楽しい。ここで仕事をすることも楽しい。自分のためには残業もした。 加奈子は、今までとは違う自分を見つけていた。 弘樹の事は常に頭にあった。会えば楽しい。加奈子は、会社での出来事ばかりを弘樹に話すようになっていた。弘樹は、ただ聞いているだけでしかない。たまに弘樹が大學の話をしても加奈子は、つまらなそうな顔をした。 勤め出してから三ヶ月ほど経った。加奈子は仕事に夢中になっていた。 そんなある日、加奈子に電話が入った。気付くと既に七時半。電話は弘樹からだった。会社の電話番号は知らせていた。しまった、今日は弘樹に会う日だった。 「弘樹っ、ご免。まだ、手が離せないんだ。今日は無理。ご免。明日は、大丈夫だと思う。七時に行くから待っててよ」 結局、翌日も同じだった。 「今日もご免。ちょっと無理なんだ。四日も空いちゃうけど、今度の土曜日にして」 弘樹は、加奈子が自分から離れていくのではと思った。 弘樹はどのクラブにも所属しなかった。講義のない時間は、クラスの仲間と過ごすようになっていた。優秀な学生が集まるクラスで |
|
ある。世界情勢、経済、政治……。堅い話ばかりだ。美術クラブの部室には顔を出しづらい。たまに、ギター倶楽部に顔を出し、合奏などを楽しむのが潤いと言えるぐらい。近づいて来る女子学生もいたが、全く興味が湧かなかった。
あと一年と八ヶ月ほどで卒業。でも、その間、このようなつまらない学生生活を送るのだろうか。弘樹は、空虚な思いに囚われていた。 加奈子は、弘樹に会えば楽しかった。しかし、二人の会話の接点がずれ出したことにも気付いていた。二人が過ごす環境が違うのだから……、当然といえば当然ね。 五月の連休。例の手を使い、二人は九十九里浜に行った。伊豆の時とは違い、明るく輝く太陽。太平洋も綺麗な青を見せている。白い砂で埋まった広い砂浜。二人はたたずみ、海の遠くを見つめた。風になびく加奈子の髪。流れた髪が弘樹の頬に触る。 「ねー、この浜辺を車で走らない」 車で乗り込んだ。運転したのは加奈子だった。タイヤが砂に埋まり動けない。近所の人たちが出てきた。 「今まで女の人が此処を乗り切った事はないよ」 皆、笑いながら手伝ってくれた。弘樹と一緒だと、このような事が起こり楽しい。 東京に戻った時、二人は互いに相手を気遣っていることに気付いた。疲れる。いつもの公園に行き駐車場に車を停めた。二人は車の |
|
中で眠ってしまった。加奈子が目を開けると、弘樹は、まだ眠っていた。疲れきった表情で眠っている。弘樹、そんなに気遣う必要なんかないのよと心の中で呟く。
弘樹が目を開けた。加奈子が覗き込んでいる。 「加奈子さん…… 眠っちゃったんだね。どうしたんだろう……運転に疲れたのかな」 弘樹は下から加奈子の顔を見たが、そこに、かなり大人になった加奈子の表情を見た。 二人が会う回数は減っていたが、加奈子の頭には、いつも弘樹がいた。 二日後が弘樹の誕生日だ。七時にいつもの場所で会う事になっていた。お給料を貰う身になった加奈子は、プレゼントを奮発しようと思っていた。この日は仕事が忙しかった。明日、買いにいこう。 当日。まだプレゼントを買っていない。買いに行く時間がなかったのではない。加奈子は仕事をしていた。楽しいのだ。夕方になった。もう買う時間はない。ま、いいか、豪華な食事を奢ろう。 気付くと七時半になっていた。いけないっ。でも弘樹からの電話はない。いつもなら、約束の時間が過ぎると会えるかどうか電話してくるのに。加奈子は急いで仕事を終え、表に出た。タクシーを使えば十分で着くはずだ。 加奈子が約束の場所に着いたのは八時半頃だった。タクシーを使ったのは失敗だった。 |
|
弘樹は下を向き、座っていた。
「ご免。遅れちゃった。タクシー使ったのがいけなかったわ」 弘樹は、ちらっと目を向けたが、また、俯いてしまった。 「弘樹。君の誕生日なのに遅れたりして……、本当にご免。ねー、弘樹、許してくれる」 弘樹が顔を上げた。 「加奈子さん」 青ざめた顔で言った。 「加奈子さん、来てくれただけで、僕は嬉しい。でも、今日は、このまま帰りたい」 弘樹は、ゆっくりと立ち上がり、加奈子を見ずに出て行こうとする。 「弘樹ッ!」 加奈子は、周りの客が驚くほどの大きな声で弘樹を呼んだ。弘樹は振り向きもせずに姿を消した。 加奈子は追いかけることが出来なかった。次に会う日を決めずに弘樹と別れたのは、この日が初めてだった。 もう連絡はくれないかな。弘樹、ご免。振られたと思ったかな。 弘樹からの連絡は途絶えた。加奈子は、仕方がないと頭の中で繰り返していた。不思議な事に悲しいとは思わなかった。 相変わらず仕事に夢中になっていた。 社員はキビキビと仕事を進める。このような仕事中心の会社でもカップルは出来上がっていく。やはり女性はチヤホヤされれば嬉し |
|
いもの。だが加奈子は違った。実に明るくテキパキと仕事をこなす加奈子に、言い寄る社員も何人かいた。しかし、加奈子は全く興味を示さなかった。
社内では、男嫌い? 既に恋人が? などと囁かれることもあった。弘樹の事は頭から消えている。加奈子は、今、仕事そのものが楽しかった。 あれほど道路を彩っていた落ち葉も消え、コートが欲しくなってきた。気付けば十一月。加奈子は、ふと、文化祭を思い出した。遊びに行きたい気持ちもあったが、ちらっと弘樹の顔が浮かんだ。止めておこう。 加奈子の仕事は順調だった。新入社員でありながら重要な仕事も任されるようになっていた。評判も良い。しかし加奈子は会社からの評判など、どうでも良かった。楽しい時間を仕事に見出せれば、それだけで良かった。昇進も昇給にも余り関心がなかった。 仕事の関係で、ある会社の社員と軽い付き合いを始めた。たまに会って食事をする程度。会話も楽しい。 仕事に夢中になるとスケジュール表に書かれた日付は、ただの数字でしかなくなる。そこからは季節感など出てこない。加奈子は過ぎ行く季節を忘れていた。 ふとカレンダーを見た。 ――十一月。あら、もう一年が過ぎたんだわ。 |
|
加奈子は、彼を文化祭に誘った。弘樹を思い出したが、もう良いだろうと思った。それに必ず会うとは限らないし、会ったとしたら……。その時は、その時。それに、キャンパスの連中も私のことなど覚えていないはず。
二年ぶりの大學。加奈子は、饒舌すぎるほど彼に話し掛けた。彼も、そんな加奈子を可愛いと思うのか、相づちを打ちながら聞いている。 「あそこにテントがあるでしょう。私がいた美術クラブでは焼鳥屋を出したの。楽しかったなー」 テントに近づいた。 弘樹が立っていた。 加奈子は別に驚かなかった。まさかとは思っていたが、こうなると予感めいたものも感じていた。二人は、チラッと目を合わせた。加奈子も弘樹も無意識のうちに微かだが頷いたようだった。それが何を意味するのか、何となく判ったように思った。 加奈子はテントを離れた。変ね、弘樹は美術クラブを辞めたはずなのに、なぜ模擬店のそばにいたんだろう。気になった。 文化祭を一通り案内した。彼も楽しそうだった。明日は朝が早いと言っていた。加奈子は駅まで送った。 「私は、また大學に戻ります」 「じゃあ、また」 二人は言葉を交わし別れた。 加奈子は大學に急いだ。テントの前で弘樹が待っていた。 |
|
「お久しぶり」
「久しぶりだね。元気そうだ。さっきの人、新しい彼氏?」 「あら、そんな言い方は止めてよ。たまに食事をするくらいなんだから」 「……戻ってくると思ってたよ。走って来たんだね」 「弘樹さん……。弘樹も絶対に待っててくれると思った」 互いの姿を見た。目を合わせ、ふっと笑顔で見つめ合う。 二年近くが過ぎているのに、このように向かい合っていると昔のままの雰囲気を感じる。安らいだ気分。 「弘樹、もう、文化祭は見たんでしょう」 「いや、まだ見ていない。加奈子さんは彼と見たんでしょ」 「あまり印象に残ってないな」 「じゃー、一緒に廻らないか。そうして欲しい」 「うん、そうしよう」 二人は並んでキャンパスを歩いた。昔のままの二人がいた。 「加奈子さん、お願いがあるんだ」 「何? 言ってみて」 「僕は、あと三、四ヶ月で卒業する。僕が大學にいる間は、男の人と大學にくるの止めて欲しいんだ。まだ、二人の事を覚えている人がいるからね。僕は、あれから、ずーっと一人。加奈子さん、僕にもほんのちょっと面子がある。僕が言いたい事判るかな」 「判る。大丈夫よ、当分、此処には来ないから。今日は気が利かなくてご免ね」 「いや、謝らなくてもいいよ。加奈子さんは気付くのが、ちょっと遅いところがある」 |
|
弘樹は小声で言った。
「えっ、何?」 「い、いや、何でもない」 二人は、ギター倶楽部が演奏をしている部屋に入った。 「弘樹、弾いてるの」 「たまにね。ギターはいいよ。一生続けると思う。加奈子さん、絵の方は?」 「描いてないの。仕事一途。何でこんなに仕事が好きになっちゃったのかしら。人間てどうなるか判らない。ねー美術クラブの展示、見に行かない?」 「そうだね。懐かしいな」 「クラブには顔を出してるの」 「全然。僕の中では、あのクラブは、とっくに終っている」 「でも、さっきはクラブの焼鳥屋にいたけど……」 「不思議なんだよ。手伝ってくれって言われてね。僕は、どこのクラブにも所属してない。最後の文化祭だし…… 一回生の頃を思い出し手伝ったんだ。懐かしかったよ」 「そうだったの」 加奈子は、二人が退部届けを出した頃を思い出した。 「弘樹。あの時は、ご免ね」 「えっ、あの時って?」 「二人で辞めようって言った事……」 「何だ、そんなことか。加奈子さんが、今日、ご免て言ったのは、これで何度目かな。僕は全然気にしてない。これも何かの流れの一 |
|
つだと思っている」
美術クラブは、図書館ロビーを使って展示していた。加奈子は、幾つかの絵を見たが興味が湧いてこなかった。 ――私、もう絵を描かないのかしら。あんなに好きだったのに。私って適当なところがある。真剣になるのは一時的なのかしら……。 弘樹は時間をかけて見ている。そんな弘樹の姿を見ていて、加奈子は、あっ! と声を上げた。 今まで気が付かなかった。さっきの彼は弘樹に似ている。彼の方が背は高い。しかし雰囲気、しぐさなど弘樹にそっくりだった。加奈子は、少し離れて弘樹を見つづけた。弘樹が振り向いた。 「加奈子さんは、さっきから余り絵を見てないね」 「ふふ、あんなに夢中になって描いていたのに……。何だか感じるものがないの。私って、続かないのかしら……」 弘樹は、少し強張った顔で言った。 「そうかも知れない。でも、夢中になっている時の加奈子さんは、本当に素敵だった」 加奈子は、この言葉が絵に対するものなのか、弘樹に夢中になっていた頃の自分なのかが判らなかった。 二人は、キャンパスを見た。今日は最終日ではない。キャンプ・ファイヤーの火は焚火程度のものだった。二人は、その炎を黙って見ていた。しかし、互いに何を思い出しているかは判った。 たった三年前なのに遠い昔のことのように思える。加奈子の頭の中では、弘樹と楽しい日々を送っていた頃の自分と、そして、今、仕事に喜びを感じている自分が走馬灯のように廻っていた。 |
|
「加奈子さん、送るよ」
「もうそんな時間? あら本当、そろそろ帰らないと……」 弘樹の車に乗った。車は変わっていた。 「買い換えたの」 「親父からの就職祝い」 「大きいわね」 「そう。親父は、世間体を気にするからね。これ位の車じゃないと社会人として見っともないって言ってたよ」 「弘樹、ご免。君、就職決まったんだ。こんな大切な事、訊かなかった」 「加奈子さん、また、ご免ですか。一年ちょっと前から、ご免、ご免て言われ続けている。もう、そのご免は止めて欲しい」 「ご免。あっ、またか。ご免。駄目ね、私って」 「あーあ、加奈子さん、堪忍してよ」 今日、初めて弘樹は笑った。 「就職先は?」 「うん。上級試験に受かったんだ。外務省に決まった」 「凄ーい。弘樹って、やっぱり頭、イイんだ。おめでとう」 「ありがとう。でも、加奈子さん、これで良いのかどうか判らないんだ。親父の言いなり……」 さっきの笑い顔は、なくなっている。 「ご両親は、お元気?」 「あー、元気だ。全く、相変わらずだよッ」 弘樹は吐き捨てるような強い口調で言った。 |
|
加奈子は、言葉に詰まってしまった。
懐かしい公園に着いた。車を降りて歩くことにした。まだ、それ位の時間はある。 二人は暗い公園を、ほとんど口を聞かずに歩いた。以前は手をつなぎ歩いた。今日は肩が触れるか触れないほどの間をあけて歩く。 弘樹は両手をポケットに入れている。たまに下を向いたり暗い空を見上げたりしている。 加奈子の胸には、昔のこと今のことが無造作に思い出として飛び出ていた。そう、現在のことも思い出として……。それらが入り混じり渦を巻いていた。私は……、どっちが本当の私なのかしら。 ふと、弘樹の手に触れてみたいと思った。 「加奈子さん……」 公園に来て初めて弘樹が口を開いた。 「さっ、帰ろう。送るよ」 「弘樹、私、ここから一人で帰る」 「エッ、何故?」 「うん。何となく……そうしたいの」 加奈子は弘樹と付き合っていた頃の出来事が、これほど鮮明に思い出されるとは考えてもいなかった。もう終わったこと。それに、私が弘樹から離れたんじゃない。加奈子は一人で帰ることで、はっきりと気持ちを整理したいと思っていた。 二人は車に戻り中に入った。無言だった。口を開いたのは加奈子の方だった。 |
|
「弘樹、元気でね」
「加奈子さんも……」 二人は握手をした。加奈子は車から降りた。弘樹がエンジンをかける。加奈子は車が走り去るのを見送ろうと思っていた。車が動き出した。 「危ないっ!」 弘樹は、ハンドルを切り間違えたのか隣の車にぶつかりそうになった。弘樹は動揺している。 車が走り出した。加奈子は手を振った。そして、ふっと空を見上げた。 「あーッ!」 加奈子は大声を上げた。 「駄目ッ! 弘樹、行かないでっ!」 加奈子は車を追いかけた。大声で叫びながら……。 「弘樹ッ! 弘樹ッ!」 加奈子は、自分にとり一番大切なものが走り去っていくように思えた。 「弘樹ッ! 待ってーッ!」 空しいことだった。車は速度を上げ走り去っていく。追い着くはずもない。だが加奈子は、なおも追った。車は、もう見えない。 どれほど追いかけただろうか。 「弘樹……」 加奈子は、小声でつぶやき立ち止まった。涙が溢れてきた。加奈 |
|
子は、涙を拭おうともしないで呆然と立ちすくんでいた。
「あー!」 加奈子は地面に泣き伏した。地面にうずくまり大声で泣きつづけた。どうしよう、どうしよう。頭の中には、この言葉しか出てこなかった。 翌日、加奈子は会社を休んだ。 カラッポな頭の中には弘樹だけがいた。会いたい。もう一度だけで良い、会いたい。弘樹が会ってくれない事は判っている。 もし……、もし仮に会えたとしても、加奈子は何を話したいのか判っていない。でも会いたい。加奈子の心を占領しているのは、この思いだけであった。 辛い日々が続いた。せめてもの救いは仕事をしている時だけであった。仕事をしていると、あの辛い思いは薄らいでくれる。しかし仕事の時間は八時間だけ。それ以外の時間は、総て弘樹への思いだけであった。 気晴らしにと同僚たちと呑んでみた。だが、思いは消えない。消えるどころか、この居酒屋のどこかに弘樹が居るのではないかなどとあり得ないことが頭に浮かんだりする。 声を掛けてくる社員もいたが、加奈子は、全く関心も興味も湧いてこなかった。 辛いのは夜中だった。昼間の弘樹は顔を見せてくれる。でも夢の中では後ろを向いて遠くにいるだけ。顔も見せてくれない。 |
|
――弘樹っ!
加奈子が、いくら叫んでも、こっちに来てくれない。その度に胸が締め付けられる。ハッ! と目が覚める。暗い部屋があるだけ。 誰もこのような加奈子に気付いていない。家族も同じだった。加奈子は誰にも苦しい胸の内を話さなかった。 消えて欲しい。お願いだから、早く消えて欲しい。 いくら願っても辛い思いは、消えてはくれなかった。加奈子の頭に、一つの言葉が浮かんできた。 ――失恋。そうなんだ。もう無理なのに会いたいと願う気持ち。 弘樹も失恋したと思ったんじゃないかな。でも、今は私の方が、こんな辛い思いになっている。ふふ、二人とも失恋したんだ。 自嘲気味につぶやいた。 ――こんなのって変。 加奈子は、ものごとに夢中になるが長続きはしない。辛い思いも長続きしない事を祈っていた。だが、三年が過ぎたというのに思いは募っていくばかりだった。 「カタツムリちゃん。今日ねー、私、ある人から葉書を貰ったの。その人ねー、結婚したんだって」 加奈子は、今朝、弘樹から結婚したことを知らせる葉書をもらっていた。その葉書には、ありきたりな内容が印刷されていた。 |