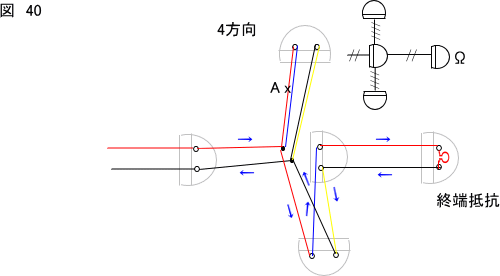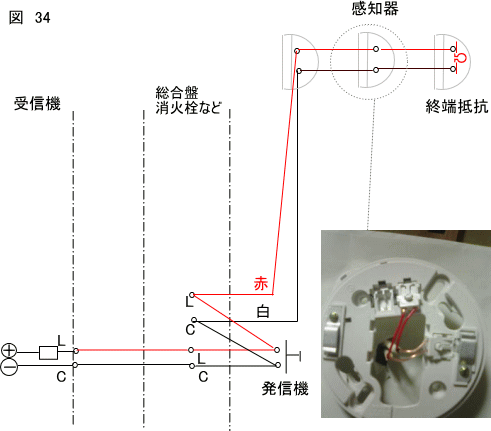
現在、当サイトは引っ越し作業中です。
しばらくはブログ図解火災報知設備工事方法をご覧ください。
新しい引っ越し先はブログでお知らせいたします。
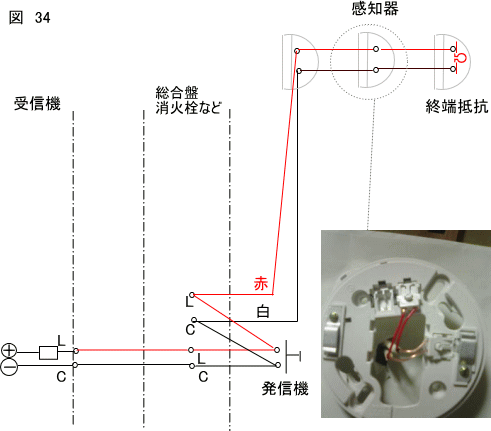
感知器間の配線に4芯の電線を使用するケースは前述しましたが、
図 34のように2芯の電線を使用する場合もあります。その場合図のように、受信機から配線された電線を発信機に接続し発信機の2次側に感知器を接続し最終の感知器に終端抵抗を接続することで送り配線が可能になります。
図 35のように発信機に終端抵抗を接続してしまうとA地点で断線しても常時C、L間に終端抵抗が入っている状態なので受信機が断線を検出できません。
このような結線は誤りです。
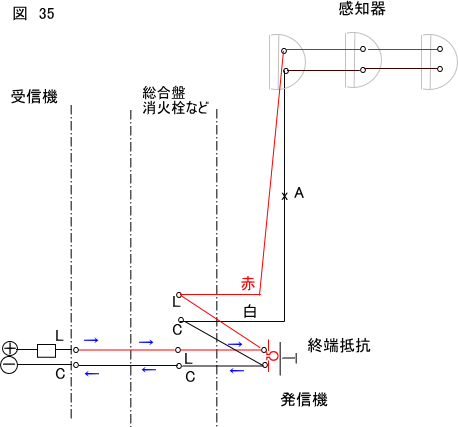
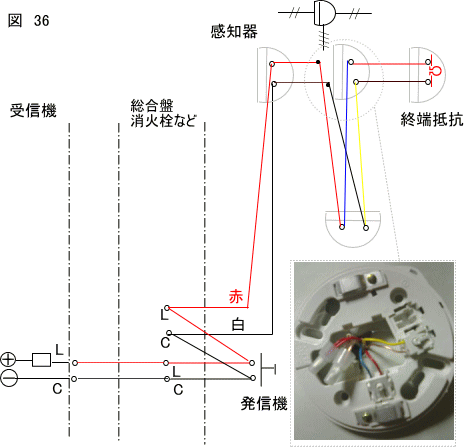
2芯の電線を使って感知器の結線をする場合でも、図 36のように3方向から配線されている場合はそのうち1方向は4芯が必要になります。図のように結線することにより電線が一箇所でも切れた場合に受信機が断線を検出できる配線(送り配線)が出来るからです。
図 36−2のように結線しても同じことです。
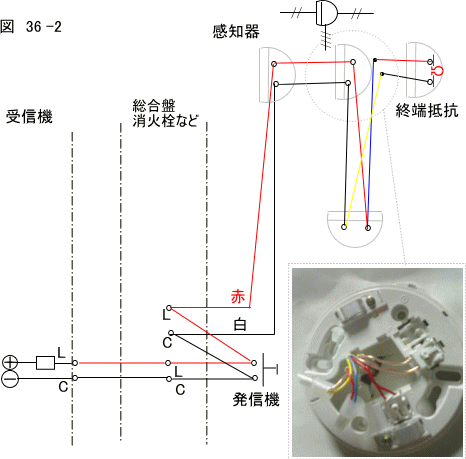
図 37のように結線してしまうと、A地点で断線しても常にLから出た微弱電流が終端抵抗を通過しCに流れているので受信機で断線が検出できません。
このような結線は誤りです。
感知器ベースの一つの端子に3本以上の電線が結線されていたり、終端抵抗の場所以外で1本しか結線されていなのは誤りです。
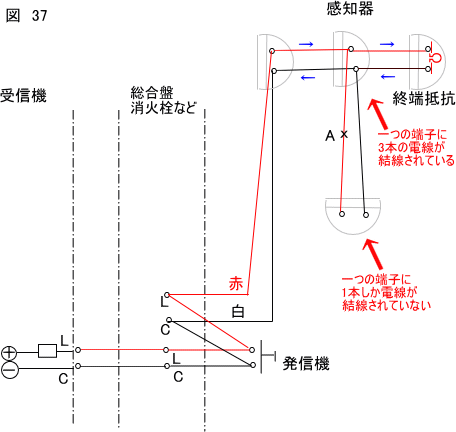
2芯の電線を使って感知器の結線をする場合でも、図 38のように4方向から配線されている場合はそのうち2方向は4芯が必要になります。図のように結線することにより電線が一箇所でも切れた場合に受信機が断線を検出できる配線(送り配線)が出来るからです。
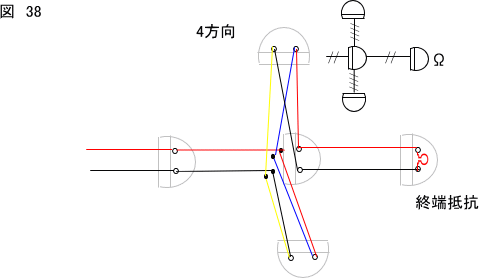
図 39のように結線しても同じことです。
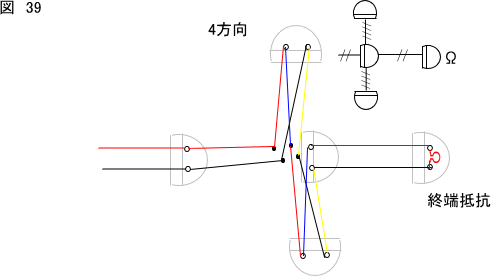
図 40のように結線してしまうと、A地点で断線しても常にLから出た微弱電流が終端抵抗を通過しCに流れているので受信機で断線が検出できません。
このような結線は誤りです。
感知器ベースの一つの端子に3本以上の電線が結線されているのは誤りです。