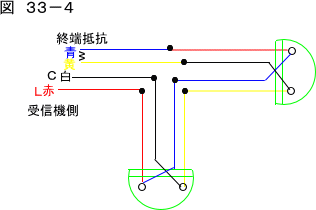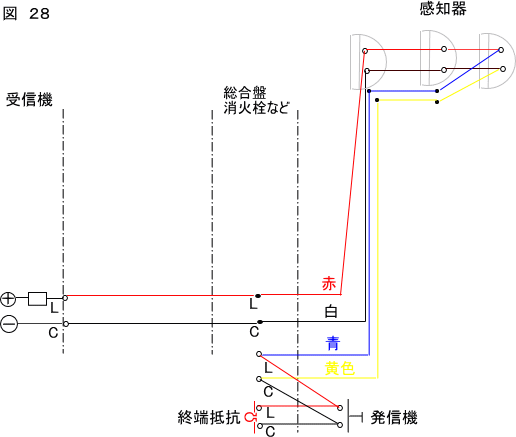
現在、当サイトは引っ越し作業中です。
しばらくはブログ図解火災報知設備工事方法をご覧ください。
新しい引っ越し先はブログでお知らせいたします。
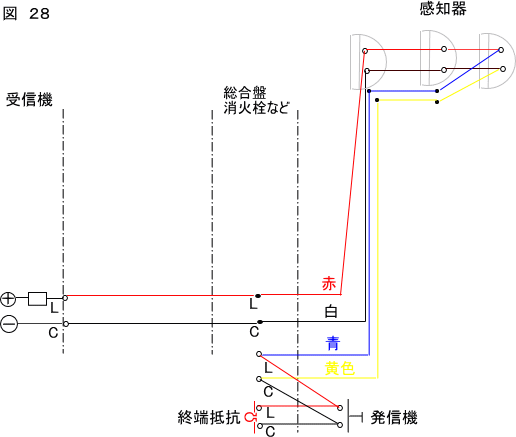
図 28は一番基本的な結線です。
通常、配線は受信機から発信機(総合盤)、発信機(総合盤)から感知器に流れ、発信機から感知器は赤、白、青、黄の4色の電線が一束になった4芯(4C)の電線(図 28−3)を使います。赤、白を感知器に接続して最後の感知器から青、黄を使い発信機に接続し、終端抵抗は発信機の2次側に接続します。
一般的に赤と青をL(+)、白と黄をC(−)に用いることが多いです。

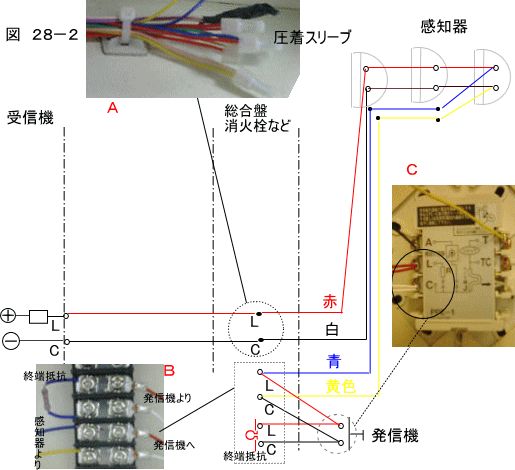
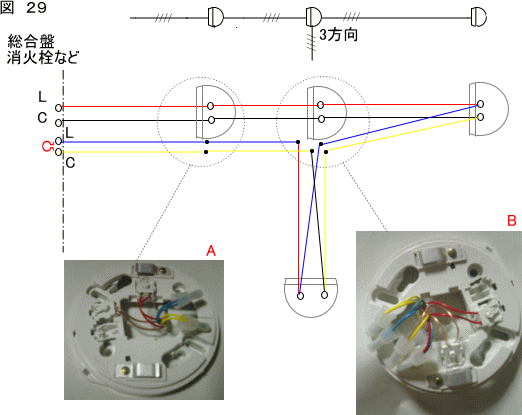
図 29のように電線が3方向から配線される場所で感知器を結線する場合
Bが一例です。また、図 30のAのように結線しても全く問題ありません。
重要なのは感知器の電線が一本でも切れた場合に受信機で異常を知らせる事が出来るということです。
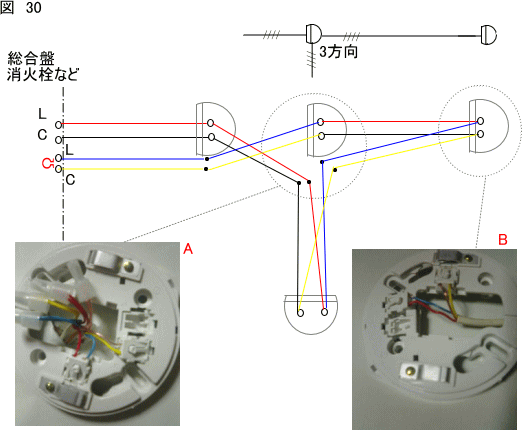
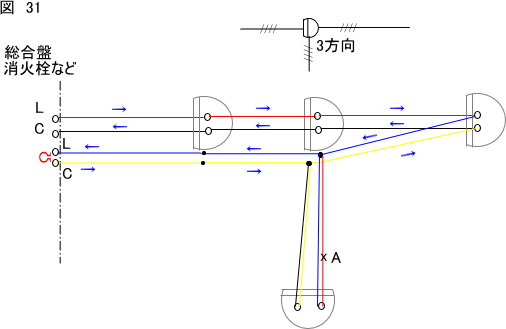
図 31は結線の間違った例。電線が3方向から配線されている場所を図のように結線してしまうとAの地点で断線しても LとC の間に終端抵抗Ωが入るため受信機で断線が検出できません。
P型の感知器工事を行う場合、終端抵抗の入る場所以外の感知器ベースの1つの端子には、結線される電線は必ず2本です。また圧着スリーブで電線を接続する場合も同様で、1つの圧着スリーブで接続される電線も必ず2本です。3本以上の電線が感知器の1つの端子に接続されたり、1つの圧着スリーブで接続されることはありません。
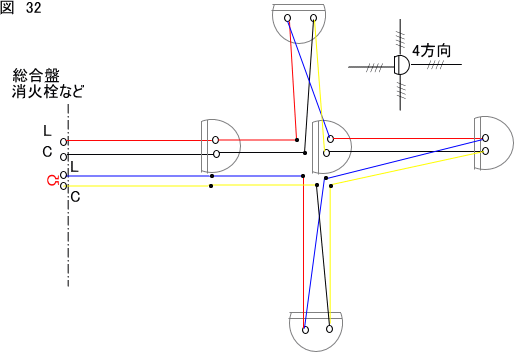
図 32は電線が4方向から配線されている場合の結線の例。
図 33のように結線してしまうとA B C の場所で断線しても受信機が断線を検出できないので誤りです。
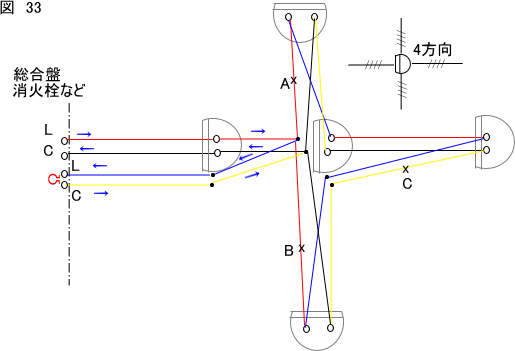
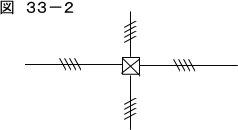
感知器回路の配線の都合上、図33−2のようなジャンクションが出来てしまうことがあります。ジャンクションの場合も図 33−3−2のように送り配線で結線します。
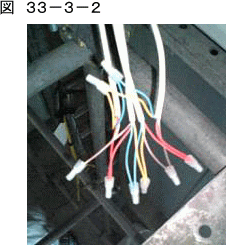
解りやすく図に表したのが図 33−3ですが、このように結線すればどこで断線しても受信機で警報が出せるわけです。
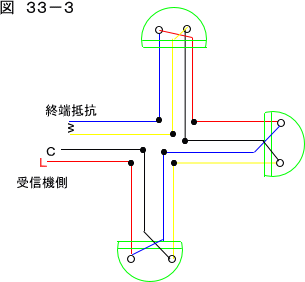
電線が3方向のジャンクションでは図33−4のように赤と青、白と黄色の電線が圧着されるのがポイントです。