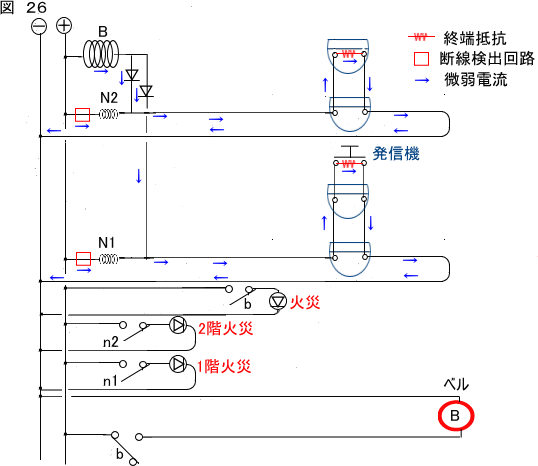
図 26のように各回路の感知器の最後には終端抵抗(Ω)というものを接続する決まりがあります。
終端抵抗とは微弱な電流だけを流す性質があります。
電気の特性として+と−の間に抵抗を接続するとその回路全体に流れる電流が微弱になりリレーB,N1,N2は作動しません。
感知器の最後に終端抵抗を接続することにより受信機内部にある断線検出回路に常時微弱電流が流れることになります。受信機は断線検出回路に微弱電流が流れている状態を「正常」と判断し、微弱電流が流れなくなった状態を「異常」と判断して音や表示灯で知らせます。(図 26−2)
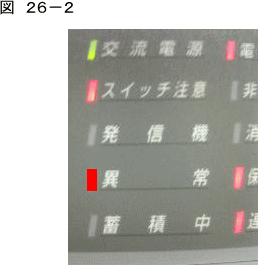
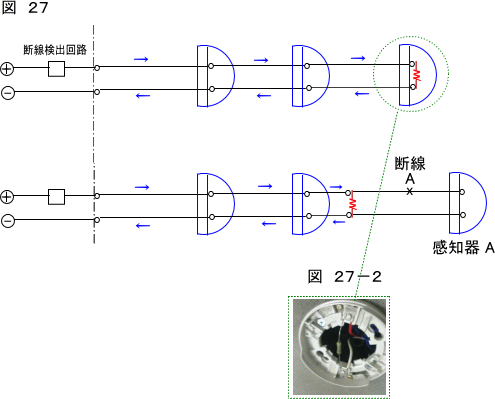
図 27は断線検出回路と終端抵抗の接続例を簡単に描いた例です。上の段は終端抵抗を感知器の最後に接続している例です。このように接続することにより感知器の電線が一箇所でも断線すれば受信機は断線を検出し「異常」を知らせることができる。
感知器は送り配線で結線することとありますが、送り配線とは「感知器の電線が一箇所でも断線した場合に受信機がそれを検出できるような結線」をいいます。図の下の段では終端抵抗を回路の途中に入れてしまっているのでAの場所で断線したとしても微弱電流は断線検出回路に流れているので受信機は断線を検出できない。また断線した状態では一番右の感知器Aが火災を感知してもベルや表示灯を作動させることができず火災の発見が遅くなり大変危険である。
このような結線は間違いであり消防法違反です。