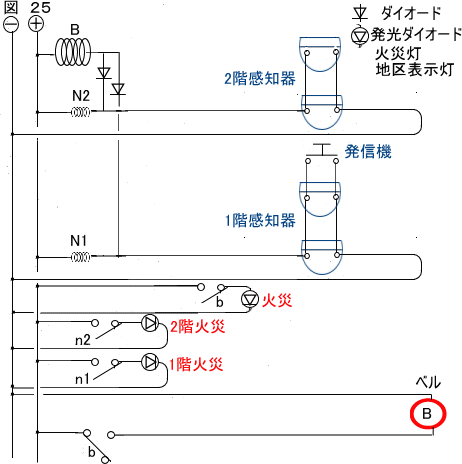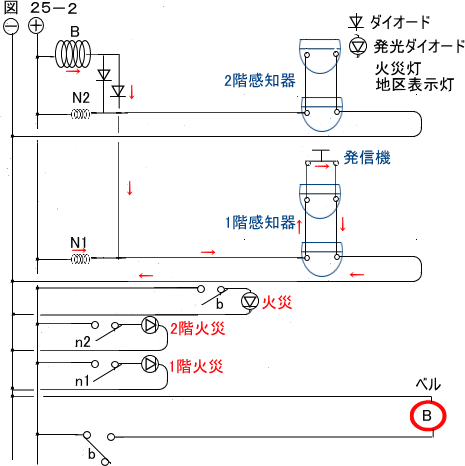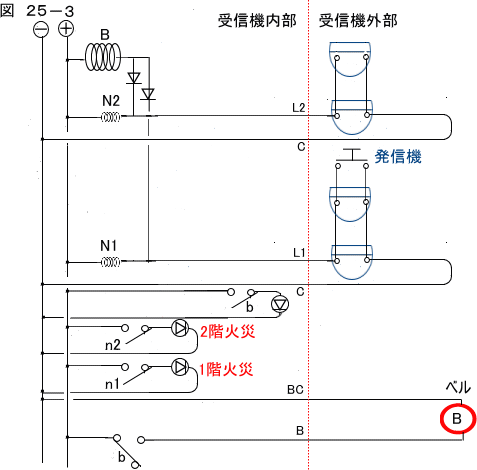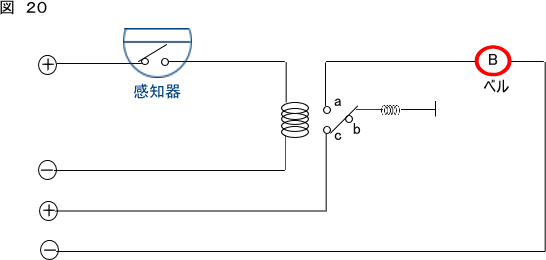
図 20のように感知器、リレー、ベルが接続されていると、
感知器が温度変化を感知し内部の接点が閉じる→
リレーに電流が流れる(磁石に変化する)→
接点CとAが閉じる→
ベルに電流が流れ鳴動する。
以上は図19−2でも説明しました。
一つの警戒区域には複数の感知器が設置されているのが普通です。
どの感知器が作動してもベルが鳴動しなくてはなりませんから、複数の感知器を設置する場合は図 21のように接続します。
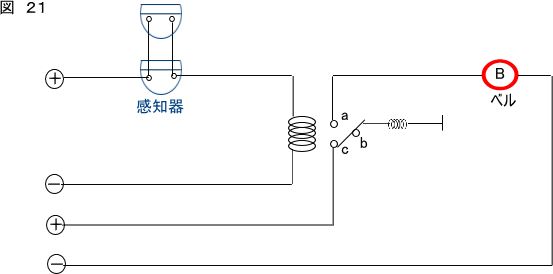
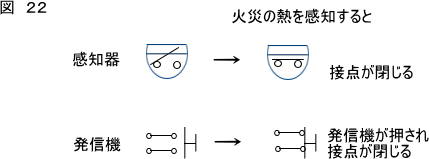
感知器は温度変化などに応じ自動的に接点が閉じるのに対し
発信機は火事を発見した人が手動で接点を閉じる。図 23のように接続することにより、どの感知器が作動しても、発信機が押されてもベルを鳴動させることが出来る。
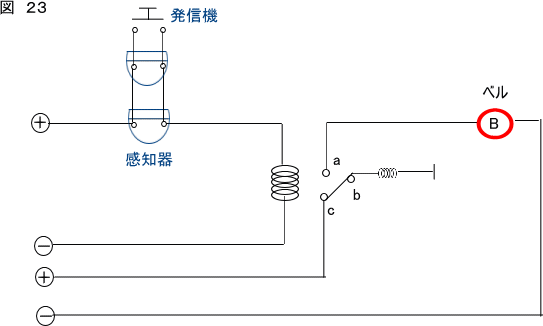
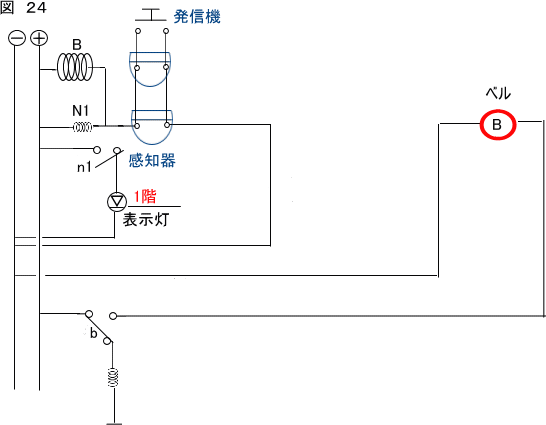
図 24のように機器が接続されていると感知器か発信機が作動したときに
リレー B とN1が作動し、接点bとn1が閉じ、ベルが鳴動し、表示灯が点灯することがわかる。