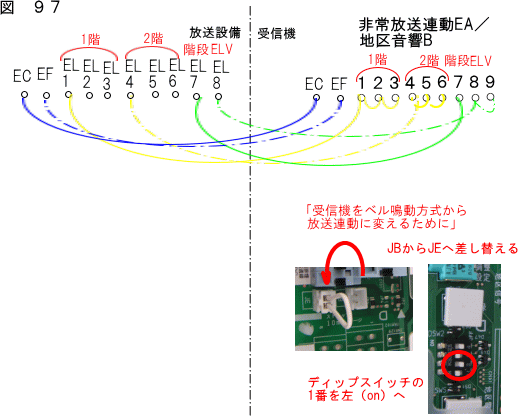
現在、当サイトは引っ越し作業中です。
しばらくはブログ図解火災報知設備工事方法をご覧ください。
新しい引っ越し先はブログでお知らせいたします。
放送連動の接続と設定 受信機パナソニック社 BVF3325H 放送設備TOA社 FS991
例
火災報知設備の警戒区域の1・2・3が「1階」、4・5・6が「2階」、7が階段、8・9がELV、
非常放送の1・2・3が「1階」、4・5・6が「2階」、7が「階段」、8が「ELV」の例。
接続の例
図97のように接続する。
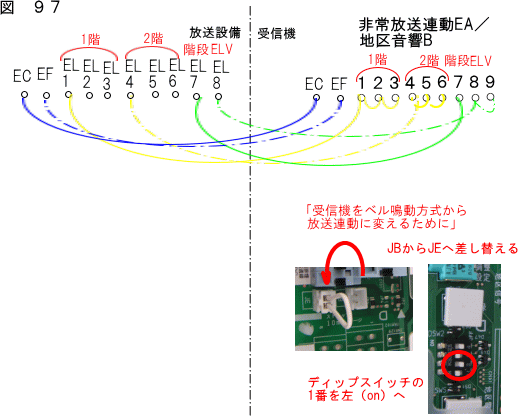
放送階選択スイッチの設定
まず最初に、何番と何番の回線が同じ階に存在しているのかを非常放送用のアンプに認識させる必要があります。(図 97-3)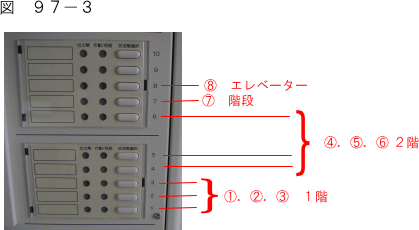
階別情報設定
放送アンプの階情報設定モード画面で以下のような設定をおこなう。 (図 97-2)
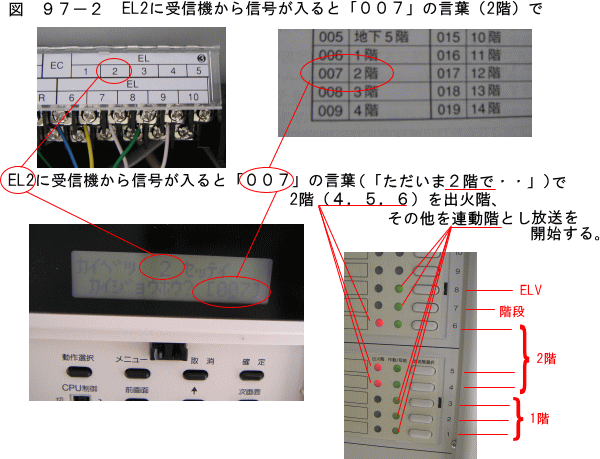
自動火災報知設備が非常放送設備と連動する場合の例です。
まず、非常放送アンプの特性ですが、図 83は非常放送アンプの一例で、ほとんどの非常放送アンプにはEC、EF、EL1、EL2、・・・といった端子があります。
非常放送アンプの外部でECとEL1が短絡するとR1のリレーがECとEL2が短絡するとR2のリレーが・・・作動するのがわかります。
非常放送アンプ本体の設定により、図のようにR2のリレーが作動したときは「只今、2階の火災報知器が作動しました。・・・」と音声が流れるように色々と変更が出来ます。現場の構造に見合うように非常放送アンプを設定する必要があります。
今回はR1で「1階の・・・」、R2で「2階の・・・」、R3で「階段の・・・」、R4で「エレベーターの・・・」、と音声が流れるように設定しました。
また、ECとEFが短絡することによりREFのリレーが作動することがわかりますが、このリレーが作動すると発報放送が省略され火災放送(「火事です、火事です、2階で・・・」)が流れたり、発報放送と、火災放送との間合いが省略されるような動作に切り替わります。火災報知設備の発信機が押されたときはこのリレーを作動させる必要があります。
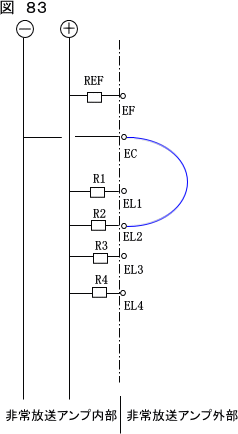
次は火災報知設備の受信機の特性ですが、2番の警戒区域で火災が起きたとき(C(共通線)と、L(ライン線)が受信機外部で短絡したとき)に、L2のリレーが作動し、l 2の接点が閉じますから、ECとEA2が受信機内部で短絡することがわかります。同様に1番の警戒区域で火災が起きたときはECとEA1が、3番の警戒区域ならECとEA3が短絡することがわかります。
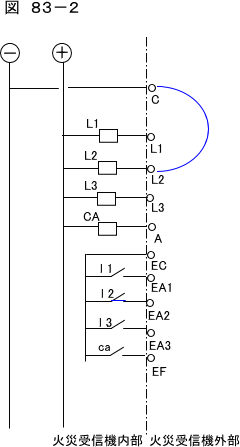
また受信機には応答回路があり自動火災報知設備の発信機が押された時だけ作動するリレー(図 83-2-2ではCA)があり、接点caが閉じるためECとEFが内部で短絡するわけです。
発信機が押されたときに消火栓が起動したり、蓄積が解除されたりするのは皆応答回路の作用です。P型2級の発信機などでは応答ランプが無いのにも係らずA(応答線)が結線されているのは以上のような理由からです。
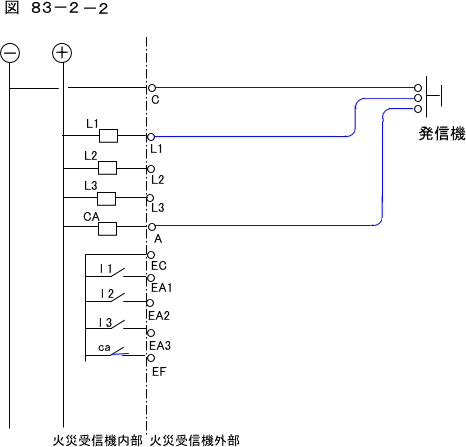
今回の現場は警戒区域の1番が1階、2番が2階、3番が階段、4番がエレベーターでしたので受信機のEA1を放送のEL1へ、EA2をEL2へ・・結線します。今回の現場は受信機と非常放送アンプの間に5Pのケーブルが配線されていましたので、青、白/青、黄、/白黄、緑、白/緑、の順でEC,EF,EL1,EL2,EL3,EL4と結線しました。
また1階に2警戒ある場合などは受信機の設定を変更することにより、使用可能になります。(例、警戒区域が1番「1階東」、2番「1階西」などの場合、1番、2番のどちらが発報してもEC,EA1が閉じるように受信機の設定を変更します。)
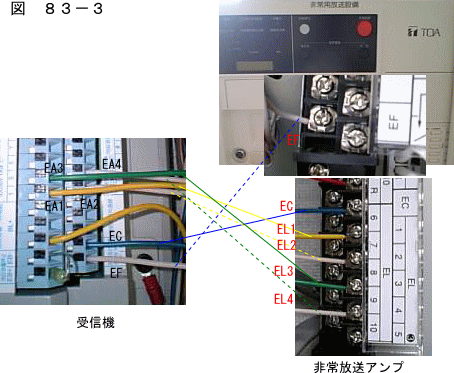
また、今回の受信機では地区ベル鳴動ではなく、放送連動に使用する場合は図 83-4のように内部のコネクターを差し替える必要があります。
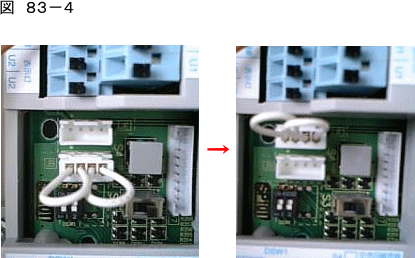
非常放送の結線と設定
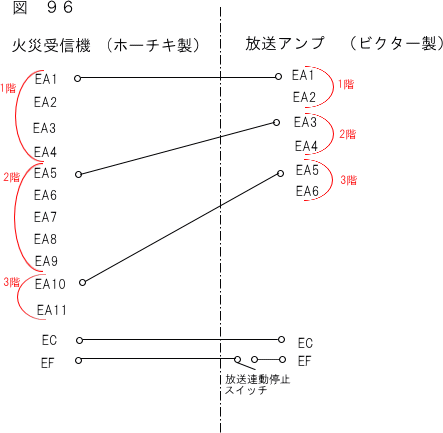
① 火災受信機の設定で1、2、3、4が発報時にECとEA1が短絡するように設定する。
同様に5、6、7、8、9が発報でECとEA5が、10、11が発報でECとEA10が短絡するように設定する。
② 放送アンプでEA1とEA2が同一階、EA3とEA4が同一階、EA5とEA6が同一階になるように設定する。
③ 放送アンプで(EA1+EA2)の連動階(直上階)が(EA3+EA4)、(EA3+EA4)の連動階が(EA5+EA6)になるように設定する。
④ 放送アンプでEA1に文言(階情報)「1階」を設定、EA3に「2階」、EA5に「3階」を設定する。