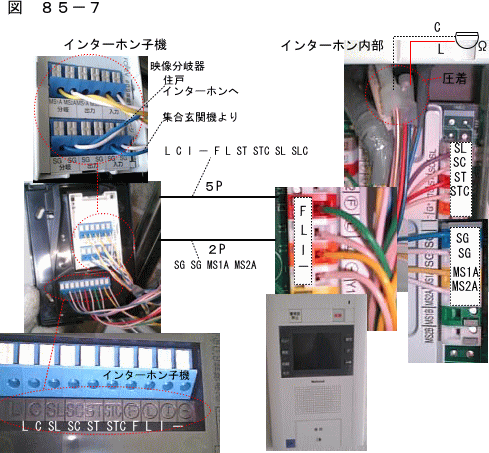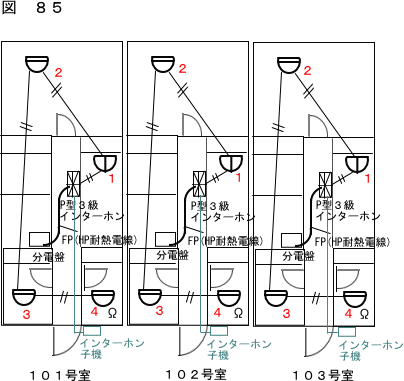
現在、当サイトは引っ越し作業中です。
しばらくはブログ図解火災報知設備工事方法をご覧ください。
新しい引っ越し先はブログでお知らせいたします。
220号住戸用自動火災報知設備(住戸完結型)
220号の住戸完結型の特徴(図 85)
両隣の住戸とは渡りの電線は有りません。
P型3級受信機(インターホン親機)の電源は各住戸の分電盤から配線され電線には耐熱保護が必要になります。実際は耐熱電線の代わりに耐火電線を使用することがほとんどです。
各住戸の感知器には1番から重複なしの連番でアドレスを設定する必要があります。感知器に設定するアドレスは外部試験を可能にするためのもので、3級受信機の直近の感知器をアドレス1番にする必要もありませんし、終端抵抗接続の位置に必ずしもアドレス最後番の感知器を接続する必要もありません。</
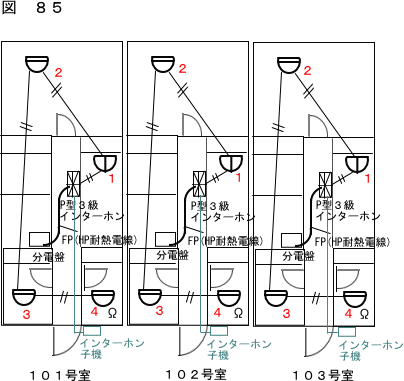
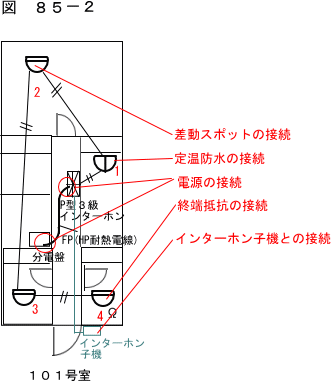
電源の接続(AC100v)
インターホンの電源を各住戸の分電盤に接続します。ブレーカーは自火報専用のもので、専用である旨の表示と、間違って電源を切断しないためのストッパー等の措置が必要です。電線は耐熱保護が必要になりますがAC100vに使用する耐熱電線というものがほとんど販売されていないため、耐火電線をしようすることが一般的です。図 85−3の写真は耐火電線です。
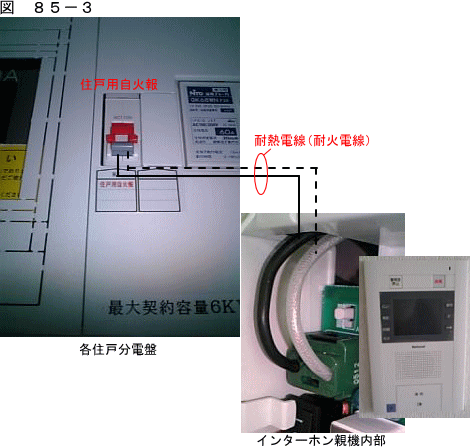
定温防水の接続
このメーカの場合定温防水の感知器のアドレスは1番に出荷段階で設定されています。
電線の赤を感知器リード線の赤へ、透明を白へ圧着し、青黄は使用しないのでビニールテープなどで先端を処理します。
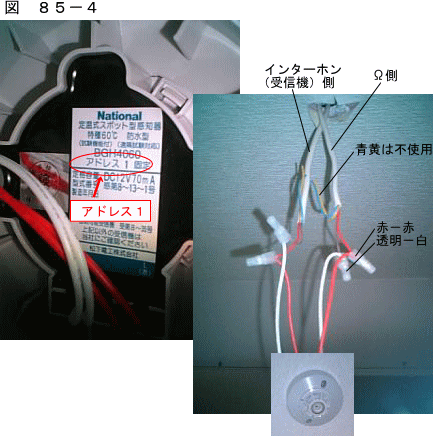
差動式スポットの接続
差動式スポット型感知器の裏にはアドレスを設定するダイヤルがあります。精密ドライバーなどで設定します。図85−5はアドレス「2」に設定したところです。
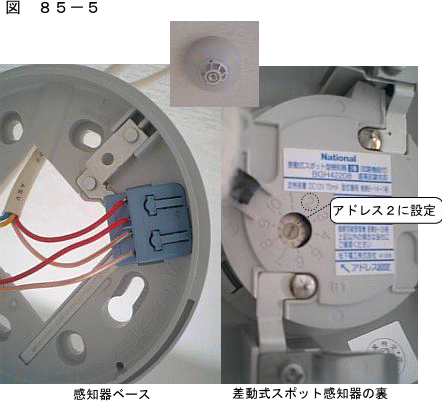
終端抵抗の接続
終端抵抗は必ずインターホン付属のものを使用します。メーカーによって抵抗値が異なるからです。抵抗値の異なる抵抗を使用すると警報音がなったり誤作動の原因になります。
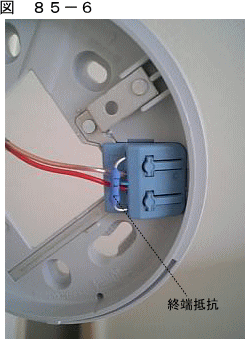
インターホン子機との接続
感知器を接続した電線はP型3級受信機には接続されていないことがわかります。P型3級受信機の内部で圧着され玄関子機のL、Cの端子に接続されます。
今回の現場では5Pを青 白/青、 黄 白/黄、 緑 白/緑、・・・を、L、C、I、−、F、L、・・・・の順で、2Pの青 白/青、 黄 白/黄をSG、SG、MS1A、MS2Aの順で使用しました。
I、−、F、Lはインターホン親機、子機間の通話などに、ST、STC、SL、SLCは感知器の遠隔試験などに、SG、SG、MS1A、MS2Aは集合玄関機との呼出し、通話、映像などに必要な線です。