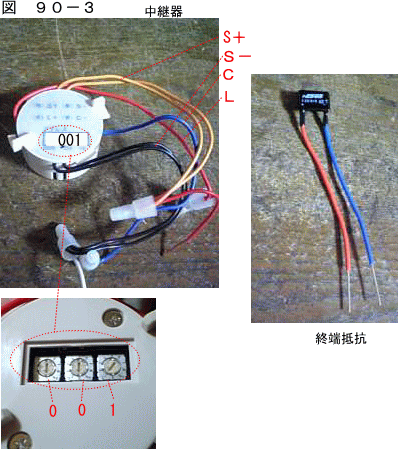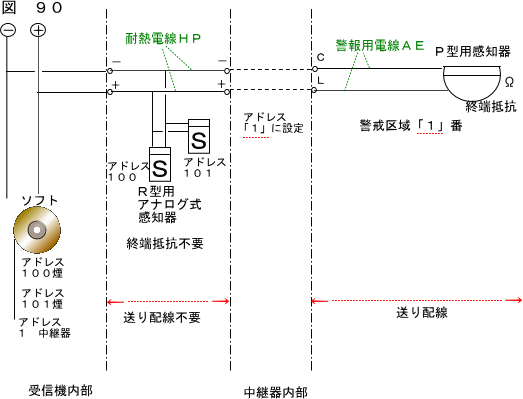
現在、当サイトは引っ越し作業中です。
しばらくはブログ図解火災報知設備工事方法をご覧ください。
新しい引っ越し先はブログでお知らせいたします。
アナログ式感知器の取り付け
R型システムの特徴
・R型受信機内部にはC(共通線)L(ライン線)の端子はありません。S+、S−、SA、SB等の中継器及びアナログ式アドレス感知器等の電源端子があります。
・中継器には電源の入力端子(S+、S−、SA、SB)と感知器回路の出力端子C、Lがあります。
・中継器をアドレス「1」に設定すると出力される感知器回路は1番の警戒区域になります。
・中継器の2次側はP型と同じように終端抵抗を用いて送り配線をして断線を監視します。(終端抵抗はR型受信機用を使用します。)
・中継器の1次側に接続するアナログ式アドレス感知器やアドレス式発信機等は送り配線の必要はありません。受信機にインストールしたソフトにより断線(感知器の脱落等)を監視できるからです。ただし、+、−の線が火災などの熱により熔け、短絡した場合に受信機には発報表示が出ないので耐熱電線を用いることとされています。
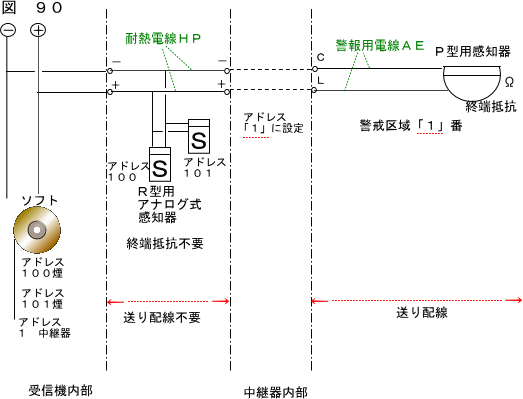
一般に感知器ベースには+、−にそれぞれ2本ずつしか結線する場所が無いので、3本以上の電線が集まった場所にアナログ式感知器を取り付ける場合は図 90−2のように3本の電線を1本にまとめて圧着し結線することも可能です。
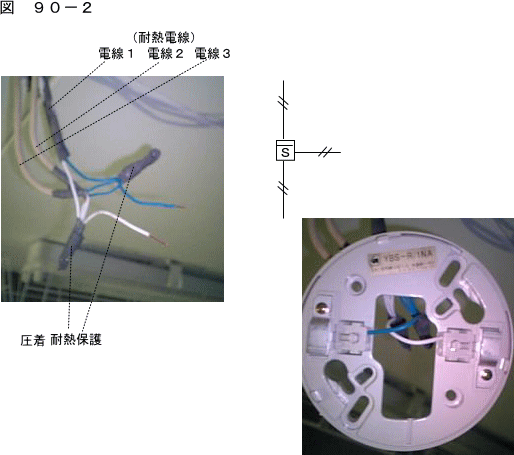
図 90−3は中継器の例、S+(オレンジ)、S−(黒)の電源線は2本ずつあります。C(青)、L(赤)はもちろん1本ずつです。中継器のアドレスは精密ドライバーなどでダイヤルを回すなどして設定します。
R型の終端抵抗には極性が有るのが多いので注意が必要です。