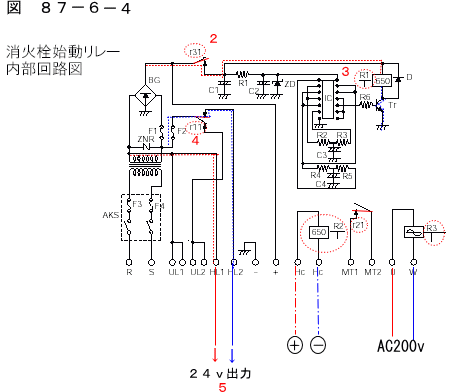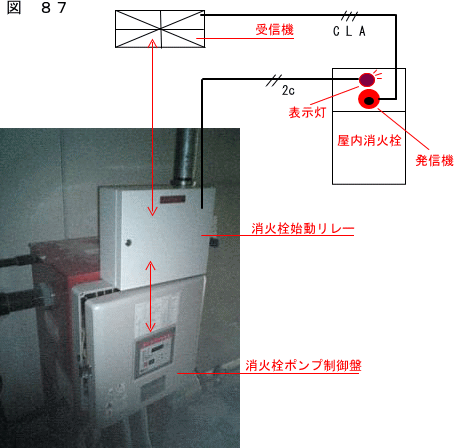
現在、当サイトは引っ越し作業中です。
しばらくはブログ図解火災報知設備工事方法をご覧ください。
新しい引っ越し先はブログでお知らせいたします。
消火栓始動リレーの取り付け 1
「消火栓始動リレーの役割」
消火栓ポンプ制御盤の内部や上部に消火栓始動リレーが設置されていることがあります。(図 87)
消火栓始動リレーは以下のような「自動火災報知設備」と「屋内消火栓設備」のリレー作業の仲介の役割をします。
「屋内消火栓に設置された発信機が押される」 → 受信機に「発信機が押された」という信号が入る →
受信機は、発信機が押されたので「消火栓ポンプを始動せよ」という信号を消火栓始動リレーに出す →
消火栓始動リレーは、その信号を消火栓ポンプ制御盤に受け渡す → 消火栓ポンプが起動する →
消火栓ポンプ制御盤は「消火栓ポンプが始動した」という信号を消火栓始動リレーに出す →
消火栓始動リレーはその信号を受け屋内消火栓に取り付けられている表示灯を「点灯」から「点滅」に変える。
※屋内消火栓設備の表示灯は自動火災報知設備の受信機のP1、P2等の端子は使用せず消火栓始動リレー内部の表示灯出力用の端子を使います。
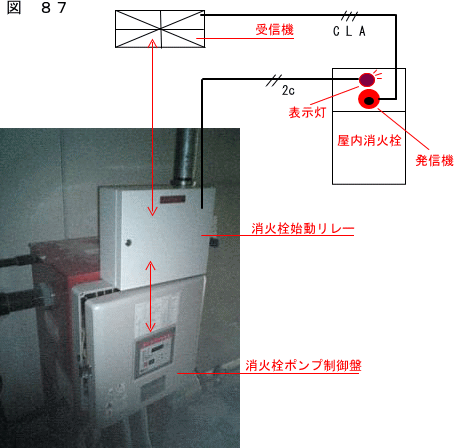
ここで消防法あるいは便宜上工事作業に求められる項目を整理しておきます。
屋内消火栓上部に設置された発信機を押すことにより消火栓ポンプが起動すること。
消火栓ポンプが起動している間は発信機上部の表示灯ランプが「点灯」から「点滅」に変わること。
消火栓ポンプが起動しているか否かは受信機で確認できるようにすること。
次に機器の特徴を整理しておきます。
※受信機
図 87−2のように一例として受信機内部には消火栓連動用のH1、H2といった端子があります。
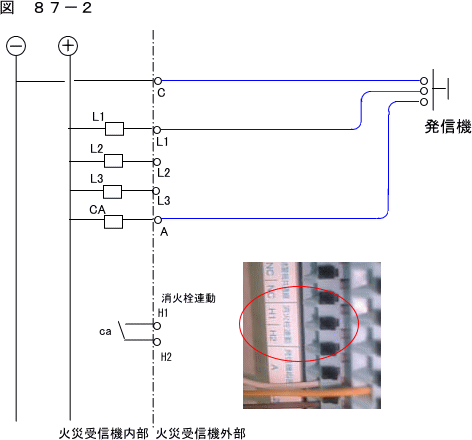
図 87−2−2のように発信機が押されるとリレーCAに電流が流れることにより接点caが閉じるので、受信機内部でH1、H2が短絡することになります。
※図ではCとAが短絡することにより消火栓連動の接点が閉じるように書かれていますが、実際は任意の回線の火災発生(C、Lの短絡)と同時にC、Aが短絡(あるいは発信機の応答ランプを介してのC、Aの短絡)することによって消火栓連動の接点が閉じます。
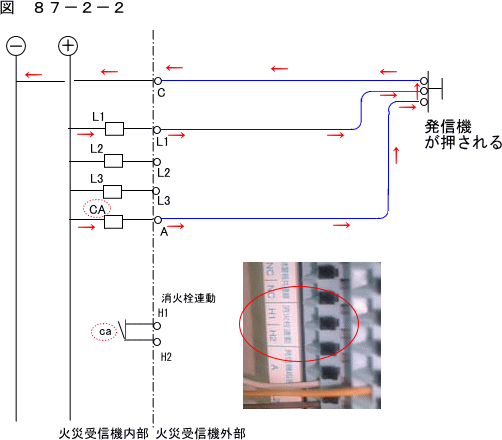
図 87−3のように一例として受信機内部には消火栓起動表示用のHL1、HL2といった端子があります。
端子HL1とHL2と受信機表面の消火栓起動表示灯は受信機内部で結線されているだけです。
つまり、HL1とHL2に電圧が加わると消火栓表示灯が点灯するわけです。
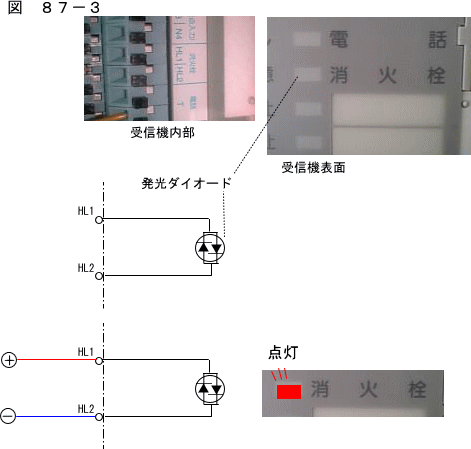
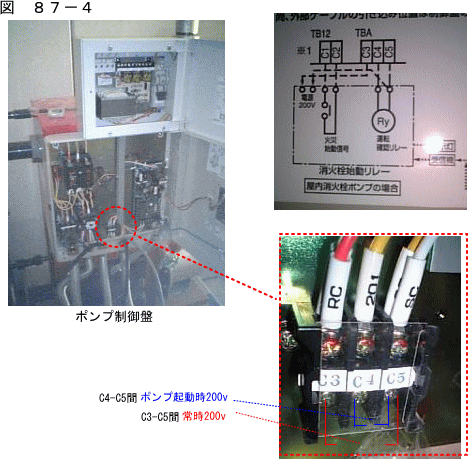
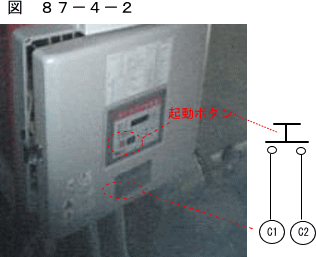
イメージが湧きやすいように描いたのが図 87−5です。上の図ではスイッチがoffなので電源がポンプに伝わりませんが、C3-C5には200vの電圧が常時かかっています。下の図ではスイッチがonなので電源がポンプに伝わりポンプの二次側に延長した回路C4-C5に200vの電圧がかかります。
つまり、ポンプが停止中のときはC3−C5に200v、ポンプが運転中のときはC5−C4に200vが発生することがわかります。
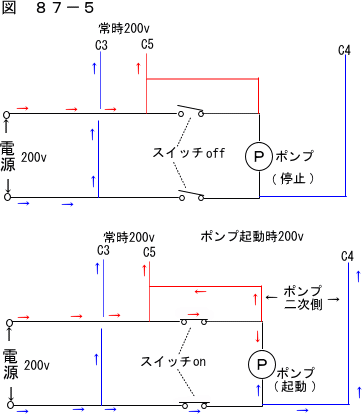
※ポンプ起動リレー
図87−6はポンプ起動リレーと結線図
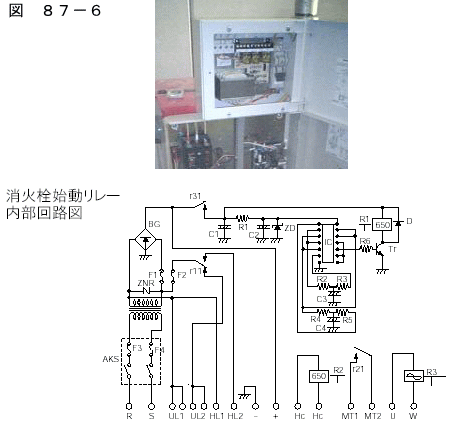
図87−6−2は電源を入れた状態。200vの電圧がトランスを経て24vの弱電に変換されます。
赤の点線が+、青の点線がマイナスを意味します。
図中の1のマークが数箇所ありますが全てマイナスへつながっていると考えてください。
よって、プラスはUL1、HL1、+へ、マイナスはUL2、−へ流れていることがわかります。
つまり、UL1、UL2に屋内消火栓の表示灯を結線すれば点灯することがわかります。
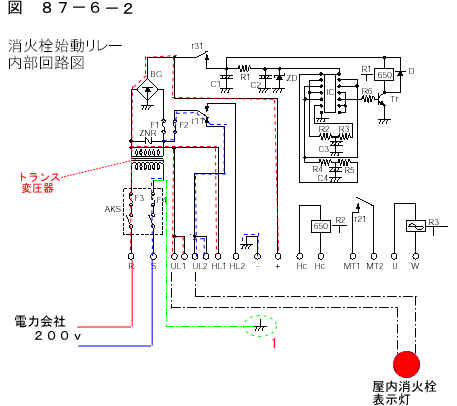
リレーのページで説明しましたが、図87−6−3はHC、HCに電圧(定格24v)が加わるとR2/1が作動しr21の接点が閉じることを意味します。接点r21が閉じるためMT1、MT2が内部で短絡します。R2/1に「650」とありますが、これは650Ωを意味します。テスターを抵抗測定モードにしてHC、HCにあてると650オームを示すはずです。
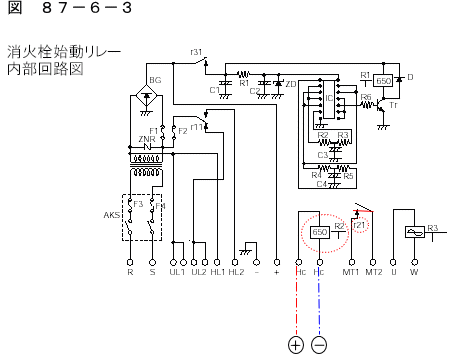
U、Wに電圧(定格AC200v)が加わるとR3/1が作動し、2のr31が閉じます。よって、R1/1が作動し4のr11が閉じ5HL1、HL2に24vの電圧が出力されます。