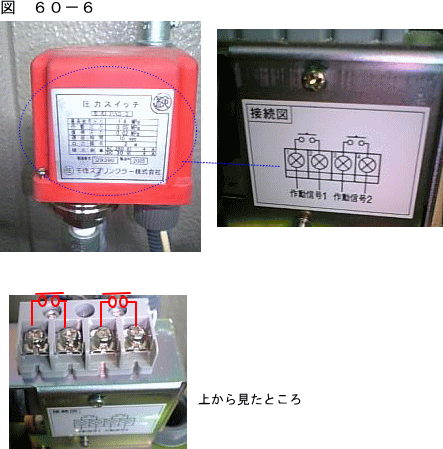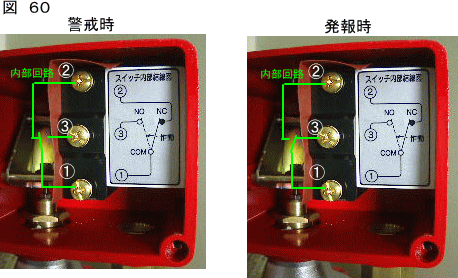
尰嵼丄摉僒僀僩偼堷偭墇偟嶌嬈拞偱偡丅
偟偽傜偔偼僽儘僌恾夝壩嵭曬抦愝旛岺帠曽朄傪偛棗偔偩偝偄丅
怴偟偄堷偭墇偟愭偼僽儘僌偱偍抦傜偣偄偨偟傑偡丅
僗僾儕儞僋儔乕愝旛傗朅徚壩愝旛偺傾儔乕儉曎偺埑椡僗僀僢僠偺寢慄偺巇曽偱偡丅
恾丂俇侽偺埑椡僗僀僢僠偺応崌寢慄恾傪尒傞偲
寈夲帪偵偼撪晹夞楬偱嘆偲嘇偑抁棈偟偰偄偰丄敪曬帪偵偼嘆偲嘊偑抁棈偡傞偺偑夝傝傑偡丅
僗僾儕儞僋儔乕愝旛傗朅徚壩愝旛偼婡婍偺嶌摦帪乮壩嵭帪乯偼抧嬫儀儖傗旕忢曻憲偺楢摦偑昁梫偵側傝傑偡偺偱
姶抦婍夞楬偲慡偔摨條偺寢慄傪峴偄傑偡丅
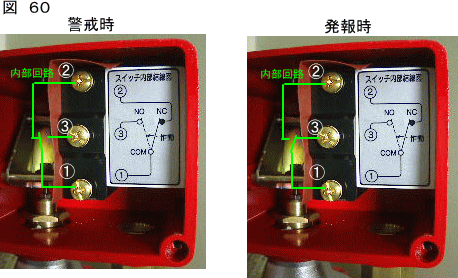
崱夞偺尰応偱偼恾丂俇侽亅俀偺傛偆偵
庴怣婡乣曻悈嬫堟嘆斣偺傾儔乕儉曎傊丄
曻悈嬫堟嘆斣偺傾儔乕儉曎乣曻悈嬫堟嘇斣偺傾儔乕儉曎傊偦傟偧傟愒敀惵偺俁恈偺揹慄偱攝慄偝傟偰偄傑偟偨丅
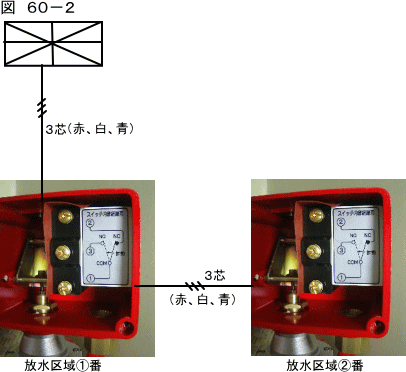
恾丂俇侽亅俁偑寢慄偺椺偱偡丅
曻悈嬫堟嘆斣傪壩嵭庴怣婡偺抧嬫憢俀侾斣傊丄曻悈嬫堟嘇斣傪抧嬫憢俀俀斣傊昞帵偡傞椺偱偡丅
姶抦婍夞楬偲摨條偵寢慄偡傞偺偱俠丄俴俀侾娫偲丄俠丄俴俀俀娫偵廔抂掞峈偑昁梫偵側傝傑偡丅
庴怣婡乣曻悈嬫堟嘆斣偺娫偑俁恈偺揹慄偱偟偨偺偱愒傪嫟捠慄偵偡傞偙偲偱傑偐側偄傑偟偨丅
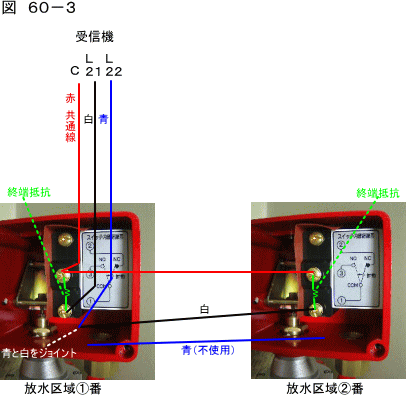
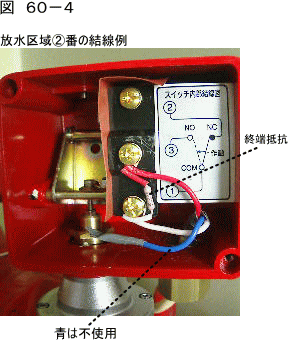
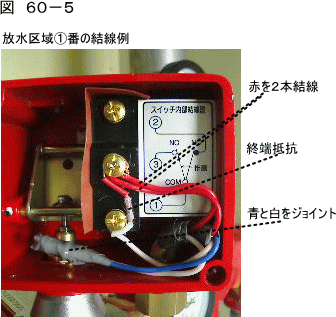
壩嵭庴怣婡偺俀侾斣偺抧嬫憢偲俀俀斣偺抧嬫憢偵乽僗僾儕儞僋儔乕嘆乿乽僗僾儕儞僋儔乕嘇乿側偳偲柤徧傪擖傟傑偡丅
幨恀偺埑椡僗僀僢僠偼壩嵭偺姶抦偐傜敪曬傑偱抶墑乮拁愊乯偑偁傝傑偡偺偱丄庴怣婡偺俀侾斣俀俀斣偼屄暿拁愊夝彍傪愝掕偟傑偡丅
傾儔乕儉曎偺寢慄 2
僗僾儕儞僋儔乕愝旛傗朅徚壩愝旛偵偁傞傾儔乕儉曎乮恾丂俇侽亅俇乯偱偡偑寢慄恾傪尒傞偲壩嵭帪偵俙愙揰偑俀偮弌椡偝傟傞偙偲偑傢偐傝傑偡丅埑椡僗僀僢僠撪晹偺愙揰偑悈棳偺椡偵傛傝暵偠傞巇慻傒偵側偭偰偄傑偡丅掕壏僗億僢僩幃姶抦婍偑擬偵傛傝撪晹偺愙揰偑暵偠傞偺偲摨條偱偡丅