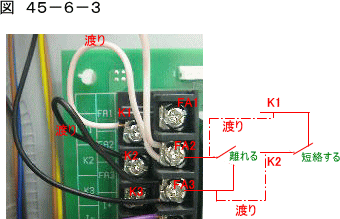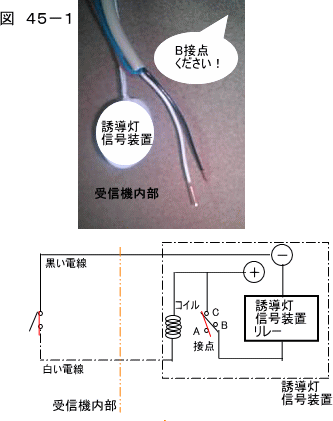
・・・・おさらい「A接点・B接点」・・・・ A接点とは、2本の電線を通常時に切り離しておいて、火災発報時に短絡させることを言います。逆に B接点とは、2本の電線を通常時に短絡させておいて、火災発報時に切り離すことを言います。・・・・・・
ここでは、誘導灯信号装置へ移報する例を説明します。誘導灯信号装置への移報の多くはB接点で行います。誘導灯信号装置の内部回路が図 45−1のようになっているからです。誘導灯信号装置から受信機へ配線されている電線があり、誘導灯信号装置を取り付けた業者さんから「黒白の電線でB接点をください」と言われます。 上の図のように受信機内部の黒と白の電線を短絡している間は誘導灯信号装置内部のコイルに電流が流れていて接点CとAが閉じるため誘導灯信号装置リレーには電流が流れません。黒と白の電線を切り離すと誘導灯信号装置内部のコイルに電流が流れなくなるので接点はCとBが短絡し誘導灯信号装置リレーに電流が流れ始め、誘導灯が点滅したり、音声が流れ始めたりするわけです。(図 45−2)
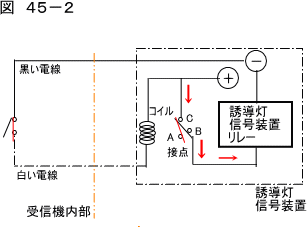
次に受信機の特徴を調べます。
図45−3−1は受信機に付属されている回路図です。最初は分かりずらいものですが、慣れてくると分かるようになります。図 45−3−2は受信機内部の接続端子です。 図 45−3−1の回路図によると、警戒時にはFA2とFA3が受信機内部で短絡していて、(図 45−3−3)火災発報時にはFA2とFA3は切り離されることが伺えます。(図 45−3−4)
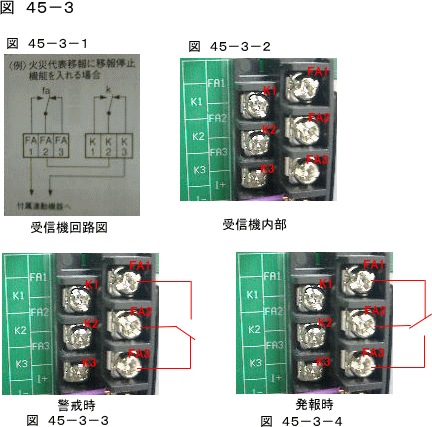
つまり、図 45−4のように誘導灯信号装置から配線された黒白の電線をFA2とFA3に結線すれば火災発生時に誘導灯を点滅させたり、音声を流したり出来るわけです。
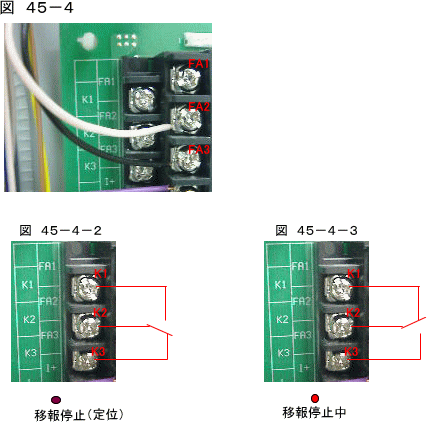
このままでも、充分に誘導灯信号装置は作動するわけですが、火災報知器の点検を行うときは、感知器が作動するたびに誘導灯が点滅してしまうため、少々不便です。そこで受信機の「移報停止」のボタンを操作することで誘導灯へ移報がいかないように結線を追加します。
図 45−3−1の回路図によると、常時受信機内部でK2とK3が短絡されています(図 45−4−2)が移報停止のボタンを押すとK2とK1が短絡するのがわかります。(図 45−4−3)
そこで、図 45−6のようにFA2からK1へ、FA3からK2へ渡りを作ってあげます。
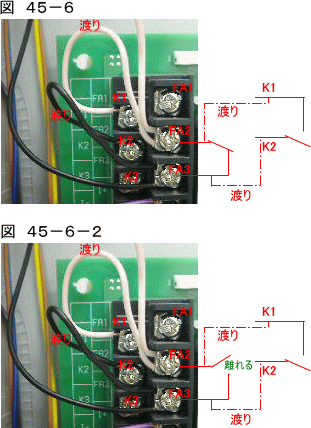
それにより、火災発生時にはFA2とFA3が切り離されるので(図 45−6−2)誘導灯信号装置は作動しますが、受信機の移報停止のボタンを操作することによりK1とK2(つまり、白と黒の電線)が短絡するので、点検時に感知器を発報させても誘導灯信号装置は作動しなくなります。(図 45−6−3)