ポンプで吐出された水を各消火栓に送り消火活動に使用できるわけですが、一刻も早く消火活動が開始できるように、全ての配管内を水で満たしておく必要があります。そのために必要なのが「高架水槽」です。
高架水槽を、どの消火栓よりも高い位置に設置し重力を利用して配管内を水で満たします。高架水槽は呼水槽同様ボールタップを設け、減水した時には自動給水されるようにします。
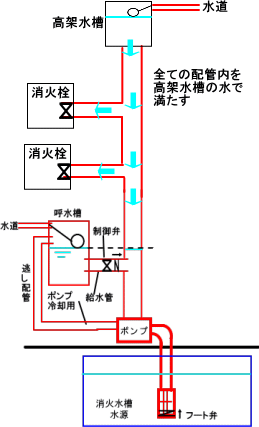
消火設備等に用いられるポンプについて (その2)
高架水槽
ポンプで吐出された水を各消火栓に送り消火活動に使用できるわけですが、一刻も早く消火活動が開始できるように、全ての配管内を水で満たしておく必要があります。そのために必要なのが「高架水槽」です。
高架水槽を、どの消火栓よりも高い位置に設置し重力を利用して配管内を水で満たします。高架水槽は呼水槽同様ボールタップを設け、減水した時には自動給水されるようにします。
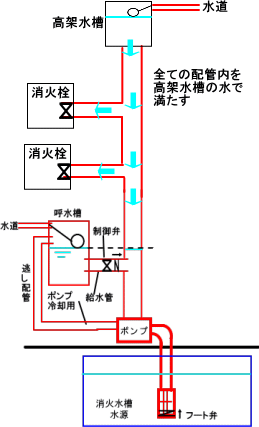
しかし、このままでは高架水槽の水はポンプを通過し逃し配管を通り呼水槽をあふれさせてしまいます。
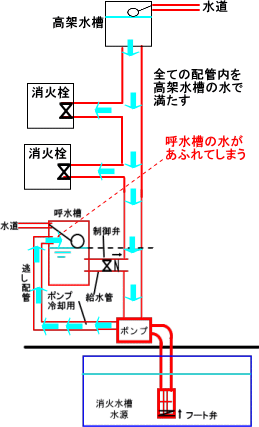
逆止弁 (その2)
そこで逆止弁が必要になります。
逆止弁を図の位置に設けることにより高架水槽からの水を止めることができます。
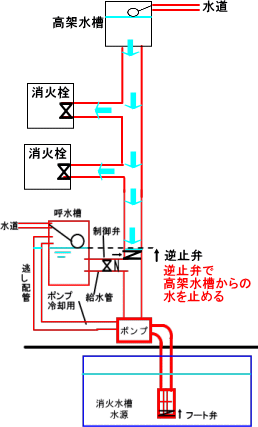
つまり、①のような逆止弁より上の位置で水漏れがある場合(消火栓のバルブが開いている、配管に漏れがあるなど)は高架水槽のボールタップの作用で給水が止まらないはずです。このままポンプを起動させると建物内に大量の水漏れが発生する危険性があるので、事前に高架水槽のボールタップの給水が止まっているかを確認することが大切です。
また、②のような逆止弁より下の位置で水漏れがある場合は呼水槽のボールタップの給水が止まらないはずです。
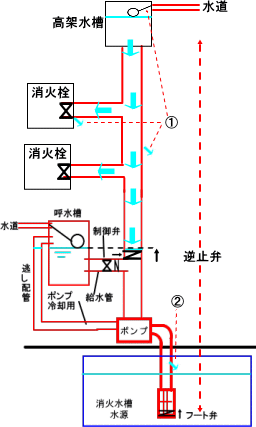
逆止弁 (その3)
この状態でポンプを起動してしまうと、ポンプから吐出された水が高架水槽へ流れ込んで高架水槽はあふれてしまいます。
そこで高架水槽の下にも逆止弁を取り付けます。
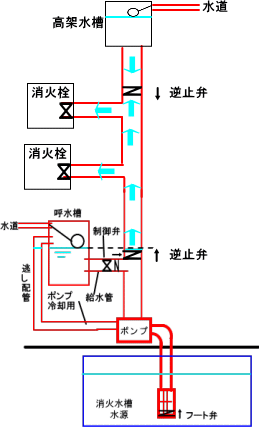
消火栓ポンプの横に小さなポンプが設置されていることがあります。建物の構造上、高架水槽を設置することが出来ない場合などに、高架水槽の役割を果たすように図のように接続させます。配管内の圧力が下がると自動的に起動し、圧力が上がると停止するようになっています。ジョッキーポンプ、ベビーポンプ等と呼ばれることがあります。
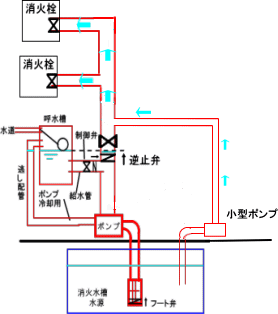
ジョッキーポンプの例

また屋外消火栓設備のように全ての設備が呼水槽よりも低い位置に設置されている場合は、呼水槽が高架水槽の役割を果たすので、高架水槽を設置しない場合もあります。
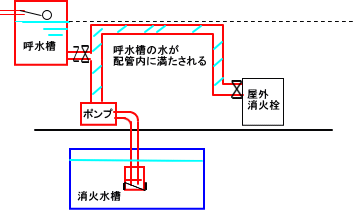
制御弁 (その2)
逆止弁は経年劣化等により交換が必要になる時があります。
逆止弁を取り替えるときは一時的に高架水槽からの水を止めておかなければなりませんから、逆止弁よりも高架水槽側へ制御弁を取り付けておきます。
同じ理由で呼水槽の制御弁は逆止弁より呼水槽側に取り付けます。
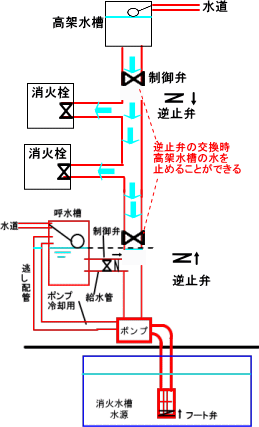
点検用の配管
流量試験管とテスト弁
ポンプの性能を点検するためにポンプには流量試験管が取り付けられています。
実際に放水テストを行うために、屋上などにテスト弁が取り付けられています。どの消火栓よりも高い位置に設けることにより、テスト弁の放水圧が0.17MPa以上であれば、全ての消火栓の放水圧がそれ以上であると証明できます。
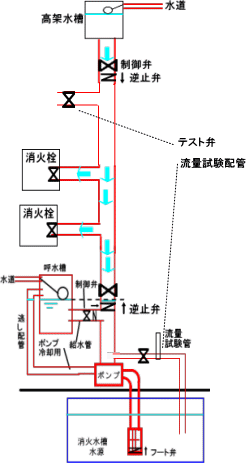
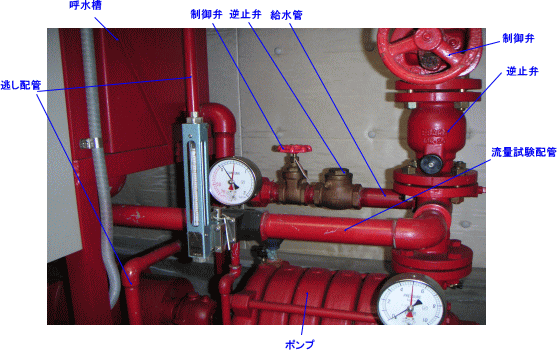
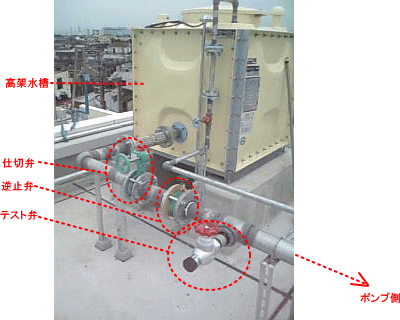
流量試験
1号消火栓の基準では、
「ポンプの吐出能力は150リットル(毎分)×消火栓設置個数(最大2)」とありますが、
分かりづらい言い方なので、もう少し簡単に言うと、
「消火栓は同時に2台までしか使いません。・・・水道の蛇口で例えると、同時に数箇所から水を出すと水圧が下がることがあります。1号消火栓の場合は3台同時に使用した時に水量及び水圧が規定量(ノズルから130リットル、水圧0.17~0.7MPa)に達しなくても構いません。ただし2台までを同時に使う時は水量及び水圧が規定範囲内でなくてはなりません」・・・という意味です。
スプリンクラー消火設備に関しても同じです。スプリンクラーヘッド個数15・・・という書き方の文献が多いようですが、この場合も
「16個目のヘッドが破裂した際には水量及び水圧が規定量に達しなくても構わないので、同時にヘッドが15個まで破裂した際の火災を考慮したポンプや水源や配管の設置をしなさい」
という意味です。
ポンプの流量試験とは実際の火災を想定した点検なので、1号消火栓の流量試験は150リットル×2台=300リットルで行います。

ただし、比較的小さな建物で同時に使用する消火栓を1台として設計されたものもあります。建築時に消防との事前協議の上、経済的負担を軽減するため等の措置でポンプや水源を小さくしている場合があります。この場合の流量試験は消火栓1台分の150リットルで行います。流量試験器の目盛りが300リットルまで無いものはこれにあたると考えていいでしょう。
スプリンクラーに関しては、使用されているスプリンクラーヘッドが高感度型なのかどうかが外観では判断がつかないことがほとんどなので、何個のヘッドが同時に破裂したことを前提としているかが点検時に分からないのが現状です。送水口に写真のような記述があれば、それが当該建築物に求められたポンプの能力なので、その流量(写真では1080リットル)でポンプの流量試験を行います。

流量試験で水圧が上がらない
ポンプの流量試験を行なった時に水圧が急激に落ちてしまうといった現象がまれに見受けられます。
これにはほとんどの場合次のような理由が考えられます。
流量試験器の2次側の配管が消火水槽へ接続されている場合、その配管とフート弁との間隔が十分でない上に、消火水槽の水面より上部から流量試験に用いた水が勢いよく排水されるような構造になっていると、消火水槽内に大量の気泡が発生し、それがフート弁を通じポンプ内に入りポンプの吐出圧力を落としてしまいます。
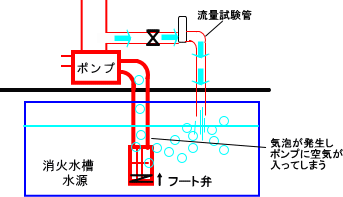
流量試験管をフート弁から遠ざけ、消火水槽の水面より下まで延長することにより、このような症状は軽減できます。
放水量と水源水量
放水量と水源水量等は消火栓の種類別に以下のように定められています。
水源水量は、放水量×20分間×消火栓設置個数(ただし最大でも2まで)となります。
(例 130リットル×20分間=2.6立方メートル)×消火栓設置個数(ただし最大でも2まで)
水源のボールタップなどによる自動給水が止まっていても、20分間は消火活動に支障をきたすことがあってはならないということです。
ただし、消火栓設備の非常電源は30分間以上運転する性能が要求されています。
| 1号消火栓 | 易操作性1号消火栓 | 2号消火栓 | |
| 放水量(リットル毎分) | 130 | 130 | 60 |
| 水源水量(立方メートル) | 2.6×消火栓設置個数(ただし最大でも2まで) | 2.6×消火栓設置個数(ただし最大でも2まで) | 1.2×消火栓設置個数(ただし最大でも2まで) |
| ポンプ吐出能力(リットル毎分) | 150 | 150 | 70 |