引き出し部の出し入れがスムーズにできるよう、レールとキャスターを使用しました。
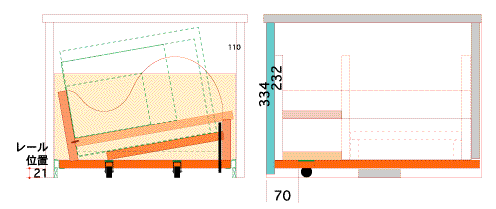
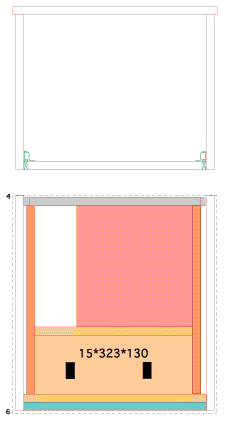
下の図面を持ってホームセンターに行き、カットサービスを利用しました。
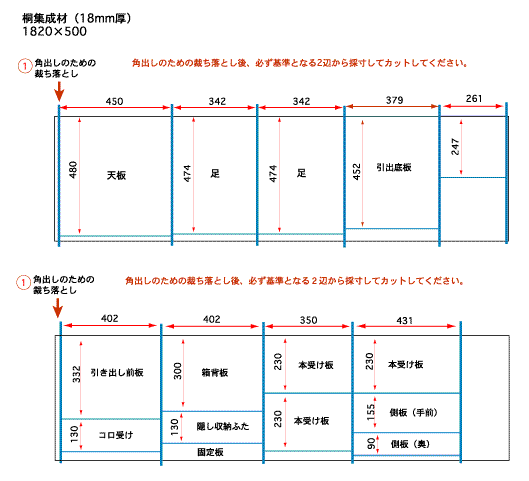
ボックス部の組み立て
1.レールとアングル金物を取り付けるためのビス位置がずれないよう、丁寧にマークした後、錐で中心に穴をあけておく。
| ○引き出し収納型の本棚 | ||
|
|
||
| 文机の右側に並べて置く引き出し型の本棚を作ってみました。広辞苑とA4ファイルを収納できるサイズで作成。取り出ししやすいよう本やファイルが少し斜め(10°)に傾いた形で収納できる構造にしたため、工作に少し手間がかかりました。本をまっすぐ立てて置く形なら、製作は楽になります。中敷き板の下部空間は秘密の隠し場所に。 引き出し部の出し入れがスムーズにできるよう、レールとキャスターを使用しました。 |
||
| ▲レールは安価な物を採用。お小遣いに余裕がある人は、もっと性能のいいレールがありますのでご検討ください。組み立てが楽になるかも。 | ||
| ▲キャスター(小)を2個用意 | ||
| ▲ツーバイフォー材用のアングル金物を6個使います。 | ||
| [図面] | ||
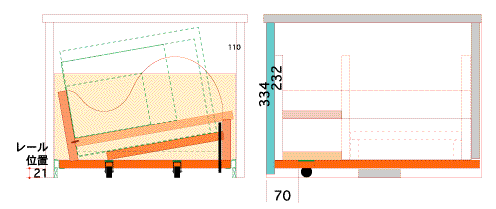 |
||
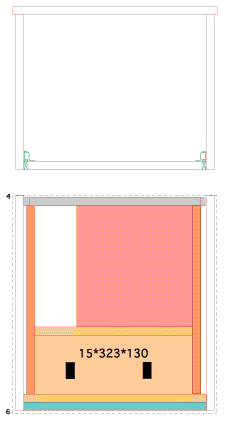 |
||
| [木取り図]
下の図面を持ってホームセンターに行き、カットサービスを利用しました。 |
||
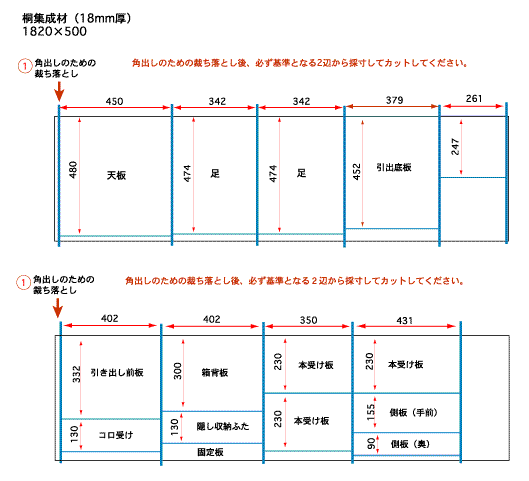 |
||
| ▲カットサービスで切ってもらいました。 | ||
| [組み立て]
ボックス部の組み立て 1.レールとアングル金物を取り付けるためのビス位置がずれないよう、丁寧にマークした後、錐で中心に穴をあけておく。 |
||
| ▲レールのビス位置の中心に錐で穴を少しあけているところです。 | ||
| ▲ボックス部の側板に金具とレールを取り付けます。 | ||
| ▲ボックス部の背板に金具を取り付けます。 | ||
| ▲ボックス部を組み立てる前に、背板の位置決め用のガイド板を仮止めしておくと組み立てやすくなります。 | ||
| ▲箱の組み立て。金物部分にビスを打って天板と背板を固定後、側板の外側からビスを打って側板と背板をしっかり固定します(埋木でビス頭は隠しましょう)。 | ||
| ▲背板と側板の取り付けが済めば、背板の位置決め用のガイド板は取り外します。 | ||
| ▲この後、『板(A)』を底の中央あたりに取り付けてボックス部の完成(下写真) | ||
| ▲引き出し内部の曲線加工用の型を厚紙で作り、カットラインを記します。 | ||
| ▲曲線部分はジグソー、または、突っ切りノコを使います。 | ||
| ▲突っ切りノコ | ||
| ▲曲線部をなめらかに研磨。瓶や缶などにサンドペーパーを巻き付けて研磨しました。 | ||
| ▲斜め10°にカットしているところ。ソーガイドミニを少しずつずらしながら切りました。 | ||
| ▲作図時点で、キャスターを埋め込む形で底板に取り付けないとA4ファイルが収納できないことが判明。底板に穴をあけました。 | ||
| ▲ドリルで穴をあけた後、突っ切りノコで四角くカット。 | ||
| ▲底板の中側にもう一枚 板を固定し、その板にキャスターをビス止めしています。 | ||
| ▲引き出し内部の敷き板の作成(裏返した状態) | ||
| ▲引き出し部の組み立て。仕切り板を取り付けようとしていますが、下写真の前板取り付け作業が済んだ後、取手を取り付けてから仕切り板を付けます(取手のビス止めがしやすいので)。 | ||
| ▲引き出しの前板の固定(埋木でビス頭を隠します)。 | ||
| ▲引き出し部のレールを取り付けます。 | ||
| ▲取手位置を決めて取手を付け、仕切り板を固定して、中敷きをはめて完成。 | ||
| ▲埋木のはみ出ている部分を切り落としているところ。桐材はやわらかいのでカッターナイフでも切り落とせます。切り落とした後、サンドペーパーで平滑に研磨します。 | ||
| ▲使用したレールはストッパーとなる出っ張りがあるため、一番奥に置いた本を取り出す時は、引き出しをほんの少し持ち上げて引き出します。 | ||
| ▲この本棚は“隠す収納”が好きな人向けです。ずぼらな人は“引き出す”というひと手間が面倒に感じることになるでしょう。 | ||