「DIYハンドブック」の手順とは少し異なります。
この方法の方が、手間が少なく、かつ、不具合が出にくい、と
私は思っています。
壁材で汚してはいけない箇所を養生します。
下の写真は、マスカーを使っています。マスカーは、粘着テープ付きの薄いシートなので、床養生に使った場合、破れやすく、また、すべりやすいのでご注意を。破れたときはすぐに補修しておかないと、床面を汚すことになります。
ノンスリップタイプの厚手の養生シート(ロールタイプ)を床養生に使用する手もあります。
マスキングテープの貼り方は2通りあります。
マスキングテープは、「施工面から3mm(下塗りの厚み約1mm+仕上げ厚み約2mm)ほど離してていねいに貼る」と、マニュアルには紹介されていますが、
少しでもきれいな仕上げを望むのであれば、
「下塗り用のマスキング」と「仕上げ塗り用のマスキング」の2回に分けることをおすすめします。
なぜなら、
壁塗り初挑戦の方が下塗りすると、下の写真のようになり、きわをゴテゴテに汚してしまうからです。これでは、下塗材が仕上げ面からはみだして見えてしまうということになりかねません。
クチャクチャになってしまう一番の原因は、「急ぎすぎ」です。
ムリなスケジュールはたてないようにしましょう。
まず、施工面のボードジョイント部、そして、コーナー部(出隅、入隅)をよく見てください。
ボードが裁断されて突き合わされている場合、ボードの中身の石こうが丸見えになっています。石こう部分はすごく吸水しますから、水性シーラーを塗布して吸水を抑えておかねばなりません(色ムラ防止)。
刷毛で1回通すだけでは不十分。1回たっぷりしみ込ませた後、しばらく時間をおいてから再度シーラーを塗ってしっかり吸水を抑えます(ボード面にはみ出たシーラーは雑巾で拭き取っておく)。
コーナー部は、すき間なく突き合わされている場合はシーラーの塗布は不要。すき間がある場合はボードの合わせ目からシーラーをしみ込ませる感じで塗ります。
厳密に言えばビス穴凹みも石こうが少し見えていますが、色ムラ等の不具合は出ませんので、シーラー塗布は不要です。
水性シーラーが乾いたら、ファイバーテープ貼りです。
ファイバーテープを貼る場所は、ボードのジョイント部(出隅、入隅も)、
そして、ドアや窓などの開口部角にもファイバーテープを斜めに貼って補強しておきます。
ファイバーテープはたるんだり、浮き上がったりしないよう、しっかりと密着させておくこと! 施工面から浮き上がっていると、仕上げ面に出てしまうことがあります。
また、出っぱったコーナー部(出隅)に折り曲げて貼ったファイバーテープがテープの弾力で剥がれてくる場合は、タッカーで留めておくとよいでしょう。
(入隅部分にきっちりと貼るコツは、ビニールクロス下地の施工方法を参照)
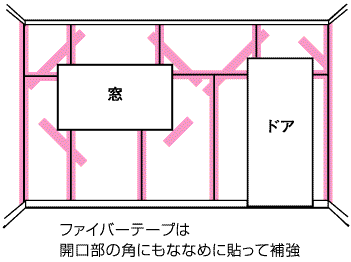
ボードのジョイント部のV字溝に〈下塗材NGU〉を、ファイバーテープの上から塗り込む作業です。
その日に下塗りする面にあるV字溝を、下の写真の要領で次々と埋めていきます。
(ビス穴凹みは埋める必要はありませんが、5〜6ミリも深く打ち込んでいるビス穴凹みは埋めておいた方がいいでしょう)。
※V字溝を埋めるための〈下塗材NGU〉は少量で足りますので、ボウルか洗面器などに〈下塗材NGU〉の粉と水を入れて、ゴムべらを使って練りましょう。
(柔らかく水練りすると作業は楽ですが、肉ヤセします)
コテを立て気味にして、力をこめてしっかりとぬぐい取りましょう。
その日に下塗りする施工面の目地埋めがすべて終えたら、下塗材〈NGU〉を水練りして、下塗りに取りかかりましょう。
※目地埋めした部分が乾燥するのを待つ必要はありません。未乾燥状態のうちに下塗りをする方がいいのです。そのわけは、ここでは書かないでおきます。ややこしくなりますので。
下塗材の水練りは、施工スピードがおそい人は、一面ずつの量を練りましょう。
一度に大量に練ると、材料が固くなっていって、塗りづらくなりますから。
下塗りは段差なく平らに塗るのが基本です。ガタガタだと仕上げ塗りをするときにコテが引っかかります。塗り方は難しくはありません。〈下塗材NGU〉は顆粒が入っていますので、塗りつけた面をコテで押さえてならせば、顆粒1個分プラスαの厚みで均一に塗ることができます。下記の要領で塗りましょう。
1.角、端、中面へと、手の届く範囲に塗り残しなく塗りつけ・・・(コテ波は気にしないで)。コテを動かすスピードは一定。
2.コテ面に付着している材料をコテ板の端を使ってぬぐい取ってから、塗りつけた面をならしますと、余分な壁材がコテに付着します。これをコテ板の端でぬぐい取り、また、施工面をならし・・・コテ面をぬぐいながら施工面をならし・・・を繰り返すことでコテ波は取れて平らになります。コテは立てすぎないでください。
3.上記1と2を繰り返しながら下塗りを進めていきます。
下塗りのためのマスキングテープを貼った人は、すみやかにマスキングテープを剥がしてください。
窓を開けて、室内の空気を入れ換え、乾燥させてましょう。
〈下塗り面〉が白く乾いたら仕上げ塗りに取りかかってください。