ほとんどの合板はアクが出ます(シナベニヤは出ません)。アクが出るかどうかは見た目ではわかりません(赤味のところからアクが出ます)。
写真上部の白いところはアク止め液を1回刷毛で塗った部分。
これまで、施工仕事で、数種類のアク止め液を使ったことがありますが、現在は、アク止め液を使わないことにしています。
理由は、
1.アク止め液は高価である。
2.アク止め液はたいてい2回塗りが必要で、その時間がもったいないし、2回塗りで確実に止められるか不安がある。
3.アク止め液のニオイが好きになれない。
ということで、現在、施工マニュアル通り、下塗りを再度おこなってアクを止めています。なお、アク止めのために塗る下塗材〈NGU〉は、少し練り水の量を多めにしないと塗りにくいです(下塗り面に水を吸われるため)。やわらかめの下塗材〈NGU〉が塗りにくいと思う人は、アクが出た下塗り面にシーラーを塗って吸水を抑えておくといいでしょう。
なお、下塗りした面に〈ペーストタイプ〉で仕上げ塗りをする場合、「アクが出た下塗り面にシーラー塗布→乾燥→ペーストタイプで仕上げ塗り」という方法でもうまくいくのではないかと思っています(テストしたことがないので保証できませんが)。気泡も出にくくなりますので、天井面の塗りが楽になります。ただし、下塗材〈NGU〉の持つ効果を低減させてしまうことになるのでは、と思っています。下塗材〈NGU〉は活発な呼吸性はありませんが、抗酸化力があるのです。ペーストタイプがそれを引き出してくれるのではと、私は勝手に思いこんでいます。
〈ペーストタイプ〉で仕上げする場合、合板部分にだけ下塗材(NGU)を塗ることはしてはいけません。段差ができてしまうだけでなく、下塗材(NGU)を塗っている場所と塗っていないところで色味が異なる仕上げになるからです。

〈ペーストタイプ=PS、PZ〉は光触媒効果が優れており、合板のアクもきれいに分解します。ただし、太陽光や蛍光灯の光が必要です。陽がよく入るリビングルームでは2週間できれいに消えてしまいました(合板下地に下塗りした面でしたので、上の写真よりもアクはうすかったですが)。光触媒効果を信じて大丈夫だと思います。
貼る場所は、ボードジョイント部、出隅(出っ張ったコーナー部)、そして、窓・ドアなど開口部の角には、斜め45度くらいに貼って補強します。
※出隅に貼ったファイバーテープが剥がれてくる場合は、タッカーを打って留めておきましょう。
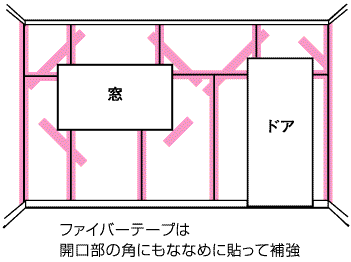
乾いて白くなったらオーケー。冬でなければ1日ほどで乾くと思います。
下地からアクが出ていたら、再度、シーラーを塗って乾燥後に下地材(NGU)を施工。
下の写真は、アクが出た下塗り面です。乾燥後に再度下塗りをしてアクを止めました。
ペーストタイプで仕上げる場合、少しやわらかめの材料でないと塗りにくく、ラフ仕上げもうまくいかないと思います(下塗り面が水を吸いますので)。
日ケイから送られてきた壁材が固いと感じた場合は、少し水を加えて練り直してから仕上げ塗りにかかりましょう。
浅く細い溝が付いている化粧合板は、その溝部からアクが出ます。表面の塗膜が剥がれかかっている古い化粧合板はその部分からもアクが出ますので、アク止めが必要になります。
また、手で押すとペコペコとたわむ場合は、仕上げ面にヘアークラックが入る可能性が高いです。
化粧合板のジョイント部にも忘れずにファイバーテープを貼るように。