どうも、昔の定説というのは、鉄砲こと、火縄銃を過大評価しすぎているような気がします。「鉄砲の普及が石垣を広めた」という昔の定説も、そのような過大評価の一例のように私は思います。鉄砲をよけるために石垣が普及したという短絡的発想に対する批判は下記の文献が雑誌に掲載されていたので、そのままそれを提示し、その補足として、火縄銃、もっと広義にいってマスケット銃と、第1次世界大戦から第2次世界大戦の頃のライフル銃との違いについてを、私こと参謀足軽が解説しましょう。
追記 そもそも、火縄銃というのは大変原始的です。ただ発射速度が、現在の銃に近い第1次世界大戦や第2次世界大戦の頃のライフル銃(以下ライフル銃と略します。)よりおそいだけというだけでなく銃身の構造が全然違います。(現在の兵士の使用する銃は短機関銃や自動小銃ですので、これらの銃だと別のニュアンスが加わってちょっと比較しづらくなってしまうのでライフル銃で比較することにしました。) 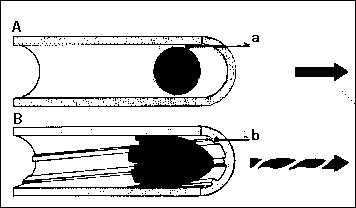 左図は銃の銃身の構造を示し、Aは滑腔銃で火縄銃はこの部類に入ります。銃身の内側は図の示すとおり、何の工夫もなくただの筒です。これだと、銃身と玉のあいだに隙間aが生じ、ここから爆発したガスが漏れるし、玉が回転しないので弾道が不安定です。ガスが漏れるので火薬の爆発力が有効に利用されていません。 左図は銃の銃身の構造を示し、Aは滑腔銃で火縄銃はこの部類に入ります。銃身の内側は図の示すとおり、何の工夫もなくただの筒です。これだと、銃身と玉のあいだに隙間aが生じ、ここから爆発したガスが漏れるし、玉が回転しないので弾道が不安定です。ガスが漏れるので火薬の爆発力が有効に利用されていません。Bは施線腔銃すなわちライフル銃です。銃身に螺旋状の溝が刻まれており、突出部は条丘と呼ばれ、これが弾丸に食い込み発射された弾丸に回転がかかり、弾道が安定します。弾丸と銃身との隙間bが少ないので爆発したガスがほとんど漏れません。 銃身だけでなくライフル銃は金属薬莢なので発射の際に薬莢が膨張して銃身に密着して銃の底に気密性が保たれる。火縄銃は銃の外から銃の底に入った火薬に点火するのでおそらく点火部からもガスがもれて火薬の爆発力が弱まってしまうと思われます。 この気密性と弾道の安定が火縄銃等のマスケット銃との性能に著しく差を付けます。マスケット銃の有効射程(命中精度がよい射程で最大射程ではありません)はせいぜい80メートルくらいです。(「武器」 1989年 マール社発行より)これが火縄銃のデータかどうかはわかりませんが火縄銃はマスケット銃のうち(中世のハンドキャノンを銃と見なさない場合)もっとも下等な銃であるのでこれ以上の性能は出さないと思います。ところが、ライフル銃の有効射程は最大800メートルとなんと十倍も違うのです。(ション・ウィークス著 拳銃・小銃・機関銃 1973年 サンケイ新聞社発行より) 日本の三十八式歩兵銃は発射速度はボルトアクションなので当時としては時代遅れですが、命中精度等、狙撃銃としてはとても優秀でした。有効射程のデータがちょっと見つかりませんでしたが、かなりいい銃なので、おそらく800メートル近くの有効射程を持っていたものと思われます。 その三十八式歩兵銃が1mの土手を貫通できないのに、なんで火縄銃の破壊力で貫通できるんでしょう。さらに第1次世界大戦、第2次世界大戦でも銃弾を避けるのに土のうという土を入れた袋を用いたのに、それより数段おとる下等な火縄銃が土の防壁をすたれさせ、石垣を普及させたなんていえるのでしょうか。 なお、マスケット銃はおもに発火方式で分類され、その進化の過程はおよそ火縄銃すなわちマッチロック式からスナップハンズ式→フリントロック式→パーカッション式とヨーロッパでは進化しました。ヨーロッパではマッチロック式は18世紀頃にはみられなくなりましたが、日本では19世紀半ばまで使われていました。 |