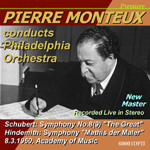
MENU PAGE → http://www.ne.jp/asahi/classical/disc/index2.html
PREMIERE(プレミエ)
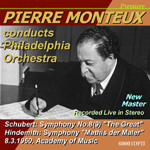
●モントゥー/フィラデルフィア ステレオ・ライブ シューベルト 「グレイト」ほか
プレミエ60001IIDF
シューベルト 交響曲第8(9)番「グレイト」
ヒンデミット 交響曲「画家マチス」
ピエール・モントゥー指揮
フィラデルフィア管弦楽団
1960年3月8日、アカデミー・オブ・ミュージック、フィラデルフィア
ライブ、ステレオ
※放送局などによるライブ収録としては初期のステレオであり、若干荒れたところやバランスが悪いところもあるが、モノラルに比べればはるかに分離も良く、素直で素朴なマイクセッティングのためか、作為のない新鮮な響きが好ましい。
今回のプレスから新たなマスターを使用しており、以前のプレスに比べて歪みが解消しダイナミックレンジが広がるなど音質が改善され、本来の会場の響きが甦った。
モントゥーは、アメリカの主要オーケストラの大半に客演していたが、フィラデルフィアとの共演は比較的珍しい。モントゥーは「グレイト」のスタジオ録音を残さず、今のところ当録音のほかに1956年ボストン響とのモスクワ・ライブが確認されているのみ。ヒンデミットはモントゥーにとって珍しいレパートリーだが、1960年代に入りしばしば取り上げていた。こちらもスタジオ録音を残さず、当録音のほかには1962年デンマーク放送響とのライブが確認されるのみ。
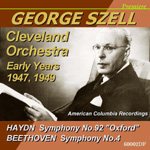
●ジョージ・セル/クリーヴランドの初録音 1947年のベートーヴェン交響曲第4番 ほか
プレミエ60002DF
ハイドン 交響曲第92番「オックスフォード」
ベートーヴェン 交響曲第4番
ジョージ・セル指揮クリーヴランド管弦楽団
1949年4月27日、1947年4月22日録音(米コロンビア原盤)モノラル
※ベートーヴェンは、セルがクリーヴランド管と行った初録音。1946年に常任指揮者に就任した直後、楽員を大幅に入れ替えて厳しくトレーニングし、オーケストラの基礎作りの真っ最中であった。
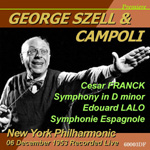
●ジョージ・セル/ニューヨーク・フィル+カンポーリ ライブ フランク ラロ
プレミエ60003DF
フランク 交響曲
ラロ スペイン交響曲
アルフレード・カンポーリ(vl)
ジョージ・セル指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
1953年12月6日、カーネギー・ホール、ニューヨーク
ライブ、モノラル
※一晩のコンサートにおける録音。セルはフランクをスタジオ録音していないが、実演では時折取り上げていた。ラロはフーベルマンとのSP録音がある。カンポーリはラロをデッカにスタジオ録音していた。音質良好。

●ミュンシュ 1958年ライブ ベートーヴェン 交響曲第9番
プレミエ60004DF
ベートーヴェン 交響曲第9番
レオンティン・プライス(s)、モーリーン・フォレスター(ms)
デイヴィッド・ポレリ(t)、ジョルジョ・トッツィ(br)
ニュー・イングランド音楽院合唱団
シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団
1958年12月20日、ボストン・シンフォニー・ホール
ライブ、モノラル
※モノラルだが録音優秀。ミュンシュは同曲を同じ頃米RCAにスタジオ録音していた。歌手陣も同一。この上演直後にレコーディングが行われたようだ。
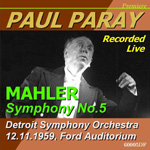
●ポール・パレー ライブ マーラー 交響曲第5番
プレミエ60005DF
マーラー 交響曲第5番
ポール・パレー指揮デトロイト交響楽団
1959年11月12日、フォード・オーディトリアム、デトロイト
ライブ、モノラル
※モノラルだが録音優秀。パレーとマーラーという異例の組み合わせだが、正規のレコーディングのみでは演奏家のレパートリーが判断できない実例。パレーは作曲家でもあり、R・シュトラウスほかドイツ近代作品なども積極的に取り上げていた。

●リヒテル/ミュンシュ 1960年ライブ ブラームス ピアノ協奏曲第2番
プレミエ60006DF
ブラームス ピアノ協奏曲第2番
スビャトスラフ・リヒテル(ピアノ)
シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団
1960年11月1日、ボストン・シンフォニー・ホール
ライブ、モノラル
※リヒテルが初訪米した際のライブ。モノラルながら録音は優秀。ピアノ独奏も明確で管弦楽とのバランスも良好。詳しくは後で述べるが、モノラルにもかかわらず、なぜか若干のステレオ・プレゼンスを感じ、純粋なモノラルよりも聴きやすい。当時FM放送を担当したボストンの放送局WGBHは、1959年頃からステレオでボストン響の演奏会を収録しており、当ディスクの演奏も当然ステレオで録音・保存されたと思われる。ただし、1960年代の社屋火災によって、1959年秋から60年夏頃までの演奏会のステレオ・テープが失われ、現在は火災を免れた同時収録のモノラル・テープしか残っていないと言われる。しかし当録音は時期が少し遅いためステレオ・テープが失われたとは考えにくく、実際にオリジナル音源の波形を見ると左右チャンネルにわずかな違いがあることが確認できる。ステレオ・マイクとステレオ・レコーダーで収録したものの、マイク・セッティングに失敗したか補助マイクなど一部機器のトラブルでモノラルと大差ない録音結果となったのではないかと想像される。
リヒテルは1960年にアメリカ・デビューしてセンセーショナルな成功を収め、一躍国際的な名声を得た。アメリカ滞在時にはコンサートと並行してレコーディングも行い、このブラームスの協奏曲も当録音の10日ほど前、米RCAにラインスドルフ指揮シカゴ響とスタジオ録音している。ただし指揮者は、当初予定されていたライナーと意見が合わずラインスドルフに交代したといわれ、ラインスドルフとの録音も、リヒテル本人は「不出来な演奏だった」と語る一方、ミュンシュと共演した当ディスクの演奏を気に入っていたらしい。ミュンシュとはベートーヴェンのピアノ協奏曲第1番をスタジオ録音しているが(当ディスクの演奏翌日に録音。当コンサート前半にも演奏している)、ミュンシュとのブラームスのスタジオ録音が実現しなかったことは残念である。米RCAは、ブラームスについては独墺系の指揮者を優先的に選択したのだろうが、その意味でミュンシュとの共演は貴重な録音といえる。

●音質一新! クレンペラー/フィラデルフィア ステレオ・ライブ ベートーヴェン「英雄」
プレミエ60007DFII
ベートーヴェン 交響曲第3番「英雄」
オットー・クレンペラー指揮フィラデルフィア管弦楽団
1962年10月19日録音、アカデミー・オブ・ミュージック、フィラデルフィア
ライブ、ステレオ
※クレンペラーが1962年秋、フィラデルフィア管に客演した際のライブ録音の一つ。一連の録音のうち、10月19日の「英雄」と「田園」は特に音質が悪く、一般向けではないという評価がされていた。今回、新たに発見された音源からのCD化により音質が一新。歪みが大幅に低減され、貧相でドライと言われていた音質に潤いが復活した。フィラデルフィア管の本拠地アカデミー・オブ・ミュージックは残響が少ないホールだが、それでも音質が改善されたことで、残響が少ない中でも臨場感が増し、十分鑑賞に堪えるようになった。また音質が明るくなり、フィラデルフィア管らしい響きを聴くことができる。
音質が大幅に改善されたことで、演奏の印象も変わった。既出盤は、遅いテンポがクレンペラーらしいものの、緊張感が乏しく鈍重なイメージがあったが、新盤は響きが充実し、悠揚迫らぬスケールの大きな演奏という、本来の姿がよみがえった。
クレンペラーがフィラデルフィア管に客演した際、ストコフスキー以来伝統の第1・第2ヴァイオリンの配置を、両翼配置に変更させたことは有名な話だが、ステレオ録音であることでそれが確認できる。おそらく客演する条件として配置の変更が含まれていたと思われるが、楽員などからの反発はなかったのだろうか。
クレンペラーは上記CDのほかにベートーヴェンの「英雄」を、1955年と1959年に英EMIにフィルハーモニア管とスタジオ録音したほか、5または6種類ほどのライブ録音を残している。
ちなみに、「英雄」と同日に演奏された「田園」は、当レーベル・プレミエ60082DFで発売されている。
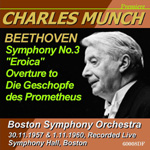
●ミュンシュ/ボストン ライブ ベートーヴェン 交響曲第3番「英雄」
プレミエ60008DF
ベートーヴェン 交響曲第3番「英雄」、序曲「プロメテウスの創造物」
シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団
1957年11月30日、1960年11月1日、ボストン・シンフォニー・ホール
ライブ、モノラル
※録音優秀。ジャケット表記は序曲はステレオとあるがモノラルのようだ。ミュンシュは「英雄」をこの上演直後米RCAにスタジオ録音していた。公演とレコーディングをセットで行うのは、カラヤンでよく知られるが、これはその先行例。
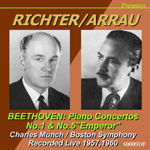
●ミュンシュ リヒテル&アラウ ライブ ベートーヴェン ピアノ協奏曲第1番、第5番「皇帝」
プレミエ60009DF
ベートーヴェン ピアノ協奏曲第1番、第5番「皇帝」
スビャトスラフ・リヒテル(p)、クラウディオ・アラウ(p)
シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団
1960年11月1日、1957年11月30日、ボストン・シンフォニー・ホール
ライブ、モノラル
※ジャケット表記は、リヒテルの1番がステレオとあるが実際はモノラル。ちなみにアラウとの「皇帝」の後、60008DF「英雄」が演奏された。ミュンシュ/ボストン響の黄金期を象徴するプログラム。リヒテルの方は60006DFのブラームスのピアノ協奏曲第2番と同じ日の演奏、一晩で協奏曲2曲というこれまた贅沢なプログラム。いずれも録音優秀。
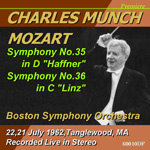
●ミュンシュ/ボストン ステレオ・ライブ モーツァルト 交響曲第35番「ハフナー」、第36番「リンツ」
プレミエ60010DF
モーツァルト 交響曲第35番「ハフナー」、第36番「リンツ」
シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団
1962年7月22日、21日、タングルウッド
ライブ、ステレオ
※タングルウッド音楽祭におけるライブ。音質優秀。ジャケット表記はステレオだがステレオプレゼンスのあるモノラルという感じ。ステレオレコーダーで収録しつつもマイクセッティングがモノラルに近いのだろう。ミュンシュはモーツァルトの交響曲をスタジオ録音していない。

●ミュンシュ/ボストン ステレオ・ライブ モーツァルト交響曲第40番、第41番「ジュピター」
プレミエ60011DF
モーツァルト 交響曲第40番、第41番「ジュピター」
シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団
1962年7月15日、21日、タングルウッド
ライブ、ステレオ
※タングルウッド音楽祭におけるライブ。前出60010と同様、ジャケット表記はステレオだがステレオプレゼンスのあるモノラルという感じ。ステレオレコーダーで収録しつつもマイクセッティングがモノラルに近いのだろう。40番は若干残響が乏しくデッドだが両曲とも音質は良好。ミュンシュは両曲ともなぜかスタジオ録音を残さず、41番は現在確認されている唯一の録音。この年のタングルウッドで、ミュンシュは第35番「ハフナー」やレクイエムも演奏しており、モーツァルトを集中的に取り上げたようだ、
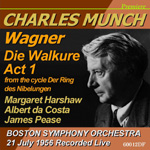
●ミュンシュ ワーグナー楽劇「ワルキューレ」第1幕
プレミエ60012DF
ワーグナー ワルキューレ 第1幕全曲
マーガレット・ハーショウ(ソプラノ)~ジークリンデ
アルベルト・ダ・コスタ(テノール)~ジークムント
ジェームズ・ピース(バス・バリトン)~フンディング
シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団
1956年7月21日録音、タングルウッド、ライブ モノラル
※タングルウッド音楽祭における演奏会形式による上演のライブ録音。ミュンシュはこの作品をスタジオ録音しておらず、珍しいレパートリーだが、彼はかつてライプツィヒ・ゲヴァントハウス管のコンサート・マスターを務めており、同オケがピットに入ったライプツィヒ歌劇場では、しばしばワーグナーを演奏した経験があったようだ。

●ミュンシュ/ボストン ステレオ・ライブ ベートーヴェン 交響曲第5番、第4番
プレミエ60013DF
ベートーヴェン 交響曲第5番、第4番
シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団
1960年1月31日、ボストン・シンフォニー・ホール
1959年8月7日、タングルウッド
ライブ、ステレオ
※5番はボストン・シンフォニー・ホール、4番はタングルウッド音楽祭におけるステレオ・ライブ。音質優秀。ミュンシュは5番を1955年米RCAにボストン響とスタジオ録音。4番を1964年フランス国立管とライブ録音していた。
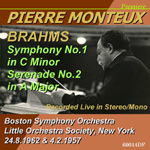
●モントゥー/ボストン ステレオ・ライブ ブラームス 交響曲第1番ほか
プレミエ60014DF
ブラームス 交響曲第1番、セレナード第2番
ピエール・モントゥー指揮ボストン交響楽団、リトル・オーケストラ・ソサエティ
1962年8月24日、タングルウッド
1957年2月4日、ニューヨーク・タウンホール
ライブ、ステレオ/モノラル
※交響曲はステレオ収録。音質良好。タングルウッド音楽祭におけるライブ。モントゥーは両曲ともスタジオ録音していない。リトル・オーケストラ・ソサエティはニューヨークに本拠をおく室内楽団。
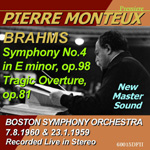
●優秀録音 モントゥー/BSO ステレオ・ライブ ブラームス交響曲第4番ほか
ブラームス 交響曲第4番、悲劇的序曲
ピエール・モントゥー指揮ボストン交響楽団
1960年8月7日、タングルウッド
1959年1月23日、ボストン・シンフォニーホール、
ライブ、ステレオ
※新音源による再発売。交響曲はタングルウッド音楽祭、序曲はボストン響の本拠地シンフォニー・ホールにおけるライブ。交響曲は今回新たに音質優秀なマスターを入手。従来の盤とは比べると、はるかに滑らかで潤いのある充実した音質で当時のメジャーレコード会社のスタジオ録音に匹敵。大幅な音質改善でモントゥーによるブラームス4番がようやく満足できる音質で聴けることになった。
モントゥーのブラームスというと、3回スタジオ録音した交響曲第2番が得意のレパートリーのように思われるが、交響曲第2番は、ボストン響との共演に限って言えば1920年代の常任時代に数回取り上げたのみで、1950年代以降の客演時代には全く演奏しておらず、第1番や第4番が多い。レコードと実演の違いが出た典型であろう。
交響曲第4番を含む1960年の演奏会は、ヴォーン・ウィリアムズのタリスの主題による幻想曲で始まり、ベートーヴェンのピアノ協奏曲第3番(レオン・フライシャー独奏)、休憩を挟んでブラームスというラインナップ。前日の昼には、公開リハーサルで同じプログラムが取り上げられたが、3曲の前には、当日夜に公演が予定されていたユージン・イストミン独奏、シャルル・ミュンシュ指揮でブラームスのピアノ協奏曲第2番のリハーサルも行われた。長大なリハーサルだったのか。それともサマーシーズンの気軽さで、重要ポイントだけ抑えた簡易なものだったのだろうか。
悲劇的序曲が演奏された1959年の録音は4回公演の定期演奏会3日目で、悲劇的序曲に続きヒンデミットの「気高き幻想」、休憩を挟んでR・シュトラウスの「ドン・キホーテ」というプログラム。ちなみに「気高き幻想」は、プレミエ60078でCD発売されている。いずれもドイツ系の作品が中心で、モントゥー好みの選曲と言えそうだ。
上記のようにモントゥーは交響曲第4番をスタジオ録音しておらず、この演奏が現在確認されている唯一の録音。悲劇的序曲は1962年にロンドン響と蘭フィリップスにスタジオ録音したほか、1949年にサンフランシスコ響、1960年にフィラデルフィア管、1962年にコンセルトヘボウ管とライブ録音していた。
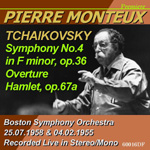
●モントゥー/ボストン ステレオ・ライブ チャイコフスキー 交響曲4番ほか
プレミエ60016DF
チャイコフスキー 交響曲4番、幻想序曲「ハムレット」
ピエール・モントゥー指揮ボストン交響楽団
1958年7月25日、タングルウッド
1955年2月4日、ボストン・シンフォニー・ホール
ライブ、ステレオ/モノラル
※交響曲はステレオ収録。タングルウッド音楽祭におけるライブ。モントゥーは交響曲第4番を米RCAにスタジオ録音している。「ハムレット」は珍しい作品でモントゥーもこれ以外には録音を残していない。
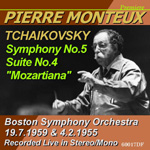
●モントゥー/ボストン ステレオ・ライブ チャイコフスキー 交響曲5番ほか
プレミエ60017DF
チャイコフスキー 交響曲5番、組曲「モーツァルティアーナ」から主題と変奏
ピエール・モントゥー指揮ボストン交響楽団
1959年7月19日、タングルウッド
1955年2月4日、ボストン・シンフォニー・ホール
ライブ、ステレオ/モノラル
※交響曲はステレオ収録。タングルウッド音楽祭におけるライブ。モントゥーは交響曲第5番を米RCAにスタジオ録音しているほか、コンサートホールソサエティや米ヴァンガードにも録音していた。「モーツァルティアーナ」は現在確認されている唯一の録音。
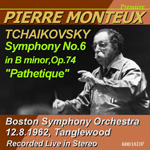
●モントゥー/ボストン ステレオ・ライブ チャイコフスキー 交響曲6番
プレミエ60018DF
チャイコフスキー 交響曲6番
ピエール・モントゥー指揮ボストン交響楽団
1962年8月12日、タングルウッド、ライブ、ステレオ
※ステレオ収録。タングルウッド音楽祭におけるライブ。音質優秀。モントゥーは同曲を1955年米RCAにスタジオ録音している。60016DF・60017DF・60018DFでチャイコフスキー後期3大交響曲がステレオ・ライブでそろう。
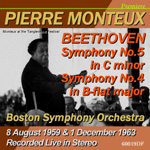
●モントゥー/ボストン ステレオ・ライブ ベートーヴェン 交響曲第5番、4番
プレミエ60019DF
ベートーヴェン 交響曲第5番、第4番
ピエール・モントゥー指揮ボストン交響楽団
1959年8月8日、タングルウッド
1963年12月1日、ボストン・シンフォニー・ホール
ライブ、ステレオ
※5番はタングルウッド音楽祭(当時はバークシャー音楽祭と呼ばれた)、4番はボストン・シンフォニー・ホールにおける定期公演のステレオ・ライブ。2曲とも音質良好。音質は、第5番は明るく開放的で、いかにも夏の音楽祭のライブというイメージ。音楽祭の会場クーセヴィツキー・シェドは、天井はあるものの客席側の壁がない半開放的ホールであり、残響が乏しいなど音響条件はあまり良くないため、やや荒れた感じもあるが、音源に近いダイレクトな臨場感が好ましい。一方、第4番は、豊かな残響で艶のある、オーソドックスなオーケストラ録音。第5番と比較すると残響が多いためか解像度はやや控えめ。伝統的なシューボックススタイル・ホールの音響が聴ける。
モントゥーは、ミュンシュのボストン響(BSO)音楽監督時代(1948~1962年)に毎シーズン客演を重ねたが、ベートーヴェンの交響曲については、第2番と6番をそれぞれ12回と最も多く演奏し、続いて4番と5番をそれぞれ8回、3番を7回、1番を6回、9番を3回取り上げている。このうち当盤の第5番は、1954~1955年シーズン以来4年ぶりの演奏で、BSOとの同曲最後の演奏機会であっただけに、良好なステレオ録音が残されたことは幸いである。この日のプログラムは、前半にフィデリオ序曲、第6番「田園」、休憩後に第5番というオール・ベートーヴェン・プロで、「田園」と「フィデリオ序曲」は当レーベルの60041DFで発売済みである。一方、第4番の録音日は12月20日が正しい。モントゥー最後のBSO客演で、19~21日の3回公演2日目に当たる。この日のプログラムは、ヴォーン・ウィリアムズの「タリスの主題による幻想曲」、ベートーヴェン交響曲第4番、休憩後にシベリウス「トゥオネラの白鳥」、エルガー「エニグマ変奏曲」という英国・北欧寄りのプログラム。当時モントゥーがロンドン響の首席指揮者に就いていた影響を考える見方もできるが、モントゥーはBSOで「エニグマ」を1950年代中頃から、「タリス幻想曲」に至っては、同曲が1910年に作曲されて間もない1920年代から取り上げており、モントゥーが古くから広大なレパートリーを持っていたことが分かる。
モントゥーは当盤以外に、ベートーヴェン交響曲第5番を、1961年英デッカにロンドン響とスタジオ録音していたほか、1947年(前半2楽章)と1950年(後半2楽章)にサンフランシスコ響、1958年にボストン響とライブ録音していた。また4番は、1952年米RCAにサンフランシスコ響、1959年英デッカにロンドン響、1960年コンサートホールソサエティにハンブルク北ドイツ放送響とスタジオ録音していた。

●ミュンシュ/ボストン ステレオ・ライブ ブラームス 交響曲第1番ほか
プレミエ60020DF
ブラームス 交響曲第1番、セレナード第1番(抜粋)
シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団
1961年11月7日、1959年2月28日、ボストン・シンフォニー・ホール
ライブ、ステレオ
※音質優秀なステレオ収録。両曲ともボストン響の本拠地シンフォニーホールにおけるライブ。ミュンシュは交響曲第1番を、1956年米RCAにボストン響、1968年仏EMIにパリ管と、それぞれスタジオ録音。1962年日本フィル、1968年フランス国立管(2~4楽章のみ)とライブ録音していた。セレナードは、2、3楽章なしの抜粋演奏。ミュンシュは同曲をスタジオ録音しておらず、これが現在確認されている唯一の演奏。

●カラヤン/ニューヨーク・フィル ライブ ベートーヴェン 交響曲第9番
プレミエ60021DF
ベートーヴェン 交響曲第9番
レオンティン・プライス(s)、モーリン・フォレスター(ms)
レオポルド・シモノー(t)、ノーマン・スコット(bs)
ウェストミンスター合唱団
ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
1958年11月22日、ニューヨーク・カーネギー・ホール、ライブ、モノラル
※ニューヨーク・フィルと唯一の共演となった1958年カラヤン渡米時のライブ。3つのプログラムで公演が行われた。交響曲第9番の前には第1番が演奏された(60025DFに収録)。年代相応の音質だがバランスも良く鑑賞に支障はない。
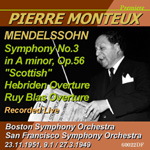
●モントゥー/ボストン ライブ メンデルスゾーン「スコットランド」ほか
プレミエ60022DF
メンデルスゾーン 交響曲第3番「スコットランド」、
序曲「フィンガルの洞窟」、序曲「ルイ・ブラス」
ピエール・モントゥー指揮ボストン交響楽団、サンフランシスコ交響楽団
1951年11月23日、ボストン・シンフォニー・ホール
1949年1月9日、3月27日、ウォー・メモリアル・オペラ・ハウス、サンフランシスコ
ライブ、モノラル
※交響曲がボストン響、序曲がサンフランシスコ響による演奏。交響曲は、アメリカの放送現場などでテープ・レコーダーが導入され始めた頃の録音。周波数レンジはやや狭いが、ノイズも少なく、安定した音質で鑑賞には問題ない。一方、2つの序曲はアセテート盤による録音。それでもディスク録音末期の技術的成熟期でもあり、わずかなスクラッチノイズが入る以外は、音質は交響曲とあまり差がない。
モントゥーは1919~1924年にボストン響の常任指揮者を務めたが、後任となったセルゲイ・クーセヴィツキーは在任中、モントゥーを客演に招こうとしなかった。モントゥーの伝記によれば、オーケストラ側から、退任後も翌シーズンから客演に呼びたいと言われていたが、全く実行されなかったとぼやいている。その約束が果たされたのは27年後の1951年、クーセヴィツキーの後を継いだシャルル・ミュンシュ時代になってからであった。ミュンシュはモントゥーと懇意で、ミュンシュが1962年に常任を離れるまで、モントゥーは頻繁に同響の指揮台に立った。
メンデルスゾーンの「スコットランド」は客演復帰2シーズン目にあたる演奏。モントゥーが正式なレコーディングを行わなかったレパートリーで非常に珍しい。ボストン響との演奏も当録音を含む1951年11月~12月の4回公演のみで、後のロンドン響首席時代にも演奏していない。23日のプログラムは、バッハ=レスピーギ編曲のパッサカリアとフーガ・ハ短調、「スコットランド」、休憩をはさんで、後半はモントゥーお気に入りの2曲、ヒンデミットの交響曲「画家マチス」、R・シュトラウスの「ティル・オイレンシュピーゲル」というもの。「スコットランド」はメイン・プログラムではなかったことになる。
モントゥーは上記の演奏以外に、「ルイ・ブラス」のみ1947年米RCAにサンフランシスコ響とスタジオ録音していたが、その他の録音は現在まで確認されていない。
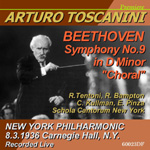
●トスカニーニ/ニューヨーク・フィル 1936年ライブ ベートーヴェン 交響曲第9番
プレミエ60023DF
ベートーヴェン 交響曲第9番
ローザ・テントーニ(s)、ローズ・バンプトン(ms)
チャールズ・クールマン(b)、エツィオ・ピンツァ(bs)
ニューヨーク・スコラ・カントルム合唱団
アルトゥーロ・トスカニーニ指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
1936年3月8日、ニューヨーク・カーネギーホール、ライブ、モノラル
※トスカニーニ/ニューヨーク・フィルによる戦前の貴重なライブ。トスカニーニ69歳前後の記録。数種残されている第9のうち、現在確認されている最初の録音。アセテート盤による古い録音だが、当代随一といわれたコンビの片鱗が伺える。
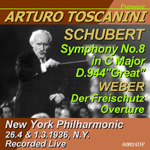
●トスカニーニ/ニューヨーク・フィル 1936年ライブ シューベルト「グレイト」、ウェーバー「魔弾の射手」序曲
プレミエ60024DF
シューベルト 交響曲第8(9)番「グレイト」
ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」序曲
アルトゥーロ・トスカニーニ指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
1936年4月26日、ニューヨーク・カーネギーホール
1936年3月1日、ニューヨーク・ラジオ・シティ・ミュージック・ホール
ライブ、モノラル
※トスカニーニ/ニューヨーク・フィルによる戦前の貴重なライブ。トスカニーニ69歳前後の記録。導入間もない初期のアセテート盤による録音でスクラッチノイズも多いが、録音そのものは意外と明瞭で、当時の標準的なSPレコード録音より多少劣る程度。トスカニーニは、シューベルトは6種、ウェーバーは3種の録音を残しているといわれているが、2曲ともこのCDの演奏が、現在確認されている最も古い録音と思われる。シューベルトはカーネギー・ホール、ウェーバーは、当時完成まもないロックフェラー・センターにおけるガラ・コンサート(ゼネラル・モーターズ・コンサート)における演奏。
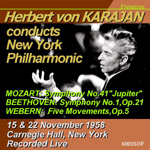
●カラヤン/ニューヨーク・フィル ライブ モーツァルト「ジュピター」、
ベートーヴェン 交響曲第1番
プレミエ60025DF
モーツァルト 交響曲41番「ジュピター」
ベートーヴェン 交響曲第1番
ウェーベルン 弦楽四重奏のための5つの楽章(弦楽合奏編曲版)
ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
1958年11月15日、22日、ニューヨーク・カーネギーホール、ライブ、モノラル
※ニューヨーク・フィルと唯一の共演となった1958年カラヤン渡米時のライブ。同フィル音楽監督のバーンスタインがリハーサルを無断で録音したため、両者の友好関係が壊れたといわれる。年代相応の音質だがバランスも良く鑑賞に支障はない。
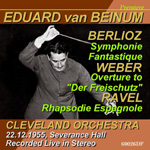
●ベイヌム/クリーヴランド ライブ 唯一の共演 ベルリオーズ 幻想交響曲ほか
プレミエ60026DF
ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」序曲
ラヴェル スペイン狂詩曲
ベルリオーズ 幻想交響曲
エドゥアルド・ファン・ベイヌム指揮クリーヴランド管弦楽団
1955年12月22日、セヴェランス・ホール、ライブ、ステレオ
※1955年という、極めて早い時期のステレオ録音。マイクセッティングに不慣れなためか、左右の広がりに少し欠けるが、音質は鮮明で分離も良い。
当時コンセルトヘボウ管に客演したジョージ・セルが、返礼のため同管の常任指揮者ベイヌムを、自ら率いるクリーヴランド管に招いたという。その後も客演の招聘があったというが、ベイヌムの早世により、この演奏が両者唯一の共演となった。クリーヴランド管はセルによる常任9年目。セルの厳しいトレーニングにより一流オーケストラの仲間入りをしつつあった時期にあたり、米コロムビア(エピック)へのレコード録音も活発化していた。
ベイヌムは、スペイン狂詩曲を1946年英デッカにスタジオ録音、幻想交響曲を1946年と1951年英デッカにスタジオ録音していたほか、1943年独ポリドールにSP録音していたが未発売に終わったという。「魔弾の射手」序曲はスタジオ録音を残さず、このライブが現在確認できる唯一の演奏と思われる。

●ミュンシュ/ボストン 高音質ステレオ・ライブ サン・サーンス「オルガン付き」ほか
プレミエ60027IIDF
サン・サーンス 交響曲第3番
ラヴェル ラ・ヴァルス
ベルイ・ザムコヒアン(オルガン)
シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団
※1966年3月11日、2月2日、ボストン・シンフォニー・ホール
ステレオ ライブ
※ステレオ録音で音質優秀。今回のプレスから新たな音源をマスターとして使用し、音質がさらに向上した。当時のライブとしては驚異的な優秀録音。以前の音源よりも歪みが減り、ダイナミックレンジが拡大、オルガンの低域がよく聞き取れるようになった。ただし、繊細なピアニッシモの表現が向上した一方、フォルティッシモもパワーアップしたため、「爆発」時の大音量には要注意。サン・サーンスはかつてイタリアのマイナーレーベルからリリースされていたが、それとは比較にならない高音質。
ミュンシュ得意ののサン・サーンス交響曲第3番だが、ボストン響とは1946~47年シーズンに3公演、1949~50年7公演、1950~51年2公演、1953~54年6公演、1958~59年2公演、常任指揮者退任後の1962~63年シーズン4公演、1965~66年5公演と数多く取り上げている。本人が好んだこともあろうが、聴衆の人気も絶大だったようだ。なお、本CDの録音年月日は、以前は1962年4月20日と表記されていたが、今回初めて正確な録音年月日が判明した。1966年ということは、ミュンシュが常任退任後、最後の演奏機会となった際の録音ということになる。終楽章のコーダを延々と引き延ばすのはミュンシュならではのスタイルだが、ここでは引き延ばしすぎてトランペットが途中でブレスを入れているほど。時折ミュンシュの「かけ声」が聞こえる。
一方、ラヴェルのラ・ヴァルスも得意の曲目で、1949年のボストン響常任指揮者就任後、ほとんど毎シーズン取り上げている。後任の常任指揮者ラインスドルフが、ミュンシュ時代のレパートリーがフランス作品偏重だったことを批判したが、本CDにおける演奏後の熱狂的な喝采を聴くと、ミュンシュの熱狂的人気が分かり、レパートリーの偏りなどどうでもよいという気もする。一方で、「理知的演奏」を旨とする後任ラインスドルフはミュンシュのような大衆的人気を得ることは出来ず、結果的に貧乏くじを引いてしまった。
ミュンシュは、サン・サーンスの交響曲第3番を1947年米CBSにNYPと、1959年米RCAにボストン響とスタジオ録音していたほか、1954年ボストン響とライブ録音していた。また、ラヴェルのラ・ヴァルスを 1942年仏グラモフォンにパリ音楽院管と、1950年、1955年、1958年、1962年それぞれ米RCAにボストン響とスタジオ録音していたほか、1958年にボストン響、1963年シカゴ響とライブ録音していた。

●ミュンシュ/ボストン ステレオ・ライブ モーツァルト「レクイエム」
プレミエ60028DF
モーツァルト「レクイエム」
フィリス・カーティン(s)、フローレンス・コプレフ(ms)
ブレイク・スターン(t)、マック・モーガン(bs)
タングルウッド音楽祭合唱団
シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団
1962年7月22日、タングルウッド、ライブ、ステレオ
※ステレオ収録。タングルウッド音楽祭におけるライブ。音質優秀。現在までに確認されているミュンシュ唯一の記録。
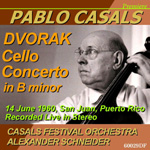
●カザルス ステレオ・ライブ ドヴォルザーク チェロ協奏曲 1960年
プレミエ60029DF
ドヴォルザーク チェロ協奏曲
パブロ・カザルス(vc)
アレクサンダー・シュナイダー指揮プエルト・リコ・カザルス音楽祭管弦楽団
1960年6月14日、プエルト・リコ大学講堂、ライブ、ステレオ
※プエルト・リコのサンフアンで開催されたカザルス音楽祭におけるライブ。米エベレストが演奏者の許可?を得ることなく録音、LP発売したものの急きょ回収した演奏と同一か。当時は放送局によるビデオ収録やラジオ中継も行われており、複数の録音ラインがあったため、本CD-Rがエベレストの音源そのものかどうかは不明。
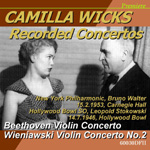
●女流ヴァイオリニスト カミラ・ウィックス ベートーヴェン ヴィエニャフスキ ヴァイオリン協奏曲
プレミエ60030DF
ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲
ヴィエニャフスキ ヴァイオリン協奏曲
カミラ・ウィックス(vl)
ブルーノ・ワルター指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
レオポルド・ストコフスキー指揮ハリウッド・ボウル交響楽団
1953年2月15日、ニューヨーク・カーネギーホール
1946年7月14日、ハリウッド・ボウル
ライブ、モノラル
※女流ヴァイオリニスト、カミラ・ウィックスの協奏曲ライブ録音をまとめたもの。ベートーヴェンはブルーノ・ワルターと共演したライブ、音質は1950年代前半のニューヨーク・フィル(NYP)のライブ録音としては上質な部類。当時のNYPのライブ録音といえば、ラフでドライ、ノイズ混じりの音質が標準的であるが、当CDの録音はノイズもなく、潤いのある滑らかな音質で、十分に音楽を楽しむことができる。当日のプログラムは、前半にモーツァルトの交響曲第38番、後半がベートーヴェンの協奏曲とレオノーレ序曲第3番というもの。現代の感覚からは演奏の順番が逆のような感もあるが、やはり演奏会におけるモーツァルトの重要度が低かったためか。またはウィックスに注目したためか。
ちなみにウィックスはNYPとは、1946年4月シベリウスのヴァイオリン協奏曲(ロジンスキー指揮)、1957年4月クラウス・エッゲのヴァイオリン協奏曲(フランコ・アウトリ(オートリ)指揮)で共演している。
ストコフスキーと共演したヴィエニャフスキは、野外劇場ハリウッド・ボウルにおけるライブで、ウィックスはデビュー間もない17歳の時の演奏。ジャケットの4月17日は誤りで、夏の夜の野外コンサートである。当時はまだテープ録音が導入されておらず、アセテート盤による録音。このため元の音源は盛大なスクラッチノイズが入っていたが、音質を損ねない範囲で低減させている。ラジオ放送のための録音であるため音質自体は良好。野外劇場のライブ録音というハンディを感じさせないところは、さすがにアメリカの放送局の技術力の高さを感じる。
当日のプログラムは、カバレフスキーのコラ・ブルニョン序曲、グリンカのホタ・アラゴネーサ、ヴィエニャフスキの協奏曲、ブリテンのピーター・グライムズからパッサカリア、同じくブリテンのソワレ・ミュージカル、ラヴェルのツィガーヌ、クライスラーのウィーン奇想曲、オネゲルのパシフィック231という、ストコフスキーらしい名曲コンサート。ウィックスはツィガーヌ、ウィーン奇想曲も演奏した。
ハリウッド・ボウル響はロサンゼルス・フィルの別名であり、同フィルのコンサートスケジュールに組み込まれているが、このコンサートに限っては、ストコフスキーがロサンゼルス在住のフリーランス演奏家を何名か起用したと言われ、それらの演奏家との混成だったようだ。
ウィックスは1951年に結婚後、家庭を優先して次第に演奏活動を控えるようになり、ノルウェーに転居するなど、演奏家としての国際的キャリアから退いたが、父がノルウェー出身であるため同国との関係は深く、上記のように1957年、29歳頃のNYPとの共演ではノルウェーの作曲家エッゲの作品を取り上げている。
ウィックスの正規の録音は少なく、上記2曲ともスタジオ録音を残していない。ブルーノ・ワルターは上記CDのほかに、ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲を、1932年英コロンビアにシゲティと、1947年米コロンビアに同じくシゲティと、1961年米コロンビアにフランチェスカッティとスタジオ録音したほか、1949年モリーニとライブ録音していた。ストコフスキーは上記CD以外には、ヴィエニャフスキのヴァイオリン協奏曲第2番を録音していない。
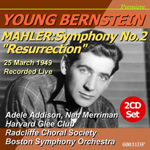
●バーンスタイン/ボストン 若き日のライブ マーラー 交響曲第2番「復活」
プレミエ60031DF
マーラー 交響曲第2番「復活」
アディル・アディソン(s)、ナン・メリマン(ms)
ハーヴァード・グリー・クラブ、ラドクリフ合唱協会
レナード・バーンスタイン指揮ボストン交響楽団
1949年3月25日、ボストン・シンフォニー・ホール、ライブ、モノラル
※バーンスタイン30歳のライブ。1947年にニューヨーク・シティ交響楽団音楽監督を退任後、当時はフリーだったが、ボストン響常任指揮者のクーセヴィツキーに師事したこともあり、同オーケストラとは、同じ1949年にメシアン「トゥーランガリラ交響曲」を世界初演するなど、密接な関係にあった。年代を考慮すれば音質は良好。

●ミュンシュ/ボストン 1962年ステレオ・ライブ ベートーヴェン 交響曲第9番
プレミエ60032DF
ベートーヴェン 交響曲第9番
アディル・アディソン(s)、フローレンス・コプレフ(ms)
ジョン・マッカラム(t)、ドナルド・グラム(bs)
音楽祭合唱団、モントリオール大学合唱団
シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団
1962年8月26日、タングルウッド、ライブ、ステレオ
※ステレオ収録。タングルウッド音楽祭(当時はバークシャー音楽祭と呼ばれた)におけるライブ。音質優秀。ボストン響のタングルウッド音楽祭におけるステレオ録音は1958年頃から開始されているが、4年目に当たる当録音は、技術的にもさすがに手慣れた感じで、バランスも良く申し分ない。もちろん、用意周到に練り上げられたメジャーレコード会社のスタジオ録音とは趣が異なり、フォルティッシモなどはやや荒れ気味で(ミュンシュの最強音が大きすぎるのだ)、ライブならではノイズも入るが(それでも会場ノイズは少ない方だ)、却って生々しい臨場感が魅力的である。
ミュンシュは1961~1962年シーズンを最後にボストン響(BSO)の常任指揮者を退任しており、この演奏は、ミュンシュが音楽監督として指揮した最後の演奏会である。とはいうものの、その後も客演指揮者として、翌1963年1~2月に10公演、7~8月に5公演行うなど、亡くなる1968年まで毎シーズンBSOと共演しており、ミュンシュの人気が相変わらず高かったことを物語る。後任のラインスドルフは厳しいリハーサルで知られ、次第に団員と軋轢が増していったと言われているから、ミュンシュの客演はラインスドルフにとって気分の良いものではなかったかも知れない。
この日のプログラムは、コープランドの「静かな都会」とベートーヴェンの交響曲第9番の2曲。前日に同じプログラムで公開リハーサルが行われた。ミュンシュはBSO在任時に第9番を20回取り上げており(先のリハーサルを含む)、当盤が最後の演奏機会となった。現在のBSOの資料では、音楽祭合唱団はバークシャー音楽祭合唱団との表記されているが、当時のプログラムには単にFestival
Chorusと表記されているため、それに従った。
ミュンシュは当盤以外に、ベートーヴェン交響曲第9番を1958年米RCAにBSOとスタジオ録音したほか、1958年8月と12月、1962年4月にBSO、同年12月日本フィルとライブ録音していた(1958年12月のライブは当レーベル600004DFで発売済み)。
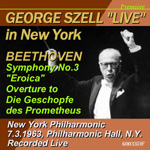
●ジョージ・セル/ニューヨーク・フィル ライブ ベートーヴェン「英雄」
プレミエ60033DF
ベートーヴェン 交響曲第3番「英雄」
プロメテウスの創造物 序曲
ジョージ・セル指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
1963年3月7日、フィルハーモニック・ホール、ニューヨーク、ライブ、モノラル
※モノラルながら音質優秀。セルはしばしばニューヨーク・フィルに客演したが、このときは1955年以来、6シーズンぶりの登場であった。カーネギー・ホールに代わる新たな本拠地として建設されながら、音響の問題から後年改築された旧フィルハーモニック・ホールにおける記録。
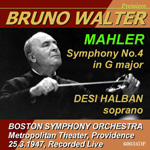
●ブルーノ・ワルター/ボストン響 ライブ マーラー 交響曲第4番
プレミエ60034DF
マーラー 交響曲第4番
デジ・ハルバン(s)
ブルーノ・ワルター指揮ボストン交響楽団
1947年3月25日、プロヴィデンス・メトロポリタン劇場、ライブ、モノラル
※ワルターとボストン響の数少ない共演の記録。ロング・アイランド州プロヴィデンスへのツアーにおけるライブ。古い録音だがノイズも少なくバランスは悪くない。ハルバンは米CBSへのスタジオ録音にも参加していた。
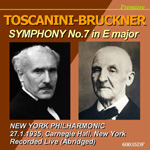
●トスカニーニのブルックナー 1935年ニューヨーク・フィル ライブ
プレミエ60035DF
ブルックナー 交響曲第7番(一部欠落あり)
アルトゥーロ・トスカニーニ指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
1935年1月27日、ニューヨーク・カーネギー・ホール、ライブ、モノラル
※トスカニーニ指揮のブルックナーとして現在確認されている唯一の録音。ウィーンの楽譜出版者グートマンによる、作曲者本人が手を入れたとする改訂版による演奏。ロベルト・ハースによる校訂版が1944年に出版される以前に広く知られていた版である。
初期のアセテート・ディスク・レコーダーによる録音であり、周波数レンジも狭く音質もややくすんだ感じで、年代的・技術的限界はあるが、ノイズは思いのほか少なく、マイクセッティングも適正であるためバランスも良く、とりあえずは音楽を鑑賞できるレベル。1930年代中期のライブ録音という前提を考えれば、そもそも録音が残っていたことが奇跡的であるとも言える。残念ながら、第1楽章の末尾7小節、第2楽章3小節、第4楽章48小節が欠落。それでも全体の8割程度は録音されている。
近年明らかになった録音当時の事情によると、当日の演奏会はコロンビア・ネットワーク(CBS)によるラジオ放送が行われ、そのマイクラインを利用して放送局関係者によって録音が行われたという。前年の1934年に米プレスト社がタイプ6Dアセテート・ディスク・レコーダーを発売しており、本機を使用したのではないかと思われる。ただし、CBSによる正式採用は1938年と言われており(ライバルのNBCは1935年採用)、先行テストケースだったようだ。
タイプ6Dアセテート・ディスク・レコーダーは33・1/3回転の16インチディスク1枚で20分程度の録音が可能だったが、レコーダー1台で録音したため、ディスクの交換時に上記の欠落が生じてしまった。第1楽章はアナウンス部分から録音を開始したためフィナーレが欠落、演奏時間9分適度の第3楽章は欠落なしという点は、このような事情から理解できる。
当初から全曲録音を行う予定があれば、レコーダーを2台用意したはずである。ちなみに当演奏1カ月後の2月から、同じくトスカニーニ/NYPによるブラームス・チクルスが行われ、同様にコロンビア・ネットワークにより中継放送され、その際にも録音が行われたが、こちらは2台(以上?)のレコーダーが使用されたため、交響曲や協奏曲などの各作品が欠落なく録音されたようだ。このような事情を考えると、ブルックナーの録音は、ブラームス・チクルス録音のためのテストだったかも知れない。
当日の演奏会は4回公演の4日目で、午後3時からのマチネー。最初にブルックナー交響曲第7番、休憩を挟んで後半は、R・シュトラウス「サロメ」から7つのヴェールの踊り、バッハ(レスピーギ編)「前奏曲とフーガ」ニ長調というプログラムで、現代の演奏会とは順番が逆のように思えるが、当時のニューヨークの聴衆には、ブルックナーよりも管弦楽編曲版バッハの方がポピュラーだったことが分かる。
トスカニーニとニューヨーク・フィルはブルックナーの交響曲について、第7番を1931年3月に4公演、1935年1月に当録音を含めて4公演、交響曲第4番を1932年に2公演、1934年に1公演取り上げているが、上記ディスクが現在確認されている唯一のブルックナーの録音と思われる。
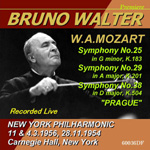
●ブルーノ・ワルター/NYP ライブ モーツァルト 交響曲第25、29、38番
プレミエ60036DF
モーツァルト 交響曲第25番、第29番、第38番「プラハ」
ブルーノ・ワルター指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
1956年3月11日(25番)、3月4日(29番)、1954年11月28日(38番)
ニューヨーク・カーネギー・ホール、ライブ、モノラル
※ワルター得意のモーツァルト。いずれも当時の放送録音の標準を超える良好な音質。バランスも良く、安心して音楽を楽しめる。第38番のライブは、ニューヨーク・フィル(NYP)による1956年米CBSスタジオ録音が1995年にCD発売されるまで、NYPとの貴重な録音と言われた。実際には、1956年録音は米CBSの提携先である仏フィリップスから1961年頃にLP発売されていたが、この事実は日本ではほとんど知られていなかった。ちなみに米本国で未発売だった経緯は不明だが、ワルターがNYPとのベートーヴェン第9第4楽章を再録音・再発売した例にみるように、一度は発売を許可しながらも、不満な部分を録り直そうと考えていたのかも知れない。モーツァルトの39番でも1953年に全曲録音した後、1956年に大半を録り直したと言われる。
ワルターはNYPとの共演でもモーツァルトをしばしば取り上げたが、1956年の交響曲第25番は、当日前半のプログラムで、後半は同じくモーツァルトのレクイエム。第29番は、オール・モーツァルト・プログラムにおけるコンサートで、前半に交響曲第29番とピアノ協奏曲第20番(マイラ・ヘス独奏)、後半に交響曲第39番(これはプレミエ60037DFⅡで発売済み)。1954年の第38番は、前半にベートーヴェンのレオノーレ序曲第3番、続いて交響曲第38番、休憩を挟んだ後半にブラームスの二重協奏曲(アイザック・スターンとレナード・ローズ独奏)、最後に大学祝典序曲という、いささか変則的なプログラムだった。
ワルターは上記の録音以外に、交響曲第25番を、1954年米CBSにNYPとスタジオ録音したほか、1956年にウィーン・フィルとライブ録音。第29番は、1954年米CBSにニューヨーク・フィルとスタジオ録音。第38番は、1936年英HMVにウィーン・フィルと、1954年米CBSにニューヨーク・フィルと、1959年米CBSにコロンビア響とスタジオ録音したほか、1954年フィレンツェ5月音楽祭管、1955年フランス国立放送管、1955年ウィーン・フィルとライブ録音していた。
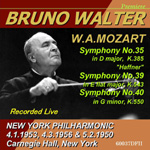
●ブルーノ・ワルター/NYP ライブ モーツァルト 交響曲第35、39、40番
プレミエ60037DFⅡ
モーツァルト 交響曲第35番「ハフナー」、第39番、第40番
ブルーノ・ワルター指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
1953年1月4日(35番)、1956年3月4日(39番)、1950年2月5日(40番)
ニューヨーク・カーネギー・ホール、ライブ、モノラル
※ワルター得意のモーツァルト。35番と39番は、当時の放送録音の標準を超える良好な音質。バランスも良く安心して音楽を楽しめる。一方40番はテープ録音導入間もない頃の録音。マイクセッティングも異なり、やや古い印象の音質だが、聴きづらいほどではなく、一応鑑賞に堪える水準。ただし注意書きにあるように、オリジナル音源には、第4楽章後半部にレコーダーのトラブルによる再生不能箇所が3秒ほどあり、欠落部分のみ1953年の米CBSによるスタジオ録音で補っており、差し替え部分のみ音質がわずかに異なる。
この交響曲第40番は、1980年代にイタリアのマイナーレーベルでLP発売されて以来久々の復活。ニューヨーク・フィル(NYP)による第40番のライブ録音として貴重だが、第4楽章のトラブルが長らく再発売されなかった理由かも知れない。
ワルターはNYPとの共演でもモーツァルトをしばしば取り上げたが、1953年の交響曲第35番は、当日前半のプログラムで、後半はマーラーの交響曲第4番(イルムガルト・ゼーフリート独唱)というワルターらしいプログラム。1956年の第39番は、オール・モーツァルト・プログラムにおけるコンサートで、前半に交響曲第29番(これはプレミエ60036DFで発売済み)とピアノ協奏曲第20番(マイラ・ヘス独奏)、後半に交響曲第39番。1950年の第40番は、こちらもオール・モーツァルト・プログラムにおけるコンサートで、前半にセレナーデ第13番、交響曲第35番、ピアノ協奏曲第20番(ルドルフ・フィルクシュニー独奏)、後半に交響曲第40番が演奏された。
ワルターは、交響曲第35番を上記の録音以外に、1953年米CBSにNYPと、1959年米CBSにコロンビア響とスタジオ録音したほか、1940年NBC響、1947年ボストン響、1950年NYPとライブ録音していた。第39番は上記以外に、1934年英HMVにBBC響と、1953/1956年米CBSにNYPと、1960年米CBSにコロンビア響とスタジオ録音したほか、1944年NYP、1945年NYP、1950年ストックホルム・フィル、1956年フランス国立放送管とライブ録音していた。第40番は上記以外に、1929年英コロンビアにベルリン国立歌劇場管と、1953年米CBSにNYPと、1959年米CBSにコロンビア響とスタジオ録音したほか、1939年NBC響、1949年ロサンゼルス・フィル、1950年ベルリン・フィル、1952年ローマ・イタリア放送(RAI)響、1952年ウィーン・フィル(5月17日と18日の2種)、1952年コンセルトヘボウ管とライブ録音していた。
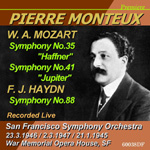
●モントゥー/サンフランシスコ ライブ モーツァルト 交響曲第35、41番、ハイドン 交響曲第88番
プレミエ60038DF
モーツァルト 交響曲第35番「ハフナー」、第41番「ジュピター」
ハイドン 交響曲第88番
ピエール・モントゥー指揮サンフランシスコ交響楽団
1946年3月23日(35番)、1947年3月2日(41番)、1945年1月21日(88番)
サンフランシスコ・ウォー・メモリアル・オペラ・ハウス、ライブ、モノラル
※モントゥー70歳代「壮年期」のライブ。古い録音だがバランスは悪くない。モントゥーは「ジュピター」と88番のスタジオ録音を残さず、現在確認されているのは当録音のみ。「ハフナー」は1964年コンサートホールソサエティにスタジオ録音している。
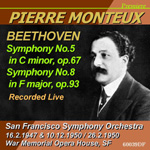
●モントゥー/サンフランシスコ ライブ ベートーヴェン 交響曲第5番、第8番
プレミエ60039DF
ベートーヴェン 交響曲第5番、第8番
ピエール・モントゥー指揮サンフランシスコ交響楽団
1947年2月16日、1950年12月10日(5番)、1950年2月26日(8番)
サンフランシスコ・ウォー・メモリアル・オペラ・ハウス、ライブ、モノラル
※モントゥー70歳代「壮年期」のライブ。古い録音だがバランスは悪くない。ラジオ放送の時間的制約のため、5番は前半2楽章が1947年、後半2楽章が1950年の録音。モントゥーは5番を1961年英デッカにスタジオ録音。8番を1950年米RCA、1959年英デッカにスタジオ録音している。
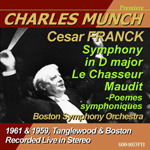
●ミュンシュ/ボストン ステレオ・ライブ フランク 交響曲、交響詩「呪われた狩人」
プレミエ60040DFⅡ
フランク 交響曲、交響詩「呪われた狩人」
シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団
1961年8月5日、1959年10月10日、タングルウッド、ボストン・シンフォニー・ホール
ライブ、ステレオ
※交響曲はバークシャー音楽祭、「呪われた狩人」は本拠地ボストンにおけるステレオライブ。録音優秀だが、メジャーレコードレーベルのスタジオ録音のような、用意周到に磨き上げられた録音というよりも、臨場感のある生々しい音質。ややラフで強奏が若干飽和気味だが、録り直しがきかない緊張感と勢いを感じる。
フランクの交響曲は、今日の日本のクラシック界では演奏機会が多い作品ではないが、第二次世界大戦前後には、巨匠指揮者が好んで取り上げ、フルトヴェングラーなどもレコーディングするなど「人気曲」だったようだ。ミュンシュは、後述するようにスタジオ録音を3回行っており、ボストン響(BSO)とは定期演奏会だけを見ても、常任指揮者就任前の1947~1948年シーズンから、1950~1951年、1956~1957年、1957~1958年、1960~1961年、1962~1963年シーズンと、極めて頻繁に取り上げており、ミュンシュ自身の好みもあったろうが、BSOの定期会員にとっては身近な曲だったことが分かる。一方、「呪われた狩人」は1959~1960年と1961~1962年シーズンにそれぞれ3公演取り上げたのみであった。なお、当レーベル60066DFにある、同じくミュンシュ指揮の同曲は1962年2月9日のライブ録音であり、本CDとは別演奏。
ミュンシュは、先に述べたように交響曲を1946年英デッカにパリ音楽院管、1957年米RCAにBSO、1966年コンサートホールソサエティにロッテルダム・フィルとスタジオ録音したほか、1957年3月BSO、1957年5月チェコ・フィル、1961年3月BSO、1963年BSO、1966年シカゴ響、1967年フランス国立放送管とライブ録音していた。また、「呪われた狩人」を1962年米RCAにBSOとスタジオ録音したほか、、同録音の直前にライブ録音していた。
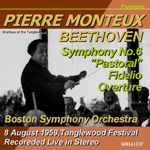
●モントゥー/ボストン ステレオ・ライブ ベートーヴェン 交響曲第6番「田園」、フィデリオ序曲
プレミエ60041DF
ベートーヴェン 交響曲第6番、フィデリオ序曲
ピエール・モントゥー指揮ボストン交響楽団
1959年8月8日、タングルウッド、ライブ、ステレオ
※タングルウッド音楽祭におけるステレオ・ライブ。録音優秀。モントゥーは6番を1958年、「フィデリオ」を1960年英デッカにスタジオ録音していた。

●優秀新音源 モントゥー/ボストン ステレオ・ライブ ベートーヴェン 交響曲第9番
プレミエ60042DFII
ベートーヴェン 交響曲第9番
エリナー・スティーバー(s)、フリーダ・グレイ=マッセ(ca)
ジョン・マッカラム(t)、デイヴィッド・ローラン(bs)
音楽祭合唱団
ピエール・モントゥー指揮ボストン交響楽団
1960年7月31日、タングルウッド、ライブ、ステレオ
※タングルウッド音楽祭(当時はバークシャー音楽祭と呼ばれていた)におけるステレオ・ライブ。従来、本演奏のライブ録音は受信状態のあまり良くない複数のエアチェックテープしか存在せず、当盤の旧プレスはそれらの中から最も良好な音質の音源を使用していた。しかし最近、画期的な優秀新音源を入手したため、改めてディスク化された。
新音源もエアチェックと思われるが、ノイズも極小で、ダイナミックレンジや周波数レンジも申し分なく、鑑賞する際のストレスは全くない。1960年のライブ録音として極めて優秀。もちろん、当時のデッカやRCAなどの超優秀録音には及ばないが、中堅以下のレコードレーベルのステレオ初期録音を凌ぐレベルと言える。また、旧盤と異なり、曲間のチューニングや第2楽章終了後、ソロ歌手入場の際の拍手なども収められており、臨場感が増している。会場ノイズも少ない。
後に述べる米ウェストミンスターによるモントゥーのベートーヴェン第9録音は、特殊な楽器配置、残響をカットした癖のある録音など、ある意味でユニークな企画内容を売り物にしており、モントゥーの意図をすべて反映出来ていたか疑問があった。一方、客演とは言え長年密接な関係を続けたボストン響(BSO)との本演奏は、モントゥーが考えたベートーヴェン第9の姿をありのままに示していると言えよう。
なお、ディスク化に当たっては、低域の過剰、高域に若干のヒスノイズと濁り、ステレオ定位の片寄りなどがあったため、マスタリングで改善・解消している。優秀録音ではあっても修正が出来ない一度限りのライブ録音であり、無編集でディスク化するわけにはいかないようだ。
この日の演奏会は、午後2時30分からのマチネーで、前半にモーツァルトの交響曲第35番「ハフナー」、後半にベートーヴェン第9というプログラム。会場はミュージック・シェド(後にクーセヴィツキー・シェドと改称)と呼ばれる、屋根とステージ後方・両袖の壁があるのみで、客席側には壁がない半開放式。夏の音楽祭らしい明るい日差しの中で演奏されたのだろう。前日に同じプログラムで公開リハーサルが行われた。なお、一部ソロ歌手の声域は、旧盤ではメゾソプラノ、バリトン、合唱もタングルウッド音楽祭合唱団と表記されていたが、当盤では当時の音楽祭パンフレット表記に従った。
モントゥーはかつてBSOの常任指揮者を務めており、ベートーヴェン第9は常任時代の1922年11月に2公演行ったことが最初である。ただし、この時は定期演奏会にもかかわらず、プログラム前半に第1~第3楽章のみ演奏という変則的な形態で、後半はフリーダ・ヘンペル(ソプラノ)が加わった管弦楽伴奏の歌曲などが演奏された。20世紀初め頃までは、交響曲を全曲ではなく1楽章のみ演奏することも多かったようだが、一方で名門BSOも当時は財政的に不安定で楽員の退団が相次ぐなど厳しい事情から、合唱やソロ歌手を呼ぶ費用や練習の手間を惜しんだのかも知れない。なお、1924年3月にようやく4楽章全曲が演奏された。その後は、30年空けて1955年8月、1960年4月(モントゥー85歳記念公演)、そして1960年7月の本演奏が最後となった。最後の演奏機会が良好なステレオ録音で残されたことは幸いといえる。
モントゥーは当録音以外にベートーヴェン第9を、1962年米ウェストミンスターにロンドン響とスタジオ録音、1958年フランス国立放送管とライブ録音したほか、ディスク化されていないが、1960年BSO(前記のモントゥー85歳記念公演、米RCAが録音)、1962年、1963年ロンドン響とライブ録音していた。
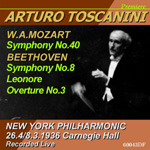
●トスカニーニ/ニューヨーク・フィル 1936年ライブ モーツァルト 交響曲第40番、ベートーヴェン 交響曲第8番、レオノーレ序曲第3番
プレミエ60043DF
モーツァルト 交響曲第40番
ベートーヴェン 交響曲第8番、レオノーレ序曲第3番
アルトゥーロ・トスカニーニ指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
1936年4月26日、3月8日、ニューヨーク・カーネギー・ホール
ライブ、モノラル
※トスカニーニ/ニューヨーク・フィルによる戦前の貴重なライブ。トスカニーニ69歳前後の記録。いずれの曲も数種の録音が残されているが、本CD-Rは現在確認されている最初の録音。初期のアセテート盤による古い録音だが、当代随一といわれたコンビの片鱗が伺える。
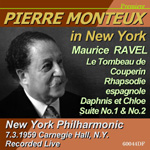
●モントゥー/NYPライブ ラヴェル クープランの墓、スペイン狂詩曲、ダフニスとクロエ
プレミエ60044DF
ラヴェル クープランの墓、スペイン狂詩曲、ダフニスとクロエ第1、第2組曲
ピエール・モントゥー指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
1959年3月7日、ニューヨーク・カーネギー・ホール
ライブ、モノラル
※ニューヨーク・フィル(NYP)とのラヴェル・プログラム。モノラルながら録音は優秀。このままステレオにしても通用する音質。
モントゥー/NYPは、我々日本人には珍しい組み合わせに見えるが、モントゥーは1927年に初めて同フィルに客演して以来、その後中断はあったものの、1943年以降1961年までほぼ毎年共演していた。特に、野外劇場ルイソン・スタジアムにおける夏のコンサートへの出演は恒例で、ニューヨーク市民に親しまれた。
当CDの1959年のコンサートは、三夜連続公演の3日目で、前半は「クープランの墓」、ヨゼフ・シゲティ独奏でバッハのヴァイオリン協奏曲ニ短調(チェンバロ協奏曲の編曲版)、「スペイン狂詩曲」が演奏され、後半は、再びシゲティ独奏でベルリオーズの「夢とカプリッチョ」、「ダフニスとクロエ」第1、第2組曲が演奏された。
モントゥーは「クープランの墓」のスタジオ録音を残さず、現在確認されているのは当演奏のみ。「スペイン狂詩曲」は1961年英デッカにスタジオ録音、「ダフニス」全
曲を1959年英デッカにスタジオ録音、「ダフニス」第1組曲を1946年米RCAにスタジオ録音しているが、第1・第2組曲の形での録音は現在確認されている限り当演奏のみ。
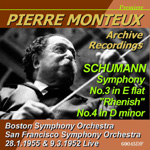
●モントゥー/ボストン&サンフランシスコ ライブ シューマン 交響曲第3番「ライン」、交響曲第4番
プレミエ60045DF
シューマン 交響曲第3番「ライン」、第4番
ピエール・モントゥー指揮ボストン交響楽団、サンフランシスコ交響楽団
1955年1月28日、ボストン・シンフォニー・ホール
1952年3月9日、サンフランシスコ・ウォー・メモリアル・オペラ・ハウス
ライブ、モノラル
※第3番「ライン」がボストン響、第4番がサンフランシスコ響による。モントゥーは「ライン」のスタジオ録音を残さず、現在確認されているのは本CD-Rのライブ演奏のみ。第4番は、この演奏会の直後米RCAにスタジオ録音している。
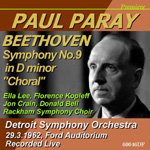
●パレー/デトロイト ライブ ベートーヴェン 交響曲第9番
プレミエ60046DF
ベートーヴェン 交響曲第9番
エラ・リー(s)、フローレンス・コプレフ(ms)
ジョン・クレイン(t)、ドナルド・ベル(bs)
ラッカム・シンフォニー合唱団
ポール・パレー指揮デトロイト交響楽団
1962年3月29日、デトロイト・フォード・オーディトリアム、ライブ、モノラル
※モノラルながら音質良好。他社の既出盤では、第1楽章冒頭に大きなノイズが入るほか、各所にドロップアウト、ヒスノイズ過多などの問題があったが、当盤はおそらく別音源を使用しており解消されている。独唱陣はドイツ語、合唱は英語訳による歌唱のようだ。パレーは同曲のスタジオ録音を残さず、現在確認されているのは、このほかにフランス国立管とのライブ録音のみ(未発売)。パレーはベートーヴェンも得意としていたが、レコード会社によるフランス音楽優先の販売政策のため、交響曲の正規録音は1番、2番、6番(2種類)、7番だけであった。

●フルトヴェングラー ヴェネズエラ・ライブ ブラームス 交響曲第1番
プレミエ60047DF
ブラームス 交響曲第1番
R.シュトラウス 交響詩「ドンフアン」
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー指揮ヴェネズエラ交響楽団
1954年3月20日、カラカス・ホセ・アンヘル・ラマス円形劇場、ライブ、モノラル
※モノラルながら音質良好。1954年3月、フルトヴェングラーはヴェネズエラの首都カラカスを訪問し、2回の公演を行った。表記では20日録音とあるが、記録によれば21日とあるので誤りか。当日は、このほかにヘンデルの合奏協奏曲、ワーグナーのタンホイザー序曲が演奏されたという。フルトヴェングラーの南米公演における録音は、コロン劇場のライブなど劣悪なものが多いが、本録音は、会場が野外劇場という不利な条件にもかかわらず優秀で、当時の欧米における放送録音と同等。また、オリジナルテープに近い音源からの復刻らしく、非常に生々しい音質。なお、ジャケット写真は、本公演よりも20年前、1925年にフルトヴェングラーがニューヨーク・フィルを客演した際の歓迎レセプション風景。フルトヴェングラーと並んで、ストラヴィンスキー、メットネル、ラフマニノフ、クライスラー、ヨーゼフ・ホフマンら、何とも豪華な顔ぶれが見える。ちなみにフルトヴェングラーのニューヨーク・フィル・デビュープログラムは、奇しくもブラームス交響曲第1番とドンフアンであった(もう1曲は、カザルス独奏!によるハイドンのチェロ協奏曲ニ長調)。
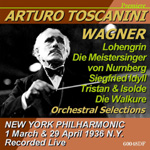
●トスカニーニ/ニューヨーク・フィル 1936年ライブ ワーグナー管弦楽曲集
プレミエ60048DF
ワーグナー
歌劇「ローエングリン」第3幕への前奏曲
楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲
ジークフリート牧歌
楽劇「トリスタンとイゾルデ」第1幕への前奏曲と愛の死
楽劇「ワルキューレ」ワルキューレの騎行
アルトゥーロ・トスカニーニ指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
1936年3月1日、ラジオシティ・ミュージックホール
1936年4月29日、ニューヨーク・カーネギー・ホール
ライブ、モノラル
※トスカニーニ/ニューヨーク・フィルによる戦前の貴重なライブ。ローエングリン以外は、トスカニーニのニューヨーク・フィル常任指揮者退任公演から。これはプログラムの後半で、前半は、ベートーヴェンのレオノーレ序曲第1番、ハイフェッツ独奏で同ヴァイオリン協奏曲が演奏されたという。アセテート盤による古い録音ではあるが、トスカニーニ「壮年期」の凄さが伝わる。ローエングリンは、当時、完成間もないロックフェラーセンターのラジオシティ・ミュージックホールにおける

●シュワルツコップとボスコフスキーによるウィンナ・オペレッタ・アリア ハリウッド・ボウル ライブ
プレミエ60049DF
ヨハン・シュトラウス2世:喜歌劇『こうもり』から序曲
ヨハン・シュトラウス2世:喜歌劇『ウィーン気質』からワルツ「ウィーン気質」
ヨハン・シュトラウス2世:喜歌劇『こうもり』からチャールダーシュ「故郷の調べ」
ホイベルガー:喜歌劇『オペラ舞踏会』から「別室に行きましょう」
ツェラー:喜歌劇『小鳥売り』から「チロルで薔薇を贈る時は」
ツェラー:喜歌劇『坑夫長』から「気を悪くしないで」
レハール:喜歌劇『メリー・ウィドウ』から「ヴィリアの歌」
シーチンスキー:「ウィーン,わが夢の街」
シーチンスキー:「ウィーン,わが夢の街」(アンコール)
エリーザベト・シュワルツコップ(ソプラノ)
ウィリー・ボスコフスキー指揮ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団
1963年7月9日、ハリウッド・ボウル、ライブ、ステレオ
※野外劇場ハリウッド・ボウルにおけるライブ。優秀なステレオ録音。この公演では、ほかにボスコフスキー指揮によるシュトラウスのワルツやポルカなども演奏されている。シュワルツコップ得意のレパートリー。すべての曲にスタジオ録音があるが、ライブは珍しい。1963年秋、シュワルツコップとボスコフスキーは、ウィンナ・オペレッタや歌曲のプログラムで北米ツアーを行ったらしく、一部が重複したプログラムでカナダCBC放送にテレビ出演している。
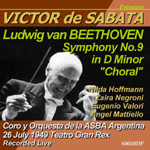
●ヴィクトル・デ・サバタのベートーヴェン第9!! 新発見1949年ライブ
ベートーヴェン 交響曲第9番
ニルダ・ホフマン(s)、ザイラ・ネグローニ(ms)
エウジェニオ・ヴァローリ(t)、アンヘル・マッティエロ(br)
ヴィクトル・デ・サバタ指揮
ブエノスアイレス交響楽協会合唱団・交響楽団
1949年7月26日、ブエノスアイレス・グラン・レックス劇場、ライブ、モノラル
プレミエ60050DF
※今まで存在が知られていなかった驚愕の新発見録音。名声の割には録音に恵まれなかったイタリアの巨匠サバタの第9。1949年ブエノスアイレスにおけるライブ。アセテート盤による録音はスクラッチノイズが持続し、第3楽章に2~3秒のワウ(音揺れ)があるなど一般的な意味で良好とは言い難いが、マイクセッティングは妥当で、歌手や合唱、オーケストラのバランスも良く、音質そのものは悪くない。第2次世界大戦中のヨーロッパにおける、アセテート盤による標準的なライブ録音と同等か。
ブエノスアイレス交響楽協会の実体は不明だが、当時活発に演奏会を主催していた団体。クラウディオ・アラウなども出演しており、高水準の活動を行っていたようだ。オーケストラは、おそらくコロン歌劇場やアルゼンチン国立管などのメンバーも参加した特別編成だったと思われる。
サバタはベートーヴェンの交響曲について3番を英デッカに、6番を英EMIにスタジオ録音したほか、5番、8番をライブ録音していた。

●フリッツ・ライナー/NYP 1960年ライブ 展覧会の絵、不思議な中国の役人
ムソルグスキー(ラヴェル編曲) 組曲「展覧会の絵」
バルトーク 舞台音楽「不思議な中国の役人」演奏会用組曲
フリッツ・ライナー指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
1960年3月20日、12日、ニューヨーク・カーネギー・ホール、ライブ、モノラル
プレミエ60051DF
※共にニューヨーク・フィルとのライブ録音。音質良好。特に「展覧会の絵」は臨場感のある生々しい録音。ライナーは1940年代にしばしばニューヨーク・フィルを客演したが、1960年に2つのプログラムでそれぞれ4回の公演を行い、この録音が両者の最後の共演の機会となった。ライナーは「展覧会の絵」を1957年米RCAにシカゴ響とスタジオ録音、「不思議な中国の役人」を1946年にNBC響とライブ録音していた。
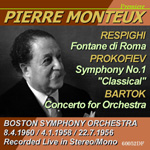
●モントゥー/ボストン ライブ レスピーギ、プロコフィエフ、バルトーク
レスピーギ 交響詩「ローマの噴水」
プロコフィエフ 交響曲第1番「古典交響曲」
バルトーク 管弦楽のための協奏曲
ピエール・モントゥー指揮ボストン交響楽団
1960年4月8日、1958年1月4日、ボストン・シンフォニー・ホール
1956年7月22日、タングルウッド
ライブ、ステレオ/モノラル
プレミエ60052DF
※モントゥーによる近代音楽作品を集めたもので、ボストン響の本拠地シンフォニーホールとタングルウッド音楽祭におけるライブ。レスピーギとプロコフィエフはステレオ録音、バルトークのみモノラルだがそれぞれ聞きやすい録音。プロコフィエフは、放送局としてはごく初期の実験的ステレオ録音と言われ、左右チャンネルの広がりがやや極端で音像も大きめ。試行錯誤中であることが理解できるが、音質や解像度は優秀。1960年のレスピーギ録音では技術的にも確立され、違和感のないステレオ録音となっている。
「ローマの泉」が演奏された1960年4月8日の演奏会は、8日・9日2公演の初日。前半にベートーヴェンの交響曲第3番「英雄」、休憩を挟んで、後半が「ローマの泉」とR・シュトラウスの交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」というプログラム。現在の演奏会とは順序が逆のようにも感じる。実は、この公演はフリッチャイが指揮する予定だったが急病でモントゥーに交替したという。フリッチャイがベルリン・ドイツ・オペラ音楽総監督の契約を交わしたものの、健康状態を理由に辞退した時期と重なる。
モントゥーは、これら3作品のスタジオ録音を残さず、レスピーギにボストン響との1963年ライブ(未発表)、プロコフィエフにフランス国立管との1958年ライブ、ミラノRAI響との1964年ライブ(未発表)があるが、バルトークは現在までに確認されている唯一の録音。

●ミュンシュ/ボストン ライブ ドヴォルザーク「新世界から」ほか
ドヴォルザーク 交響曲第9番「新世界から」
ブラームス 大学祝典序曲
シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団
1954年10月8日、1957年12月6日、ボストン・シンフォニー・ホール
ライブ、モノラル
プレミエ60053DF
※モノラルで特別に優秀というわけではないが、ノイズもなくバランスの良い録音。ボストン響の本拠地シンフォニーホールにおけるライブ録音。ミュンシュは意外にも両曲のスタジオ録音を残さず、両曲とも現在確認されている唯一の録音。特にドヴォルザークは、米RCAへのスタジオ録音である交響曲第8番とチェロ協奏曲しか録音が確認されておらず、珍しい録音である。
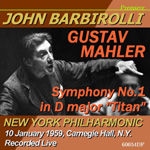
●バルビローリ/NYP ライブ マーラー 交響曲第1番「巨人」
マーラー 交響曲第1番「巨人」
サー・ジョン・バルビローリ指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
1959年1月10日、ニューヨーク・カーネギー・ホール、ライブ、モノラル
プレミエ60054DF
※モノラルながら音質良好。かつて常任を務めた古巣ニューヨークフィルへの客演ライブ。バルビローリは同曲を1957年に英パイにハレ管とスタジオ録音していた。バルビローリによるマーラー録音はライブも含めて数多いが、第1番のライブは、これが現在確認されている唯一の録音。
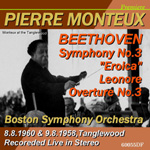
●モントゥー/ボストン ステレオ・ライブ ベートーヴェン「英雄」ほか
プレミエ60055DF
ベートーヴェン 交響曲第3番「英雄」
レオノーレ序曲第3番
ピエール・モントゥー指揮ボストン交響楽団
1960年8月8日、1958年8月9日、タングルウッド、ライブ、ステレオ
※ステレオ録音。2曲ともタングルウッド音楽祭におけるライブ。「英雄」は特に録音優秀。既出の交響曲全集セットでは、ステレオバランスの左チャンネルへの偏り、第2楽章冒頭部欠落、過大なヒスノイズなどの問題があったが、このCDでは改善されている。レオノーレ序曲第3番は英雄より2年前の録音で、英雄ほどではないが優れた録音。
モントゥーは、「英雄」を1957年英デッカにウィーン・フィルと、1962年にコンセルトヘボウ管と蘭フィリップスにスタジオ録音したほか、1960年ロイヤル・フィルとライブ録音していた。また、レオノーレ序曲第3番は、1952年サンフランシスコ響、1953年NBC響、1960年ベルリン・フィル、1962年ボストン響とのライブ録音が確認されているほか、1960年米RCA(提携先の英デッカ制作)にロンドン響とスタジオ録音したが未発売になっているという。
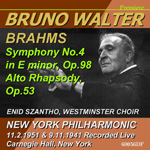
プレミエ60056DF
ブラームス 交響曲第4番、アルト・ラプソディ
エニッド・サントー(コントラルト)
ブルーノ・ワルター指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
1951年2月11日、1941年11月9日、ニューヨーク・カーネギー・ホール
ライブ(モノラル)
※1951年(交響曲)はテープ、1941年はアセテート盤によるライブ録音。音質は年代相応だが、それぞれの録音技術が安定期に入った頃で聴きづらさはない。1951年録音は残響が適度に入り、1941年録音はディスク録音にもかかわらずノイズの少なさが印象的。
エニッド・サントーは、日本ではなじみがないが、ハンガリー出身で第2次世界大戦前後にメトロポリタン歌劇場やウィーン国立歌劇場などで活躍したコントラルト。「トリスタン」のブランゲーネ、「リング」のエルダなどを持役とした。
ワルターは、交響曲第4番をこのほかに1934年英HMVにBBC響、1951年(このライブの翌日)米CBSにニューヨーク・フィル、1959年米CBSにコロンビア響とスタジオ録音したほか、1946年ニューヨーク・フィル、1954年ミラノ・イタリア放送管とライブ録音していた。アルト・ラプソディは、1961年米CBSにコロンビア響とスタジオ録音していた。
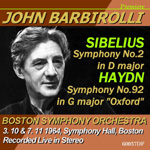
●バルビローリ/ボストン響 シベリウスとハイドン ステレオ・ライブ
プレミエ60057DF
シベリウス 交響曲第2番、ハイドン 交響曲第92番「オックスフォード」
サー・ジョン・バルビローリ指揮ボストン交響楽団
1964年10月3日、11月7日 ボストン・シンフォニー・ホール
ライブ、ステレオ
※優秀なステレオ・ライブ録音。ボストン・シンフォニー・ホールの美しい響きが記録されている。従来発売されていた盤は、シベリウスでは冒頭の録音レベルが異常に高く、その後徐々に低下、ダイナミック・レンジも狭いなど音質に不満があったが、このCDでは改善されている。
バルビローリは、当時ヒューストン響の常任指揮者を務めていたが、ボストン響にもたびたび客演したようだ。バルビローリによるシベリウス交響曲第2番の録音は、スタジオ/ライブを含めて多数にのぼるが、録音状態の良いステレオライブはこの演奏が随一か。ハイドンは現在確認されている唯一の演奏と思われる。
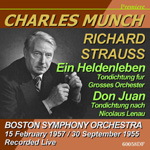
●ミュンシュ/ボストン響 R・シュトラウス「英雄の生涯」「ドンファン」
プレミエ60058DF
R・シュトラウス 交響詩「英雄の生涯」「ドンファン」
シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団
1957年2月15日、1955年9月30日 ボストン・シンフォニー・ホール
ライブ、モノラル
※ボストン・シンフォニー・ホールにおけるライブ録音。モノラル時代後期の録音だけに、音質も良く聞きやすい。ミュンシュはこれら2曲のスタジオ録音を残さず、上記のライブのほか、現在確認されているのは、ドンファンの1956年モスクワ公演ライブのみ。R・シュトラウスは、ミュンシュにとっては比較的珍しいレパートリーと思われるが、「ドン・キホーテ」「ティル」を米RCAにスタジオ録音していたほか、アルザス出身(出生当時はドイツ領)で、かつてはライプツィヒ・ゲヴァントハウス管のコンサートマスターを務めていたように、シュトラウスは決して縁遠い作曲家ではなかったようだ。
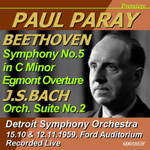
●パレー/デトロイト響ライブ ベートーヴェン交響曲第5番、バッハ管弦楽組曲第2番
プレミエ60059DF
ベートーヴェン 交響曲第5番、エグモント序曲
バッハ 管弦楽組曲第2番
1959年10月15日、11月12日(バッハ) デトロイト・フォード・オーディトリアム
ライブ、モノラル
※デトロイトにおけるライブ録音。録音状態は、ベートーヴェンの2曲については、1950年代中頃の録音といったレベルだが、安定していて聞きづらくはなく、同時期のミトロプーロス/NYPなどのライブ録音と同水準か。翌月のバッハは、より明快な録音で年代の標準を上回る。
パレーはベートーヴェンの2曲とバッハについてスタジオ録音を残しておらず、現在確認できるのは上記のライブのみ。メジャーオーケストラの音楽監督として、おそらく実演では定期的に取り上げていたと思われる。
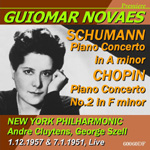
●ノヴァエス/クリュイタンス、セルによるシューマン、ショパン協奏曲 ライブ
プレミエ60060DF
シューマン ピアノ協奏曲
ショパン ピアノ協奏曲第2番
ギオマール・ノヴァエス(ピアノ)
アンドレ・クリュイタンス、ジョージ・セル指揮
ニューヨーク・フィルハーモニック
1957年12月1日、1951年1月7日、ニューヨーク・カーネギー・ホール
ライブ、モノラル
※ブラジル出身の名女流ピアニスト、ギオマール・ノヴァエスのニューヨーク・フィル定期演奏会におけるライブ。ノヴァエスはニューヨークとパリで人気を博し、ニューヨーク・フィルと度々共演した。1957年のシューマンの協奏曲は、音楽評論家ハロルド・ショーンバーグが、名著「ピアノ音楽の巨匠たち」の中で言及した伝説的演奏。実際は11月28、29日、12月1日の3回公演だったため、ショーンバーグが聴いた演奏がこの録音そのものかどうかは不明だが、参考資料として貴重だ。ちなみにクリュイタンスとニューヨーク・フィルも珍しい顔合わせで、1957年11~12月に、この演奏を含む14回共演したのみであった。ショパンは、ニューヨーク・フィルと関係が深かったジョージ・セルのオーケストラ編曲版による演奏。第1楽章序奏部は短縮されており、一部にオリジナルと異なる音が聞こえる。
録音状態は、古いショパンの方が明快。一部かすかに電気的ノイズが数秒入るが、鑑賞に影響はない。シューマンはオーケストラが少し不鮮明だが、聞きづらくはなく、ショパンよりも会場の雰囲気が感じられる。
ノヴァエスは、両曲とも1950年米ヴォックスにクレンペラーとスタジオ録音、シューマンについては1954年同じく米ヴォックスにスワロフスキーと再録音していた。

●ミュンシュ・ボストン ライブ ベートーヴェン7番、ハイドン98番
プレミエ60061DF
ベートーヴェン 交響曲第7番
ハイドン 交響曲第98番
シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団
1960年10月8日、ボストン・シンフォニー・ホール
1960年10月18日、ハーバード大学サンダース・シアター
モノラル ライブ
※モノラルながら音質良好。特にベートーヴェンは、若干ヒスノイズはあるものの、そのままステレオ化してもよいと思われる音質。ちなみに既出盤ではステレオ表記されているがおそらく誤り。既出盤は弱音が痩せ、強音が歪むという不安定な音質だったが、異なる音源からにCD化により改善され、演奏本来の姿が甦った。
ミュンシュ・ボストン充実期の演奏。ハイドンはボストン近郊のハーバード大学における公演。定期演奏会のシーズン中でも周辺地域には頻繁に客演したようだ。
ミュンシュは、ベートーヴェンの交響曲第7番を1949年米RCAにボストン響とスタジオ録音したほか、1954年にボストン響と、1963年にフランス国立放送管とライブ録音していた。一方、ハイドンの交響曲第98番は、スタジオ録音を残しておらず、本CDの演奏が現在確認されている唯一の録音。

●ミュンシュ・ボストン ライブ モーツァルト39番、31番「パリ」
プレミエ60062DF
モーツァルト 交響曲第39番、第31番「パリ」
シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団
1955年4月9日、1954年4月2日、ボストン・シンフォニー・ホール
モノラル ライブ
※交響曲第39番はこの年代の標準的な音質。特に優秀というわけではないが、ノイズもなく鑑賞に支障はない。一方、31番はこの年代の水準以上の良好な音質。ミュンシュはコンサートではしばしばモーツァルトを取り上げていたが、モーツァルトの正式なレコーディングは、協奏曲の伴奏を除けば、アダージョとフーガ(1939年)と「フィガロの結婚」序曲(1951年)の2曲のみ。理由は不明だが、米RCA時代はフリッツ・ライナーとレコーディング・レパートリーを分け合った可能性もある。交響曲ついても、残されている録音はライブ録音のみで、上記CD以外に39番は1959年、31番は1956年のライブが残されている。

●モントゥー ライブ モーツァルト「ジュピター」、シューベルト「未完成」ほか
プレミエ60063DF
モーツァルト 歌劇「魔笛」序曲、交響曲第41番「ジュピター」
シューベルト 交響曲第7(8)番「未完成」
ピエール・モントゥー指揮
サンフランシスコ交響楽団(「魔笛」序曲、「未完成」)
ボストン交響楽団(「ジュピター」)
1952年2月3日(「魔笛」序曲)、1952年4月18日(「ジュピター」)
1944年1月23日、1952年3月30日(「未完成」)
サンフランシスコ・ウォー・メモリアル・オペラハウス
ボストン・シンフォニー・ホール
モノラル ライブ
※「魔笛」序曲と「ジュピター」は、高域に少しヒスノイズがあるもののクリアで明快な音質。「未完成」は2曲に比べればややレンジが狭い感じだが、バランスも良く十分鑑賞に耐える音質。
「未完成」は、ラジオ放送の収録時間の都合で一度に全曲演奏されておらず、第1楽章は1944年、第2楽章は1952年の録音から編集したという。ただし、音質はほぼ同等で、第1楽章が1944年の録音にしては良好であることから、2つの楽章とも1952年録音かも知れない。
モントゥーは1953年にサンフランシスコ響の常任指揮者を退任する一方、1951年からはミュンシュの招きでボストン響に客演を開始しており、1952年はその端境期の演奏である。
モントゥーは、「魔笛」序曲と「ジュピター」をスタジオ録音しておらず、現在確認されている録音は、「魔笛」序曲は本CDのみ。「ジュピター」は本CD以外に1947年サンフランシスコ響とのライブ録音がある(当レーベル・プレミエ60038DFでCD化)。「未完成」は、本CD以外に1963年蘭フィリップスにコンセルトヘボウ管とスタジオ録音していた。
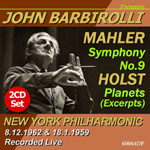
●バルビローリ/NYPライブ マーラー交響曲第9番、ホルスト「惑星」
プレミエ60064DF
マーラー 交響曲第9番
ホルスト 組曲「惑星」抜粋(火星、金星、水星、土星、木星)
サー・ジョン・バルビローリ指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
1962年12月8日、ニューヨーク・フィルハーモニック・ホール
1959年1月18日、ニューヨーク・カーネギー・ホール
モノラル ライブ
※マーラーはノイズもなく音質良好。ホルストも基本的には良好だが、元の音源のヒスノイズが多かったため、音質を損ねない範囲でカットしてある。この時代における録音技術の3年間の進歩は大きいようだ。なお、ホルストは天王星と海王星を除いた、5曲のみの抜粋による演奏。木星と土星を入れ替えている理由は不明だが、演奏効果を考慮したためか。
ちなみに1962年9月、ニューヨーク・フィルの新しい本拠地であるフィルハーモニック・ホールが完成しており、マーラーの演奏は完成間もない時期のライブである。
バルビローリは1936から1943年までニューヨーク・フィルの主席指揮者を務めたが、退任後は同フィルに1959年、1962年、1968年の3回客演した。1959年のコンサートは6プログラムで16公演行われたが、1月18日の演奏は15~18日の4夜連続公演の最終日に当たり、「惑星」の前後にウェーバー「魔弾の射手」序曲、ブラームスのヴァイオリン協奏曲(独奏バール・セノフスキー)というプログラムだった。協奏曲がメインプログラム?で、「惑星」が抜粋というのは、この曲がニューヨークの聴衆に馴染みがなかった時代を物語る。ちなみにニューヨーク・フィルによる「惑星」の演奏は、1932年アルバート・コーツが夏の野外コンサートで4曲を抜粋演奏して以来35年ぶり。全曲演奏は、同じくコーツが1921年に2回行った後は、1971年のバーンスタインまで50年間空いた。
一方、1962年は2プログラム8公演で、12月8日の演奏は6~9日4夜連続公演の3日目。前半がハイドンのチェロ協奏曲ニ長調(独奏アルド・パリゾ)で、マーラーは当然ながらメインプログラム。同フィルでは古くはマーラー自身やメンゲルベルクが、その後もミトロプーロスやワルターなどがさかんにマーラー作品を取り上げていたが、意外にも交響曲第9番は、バルビローリ以前には1945年にワルター、1960年にミトロプーロスが取り上げたのみだった。
バルビローリは、マーラー交響曲第9番を1964年英EMIにベルリン・フィルとスタジオ録音したほか、1960年にトリノ・イタリア放送(RAI)交響楽団とライブ録音していた。一方、ホルスト「惑星」はスタジオ録音を残さず、上記のライブが現在確認されている唯一の録音。

●ライナー/NYP ライブ
ブラームス交響曲第2番、コダーイ「ハンガリー民謡『孔雀は飛んだ』による変奏曲」
プレミエ60065DFII
ブラームス 交響曲第2番
コダーイ ハンガリー民謡「孔雀は飛んだ」による変奏曲
フリッツ・ライナー指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
1960年3月12日、ニューヨーク・カーネギー・ホール
モノラル ライブ
※モノラルながら2曲とも音質は良好。ダイナミックレンジも広く十分鑑賞に耐える。ブラームスは、元の音源では第1楽章冒頭でヒスノイズや会場ノイズが大きかったが、音質を損ねない範囲で低減されている。
2曲とも、ライナーがニューヨーク・フィル(NYP)に最後に客演した際のライブ。このときは定期演奏会2プログラム8公演が行われた。ブラームスを含むプログラムは、3月10日~13日の4回公演で当録音はその3日目。午後8時半開演で、前半が「孔雀は飛んだ」による変奏曲とバルトークの「中国の不思議な役人」。後半がブラームスというもの。当日のバルトークと別プログラムのムソルグスキー「展覧会の絵」は、当レーベルのプレミエ60051DFで発売済み。バルトークとコダーイは、ライナーが若き日に故郷のリスト音楽院で師事した間柄でもある。
ライナーはオーケストラに対する要求水準が高く厳格な対応も有名で、楽員との軋轢が多かったが、それでもオーケストラ(というよりも経営陣)や聴衆からの評価は高かったようで、NYPには1924年以来100回以上客演しており、特に1949年まではほぼ毎年登場している(その後は当ディスク公演の1960年まで空くことになる)。ただ不思議な点は、その大半が夏のスタジアム(野外)コンサートか、会場がカーネギーホールの場合もコロンビア・ネットワークによる放送を前提としたサマー・ブロードキャスト・コンサートであり、定期演奏会は当ディスクの公演を含めても16回しかないこと。おそらく定期演奏会シーズンの冬季は、当時音楽監督を務めていたシンシナティ響やカーティス音楽院教授、ピッツバーグ響の仕事が中心となり、それらの「夏休み」の時期にNYP客演を重ねたのではないかと思われるが実情は不明である。
ライナーは、2曲ともスタジオ録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音。ただしブラームスは、シカゴ響在任中の1953年から1963年の間、ほぼ1年おきに6回も演奏機会があり(多くは2回公演)、これらの録音も残されている可能性が高い。

●ミュンシュ/ボストン ライブ ショーソン交響曲 フランク「呪われた狩人」
プレミエ60066DF
ショーソン 交響曲 変ロ長調
フランク 交響詩「呪われた狩人」
シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団
1962年2月9日、ボストン・シンフォニー・ホール
ステレオ ライブ
※ボストン・シンフォニー・ホールにおける定期公演のライブで、優秀なステレオ録音。会場ノイズもほとんどなく、当時のレコード用スタジオ録音に匹敵する音質。ミュンシュは1961~1962年シーズンを最後にボストン響の常任指揮者を退任したため最後期の記録。この日は上記の2曲の後に、ルドルフ・ゼルキン独奏によるベートーヴェン「皇帝」が演奏された。
ミュンシュは、ショーソンの交響曲と「呪われた狩人」を1962年本公演直後に米RCAにスタジオ録音していたほか、「呪われた狩人」を1959年にライブ録音していた。
ミュンシュ/ボストン響によるショーソンの交響曲の実演は少なく、1953年の3公演と上記演奏を含む1962年の3公演のみ。「呪われた狩人」も1959年と1962年のそれぞれ3公演のみであった。1962年の公演は、直後の26日に予定されていたスタジオ録音を控えた演奏会プログラミングだったようだ。

●ミュンシュ/ボストン ライブ R・シュトラウス 家庭交響曲、死と変容
プレミエ60067DF
R・シュトラウス 家庭交響曲、交響詩「死と変容」
シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団
1959年2月28日、1951年10月6日、ボストン・シンフォニー・ホール
ステレオ/モノラル ライブ
※家庭交響曲はステレオ。1950年代末のライブとは思えない極めて良好な音質。「死と変容」も年代を考慮すれば好録音。
ミュンシュは、家庭交響曲、死と変容ともにスタジオ録音を残さず、家庭交響曲は上記CDが現在確認されている唯一の録音。死と変容は他に1962年のライブ録音が残されている。2曲ともボストン響における演奏回数は少なく、家庭交響曲は1949年に7公演、1959年にこのCDの演奏を含む7公演。死と変容は1951年に8公演、1962年に4公演行われたのみであった。このCDの1951年の演奏は、同年6月4日に死去したボストン響の前常任指揮者セルゲイ・クーセヴィツキー追悼公演の際の1曲。同曲の前後に、モーツァルトのフリーメーソンのための葬送音楽、チャイコフスキーの「悲愴」が演奏された。

●ライナー/シカゴ響 シベリウス フィンランディア 交響曲第5番
プレミエ60068DF
シベリウス 交響詩「フィンランディア」、交響曲第5番
ヴォーン・ウィリアムズ タリスの主題による幻想曲
フリッツ・ライナー指揮シカゴ交響楽団
1957年10月17日、11月28日、シカゴ・オーケストラ・ホール
モノラル ライブ
※3曲ともシカゴ・オーケストラ・ホールにおける定期演奏会の録音。シベリウスの2曲は、交響曲は当時の水準を上回るクリアで優れた音質。一方フィンランディアは同じ日の録音であり、マイクセッティングも同等と思われるが、わずかにゆがみが感じられる。録音テープの保存状態に問題があったか、ポピュラー名曲であるため繰り返し再生されて劣化したのかもしれない。2曲とも拍手がカットされ、聴衆の咳など会場ノイズもわずかにしか聞こえないため、当時のメジャーレーベルによるレコード用スタジオ録音のような趣がある。
ヴォーン・ウィリアムズは1か月後の録音だが、こちらも優秀な音質で当時の水準以上のレベル。若干会場ノイズも入り、ライブ録音らしい雰囲気。こちらも拍手がカットされている、
シベリウスの2曲は、1カ月ほど前の9月20日に死去した作曲家追悼のため、急きょプログラムが組まれたと言われる。拍手が収録されていないのは、追悼のために拍手を控えたためかも知れない。これはプログラムの後半で、前半は、バッハ(フレデリック・ストック編曲)の前奏曲とフーガ変ホ長調、ドビュッシー「海」が演奏された。11月のヴォーン・ウィリアムズは前半のプログラムで、バッハ(リュシアン・カイエ編曲)のフーガト短調に続いての演奏。さらに続けてユージン・イストミン独奏によるベートーヴェンのピアノ協奏曲第4番が演奏され、休憩の後、ハイドンの交響曲第104番が演奏された。
シベリウスは、ライナーにとって比較的珍しいレパートリー。当録音以外に、シカゴ響とは、1954年にトゥオネラの白鳥、カレリア組曲から行進曲、1955年に交響曲第2番、1957年に交響曲第4番、1959年にヴァイオリン協奏曲を取り上げているが、いずれもスタジオ録音は残さなかった。ヴォーンウィリアムズは、当録音以外には、1957年3月に交響曲第3番を取り上げたのみで、こちらも珍しいレパートリーだった。

●セル/NYP ライブ ブルックナー 交響曲第7番
プレミエ60069DF
ブルックナー 交響曲第7番(ノヴァーク版)
ジョージ・セル指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
1964年3月29日、ニューヨーク・フィルハーモニック・ホール
モノラル ライブ
※ニューヨーク・フィルハーモニック・ホールにおける定期公演のライブ。1964年といえばステレオ録音が一般化していた頃だが、残念ながらモノラル。ボストン響などの保存音源は1950年代末からステレオ化されているが、ニューヨーク・フィルでは1960年代中頃でもモノラル録音が多いようだ。ただし、当盤も音質自体は悪くなく、強音でやや飽和気味になること以外は、鑑賞に支障はない。演奏会場のフィルハーモニック・ホール(現エイヴリー・フィッシャー・ホール)は音響が不評で、1976年に柱(構造体)を残して全面改築されたが、この録音を通して聞く限りは良好である。
セルは、晩年にニューヨーク・フィルのミュージック・アドバイザー兼首席客演指揮者を務めるなど、同フィルとは長らく密接な関係にあったが、ブルックナーの演奏機会は極めて少なく、第7番をこの演奏を含む1964年と1965年に定期演奏会で4公演ずつ計8回取り上げたのみだった。1964年の当演奏はプログラムの後半で、前半にはワーグナーの楽劇「パルシファル」から前奏曲と聖金曜日の音楽が演奏された。
セルは、ブルックナー交響曲第7番のスタジオ録音を残さず、1968年ウィーン・フィルと、当演奏の翌年1965年ニューヨーク・フィルとのライブ録音が現在までに確認されている。
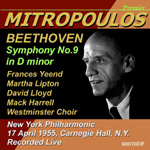
●ミトロプーロス/NYPライブ ベートーヴェン 交響曲第9番
プレミエ60070DF
ベートーヴェン 交響曲第9番
フランシス・イーンド(ソプラノ)、マーサ・リプトン(アルト)
デイヴィッド・ロイド(テノール)、マック・ハレル(バス)
ウェストミンスター合唱団
ディミトリ・ミトロプーロス指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
1955年4月17日、ニューヨーク・カーネギー・ホール
モノラル ライブ
※米ミトロプーロス協会提供による音源からCD化。10数年前に同協会のプライベートCD-Rが少数流通したのみでほぼ初出といえる。現在確認されている唯一のミトロプーロスのベートーヴェン第9。
音質は1950年代中頃のライブ録音としては標準的。特に優秀というわけではないが、バランスも良く、当時のテープ録音では避けられないヒスノイズも許容範囲で鑑賞に支障はない。ただし、注意書きにあるように第3楽章の一部(タイミングの6分28秒~7分30秒)に、保存テープのトラブルによる再生不能箇所があり、欠落箇所はフリッツ・ブッシュ指揮デンマーク放送響の1950年ライブ録音で補われている。幸いテンポ設定や音質などがよく似ており、違和感なく収まっている。
ミトロプーロスはニューヨーク・フィルとベートーヴェン第9を、本CDを含む1955年に3公演、1956年に1公演指揮しており、4月17日の公演は1954~1955年シーズン最後の定期演奏会であった。1955年の3公演では、第9の前にヤン・マイエロヴィツ(1913~1988年)による「The
Glory Around His
Head」(復活のカンタータ)が初演された。ミトロプーロスは、1951~1957年のニューヨーク・フィル音楽監督の在任中、数々の現代曲を取り上げており、1954~1955年シーズンだけを見ても、ショスタコーヴィチの交響曲第10番(アメリカ初演)、ロイ・ハリスの交響的警句(初演)のほかスカルコッタス、ミヨー、リエティ、メニンなど、珍しい作品が数多く演奏されたが、これらがニューヨークの保守的な聴衆の不興を買い、後にバーンスタインへ交代する要因となった。
ミトロプーロスによるベートーヴェンの交響曲録音は、スタジオ録音では、1940年米コロンビアにミネアポリス響と第6番を録音したのみ。その他にライブ録音として1~3、5、8番が残されている。ちなみに本CDの独唱陣と合唱は、1953年に行われたブルーノ・ワルターによる米コロムビアへのベートーヴェン第9第4楽章再録音とまったく同一である。NYPによる第9公演のレギュラー・メンバーという位置づけだっだのかも知れない。

●ライナー/シカゴ響ライブ ベートーヴェン 交響曲第4番、第7番
プレミエ60071DF
ベートーヴェン 交響曲第4番、第7番
フリッツ・ライナー指揮シカゴ交響楽団
1958年4月17日、シカゴ・オーケストラ・ホール
1954年3月24日、シカゴWGN放送スタジオ
モノラル ライブ
※第4番はシカゴ・オーケストラ・ホールにおける定期演奏会の録音。第7番は、シカゴの放送局WGN(World's Greatest
Newspaper)スタジオにおける、聴衆を入れたテレビ放送用ライブ(番組名Hour of Music)。
音質は、第4番はモノラルながら優秀。会場ノイズも少ない。第7番は、第4番より録音年が4年さかのぼることもあり、少し古い音質で、この年代の標準レベルといったところ。それでもノイズは少なくバランスも良好で鑑賞には差し支えない。
ちなみに第7番は海外レーベルで発売されているDVDと同一の演奏だが、それよりも音質が良く、おそらくDVDの元となったビデオテープではなく、同じマイクラインながら別収録されたオーディオテープからCD化されているようだ。
ライナーは、ベートーヴェン交響曲第4番のスタジオ録音を残していないが、シカゴ響在任中には、1953年3公演、本CDライブを含む1958年、1959年、1962年にそれぞれ2公演行っている。1958年の公演は、前半がファリャ「三角帽子」から3つの踊り、ドヴォルザークのピアノ協奏曲(独奏:ルドルフ・フィルクシュニー)。休憩の後、後半にベートーヴェン第4というプログラムだった。一方、第7番は、1955年米RCAにスタジオ録音していたほか、シカゴ響在任中には、1954年3公演、1955年4公演、1957年3公演、1958年4公演、1962年2公演、1963年2公演と頻繁に取り上げており、WGNへのテレビ収録は、1954年3月9日公演後の演奏だった。テレビ収録の際は、併せてエグモント序曲、ヘンデルのオラトリオ「ソロモン」からシバの女王の入城が演奏された。

●ミュンシュ/ボストン響ライブ ベルリオーズ レクイエム
プレミエ60072DF
ベルリオーズ レクイエム(死者のための大ミサ曲)
レオポルド・シモノー(テノール)
ニュー・イングランド音楽院合唱団
シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団
1959年4月25日、ボストン・シンフォニー・ホール
ステレオ ライブ
※ボストン・シンフォニー・ホールにおけるステレオ・ライブ。録音状態は良好。ステレオの分離も良く定位も安定している。ミュンシュは、この公演の直後の26と27日、米RCAに同じキャストでスタジオ録音しているが(会場も同じシンフォニー・ホール)。当CDのライブは、よりダイレクトなスタジオ録音に比べると、会場の響きを素直に捉えており、加工や演出が行われていない良さを感じる。
ベルリオーズを得意としていたミュンシュはボストン響在任中、1951年3公演、1952年2公演、1954年2公演、1959年5公演と、大規模な作品にもかかわらず定期的に取り上げた。1959年の公演は、上記のようにスタジオ録音の準備という意味もあったようだ。
ミュンシュはベルリオーズのレクイエムを、上記RCA録音に加えて、1967年独グラモフォンにバイエルン放送響とスタジオ録音していたほか、1943年パリ音楽院管、1959年7月ボストン響とそれぞれライブ録音していた。
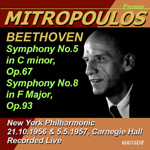
●ミトロプーロス/NYPライブ ベートーヴェン 交響曲第5番、8番
プレミエ60073DF
ベートーヴェン 交響曲第5番、第8番
ディミトリ・ミトロプーロス指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
1956年10月21日、1957年5月5日、ニューヨーク・カーネギー・ホール
モノラル ライブ
※2曲ともNYPの定期演奏会におけるライブ。音質は、1950年代中盤のライブ録音としては標準レベル。特別な優秀録音というわけではないが、大きなノイズや破綻はなく安定しており、十分鑑賞に堪える。第5番の方が滑らかでやや上質。第8番は、NYPの古いライブ録音によくみられるような、わずかにラフな感じがあるが支障があるほどではない。ミトロプーロスの演奏の特徴をよく捉えた録音といえる。
NYP音楽監督在任中、現代音楽ばかり取り上げているとニューヨークの聴衆から批判されたミトロプーロスだが、シューベルトやブラームス、ベルリオーズなどロマン派作品も数多く演奏会プログラムに含まれており、決して現代音楽偏重というわけではなかったようだ。ベートーヴェンの交響曲第5番も、1956~1957年の定期演奏会シーズン中に上記の演奏を含む6公演、1952~1953年シーズンに4公演、1947~1948年シーズンに4公演で取り上げ、第8番は、1956~1957年シーズンに上記の演奏を含む5公演、1952~1953年シーズンに3公演で取り上げており、極端に少ないわけでもない。
しかしその一方で、1956~1957年シーズンに限ってみても、スターラー、シュラー、ヒナステラ、キュービックなど当時の現代作家の作品が並ぶほか、スクリャービン、プロコフィエフ、ザンドナイなど、当時は馴染みのない近代作品も加わっており、当時の聴衆にとって不満が大きかったことは想像できる。また、前年の1955~1956年シーズンは、ベートーヴェンの交響曲を定期演奏会では取り上げず(イタリア海外公演で第3番を1回演奏)、翌1957~1958年シーズンにも第2番を8回演奏したのみだったことが、問題の原因となったのかも知れない。
ミトロプーロスによるベートーヴェンの録音は、スタジオ録音では、1940年米コロンビアにミネアポリス響と第6番を録音したのみ。その他にライブ録音として1~3、9番が残されている。

●モントゥー/トラウベル サンフランシスコ響 ワーグナー・ライブ
プレミエ60074DF
ワーグナー
歌劇「タンホイザー」序曲
歌劇「ローエングリン」第1幕への前奏曲
歌劇「ローエングリン」~「エルザの夢」
楽劇「ワルキューレ」~「君こそ春」
楽劇「ワルキューレ」~「魔の炎の音楽」
楽劇「トリスタンとイゾルデ」~第1幕への前奏曲
楽劇「トリスタンとイゾルデ」~愛の死
ヘレン・トラウベル(s)
ピエール・モントゥー指揮サンフランシスコ交響楽団
1951年4月22日、リッチモンド・メモリアル・オーディトリアム
モノラル ライブ
※NBC放送のラジオ番組「スタンダード・アワー」の公開収録ライブ。この番組はスタンダード石油の提供により1930年代から1950年代まで、サンフランシスコ地域で毎週日曜日に放送されていた。番組収録用のプログラムのため、通常の演奏会より時間が短い。第3曲、4曲、7曲はトラウベルの独唱付き。
放送局に導入間もない時期のテープ録音。年代が古いためレンジはやや狭いが、ディスク録音では不可避の持続的なスクラッチノイズなどがないため、聴きやすく安定している。
モントゥーは1935~1954年の間、サンフランシスコ響(SFSO)の音楽監督を務めており、就任当初は停滞期にあった同響の実力を、当時のアメリカ・ビッグ3オーケストラ(NYP、ボストン、フィラデルフィア)に次ぐまでに高めたと言われた。
モントゥーとワーグナーの組み合わせは、春の祭典やダフニスとクロエの初演者というイメージからは意外に思われるが、実際の演奏会では頻繁に取り上げており、レコーディングも残している。モントゥーは若い頃からドイツ音楽に傾倒しており、モントゥー夫人ドリスの回想録によれば、モントゥーは学生時代にパルシファルのリハーサルを聞き、「完全な和声、完全な解決、完全な魅惑を発見した」という。また、バレエはともかく、モントゥーとオペラの関係も縁遠いように思われるが、モントゥーは、1900年代初頭から数年間、フランス北部の避暑地ディエップのカジノ付属劇場で主席指揮者兼音楽監督を務めており、膨大なレパートリーのオペラ作品を上演したという。同時にコンサートも行い、モントゥー自身は、レパートリーを拡げる貴重な経験になったと語っている。1963年にコンセルトヘボウ管と当CDとよく似たプログラムのライブ録音を残しており、グループレーベル・オルガヌムから110023として発売済みである。
モントゥーは、上記CDの曲目のうち、タンホイザー序曲を1963年にコンセルトヘボウ管とライブ録音、トリスタン前奏曲と愛の死について、1964年コンサート・ホール・ソサエティにハンブルク北ドイツ放送響とスタジオ録音したほか、1952年SFSO、1963年にコンセルトヘボウ管とライブ録音。愛の死を1943年SFSOとライブ録音していたが、それ以外の曲目は上記CDが初登場と思われる。
ヘレン・トラウベル(1899~1972)(トローベルとの表記もあるが、トラウベルが実際の発音に近い)は、1930年代後半から1950年代にかけて、メトロポリタン歌劇場などを中心に活躍したアメリカのドラマチック・ソプラノ。ワーグナーを主要レパートリーとしており、1952年に来日しているが、なぜか日本における評価や知名度はあまり高くない。活動の大半がアメリカ国内であり、メトでは、フラグスタートが第二次世界大戦勃発でアメリカを離れ、ヴァルナイが本格的に活躍する前の狭間に位置していること、メトの支配人ビングと意見が対立、1953年にメトを去り、その後はナイトクラブやテレビなどに活動の中心を移したことが原因かも知れない。しかし、トスカニーニが、テノールのメルヒオールとともにレコーディングに起用したように、実力は第一級といえる。

●セル/NYPライブ チャイコフスキー 交響曲第5番 ほか
プレミエ60075DF
チャイコフスキー 交響曲第5番
ドヴォルザーク 謝肉祭 序曲
ジョージ・セル指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
1965年10月30日、11月20日、ニューヨーク・フィルハーモニック・ホール
モノラル、ライブ
※2曲ともNYPの定期演奏会におけるライブ。音質は、1965年の録音としては少し古い感じで、1950年代末~1960年代初頭といったレベル。既発売のセル指揮ブルックナー交響曲第7番と同様、当時のNYPの記録用音源は、ボストン響などのライバル・オケに比べると技術的に少し遅れていたようだ。それでも、大きなノイズや破綻もなく安定しており、音楽を鑑賞するには問題ない音質で、演奏を楽しめる。
10月30日のチャイコフスキーは、4回公演の3日目に当たり、プログラム前半にムソルグスキーのホヴァンチシナ前奏曲、プロコフィエフのピアノ協奏曲第3番(ゲーリー・グラフマン独奏)というロシア・プログラム。11月20日のドヴォルザークは、同じく4回公演の3日目。謝肉祭序曲の後、同じくドヴォルザークの交響曲第7番、休憩をはさんで後半にチェロ協奏曲(ロストロポーヴィチ独奏)という、オール・ドヴォルザーク・プログラムであった。セルは、スラブ系の作品も得意としており、演奏会でも頻繁に取り上げたが、NYPとは、上記の2曲とも1965~66年シーズンに取り上げたのみだった。
セルは、チャイコフスキー交響曲第5番を1959年、ドヴォルザーク「謝肉祭」序曲を1958年に、それぞれ米CBSにクリーヴランド管とスタジオ録音していた。ちなみに、上記NYPとのチャイコフスキーは、CBSによる端正なスタジオ録音とは様相がかなり異なり、テンポやダイナミックスを大きく動かすという、ライブならではの演奏。

●ミュンシュ/ボストン ライブ ブラームス交響曲第2番 ハイドンの主題による変奏曲
プレミエ60076DF
ブラームス 交響曲第2番、ハイドンの主題による変奏曲
シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団
1960年4月22日、1961年9月29日、ボストン・シンフォニー・ホール
ステレオ、ライブ
※2曲とも本拠地ボストンにおける定期演奏会のステレオ・ライブ。1966年にドルビー・ノイズ・リダクションシステムが開発される以前のテープ録音であるため、ヒスノイズが残るものの比較的軽微。音質は当時のライブ録音として最良の部類で、バランスやダイナミックレンジ、左右チャンネルの分離などまったく申し分ない。
ミュンシュによるブラームス交響曲といえば、パリ管による第1番の録音が有名だが、第2番はボストン響で演奏回数が多かった曲の1つ。ほとんど毎シーズン定期演奏会で取り上げているが、特に1953~54年シーズンはアメリカ国内ツアーとタングルウッド音楽祭を含めて13公演。1955~56年シーズンも国内ツアーとヨーロッパ公演で23公演。当録音が行われた1959~60年シーズンは、5月から始まる日本公演とオーストラリア公演を含めて13公演で演奏している。ミュンシュ/ボストン響の看板プログラムの1つだったと思われる。
後述するフランス国立放送管とのライブ録音と同じく、第4楽章コーダを引き延ばし、演奏が終わらないうちに拍手喝采がかぶさる様子がこのCDでも聴ける。というよりも年代順ではこちらが先で、ミュンシュ得意のスタイルだったようだ。
1960年の演奏は、前半に、指揮者としても有名なマルティノンの前奏曲とトッカータ(世界初演)、ブラックウッドの交響曲第1番という現代作品。後半がブラームスというプログラムだった。
ハイドンの主題による変奏曲も頻繁に演奏された曲で、1950~51年シーズン以降、ほぼ1シーズンおきに必ず取り上げている。「爆発」がないためミュンシュ向き?の曲とはいえないが、好みの作品だったようだ。
1961年の演奏は、プログラム1曲目がハイドン変奏曲で、ドビュッシー「イベリア」と続き、後半にチャイコフスキー交響曲第6番という、いささか変則的な組み合わせ。
ミュンシュは、当CDのほかに、ブラームスの交響曲第2番を1955年米RCAにボストン響とスタジオ録音したほか、1955年と1956年にボストン響、1965年にフランス国立放送管とライブ録音していた。ハイドンの主題による変奏曲は、意外にもスタジオ録音を残していないが、1953年、1958年、1962年にそれぞれボストン響、1962年に日本フィルとライブ録音していた。
●セル/クリーヴランド管 ステレオライブ チャイコフスキー 交響曲第4番ほか
プレミエ60077DF
チャイコフスキー 交響曲第4番
シベリウス エン・サガ(伝説)
ジョージ・セル指揮クリーヴランド管弦楽団
1965年10月5日(?)(チャイコフスキー)、12月9日(シベリウス)
クリーヴランド・セヴェランス・ホール
ライブ ステレオ
※2曲とも優秀なステレオ・ライブ録音。当時のメジャーレーベルのレコード会社の録音水準に匹敵。会場ノイズも少なく、ストレスなしに音楽を楽しみことができる。オリジナル音源は、ラジオ放送用にダイナミックレンジが圧縮されていたため、若干のイコライジングを行っているが、不自然さは全くない。なお、チャイコフスキーの演奏日時は誤り(表記はおそらく放送日)で実際は9月23日が正しい。また、シベリウスもジャケット表記の11月9日は誤りで12月9日が正しい。
ちなみに9月23日のプログラムは、ワーグナーのリエンツィ序曲、ポーランドの現代作曲家タデウシュ・バイルトの「4つのエッセイ」、ラヴェルの「クープランの墓」、最後にチャイコフスキーというもの。12月9日はシベリウスの生誕100年記念プログラムで、エン・サガ、交響曲第4番、ヴァイオリン協奏曲(独奏クリスチャン・フェラス)の順に演奏された。それぞれ晦渋な作品とエンターテインメント的なプログラムを組み合わせた、セルらしい「教育的」プログラムである。
セルはクリーヴランド管に在籍中、チャイコフスキーの後期3大交響曲を毎シーズンのように取り上げた。第4番については、1948年以降ほぼ1シーズンおきに演奏、最後の演奏は1968年であった。3曲とも頻繁に取り上げたにもかかわらず、クリーヴランド管とのレコード録音は第5番のみであり、ロンドン響との第4番(デッカ)は、1962年に録音されたが未発売のままセルの死後1971年に廉価盤として発売。第6番では録音が実現しなかった。当人が録音を望まなかったというより、レコード会社の営業政策の影響もあったと思われる。
一方、シベリウスのエン・サガは珍しいレパートリーで、1954年と1956年に取り上げたほかは、このCDに聴く1965年の演奏のみであった。当然レコード録音も残さなかった。
セルは上記のように、チャイコフスキー交響曲第4番を、1962年英デッカにスタジオ録音したほか、1968年にクリーヴランド管とライブ録音していた。
●モントゥー/ボストン ステレオライブ シベリウス 交響曲第2番ほか
プレミエ60078DF
シベリウス 交響曲第2番、交響詩「トゥオネラの白鳥」
ヒンデミット バレエ音楽「気高き幻想」(管弦楽組曲版)
ピエール・モントゥー指揮ボストン交響楽団
1961年8月4日(交響曲第2番)、1963年12月21日(トゥオネラの白鳥番)、1959年1月23日(気高き幻想)
タングルウッド音楽祭(交響曲第2番)
ボストン・シンフォニー・ホール(トゥオネラの白鳥、気高き幻想)
ライブ、ステレオ
※3曲とも良好なステレオ録音。交響曲第2番のオリジナル音源は、左右チャンネルのバランスが右に片寄り、フォルテが荒れ気味の一方で弱音が弱いという問題があったが、定位を補正し、ダイナミックレンジを調整するなどの手直しの結果、十分鑑賞に堪える状態となった。音質そのものには手を加えていないため、タングルウッド音楽祭会場のダイレクトで素直な録音を楽しむことができる。トゥオネラの白鳥と気高き幻想はいずれもボストン響の本拠地シンフォニー・ホールでのライブ録音。こちらも飛び抜けて優秀というわけではないが安定した音質。
モントゥー/ボストン響は早い時期からシベリウスの交響曲を取り上げており、交響曲第2番については、最初の演奏はモントゥーが同響首席指揮者時代の1921年、最後はこのCDに聴く1961年のタングルウッド音楽祭においてであった。この日のプログラムは、ベートーヴェンのフィデリオ序曲、シューマンのピアノ協奏曲(ユージン・イストミン独奏)、R・シュトラウス「サロメ」から7つのベールの踊り、最後に交響曲第2番が演奏された。
「トゥオネラの白鳥」は、モントゥー/ボストン響が交響曲第2番に次いで最も多く取り上げたシベリウスの作品で、9公演で演奏した記録が残っている。1963年の演奏会は、前半にヴォーン=ウィリアムズの「タリスの主題による幻想曲」とベートーヴェンの交響曲第4番、後半に「トゥオネラの白鳥」、エルガー「エニグマ変奏曲」という、英国と北欧音楽を中心としたもの。
一方ヒンデミットは、モントゥーがキャリア後期に好んで取り上げた作曲家。ヒンデミットの即物的・新古典的作風がモントゥーの好みに合ったのだろうか。ただし演奏した作品は、このCDにある「気高き幻想」と交響曲「画家マチス」にほぼ集中していた。ちなみに「画家マチス」は、フィラデルフィア管とのライブが当レーベルの60001DFIIで聴くことができる。1959年の演奏会は、ブラームスの「悲劇的序曲」、「気高き幻想」、R・シュトラウス「ドン・キホーテ」というなかなか渋いプログラム。
モントゥーは、シベリウスの交響曲第2番を1958年英デッカにロンドン響とスタジオ録音していた。一方「トゥオネラの白鳥」はスタジオ録音を残さず、現在確認されているのは上記のライブ録音のみ。また、「気高き幻想」もスタジオ録音を残さず、上記ライブ録音のほかに、1958年フランス国立放送管と、1963年ボストン響とのライブ録音が残されている。
●ミュンシュ/ボストン ライブ ブラームス ドイツ・レクイエム
プレミエ60079DF
ブラームス ドイツ・レクイエム
ヒルデ・ギューデン(ソプラノ)、ドナルド・グラム(バス・バリトン)
バークシャー音楽祭合唱団
シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団
1958年7月19日、タングルウッド音楽祭
モノラル、ライブ
※タングルウッド音楽祭(当時はバークシャー音楽祭と呼ばれた)におけるライブ。優秀録音が多いボストン響の保存音源だが、これは年代相応の音質。現代のステレオ録音に慣れた耳には少し古い感じで、もう少しクリアに聞きたい部分もあるが、天井のみで壁がない、開放型の演奏会場における管弦楽伴奏付き合唱作品のライブ録音という、厳しい条件であることを考えれば健闘しており。特にノイズもなくバランスも良好であるため、大きなストレスなく聴くことができる。元々のオリジナル音源は歪みが多く、聴きづらい音質だったが、イコライジング等の補正により鑑賞できるレベルまで改善したという。
ミュンシュにとって、ドイツ・レクイエムは珍しいレパートリー。ボストン響在任中、1953年と上記演奏の1958年にいずれもタングルウッド音楽祭で取り上げたのみ。1958年の当演奏は、同響の前任指揮者クーセヴィツキーを偲んで演奏され、プログラムはこの1曲のみだった。
ちなみに当演奏(午後8時半開演)に先立ち、当日昼、ドイツ・レクイエムに加えて、翌20日午後に演奏予定のモントゥー指揮、レオン・フライシャー独奏によるブラームスのピアノ協奏曲第1番の公開リハーサルも行われた。スケジュールの都合とはいえ、大曲2作品を続けてリハーサルを行い、さらに夜の公演を行うオーケストラのタフさには脱帽する。
ミュンシュはドイツ・レクイエムのレコード録音も残さず、上記ライブ録音が現在確認されている唯一の録音。1950年代末、ミュンシュがレコーディング契約を結んでいた米RCAビクターにとっては、同曲の独自録音はロバート・ショウによる1948年録音しか保有しておらず、1969年にラインスドルフが録音するまで空白のレパートリーであった(おそらくロバート・ショウ盤の販売が振るわなかったのだろう)。このため当時は提携先の英HMVからケンペ指揮ベルリン・フィル盤をビクター・レーベルで発売していた。
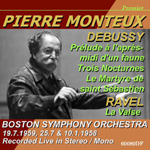
●モントゥー/ボストン ライブ ドビュッシー「牧神」「夜想曲」ほか
プレミエ60080DF
ドビュッシー「牧神の午後への前奏曲」「夜想曲」「聖セバスチャンの殉教」(第1幕から前奏曲、法悦の舞と終曲)
ラヴェル ラ・ヴァルス
ピエール・モントゥー指揮ボストン交響楽団、バークシャー音楽祭合唱団
1959年7月19日、7月25日、バークシャー音楽祭
1958年1月10日、ボストン・シンフォニー・ホール
ステレオ/モノラル
※「牧神の午後への前奏曲」「夜想曲」がステレオ。「聖セバスチャンの殉教」と「ラ・ヴァルス」がモノラル。いずれも良好な録音で、特にステレオの2曲は優秀。同じ日のコンサートの録音である「夜想曲」と「ラ・ヴァルス」のうち、後者がモノラル収録となっているのは、おそらくステレオ機材導入間もない頃のスタイルとして、モノラルとステレオのレコーダーを併用して録音していたが、「ラ・ヴァルス」については、ステレオ・レコーダーがトラブルを起こして録音に失敗したか、収録済みのステレオ・テープが紛失したのだろう。
1951~1962年、モントゥーは、かつて常任指揮者を務めたボストン響に毎シーズン招かれた。1959年7月19日の公演は、タングルウッドのバークシャー音楽祭におけるもので、当日は、リムスキー・コルサコフの「金鶏」から序奏と結婚行進曲、ドビュッシーの「牧神」、ダンディのフランス山人の歌による交響曲(ピアノ独奏:ニコール・アンリオ)、チャイコフスキー交響曲第5番(当レーベルプレミエ60017DFで発売済み)という盛りだくさんなプログラム。モントゥーとボストン響はドビュッシーの「牧神」を1919年以来32回取り上げたが、1959年の演奏が最後となった。
7月25日の公演もバークシャー音楽祭からのライブで、グリンカの「ルスランとリュドミラ」序曲、チャイコフスキー交響曲第4番(プレミエ60016DFで発売済み)、ミヨー劇音楽「エウメニデス」から第3幕への前奏曲、ドビュッシー「夜想曲」、ラヴェル「ラ・ヴァルス」というこちらも賑やかなプログラム。モントゥーとボストン響は、「夜想曲」については、当演奏以外に1954~55年シーズンに2回取り上げたのみであった。合唱が入るという制約のためであろう。
1958年1月10日の公演は、本拠地ボストン・シンフォニー・ホールにおけるライブ。当日は、ベートーヴェン=ワインガルトナー編曲「大フーガ」、ドビュッシー「聖セバスチャン」、R・シュトラウス「死と変容」、ブラームスのヴァイオリン協奏曲(独奏:レオニード・コーガン)という、さすがに定期演奏会らしい渋めのプログラム。モントゥーとボストン響は、ドビュッシー「聖セバスチャン」について、抜粋する曲目は多少異なるものの意外に頻繁に取り上げており、1924年以来17回取り上げ、最後の演奏は1963年4月であった。
モントゥーは上記CD以外に、ドビュッシーの「牧神」を、1961年英デッカにロンドン響とスタジオ録音したほか、1950年コンセルトヘボウ管とライブ録音していた。また「夜想曲」を1955年米RCAにボストン響とスタジオ録音したほか、「雲」と「祭」を1961年英デッカにロンドン響とスタジオ録音。1943年ニューヨーク・フィルとライブ録音。「祭」を1944年同じくニューヨーク・フィルとライブ録音していた。「聖セバスチャンの殉教」(抜粋)については、1963年蘭フィリップスにロンドン響とスタジオ録音したほか、1951年にボストン響とライブ録音していた。ラヴェルの「ラ・ヴァルス」については、1930年仏グラモフォンにパリ響と、1941年米RCAにサンフランシスコ響と、1964年蘭フィリップスにロンドン響とスタジオ録音していた。
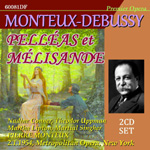
●モントゥー/METライブ ドビュッシー ペレアスとメリザンド全曲
プレミエ60081DF(2枚組)
ドビュッシー 歌劇「ペレアスとメリザンド」
ペレアス:セオドア・アプマン(バリトン)
メリザンド:ナディーン・コナー(ソプラノ)
ゴロー:マルシアル・サンゲル(バス)
アルケル:ジェローム:ハインズ(バス)
ジュヌヴィエーヴ:マーサ・リプトン(メゾ・ソプラノ)
イニョルド:ヴィルマ・ゲオルギュー(ソプラノ)
医者:ルーベン・ヴィシェイ(バス)
ピエール・モントゥー指揮メトロポリタン歌劇場管弦楽団・合唱団
1954年1月2日、ニューヨーク・メトロポリタン歌劇場
ライブ、モノラル
※おそらく初登場となるモントゥー指揮による「ペレアスとメリザンド」全曲。メトロポリタン歌劇場(MET)におけるライブ録音。おそらくエアチェックテープがオリジナルソースと思われるが、残念ながら録音状態は優秀とはいえず、ややくすんだノイズっぽい音質。テープによる録音にもかかわらず第4幕~第5幕には、ディスク録音に聞かれるスクラッチのようなノイズも若干入り、第5幕の末尾にはわずかな周期的なレベル変動もある。それでも大きなノイズや破綻、ピッチの変動はなく、中継放送用のマイクセッティングも適正であるため、歌手とオーケストラのバランスも問題なく、聞こえるべき音は聞こえる。総じて言えば1950年代前半のマリア・カラスによるミラノ・スカラ座ライブなどと同等か。CD化に当たって音質を若干改善させており、第4幕~第5幕のノイズは鑑賞の妨げにならないレベルまで低減してある。モントゥーの演奏を知るために不足はない。
なお、ジャケットの断り書きにあるように、オリジナルの音源は、トラック10第2幕第1場の2分14秒(メリザンドのNon, non, nous ne la
retrouverons
plus,)から、続くトラック11間奏曲末尾まで4分40秒弱の欠落があるため、1962年6月19日ブエノスアイレス・コロン歌劇場におけるジャン・フルネ指揮、ビクトリア・デ・ロス・アンヘレス、ピエール・モレ出演のライブ録音で補っている。また、第4幕第3場、公園の泉水の場面は上演時にカットされ演奏されていない。
「ペレアスとメリザンド」は、1902年パリ・オペラ・コミックで世界初演されたが、モントゥーはこの初演にヴィオラ奏者として参加した(指揮は作曲家としても知られるアンドレ・メサジェ)。リハーサルでは、演奏者に対してドビュッシー本人からの指示や指摘もあったと思われ、初演を知る演奏家による指揮として興味深い(ただし、伝えられるところでは、メリザンド役選定をめぐって原作者メーテルランクとドビュッシーが激しく対立、リハーサルは、それぞれの支持者による妨害があったとも言われ、「春の祭典」に近い騒動の中で進められたようだ)。
上記CDの「ペレアス」公演は、モントゥーが1953~1956年にかけて、METで「ファウスト」「ホフマン物語」「カルメン」「マノン」「オルフェオとエウリディーチェ」「トラヴィアータ」などを指揮した中の一作品。「ペレアス」は6公演が行われた。ちなみにモントゥーのMET指揮は1917~1919年シーズン以来、実に30数年ぶりであった。
モントゥーは1908年から1914年まで、フランス北部の保養地ディエップのカジノ劇場と契約し、劇場のオーケストラを指揮してオペラ・オペレッタを含むおびただしい数の作品を上演した。モントゥー自身の言葉によれば、この経験により、いかなる作品の演奏依頼にも応えられる幅広いレパートリーを身につけたという。後年、モントゥーの活動は歌劇場のキャリアとは無縁であったが、ディエップの経験が、上記のようなMET公演に活かされているのだろう。
出演者は、日本でよく知られているスター歌手は見当たらないが、当時METで、シーズンオープニングなど重要公演以外の、普段の公演を支えた実力派が揃っている。とりわけペレアス役のアップマンは、1947年モントゥー指揮サンフランシスコ響による「ペレアス」演奏会形式上演(メリザンド役はマギー・テイト)において、この役を演じたことで注目され、翌年にニューヨーク・シティ・オペラで同じくペレアスを演じ、1953年METにデビューするに至った。このような経緯を考えると、この1954年の公演でも、アップマンの歌唱にはモントゥーの意図が十分に反映されていると思われる。ちなみにモントゥー指揮による「ペレアス」6公演すべてにアップマンが出演した。
ゴロー役のサンゲルは、フランス出身でアメリカで活躍。1955年ミュンシュ指揮ボストン響によるファウストの劫罰のRCA録音にメフィストフェレス役で参加している。興味深いことに、1945年METの「ペレアス」公演ではペレアスを演じていた。年齢とともに声域が低くなったか。
メリザンド役のコナーは、当時METでリリックソプラノ役を一手に引き受けていた名手。メリザンド役は、少なくともMETでは、モントゥー指揮による1953~1954年公演のみのようだ。なお、コナーは6公演中4公演に参加。残り2公演はビクトリア・デ・ロス・アンヘレスが出演した。
モントゥーは、上記ライブ録音以外に「ペレアスとメリザンド」の録音を残しておらず、1957年にボストン響と管弦楽抜粋をライブ録音していたのみである。

●音質一新! クレンペラー/フィラデルフィア ステレオ・ライブ ベートーヴェン「田園」
プレミエ60082DF
ベートーヴェン 交響曲第6番「田園」
エグモント序曲
オットー・クレンペラー指揮フィラデルフィア管弦楽団
1962年10月19日、27日録音、アカデミー・オブ・ミュージック、フィラデルフィア
ライブ、ステレオ
※クレンペラーが1962年秋、フィラデルフィア管に客演した際のライブ録音の一つ。一連の録音のうち、10月19日の「英雄」と「田園」は音質が悪く、一般向けではないという評価がされていたが、今回、新たな音源を入手したことで発売できることとなった。新たな音源は歪みが大幅に低減され、貧相でドライと言われていた音質に潤いが復活。フィラデルフィア管の本拠地アカデミー・オブ・ミュージックは、残響が乏しいホールだが、それでも音質が改善されたことで、残響が少ない中でも臨場感が増し、十分鑑賞に堪えるようになった。また音質が明るくなり、フィラデルフィア管らしい響きが「田園」という曲目に効果をもたらしている。
10月27日のエグモント序曲も新たな音源を使用しているが、従来からの音源が「田園」よりも良好であるため大きな変化はないが、鑑賞に差し支えない音質。
クレンペラーがフィラデルフィア管に客演した際、ストコフスキー以来伝統の第1・第2ヴァイオリンの配置を、両翼配置に変更させたことは有名な話だが、ステレオ録音であることでそれが確認できる。おそらく客演する条件として配置の変更が含まれていたと思われるが、楽員などからの反発はなかったのだろうか。
クレンペラーは上記CDのほかにベートーヴェンの「田園」を、1951年米ヴォックスにウィーン響と、1957年に英EMIにフィルハーモニア管とスタジオ録音したほか、4種類ほどのライブ録音を残している。一方、エグモント序曲は、1926年独ポリドールにシュターツカペレ・ベルリンと、1957年に英EMIにフィルハーモニア管とスタジオ録音したほか、1960年フィルハーモニア管とライブ録音していた。
ちなみに、「田園」と同日に演奏された「英雄」は、当レーベル・プレミエ60007DFIIで発売されている。

●ライナー・シカゴ響ライブ チャイコフスキー交響曲第4番ほか
プレミエ60083DF
チャイコフスキー 交響曲第4番
ベルリオーズ 歌劇「ベンヴェヌート・チェッリーニ」序曲
フリッツ・ライナー指揮シカゴ交響楽団
1957年11月21日、12月5日、シカゴ・オーケストラ・ホール
ライブ、モノラル
※録音状態良好。モノラル録音完成期のライブ録音で、音質は当時の水準を上回る。チャイコフスキーは高音が少し不足気味で歪みがあったため、補正してバランスを取り直している。またベルリオーズは若干ダイナミックレンジを拡大させているが、いずれも全く違和感なく仕上がっている。
両曲ともシカゴ響定期における演奏。11月21日はシューマン「マンフレッド序曲」、ヒンデミットのヴァイオリン協奏曲(ジョセフ・フックス独奏)、休憩をはさんで後半にチャイコフスキー。12月5日はベルリオーズに続いてヒンデミットのチェロ協奏曲(ヤーノシュ・シュタルケル独奏)、休憩をはさんでムソルグスキー「ホヴァンチシナ」前奏曲、「展覧会の絵」というプログラム。ヒンデミットの協奏曲が重なっているが、ヒンデミット作品は1957~1958年シーズン中この2曲のみであり偶然であろう。ポピュラー名曲と馴染みのない(当時の)現代曲の組み合わせは、レパートリーを広げる目的で行われ、現代のオーケストラ・プログラムでも見かける手法である。
ライナーは、チャイコフスキーの交響曲は第6番のみ米RCAにスタジオ録音を行っているほか、シカゴ響の定期演奏会では、第4~6番は頻繁に取り上げ、第2番やマンフレッド交響曲も1度ずつではあるが演奏した記録がある。第4番のスタジオ録音を残さなかったのは、すでに米RCAには、1955年録音のミュンシュ盤、1959年録音のモントゥー盤があり、単にレコード会社の営業政策によるものだろう。
「ベンヴェヌート・チェッリーニ」序曲は、シカゴ響在任中4回ほど取り上げているが、スタジオ録音は残さなかった。

●ライナー・シカゴ響ライブ マーラー「大地の歌」新マスター音源
プレミエ60084DF
マーラー「大地の歌」
クリスタ・ルートヴィヒ(アルト)、リチャード・ルイス(テノール)
フリッツ・ライナー指揮シカゴ交響楽団
1958年2月20日、シカゴ・オーケストラ・ホール
ライブ、モノラル
※録音状態は、特に優秀とは言えないが鑑賞には十分堪えるレベル。1958年のアメリカにおけるライブとしては若干古い感じで1950年代中頃くらいのイメージか。ちなみに海外レーベルの既出盤は、編集?に使用したレコーダーの左右チャンネルのレベルにばらつきがあったためか、モノラル録音であるにもかかわらず。左右の音量レベルが変動し、音像がふらついて疑似ステレオのような状態となっていた。本CDの音源は、正常なモノラルであり、レベル変動もなく安定した音質。ただし既出盤と同様に、第1楽章後半から第2楽章かけてテープヒスノイズが盛大であったため、音質を損ねない範囲で低減させている。また、アルト歌手に比べて、テノール歌手の音量レベルが低い(マイクが遠い?)ため、バランスを修正している。
フリッツ・ライナーの伝記によると、ライナーは、1958年シーズンに「大地の歌」を取り上げるに当たって、歌手には楽器のような信頼性(安定性という意味か?)を要求したという。これは、彼が歌劇の上演に際して、歌手に求めたものと同じだったが、当時のアメリカ国内には、その要求を満たせるアルト歌手が見当たらず、エリーザベト・シュワルツコップに推薦を依頼したところ、クリスタ・ルートヴィヒが候補となり、これが彼女のアメリカ・デビューとなった。ルートヴィヒの証言では、ライナーはリハーサルで彼女の知識不足を皮肉るなど、彼女にとってあまり愉快な経験ではなかったらしいが、ライナー自身はルートヴィヒの歌唱には満足していたようだ。
「大地の歌」の公演は1958年2月20、21、25日の3日間行われ、プログラム前半に20、21日はモーツァルトの交響曲第36番、25日公演はラヴェルのスペイン狂詩曲が演奏された。歌手はいずれも同一であった。なお、1959年11月にも「大地の歌」の公演が行われたが、こちらはアルトをモーリン・フォレスターが務め、公演直後に米RCAにスタジオ録音している。
一連の流れから推測すると、「大地の歌」を米RCAにレコーディングするに当たり、ライナーが本来希望したアルト歌手はルートヴィヒだったが、彼女が英コロンビアと契約しており(アメリカにおける提携先はRCAのライバルCBSコロンビア)、あらためて翌シーズンに、契約に縛られないフォレスターと共演後、レコーディングを行ったとも考えられる。
ちなみにライナーがシカゴ響定期で取り上げたマーラー作品は、交響曲第4番と「大地の歌」のみであり、交響曲第4番も1958年12月の演奏会直後にレコーディングされている。
ライナーは、上記のように同曲を1959年米RCAにシカゴ響とスタジオ録音しているが、リチャード・ルイスはこの録音に参加したほか、1966年米CBSにオーマンディとスタジオ録音。また1952年にバルビローリ、1960年にワルターとマゼール、1967年と1970年にセルとライブ録音していた。クリスタ・ルートヴィヒは、同曲を1964/1966年英EMIにクレンペラー、1972年米CBSにバーンスタイン、1974年独グラモフォンにカラヤンとスタジオ録音したほか、1967年にカルロス・クライバー、1970年と1972年にカラヤン、1983年にノイマンとライブ録音していた。
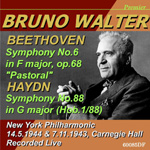
●ワルター/NYPライブ べートーヴェン「田園」、ハイドン88番
プレミエ60085DF
ベートーヴェン 交響曲第6番「田園」
ハイドン 交響曲第88番
ブルーノ・ワルター指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
1944年5月14日、1943年11月7日、ニューヨーク・カーネギーホール
ライブ、モノラル
※アセテートディスクへのライブ録音。第2次世界大戦中という年代を考慮すると、ディスク録音特有のスクラッチノイズも非常に少なく、音の濁りは若干あるもののバランスも良好、適度に残響もあり柔らかい音質で鑑賞に十分堪えるレベル。さらにクリアに響くと申し分ないが、戦時中のディスク録音にこれ以上の要求は無理な注文かも知れない。客席からの咳などのノイズも聞こえない。ディスクの傷や損傷によるクリックノイズやドロップアウトはマスタリングで解消・除去している。条件が異なるため比較は難しいが、音質そのものは、同じ頃に放送局スタジオで収録されたトスカニーニ/NBC響の録音には及ばないが、メトロポリタン歌劇場などのライブ録音よりも良好といえる。
「田園」は、定期演奏会シーズンを終えた1944年5月7日と14日の2回行われた「サマー・ブロードキャスト・コンサート」からの1曲。CBS放送によるラジオ中継を兼ねた演奏会で、14日は、アメリカ国歌と「田園」の後、休憩を挟んでワーグナー「ローエングリン」から第1幕と3幕の前奏曲、「トリスタンとイゾルデ」から前奏曲と愛の死というプログラム。中継放送を前提としたためか、定期演奏会などに比べて若干短い組み合わせ。アメリカ国歌は戦時中特有のプログラムと思われがちだが、記録を見ると毎回演奏されていたわけでもなく、7日のコンサートでも演奏されていない。
ハイドンの88番は、前年11月の定期演奏会からの1曲。当日は、ベートーヴェン「エグモント」序曲、ハイドン、休憩を挟んで後半にブラームス交響曲第1番というプログラム。通常のNYPの定期演奏会は3~4公演行われることが通常だが、このプログラムでは7日のみ。11月4~6日に「エグモント」序曲をミクロス・ローザ(ロージャ)の「主題と変奏、終曲」に替えたプログラムで3公演が行われており、7日は追加公演だったかもしれない。
ワルターにとって「田園」は、ウィーン・フィルとのSP録音やコロンビア響とのステレオ録音などで定評あるレパートリーと言われているが、NYPとの演奏は意外に少なく、1933年4公演、1943年2公演、1944年の当公演、1949年3公演、1957年1公演のみ。ちなみにウィーン・フィルとは1947年と1953年の2回しか演奏しておらず、「たまに取り上げる曲目」といった状態で、レコードの印象と実際の演奏会レパートリーの違いがよく分かる。一方、ハイドンの88番もNYPとは「田園」と同程度の演奏頻度。1933年4公演、1943年当演奏を含む4公演、1954年1公演、1951年1公演であった。
ワルターは当CDの録音以外に、ベートーヴェンの「田園」を1936年英HMVにウィーン・フィルと、1946年米CBSにフィラデルフィア管と、1958年同じく米CBSにコロンビア響とそれぞれスタジオ録音したほか、1951年ロサンゼルス・フィルとライブ録音していた。また、ハイドンの88番を1961年米CBSにコロムビア響とスタジオ録音していた。

●ジャンヌ=マリー・ダレ シューマン ピアノ協奏曲 サン=サーンス ピアノ協奏曲第5番「エジプト風」 1963年、1965年ライブ
プレミエ60086DF
シューマン ピアノ協奏曲
サン=サーンス ピアノ協奏曲第5番「エジプト風」
ジャンヌ=マリー・ダレ(ピアノ)
リチャード・バーギン指揮ボストン交響楽団
1963年11月9日、ボストン・シンフォニー・ホール
トーマス・シッパース指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
1965年1月2日録音、ニューヨーク・カーネギー・ホール
ライブ、ステレオ/モノラル
※シューマンはステレオ録音。ただし、オリジナル音源は高域が不足気味で若干歪みが感じられ、ヒスノイズも多く鮮明さも欠いていた。慎重なマスタリングにより、高域を補完してバランスを取り直す一方、ノイズ低減とともに音質改善を図った結果、優秀な音質とまでは言えないが、鑑賞に堪える状態となった。一方、サン=サーンスはモノラルながら音質は優れており、ステレオでないことが惜しまれるほど。ニューヨーク・フィル(カーネギー・ホール?)のライブ収録はなぜかステレオ録音の導入が遅く、1960年代末までモノラルのままだった。こちらもヒスノイズが目立ち、高音にピークがあったためマスタリングで改善し、鑑賞に支障がないレベルとしている。両曲とも会場ノイズは極小。
フランスの名女流ジャンヌ=マリー・ダレ(1905~1999年)は、1962年2月、ミュンシュ指揮ボストン響とサン=サーンスのピアノ協奏曲第2番で共演してアメリカデビュー以降、しばしば渡米を重ねた。シューマンはデビュー翌年のライブで3回公演のうち2日目の録音。第1楽章が終わると会場から拍手が出ており、これは第二次世界大戦中から1950年代前半頃までニューヨーク・フィルなどで見られた(聞かれた)光景だ。また、第3楽章では演奏終了を待たずに拍手が入るところも珍しい。こちらはミュンシュ指揮の「爆演」の際には見られるが、いずれにしてもジャンヌ=マリー・ダレの演奏が大好評だったことを物語る。
指揮のリチャード・バーギン(1892~1981年)は、ボストン響の元コンサートマスター兼副指揮者(associate
conductor)。1920年にコンサートマスターに就任し1924年から指揮台にも上ったというベテラン。1962年に退任したが、このライブが行われた1962~63シーズンには、客演として定期演奏会・ツアー含めて9公演を指揮している。ミュンシュ在任当時は、ブルックナーやマーラーなど、ミュンシュがあまり手がけない作品も指揮した。この日のプログラムは、ハイドンの交響曲第97番、シューマンの協奏曲、シベリウスの交響曲第5番というプログラム。当時のボストン響はミュンシュが退任しラインスドルフの時代だったが、シベリウスもまさしくミュンシュやラインスドルフの守備範囲外のレパートリーである。
一方、スタジオ録音も行ったサン=サーンスはジャンヌ=マリー・ダレの看板とも言える曲目。1964年12月~1965年1月に行われた4公演の3日目で、若くして亡くなったトーマス・シッパース指揮ニューヨーク・フィルとの共演。この日のプログラムは、サリエリの歌劇「オルムスの王アクスール」序曲、ビゼーの交響曲第1番、サン=サーンスの協奏曲、休憩後にストラヴィンスキーの「ペトルーシカ」というもの。
ジャンヌ=マリー・ダレは、ニューヨーク・フィルとは3回共演しており、1963年12月にジョージ・セルの指揮で初共演後(曲目はリストのピアノ協奏曲第2番)、1964年7月のスタジアムコンサートでハンス・シュヴィーガーの指揮で再び共演(曲目は同じ)、上記ライブが3度目であった。
ジャンヌ=マリー・ダレは、シューマンのピアノ協奏曲のスタジオ録音を行わず、上記ライブが現在確認されている唯一の録音。一方、サン=サーンスのピアノ協奏曲第5番は、同曲を含む協奏曲全集を、1956~57年仏EMIパテにルイ・フーレスティエ指揮フランス国立放送管とスタジオ録音していた。
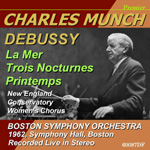
●ミュンシュ/ボストン 1962年ステレオ・ライブ ドビュッシー「海」「夜想曲」「春」
プレミエ60087DF
ドビュッシー 交響詩「海」、「三つの夜想曲」、交響組曲「春」
シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団
1962年3月30日、2月2日、1月12日、ボストン・シンフォニー・ホール
ライブ、ステレオ
※3曲とも良好なステレオ録音。1951年からボストン響(BSO)演奏会の中継放送を開始した地元放送局WGBH(Western Great Blue
Hill)は、1958年頃からステレオ収録を導入しており、3シーズン目に当たる当録音は技術的にも安定した音質で楽しめる。ただし、オリジナル録音はダイナミックレンジが広大であるため(ミュンシュのフォルティッシモが大きすぎるのだ)、家庭での鑑賞を考慮し、音質を損ねない範囲でコンプレッサーによって強音を若干圧縮している。会場ノイズは少ない。
当録音の3曲まとめて「オール・ドビュッシー・プログラム」の公演が行われたように錯覚するが、実際は1961~62年定期公演シーズンの演奏会からの抜粋である。3月30日は3回公演2日目で、ベルリオーズ「幻想交響曲」、「海」、ラヴェル「ダフニスとクロエ第2組曲」というフランス・プログラム。2月2日は2回公演1日目で、ベートーヴェンの弦楽四重奏曲第16番から第3楽章(弦楽合奏版)、「夜想曲」、オネゲルの交響曲第5番「三つのレ」、サン=サーンスのピアノ協奏曲第2番(独奏ジャンヌ=マリー・ダレ)、ラヴェルの「ラ・ヴァルス」という、これもほぼフランス・プログラム。ベートーヴェンは当初予定になく、この年の1月29日に亡くなったフリッツ・クライスラーの追悼のため演奏された。1月12日は4回公演1日目で、「春」、ウォルター・ピストンの交響曲第6番、ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲(独奏エリカ・モリーニ)というプログラム。近・現代曲(といってもかなり保守的だが)の後に、メイン・プログラムとしてポピュラー名曲(と人気独奏者)を配置した構成である。
ミュンシュ得意のドビュッシーだが、BSOにおける3曲の演奏回数はかなりばらつきがある。この中では「海」が最も多く、音楽監督時代の1950~1963年に何と88回も取り上げている。1952~53年と1956~57年シーズンを除けば、毎シーズン演奏している状態で、後任のラインスドルフが「レパートリーが特定の曲に偏っている」と批判した典型だが、トスカニーニやセルも好んだ作品であり、現在以上に人気の演目だったようだ。一方、「夜想曲」は、「シレーヌ」を含む全曲の演奏は当録音を含む1962~63年シーズンの3公演のみと極端に少ない。「シレーヌ」を除く2曲の演奏は10公演行っており、女声合唱が入るという特殊性が演奏回数の少なかった理由だろう。「春」は、1952~53年と1961~62年シーズンにそれぞれ9回取り上げているが、BSOは1プログラムで定期3~4回公演のほか、一部異なるプログラムでボストン近郊のツアーやサマーコンサートも行うため、多いというわけではないようだ。
ミュンシュは当盤以外に「海」を、1942年仏グラモフォンにパリ音楽院管、1956年米RCAのBSO、1968年仏コンサートホールソサエティにフランス国立放送管とスタジオ録音したほか、1951年トリノ・イタリア放送管、1956年BSO、1957年シンフォニー・オブ・ジ・エア、1958年BSO(2種)、1960年BSO、1962年4月BSO、1962年5月フランス国立放送管、1963年シカゴ響、1963年3月フィラデルフィア管、1963年8月BSO、1965年フィラデルフィア管、1966年フランス国立放送管、1967年7月シカゴ響、1967年11月パリ管とライブ録音していた。また、「3つの夜想曲」を1968年仏コンサートホールソサエティにフランス国立放送管とスタジオ録音、「春」を1962年米RCAにBSOとスタジオ録音していた。
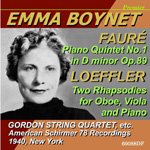
●エンマ・ボワネ フォーレ ピアノ五重奏曲第1番、レフラー 2つの狂詩曲 米シャーマー78回転SP復刻
プレミエ60088DF
フォーレ ピアノ五重奏曲第1番
レフラー オーボエとヴィオラ、ピアノのための2つの狂詩曲
エンマ・ボワネ(ピアノ)
ゴードン弦楽四重奏団
ブルーノ・ラバテ(オーボエ)、ジャック・ゴードン(ヴィオラ)
1940年、ニューヨーク(スタジオ・セッション録音)
モノラル
※米シャーマー・レーベルによる78回転SPスタジオ録音の復刻。特に優秀な録音・復刻というわけではないが、大きなノイズもなく一応は及第。スタジオ録音であるため各楽器のバランスも問題ない。なお、バックジャケット表記にあるレフラー作品のジャック・ゴードンの担当楽器はヴィオラが正しい。
シャーマーは、ニューヨークに本拠を置く楽譜出版社。1940年代から50年代にかけてレコード製作を行った。ジャズやポピュラーが多かったようだが、クラシック・レパートリーでは、英国のピアニスト、ハロルド・バウアーの録音が知られており、上記ゴードン弦楽四重奏団による近代作品も録音していた。
エンマ・ボワネ(1891~1974年)は、フランス・パリ出身の女流ピアニスト。パリ音楽院でイシドール・フィリップに師事。プリミエ・プリを取得して卒業後デビューしたが、1940年にナチス・ドイツのパリ侵攻を逃れ、師フィリップとともにアメリカへ避難した。上記録音はアメリカ到着後間もない頃の録音ということになる。クーセヴィツキーはボワネの演奏を好み、しばしばボストン響の定期演奏会に招いたと言われ、記録によれば1935年~1943年にモーツァルトとサン=サーンスの協奏曲で3回・計7公演している。レコーディングはあまり多くなく、当録音以外に、戦前に英HMVや仏パテ、米ビクターなどにSP8枚程度、戦後は米ヴォックスに3枚のLPと1枚のEPを録音している。近年は入手出来る録音が少ないこともあり、一部に熱狂的愛好家が存在する。
ボワネは、フォーレを得意としており、戦後録音の3枚のLPのうち2枚もフォーレ作品であるが、上記のピアノ五重奏曲第1番はおそらく唯一の室内楽作品録音である。
一方のレフラー(1861~1935年)は、日本ではほとんど知られていないが、ベルリン出身のアメリカの作曲家で、フランス印象主義を影響を受けた作品を発表した。本CDの「2つの狂詩曲」も確かにフランス近代風だ。
共演のゴードン弦楽四重奏団は、ロシア出身でシカゴ響のコンサートマスターだったジャック・ゴードン(1899~1948年)によって1921年に設立された団体。先述したように米シャーマーにフランク・ブリッジ、カーペンターなどの近代作品を録音するなど意欲的な活動を行った。
オーボエのブルーノ・ラバテ(1883~1968年)は、イタリア出身で1920~43年にニューヨーク・フィル(NYP)の首席奏者を務めた。ラバテの有名なエピソードとして、NYPに客演したオットー・クレンペラーが、リハーサルで「ベートーヴェンの作品やその時代、精神」について長講釈を垂れたところ、ラバテが「クレンプ、あんたしゃべりすぎだ」(Klemp,
you talka too
much)と言って遮った。ラバテは「銀行に5万ドルあれば心配ない」と語っており、トラブルを起こしてNYPのポジションを失うことも気にしなかったようだが、一方のクレンペラーは面子丸つぶれとなったという。
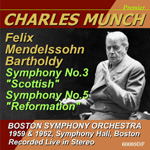
●ミュンシュ/ボストン ステレオ・ライブ メンデルスゾーン「スコットランド」「宗教改革」
プレミエ60089DF
メンデルスゾーン 交響曲第3番「スコットランド」、第5番「宗教改革」
シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団
1959年11月7日、1962年4月19日、ボストン・シンフォニー・ホール
ステレオ ライブ
※2曲ともボストン響(BSO)定期演奏会のステレオ・ライブ録音で、「スコットランド」は特に優秀録音。クリアで解像度が高く、ダイナミックレンジも十分で1959年録音とは信じがたい音質である。各セクションのバランスも問題ない。「宗教改革」は3年後の録音だが、「スコットランド」には及ばず少し荒れた音質。それでも年代を考えれば良好で鑑賞には差し支えないレベル。2曲とも会場ノイズは極小。
1959年の演奏会は、前半にバッハのヴァイオリン協奏曲第1番とベルクのヴァイオリン協奏曲(2曲ともアイザック・スターン独奏)、後半に「スコットランド」という、やや変則的なプログラム。ミュンシュ/BSOによる「スコットランド」は1959~1960年シーズンに10公演を集中的に演奏したのみで極めて珍しいレパートリー。1カ月後の12月7日、米RCAに同曲の録音が予定されており、そのための「予行演習」だったようだ。
一方、1962年の演奏会も変則的で、前半はミュンシュ指揮でモーツァルトの「フリーメーソンのための葬送音楽」「宗教改革」、後半はナディア・ブーランジェの指揮で、妹リリ・ブーランジェの詩編第130番、129番、第24番が演奏された。定期演奏会では作曲家による自作自演の機会を設けることがあるが、姉であるナディア・ブーランジェの指揮によるその変形版といえる。ミュンシュ/BSOによる「宗教改革」は「スコットランド」に比べると演奏機会がはるかに多く、1949~1950年シーズンに4公演、1957~1958年シーズンに8公演、1961~1962年シーズンに3公演、1964~1965シーズンに5公演行われている。現在の日本では人気がある作品とは言えないが、宗教的要素があるためか、当時のボストンの聴衆にはなじみ深い曲だったようだ。
ミュンシュは上記録音のほかに、「スコットランド」を1959年12月に米RCAにBSOとスタジオ録音、「宗教改革」を1947年英デッカにパリ音楽院管、1957年に米RCAにBSOとスタジオ録音していた。
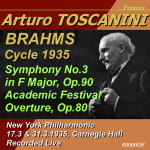
●トスカニーニ/NYP1935年ライブ ブラームス 交響曲第3番、大学祝典序曲
プレミエ60090DF
ブラームス 交響曲第3番
大学祝典序曲
アルトゥーロ・トスカニーニ指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
1935年3月17日、3月31日、ニューヨーク・カーネギーホール
ライブ、モノラル
1935年2月から4月にかけて、トスカニーニとニューヨーク・フィル(NYP)は、本拠地カーネギーホールにおいてブラームス・チクルスを開催した。定期演奏会の一環ではあったが、交響曲全曲をはじめとして協奏曲や合唱曲なども大規模なもので、奇跡的にも、コロンビア・ネットワーク・ラジオによって、コンサート数か月前に導入された米Presto社製タイプ6Dアセテート・ディスク・レコーダーですべての演奏がライブ録音された。
プレミエ60035DFで発売されているトスカニーニ指揮ブルックナー7番の解説でも触れたが、同レコーダーは33・1/3回転の16インチディスク1枚で20分程度の録音が可能であり、ブルックナーの録音時とは異なり、2台(以上?)のレコーダーを使用して、欠落なしに録音された。国土が広いアメリカでは時差があるため、各地に放送するためには、録音して時間をずらして放送する必要があったためと思われる。
3月17日の交響曲第3番はチクルス第4回目の録音。14、15、17日と同一プログラム3日目の演奏会で日曜日午後3時開演のマチネー。プログラム前半はセレナーデ第1番の抜粋(アレグロ・モルト)に続き、ヴラディミール・ホロヴィッツをソリストに迎えたピアノ協奏曲第1番という豪華な演目。休憩を挟んでプログラム後半に交響曲が演奏された。
3月31日の大学祝典序曲はチクルス第5回目の録音、28、29、31日と同一プログラム3日目の演奏会でこちらも日曜日午後3時開演のマチネー。プログラム前半にセレナーデ第2番、ワルツ集「愛の歌」(ピアノ連弾伴奏)、休憩を挟んで後半に合唱曲4曲(ホルン、ハープ、ファゴット伴奏)、ハンガリー舞曲3曲(こちらは管弦楽版)、最後に大学祝典序曲という、現在から見るとやや異例のプログラム。ただし、当時はオーケストラの定期演奏会でもピアノ伴奏付き歌曲やオペラ・アリアなど、多彩なプログラムが組まれることが通常であり、今日のプログラミングの方が硬直的という見方もあろう。
広大なレパートリーを持っていたトスカニーニだが、ブラームスは好んだ作曲家の一人。特に交響曲は残された録音も多いが、当CDの録音はおそらく最古で最も若い(といっても68歳前後だが)頃の録音と思われ、後年、NBC響との録音に比べると伸びやかさや柔軟さが感じられる。なお、トスカニーニはNYPとのブラームス・チクルスを終えた後、イギリスへ渡りBBC響と初共演。こちらのコンサートもBBCによってライブ録音されており、比較すると興味深いかもしれない。
この種の古い録音で最も注目されることは録音状態や音質だが、すでに80年以上を経た古いアセテート・ディスクでもあり、原盤はノイズが過大で音質改善は困難を極めた。ただし、中継放送用にプロのエンジニアによって録音されていることもあり、バランスや音質自体は問題なく、音楽情報を削らずにノイズのみを除去することに徹した結果、思いのほか良好な状態に仕上がっている。交響曲は、確かに周波数レンジは狭いが、音楽として必要な帯域は確保されており、アセテート・ディスク特有のサーフェイス・ノイズもごく一部を除き微少で、十分鑑賞に堪える状態。第二次世界大戦中のブルーノ・ワルター/NYPなどによる状態の悪いライブ録音よりは、はるかに上質といえる。一方、序曲のオリジナル原盤は交響曲よりもノイズが少なく、さらに良好な状態。おそらく録音後の再生回数の差によるものと思われ、1950年代のライブ録音と言われても不思議ではない。
なお、交響曲と同日に録音されたホロヴィッツ独奏のピアノ協奏曲がすでにLPやCDで発売されているが、交響曲に比べて極めて劣悪な録音状態である点は、おそらく録音後に繰り返し再生され、ディスクが摩耗・損傷した結果であろう。
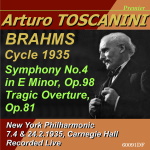
●トスカニーニ/NYP1935年ライブ ブラームス 交響曲第4番、悲劇的序曲
プレミエ60091DF
ブラームス 交響曲第4番
悲劇的序曲
アルトゥーロ・トスカニーニ指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
1935年4月7日、2月24日、ニューヨーク・カーネギーホール
ライブ、モノラル
1935年2月から4月にかけて、トスカニーニとニューヨーク・フィル(NYP)は、本拠地カーネギーホールにおいてブラームス・チクルスを開催した。定期演奏会の一環ではあったが、交響曲全曲をはじめとして協奏曲や合唱曲なども大規模なもので、奇跡的にも、コロンビア・ネットワーク・ラジオによって、コンサート数か月前に導入された米Presto社製タイプ6Dアセテート・ディスク・レコーダーですべての演奏がライブ録音された。
プレミエ60035DFで発売されているトスカニーニ指揮ブルックナー7番の解説でも触れたが、同レコーダーは33・1/3回転の16インチディスク1枚で20分程度の録音が可能であり、ブルックナーの録音時とは異なり、2台(以上?)のレコーダーを使用して、欠落なしに録音された。国土が広いアメリカでは時差があるため、各地に放送するためには、録音して時間をずらして放送する必要があったためと思われる。
4月7日の交響曲第4番はチクルス最終回第6回目の録音。3、5、7日と同一プログラム3日目の演奏会で日曜日午後3時開演のマチネー。プログラム前半はセレナーデ第1番。休憩を挟んでプログラム後半に交響曲が演奏された。
2月24日の悲劇的序曲はチクルス第2回目の録音、21、22、24日と同一プログラム3日目の演奏会でこちらも日曜日午後3時開演のマチネー。プログラム前半に悲劇的序曲、ハイフェッツ独奏によるヴァイオリン協奏曲、休憩を挟んで後半に交響曲2番というプログラムで、今日よく見られるオーソドックスなプログラミング。ヴァイオリン協奏曲はすでにLPやCDで発売されているが、交響曲第2番のディスクはまだ発見されていないとのこと。
広大なレパートリーを持っていたトスカニーニだが、ブラームスは好んだ作曲家の一人。特に交響曲は残された録音も多いが、当CDの録音はおそらく最古で最も若い(といっても68歳前後だが)頃の録音と思われ、後年、NBC響との録音に比べると伸びやかさや柔軟さが感じられる。なお、トスカニーニはNYPとのブラームス・チクルスを終えた後、イギリスへ渡りBBC響と初共演。こちらのコンサートもBBCによってライブ録音されており、比較すると興味深いかもしれない。
この種の古い録音で最も注目されることは録音状態や音質だが、すでに80年以上を経た古いアセテート・ディスクでもあり、原盤はノイズが過大で音質改善は困難を極めた。ただし、中継放送用にプロのエンジニアによって録音されていることもあり、バランスや音質自体は問題なく、音楽情報を削らずにノイズのみを除去することに徹した結果、思いのほか良好な状態に仕上がっている。交響曲は、確かに周波数レンジは狭いが、音楽として必要な帯域は確保されており、アセテート・ディスク特有のサーフェイス・ノイズもごく一部を除き微少で、十分鑑賞に堪える状態。第二次世界大戦中のブルーノ・ワルター/NYPなどによる状態の悪いライブ録音よりは、はるかに上質といえる。一方、序曲のオリジナル原盤は交響曲よりもノイズが少なく良好な状態だったため、より良い音に仕上がりとなっている。

●セル/クリーヴランド管 高音質ステレオライブ モーツァルト 交響曲第38番「プラハ」、41番「ジュピター」
プレミエ60092DF
モーツァルト 交響曲第38番「プラハ」、41番「ジュピター」
ジョージ・セル指揮クリーヴランド管弦楽団
1965年10月14日(38番)、1967年2月8日(41番)
クリーヴランド・セヴェランス・ホール、ボストン・シンフォニー・ホール
ライブ、ステレオ
38番は本拠地セヴェランス・ホールにおける定期公演、41番はボストンへのツアーにおける演奏で、
2曲とも優秀なステレオ録音。38番はエアチェックのようだが、高品質な録音機材を使用したらしく音質は極めて良好。ただし、受信障害によると思われるノイズが若干あり、マスタリングの際に慎重に除去している。また、高域が強め出ていたためバランスを取り直している。41番もエアチェックらしくヒスノイズが多かったため音質を維持しつつ除去した。両曲とも会場ノイズも少なく、ストレスなしに音楽を楽しみことができる。マスタリング後の状態は、いずれも1960年代中期のメジャーレーベル・スタジオ録音に匹敵する高音質で、当時の米放送局(+エアチェックリスナー)の技術レベルの高さを感じさせる。
1965年10月14日のプログラムは、16日との2回公演で、モーツァルトの38番「プラハ」、ヨゼフ・スークの独奏で同じくモーツァルト「ヴァイオリンと管弦楽のためのアダージョ」ホ長調K.261、スーク独奏でスーク(ヴァイオリニストの祖父)「幻想曲」、(おそらく休憩を挟んで)ヤナーチェク「シンフォニエッタ」という、スークを客演に招いたためかチェコがらみの特集。1967年2月8日のツアー公演は、前半が最初に41番、続けてアメリカの現代作曲家ベンジャミン・リースの「弦楽四重奏と管弦楽のための協奏曲」(弦楽四重奏はクリーヴランド管の首席奏者たちによる)、休憩を挟んで後半にシューマンの交響曲第3番「ライン」という、現代作品とポピュラーな交響曲を織り交ぜたセルらしい「教育的プログラム」。
セルは、モーツァルトの38番のセッション(スタジオ)録音を残しておらず。クリーヴランド管の定期演奏会でも1959年11月と当CDに聴く1965年10月のわずか2回しか取り上げなかった。ちなみに、1965年の演奏会直後?の同月に第1楽章のみレコーディングが実施されており(当然CBSによる録音だろう)、全曲を録音する計画があったと思われるが、セルが出来映えに不満を持ったか、その後の録音は中止されLP発売も実現しなかった。セルはモーツァルトを主要なレパートリーとしており、レコーディングも多いが、36番「リンツ」のようにクリーヴランド管の定期で全く取り上げなかった曲目もあり、作品ごとの評価には差があったようだ。
一方、41番は当CDの演奏以外に、クリーヴランド管の定期では1948年1月、1949年12月、1955年11月、1963年11月、1966年10月と時期を空けながらも取り上げており対照的であるが、1966年以降は、意外なことに定期演奏会で取り上げなかった。
上記のように、セルは38番のスタジオ録音を残さず当CDが現在確認されている唯一の録音。41番は、1955年と1961年にクリーヴランド管と米CBSにスタジオ録音したほか、1958年にコンセルトヘボウ管、1968年にクリーヴランド管とライブ録音していた。
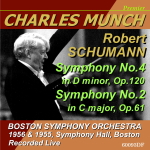
●ミュンシュ/ボストン響 ライブ シューマン 交響曲第4番、第2番
プレミエ60093DF
シューマン 交響曲第4番、第2番
シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団
1956年10月26日、1955年11月12日、ボストン・シンフォニー・ホール
ライブ、モノラル
2曲ともボストン響(BSO)定期演奏会のライブ録音で、モノラルながら当時の水準を超える良好な音質。前年の第2番の方がわずかに上だが大差はなく、おそらく音源は放送局保有のオリジナルテープのダイレクトコピーと想像され、バランスも良好で破綻もなく、いずれにしても鑑賞には全く問題ない音質。会場ノイズも極小。
1956年10月26日の演奏会は翌27日との2回公演で、前半にモーツァルトの交響曲第31番「パリ」、ウォルター・ピストンの交響曲第5番、後半は、長年BSOのライブラリアンを勤め10月11日に亡くなったレスリー・ジャドソン・ロジャーズを追悼したベートーヴェン弦楽四重奏曲第16番第3楽章(弦楽合奏版)、交響曲第4番というプログラム。
1955年11月12日の演奏会は前日11日との2回公演で、前半にシベリウスの紹介者として知られ同年8月22日に亡くなった音楽評論家オーリン・ダウンズを追悼したモーツァルトの「フリーメーソンのための葬送音楽」、続いて同じくモーツァルトのオーボエ、クラリネット、ホルン、ファゴットと管弦楽のための協奏交響曲、後半に交響曲第2番というプログラム。
ミュンシュはシューマンの交響曲第4番を大変好んだようで、BSOの定期では、1947-48シーズンに3回、1949-50シーズンに13回、1950-51シーズンに1回、1951-52シーズンに4回、1954-55シーズンに12回、1956-57シーズンに4回、1960-61シーズンに5回取り上げている。定期演奏会は同一プログラムで2~4回公演を行うが、それを差し引いても定期で10回以上取り上げるというのは異例である。一方、第2番は一般に演奏回数が多い曲ではないが、それでもミュンシュは、1952-53シーズンに3回、1955-56シーズンに12回、1958-59シーズンに8回取り上げており、こちらもかなり多い方だ。
ミュンシュは当CD以外に、シューマンの交響曲第4番を1947年ロンドン・フィルと英デッカにスタジオ録音したほか、1960年BSO、同年シカゴ響、1966年フランス国立放送管、1967年シカゴ響とライブ録音していた。また、交響曲第2番を1958年と1966年にBSOとライブ録音していた。

●モントゥー/ニューヨーク・フィル ライブ ベルリオーズ 幻想交響曲ほか
プレミエ60094DF
ベルリオーズ 幻想交響曲、ヴァイオリンと管弦楽のための「夢とカプリッチョ」
ヨゼフ・シゲティ(ヴァイオリン)
ピエール・モントゥー指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
1959年2月28日、3月7日、ニューヨーク・カーネギー・ホール
モノラル ライブ
※2曲ともニューヨーク・フィル(NYP)定期演奏会のライブ録音。幻想交響曲は、当時のライブ録音の平均レベルの音質。特に優秀というわけではないが、ノイズや破綻・欠落はなく、各セクションの録音バランスも良く、周波数レンジや解像度も不足していないため、鑑賞には全く問題ない水準。ただし、当時ニューヨークでは風邪が流行っていたのか、数人の聴衆の咳が聞こえる。「夢とカプリッチョ」は「幻想」から一週間後の録音だが、こちらは当時の水準を超える高音質。いずれの音源も公式には「ヴォイス・オブ・アメリカ」(VOA)が保管しているとされているが、おそらく「夢とカプリッチョ」はVOA音源のコピー、「幻想」はエアチェック(ただしエアチェックとしてはかなり上質)による音質の違いであろう。
1927年の初共演以来、NYPと関係が深かったモントゥーによる同オケとの最後期の客演。3月7日を含む公演は、定期演奏会への最後の登場であった(その後、1960~1961年にスタジアム(野外)コンサートを5回指揮している)。
2月28日の演奏会は4回公演の3日目、午後8時半開演で、前半にミヨー(クープラン原曲)のプレリュードとアレグロ、ルドルフ・ゼルキンを迎えてベートーヴェンの「皇帝」、後半に「幻想」というプログラム。
3月7日の演奏会は4回公演の3日目(ただし、4日目の公演はソリストが異なり、曲目も一部異なる)、同じく午後8時半開演で、前半にラヴェルの「クープランの墓」、シゲティとの共演によるバッハのヴァイオリン協奏曲BWV1052R(ウィルフリード・フィッシャーによるチェンバロ協奏曲第1番の編曲版)、ラヴェルのスペイン狂詩曲、後半にシゲティ共演の「夢とカプリッチョ」、ラヴェルの「ダフニスとクロエ」第1、第2組曲というプログラム。通常であればオール・ラヴェル・プログラムとすべきかもしれないが(ヴァイオリン曲であれば「ツィガーヌ」など)、シゲティの要望?を入れたためか、上記のようなフランス作品とバッハの混合プログラムとなっている。ちなみにラヴェル作品はすべてプレミエ60044DFで発売済みである。
当録音の「幻想」は1980年代にイタリアのレーベルでLP発売されたのみで初CD化、「夢とカプリッチョ」は初出と思われる。
モントゥーは「幻想」を得意としており、5回のスタジオ録音を行っているが、ニューヨーク・フィルへの客演では、1951年のスタジアム・コンサート1回と当公演を含む4回演奏したのみであった。「夢とカプリッチョ」は珍しい作品だが、モントゥーも当公演3回のみの演奏。NYPとしても今日に至るまで当公演の演奏のみであるようだ。
モントゥーは当CD以外に、「幻想交響曲」を1930年仏グラモフォンにパリ交響楽団と、1945年と1950年米RCAにサンフランシスコ響と、1958年英デッカにウィーン・フィルと、1964年コンサート・ホール・ソサエティにハンブルク北ドイツ放送響とスタジオ録音したほか、1948年コンセルトヘボウ、1961年ロンドン響、1962年6月コンセルトヘボウ(オルガヌム110018ALで発売済み)、同年11月ロンドン響、1964年ミラノRAI放送響とライブ録音していた。一方「夢とカプリッチョ」は当CDが唯一の録音である。
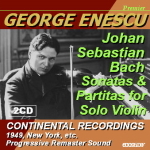
●エネスコ/バッハ 無伴奏ヴァイオリン・ソナタとパルティータ全曲 米コンチネンタルLP高音質復刻
プレミエ60095DF
J・S・バッハ
無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ第1番~第3番
無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第1番~第3番
ジョルジュ・エネスコ(ヴァイオリン)
1949年、ニューヨークおよびウェブスター(マサチューセッツ)
(米コンチネンタル CLP104/106原盤)
モノラル
※CD-R2枚組。有名な「エネスコのバッハ」の復刻。オリジナルのコンチネンタル盤LPは1950年に発売されたものの、アメリカ国内ではあまり評価されず、3年足らずでカタログから落とされ、1957年に再発売されたようだが、これもごく少数・短期間の発売に終わった。1970年代以降、正式なライセンスを得て米オリンピックやフィリップス・レーベルでLPやCDが発売されたが、疑似ステレオ化された音質に不備や不満が多く、日本や英国などの個人コレクターやマニアによって、独自にオリジナルLPから復刻したLP・CDが数多く発売されている。
当ディスクの音源はアメリカの匿名エンジニアの手によるもので、復刻自体は数年前に行われたようだが、このほどディスク化の許可が得られたため発売することになった。「先進的なリマスターサウンド」と称する復刻作業の詳細は不明だが、数セットのコンチネンタル盤および一部は再発盤を使用し、適正なイコライザーカーブで再生してデジタル・コピー。盤の状態の良い部分のみをつなぎ合わせ、さらにノイズ処理を行ったものと言われ、基本的には極めてオーソドックスな復刻プロセスを踏んだものと思われる。ただし、依然として、オリジナルLP由来の製盤不良などによる様々なノイズが残っていたため、音質を損ねない軽度のリマスタリングを行っている。
肝心の音質であるが、オリジナル盤特有のスクラッチノイズは皆無である一方、デジタルノイズリダクションを過剰に使用した際の悪弊である音質変化や妙な付帯音はなく、余分なステレオプレゼンスや残響なども付加されていないため、一切のストレスなくエネスコの演奏を鑑賞でき、復刻は成功したようだ。
コンチネンタル盤は、初出がLPであるにもかかわらず、テープではなくアセテート盤に収録されたと言われる。当時アメリカの放送局などに広く普及していた、最大20分程度録音可能な16インチディスクレコーダーを使用したと思われるが、バッハの無伴奏であれば各曲とも20分以内に収まること(実際は数曲連続して録音したのだろう)。普及間もないテープレコーダーを使用するよりもコストダウンを図ったためと想像される(コンチネンタル・レーベルのオーナーであるドン・ガボール(ガボー)は、後に廉価盤のレミントン・レーベルを立ち上げ、メジャーレーベルに低価格で対抗した)。ただし、LP製造の際の原盤となるラッカー盤のカッティングには、通常はテープレコーダーが必須とされるから、米コロンビアによるLP発表の2年後という時期であれば、78回転SPによる発売を意識していたかもしれない。
なお、コンチネンタル・レーベル(および後身のレミントン)の現在の原盤所有者はヴァレーズ・サラバンド・レーベルとされるが(1980年代に一部のレミントン録音をCD化・発売していた)、エネスコのバッハについては、熱狂的な支持者がいる反面、当時67歳で関節炎を患っていたと言われるエネスコの技巧上の不備により、専門家の多くは否定的であるため、正規盤CDの発売は難しいであろう。

●モニク・ドゥ・ラ・ブリュショルリ アメリカ・デビュー・ライブ
ラフマニノフ ピアノ協奏曲第3番ほか
プレミエ60096DF
ラフマニノフ ピアノ協奏曲第3番
ラヴェル マ・メール・ロア
モニク・ドゥ・ラ・ブリュショルリ(ピアノ)
エルネスト・アンセルメ指揮ボストン交響楽団
1951年12月14・21日、ボストン・シンフォニー・ホール
モノラル ライブ
※超絶技巧の名手モニク・ドゥ・ラ・ブリュショルリによるアメリカ・デビュー・ライブ録音。ドイツの高名な音楽評論家ヨアヒム・カイザーが著書で「彼女はヴァルキューレとなり、グランド・ピアノは軍馬となり、いまオクターヴ征討の戦いに進発する」と言わしめたが、当ディスクに聴くラフマニノフは、ヨアヒム・カイザーの表現にふさわしい貴重な演奏記録。オリジナル音源はおそらくボストン響(BSO)の記録保存音源または直前の同年10月から放送を開始した地元ラジオ局WGBHによる収録と思われる。ことさら優秀録音というわけではないが安定した音質で鑑賞には問題のないレベル。協奏曲におけるモニク・ドゥ・ラ・ブリュショルリの強力な打鍵を音割れせずに収録しており、ピアノとオーケストラのバランスも良好。後述するが、このような歴史的名演奏を過不足のない形で収録してくれたことに感謝したい。
モニク・ドゥ・ラ・ブリュショルリの公演は、ボストン響の定期演奏会として12月14日を含む14・15日の2公演が行われたが(13日にもオープン・リハーサルが行われた)、デビュー公演にラフマニノフのピアノ協奏曲第3番という難曲を選択したこと自体、空前のことであった。当時この作品は、ボストン響の聴衆にとってはラフマニノフ自身やホロヴィッツによる演奏機会が大半で、それ以外には1947年のヴィトルト・マウツジンスキ、1942年のポップスコンサートのおけるゼルマ・クレーマーによる演奏があったのみだったが、これほど完成度が高い演奏は、ラフマニノフやホロヴィッツに比肩するものではなかったろうか。しかもホロヴィッツの演奏に見受けられる「演出」がない分、明晰さでは勝るかもしれない。
公演はセンセーショナルな成功を収め、翌1952年2月BSOのニュージャージーとニューヨーク・ツアーでも同曲を演奏。同月21日にはカーネギーホールでリサイタルを行ってこちらも大反響を呼び。1953年にはニューヨーク・フィルの定期演奏会に招かれ(プログラムはチャイコフスキーの協奏曲第1番)、さらにカーネギーホールで再びリサイタルを行うなど、モニク・ドゥ・ラ・ブリュショルリはアメリカにおける名声を確立した。
これを契機として、米VOXへ一連のレコーディングを行ったが、意外なことにラフマニノフのピアノ協奏曲第3番の録音は行われなかった。おそらく作品のポピュラリティが劣ると判断されたと思われるが、これはチャレンジングなレコーディングレパートリーを開拓していたVOXにとっては大きな疑問であり、この辺りの事情を知りたいところ。
余白に収められた「マ・メール・ロア」は、同じくアンセルメ指揮による6日後の公演のライブ録音。アンセルメにとって1949年以来、2回目のBSO客演。1949年にシャルル・ミュンシュが常任指揮者に就任後、フランス系演奏家の招聘が増えたが、アンセルメやモニク・ドゥ・ラ・ブリュショルリもその一環であろう。ちなみにアンセルメによるラフマニノフの協奏曲伴奏はやや意外に思われるが、元来、広大なレパートリーを持ち、ロシア作品も得意としていたアンセルメにとっては、ラフマニノフの語法に全く問題なく対応している。
モニク・ドゥ・ラ・ブリュショルリは、上記のように、ラフマニノフのピアノ協奏曲第3番のスタジオ録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音である。
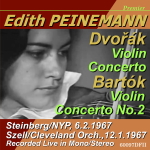
●エディット・パイネマン モノラル/ステレオ高音質ライブ
ドヴォルザーク、バルトーク ヴァイオリン協奏曲
プレミエ60097DFII
ドヴォルザーク ヴァイオリン協奏曲
バルトーク ヴァイオリン協奏曲第2番
エディット・パイネマン(ヴァイオリン)
ウィリアム・スタインバーグ指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
ジョージ・セル指揮クリーヴランド管弦楽団
1967年2月6日、ニューヨーク・カーネギー・ホール
1967年1月12日、クリーヴランド・セヴェランス・ホール
モノラル/ステレオ ライブ
※近年再評価が高まっているエディット・パイネマンの1967年アメリカ・ツアー時、スタインバーグとセルの共演ライブ。2曲ともオリジナル音源はエアチェックと思われるが、ドヴォルザークは残念ながらモノラル。1967年と言えばステレオLPやステレオ・レコーダーが一般化していた頃だが、この時期に至ってもニューヨーク・フィル自身の保存音源はモノラルが多く、放送もモノラルだった可能性がある。バルトークは幸いステレオ録音。録音についてはニューヨークよりも地方都市クリーヴランドの方が進歩的だったようだ。
ただし、両者とも元の音源は古ぼけたカセットテープのような艶のないくすんだ音質で、若干歪みもあり高域が不足する一方、ヒスノイズも耳に付いた。ただし、いずれも必要な音楽情報は記録されていたため、ディスク化に当たっては、イコライジングによる周波数特性の補正、ヒスノイズ低減、見かけ上の周波数帯域拡大等の音質改善を行った結果、ドヴォルザークはモノラルながら音質一新、バルトークはさらに見違えるような高音質となった。両者とも音質改善前は線が細く頼りない印象だった演奏が、自信に満ちた堂々たる演奏へと変貌した。特にバルトークはすごみさえ感じる音質で(曲想の影響もあるが)、ステレオ録音の完成期である1967年という年代を考慮しても優秀な音質となった。
エディット・パイネマンは、前記のように再評価高まるにつれて放送録音などの発掘も進み、ジョージ・セルが高く評価したことも周知されるようになった。エピソードの一部はオルガヌム110064AL(ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲)の解説でも紹介したが、実は、1956年のARDミュンヘン国際コンクールでパイネマンが優勝した際、審査員の一人だったスタインバーグが才能を評価し、1962年に彼が音楽監督を務めていたピッツバーグ響に出演依頼したことがアメリカ・デビューとなった(曲目はバルトークのヴァイオリン協奏曲第1番という珍しい作品)。そして演奏の評判をマックス・ルドルフ(当時シンシナティ響音楽監督)を通じてセルが知るところとなり、両者の共演につながったという。その意味では当ディスクは二人の支援者がバックを務めた貴重な録音でもある。なお、当ディスクは、セルの援助で1965年に入手したグァルネリの名器による演奏と推定され、入手前と思われるベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲よりも輝かしい音色を奏でている。パイネマンは当時30歳だったが、名器を得たこともあってか、ドヴォルザークはもとより、演奏困難と言われるバルトークの協奏曲を大家のように余裕を持って演奏している
ドヴォルザークはNYPの定期演奏会から。2月2、3、4、6日の4回公演の4日目(ただし、2月4日録音との情報もある)。プログラム前半は、最初にモーツァルトの「コシ・ファン・トゥッテ」序曲、続いてドヴォルザーク、後半はブルックナー交響曲第4番というもの。ドヴォルザークは、ドイツ・グラモフォンへのデビューレコードで録音した作品で、名刺代わりとも言える作品。パイネマンはNYPとは2年前の1965年にもスタインバーグと共演(バルトークのヴァイオリン協奏曲第2番)、さらに1970年にはセルと共演しており(モーツァルトのヴァイオリン協奏曲第5番)、両指揮者のお気に入りだったことが分かる。
バルトークはクリーヴランド管の定期演奏会から。NYP公演に先立つ1月12日と14日の2回公演の初日。プログラムは、前半にメンデルスゾーン「真夏の夜の夢」序曲と劇付随音楽抜粋およびバルトークの協奏曲、後半にドビュッシー「海」というもの。しかし、バルトークの協奏曲のみでも40分近い大曲かつ難曲であり、聴衆はパイネマンの名演だけで「お腹いっぱい」になってしまったのではないだろうか。前記1965年のNYP定期でも同作品を取り上げているように、パイネマンの知的で端正な演奏スタイルは、ドヴォルザークなどのロマン派よりも近現代作品(と古典)の方がよりふさわしい感もある。
エディット・パイネマンは、上記のようにドヴォルザークのヴァイオリン協奏曲を1965年ドイツ・グラモフォンにスタジオ録音したほか、1958年ミュラー=クライ指揮シュトゥットガルト放送交響楽団と放送用スタジオ録音を行っていた。一方、バルトークのヴァイオリン協奏曲第2番はレコード用スタジオ録音を残さず、1957年ロスバウト指揮南西ドイツ放送交響楽団と放送用スタジオ録音を行っていた。

●ミュンシュ/ボストン響 高音質ステレオライブ
チャイコフスキー「悲愴」、シベリウス交響曲第7番
プレミエ60098DF
チャイコフスキー 交響曲第6番「悲愴」
シベリウス 交響曲第7番
シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団
1961年9月29日、ボストン・シンフォニー・ホール
1965年7月30日、タングルウッド・ミュージック・シェード
ステレオ ライブ
※チャイコフスキーはボストン響の定期演奏会、シベリウスはバークシャー(タングルウッド)音楽祭からのステレオ・ライブ録音。1950年代末からFMステレオ放送を行っていた地元ラジオ局WGBHのエアチェックと思われるが、いずれも音質は極めて優秀で、良好な受信環境の元で優れた機器を使用して録音されたもの想像される。2曲の録音年には4年の開きがあるが、シベリウスにやや音に厚みが感じられる程度で音質差はほとんど感じられず、演奏会場の違いの方が大きいかもしれない。ただ、1961年のチャイコフスキーは、元々の演奏のダイナミックレンジが広すぎて(ミュンシュのフォルティッシモが大きすぎるのだ)、家庭内で鑑賞する際のボリューム設定では、弱音は聴き取れない一方、強音は近所迷惑?になる恐れがあったため、コンプレッサーを微量使用して強音をわずかに抑えた。
1961年録音のチャイコフスキーは4回公演の初日で午後2時15分開演のマチネー。プログラムは、前半にブラームスのハイドン変奏曲、ドビュッシーのイベリア、後半にチャイコフスキーという、名曲集ではあるがいささかまとまりに欠く構成。この辺りは、入念に考え抜いてプログラムを組むジョージ・セルなどとは異なり、「聴衆に楽しんでもらえればよい」という発想か。ちなみにミュンシュはチャイコフスキーが得意という印象はないが、「悲愴」については、ボストン響常任指揮者就任直後の1949~1950年シーズンに8公演、1950~1951年シーズンに1公演(バークシャー音楽祭)、1951~1952年シーズンに11公演、1955~1956年シーズンに1公演、1956~1957年シーズンに15公演、1958~1959年シーズンに1公演(バークシャー音楽祭)、1961~1962年シーズンに9公演と、頻繁に取り上げている。有名曲だけにメジャーオーケストラの常任指揮者としては必携のレパートリーだったとも言えるが、一方で交響曲第4番は、ボストン響とは全期間通じても12公演、第5番に至っては全く取り上げていないなど落差が大きい。第5番などは「ミュンシュ向き」とも言える作品だけに意外である。
一方、1965年録音のシベリウスの交響曲第7番は、夏の音楽祭バークシャー・フェスティバルにおけるライブ。ミュンシュがボストン響の常任を退いた後の時期だが、頻繁に客演を繰り返していた。午後8時の開演で、プログラムは前半にヴィヴァルディ(ジロティ編曲)の合奏協奏曲ニ短調作品3の11、続けてシベリウス、後半にオネゲルの交響曲第4番「バーゼルの喜び」、ルーセルの「バッカスとアリアーヌ」第2組曲というもの。プログラム後半はミュンシュ得意の作品だが、シベリウスの交響曲第7番もなぜかミュンシュが好んだ作品。ボストン響とは、1955~1956年シーズンに4公演、1957~1958年シーズンに2公演、1964~1965年シーズンに1公演(当ディスクの録音)、1965~1966年シーズンに2公演と、作品のポピュラリティを考えるとかなり多い。しかもシベリウスの交響曲では第7番のみしか取り上げておらず、有名な「フィンランディア」も1953~1954年シーズンに2回演奏したのみという片寄りぶりが面白い。
シャルル・ミュンシュは当ディスク以外に、チャイコフスキー「悲愴」を1948年英デッカにパリ音楽院管弦楽団と、1962年に米RCAにボストン響とスタジオ録音していた。また、シベリウスの交響曲第7番を1964年にフランス国立放送管弦楽団とライブ録音していた。
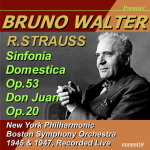
●ブルーノ・ワルター/ニューヨーク・フィルほか 1945年、1947年ライブ
R・シュトラウス 家庭交響曲、ドン・ファン
プレミエ60099DF
R・シュトラウス 家庭交響曲、交響詩「ドン・ファン」
ブルーノ・ワルター指揮ニューヨーク・フィルハーモニック、ボストン交響楽団
1945年12月23日、ニューヨーク・カーネギー・ホール
1947年1月21日、ボストン・シンフォニー・ホール
モノラル ライブ
※家庭交響曲はニューヨーク・フィル(NYP)、ドン・ファンはボストン響(BSO)の演奏会におけるライブ録音。いずれもテープ録音導入前に放送局などで広く普及していたアセテート・ディスク・レコーダーで収録されたもの。アセテート盤は、耐摩耗性が低いため繰り返しの再生や経年劣化によりスクラッチノイズなどが増える傾向にあるが、家庭交響曲はノイズが全くない非常に良好な状態。再生回数が極小かつ最良の環境で保存されていたか、または劣化が進んでいない1950年代前半頃にテープにダビングされ、今日まで保存されていたと思われる。ただし、オリジナル音源は地味な音質で高域も不足し、R・シュトラウスらしいオーケストレーションの華やかさに欠けていた。そのためイコライジングにより周波数特性を補正し。音にわずかに膨らみを与えた結果、モノラルLPの音質に匹敵するレベルまで改善することが出来た。一方、ドン・ファンのオリジナル音源は残念ながら保存状態が悪く、スクラッチノイズ等が盛大で原状のままではディスク化不可能だったため、音質を損ねない範囲で可能な限りノイズを低減した結果、わずかにノイズは残るものの一応鑑賞に堪える状態となった。音質自体は比較的良好で問題は少なく、高域を若干補正した程度であった。
1945年の家庭交響曲はNYP定期演奏会のライブ録音から。12月13・14日の2回公演の初日で午後8時45分開演。プログラムは、前半にコレルリの合奏協奏曲第8番「クリスマス協奏曲」とシューマンの交響曲第1番「春」。休憩を挟んでR・シュトラウスの家庭交響曲というもの。家庭交響曲はワルターにとって珍しいレパートリーで、NYPでは当録音を含む1945年12月13・14日と23日、1933年の定期演奏会でしか取り上げておらず、他のオーケストラにおける上演記録も見当たらない。しかし、NYPにとってこの作品は、合併前の前身のニューヨーク交響楽団が1904年に作曲者自身の指揮で初演した縁もあり、少なくとも1960年以前には、頻繁ではないもののメンゲルベルクやミトロプーロスらが演奏、1926年に一度だけ客演したフルトヴェングラーも取り上げていた。ワルターの演奏もオーケストラ側からの要請かもしれない。
一方、1947年BSOのドン・ファンは、1月17・18日の定期演奏会に続く追加公演のライブ録音から。追加公演と言っても、ラジオ放送を前提に当初から予定されていた特別公演らしく、当時の定期演奏会プログラムにも予告されている。午後8時半の開演で、プログラムはベートーヴェン「プロメテウスの創造物」から序曲、ハイドンの交響曲第92番「オックスフォード」、ドン・ファン、休憩を挟んでブラームスの交響曲第2番というもの。1月17・18日の定期プログラムにベートーヴェンを追加した形となっている。ドン・ファンは、当時既に人気作品であり、家庭交響曲とは異なり、ワルターも通常のコンサート・レパートリーとしてたびたび演奏していた。
ちなみに当録音の1945~1947年当時、R・シュトラウス本人はナチスへ協力した戦犯容疑による非ナチ化裁判の最中であった。1948年に無罪となったものの、容疑がかけられていた人物の作品を公然と演奏していたわけであり、「作品と作曲者は別個の存在」という認識と思われるが、コンサート・レパートリーとしてR・シュトラウスの作品が不可欠だったということだろう。
ブルーノ・ワルターは、家庭交響曲のスタジオ録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音。ドン・ファンは、当ディスク以外に1926年英コロンビアにロイヤル・フィル、1952年米コロンビアにNYPとスタジオ録音したほか、1940年NBC響、1950年ベルリン・フィル、1952年コンセルトヘボウ管、1955年フランス国立放送管とライブ録音していた。

●ストコフスキー/ハリウッド・ボウル響 1946年ライブ 音質良好
ラフマニノフ 交響曲第2番
プレミエ60100DF
ラフマニノフ 交響曲第2番
レオポルド・ストコフスキー指揮ハリウッド・ボウル交響楽団
1946年8月13日、ロサンゼルス・ハリウッド・ボウル
モノラル ライブ
※ロサンゼルス近郊の有名な野外ホール、ハリウッド・ボウルにおけるライブ録音。ラジオ放送のための録音と推定される。テープ録音導入前のアセテート・ディスク・レコーダーによる録音だが、ディスクの保存状態が良好だったためか、第3楽章冒頭にスクラッチノイズがかすかに聞こえる以外にノイズもなく、ディスク録音とはにわかに信じられない高音質。野外というハンディキャップも感じさせず、巧みなマイクセッティングを行っているのであろうか、バランスも良好で弦の美しさや金管の輝かしさなど、モノラルながら鑑賞には全く不満がない。ストコフスキーが録音に造詣が深いことはよく知られているものの、レコード化を前提としない放送録音にまで関与していたとは思えないが、事前に注文を付けていた可能性はある。演奏終了後、拍手の音質の古さでようやく1946年という年代に気付く(客席に天井がないのでマイクが遠いこともある)。かつて海外盤で同一の音源がCD化されていたが、さらに音質が改善されていると思われる。
ラフマニノフの交響曲第2番は、いかにもストコフスキーにふさわしい作品に思えるが、1977年にCBSへのレコーディング予定がありながら、惜しくもその数日前に95歳で亡くなり実現せずに終わった。思えば当ディスク録音後30年間にこの作品のレコーディング計画がなかったことの方が不思議だが、ストコフスキーという人は、一般に認識されるような大衆向けのエンターテイナーではなく(その要素もあるが)、現代音楽の初演を数多く手がけたり、オーケストラ配置を大胆に変更したように、あくまで実験的・啓蒙的発想で聴衆に音楽を届けるスタンスだったのだろう。その意味では、過去指向的なラフマニノフの交響曲第2番にはあまり興味がなかったとも考えられる。とはいうものの、当ディスクに聴く演奏は、ストコフスキーらしさ全開の豪華絢爛を極めたものとなっている。
ちなみに、演奏しているハリウッド・ボウル響は、1945年にストコフスキー自らが設立した団体で、1950年代中期からカーメン・ドラゴンが指揮した同名のライト・ミュージック中心の団体とは異なる(キャピトル・レーベルに録音する際にはキャピトル響とも称した)。ただし、わずか2年でコンサート活動を休止し、その後は1960年代までレコーディング専門の団体として存続したと言われる。いずれにしても楽員は専属ではなく、演奏会の度に契約するフリーランスだったと考えられ、コンサート活動休止後は、メンバーの一部ないし多くがカーメン・ドラゴン指揮の団体にその都度参加したのだろう。ハリウッド周辺のオーケストラには複数の紛らわしい名称の団体があり、ブルーノ・ワルターのために特に編成されたコロンビア響とロサンゼルス・フィルとの関係や、ハリウッドの映画音楽関係者が関わったと言われるグレンデイル響と(カーメン・ドラゴンの)ハリウッド・ボウル響の関係なども含め、実態の解明が求められる。
ストコフスキーは、1940年にフィラデルフィア管弦楽団の常任指揮者を退任後、オール・アメリカン・ユース管、ニューヨーク・シティ響、ハリウッド・ボウル響と団体を次々と設立するものの、フィラデルフィア管時代のような経営的安定を確保できないため長続きせず(第二次世界大戦前後という事情もあったが)、キャリア的には模索の時期だったかもしれない。その後は、ニューヨーク・フィル、ヒューストン響などのポストを経て、1962年のアメリカ響設立によりオーケストラ遍歴は落ち着くことになる。
ストコフスキーは上記のように、ラフマニノフの交響曲第2番のスタジオ録音を残さず、当ディスクのライブが現在確認されている唯一の録音である。

●フランチェスカッティ 音質良好1959・1955年ライブ
パガニーニ ヴァイオリン協奏曲第1番、ラロ スペイン交響曲
プレミエ60101DF
パガニーニ ヴァイオリン協奏曲第1番
ラロ スペイン交響曲
ジノ・フランチェスカッティ(ヴァイオリン)
ジョージ・セル指揮クリーヴランド管弦楽団
ディミトリ・ミトロプーロス指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
1959年10月29日、クリーヴランド・セヴェランス・ホール
1955年4月3日、ニューヨーク・カーネギー・ホール
モノラル ライブ
※名手フランチェスカッティの「十八番」(おはこ)といえるパガニーニとラロのライブ。パガニーニは、放送用ではなくホールまたはオーケストラの保存用音源と思われ、オリジナルの状態は「とりあえず記録しました」という水準で、1959年のアメリカ録音としてはやや物足りない煤けた音質。録音済みテープを再利用して上書きしたらしく、消去が不十分で以前に記録した音声(音楽?)が聞こえる箇所もあった。ディスク化に当たっては、周波数バランスの改善などにより、独奏ヴァイオリンの輝かしい音色を蘇らせ、消去不十分な古い音声については大半は除去、鑑賞にほとんど支障がない状態とすることができ、音質改善後は、当時の聴衆の熱狂が理解できるような十分鑑賞に堪える状態となった。ラロはパガニーニよりも4年古いが、こちらは、おそらく放送局によるラジオ放送用録音が音源。オリジナルの音質はパガニーニよりも良好だが、独奏ヴァイオリンに対してオーケストラがやや録音レベルが高くバランスが悪かった(ミトロプーロスがオーケストラを鳴らしすぎる反面、フランチェスカッティの音が元々小さいことも原因だ)。ディスク化に当たっては、両者の音量バランスを調整したほか、古い録音テープに付きもののヒスノイズの低減等を行った結果、こちらも十分鑑賞に堪える状態とすることが出来た。
フランチェスカッティは、前述のようにパガニーニやラロ、サン=サーンスなどラテン系作品の演奏で評価が高く、米コロンビアに録音したレコードは歴史的名盤として名高い。しかし、それらの曲についてのライブや放送録音の復刻は意外に少なく、却ってベートーヴェンやブラームスの協奏曲などが複数以上CD化されている点は若干疑問に思える。そこで1939年から1975年まで計80公演と、最も多く共演したと思われるニューヨーク・フィルハーモニック(NYP)の資料を見ると、1939~1940年シーズンのNYPデビューの学生向け公演はパガニーニであり、1941年から1943年にかけてはラロを4公演取り上げているものの、デビュー公演に次ぐ定期公演ではブラームスを2回演奏、その後もチャイコフスキーやメンデルスゾーン、ベートーヴェンなど協奏曲のスタンダード・レパートリーを多岐にわたって演奏。80公演中パガニーニは5公演、ラロは7公演しか取り上げておらず、しかもパガニーニは1959年夏のスタジアム・コンサート、ラロは1957年の定期公演が最後の演奏機会となっており、レコードと実演の印象が大きく異なる典型かもしれない。
当ディスクのパガニーニは、セル/クリーヴランド管の定期公演のライブ録音(2回公演の1日目)。フランチェスカッティの全盛期は1940~1950年代と言われ、当ディスクの演奏はその後期に当たるが、フランチェスカッティは「人々はレコードで私の最高の演奏を知っている。実演でも最高の演奏を行わなければならない」と語っており、確かに全盛期そのままの演奏を繰り広げている。普段はセル指揮の元で「芸術的」な演奏に親しんでいるはずのクリーヴランドの聴衆だが、その熱狂ぶりはものすごく第1楽章終了後に早くも拍手や歓声が上がっている。1940年代~1950年代初頭のアメリカでは協奏曲の第1楽章終了後によく見られた光景だが、1959年という時期では異例と思われる。
ちなみにパガニーニとセルというまったく異質に思える組み合わせも面白い。ほとんど解釈の余地が入らない単純なオーケストレーションの伴奏をセルはどのように評価していたのだろうか。演奏プログラム決定の全権を握っていたセル自身が曲目を選定したことは間違いなく、大衆受けする曲目にも目を配る点は、芸術至上主義ではない経営的?視点によるものかもしれない。また、セルとフランチェスカッティという組み合わせも、それぞれ音楽の方向性が異なるように思えるが、意外にもクリーヴランド管の定期では1947年以来(これもパガニーニだった)、1968年までほぼ2~3年おきに10回・計20公演で共演。曲目もバッハからベートーヴェン、メンデルスゾーン、サン=サーンス、ウォルトンと様々で、セルがフランチェスカッティの音楽性を評価していた証と言える。米コロンビアのレコーディングにおける度々の共演も、単に契約や会社の都合で実現した訳ではなかったのだ。フランチェスカッティの特徴として鮮やかな技巧と美音ばかりが強調されるが、演奏自体はオーソドックスで誇張や恣意的な解釈を行わず、世代的にも新即物主義が主流だった時代背景がある。セルとの共通点はこの辺りにあるのだろう。
一方、ラロは1955年というまさしく全盛期の録音。4月2日・3日2回公演の2日目で午後2時半からのマチネー。ただし、3日はスペイン交響曲の後にシャブリエの喜歌劇「いやいやながらの王様」から「ポーランドの祭り」が演奏されたが、2日はシャブリエの代わりに、スペイン交響曲の前にショーソンの詩曲が演奏された。完全主義者のフランチェスカッティが、2日続けて大曲2曲の演奏は困難と判断したのかもしれない。
1950年代中期は、フランチェスカッティが最も多くNYPと共演した時期であり、1954~1956年にかけて8回も登場している。定期演奏会は同一プログラム2回公演とされているから、1シーズンに別プログラムで複数回登場した年もあったことになり、当時の人気の高さを物語る。指揮者は夏のスタジアムコンサートを除き、すべて当時のNYP首席指揮者だったミトロプーロスだが、前年に同じくミトロプーロス/NYPのバックでメンデルスゾーンとチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲をスタジオ録音し、さらに2年後には同じコンビで当ディスクと同じスペイン交響曲をスタジオ録音。いずれも歴史的名盤として評価されている。ちなみに1957年2月21・22日の定期公演でミトロプーロスとスペイン交響曲を演奏。2か月後の4月22日にレコーディングを行っている(2月の公演はリハーサルを兼ねている)。おそらく当ディスクの1955年の演奏が2年後のレコーディング計画のきっかけになったと思われる。
当時、主にアメリカで活動していたヴァイオリニストの評価は、何よりもハイフェッツが第一人者であり、アウアー同門のミルシテイン、そしてメニューイン、スターン、シゲティなどが競いあい、当録音の半年後11月にはオイストラフがアメリカを初訪問、センセーショナルなデビュー公演を行っている。それぞれ出身は異なるものの、いずれもロシア・東欧・ユダヤ系であり、そのような中では、パガニーニ直系でイタリア=フランス系のフランチェスカッティは異彩を放っており、独自の存在感を発揮していたと言える(もう一人の偉大な例外はユダヤ系だがウィーン出身のエリカ・モリーニだ)。
フランチェスカッティは、当ディスクのほかにパガニーニのヴァイオリン協奏曲第1番を1950年米コロンビアにスタジオ録音したほか、1951年にライブ録音していた。またラロのスペイン交響曲を1946年仏コロンビアにスタジオ録音したほか、上記のように1957年米コロンビアにスタジオ録音していた。

●フランチェスカッティ/ワルターの貴重録音 音質に問題あり
メンデルスゾーン ブルッフ、ヴァイオリン協奏曲 1947年・1945年ライブ
プレミエ60102DF
メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲
ブルッフ ヴァイオリン協奏曲第1番
ジノ・フランチェスカッティ(ヴァイオリン)
ブルーノ・ワルター指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
フランク・ブラック指揮NBC交響楽団
1947年3月9日、ニューヨーク・カーネギー・ホール
1945年4月29日、ニューヨーク・ラジオ・シティ・スタジオ
モノラル ライブ
※名手フランチェスカッティ得意のメンデルスゾーンとブルッフのライブ。ブルーノ・ワルター指揮ニューヨーク・フィル(NYP)と共演したメンデルスゾーンは、アメリカ人コレクター所有のテープからのディスク化。非常に珍しい音源で、海外ではLP・CD化されておらず、40年ほど前に日本ワルター協会が製作したLPが唯一と思われる。ただ、名演ではあるものの残念ながら音質が極めて劣悪で一般市販できる状態ではなく、そのため今日までLP・CDの再発売が見送られてきた。オリジナル音源はアセテート・ディスクで、エアチェックと思われるが、意外に音質が良好な部分もあり、ホール備え付けのマイクラインから直接レコーダーに録音された可能性もある。また78回転SP盤のような周期的ノイズが入り、3~4分程度で音質に変化があることから、ディスク1枚で3~4分録音できる78回転のレコーダーを使用したようだ。当時、アメリカのラジオ放送局では20分程度録音できる長時間ディスク・レコーダーを使用しており、78回転のレコーダーは家庭用もしくは業務用としては旧式化していたことから、当録音は、エアチェックではない場合は、放送用の音源ではなく、ホールまたはオーケストラ関係者が記録・保存用に録音したものと推定される。
アセテート・ディスクは耐摩耗性が低く、再生を繰り返すとノイズが急速に増えていく。また経年変化にも弱く、保存状態が悪いと表面のアセテートのコーティングがはがれて再生不能となったり大きなノイズが発生する。当録音の場合、第1楽章の途中までスクラッチノイズが非常に多く、その後はスクラッチノイズが減り急速に音質が良くなるが、所々耳障りな周期的ノイズが数秒間ずつ入る。おそらく第1楽章前半を繰り返し再生し、その後は良好とは言えない環境下に放置され劣化が進んだのだろう。
音質が劣悪とはいうものの、第2楽章の一部などはノイズもなく、1947年という年代を考慮するとかなり優秀な音質を保っている。問題はディスク毎のコンディションの差が大きく、良好な状態が若干続いた後、突然盛大なノイズが発生するなど音質が一定しないことにある。
今回ディスク化に当たっては、ノイズを完全に除去することは技術的に可能ではあるものの、完全除去によりヴァイオリンの重要な周波数帯域にも悪影響を及ぼし、音質劣化の恐れがあることから、フィルター等による周波数帯域を制限する処置は行わず、イコライジングやソフトウェア等でノイズ低減と刺激的なノイズ成分の除去のみを目指した。また併せて録音レベルやピッチの変動・音揺れ、第2楽章の音飛びなども改善した。
結果として、オリジナルの状態からは大幅な改善となったが、当然ながら、依然としてノイズレスの良好な音質とは言い難い。しかし、ノイズの多いアコースティック録音の78回転SP盤や第二次世界大戦中のメンゲルベルクのライブ録音(フィリップス発売以外のもの)、ジャンルはやや異なるが、1950年代のナポリ・サン・カルロ歌劇場やヴェローナ野外歌劇場のライブ盤などを聴いた経験のあるリスナーであれば、十分演奏を楽しむことが出来るであろう。
一方のブルッフはNBCの放送録音で、幸いにも当時の水準以上の音質。アセテート・ディスク録音ではあるもののスクラッチノイズも極小で、オーケストラと独奏ヴァイオリンの音量バランスのみ調整を行ったが、音楽をストレスなく鑑賞できる。ちなみに会場のラジオ・シティ・スタジオとは、トスカニーニの録音で有名な8Hスタジオを含むNBC放送スタジオの総称であり、当録音のスタジオ名は不明だが、オーケストラを収容できるスタジオは限られていたから8Hまたは3Aスタジオだろう。
メンデルスゾーンは1947年のNYP定期演奏会のライブで午後3時からのマチネー。3月6日と7日の公演に続く3回目の公演にあたるが、6・7日のプログラムは、前半にベートーヴェン「プロメテウスの創造物」序曲、ハイドンの交響曲第92番「オックスフォード」、メンデルスゾーン、休憩を挟んでブラームスの交響曲第4番だったのに対し、当録音の9日は、コロンビア・ネットワークによる全米向けラジオ放送用にプログラムが組まれ、前半にハイドンの代わりにブラームスの交響曲第4番、後半にメンデルスゾーンという、やや変則的な構成となっている、ハイドンを省略したのは放送時間の都合だろうが、メンデルスゾーンを最後に置いたのは、曲目のポピュラリティによるものか、フランチェスカッティの当時の人気を示しているのかもしれない。
フランチェスカッティは当時44歳。音楽的にも技術的にもまさに絶頂期で、劣悪な録音でもその美音が聴き取れ、早めのテンポ設定にもかかわらず、余裕を持って自在な演奏を繰り広げている。ブルーノ・ワルターは温厚な人柄だが共演者には注文が多く、フランチェスカッティ自身も「やりにくいことがあった」と証言している。しかし当ディスクの演奏ではそのようなことは微塵も感じさせず、十全にフランチェスカッティの音楽を表現しており、後年のスタジオ録音を凌ぐベストパフォーマンスと言っても過言ではない。ちなみに複数残されているメンデルスゾーンの協奏曲の録音としては最も早い時期のものでもある。
一方のブルッフはメンデルスゾーンより2年前の放送録音。相変わらずの美音と鮮やかなテクニックで魅了させる。指揮のフランク・ブラックは当時NBC放送のミュージック・ディレクター。アメリカの埋もれた作曲家の作品紹介に尽力したことでも知られるが、NBC響の結成と運営に関わり、数回指揮台にも上がったが、そのうちの1回が当録音に当たる。ちなみにブルッフの協奏曲は、元々第1楽章と第2楽章はアタッカで切れ目なくつながっているが、当演奏では2楽章と3楽章についても、2楽章のコーダを引き延ばして連続して演奏している。放送のために、楽章間に聴衆に咳などをさせない工夫だろうか。
ジノ・フランチェスカッティは当ディスク以外に、メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲を1954年と1961年米コロンビアにスタジオ録音したほか、1953年と1972年にライブ録音していた。また、ブルッフのヴァイオリン協奏曲第1番を1952年と1962年に米コロンビアにスタジオ録音したほか、1952年に第3楽章のみをライブ録音していた。

●フランチェスカッティ 優秀録音1958・1956年ライブ
チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲、プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲第2番
プレミエ60103DF
チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲
プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲第2番
ジノ・フランチェスカッティ(ヴァイオリン)
シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団
1958年7月27日、タングルウッド・ミュージック・シェード
1956年4月13日、ボストン・シンフォニー・ホール
ステレオ/モノラル ライブ
※名手フランチェスカッティによるチャイコフスキーとプロコフィエフのライブ。いずれもミュンシュ指揮ボストン交響楽団(BSO)との共演で、チャイコフスキーは幸いなことにステレオ録音。BSOのコンサート中継を担当した地元ボストンの放送局WGBH(Waltham
Great Blue
Hill)は、非常に早期から実験的にステレオ録音・放送を開始しており、当録音はおそらくその最初期の例。夏の音楽祭バークシャー・フェスティバルにおける録音で、客席の後方に壁がない半開放型のホールのため、音響条件は万全とは言えないものの音質は良好で、左右チャンネルが分離した立派なステレオとなっている、やや定位が不安定だったり、オーケストラがレベルオーバー気味(ミュンシュのフォルティッシモが大きすぎるのだ)、ソロ・ヴァイオリンが中央左に寄っているなど(これはステージにおける実際の立ち位置なので仕方がない)、やや不自然な箇所もなくはないが、十分鑑賞に堪えるものとなっている。なお、同じ音源が海外レーベルでCD化されているが、おそらくダビングを重ねて劣化した音源を使用しているらしく、ヒスやハムノイズが過大、左右チャンネルが逆転、高音域が失われてヴァイオリンの輝きが不足するなど歪みが多く、ダイナミックレンジを補正していないため、ソロ・ヴァイオリンの音量が小さい反面、オーケストラの強音が大きすぎするなど問題が多い音質であった。当ディスクの音源は、アメリカ人コレクターの個人コレクションだが、良好な受信状態でエアチェックされたオリジナルに近い世代のテープと思われ、極めて状態が良く、家庭における鑑賞を考慮してダイナミックレンジを調整したのみ。第1楽章終了後は盛大な拍手が入り、夏の音楽祭のリラックスした雰囲気が漂うが、演奏中の会場ノイズは少なく、聴衆のマナーの良さを感じる。
一方のプロコフィエフもモノラルながら音質良好で年代の水準を上回る。ボストン・シンフォニー・ホールの音響の良さも貢献しているようだ。こちらもエアチェック録音と思われるが、ノイズレスで周波数レンジも広く、放送局のオリジナル音源だと言われれば信じてしまいそうだ。鑑賞する上で全く不満はないだろう。会場ノイズも極小。
チャイコフスキーは先に述べたように、夏の音楽祭バークシャー・フェスティバルにおけるライブ。午後2時半開演で、前半にバルトークの「弦楽器、打楽器、チェレスタのための音楽」(録音は残されているらしいがミュンシュの大注目レパートリーだ)、ラヴェルの「ダフニスとクロエ」第2組曲、後半にチャイコフスキーというプログラム。定期演奏会と異なる音楽祭らしく大衆向けの曲順だが、フランチェスカッティの当時の人気の高さもあっただろう。なお、前日の26日午前10時にも、一部曲目は異なるもののオープンリハーサルが行われた。BSOにおけるフランチェスカッティのチャイコフスキーは大好評だったらしく、1956年8月のバークシャー・フェスティバルから、1957年10・11月の定期演奏会、当録音の1958年まで、オープンリハーサルを含めると続けて7回も演奏している。
プロコフィエフは、本拠地ボストン・シンフォニー・ホールにおける定期演奏会から。4月13日と14日の2回公演の1日目で午後2時15分開演のマチネー。プログラムは、前半にチャイコフスキー「フランチェスカ・ダ・リミニ」とプロコフィエフ、後半もフランチェスカッティ(とBSOのチェロ主席サミュエル・メイズ)が加わったブラームスのヴァイオリンとチェロの二重協奏曲という、まさにフランチェスカッティ特集とも言うべきもの。
フランチェスカッティとBSOは、1944年10月定期公演で初共演。当時はクーセヴィツキーが常任だったが、公演の指揮は副指揮者リチャード・バーギン(バージン)でなぜか格下扱い。曲目がパガニーニということで、クーセヴィツキーが地味な伴奏に徹するのを嫌ったのかもしれない。その後ミュンシュ常任時代を迎えると共演回数が急増。1950年3・4月の定期演奏会では、バッハおよびサン=サーンスと協奏曲2曲を演奏。その後1958年までに15回も共演し、指揮はすべてミュンシュであった。ミュンシュ時代はBSOにフランス系ソリストの招聘が増えたが、フランチェスカッティは多い方だった(最も多かったのはピアニストのニコール・アンリオ=シュヴァイツァーだろう)。フランチェスカッティ自身、ミュンシュとの共演は「何か起こるか分からないので面白かった」と語っており、ミュンシュが得意とした打ち合わせにない即興的な指揮を楽しんでいたようだ。
フランチェスカッティは、当ディスク以外にチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲を1954年と1965年米コロンビアにスタジオ録音したほか、1943年と1970年にライブ録音していた。また、プロコフィエフのヴァイオリン協奏曲を1952年米コロンビアにスタジオ録音していた。

●フランチェスカッティ/ワルターの貴重録音
ブラームス、ヴァイオリン協奏曲、二重協奏曲 1951年・1956年ライブ
プレミエ60104DF
ブラームス ヴァイオリン協奏曲、ヴァイオリンとチェロの二重協奏曲
ジノ・フランチェスカッティ(ヴァイオリン)
サミュエル・メイズ(チェロ)
ブルーノ・ワルター指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団
1951年1月21日、ニューヨーク・カーネギー・ホール
1956年4月13日、ボストン・シンフォニー・ホール
モノラル ライブ
※名手フランチェスカッティによるブラームス2作品のライブ。ブルーノ・ワルター指揮ニューヨーク・フィル(NYP)と共演したヴァイオリン協奏曲はアメリカ人コレクター所有のテープからのディスク化で、既発売プレミエ60102DFのメンデルスゾーンと同様に海外ではLP・CD化されておらず、40年ほど前に日本ワルター協会が製作したLPが唯一と思われる。ただし、メンデルスゾーンと同じく音質が劣悪で一般市販できる状態ではなく、今日までLP・CDの再発売が見送られてきた。オリジナル音源はエアチェックと思われるが、メンデルスゾーンとは異なり、元々はテープ録音され、楽章別にテープからアセテート・ディスクにダビングされて保存されたらしい(当時は高価だったテープを再利用したのだろう)。オリジナルの音質は楽章ごとに異なり、第1楽章は高音域が欠落してこもった鈍い音質。第3楽章は盛大なスクラッチノイズが入り、第2楽章のみ音の崩れや歪みがあるものの一応の水準にあり音楽として聴けるという状態だった。なお、日本ワルター協会盤LPは、第1楽章序奏部に音切れ・がさつきノイズがあったが、当音源では、音質は悪いもののそのような現象はない。当ディスクはアセテート・ディスクから再ダビングしたテープが音源となっているので、アセテート・ディスクが劣化する以前の、日本ワルター協会盤より早い時期にダビングされたものと思われる。
ディスク化に当たっては、第1楽章は高音域の復活によるソロ・ヴァイオリンの明確化と周波数レンジ拡大、副作用として生じるアセテート・ディスク由来のスクラッチノイズ低減、第3楽章は何よりもノイズ低減、さらに全体として、オーケストラに対してソロ・ヴァイオリンの音量が小さいため、音量バランスの修正等を行った。音質を損ねない範囲でノイズをほとんど低減できたが、ヴァイオリンの周波数帯域に悪影響を及ぼすため、ノイズを完全に除去することは避けた。また、一部の瞬間的な音の崩れは可能な範囲で修復した。
結果的に、依然として一部の瑕疵は残るもののオリジナルの音源からは大幅な改善となり、1950年前後の録音水準にようやく達することとなった。元々テープ録音ということもあり、上記のメンデルスゾーンより情報量が多く、音質改善の余地が大きかったことが幸いした。この時代のライブ録音に慣れたリスナーであれば問題なく演奏を楽しめるであろう。
一方の二重協奏曲は、1956年という年代の水準を大きく上回る高音質。こちらもエアチェックだが、放送局のマスターをダイレクトコピーしたと言われても疑わないほど。よほど好条件の受信環境の元で良質の機材を使用して録音したものと思われ、一般のリスナーではなく専門家による録音だろう。ボストン・シンフォニー・ホールにおける録音としては、残響がやや乏しい感はあるが、これは会場のマイクセッティングの問題と思われる。
協奏曲は、1951年1~2月に行われたワルター/NYPによる定期演奏会におけるブラームス・チクルス(サイクル)の中の1曲。チクルスでは、交響曲4曲のほか、協奏曲4曲と主要な管弦楽曲が演奏された。ちなみに1935年にも当時NYP常任だったトスカニーニが同様にブラームス・チクルスを実施している。こちらはセレナードや合唱曲も含むさらに大規模なものだったが、ワルツ集「愛の歌」(ピアノ連弾伴奏)や合唱曲4曲(ホルン、ハープ、ファゴット伴奏)が加わるなど、オーケストラの定期演奏会としてはやや散漫な“19世紀的プログラム”で1935年という時代を感じる。ワルターの場合は規模が縮小されており、こちらの方が今日の演奏会のイメージに近い。なお、同チクルス第4回目、2月11日公演の交響曲第4番はプレミエ60056DFでディスク化されている。
フランチェスカッティが登場したのはチクルス第1回。18~21日の4回公演で当ディスクの録音は4日目に当たり、午後2時45分開演のマチネー。前半に「悲劇的序曲」と協奏曲、後半に交響曲第1番というオーソドックスなプログラムで、おそらくコロンビア・ネットワークによるラジオ中継が行われたと思われる。フランチェスカッティの得意のレパートリーというと、パガニーニを始め、ラロやサン=サーンスなどラテン系作品がまず第一に挙げられ、LPがベストセラーとなったメンデルスゾーンとチャイコフスキーの協奏曲が言及されることが多いが、NYPなどの演奏会記録を見ると、実はベートーヴェンやブラームスの協奏曲がかなり多いことが分かる。1939年から1975年まで計80公演と、最も多く共演したと思われるNYPの資料を見ると、ブラームスは19公演と最も多く、パガニーニ(第1番)は7公演、ラロ(スペイン交響曲)は5公演しか取り上げておらず、しかもパガニーニは1959年夏のスタジアム・コンサート、ラロは1957年の定期公演が最後の演奏機会となる一方、ブラームスはキャリア後期の1967年1月定期公演が最後となっており、本人がブラームスを得意とし、しかもニューヨークの聴衆から高く評価されていたことが分かる。NYP(ワルター?)がブラームス・チクルスのソリストとして、(同様にブラームスを得意とした)ハイフェッツやシゲティではなく、フランチェスカッティを選んだことは当然のことだったと言える。
フランチェスカッティの全盛期は1950年代と言われ、1960年代に入ると技術的な衰えよりも、ヴァイオリンの音色が細身になっていったように感じる。本人が時代の趨勢に併せて、敢えて美音を抑えたとも考えられるが、フランチェスカッティの本領は何と言っても鮮やかなテクニックと魅惑的な美音にあり、当ディスクの演奏はまさしく全盛期の姿を捉えたものであり、音質改善により、ようやく本来の演奏の姿を蘇らせることが出来たと言える。
一方のヴァイオリンとチェロの二重協奏曲は、ミュンシュ指揮ボストン交響楽団(BSO)との共演で、本拠地ボストン・シンフォニー・ホールにおける定期演奏会から。4月13日と14日の2回公演の1日目で午後2時15分開演のマチネー。プログラムは、前半にチャイコフスキー「フランチェスカ・ダ・リミニ」とフランチェスカッティ独奏でプロコフィエフのヴァイオリン協奏曲第2番、後半はフランチェスカッティにBSOのチェロ主席サミュエル・メイズが加わったブラームスのヴァイオリンとチェロの二重協奏曲という、まさにフランチェスカッティ特集とも言うべきもので、プロコフィエフはプレミエ60103DFでディスク化済みである。フランチェスカッティは、二重協奏曲という渋い作品の演奏機会が意外に多かったらしく、スタジオ録音のほか2種のライブ録音が残っている。ここでは持ち前の美音を抑え気味に、アンサンブルに徹した演奏を繰り広げている。ロベール・カサドシュなどとの室内楽録音でも知られるように、柔軟性に富んだ演奏家だったことが分かる。二重協奏曲は、交響曲の構想を転用して協奏曲に改作したせいか、晦渋であるとも言われるが、ミュンシュのラテン的とも言える快活な演奏も貢献して、通常よりも魅力的な作品に聴こえる。
フランチェスカッティは、当ディスク以外にブラームスのヴァイオリン協奏曲を1956年と1961年米コロンビアにスタジオ録音したほか、1958年・1969年・1974年にライブ録音していた。また、二重協奏曲を1959年米コロンビアにスタジオ録音したほか、1955年にライブ録音していた。

●フリッツ・ライナー/シカゴ響 ライブ
メンデルスゾーン「イタリア」、シューマン 交響曲第2番
1954年・1957年ライブ
プレミエ60105DF
メンデルスゾーン 交響曲第4番「イタリア」
シューマン 交響曲第2番
フリッツ・ライナー指揮シカゴ交響楽団
1954年2月10日、シカゴWGNスタジオ
1957年10月31日、シカゴ・オーケストラ・ホール
モノラル ライブ
※フリッツ・ライナーとシカゴ響によるロマン派の交響曲2作品。メンデルスゾーンは、シカゴの放送局WGN(World's Greatest
Newspaper)スタジオにおける、聴衆を入れたテレビ放送用ライブ(番組名Hour of
Music)から。ビデオテープが広く普及する以前の時代でもあり、映像が残っているかは不明(当時はテレビ画面をフィルム撮影して保存した例もあった)。当ディスクの音源はビデオテープではなく、テレビ放送の音声のみをエアチェックしたオーディオテープで、おそらく音質は当時のビデオテープよりも優れていたと思われる。ただし、オリジナルの音質は、コンサートホールよりも室内容積が小さく、音楽専用ではない放送スタジオ内の収録のため、残響は短めで歪みもあり、テレビ放送特有?のハムノイズがあるなど、音楽を楽しめるというレベルではなかった。ディスク化に当たっては、ハムノイズの低減、イコライジングによる歪みの解消(周波数特性の改善)等々を行った結果、1950年代中期の水準を一応クリアできる音質となった。マイクセッティングの自由度が高いスタジオ収録のため情報量には不足がなく、改善の余地が大きいことが幸いした。なお、当ディスクの約1か月後の3月24日にもライナーはWGNで収録を行っており、当日のベートーヴェン交響曲第7番は当レーベルのプレミエ60071DFで発売済みである(こちらは録画が残っている)。
一方のシューマンは本拠地シカゴ・オーケストラ・ホールにおける定期演奏会のライブから。ラジオ放送のエアチェックだが、こちらは音楽専用ホールによる収録で、メンデルスゾーンよりも3年後という技術的進歩もあり(当時はわずか3年でも技術発展は急激だった)、格段に優れた音質。シカゴのオーケストラ・ホールは残響が乏しいデッドなホールとして知られているが、さすがにテレビスタジオよりも「音楽的」な響きがする。1960年代中期、モノラル末期のラジオ放送録音と同等以上の音質で、鑑賞する上で全く不満がない。
なお、シカゴ響のコンサート中継は、地元ラジオ局WFMTまたはニューヨークのWBAI-FMが長年担当しているが、ライナー時代のライブ音源の多くは、会場ノイズが異常に少ない、明らかな演奏ミスがないなど、放送前に編集されているようだ。ヴィルヘルム・シュヒター常任時代のNHK交響楽団でもシュヒターの指示により、数回公演の録音テープから演奏ミスを差し替えるなど編集して放送したという事実があり、当ディスクのシューマンも、ライナーの指示によるものかは不明だが完成度が高く、当時このままLPとして発売しても不思議ではないほど。ただし、メンデルスゾーンに比べて弱音が小さすぎ、強音が大きすぎるという問題があったため、家庭内の鑑賞を考慮して、若干ダイナミックレンジをわずかに圧縮している。
メンデルスゾーンのスタジオ収録当日は、ほかにブラームス「ハイドン変奏曲」、ディーリアス「イルメリン」前奏曲、ラヴェル「序奏とアレグロ」、コダーイ「ガランタ舞曲」も演奏され、コダーイは当レーベルのプレミエ60107DFで発売済みである。やや「ごった煮」的ではあるものの、定期演奏会のようなプログラム。ロマン派と近代作品で個別の放送を予定していたのかもしれない。近代作品が多いのはライナーの希望もあっただろう。ライナーとシカゴ響は、1954年3月6日に初のレコーディング(米RCA、R・シュトラウス「英雄の生涯」)を行っているが、WGNの収録は正式なスタジオ録音よりも早かったことになる。
メンデルスゾーン「イタリア」は、ライナーにとって比較的珍しいレパートリー。シカゴ響在任時代は、1953年11月の2公演、1959年10月の2公演しか取り上げておらず、当ディスクの演奏は1953年公演の「追加公演」に当たるものだろう。ライナーの芸風にはふさわしい作品であり、不人気作品とも言えないので、スタジオ録音を残さなかったのは不思議だ。
実は、メンデルスゾーンなどが録音された1954年2月10日は、ブルーノ・ワルターによる定期演奏会の狭間に当たり、前日の9日はハイドン交響曲第88番とベルリオーズ「幻想交響曲」ほかが、翌11日と12日は、ソプラノのヒルデ・ギューデンによる歌曲6曲とブルックナー交響曲第7番ほかという、重量級プログラムが演奏された。11日の演奏会のリハーサルをいつ設定したのか不明だが、テレビ収録もかなり長時間だったと想像され、メンバーの一部入れ替えはあるにせよ、プロオーケストラの仕事のハードさには恐れ入る。
シューマンは1957年10月31日と11月1日の定期演奏会2回公演のうち1回目のライブ。当日は、前半にワーグナー「ファウスト序曲」とシューマン。後半にアメリカの作曲家カール・エッパート(1882~1961)のsymphonic
fantasy for orchestra : a symphony of the city,
op.50から“Speed”(シカゴ響初演)、R・シュトラウス「ティル・オイゲンシュピーゲル」というプログラム。“Speed”がどの程度の規模の作品か不明だが、連作交響曲?の一部と思われ、前半より後半が軽いプログラミングとなっている。今日とは異なる前半が長く(重く)、後半が短い(軽い)構成は、第二次世界大戦前の欧米ではよく見られた。フルトヴェングラーとベルリン・フィルのプログラムでも、前半がブルックナーの交響曲第8番、後半がリストのピアノ協奏曲第1番という例があり、独奏のホロヴィッツ(!)は待ち時間の長さにうんざりしたというエピソードも残っている。ライナーも古い伝統を引きずっていたのだろう。
ライナーとシカゴ響にとって、シューマンの交響曲第2番もかなり珍しいレパートリーで、当ディスクの公演以外には1955年10月の2公演しか記録に見当たらない。シューマンの交響曲第2番は、日本においてはシューマンの交響曲で最も人気のない作品と言っても過言ではないが、欧米では、ジョージ・セルが海外ツアーでも取り上げるなど、それなりに評価されていたようだ。ライナーは演奏機会こそ少なかったものの、散漫になりがちな同作品をさすがにうまくまとめている。
ライナーは、メンデルスゾーン「イタリア」とシューマンの交響曲第2番をブラームスのスタジオ録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音である。

●フリッツ・ライナー/シカゴ響 ライブ ワーグナー名曲集
1958・1960・1962年ライブ
プレミエ60106DF
ワーグナー
「ローエングリン」第1幕への前奏曲
「トリスタンとイゾルデ」第1幕への前奏曲と愛の死
「パルシファル」聖金曜日の奇蹟
「リエンツィ」序曲
「ジークフリート牧歌」
フリッツ・ライナー指揮シカゴ交響楽団
1960年3月25日、1958年3月27日、シカゴ・オーケストラ・ホール
1962年1月31日、シカゴWGNスタジオ
モノラル/ステレオ ライブ
※フリッツ・ライナーとシカゴ響によるワーグナー名曲集。ローエングリンは1960年、トリスタン、パルシファル、リエンツィは1958年の定期演奏会のライブから。ジークフリート牧歌はシカゴの放送局WGN(World's
Greatest
Newspaper)スタジオにおける、聴衆を入れたテレビ放送用ライブで、これのみステレオ。いずれも当時の水準を上回る優秀な音質で、鑑賞上は全く不満がない。当然ながら、年代を追うごとに音にふくらみができて豊かになり、音質が良くなっているのが分かる。なお、シカゴ響のコンサート中継は、地元ラジオ局WFMTまたはニューヨークのWBI-FMが長年担当しているが、ライナー時代のライブ音源の多くは、会場ノイズが異常に少ない、明らかな演奏ミスがないなど、放送前に編集されていたようだ。拍手がカットされている場合も多く、レコード化を前提としたスタジオ(セッション)録音に遜色ない仕上がりとなっている。ただし、ローエングリン第1幕への前奏曲については、前半でライナー本人の鼻歌がかすかに聞こえ、こればかりはラジオ局もカットできなかった模様。冷徹な性格で敵も多かったライナーだが、音楽の解釈は意外にもロマンチックで、その素顔を覗かせているようだ。ジークフリート牧歌はやや不思議な録音で、当時テレビではステレオ放送は実施されておらず、実験的にステレオ録音可能なビデオレコーダーを使用したか、音声のみステレオレコーダーで別録りした可能性もある。音響効果が悪いスタジオ収録のハンディキャップは感じないが、小編成であるためだろう。これは録画が残っている可能性が高い。なお、1958年と1960年の録音は若干リミッターがかかっていたため、ダイナミックレンジを若干広げ、1962年の録音は逆にダイナミックレンジが広すぎたため、わずかに圧縮した。
1960年の定期演奏会は、前半にローエングリン、アメリカの作曲家アンソニー・ドナート(1909~1990)のシンフォニエッタ第2番(シカゴ響初演)、ハイドンの協奏交響曲、後半にサティ(ドビュッシー編曲)の「2つのジムノペディ」、ラヴェル「ラ・ヴァルス」という、なかなか意欲的ではあるものの少々まとまりに欠ける感もあるプログラム。後半はフランス近代作品でまとまっているが、前半は時代を行ったり来たり、19世紀から20世紀前半まで主流だった統一感を考慮しないプログラム編成の名残だろう。1958年の定期演奏会は、前半にハイドンの交響曲第95番、ラヴェルのピアノ協奏曲(独奏ザデル・スコロフスキー)、後半にトリスタン、パルシファル、リエンツィという、1960年よりは多少まともなプログラム。1962年のテレビ収録では、同時にヴィヴァルディ「四季」から「春」「冬」も演奏された。
ライナーは元来ヨーロッパ各地の歌劇場で修行を積んだオペラ指揮者であり、1922年に渡米後も、全米各地やヨーロッパで多くのオペラ作品を手がけていた。1955年ウィーン国立歌劇場再開記念公演でも「マイスタージンガー」を指揮し、1963年の死去直前にもメトロポリタン歌劇場で「神々の黄昏」の公演準備を行うなど、ワーグナーの諸作品は自家薬籠中の物だったろう。ただし、ワーグナーをまとめてコンサートで取り上げる機会は少なく、1956年11月、1959年4月のオール・ワーグナー・プログラムと、3曲取り上げた当ディスクの1958年3月・4月、1963年3月くらいだった。ワーグナーの本質を知るにはオペラ全曲を聴くべきという考えだったかも知れない。
ライナーは歌劇全曲録音からの抜粋を除き、ローエングリン第1幕への前奏曲を1941年ピッツバーグ響と米コロンビアにスタジオ録音したほか、リエンツィ序曲を1941年デトロイト響、1954年シカゴ響と放送録音していたが、その他は当ディスクが現在確認されている唯一の録音と思われる。

●フリッツ・ライナー/シカゴ響 ライブ
プロコフィエフ 交響曲第5番、コダーイ ガランタ舞曲
1958・1954年ライブ
プレミエ60107DF
プロコフィエフ 交響曲第5番
コダーイ ガランタ舞曲
フリッツ・ライナー指揮シカゴ交響楽団
1958年2月27日、シカゴ・オーケストラ・ホール
1954年2月10日、シカゴWGNスタジオ
モノラル ライブ
※フリッツ・ライナーとシカゴ響(CSO)による近代2作品のライブ。プロコフィエフは定期演奏会のライブから。ラジオ放送のエアチェックで、1958年のCSOのライブ録音としては標準的な音質。ということは当時としてはかなりの高水準で、特に派手さはないがバランスが良く、解像度も良好、モノラルながら鑑賞する上でのストレスは全くない。ただし弱音が小さすぎ強音が大きすぎたため、ダイナミックレンジをわずかに圧縮すると共にヒスノイズを若干低減している。例によって、放送のために地元ラジオ局WFMTまたはニューヨークのWBAI-FMが2日目の公演またはリハーサル録音?を利用して、演奏ミス修正や会場ノイズ除去などの編集を行っていると思われるが、終演後の拍手は入っている。
1954年のコダーイは、既発売プレミエ60105DFのメンデルスゾーンと同じ日に行われた地元テレビ局WGNによる放送用スタジオライブ。テレビ放送の音声のみを録音したエアチェックが音源と思われるが、なぜかメンデルスゾーンよりも音質が良く歪みもない。おそらく放送の合間にマイクセッティングを変更したのかも知れない。あいかわらず残響は短めだが、このような近代作品では違和感があまりない。ただしメンデルスゾーン同様にハムノイズが乗っており、ディスク化に当たっては若干低減を図った。いずれにしても十分鑑賞に堪える音質となっている。
1958年のプロコフィエフは、同年の4月1日録音という説もあるが、この日はコンサートは開催されておらず、直近は3月28日と4月3日でプログラムも異なる。2月27日は28日との2日公演の初日。この日のプログラムは、前半にロッシーニ「セビリアの理髪師」序曲(シカゴ響では驚きの初演!)、ソプラノのロバータ・ピーターズを迎えてモーツァルトの演奏会用アリア「あなたはいかなる苦しみか知らない」、続けてプロコフィエフ、後半にロバータ・ピーターズによるR・シュトラウスの管弦楽伴奏付き歌曲4曲、最後に同じくR・シュトラウス「サロメ」から「7つのヴェールの踊り」というもの。プロコフィエフだけ関連性が薄く異質な感じもするが、プログラムの統一感重視が主流となったのは1960年代以降と言われるから致し方ない面もある。トスカニーニなどはもっと奇妙な組み合わせでプログラムを組んでいた。
ライナーはCSOで多くの近現代作品を取り上げたが、プロコフィエフもその一人。交響曲第5番は、当ディスクの1958年と1954年10月に演奏したのみだったが、それ以外の作品、交響曲第1番、第7番、キージェ中尉、ロミオとジュリエット組曲、アレクサンドル・ネフスキーと主要曲をまんべんなく取り上げている。ただし、正式にレコーディングを残したのはキージェ中尉とアレクサンドル・ネフスキーのみで、交響曲(特に人気の第1番)が抜けているのは、レコード会社(RCA)の営業政策を考えると奇妙としか言いようがない。
コダーイは、ライナーが若き日に故国ハンガリーのリスト音楽院で学んだ時代の恩師。同じく恩師のバルトークと併せて作品の普及に尽力した。冷徹な性格で対人関係で軋轢を起こすことも多かったライナーだが、アメリカに亡命し経済的に困窮したバルトークを支援するなど、意外に義理堅いところもあったようだ。ただしCSO在任中コダーイ作品の演奏回数は意外に少なく、ガランタ舞曲は1953年12月公演のみ。ハーリ・ヤーノシュも1955年12月公演のみ。ハンガリー民謡「孔雀は飛んだ」による変奏曲は1959年10月と1960年2月公演の2回だった。
ライナーはプロコフィエフ交響曲第5番のスタジオ録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音と思われる。一方ガランタ舞曲は、当ディスク以外に1945年ピッツバーグ響と米コロンビアにスタジオ録音していた。

●フリッツ・ライナー/シカゴ響 ライブ
バルトーク ディヴェルティメント、シェーンベルク 浄められた夜
1957年ライブ
プレミエ60108DF
バルトーク 弦楽のためのディヴェルティメント
シェーンベルク 浄められた夜(弦楽合奏版)
ジョン・ウェイチャー、フランシス・エイコス(ヴァイオリン)
ミルトン・プリーヴス(ヴィオラ)、ヤーノシュ・シュタルケル(チェロ)
フリッツ・ライナー指揮シカゴ交響楽団
1954年2月21日、シカゴWGNスタジオ
1957年11月7日、シカゴ・オーケストラ・ホール
モノラル ライブ
※フリッツ・ライナーとシカゴ響(CSO)による近現代2作品のライブ。バルトークは地元テレビ局WGNによる放送用スタジオライブ。テレビ放送の音声のみを録音したエアチェックが音源と思われる。オリジナルの音質は、コンサートホールよりも室内容積が小さく、音楽専用ではない放送スタジオ内の収録のため、残響は短めで歪みもあり、テレビ放送特有?のハムノイズがあるなど若干荒れた感じの音質。ディスク化に当たっては、ハムノイズの低減、イコライジングによる歪みの解消(周波数特性の改善)等々の改善を行った。結果として、格別に優秀とは言えないが鑑賞に堪えられる音質となった。管楽器を含まない小編成の弦楽合奏であるため、改善が容易だったことも幸いした。
シェーンベルクは定期演奏会のライブから。ラジオ放送のエアチェックと思われるが、1957年とは思えない良好な音質。このままステレオ化すれば1960年代中期以降の録音として通用するレベル。良好な受信環境の元で良質な機材で録音したと思われる。バルトークを同じ録音年で、規模は異なるものの同様な弦楽合奏だが、音楽専用のコンサートホールの威力を感じる(それでも残響が短くデッドと批判されているが)。ディスク化に当たっては、オリジナル音源はラジオ放送用にリミッターがかけられていたため、ダイナミックレンジをわずかに広げる処理を行った。
バルトークは、ライナーが若き日に故国ハンガリーのリスト音楽院で学んだ時代の恩師。第二次世界大戦中、アメリカに亡命し経済的に困窮したバルトークに新作を依頼するなど、物心両面で支えた。CSO在任中も1953年から1962年まで毎シーズンバルトーク作品を取り上げ、ディヴェルティメントについても1957年2月21・22日と3月の定期で取り上げており、当ディスクの20日の演奏は、21日の演奏会のリハーサルも兼ねていたのだろう。ただ、21日録音という資料もあり、こちらが正しければ当日昼間にテレビ収録、夜に演奏会というスケジュールで、それほど不可能ではない。
なお、資料では4人の参加メンバーが記録されているが、この作品は第1、第2ヴァイオリン各6、ヴィオラ、チェロ各4、コントラバス2以上を必要する弦楽5部構成であり、主だったメンバー(有名人?)のみを記載したものであろう。このうち、当時ウェイチャーはコンサートマスター、エイコスは第2プリンシパル、プリーヴスとシュタルケルはそれぞれの主席だった。シュタルケルは翌年CSOを退団してソリスト(と教育活動)に転向したため、アンサンブル・メンバーとしては最後期にあたる貴重な録音。
1957年のシェーンベルクは、11月7日・8日2回公演の1日目。プログラムは、前半にウェーベルンの管弦楽のための6つの小品(CSOにおける初演)、シェーンベルク、後半にドヴォルザークの交響曲第9番「新世界より」というプログラム。難解作品とポピュラー作品という硬軟取り混ぜたもので(シェーンベルクはそれほど難解ではないが)、プログラム前半の聴衆に「入り」はどうだったか興味深い。
近現代作品を多く取り上げたライナーだが、シェーンベルクは例外で、当ディスクの1957年ただ1度のみ。CSO在任前のピッツバーグ響では「浄められた夜」を3回取り上げているから、意図して避けたわけではないだろう。ライナーとシェーンベルクは書簡をやりとりするような親密な関係だった。
ライナーはバルトーク「ディヴェルティメント」とシェーンベルク「浄められた夜」のスタジオ録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音と思われる。

●カザルス指揮 バッハ「マタイ受難曲」
1963年ニューヨーク・ライブ
プレミエ60109DF
バッハ マタイ受難曲 全曲
(ロバート・ショウ英訳版)
エルンスト・ヘフリガー(テノール、福音史家)
ウィリアム・ウォーフィールド(バス、イエス)、
アラ・バーベリアン(バス)[アリア]
モーリーン・フォレスター(アルト)
オルガ・イグレシアス(ソプラノ)
クリーヴランド管弦楽団合唱団員
(合唱指揮:ロバート・ショウ)
パブロ・カザルス指揮プエルト・リコ・カザルス音楽祭管弦楽団
1963年6月16日、ニューヨーク・カーネギーホール
モノラル ライブ
※CD-R3枚組。録音が残されていると言われながら、未発表だったカザルス指揮によるバッハ「マタイ受難曲」のライブ。アメリカ人コレクターの個人所有テープからのディスク化。音源データには「Broadcast
performance from Carnegie
Hall」との記載があるが、当然ライブであり、しかも放送のための録音としては不備が多く、実際に放送された可能性は極めて低い。オリジナルの音質は、オーケストラや合唱のマイクセッティングはほぼ妥当だが、独唱については、福音史家(エヴァンゲリスト)はマイクが近くて録音レベルが高すぎ(音が大きい)、演奏会場ではなく別室で語るアナウンサーのように聴こえる違和感がある一方、他の独唱者、特に女声はマイクが遠すぎて残響ばかり響き(専用マイクがなかったようだ)、強音ではレベルオーバーで歪み、しかも一部は伴奏に消されがちになるなど、プロのエンジニアがセットしたとは思えない状態であった。おそらくカザルス音楽祭またはホールの関係者が単なる記録のために、ホール常設の天吊りマイクに加えて、事前テストなしに適当に補助マイクを置いたのだろう。一部の楽器独奏もマイクに近すぎてバランスが悪い。当音源は出演者も含むこれらの関係者のコピーがアメリカ人コレクターに渡ったものと想像されるが、このような音質の問題からLP・CD化が見送られてきたと思われる。
今回ディスク化に当たっては、福音史家をはじめとする独唱の音量バランスを揃えること、さらに技術的に難易度は高いが、個々のホールトーン(残響)の響き方や長さも異なるため、これらについても均一化すること、女声歌唱を明確化すること等の対策を行った。結果として、独唱パートについては、当然ながら限界はあるものの、オリジナル音源と比較して大幅な改善となった。元来1963年のテープ録音であるから、音質自体は良好でノイズも極小、会場ノイズもほとんど聞こえず、1950年代のイタリア・オペラのライブCDなど聴いたことのあるリスナーであれば、大きなストレスなく十分に作品を鑑賞することができると思われる。
1963年の第7回カザルス音楽祭はプエルト・リコで開催されたが、当地で演奏されたバッハ「マタイ受難曲」がニューヨークでも追加公演という形で演奏された。6月16日日曜日の午後5時に第1部開演、6時半から8時半まで「intermission
for
dinner」、8時半から第2部というスケジュール。カットなしの全曲版であるが、合唱指揮で有名なロバート・ショウによる英訳版が使用されている。1950年代までのアメリカでは、聴衆の理解を深めるため、モーツァルトの「魔笛」やベートーヴェンの第9なども英訳で上演されたが、そのような習慣の末期に当たる。それでも福音史家役で定評があったエルンスト・ヘフリガーは、慣れないはずの英訳版を難なくこなしているようだ。その他の歌手は、フォレスターを除き日本では知名度が高くないが、バッハなど宗教音楽作品の歌唱で経験豊かなメンバー。合唱がクリーヴランド管合唱団というのは意外に思えるが、当時ロバート・ショウが同合唱団の指揮者を務めており(ジョージ・セルのアシスタントでもあった)、1960年にクリーヴランド管のコンサートにおいて、ショウ自身が同合唱団と「マタイ受難曲」英訳版を指揮・演奏したという実績から参加したのだろう。ただし参加は合唱団全員ではなく「member
of」ということでピックアップメンバーだったようだ。
オーケストラはカザルス音楽祭のための臨時編成であり、メンバーには学生も多かったが、コンサートマスターのアレクサンダー・シュナイダー以下、シドニー・ハース(ニューヨーク・フィル及びシカゴ響のコンサートマスター)、フランク・ミラー(NBC響及びシカゴ響首席チェロ)、ロナルド・ローズマン(ニューヨーク・フィルのコ・プリンシパル・オーボエ)など、要所には名手が揃っていた。一説には、ニューヨーク公演の主要メンバーはプエルト・リコ公演と同様だが、他の団員はアメリカのメジャー・オーケストラのピックアップメンバーで構成されていたと言われている。確かに当時のニューヨーク公演プログラムの冒頭にはFestival
Casals of Puerto Ricoと表記されながら、オーケストラはCasals Festival Orchestraとのみ表記され、Puerto
Ricoの地名がないが、主要メンバー以外の奏者全員が入れ替わったわけではないと思われ、当ディスクでは便宜上、旧称表記とした。カザルス指揮のバッハは、20世紀前半まで主流だった荘重で重厚なロマン的スタイルだが、名手揃いのオーケストラと合唱により、ライブとは思えない完成度を示している。
カザルスは、管弦楽組曲やブランデンブルク協奏曲をはじめ、バッハ作品を数多くスタジオ録音しているが、マタイ受難曲は正規の録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音と思われる。
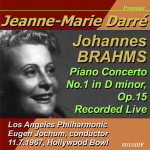
●ジャンヌ=マリー・ダレ ライブ ブラームス ピアノ協奏曲第1番
1967年ハリウッド・ボウル・ライブ
プレミエ60110DF
ブラームス ピアノ協奏曲第1番
ジャンヌ=マリー・ダレ(ピアノ)
オイゲン・ヨッフム指揮ロサンゼルス・フィルハーモニック
1967年7月11日、ロサンゼルス・ハリウッド・ボウル
モノラル ライブ
※フランスの名女流・ジャンヌ=マリー・ダレ(ダルレ)の意外と思えるレパートリー、ブラームスのピアノ協奏曲第1番のライブ。アメリカ人コレクターの個人所有テープからのディスク化。オリジナルの音源は放送のエアチェックではなく、ホールまたは主催者(オーケストラ)による記録音源と思われる。というのは、FMステレオ放送が一般化していた1967年時点でモノラルという点も理解しがたく(AM放送用という可能性はあるが)、また、オーケストラは特に冒頭の高域不足、逆にピアノは低域不足というバランスの悪さ、全体に歪みが多いなど、放送のための録音としては問題が多いという理由による。
ディスク化に当たっては、歪みを取るための周波数バランスの改善、異常に硬いピアノの音質改善(ジャンヌ=マリー・ダレは元々タッチが硬めだが)、ピアノとオーケストラの音量調整等々、様々な手立てを講じた結果、一応ストレスなく鑑賞できるレベルまで改善することが出来た。モノラルではあるが、1960年代後半の録音だけに音質自体は悪くなく、ステレオLPをモノラルで聴いている感がある。
ジャンヌ=マリー・ダレは、1962年にアメリカ・デビューで好評を得て以降、引退する1980年代まで定期的にアメリカ公演を行った。1967年の公演はおそらく1965年に次ぐもので、ロサンゼルス・フィル恒例、夏の夜の星空の下、野外コンサートにおける録音。といっても曲目は本格的なオール・ブラームス・プログラムで、大学祝典序曲に始まり、ピアノ協奏曲第1番、交響曲第1番というもの。ジャンヌ=マリー・ダレは、サン=サーンスのピアノ協奏曲を得意としており、全集のレコーディングもあるが、元来サン=サーンスの協奏曲は高度な演奏技術と音楽性を必要としており、凡庸なピアニストが弾くと、単に鍵盤上を指がせわしなく動き回るだけの外面的な作品と受け取られがちである。技術に十分な余裕があり、さらに豊かな音楽性を備えていて初めて真価を発揮する作品と言える(日本であまり人気がないのは、そのように弾きこなせる演奏者がいないためか)。このようなジャンヌ=マリー・ダレにとっては、ブラームスの作品も十分に守備範囲であり、持ち前の強靱なタッチが威力を発揮している。
ブラームスのピアノ協奏曲というと、女流ピアニストには演奏困難などと言われた時期があったが、かつてマイラ・ヘスやマリヤ・グリンベルク、ジーナ・バッカウアー、アリシア・デ・ラローチャなどがレパートリーとしており(後の二人は第2番だが)、誤解であったことは明白である。そもそもピアノ協奏曲第1番自体、1859年の初演は不評だったが、1873年にクララ・シューマンが再演したことでその真価が認められた経緯がある。近年ではエレーヌ・グリモーなどがレパートリーとしており「偏見」もなくなったようだ。
ジャンヌ=マリー・ダレは、男女問わず往年のフランス系ピアニストの中では、モニク・ドゥ・ラ・ブリュショルリと並ぶヴィルトゥオーゾだったと思われるが、レコード会社の怠慢?もあって、サン=サーンスの協奏曲とリストのピアノ・ソナタ以外にその技量を十全に示す録音を残さなかったことは残念である。当ディスクがジャンヌ=マリー・ダレの知られざる一面を示していると言える。
ジャンヌ=マリー・ダレは、上記のようにブラームスのピアノ協奏曲第1番のスタジオ録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音である。

●ミュンシュ/ボストン響 1963・1966年ステレオ高音質ライブ
バッハ 管弦楽組曲、ヘンデル「水上の音楽」
プレミエ60111DF
バッハ 管弦楽組曲第2番、第3番
ヘンデル「水上の音楽」(ハーティ編)
ドーリオー・アンソニー・ドワイヤー(フルート)
シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団
1963年7月20日、タングルウッド・ミュージック・シェード
1966年3月18日、ボストン・シンフォニー・ホール
ステレオ ライブ
※ミュンシュ/ボストン響(BSO)によるバロック期の二大作曲家の作品集。バッハは夏のバークシャー音楽祭、ヘンデルは本拠地ボストンにおける定期演奏会におけるステレオ・ライブ録音。アメリカ人コレクターによる提供音源。エアチェックと思われるが、いずれも高音質な優秀録音。ノイズレスでバランスも良好。ステレオ左右チャンネルの分離も自然で、鑑賞する上で全く不満はない。会場ノイズも極小。例によってミュンシュの強音が大きすぎるため(当時の批評では、フォルティッシモよりもさらに大きいミュンシュ流の“ミュニッシモ”があると言われた)、コンプレッサーで一部の強音を抑えたほか、ヒスノイズをわずかに低減した以外、特に手を加えていない。
バッハやヘンデルなどのバロック期の作品は、現在のモダン・オーケストラのコンサートではほとんど姿を消したレパートリー。ある意味ではピリオド楽器の認知度の高まりに伴う「被害」とも言えるが、学問的・音楽史的には誤っていると認識しつつも、ミュンシュによる絢爛豪華かつ巨大なスケールの演奏を聴くと、実演でこのような演奏を聴くことができない昨今の状況を少々残念に思う。
1960年代までは、バッハやヘンデルはオーケストラ(もちろん現在呼ぶところのモダン・オーケストラ)の主要レパートリーの一つであり、ミュンシュ/BSOの演奏会記録を見ても、管弦楽組曲第2番は1952年から当演奏の1963年まで、1960年を除き各シーズンで取り上げており計24公演。管弦楽組曲第3番は1950年から1963年まで、1951年と1954年を除き各シーズン取り上げており計29公演。「水上の音楽」は1949年から1966年まで、1952、1956、1957、1959、1961年とミュンシュの常任指揮者退任後の1963年~1965年を除けば各シーズンで取り上げており計63公演と、膨大な演奏回数にのぼる。バッハやヘンデルの作品が当時の聴衆にいかに人気があり、オーケストラもそれに応えていたことがよく分かる。
1963年のプログラムはすべてバッハで、前半がブランデンブルク協奏曲第6番と2番、休憩を挟んで後半が管弦楽組曲第2番と3番というもの。一方、1966年の公演は3月18日・19日の2回公演の初日。プログラムは前半が「水上の音楽」、シベリウスの交響曲第7番、休憩を挟んで後半がモーツァルトの交響曲第41番「ジュピター」、ルーセルの「組曲」ヘ長調というもの。作品の時代も様式もばらばらでまとまりに欠けるというか、得意な曲やりたい曲をただ並べたという印象で、ある意味ミュンシュらしい。
ちなみに管弦楽組曲第2番のフルート・ソロを担当したドーリオー・アンソニー・ドワイヤーは、1952年から1990年まで38年間BSOの首席フルートを務めた名手。入団当初は、ハープ奏者を除けば初の女性団員であり、オーディションではミュンシュも採用に躊躇し、決定後はオーケストラ・メンバーやジャーナリストから驚き(と疑心暗鬼)を持って迎えられたという。しかし、入団早々の1952年10月、当ディスクでも聴ける管弦楽組曲第2番のフルート・ソロにおいて、万全の技巧と高い芸術性を兼ね備えた演奏を披露して賞賛を浴び、一挙に評価を確立したと言われている。BSOは彼女のために専用の楽屋を用意するなど様々な対応をとったと言われ、メジャー・オーケストラへの女性奏者進出の先駆けの一人とも言えよう(ちなみに米メジャー・オーケストラにおける初の女性首席奏者は1941年にシカゴ響ホルン首席となったヘレン・コータス)。
ちなみにバッハもヘンデルも、1962年にミュンシュがBSOの常任指揮者を退任後の演奏である。ミュンシュは1963年以降亡くなる1968年まで、1967年を除き毎年BSOを指揮、57公演を行っている。後任のラインスドルフがミュンシュ時代のレパートリーの片寄りを批判していることから、ミュンシュの客演はラインスドルフではなくオーケストラ側の決定と思われる。ミュンシュのBSO常任指揮者在任後期には、アンサンブルのレベル低下が指摘されていたため(ミュンシュのリハーサルは「自由奔放」で正確さを要求しなかった)、技術精度向上のために厳しいリハーサルで知られるラインスドルフを迎えたと言われるが、当然、団員には不評で、専門家の評価は高かったものの、聴衆からもラインスドルフはミュンシュほどの高評価を得ることができなかった。ミュンシュへの客演招聘は、ある意味でオーケストラ・メンバーと聴衆双方の要望に応えたものと言えるかも知れない。
ミュンシュは当ディスク以外に、バッハの管弦楽組曲第2番の録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音。第3番は1966年ロサンゼルス・フィルとライブ録音していた。また、ヘンデルの「水上の音楽」は、1950年米RCAにBSOとスタジオ録音したほか、1954年、1960年(2種)、1962年(2種)BSOと、1966年シカゴ響とそれぞれライブ録音していた。

●ミュンシュ/ボストン響 1956・1953年ライブ
ベートーヴェン交響曲第6番「田園」、第2番
プレミエ60112DF
ベートーヴェン 交響曲第6番「田園」、交響曲第2番
シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団
1956年12月8日、1953年10月17日、ボストン・シンフォニー・ホール
モノラル ライブ
※ミュンシュ/ボストン響(BSO)によるベートーヴェンの交響曲2曲。BSOの本拠地ボストンにおける定期演奏会のライブ録音。アメリカ人コレクターによる提供音源。エアチェックとのことだが、モノラルながら年代の平均を上回る優秀な音質。1956年の「田園」はメジャー・レコード・レーベルの初期ステレオ録音と同等の美しい音質。録音が3年古い第2番は「田園」よりややわずかに膨らみに欠けるものの(曲想や楽器編成の違いもあるかも知れない)、1956年の「田園」に見劣りしない音質。両者ともにヒスノイズもわずかでバランスも良好、いずれにしても音楽を鑑賞する上で全く問題ない。会場ノイズも極小。当時のアメリカにおける受信・録音機器などのエアチェック環境が驚異的に優れていたのだろう。ディスク化に当たっては、古い保存テープに発生しがちな一部のドロップアウトや突発的ノイズなどを解消した。
1956年の「田園」は12月7日・8日の2回公演の2日目。土曜日の夜8時半開演で、プログラムは、前半がブリテンの「フランク・ブリッジの主題による変奏曲」、イベールの「寄港地」。休憩を挟んで後半に「田園」という、ミュンシュにしては意外にまともな(!)構成。当演奏会前後には国内5カ所でツアーが実施されており、「田園」はツアーでも他の曲目を入れ替えつつ演奏されている。
1953年の第2番は10月16日・17日の2回公演の2日目。1956年公演と同じく土曜日の夜8時半開演で、プログラムは、前半がモーツァルト「ディヴェルティメント」ニ長調K.136、ラヴェル「クープランの墓」、コープランドのピアノ協奏曲(レオ・スミット独奏)、休憩を挟んで後半がレオ・スミットのパルカイ(The
Parcae)序曲(初演)、交響曲第2番というもので、定期演奏会らしい少々渋いというか凝ったもの。
ミュンシュはコンサート指揮者として、当然ながらベートーヴェン交響曲全曲をレパートリーとしているが、BSO時代の演奏回数には片寄りがあるようで、「田園」については、
1949~1950年シーズンに2公演、1950~1951年シーズンに1公演(夏のバークシャー音楽祭)、1954~1955年シーズンに5公演、1956~1957年シーズンに7公演、1958~1959年シーズンに9公演取り上げているが、第2番については、当録音を含む1953年の2公演のみで非常に珍しく、録音が残されたことは幸いと言える。ちなみにレコーディングについても、ミュンシュは米RCAに膨大な録音を残しているにもかかわらず。ベートーヴェン交響曲全曲の録音を行っていないが、こちらは、米RCAが交響曲全集といった体系的な録音には消極的だったことが影響しているかも知れない。
ミュンシュは当ディスク以外に、ベートーヴェンの「田園」を1955年米RCAにBSOと、1966年コンサート・ホール・ソサエティにロッテルダム・フィルとスタジオ録音したほか、1951年トリノRAI放送響とライブ録音していた。また、交響曲第2番は当ディスクが現在確認されている唯一の録音である。

●ギオマール・ノヴァエス 1940~1947年米コロンビア未発表録音集
ショパン ピアノ・ソナタ第3番、第2番ほか
プレミエ60113DF
ショパン ピアノ・ソナタ第3番、第2番、スケルツォ第3番、エチュード第4番
ギオマール・ノヴァエス(ピアノ)
1941年2月26~28日(ソナタ第3番)、1947年1月8、9日(ソナタ第2番)
1940年3月29日(スケルツォ第3番)、1947年2月20日(エチュード第4番)
ニューヨーク・コロンビア・スタジオ
モノラル
※ブラジル出身の名ピアニスト、ギオマール・ノヴァエスによる米コロンビア未発表(未発売)録音集。アメリカ人コレクターからの提供音源。78回転SP録音の成熟期から末期にかけての録音で、テスト・プレス盤からの復刻。テスト・プレスというと門外不出のように思えるが、いわゆる試聴盤の意味もあり、レコード会社内のみならず、演奏家本人や所属事務所のほか、一部は大手販売店にも発売予告を兼ねて配布されたらしい。所有者が不要になったテスト・プレス盤を処分することもあるため、フリッツ・クライスラーやミッシャ・エルマン、ネリー・メルバなど、SP時代の有名演奏家のテスト・プレス盤は少なからず市場に出回っており、それほど珍しいものでもないようだ。
当ディスクに収められた曲は、テスト・プレス盤が完成後、何らかの理由で演奏家本人が発売を認めなかったか、レコード会社が発売を見送ったもの。
音質は、後述するソナタ第3番を除けば、さすがにSP録音の完成期であり、また、1948年にはLPを発売するなど、当時世界最先端の技術を誇っていた米コロンビアということで非常に優れており、特にソナタ第2番はモノラルLPと同等。また、スクラッチノイズはソナタでは皆無、スケルツォも極めて微少。ただし、エチュード第4番は元の録音は良かったようだがやや鮮明さに欠けるのは、盤のコンディションが悪いのかも知れない(有名曲であるため繰り返し再生されたか)。
ちなみに20年ほど前にほぼ同一内容の海外盤CDが出ているが、少なくともソナタ第3番の音質が大きく異なるため、当音源は新たにテスト・プレス盤から復刻したものと思われる。既出CDのソナタ第3番は、中高域に若干ピークがあり耳障りな一方、高域は不足しているというバランスの悪い音質で、全体にラフで大味な印象。これがノヴァエスが発売を許可しなかった理由かも知れないが、今回の復刻では、再生針やイコライザーの選定などにトライアルを重ねたとのことで、ショパンらしい繊細な音色が再現されるようになった。
ちなみに米コロンビアにおけるノヴァエスの未発表録音は、当ディスクの音源以外にバッハのトッカータ数曲、ショパンのバラード第3番(これは再録音が発売された)などがあるようだが、残念ながらこれらのテスト・プレス盤は外部に出ていないようだ。
ギオマール・ノヴァエスはパリ音楽院を修了後、1911年17歳でデビュー、早々に高い評価を確立し、1919~1927年米ビクター、1940~1947年米コロンビアと録音契約を行うなど、若い頃から多くのレコーディングを行った(1930年代の録音が存在しない理由はよく分からない)。ただし、その大半は当時「1枚もの」と呼ばれたSP盤片面ないし両面に収まる小品が多くを占め、ソナタなどSP盤数面に渡る作品(いわゆる「組みもの」)はほとんど録音していない。これはノヴァエス本人が、SPの場合は片面3~4分しか収録できず、長尺の作品では録音・再生ともに演奏が中断されることを嫌ったのかも知れない。フルトヴェングラーが第二次世界大戦前、独ポリドールには最初期を除き小品しか録音しなかった理由と共通するところがある(フルトヴェングラーはその後、英HMVと契約して「宗旨替え」するが)。その数少ない例外が当ディスクに聴くソナタ第2番と第3番であるが結局未発売に終わった。なお、当時米コロンビアでは、20分程度録音可能な16インチ・ラッカー盤によるレコーディング・システムを導入しており(ブルーノ・ワルター指揮ニューヨーク・フィルの録音にも使用された)、ノヴァエスのソナタ録音もこのシステムを使用していた可能性がある。
先に記したように1948年に米コロンビアはLPを発売し、同年に米アンペックスが世界初の商用テープレコーダー「モデル200」を発売、高音質の長時間録音と再生が可能となったが、ノヴァエスは1947年を最後に米コロンビアとの録音契約を終了。新興レーベルのヴォックスと契約し、これら未発表作品の再録音は行われなかった。
正確な時期は不明だが、1930年代にノヴァエスはアメリカの有力エージェント(音楽事務所)であるコロンビア・コンサーツ(後のコロンビア・アーティスツ=CAMI)と契約。北米において広範なコンサート活動が可能となった。コロンビア・コンサーツはその名の通り、米コロンビア(及び放送局のコロンビア・ネットワーク=CBS)と密接な関係があり、音楽事務所とは契約を継続しつつ録音契約は終了するということで、やや矛盾した行動に思えるが、背景には、レコーディング契約に関して有利な契約、この場合はギャランティよりも録音レパートリーやスケジュール(日程のみならず納得いくまでテイクを行う)等々、自らの自由度を高めたいという意思の表れがあったのではないか。当時米コロンビアには主なピアニストとして、ノヴァエス以外にルドルフ・ゼルキン、ロベール・カザドシュなどが契約しており、ノヴァエスが録音を希望するレパートリーと重なることもあったと思われる。新興の米ヴォックスであれば、トップ・アーティスト待遇となり自らの希望が通りやすいと考えたように想像する(加えて米ヴォックスの敏腕経営者ジョージ・メンデルスゾーンの営業力もあったろう)。ちなみに指揮者のギュンター・ヴァントが1950年代の壮年期、フランスの通販専門レーベルであるクラブ・フランス・デュ・ディスク(CFD)とレコーディング契約したことについて、後にヴァントは「当時は(英?)EMIなどからも声がかかったが、小さい会社の方が自らの希望を受け入れてくれそうだったから」と語っており、確かにCFDではベートーヴェンの交響曲全集など、EMIでは実現しなかっただろう録音を残している。
同様に米ヴォックスを選んだノヴァエスも、ショパンの主要作品のほか、モーツァルト、ベートーヴェン、シューマン、ドビュッシー、ファリャほか膨大な録音を残すことができ、後述するようにピアノ・ソナタ第3番は1951年・1952年、シューマンのピアノ協奏曲も1951年・1956年とそれぞれ短期間に再録音・再発売するなど、ノヴァエスの希望(わがまま?)が実現したことは満足だったろう。しかし一方で、「レコードは実演におけるノヴァエスの良さを伝えていない」(評論家ハロルド・ショーンバーグ)とも言われ、米ヴォックスの録音の悪さや、テイクを必要以上に繰り返すことによる演奏の流れの悪さや硬直化(これはノヴァエス本人の問題だが)など、結果的に移籍が成功だったかどうかは意見が分かれるところだ。
その点で当ディスクに聴く米コロンビアによるショパンの未発表録音は、ヴォックスへの再録音とは異なった評価がなされるのではないかと思われる。
ノヴァエスは、当ディスク以外にショパンのピアノ・ソナタ第3番を1951年と1952年、ピアノ・ソナタ第2番、スケルツォ第3番、エチュード第4番をそれぞれ1952年米ヴォックスにスタジオ録音していた。
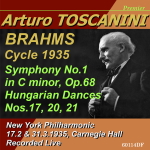
●トスカニーニ/NYP1935年ライブ
ブラームス 交響曲第1番、ハンガリー舞曲第17、20、21番
プレミエ60114DF
ブラームス 交響曲第1番
ハンガリー舞曲第17、20、21番(ドヴォルザーク編曲)
アルトゥーロ・トスカニーニ指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
1935年2月17日、3月31日、ニューヨーク・カーネギーホール
モノラル ライブ
1935年2月から4月にかけて、トスカニーニとニューヨーク・フィル(NYP)は、本拠地カーネギーホールにおいてブラームス・チクルスを開催した。定期演奏会の一環ではあったが、交響曲全曲をはじめとして協奏曲や合唱曲なども大規模なもので、奇跡的にもコロンビア・ネットワーク・ラジオによって、コンサート数か月前に導入された米Presto社製タイプ6Dアセテート・ディスク・レコーダーですべての演奏がライブ録音された。
同レコーダーは33・1/3回転の16インチディスク1枚で20分程度の録音が可能であり、2台(以上?)のレコーダーを使用して、欠落なしに録音された。国土が広いアメリカでは時差があるため、全米各地に放送するためには、録音して時間をずらして放送する必要があったためと思われる。
今回紹介する交響曲第1番は、同時発売の第2番とともに、既出第3番(プレミエ60090DF)・第4番(プレミエ60091DF)の続編に当たる。アメリカ人コレクターからの提供音源。第3番・第4番の発売当時は所在不明だったアセテート・ディスクがその後発見され、これでブラームスの交響曲全曲が揃った。
既出の交響曲第3番・第4番のディスク化の際も同様だったが、すでに80年以上を経た古いアセテート・ディスクでもあり、原盤はスクラッチ・ノイズが過大で音質改善は困難をきわめた。ただし、当ディスクに収められた交響曲第1番は比較的ノイズが軽度な部類で、中継放送用にプロのエンジニアによって録音されていることもあり、バランスや音質自体は問題なく、ディスク化に当たってはノイズのみを低減することに専念した。全くのノイズレスとすると音楽情報も削ってしまう弊害があり、微少ではあるものの断続的ノイズは残っているが、思いのほか良好な状態に仕上がっている。アセテート・ディスクの高域の周波数レンジは11khz程度までと狭いが、仮想的に15khz程度まで拡大した結果、十分鑑賞に堪える状態となり、第二次世界大戦中のブルーノ・ワルター/NYPなどによる状態の悪いライブ録音よりは上質といえる。録音日の異なるハンガリー舞曲も同程度の音質。
2月17日の交響曲第1番はチクルス第1回目の録音。14・15・17日と同一プログラム3日目の演奏会で日曜日午後3時開演のマチネー。プログラム前半は、ハイドンの主題による変奏曲(プレミエ60115Fで同時発売)、ヴァイオリンとチェロの二重協奏曲(独奏はNYPコンサートマスターのミシェル・ピアストロ、同首席のアルフレッド・ウォーレンスタイン=後に指揮者に転身した)。休憩を挟んでプログラム後半に交響曲第1番が演奏された。
3月31日のハンガリー舞曲はチクルス第5回目の録音、28、29、31日と同一プログラム3日目の演奏会でこちらも日曜日午後3時開演のマチネー。プログラム前半にセレナーデ第2番、ワルツ集「愛の歌」(ピアノ連弾伴奏)、休憩を挟んで後半に合唱曲4曲(ホルン、ハープ、ファゴット伴奏)、ハンガリー舞曲3曲、最後に大学祝典序曲(プレミエ60090DFで発売済み)という、現在から見るとやや異例のプログラム。ハンガリー舞曲はブラームス自身がオーケストレーションした第1番や3番・10番ではなく、ドヴォルザーク編曲の第17・20・21番であることが奇妙だが、後年3曲ともレコーディングしていることから、トスカニーニお気に入りの作品だったのだろう。
広大なレパートリーを持っていたトスカニーニだが、ブラームスは好んだ作曲家の一人。特に交響曲は残された録音も複数存在するが、当ディスクの録音はおそらく最古の最も若い(といっても68歳前後だが)時期の録音と思われ、わずか2年後、1937年に行われたNBC響との同曲の録音に比べても伸びやかさや柔軟さが感じられる。晩年トスカニーニは、グイド・カンテルリの演奏を聴いて「若い頃の自分の演奏のようだ」と評したが、確かに68歳のトスカニーニの演奏はカンテルリの演奏と共通点を感じる。
ちなみにトスカニーニとNYPの演奏会記録を見ると、ブラームスの交響曲第1番は、1930年11月に初公演以降、NYP常任指揮者退任直前の1935年まで6回計10公演行い、ほぼ毎シーズン演奏していたことになり、確かにブラームスを好んでいたことが分かる。一方、ハンガリー舞曲は当ディスクに聴くチクルスの演奏のみだったようだが、正式な記録に残らないツアーのアンコールなどで演奏した可能性はある。
トスカニーニは、ブラームスの交響曲第1番を1941年と1951年米RCAにNBC響とスタジオ録音したほか、1937年・1940年・1943年・1951年NBC響、1952年フィルハーモニア管とライブ録音していた。一方、ハンガリー舞曲第17、20、21番を1953年にNBC響とスタジオ録音していた。
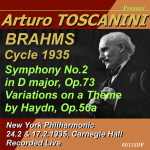
●トスカニーニ/NYP1935年ライブ
ブラームス 交響曲第2番、ハイドンの主題による変奏曲
プレミエ60115DF
ブラームス 交響曲第2番
ハイドンの主題による変奏曲
アルトゥーロ・トスカニーニ指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
1935年2月24日、2月17日、ニューヨーク・カーネギーホール
モノラル ライブ
1935年2月から4月にかけて、トスカニーニとニューヨーク・フィル(NYP)は、本拠地カーネギーホールにおいてブラームス・チクルスを開催した。定期演奏会の一環ではあったが、交響曲全曲をはじめとして協奏曲や合唱曲なども大規模なもので、奇跡的にもコロンビア・ネットワーク・ラジオによって、コンサート数か月前に導入された米Presto社製タイプ6Dアセテート・ディスク・レコーダーですべての演奏がライブ録音された。
同レコーダーは33・1/3回転の16インチディスク1枚で20分程度の録音が可能であり、2台(以上?)のレコーダーを使用して、欠落なしに録音された。国土が広いアメリカでは時差があるため、全米各地に放送するためには、録音して時間をずらして放送する必要があったためと思われる。
今回紹介する交響曲第2番は、同時発売の第1番とともに、既出第3番(プレミエ60090DF)・第4番(プレミエ60091DF)の続編に当たる。アメリカ人コレクターからの提供音源。第3番・第4番の発売当時は所在不明だったアセテート・ディスクがその後発見され、これでブラームスの交響曲全曲が揃った。
既出の交響曲第3番・第4番のディスク化の際も同様だったが、すでに80年以上を経た古いアセテート・ディスクでもあり、原盤はスクラッチ・ノイズが過大で音質改善は困難をきわめた。元来、中継放送用にプロのエンジニアによって録音されていることもあり、バランスや音質自体は問題ないものの、残念ながら当ディスクに収められた交響曲第2番はあまり保存状態が良くなかったためか、第1・第2楽章は比較的ノイズは軽度だがいくつか再生不能箇所があり(アセテートのコーティングがはがれていたらしい)、第3・第4楽章は楽曲とノイズが混合した状態でノイズの分離が困難な箇所が散見された。このため、一部は同じくトスカニーニ/NYPによる1936年2月16日録音で補われており、この状態でアメリカ人コレクターから提供されている(1936年録音の交響曲第2番全曲が残っているかは不明)。オリジナルの音源は1楽章ごとに1枚のアセテート・ディスクに録音されているが、当ディスクで楽章の途中で音質に変化がある箇所は差し替え部分に当たると思われる。ディスク化に当たっては、ノイズを低減することに専念したものの、全くのノイズレスとすると音楽情報も削ってしまう弊害があり、第3・第4楽章などはノイズを残さざるを得ない部分もあった。また、アセテート・ディスクの高域の周波数レンジは11khz程度までと狭いが、仮想的に15khz程度まで拡大した結果、一応は鑑賞に堪える状態となった。一方、ハイドンの主題による変奏曲は、オリジナルの状態でもノイズが少なく極めて音質良好で、当時の正規のスタジオ録音と同等。鑑賞する上野不満は全くない。
2月24日の交響曲第2番はチクルス第2回目の録音。21、22、24日と同一プログラム3日目の演奏会で日曜日午後3時開演のマチネー。プログラム前半に悲劇的序曲((プレミエ60091DFで発売済み)、ハイフェッツ独奏によるヴァイオリン協奏曲、休憩を挟んで後半に交響曲2番というプログラムで、今日よく見られるオーソドックスなプログラミング。
2月17日のハイドンの主題による変奏曲はチクルス第1回目の録音、14・15・17日と同一プログラム3日目の演奏会で日曜日午後3時開演のマチネー。プログラム前半は、ハイドンの主題による変奏曲、ヴァイオリンとチェロの二重協奏曲(独奏はNYPコンサートマスターのミシェル・ピアストロ、首席のアルフレッド・ウォーレンスタイン=後に指揮者に転身した)。休憩を挟んでプログラム後半に交響曲第1番(プレミエ60114Fで同時発売)が演奏された。
広大なレパートリーを持っていたトスカニーニだが、ブラームスは好んだ作曲家の一人。特に交響曲第2番は残された録音も複数存在するが、当ディスクの録音はおそらく最古の最も若い(といっても68歳前後だが)時期の録音と思われ、例えば1952年に録音されたフィルハーモニア管との録音では、緩徐楽章でも先へ急ごうという「せっかちさ」を感じたが、1935年の当録音ではそのような印象はなく、伸びやかさや柔軟さが感じられる。晩年トスカニーニは、グイド・カンテルリの演奏を聴いて「若い頃の自分の演奏のようだ」と評したが、確かに68歳のトスカニーニの演奏はカンテルリの演奏と共通点を感じる。
ちなみにトスカニーニとNYPの演奏会記録を見ると、ブラームスの交響曲第2番は、1928年1月に初公演以降、NYP常任指揮者退任直前の1936年まで9年間で11回計23公演。一方、ハイドンの主題による変奏曲も1926年2月に初公演以降、1935年まで10年間で10回計17公演行い、確かにブラームスを好んでいたことが分かる(両作品とも1930年のNYPヨーロッパ・ツアーでも取り上げている)。
トスカニーニは、ブラームスの交響曲第2番を1952年米RCAにNBC響とスタジオ録音したほか、1938年BBC響・1943年・1951年NBC響、1952年フィルハーモニア管とライブ録音していた。一方、ハイドンの主題による変奏曲を1936年米RCAにNYP、1952年同じく米RCAにNBC響とスタジオ録音したほか、1952年フィルハーモニア管とライブ録音していた。

●カミラ・ウィックス チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲、ラヴェル「ツィガーヌ」ほか
1953・1946年ライブ
プレミエ60116DF
チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲
ラヴェル「ツィガーヌ」
サラサーテ「序奏とタランテラ」(管弦楽伴奏編曲版)
カミラ・ウィックス(ヴァイオリン)
ウィリアム・スタインバーグ、レオポルド・ストコフスキー指揮ハリウッド・ボウル交響楽団
エーリヒ・ラインスドルフ指揮スタンダード交響楽団(サンフランシスコ交響楽団)
1953年8月18日(チャイコフスキー)、1946年7月14日(ラヴェル)、ロサンゼルス・ハリウッド・ボウル
1953年1月4日、サンフランシスコ・ウォー・メモリアル・オペラハウス
モノラル ライブ
※カミラ・ウィックスによるチャイコフスキーの協奏曲ほかの貴重なライブ録音。アメリカ人コレクターからの提供音源。チャイコフスキーとラヴェルは、有名な野外ホール、ハリウッド・ボウルにおける夏の夜のコンサートから。また、サラサーテはスタンダード石油がスポンサーとなったNBC系列のラジオ番組「スタンダードアワー」の公開収録から。詳細は後述するが、いずれもアセテート・ディスクに録音されており、それをダビングしたテープが当ディスクの元となっている。いずれもラジオ放送のために録音されたものであるため、特に優秀な音質というわけではないが、マイクセッティングも適正でバランスも問題なく、当時の水準をクリアしている。ただし、ディスク化に当たっては、アセテート・ディスク特有のスクラッチノイズがわずかに残っていたため低減し、周波数レンジが10khz程度までと狭いため15khz程度(FM放送並み)まで仮想的に広げる操作などを行った。結果的にソロ・ヴァイオリンの音色もクリアで鮮やかになり、ストレスなく音楽を鑑賞できる状態となった。なお1946年録音のラヴェルは一つ問題があり、演奏が開始して10分過ぎ頃、ホール上空を航空機が通過する騒音が収録されてしまっている。野外劇場であるハリウッド・ボウルについては、公演中は上空を航空機が飛んではいけないという条例があり、公演中であることをサーチライトで表示しているはずだが、緊急の飛行要請でもあったのだろうか。蛇足だが航空機専門家の分析によれば、エンジン音から機種はダグラスDC3(または同型機の軍用版C47)とのこと。
ちなみに、チャイコフスキーとサラサーテが録音された1953年といえば、米アンペックス社が1948年に商用テープレコーダーを発売してから5年後、既に放送現場ではテープ録音が常用されていた時期に当たる。1950年代前半のヨーロッパの放送局などでは、いったんテープで収録して放送に使用した後、当時は高価だったテープを再利用するため、音源をアセテート・ディスクにダビングして保存することが日常的に行われていた。しかし、資金的な問題がなかったアメリカでは、1950年代前半には録音済みテープはそのまま保存することが通常であったから、原盤がアセテート・ディスクである理由は理解できない。おそらくテープ収録されたものの、オリジナル・テープが行方不明または紛失、バックアップ用のアセテート・ディスクのみ現存が確認されているということか。
チャイコフスキーはカミラ・ウィックス25歳の時の録音。1951年に結婚し、最初の子を産んでからわずか2か月後の演奏とのこと。ということはチャイコフスキーよりも8か月前に録音されたサラサーテは妊娠3か月頃の録音に当たるが、演奏は充実しており、そのような事情はまったく感じさせない。以前の略歴紹介では結婚を機に引退し、両親の母国ノルウェーに移住したとされていたが、最近明らかになった詳細な経歴によると、実際には結婚後もカリフォルニアに在住して演奏活動を継続、ノルウェーにはしばしば渡航しつつ、30歳を過ぎた頃に(一度目の)引退をしたというのが事実のようだ(1970年頃から徐々に演奏活動を再開する)。ウィックスは5人の子をもうけたが、演奏活動は家庭生活に悪影響を与えない範囲で行い、長期のツアーなどは避けたというのが事実のようだ。
ウィックスは結婚前の1946年、ノルウェーで4か月間に88回の演奏会を行い、以降10年間でヨーロッパ・ツアーを10回行い、特に1951年には8か月間に10カ国で100回の演奏会を行ったというが、本人の語るところでは、「疲れ果て、しかも収益はリハーサルや移動の費用に見合うものではなかった」とのことで、若い新人演奏家の場合、知名度を高めるためにツアーで多くの演奏会を行うことがあるが、(おそらく)所属音楽マネージメント事務所のもくろみとは異なり、演奏旅行で各地を飛び回る「スター演奏家」の生活を嫌っていたようだ。
かつてクラウディオ・アラウが来日時のインタビューで「私の日常は日々旅行です。自宅に戻るのは1年のうちわずかな期間です」とやや寂しげに語ったように、世界的名声を得る(保つ)には、演奏旅行の毎日を続けざるを得ないのだろう。アルトゥール・ルービンシュタインのように「同じ町に1~2週間も滞在すると飽きてしまい、他の新しい場所に行きたくなる」ような気質の演奏家でなければ務まらない厳しい世界といえる。
また、ウィックスは、当ディスクのチャイコフスキーの演奏について「演奏家として大きな成功を収めたことは間違いないが、作品を自分自身のキャリアの手段として扱いたくない」と語り、優れたノルウェーの作曲家の紹介を自らの理想と考えていたようだ。事実、チャイコフスキーの演奏後のアンコールには、ビャルネ・ブルスタードの作品を演奏。1949年にはファルテイン・ヴァレンの協奏曲を英HMVにレコーディング、1957年のニューヨーク・フィルの定期演奏会ではクラウス・エッゲの協奏曲を演奏している。
その点で、ラヴェルのツィガーヌを演奏したハリウッド・ボウルの演奏会のプログラムは、カバレフスキーのコラ・ブルニョン序曲、グリンカのホタ・アラゴネーサ、ヴィエニャフスキの協奏曲(プレミエ60030DFIIとして発売済み)、ブリテンのピーター・グライムズからパッサカリア、同じくブリテンのソワレ・ミュージカル、ラヴェルのツィガーヌ、クライスラーのウィーン奇想曲、オネゲルのパシフィック231という、ストコフスキーらしい名曲コンサート。サラサーテを演奏したスタンダードアワー公開収録も、サラサーテの他にラロのスペイン交響曲の抜粋、オーケストラのみでベートーヴェン交響曲第7番第2・第3楽章、プロコフィエフ「ロミオとジュリエット」抜粋などが演奏されたが、このような“エンターテインメント・ショー」は、ウィックスの考えとは「ずれ」があったのだろう。
この辺りから、1951年米キャピトルにシベリウスのヴァイオリン協奏曲という歴史に残る名演奏を録音したにもかかわらず、その後は若くしてレコード業界から距離を置き、シベリウスを除けば、有名作品のスタジオ録音をほとんど残さなかった点も理解できる。演奏活動そのものは長期にわたって行っており、今後はライブ録音のさらなる発掘を期待したい。
なお、当ディスクのオーケストラ表記には説明を要する。チャイコフスキーとラヴェルを演奏している団体はいずれもハリウッド・ボウル交響楽団だが、前者の実態はロサンゼルス・フィル(LAPO)で、ハリウッド・ボウルで夏季シーズンに開催されるコンサートにおける表記名。後者は1945年にストコフスキー自らが設立し、2年ほどコンサート活動を行った団体でLAPOとは別団体である(この団体の詳細はプレミエ60100DFの紹介で触れている)。また、スタンダード交響楽団の実態はサンフランシスコ交響楽団で、「スタンダードアワー」出演時のいわば「芸名」である。
カミラ・ウィックスは、当ディスクに収められたすべての作品のスタジオ録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音と思われる。

●新発見 音質良好新音源 バルビローリ/ヒューストン響
マーラー 交響曲第5番 1966年ライブ
プレミエ60117DF
マーラー 交響曲第5番
サー・ジョン・バルビローリ指揮ヒューストン交響楽団
1966年3月24日、ニューヨーク・カーネギー・ホール
モノラル ライブ
※バルビローリとヒューストン交響楽団によるマーラーの交響曲第5番。1966年ニューヨーク・ツアーの際のライブ録音である。当録音には既出盤が数種あるが、いずれもヒスノイズ過多、高域不足の鈍く不鮮明な音質で、一般的な鑑賞に耐える状態ではなかった。当レーベルでも複数のルートでこのライブ録音を数種入手していたが、いずれも同様に劣悪な音質だった。既出音源のオリジナルはダビングを重ねて劣化したカセットテープだったと言われている。しかし、このほどアメリカ人コレクターから入手した音源は、既出音源よりも鮮明な音質で、おそらくオリジナル録音またはそれに近い世代のコピー音源と思われ、ようやくディスク化が可能となった。アメリカ人コレクターはカザルス指揮のマタイ受難曲(プレミエ60109DF)の音源とともに入手したとのことで、出所は会場であるカーネギー・ホールの関係者またはそのOB辺りと推察される。
ただし、当ディスクの音源は鮮明な音質とは言え、バランスの悪さなどから、プロのエンジニアがマイクセッティングを行ったラジオ放送のための録音などではなく、おそらくホールまたはオーケストラ側が行った単なる記録のための録音で、事前のテストなしにステージ上方の天吊りマイク1本によって録音されたようだ。この点でステレオ録音が一般化していた1966年時点でモノラル録音という理由も理解できるが、全体に高域がやや不足する反面、低域過多でブーミー、またわずかではあるがヒスノイズも感じられた。
ディスク化に当たっては、高域不足・低域過多の周波数バランスを整えることから開始し、またトランペット・ソロなど一部楽器の「飛び出し」を抑え、複数のドロップアウトを解消、音楽を削ることなく慎重にヒスノイズを低減する等の作業を行った。結果として、一部限界はあるがモノラルながら1960年代半ばの録音水準と同等の音質改善が実現でき、ようやくストレスなく音楽を鑑賞できる状態となった。
バルビローリは1961年から1967年までヒューストン交響楽団の常任指揮者を務めていたが、このコンビによるスタジオ録音は行われず、来日公演もなかったため、日本においてはほとんど未知の存在といえる。ただし、実演に接したアメリカ国内では評価が高かったらしく、1964年から1966年まで3年連続でニューヨーク公演を行っている。当時アメリカの音楽業界は、ニューヨーク・フィルを含む「ビッグ・ファイブ」と言われる5団体に、ヒューストン響を含む6団体を加えて「エリート・イレブン」と呼んでメジャー・オーケストラのステータスを与えており、当ディスクでもさすがにその名に恥じない演奏を繰り広げているが、アメリカ国内においては、ニューヨークで認められることがメジャー・オーケストラとしても必須であり、1961年から常任指揮者に就任したバルビローリの貢献も大きかったと思われる。
一方、カーネギー・ホール側の事情としては、同ホールで定期演奏会を開催していたニューヨーク・フィルが1962年、新設のフィルハーモニック・ホールに演奏会場を移したことで、言わばレジデント・オーケストラを失ったことになり(ストコフスキー率いるアメリカ響も同ホールを本拠地としていたが歴史が浅く実力不足だった)、全米各地のメジャー・オーケストラに客演してもらう必要性もあったようだ。
当ディスクの1966年の公演は午後8時開演。最初にバルビローリ編曲による「エリザベス朝の組曲」、R・シュトラウスのオーボエ協奏曲(オーボエ独奏はバルビローリ夫人のイヴリン・ロスウェル)、休憩を挟んで後半がマーラーという、典型的な「バルビローリ・プログラム」。この年は7日後の8月31日にも公演が行われ、こちらもヴォーン・ウィリアムズやニールセンなどを含むバルビローリらしいプログラムだった。
バルビローリはマーラーの交響曲第5番を1969年英EMIにニュー・フィルハーモニア管とスタジオ録音しているが、ロマンチックでテンポが遅めのスタジオ録音に対し、ヒューストン響とのライブは同様のスタイルながら、より速めのテンポで活気にあふれており異なった表情を見せている。
バルビローリはマーラーを主要レパートリーとしていたと言われるが、実際に本格的に取り組んだのは第二次世界大戦後と言われ、定評がある第9番も1954年、50歳代半ばに初めて演奏会で取り上げている。聴衆(特に英国)のマーラー理解とバルビローリ本人の指揮者としての円熟がそれだけの時間を必要としていたと言えよう。

●フリッツ・ブッシュ/ニューヨーク・フィル、ロサンゼルス・フィル
ブラームス 交響曲第1番ほか 1942年・1946年ライブ
プレミエ60118DF
ブラームス 交響曲第1番
ワーグナー 楽劇「トリスタンとイゾルデ」から第1幕への前奏曲と「愛の死」
フリッツ・ブッシュ指揮ニューヨーク・フィルハーモニック、ロサンゼルス・フィルハーモニック
1942年2月1日、ニューヨーク・カーネギー・ホール
1946年3月10日、ロサンゼルス・アルハンブラ・ハイスクール・オーディトリアム
モノラル ライブ
※フリッツ・ブッシュがアメリカ東西両岸のオーケストラを振った貴重なライブ録音。アメリカ人コレクターからの提供音源。ニューヨーク・フィル(NYP)を振ったブラームスは、CBS放送(コロンビア・ネットワーク)によるラジオ放送用録音、ロサンゼルス・フィル(LAPO)を振ったワーグナーはNBC放送系列のラジオ番組「スタンダードアワー」における公開収録。いずれもアセテート・ディスクに録音され、ディスクからダビングされたテープが当ディスクの音源となっている。それぞれ1942年・1946年と古い時代の録音だが、アセテート・ディスク・レコーダーによる録音技術の安定期に入っており、特に1942年のブラームスは、手を加えないオリジナルの状態でもディスク録音特有のスクラッチノイズも極小、1942年録音という条件付きながら良好な音質で、明快さはわずかに欠けるものの一般的な鑑賞に十分堪える音質。録音後のアセテート・ディスクは、再生を繰り返すと急激にノイズが増え、音質が劣化する。幸い録音後の再生回数が少なかったのだろう。
なお、既出の海外盤には疑似ステレオ化した上に長大な残響を加えているものがあり、音に広がりと艶が出て聴きやすくなっているらしいが、さすがに「やり過ぎ」で、カーネギー・ホールではなく、パリのノートルダム寺院など大聖堂で聴くような音響に変化してしまっているようだ。当ディスクでは、オリジナルの音響を尊重しつつ、突発的なポップノイズの削減、低域過剰など周波数バランスの改善と周波数帯域の拡大(両者により高域が伸びてクリアに聴こえる効果がある)など、基本的な音質改善に努めた。
1946年録音のワーグナーは、ブラームスより4年後の録音だけに音質はさらに良好で、スクラッチノイズはさらに少なかったが、ディスク化に当たっては、こちらも低域過剰の改善、休止部分のノイズ低減、周波数バランスの改善等を行った。
1942年のブラームスはNYPの定期演奏会から。日曜日午後3時開演のマチネー。前半に、モーツァルト(ブゾーニ編曲)の「後宮からの逃走」序曲、ブラームス、休憩を挟んで後半に、シューベルト「未完成」。ドヴォルザークのスラヴ舞曲第7番・5番というプログラム。なぜか1プログラム1回のみの公演だが、直前の1月30・31日の定期演奏会で、ブラームスの代わりに、弟のアドルフ独奏でレーガーのヴァイオリン協奏曲(NYP初演)が入ったプログラムが組まれており(その他の曲は同一)、家族連れも多い日曜日のマチネーでは晦渋なレーガーからブラームスに変更したということだろう。
1946年のワーグナーは、前述のように「スタンダードアワー」の公開収録。曲順は不明だが、ベートーヴェンのエグモント序曲、シューベルト(フリッツ・ブッシュ編曲)の舞踊組曲、ワーグナーの「トリスタン」、「マイスタージンガー」から第3幕への前奏曲~徒弟たちの踊り、マイスタージンガーの入場というプログラム。「スタンダードアワー」は、セミクラシックも含む大衆向けのラジオ番組だが、さすがにフリッツ・ブッシュは妥協なく本格的なコンサート・プログラムでまとめている。通常の番組では、オーケストラ名はLAPOではなくスポンサーの石油会社名から「スタンダード交響楽団」と称するはずだが、この放送に限り、2日前に行われたLAPOの定期演奏会の抜粋を演奏したとのことで、番組のオリジナル・プログラムではないためか、資料ではLAPOと表記されており、当ディスクでもそれに従った。
1933年、ドイツでナチス政権が成立すると、ナチスに嫌悪感を抱いていたフリッツ・ブッシュは弟のアドルフらとともにドイツを出国。英国(グラインドボーン音楽祭の音楽監督)や南北アメリカ大陸、スウェーデンやデンマークを中心に活動を行い、ドイツで再び指揮台に立ったのは亡くなる数か月前の1951年だった。NYPには1942年に7回10公演(同一プログラムの複数回公演を含むため)、1950年国連の世界人権宣言記念コンサートで指揮したのみだったが(1927~1928年にNYPと合併前の旧ニューヨーク交響楽団を20回指揮している)、これは彼が当時ニューヨークのニュー・オペラ・カンパニー(後のニューヨーク・シティ・オペラ)の音楽監督を務めており、多忙だったことも大きな理由だろう。ただしNYP側の評価は以前から高かったようで、1936年トスカニーニのNYP常任指揮者辞任後の候補にも上がっていた。新即物主義に根ざしたブッシュの演奏はトスカニーニの後任としてふさわしかったと思われるが、ブッシュ自身は当時グラインドボーンの仕事を気に入っており固辞したという。
フリッツ・ブッシュは、かつてのドレスデンや上記のグラインドボーン、ニューヨーク・ニュー・オペラ・カンパニー音楽監督など経歴から、歌劇場の指揮を本来の仕事と考えていたらしく、才能のある若い歌手を発掘し育成することが喜びであるとも語っている。一方、オーケストラ指揮者としての経歴を見ると、ストックホルム・フィル音楽監督やデンマーク放送響首席など、二流とは言えないが決して超一流でもない団体のポストを歴任している。ブッシュの実力を持ってすれば、さらにランクの高いオーケストラとの仕事も可能だったと思われるが、晩年にアメリカを離れたのは、商業主義的なアメリカ音楽界に嫌気がさしたとも、アメリカ・メジャー・オーケストラの常任指揮者・音楽監督はスポンサーである大企業経営者や富裕層との付き合いも重要な仕事とされるが、そのような「非芸術的」な負担を嫌ったとも想像される。先のNYP常任指揮者への就任要請固辞など、メジャー・オーケストラの指揮は、客演以外は敢えて避けていたのかも知れない。
レコーディングについてブッシュは、おそらく第二次世界大戦前のドイツ出国以前に「現在の蓄音機はすべての音楽家にとって必要不可欠なものであると考えています。留学の機会を与えられなかった歌手とカペルマイスターは、蓄音機のレコードでしかイタリア・オペラの特殊な発声法を学ぶことができません。非常に多様なレパートリーは、すべての音楽家が比較して自分を教育する機会を与えてくれます。しかし、何よりも大切なのは、自分が持っているレコードを聴くことである。したがって、本格的な音楽を愛する人の家には、良いレコードがないといけません。蓄音機のさらなる発展は、最大の関心をもって見守るしかありません。」と語っており、レコードの重要性とその将来性を認識していたようだ。
実際にグラインドボーンにおけるモーツァルトの主要歌劇の全曲録音など、78回転SP時代には大変な労力を要したであろう仕事を成し遂げているが、第二次世界大戦後は、当時主流だった特定のレコード会社との専属契約も行わず、メジャー・レーベル、マイナー・レーベル交えて散発的にレコーディングするという状況で、LPレコードが本格的に普及する前の1951年に心臓発作で亡くなってしまった。おそらく歌劇全曲録音を要求するブッシュと、交響曲など管弦楽曲を要求するレコード会社との間の意見の相違があったのかも知れない(両者妥協の結果か、英EMIには1950~1951年に「コシ・ファン・トゥッテ」「イドメネオ」抜粋を録音している)。それだけに亡くなる直前に米レミントンというマイナー・レーベルにベートーヴェンやブラームスなどの交響曲を数曲まとめて録音したことは奇跡的だったとも言える。レミントンのやり手プロデューサー、ドン・ガボー(ガボール)にうまく乗せられたのだろうか。
フリッツ・ブッシュはブラームスの交響曲第1番をスタジオ録音しておらず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音。また、ワーグナーの「トリスタンとイゾルデ」前奏曲と愛の死もスタジオ録音しておらず、こちらも当ディスクが現在確認されている唯一の録音。ただし楽劇全曲のライブ録音は数種残している。
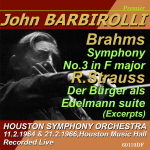
●音質良好 バルビローリ/ヒューストン響 1964・1966年ライブ
ブラームス交響曲第3番、R・シュトラウス「町人貴族」組曲抜粋
プレミエ6011D9F
ブラームス 交響曲第3番
R・シュトラウス「町人貴族」組曲抜粋
サー・ジョン・バルビローリ指揮ヒューストン交響楽団
1964年2月11日、1966年2月21日、ヒューストン・ミュージック・ホール
モノラル、ライブ
※バルビローリとヒューストン響によるコンサート・ライブ録音。アメリカ人コレクターによる提供音源。2曲ともエアチェック録音で、ブラームスはテレビ放送の音声を録音したもの。オリジナル音源の音質は年代相応でそれほど悪くはなかったが、ブラームスはテレビ音声特有?のジリジリというノイズが乗っており、時折、テープ劣化が原因と思われる微弱なポップノイズも発生していた。またテレビ局によるマイクセッティングが不適正だったか、そのような音作りだったかは不明だが、ナローレンジで中域ばかりが強調されたバランスが悪いもの。おそらくポピュラー・ミュージック的な録音スタイルかも知れない。ディスク化に当たって、ノイズについては完全に除去することは可能だが、音楽の弱音部分の音質劣化を招く恐れがあったため、鑑賞の妨げにならない程度、または大音量で再生しない限り聴き取れないレベルまで低減、周波数レンジも高域を15khz程度まで拡大、またイコライジングによってバランスを「シンフォニー・オーケストラ向き」に修正した結果、鑑賞する上で不満のない状態まで改善できた。一方、R・シュトラウスはヒスノイズが目立ったため、音質に影響を与えない範囲で低減した。なお「町人貴族」は、組曲9曲のうち、第6・7曲をカットした抜粋演奏。理由は不明だが、抜粋のみでも演奏時間が30分に達するため、聴き慣れない作品に聴衆が飽きない時間でおさめたのかも知れない。2曲とも会場ノイズは微少。
バルビローリは1960年、ヒューストン響からストコフスキーの後任として首席指揮者就任の打診があり、1961年から1967年まで首席指揮者を務めた。ヒューストン響は、アメリカ国内ではニューヨーク・フィル(NYP)やフィラデルフィア管を含む「ビッグ・ファイブ」と言われるトップ・グループ5団体に次ぐ11の団体、「エリート・イレブン」に位置づけられており、後任にストコフスキーと同格以上の指揮者を求めていた。バルビローリは当時英ハレ管の首席指揮者を務める一方、各地の団体を客演しており多忙だったが、少なめの演奏回数(それでも1シーズン12週間)など条件面でバルビローリの要望を受け入れたため、就任が実現したと言われている。
バルビローリは1936年から1943年にかけて、30歳代の若さでNYPの音楽監督を務めたが、ことあるごとに前任のトスカニーニと比較され、高評価を得られなかったと日本では認識されている。しかし、在任中に第二次世界大戦が始まったという状況下にもかかわらず、観客動員数などはトスカニーニ時代を上回り、米コロンビアとレコーディング契約を結ぶなど、実態は意外に好評だったことがうかがえる。低評価の出所は、NYP退任時に後任指揮者選定に自らの希望が通らず、NYPとの関係が悪化していたトスカニーニや、バルビローリとNYP後任を争ったロジンスキによる批判、それに追随した評論家の批評が第二次世界大戦前の日本に伝わったというのが実態のようだ。当時の日本におけるバルビローリ像は、フリッツ・クライスラーやアルトゥール・ルービンシュタインなどの協奏曲レコーディング時の伴奏指揮者という位置づけで「二流人」という認識であったから、そのまま無条件に受容されたのだろう。しかも、その影響により戦後も長らく優れた指揮者という評価を得ることはできなかった。真の意味で日本でバルビローリが高く評価されるようになったのは、晩年のレコーディングが広く聴かれるようになったバルビローリの没後と思われる。
一方アメリカでは、NYP時代のバルビローリ評価が決して低くなかったことが、ストコフスキーという大物の後任を要請された大きな理由だろう。ヒューストン響におけるバルビローリの活動は、来日公演もなく正式なレコーディングも残されていないため、日本ではほとんど未知の状態にある。しかし、海外公演こそ行わなかったものの1964年以降は毎シーズン国内ツアーを実施、ニューヨーク・カーネギー・ホールで公演を行うなど、メジャー・オーケストラとしてのステータスを保ち続けたようだ。1967年の退任後はその功績が評価され、バルビローリは名誉指揮者の称号を受けている。また、退任間際のシーズンではあったが、新たなコンサート・ホールが完成するなど、バルビローリの在任中はヒューストン響にとってエポックメイキングな時代だったといえる。
ちなみにブラームスが録音された1964年は、1月10~18日にかけて、ベルリン・フィルのメンバー自身が録音を希望したことで知られるマーラー交響曲第9番をEMIにレコーディング。続けてベルリン・フィルと公演、その後、同月下旬にハレ管を指揮、直後に渡米して当ディスクに聴くブラームスを含む公演を指揮、その後国内ツアーという、多忙ではあるが充実した活動を行っていた。一方の1966年録音のR・シュトラウスも、1964年と同じく1月上旬にベルリン・フィルに客演、同月下旬から2月上旬にハレ管を指揮、下旬に渡米して当ディスクに聴く「町人貴族」を含む公演を指揮、続けて国内ツアーというスケジュール。なお、3月24日ニューヨーク公演時のマーラー交響曲第5番は、プレミエ60117Fでディスク化済みされている。
ブラームスは、ドイツ系作品の中ではマーラーと並んでバルビローリが好んだ作曲家。4曲の交響曲の中では特に2番と4番を多く取り上げ、次いで3番、1番だったようだ。バルビローリとの相性の順にも思えるが、3番の2・3楽章などはバルビローリの音楽性と合致している。R・シュトラウスの「町人貴族」組曲は比較的演奏機会が少ない作品だが、バルビローリはNYPやハレ管とも演奏している。バルビローリは英バロック期の作品を自ら編曲した「エリザベス朝の組曲」を頻繁に取り上げており、「町人貴族」組曲も作品の時代は異なるものの同傾向の作品として好んでいたようだ。
バルビローリは当ディスク以外にブラームスの交響曲第3番を1967年英EMIにウィーン・フィルとスタジオ録音していた。一方、R・シュトラウスの「町人貴族」組曲はスタジオ録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音である。

●音質良好 フリッツ・ライナー/シカゴ響 1957・1958年ライブ
シューベルト交響曲第8(9)番「ザ・グレート」、オーベール「マサニエロ」序曲
プレミエ60120DF
シューベルト 交響曲第8(9)番「ザ・グレート」
オーベール「マサニエロ(ポルティチの唖娘)」序曲
フリッツ・ライナー指揮シカゴ交響楽団
1957年12月19日、1958年4月10日、シカゴ・オーケストラ・ホール
モノラル、ライブ
※ライナー/シカゴ響によるライブ録音。アメリカ人コレクターによる提供音源。2曲ともエアチェック録音で、シューベルトは、音質自体は悪くないものの、音量レベルの変動のほか、受信障害によって一部ノイズが混入していた。また、弱音と強音の差が大きく、家庭で聴く場合、弱音が聴こえるように音量調整すると強音が大きすぎるという問題があった。ディスク化に当たっては、音量レベルの調整、ノイズの除去、広すぎるダイナミックレンジの若干の圧縮等を行った。これに対して、オーベールは受信状態も良好でノイズも皆無。シューベルトと同様、ダイナミックレンジの調整のみ行った。
なお、拍手は入るが会場ノイズは皆無。これには理由があり、シカゴ響の公演は、地元ラジオ局WFMTまたはニューヨークのWBAI-FMが放送を行っていたが、いずれも放送前に2日公演(+リハーサル?)の録音をミックスし、演奏ミスや会場ノイズを除去するなどの編集が行われていたようだ。当ディスクの場合、録音の良さもあって、1950年代後半のスタジオ録音によるLPレコードに匹敵するほど完成度が高く、モノラルながら鑑賞する上での不満はない。
シューベルトは、1957年12月19・20日に行われた定期演奏会初日から。オリジナル音源の付属データには19日の公演という表記があり、19日公演を主体として上記のように「編集」されたのだろう。当日は前半にモーツァルトの歌劇「劇場支配人」序曲、ベートーヴェンのピアノ協奏曲第5番「皇帝」(ルイス・ケントナー独奏)、休憩を挟んで後半がシューベルトというドイツ系重量級プログラム。オーベールは、1958年4月10・11日に行われた定期演奏会初日から。第1曲目がオーベール、続いてコープランドの「入札地」組曲(世界初演)、モーツァルトの2台のピアノのための協奏曲K.365(ヴィトヤ・ヴロンスキー&ヴィクター・バビンのデュオ)、休憩を挟んで後半はグラナドスの歌劇「ゴイェスカス」から間奏曲、ファリャの歌劇「はかなき人生」から間奏曲とスペイン舞曲、アルベニス(アルボス編曲)のイベリアから「セビーリャの聖体祭」「トゥリアーナ」という一転してスペイン特集。ライナーという人はリハーサルは厳しく、オーケストラ・メンバーとの軋轢も多く、狷介な性格と言われたが、このような派手でエンターテインメント性の高い作品も得意としている点が面白い。
シューベルトの「グレート」は、なぜかライナーがスタジオ録音を残さなかった作品。シカゴ響とは1953年に2公演、1957年に2公演(当ディスクの録音)、かつて常任指揮者を務めたピッツバーグ響とは1945年、シンシナティ響とは1923年、1926年、1928年に取り上げているが頻度は高くなく、当時レコーディング契約を結んでいた米RCAビクターもミュンシュ/ボストン響の録音があるため、必要ないと考えたのかも知れない(ミュンシュ/ボストン響は1950~1958年に同曲を18回も演奏している)。とはいうものの、当ディスクの演奏は快速・辛口の演奏で、同じハンガリー系でよく比較されるジョージ・セルよりも緊張度や集中度が高く(セルの方がスケールが大きく開放感や余裕があるという評価も出来るが)、ライナーの個性が十分に発揮された演奏となっており、スタジオ録音を残さなかったことは惜しまれる。一方、オーベールの序曲は、シカゴ響とは当ディスクの演奏に加えて1週間後の4月19日しか取り上げていないが、おそらくライナーは20世紀初頭の修業時代、ヨーロッパの地方歌劇場でこの歌劇全曲を指揮した経験があったかも知れない。現代ではポップスコンサートを除き、定期公演においては、このような作品の演奏機会はほぼ皆無だが、往年の巨匠指揮者と言われる人たちは、意外とポピュラーな小品を取り上げることがあり、演奏会や歌劇が「娯楽」から「芸術」へ移行途中の世代の音楽家だったとも言える。
フリッツ・ライナーは、当ディスク以外にシューベルトの「グレート」とオーベールの「マサニエロ」序曲のスタジオ録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音と思われる。

●未発売テストプレス復刻&ライブ
ルービンシュタイン+ストコフスキー、ロジンスキ
ラフマニノフ ピアノ協奏曲第2番、チャイコフスキー ピアノ協奏曲第1番
プレミエ60121DF
ラフマニノフ ピアノ協奏曲第2番
チャイコフスキー ピアノ協奏曲第1番
アルトゥール・ルービンシュタイン(ピアノ)
レオポルド・ストコフスキー指揮ハリウッド・ボウル交響楽団
1945年9月4日、ハリウッド・リパブリック・スタジオ
モノラル、RCAビクター未発売テスト・プレス復刻
アルトゥール・ロジンスキ指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
1946年3月24日、ニューヨーク・カーネギー・ホール
モノラル、ライブ
※ルービンシュタインによるラフマニノフとチャイコフスキー二大協奏曲の録音。いずれもアメリカ人コレクターによる提供音源。ラフマニノフはストコフスキーとの「夢の共演」で、米RCAビクターがスタジオ収録したものの未発売に終わった曰く付きの録音。幸いテスト・プレス(試聴・サンプル盤)が作成され、それが当ディスクの音源となっている。テスト・プレス盤は少量の製作ながら、レコーディング関係者や演奏家以外に、所属マネージメント事務所、スポンサー企業、時には一部の有力販売店にも発売予告も兼ねて配布されたから、それらのいずれかが今日まで残されていたのだろう。録音日は8月1日という説もあるが、より信頼できる資料に従った。チャイコフスキーは、ニューヨーク・フィル(NYP)定期演奏会のライブ録音で、ラジオ放送のエアチェックと思われる。
ラフマニノフは、1945年という年代から当然78回転SP録音だが、テスト・プレス盤の状態が良好でスクラッチ・ノイズも比較的少なく、ディスク化に当たっては音源を損ねない範囲で、大半のノイズを除去することができた。正規のスタジオ録音であるため、音質は当時の水準を確保しており、1945年録音であることを考慮すれば鑑賞する上で不満はない。チャイコフスキーは、おそらく20分程度録音可能なプロ用アセテート・ディスク・ディスク・レコーダーを使用しているらしく、スクラッチ・ノイズも極小で、当時のライブ録音の水準を上回り、前出ラフマニノフの音質に匹敵。ディスク化に当たっては、一部音量レベルの変動や、ピアノとオーケストラのバランスが悪い箇所を修正したが、基本的には鑑賞する上で全く問題ない音質となっている。
アルトゥール・ルービンシュタインは、第二次世界大戦勃発後フランスからアメリカに避難し、大戦中は北米を中心に演奏活動を行った(1946年にはアメリカ国籍を取得)。また、レコーディングは、以前から契約していた英HMVの提携先である米RCAビクターに録音を続けた。
RCAビクターは、当時すでに「大スター」であったルービンシュタインと、同じく大スターだったストコフスキーとの共演を計画。ストコフスキーが当時音楽監督を務めていたハリウッド・ボウル響の夏の演奏会シーズン終了後、ラフマニノフのレコーディングを実施した。当時の78回転SP録音システムでは、軟弱なワックス盤に録音するため、テープレコーダーのように演奏録音を即座に再生することは不可能であり、試聴盤(テスト・プレス盤)を作成し、後日、演奏者に発売許可を得ることが通例であったが、結果として、ルービンシュタイン、ストコフスキー両者から不許可との回答があった。
不許可の理由は、ルービンシュタインは「ピアノの音が小さい」、ストコフスキーは「オーケストラの音が小さい」という互いに相反するもの。実際の録音を聴くとダイナミックレンジや周波数レンジの狭さなど、SP録音の限界はあるが、一応は適正なバランスで収録されているようだ。確かに一部修正が必要と思われる箇所もあるが、実音よりピアノがクローズアップされた古い録音スタイルのため、実態はルービンシュタインの方が分が悪い。結果として、ルービンシュタインとストコフスキーともに多忙なこともあって再セッションの機会を失い(プロデューサーも投げ出したか)、未発売に終わった。
英デッカのプロデューサーだったジョン・カルショウの自伝によると、1959年にルービンシュタインは、クリップス指揮ロンドン響とモーツァルトのピアノ協奏曲第17番、20番、23番をレコーディングしたが、プレイバックの際(当時はテープ録音)、ルービンシュタインは、またしてもピアノの音が小さ過ぎるとクレームを付け、オーケストラ伴奏を限りなく抑えて再録音を行ったがそれでも満足せず、未発売に終わったと半ばあきれながら記述している。
話を戻すと。ルービンシュタインは翌1946年、ゴルシュマン指揮NBC響と同曲を再録音し、こちらが発売された。1946年録音を聴くと、第1楽章冒頭の和音連打が最初からメゾフォルテ気味に入り、確かにピアノが常にオーケストラより前に出て明確に聴こえる。ただ、このバランスを信用して実演を聴くと失望することになるだろう。また、ピアノがオーケストラを終始リードしているような演奏で、音の大きさももちろんだが、要はルービンシュタイン自らが演奏の主導権を握りたいということだったのではないか。その意味では、ストコフスキーとの当録音は、二大巨頭の両者が対等に渡り合った演奏として価値がある。
チャイコフスキーはNYPの定期演奏会から。3月21・22・24日3回公演の3日目。24日は午後3時開演のマチネーで、前半にプロコフィエフの交響曲第5番、後半がチャイコフスキーというロシア・プログラム。なぜか21・22日の冒頭に演奏されたリャードフ「魔の湖」がカットされているが、ラジオ中継による放送時間の都合かも知れない。当時NYPはロジンスキが音楽監督を務め、定期演奏会の大半を指揮、残りをワルターやセルが客演するという時代。ロジンスキは厳しいリハーサルで知られ、オーケストラのレベルは向上したが、楽員との軋轢は多かった(リハーサルではピストルをポケットに入れていたというのは有名なエピソード)。しかし、ソリストとの間で大きなトラブルを起こすことはなかったようで、ロジンスキの音楽監督時代にも一流のソリストが多く出演している(あの気むずかしいホロヴィッツとも3回共演している)。当録音のチャイコフスキーでも、ルービンシュタインを自由に演奏させつつ、単なる伴奏に終わることなくオーケストラが主張すべき時は前面に出るなど、巧みにまとめ上げているようだ。
アルトゥール・ルービンシュタインは、当ディスク以外にラフマニノフのピアノ協奏曲第2番を、上記のように1946年、1956年、1971年それぞれRCAビクターにスタジオ録音していた。また、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番を1932年英HMV、1946年と1963年それぞれRCAビクターにスタジオ録音していた。

●高音質ステレオ・ライブ
ミュンシュ/ボストン響ほか
ベルリオーズ「ファウストの劫罰」
プレミエ60122DF
ベルリオーズ 劇的物語「ファウストの劫罰」全曲
マルグリート:エリナー・スティーバー(ソプラノ)
ファウスト:ジョン・マッカラム(テノール)
メフィトフェレス:マルシアル・サンゲル(バリトン)
ブランデル:デーヴィッド・ローラン(バス)
バークシャー音楽祭合唱団
シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団
1960年8月14日、タングルウッド・ミュージック・シェード
ステレオ、ライブ
※2枚組。ミュンシュが得意としていたベルリオーズの「ファウストの劫罰」。アメリカ人コレクターの提供音源で、オリジナルはFM放送のエアチェック録音。幸いステレオで収録されており、最終的には非常に優秀な音質で鑑賞できる状態となっているが、音源のオリジナルの状態は、必要な情報こそ記録されているものの、レコーダーの不調によるものか左チャンネルの録音レベルが低く音質もやや異なり、またテープの経年劣化が原因と思われるが、高域が低下して歪みが多く、鑑賞には支障が多い音質だった。ディスク化に当たっては、左右チャンネルのレベルの均等化と音質の均質化、イコライジングによる高域の補正、ヒスノイズ削減等、様々な対策を行った結果、見違えるような音質改善を図ることが出来た。結果的に1960年代初頭のメジャー・レーベルのステレオ録音にも匹敵する高音質で、全く不満のないものとなった。録音の不備や経年劣化はあったものの、元の放送の音質が優秀だったこと、受信環境も良好だったことが幸いした。夏の音楽祭のくつろいだ雰囲気の中での演奏だが、会場ノイズはほとんどなく聴衆のマナーの良さにも感心する。
実は、FM放送を担当したボストンの放送局WGBHは、1959年頃からステレオでボストン響(BSO)の演奏会を収録しており、当ディスクの演奏も当然ステレオで録音・保存されたが、1960年代の社屋火災によって、1959年秋から60年夏までの演奏会のステレオ・テープが失われ、現在は火災を免れた同一演奏のモノラル・テープしか残っていない。当ディスクと同じライブ録音が現在?でもBSOのウェブサイトでダウンロード販売されているが、こちらがモノラルであるのはそのような理由による。当時のリスナーがエアチェックしてくれたおかげで、ミュンシュの貴重なライブをステレオで聴くことができることは誠に幸いである。有名な「ラコッツィ行進曲」の暴力的とも言えるフォルティシモなど(ミュンシュにはフォルティシモよりも大きいミュニシモがあると言われた)、優れたステレオ録音でなければ実感できないだろう。
ミュンシュがベルリオーズを得意としていたことは冒頭に触れたが、規模も大きく長時間を要し(ついでに予算もかかり)、一般には演奏回数が少ない「ファウストの劫罰」についても、全曲をBSOの常任指揮者在任中の1954~1960年に13回演奏している。ただし、さすがに定期的に演奏というわけにはいかなかったらしく、1954年2月の定期演奏会で3回取り上げ(直後に米RCAビクターにスタジオ録音)、同年夏のバークシャー音楽祭で2回。翌1955年3月の定期演奏会で3回(うち1回目はオープン・リハーサル)、続けて同月の米国内ツアーで3回。そして4年空けて当ディスクの録音を含む1960年のバークシャー音楽祭で2回(1回目はオープン・リハーサル)などと集中的に取り上げており、当ディスクの録音は最後の演奏機会に当たるもの。その意味でも貴重な録音と言える。
8月14日の演奏会は、日曜日午後2時30分開演、第2部の後に休憩が入る単一プログラム。なお、当録音は全曲演奏ではあるものの一部にカットがあり、第3部第9場の冒頭からマルグリートの部屋におけるファウストのアリア、第4部第19場「地獄の首都(伏魔殿にて)」末尾の「悪魔たちの合唱」がない。ステレオのエアチェック音源、BSOがダウンロード販売したモノラル音源のいずれも同様の状態だが、前者の第3部第9場については、当日のプログラムにも記載があり、演奏されたものの放送局が収録に失敗したか、演奏されなかったかは不明。一方、後者の「悪魔たちの合唱」は、場面の途中なのでプログラムに記載がなく判断できないが、カット部分以降と、それに続く「エピローグ」が無理なくつながっており、こちらは実際に演奏されなかったようだ。想像だが、ミュンシュがクライマックス場面の緊張感が、合唱が入ることで緩むことを嫌ったためかも知れない。
声楽陣は充実しており、ソプラノのスティーバーとバリトンのサンゲルは、国際的にも著名な歌手で、スティーバーはニューヨーク・メトロポリタン歌劇場(MET)、サンゲルは、第二次世界大戦前はパリ・オペラ座、戦後はMETのそれぞれスター的存在。マルグリートとメフィトフェレスにはまさに適役で、サンゲルは1955年のスタジオ録音にも参加していた。題名役ファウストのマッカラム(1922~2015)は、日本ではあまり知られていないが、1952年から1971年までの約20年間、ボストン交響楽団に定期的に出演し、バッハの「マタイ受難曲」「ヨハネ受難曲」、ハイドンの「天地創造」、ベルリオーズの「レクイエム」「キリストの幼時」、「ロミオとジュリエット」、ベートーヴェン第9などにも参加した実力者だった。ブランデル役のローラン(1928~2004)は、BSOの本拠地を含むニューイングランド地方を中心に、主にオラトリオやリサイタル歌手として活動し、芸術歌曲を得意としていた。名門ブラウン大学で50年間教鞭をとり、全米歌唱指導者協会の会長を務めるなど、米国内では重鎮的存在だった
シャルル・ミュンシュは当ディスク以外に、前記のように1954年米RCAビクターにBSOとスタジオ録音していた。
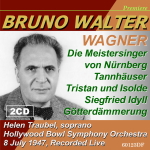
●ブルーノ・ワルター/ハリウッド・ボウル ライブ
ワーグナー 名曲集
プレミエ60123DF
ワーグナー
楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第一幕への前奏曲
歌劇「タンホイザー」序曲と「ヴェーヌスブルクの音楽」
楽劇「トリスタンとイゾルデ」第一幕への前奏曲と「愛の死」
ジークフリート牧歌
楽劇「神々の黄昏」
ジークフリートの葬送行進曲
ブリュンヒルデの自己犠牲
ヘレン・トラウベル(ソプラノ)
ブルーノ・ワルター指揮
ハリウッド・ボウル交響楽団(ロサンゼルス・フィルハーモニック)
1947年7月8日、ハリウッド・ボウル、ロサンゼルス
モノラル、ライブ
※2枚組。ブルーノ・ワルターとハリウッド・ボウル響(後述するように実態はロサンゼルス・フィル)によるワーグナーの名曲ハイライト集。同名の野外劇場におけるライブ。アメリカ人コレクターの提供音源で、ラジオ(FM?)放送を当時のリスナーがアセテート・ディスク・レコーダーでエアチェック録音したものと思われる。放送局所有の音源であれば、1947年という年代を考慮すると、もう少し良好な音質だったと想像されるが、当音源のオリジナルの状態はレンジの狭い貧しい音質。ただし一部を除いてアセテート・ディスク特有のノイズも少なく、一通りの音楽情報は記録されていたため、ディスク化に当たっては、周波数レンジの拡大、低域・高域のバランス改善、ノイズの除去、音量レベル調整等々、様々な対策を行った結果、十分鑑賞に堪える音質へと改善することが出来た。当音源の一部は既に海外でCD化済みだが、コンサート全曲のディスク化は当盤がおそらく初めてと思われ、しかも既出盤とは一線を画す音質となっている。1947年という年代を考慮すれば申し分ないレベルといえる。
なお曲順は、アナウンスが入ったエアチェック音源そのままの配置としているが、別資料では多少異なっており、今後の検証が待たれる。当ディスクの曲順に従えば、「トリスタンとイゾルデ」までが前半、休憩を挟んでジークフリート牧歌以降が後半のプログラムとなる。また「ブリュンヒルデの自己犠牲」は、ソプラノの歌唱が終わった後(燃えさかる薪の中に飛び込んだ後)、ライン川の氾濫やヴァルハラ城の崩落などの管弦楽演奏部分がカットされ、「愛の救済の動機」につなげて終了している。最後のクライマックス・シーンにおけるワルターの指揮が聴けず残念である。
ブルーノ・ワルターは、1933年にドイツでナチス政権が成立以降、ユダヤ人排斥の圧力によりドイツを出国、オーストリア、フランス、スイスを経て、最終的にアメリカ・カリフォルニア州ビヴァリーヒルズに落ち着いた。1920年代に初めて当地に訪れた際、気候が良く、いずれは住んでみたいと思った場所だという。ワルターは、アメリカおいてはニューヨーク・フィルハーモニック(NYP)の音楽顧問を務めるなど、米東海岸のオーケストラの指揮活動が多かったが(東海岸に優秀な団体が多かったこともある)、居住地に近いロサンゼルス・フィル(LAPO)への客演も頻繁に行った。特にLAPOサマー・シーズンに開催される野外劇場ハリウッド・ボウルにおける公演には、移住前の1927年以降30回以上登場している。ちなみにLAPOはハリウッド・ボウル公演の際は、ハリウッド・ボウル交響楽団と名乗っており、当ディスクもその表記に従った。ちなみに1947年当時、ストコフスキーがカリフォルニア近辺のフリーランス演奏家を集めて、ハリウッド・ボウル交響楽団という名称で同じくサマー・シーズンにハリウッド・ボウルで定期演奏会を実施しており、いささか混乱する。同一名称使用による権利の問題などはなかったのだろうか。
当ディスクにおける1947年7月の公演は、ワルターが8日、10日、13日を3回指揮した初日(プログラムはそれぞれ異なる)。8日はオール・ワーグナー・プロで、当時のアメリカにおけるワーグナー・ソプラノの第一人者だったヘレン・トラウベルが加わり、真夏の夜、リラックスしたショー的要素の強いプログラムが多いサマー・シーズンの中では本格的なもの。ちなみにトラウベルは、日本では一般にトローベルと表記されることが多いが、1952年来日時の雑誌インタビュー記事では、自身が「トラウベル」と発音すると明言している。父親がドイツ系であり、ドイツ的発音にこだわったのだろう。
ワルターは、ドイツの歌劇場における修行時代から、人気のあるワーグナー作品を指揮することは日常だったが、渡米後は歌劇の指揮は激減し、ワーグナーはコンサートで取り上げるのみとなった(メトロポリタン歌劇場における上演記録でもモーツァルトは多いもののワーグナーは見当たらない)。個々の作品は別録音が多く存在するものの、これほどまとめてワーグナーを取り上げた上演は珍しく、貴重な記録と言える。
ワルターは渡米後、アメリカのオーケストラ(主にNYP)の気風になじめず、またトスカニーニの影響を受け、演奏スタイルに迷いが出たとも言われているが、これは日本の特定の評論家の見解がなぜか一般化した影響と思われる。実際には、ワルターは(NYPと合併前のニューヨーク交響楽団を含めて)NYPには1923年から1935年までに実に100回以上客演しており、またトスカニーニとは第二次世界大戦前から交流があり、渡米後、アメリカのオーケストラの気風に戸惑ったとか、いきなりトスカニーニから影響を受けたという根拠も乏しい。純粋にレコーディングのみから判断した誤解だったようだ。
ワルターが渡米後にレコーディング契約した米コロンビアのNYP録音が、1940年代末までは、なぜか濁りが多いなど音質に問題があり、ワルターの演奏が十全に再現し切れていないきらいがあり、また、ワルター自身も時代の潮流に合わせて、ヨーロッパ時代の情緒纏綿としたロマン的表現から即物的表現へと急速に変化させ、持ち前の柔和さに加えて、よりスケールアップしていった点があったためだろう。当ディスクのワーグナーは、ワルターがすでに新しい表現様式を身に付け、完成された姿を見ることが出来るといえる。
ブルーノ・ワルターは、ワーグナーの「マイスタージンガー」第一幕への前奏曲を1930年と1959年にスタジオ録音。また、「タンホイザー」序曲とヴェーヌスブルクの音楽を1961年にスタジオ録音。「トリスタンとイゾルデ」第一幕への前奏曲と愛の死を1944年と1953年にライブ録音。ジークフリート牧歌を1924年、1926年、1930年、1935年、1953年、1959年にスタジオ録音したほか、1939年、1947年3月、1949年、1953年、1955年、1957年にライブ録音。ジークフリートの葬送行進曲を1924年と1931年にスタジオ録音。ブリュンヒルデの自己犠牲を1952年にライブ録音していた。
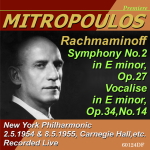
●音質良好 ミトロプーロス/NYPライブ
ラフマニノフ交響曲第2番、ヴォカリーズ
プレミエ60124DF
ラフマニノフ 交響曲第2番、ヴォカリーズ(管弦楽編曲版)
ディミトリ・ミトロプーロス指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
1954年5月2日、ニューヨーク・カーネギー・ホール
1955年5月8日、シアトル・オルフェウム・シアター
モノラル、ライブ
※ミトロプーロスとニューヨーク・フィルハーモニック(NYP)によるラフマニノフ2作品のライブ。アメリカ人コレクターの提供音源で、2曲ともオリジナルはテープ録音でラジオ放送のエアチェックと思われるが、放送局保管音源のコピーの可能性もある。ただし、音源のオリジナルの状態は低域過剰で、ヴァイオリン・セクションが目立たないなどバランスが悪く、テープ・ノイズも多かった。ディスク化に当たっては、音質劣化を避けつつノイズを低減、イコライジングによって周波数バランスを調整、強音と弱音の差が大き過ぎたためダイナミックレンジをわずかに圧縮する等の作業を行った結果、1950年代半ばの水準を上回る良好な音質まで改善することが出来た。一般的な鑑賞には不満がないレベルといえる。
当ディスクの録音当時、ミトロプーロスはNYPの音楽監督。厳しいリハーサルで団員との軋轢が多かった前任ロジンスキの後任として、オーケストラの立て直しを期待され1949年に首席指揮者に就任、実際に優れた指導力により技術レベルを急速に向上させたが、ロジンスキと同様に積極的に近現代作品を取り上げたため、保守的な聴衆からは批判を受けることも多かった。
ラフマニノフの交響曲第2番は、近現代というよりは後期ロマン派の作品であり、ミトロプーロスにとっても意外なレパートリー。しかもピアノ協奏曲第2番などに比べると人気や知名度も格段に落ちるように思えるが、NYPでは、1908年のサンクトペテルブルク初演から間もない1911年に早くも演奏会で取り上げ(指揮はダムロッシュ)、その後も1~2年のブランクはあるものの、1950年代まで継続して演奏会にかけられてきた伝統がある。ミトロプーロスもNYPとは、音楽監督就任前の1944年から1956年まで14回取り上げており、NYPのトレードマーク的存在の一つだったのだろう。ただし、さすがにミトロプーロスは、甘い旋律に満ちあふれた後期ロマン派作品としてではなく、即物的に近現代作品の視点から解釈を試みているようで、優美な旋律を特に目立たせることなく、作品の持つ先進性や革新性に価値を見出しているように感じる。ミトロプーロスによるマーラー演奏を思い起こさせ、当レーベルにあるストコフスキーの豪華絢爛たる演奏(プレミエ60100DF)と比較すると興味深い。
5月2日の公演は4月29日から続く定期公演の4日目で日曜日午後2時30分開演のマチネー。ただし、29・30日と5月1日と2日は微妙にプログラムが異なり、29・30日は、前半がヴェルディ「ナブッコ」序曲、リヒャルト・モハウプトのヴァイオリン協奏曲(世界初演、マイケル・レビン独奏)、休憩を挟んで後半がラフマニノフ。1日は、前半がウェーバー(ジョージ・セル管弦楽編曲)のピアノ・ソナタ第1番第4楽章「無窮動」、ジェームズ・ダルグレイシュのステートメント・フォー・オーケストラ(管弦楽のための声明?)(世界初演)、グラズノフのヴァイオリン協奏曲(マイケル・レビン独奏)、後半がラフマニノフ。当ディスクの2日は、前半がウェーバー(ジョージ・セル管弦楽編曲)のピアノ・ソナタ第1番第4楽章「無窮動」、グラズノフのヴァイオリン協奏曲(マイケル・レビン独奏)、後半がラフマニノフ、アンコールにヴェルディ「ナブッコ」序曲というもの。2日は聴衆に家族連れが多い日曜日のマチネーという理由から、ミトロプーロス好みの現代作品を除き、比較的分かりやすい作品でまとめたのだろう。定期演奏会でアンコールを行うのも異例だが、家族向けサービスか。
ヴォカリーズは、ミトロプーロスが1955年2月の定期演奏会で2回取り上げた後、NYPが同年4月から5月にかけて行った国内ツアー、および9月から10月にかけて行ったヨーロッパ海外ツアーのプログラムに組み込まれた曲目。5月8日はシアトルにおける公演で、プログラムは、前半がウェーバー「魔弾の射手」序曲、ヴォカリーズ、ブラームスのハイドン変奏曲、後半がプロコフィエフの交響曲第5番、アンコールにカバレフスキーの「コラ・ブルニョン」序曲というもの。ヴォカリーズはアンコールではなく正式な演目であるところが興味深く、作品の時代や傾向に一貫性がない点は第二次世界大戦前の伝統を引きずっていたと言える。
ミトロプーロスは、当ディスク以外にラフマニノフの交響曲第2番を1947年米RCAにミネアポリス響とスタジオ録音したほか、1944年にNYPとライブ録音していた。また、ヴォカリーズを1955年2月NYPとライブ録音していた。
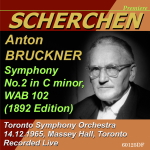
●優秀録音 シェルヘン/トロント響ライブ
ブルックナー 交響曲第2番
プレミエ60125DF
ブルックナー 交響曲第2番(改訂版)
ヘルマン・シェルヘン指揮トロント交響楽団
1965年12月14日、トロント・マッセイ・ホール
モノラル、ライブ
※シェルヘンとトロント響によるブルックナー交響曲第2番。アメリカ人コレクターの提供音源で、ラジオ放送のエアチェックと思われるが、年代が新しいため音質は優秀。ただし、オリジナルの音源はモノラルのFM放送をステレオ・レコーダーで録音したらしく、左右トラック個別にドロップアウトやノイズが入っており、低域過剰で高域不足というバランスの悪さもあった。また放送局側の問題だが、第1・2楽章と第3・4楽章を別のレコーダーで録音したらしく、第3・4楽章の音量が大きく、しかも第3楽章冒頭はレベル・オーバー気味、第4楽章コーダの強奏は録音レベルを下げ、レベル・オーバーを防いでいるという問題があった。ディスク化に当たっては、左右トラックのドロップアウトやノイズ部分をそれぞれ問題がないトラックと差し替え、1・2楽章と3・4楽章の音量レベルを調整。第4楽章コーダの強奏を復元、イコライジングにより周波数バランスを調整する等の作業を行った結果、モノラルながら、鑑賞する上で不満のない状態とすることが出来た。
ヘルマン・シェルヘンは、古くから米ウェストミンスター・レーベルに大量の録音を行う一方、スイスの自宅に音楽スタジオを開設し、現代作品の研究や実験を行ったこと、多くの優秀な弟子を育てたことが主な経歴として語られてきたが、日本では、1988年に仏ハルモニア・ムンディが、フランス国立放送管とのマーラー交響曲第5番のライブ録音がCD化、また1990年にルガーノ・スイス・イタリア語放送管と放送用に録音したベートーヴェンの交響曲全曲がCD化されると、いずれもおそるべき個性的な演奏で一躍注目されることとなった。
シェルヘンは、若い頃はベルリン・フィルなどでヴィオラ奏者として活動、ラトヴィアのリガやケーニヒスベルクの歌劇場で修行を重ねるなど、ドイツの伝統的な指揮者のキャリアを積んでいた。しかし1933年のナチス政権成立後、シェルヘン自身はユダヤ系ではなかったが、ナチスを嫌ってスイスに拠点を移し、ヴィンタートゥール管やベロミュンスター管などの指揮者を歴任するも、当初はドイツ国籍であったこと、シェルヘンの権威主義的性格が災いして、シェルヘン自身がオーケストラ・メンバーと良い関係を築けなかったこともあり短期間で辞任。1950年以降はフリーランスとして活動した。
ライナーやセル、ロジンスキ、若い頃のマルケヴィッチなど、優れた指揮者であってもオーケストラ・メンバーと良好な関係を築けない人物は数多く、クレンペラーなどは奇行やスキャンダルまで起こして解任されたりしているが、かつてはオーケストラの経営側(理事会など)や聴衆などの支持があれば、指揮者としてのポストは維持できたから、シェルヘンの実力を持ってすれば、一定ランク以上のオーケストラの常任指揮者を任されても不思議ではなかった。ただ、シェルヘンの活動を見ると、1916年にリガ歌劇場の契約が終わり、ドイツに戻ると、1920年代初頭にはグロトリアン・シュタインヴェーグ・オーケストラ(ギーゼキングが愛用したというピアノ・メーカーがスポンサーか)を育成、1930年代初頭に「ムジカ・ビバ」オーケストラを設立するなど、ゼロから音楽を作り上げることを好んだようだ。前述のヴィンタートゥール管もセミプロとアマチュアの音楽家で構成されており、この団体を短期間で夏のポップスオーケストラから、新しい音楽祭に出演したり、最近の難曲を初演できるオーケストラに育て上げたという。この辺りにシェルヘンは教育者としての喜びを見出していたのかも知れず、既に完成されたオーケストラと長く付き合う気はなかったのだろう。同様にシェルヘンが現代音楽を紹介することは、聴衆にとってもオーケストラにとっても教育的であったといえる。
ちなみに資料の出典は不明だが、フルトヴェングラー亡き後、ベルリン・フィルの後任指揮者候補の一人にシェルヘンが挙げられていたという。フルトヴェングラーが第二次世界大戦後に演奏活動を禁止された時期、ベルリン・フィルの暫定的首席指揮者を務めたボルヒャルトの師匠がシェルヘンだったという関係かも知れない。もちろん最有力候補はカラヤンであり、シェルヘンが後任となる可能性は限りなく低かったと思われるが、仮にシェルヘン/ベルリン・フィルのコンビが誕生していたら、ベルリン・フィルは、ロスバウトが指揮する南西ドイツ放送響と双璧をなす、現代音楽の実験場となっていたかも知れず大変興味深い。
当ディスクに聴くブルックナーの交響曲第2番は、現在確認されているシェルヘン唯一のブルックナー録音である。ブルックナーは現代音楽ではないが、当時の北米ではポピュラーとは言えず、しかも初期作品はほとんど演奏機会がなかったと思われ、トロントのオーケストラも聴衆も初体験の場となっただろうから、シェルヘンの求めていた理想と合致する。当時、交響曲第2番はハース版が1938年に、より原典に忠実なノヴァーク版が当録音年の1965年に出版されていたが、トロント響では改訂版しか用意できなかったようだ。それでもブルックナーの初期作品に見られる荒削りな前衛性は、トロント響のメンバーや聴衆には刺激的だったろう(もしくは退屈だったか)。ちなみにシェルヘンは約8か月前の4月にもトロント響に客演してマーラーの交響曲第7番を演奏しており、こちらも挑戦的な公演だったと思われる。なお、シェルヘンが客演した1965年12月は、小澤征爾が首席指揮者に就任した直後に当たる。
当ディスクに聴く演奏は、伝統的・一般的なブルックナー演奏とは一線を画すもので、同年1月から3月にかけて行ったルガーノ・スイス・イタリア語放送管とのベートーヴェンの交響曲全曲演奏と同様、表現主義的というかマーラーやシェーンベルクの目を通したブルックナー演奏とも言うべきもの。こんな演奏はブルックナーではないという意見が出てもおかしくないが、ブルックナー初期作品の特徴を、円熟した後期作品的なオブラートに包まず、むき出しに表現した点に意義があると言える。
上記のように、ヘルマン・シェルヘンはブルックナーの交響曲第2番のスタジオ録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音である。

●優秀録音 ストコフスキー/アメリカ響 ステレオ・ライブ
チャイコフスキー交響曲第5番 ファリャ「三角帽子」組曲
プレミエ60126DF
チャイコフスキー 交響曲第5番
ファリャ バレエ組曲「三角帽子」
レオポルド・ストコフスキー指揮アメリカ交響楽団
1967年12月3日・11月19日、ニューヨーク・カーネギー・ホール
ステレオ、ライブ
※ストコフスキーとアメリカ響による「音の饗宴」。チャイコフスキー交響曲第5番とファリャ「三角帽子」組曲のステレオ・ライブ録音。アメリカ人コレクターの提供音源で、FM放送のエアチェックと思われるが、良好な受信環境の元、優れた機材を使用したためか音質は極めて優秀。ただし、チャイコフスキーのオリジナル音源は、独特のマイクセッティングのせいか、ステレオ効果が強すぎてセンターの音像が弱く(いわゆる中抜け)、2群のオーケストラが左右に分かれて演奏しているように聴こえた。ストコフスキー自ら率いるオーケストラのコンサートであるから彼自身の意図によるものと思われるが、さすがにこれではやりすぎで違和感があり、コンサート会場(カーネギー・ホール)でもこのような状態で響いてはいなかっただろう、ディスク化に当たっては、センター部分の要素を増やすために、極端なステレオ効果を若干弱める措置を行った。ただしストコフスキーの意図を尊重?し、操作は一定程度に抑えた。措置後でも一部の木管楽器は右チャンネルの右端から聴こえるなど独特のスタイル。実際に楽器がそのように配置されていたのだろうか。また、第2楽章のホルン・ソロが異常に小さく聴こえるが、これもストコフスキーの意図かもしれないが、こちらも若干ボリュームアップしている。それに比べるとファリャはまともな録音スタイル。やや低域不足だったため、イコライジング等で補正した。2曲とも会場ノイズはほぼ皆無。なお、かつて海外盤でCD化されていたチャイコフスキーは、誤って12月4日録音と表記されていたが同一演奏である。
ストコフスキーのチャイコフスキー交響曲第5番といえば、彼の得意中の得意のレパートリーで、レコーディング回数も多く、リピートのカットやダイナミクスの変更など、ストコフスキー編曲と言って差し支えないほどの改変があることで有名だ。当ディスクは自ら設立したアメリカ響との現在確認されている唯一の録音であり、有名な1966年の英デッカ録音の翌年の演奏である。英デッカ録音は「フェイズ4」という、現在普及しているマルチトラック録音の先駆けで当時最先端の録音方式で行われたが、結果として、かなり誇張はあるものの当時のデッカ・サウンドの範疇に収まっており、ストコフスキーも録音にはあまり口出しせずにエンジニアに任せた節が見られる。その点、当録音は、基本的解釈は変わらないが、先に述べた独特のマイクセッティングなど、よりストコフスキーの意図が徹底した録音と言うことが言える。
一説によるとストコフスキーは、その長いコンサートキャリアでチャイコフスキーの交響曲第5番を93回取り上げたという。1910年オハイオ州デイトンで、当時首席指揮者を務めていたシンシナティ響と初めて演奏。最後はコンサート引退の前年、1973年ロンドンでインターナショナル・ユース・オーケストラとの共演であった。概算すると64年間で年平均1.45回取り上げていたことになり、定期演奏会などの複数回公演やツアーで集中的・連続的に演奏する場合もあり、毎年演奏していたわけではないがさすがに多い。、ただ、上には上がいるものでムラヴィンスキーは生涯に133回演奏したというが、こちらは晩年にレパートリーを極度に絞った結果と言える。
アメリカ響は、ストコフスキーが最後に音楽監督を務めた団体で、1962年、彼が80歳の時に自ら設立、当初は常設の固定メンバーはおらず、演奏会開催の度にフリーランスの演奏家を契約する形態を取っていた。理由としてストコフスキーは「若い音楽家にオーケストラで演奏する機会を与えることが目的」としていたが、固定費節減という目的もあったようだ。ただし、このシステムでは夏の音楽祭の臨時編成オーケストラと同様に、アンサンブルが急ごしらえとなり、よほどのベテラン奏者を揃えるか入念にリハーサルを行わないと、演奏の完成度は低く、オーケストラとしても成長が見込めない。ストコフスキーという名手が巧みにリードしたからこそ実現できた形態といえる。そのため1972年、ストコフスキーが退任し、秋山和慶が音楽監督を引き継ぐと常設メンバーを雇うオーソドックスな制度へ変更された。
12月3日のコンサートは、3・4日2回定期公演の1日目。前半がカール・ラッグルズの「太陽を踏む者」、エルネスト・ブロッホ「シェロモ」(チェロ独奏ハーヴェイ・シャピロ)、後半にチャイコフスキー。11月19日のコンサートは、19・20日2回定期公演の1日目、前半の冒頭にファリャ、ラヴェルのスペイン狂詩曲、ドビュッシーの「イベリア」、後半にグリエールの交響曲第3番「イリヤー・ムーロメツ」という、いずれも意欲的・挑戦的プログラム。ストコフスキーは決して大衆受けする音楽ばかりを提供していたわけではなく、ある種の啓蒙的・教育的意図を持つことが、彼のスタンスだったのだろう。その点では意外にも、演奏スタイルや音楽への考え方が全く対極にあると思えるジョージ・セルと共通するところがある。
とはいうものの、当ディスクに聴くチャイコフスキーはデフォルメの塊と称してもよく、メンゲルベルクなどの録音と双璧を成すもので、作品の姿を忠実・穏当に提供するなどという意図は感じられず、ムラヴィンスキーによる峻厳な一連の録音(これはこれで多少改変があるようだが)とは対極に位置するものといえる。
ストコフスキーは、チャイコフスキーの交響曲第5番を、1934年米RCAビクターにフィラデルフィア管、1953年同じく米RCAビクターにストコフスキー交響楽団(実態はRCAビクター響か)、1966年英デッカにニュー・フィルハーモニア管とスタジオ録音したほか、
また、第2楽章のみを1923年米RCAビクターにフィラデルフィア管、1947年同じく米RCAビクターにストコフスキー交響楽団とスタジオ録音、1942年NBC響、1952年北ドイツ放送響、1952年デトロイト響、1955年シュトゥットガルト放送響、1973年インターナショナル・フェスティバル・ユース管とライブ録音していた。一方、ファリャの「三角帽子」組曲を1953年米RCAビクターにサンフランシスコ響とスタジオ録音したが未発売に終わっている。

●優秀録音 ミュンシュ/ボストン響 ステレオ・ライブ
レスピーギ 交響詩「ローマの松」、フォーレ「ペレアスとメリザンド」組曲ほか
プレミエ60127DF
レスピーギ 交響詩「ローマの松」
フォーレ「ペレアスとメリザンド」組曲
ルーセル 組曲ヘ長調
シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団
1961年8月6日、タングルウッド・ミュージック・シェド
1959年3月7日、1958年3月8日、ボストン・シンフォニー・ホール
ステレオ、ライブ
※ミュンシュ/ボストン響(BSO)による近代イタリア・フランスの名曲集。すべてステレオ・ライブ録音。アメリカ人コレクターの提供音源で、いずれもFM放送のエアチェックと思われるが、ノイズレスで極めて良好な音質。ただしオリジナルの状態では、レスピーギは、一部BSOのエアチェック音源独特の傾向で(エアチェックしたリスナーの機器の特徴?)、高域の一部にディップ(落ち込み)があり、フォルティシモの際にパワー不足というか「空振り」になる傾向があった。また、ルーセルは低域が強すぎたほか、ミュンシュのフォルティシモが大きすぎるため、弱音を基準にボリューム設定すると強音が「近所迷惑」となる問題があった。フォーレは曲想もあるが穏健な音質で問題ない状態。
ディスク化に当たっては、3曲とも周波数レンジをFM放送の周波数上限15khzからCDの上限20khzへ拡大。レスピーギはイコライジング等により高域のディップを解消して“パワーアップ”。ルーセルについては、低域の周波数バランスを調整、コンプレッサーを慎重に使用することで適切なダイナミックレンジを確保した。
結果として、1960年前後のメジャー・レーベルの初期ステレオ・スタジオ録音と同等の音質を実現することが出来た。特にレスピーギは1961年のライブ録音とは思えない高音質。放送側のマイク・セッティング、受信環境、録音機器のいずれもが優れていたのだろうが、オーディオ的鑑賞にも十分堪えるもの。いずれの演奏も会場ノイズはほぼ皆無。
1961年のレスピーギは、毎年夏に開催されるバークシャー音楽祭から。午後2時半開演で前半にベートーヴェンの交響曲第7番、休憩を挟んで後半にバルトークのヴィオラ協奏曲(BSOヴィオラ首席のジョゼフ・ド・パスクワーレ独奏)、続けてレスピーギというプログラム。統一性のない、ややまとまりに欠ける印象もあるが、やや晦渋なバルトークの後に、派手なレスピーギで盛り上げて演奏会を終える演出。夏の音楽祭だから細かいことは言わずに楽しもうという、ミュンシュらしい大らかさを感じる。
「ローマの松」は1960年12月の定期演奏会で初めて取り上げ、8月の当演奏はその再演でBSO常任指揮者最後期の演奏に当たるが、前日5日のオープン・リハーサルを含めても4回しか取り上げなかった珍しいレパートリーである。レスピーギ自体取り上げることが少なく、「ローマの松」以外では、「リュートのための古風な舞曲とアリア」組曲第1番を1955年10月に取り上げたのみ。「アッピア街道の松」のクレシェンドなど“ミュンシュ向き”に思えるが、後述するように1967年に英デッカにスタジオ録音するなど、晩年にその価値を発見・評価したのかも知れない。ただ、同曲の代表盤として有名なトスカニーニ/NBC響の演奏と比較すると、強靱なカンタービレと鮮烈な色彩で塗り込めたトスカニーニ盤に対して、ミュンシュはパワフルながらも、どこかドビュッシー的な淡い色彩も感じるところが興味深く、「ローマの松」がフランス印象派の影響を受けた作品であることを再認識させる。ちなみにアンセルメの録音では更に柔らかくドビュッシー風に聴こえるが、指揮者の出自と教育による解釈の違いが現代よりも明確に現れていた「古き良き時代」だったとも言える。
ちなみにBSO前任指揮者のクーセヴィツキーがラヴェルに編曲を委嘱した「展覧会の絵」などは、BSO縁(ゆかり)の作品でもあり、当然ミュンシュ得意のレパートリーとなっても不思議ではないが(「キエフの大きな門」のクライマックスなどまさしくミュンシュ向きだ)、BSO常任指揮者在任当時、この作品の演奏は副指揮者兼コンサート・マスターのリチャード・バージンや客演のマルケヴィッチ、アンセルメなどに任せており、作品に対して何らかの美意識の相違があったのだろうか。同様にクーセヴィツキーがバルトークに委嘱した「管弦楽のための協奏曲」も取り上げておらず、前任者のカラーを消す対抗意識があったのかも知れない。
1959年のフォーレは、ボストン・シンフォニー・ホールにおける定期演奏会から。6日・7日2回公演の2日目、午後8時半開演で、最初にフォーレ、続いてオネゲルの交響曲第4番、休憩を挟んで後半にブラームスのヴァイオリン協奏曲(クリスチャン・フェラス独奏)という、やや短いプログラム。
ミュンシュは「ペレアスとメリザンド」組曲を、BSO常任指揮者就任直後の1947年11月に最初に取り上げた後、常任指揮者退任後の1966年12月まで計30回(ほかにオープン・リハーサル6回)と多く演奏しており、2回レコーディングを行うなど好みの作品だったようだ。
1958年のルーセルもボストン・シンフォニー・ホールにおける定期演奏会から。7日・8日2回公演の2日目、午後8時半開演で、前半にヘンデルの「水上の音楽」組曲、アンリ・ラボーの交響曲第3番、休憩を挟んで後半にウォルター・ピストンのヴィオラ協奏曲(世界初演、BSOヴィオラ首席のジョゼフ・ド・パスクワーレ独奏)、最後にルーセルの組曲ヘ長調という、なかなか意欲的プログラム。ミュンシュはBSO在任中ルーセルを多く取り上げており、その多くは「バッカスとアリアーヌ」組曲だが、組曲ヘ長調についても在任中は1955年4月に2回、1958年3月に5回(うち1回が当録音)、同年7月に1回、BSO常任指揮者退任後の1966年3月に2回と、頻繁というわけではないが、それほどポピュラーとは言えない作品をしばしば取り上げていた。
シャルル・ミュンシュは前記のように、当ディスク以外にレスピーギの「ローマの松」を1967年英デッカにニュー・フィルハーモニア管とスタジオ録音したほか、1960年にBSOとライブ録音していた。また、フォーレの「ペレアスとメリザンド」組曲を1947年英デッカにロンドン・フィルと、1963年米CBSコロンビアにフィラデルフィア管とスタジオ録音したほか、1959年4月、1963年、1966年10月と12月、1967年2月にそれぞれライブ録音していた。

●優秀録音 ミュンシュ/ボストン響 ステレオ・ライブ
ベルリオーズ 幻想交響曲、ベンヴェヌート・チェッリーニ序曲ほか
プレミエ60128DF
ベルリオーズ
幻想交響曲
歌劇「ベンヴェヌート・チェッリーニ」序曲
歌劇「トロイ人」から第4幕「王の狩と嵐」
シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団
1962年3月30日、1959年2月28日、1963年1月26日
ボストン・シンフォニー・ホール
ステレオ、ライブ
※シャルル・ミュンシュ得意中の得意とも言えるベルリオーズ名曲集。すべてステレオ・ライブ録音でアメリカ人コレクターの提供音源。いずれもFM放送のエアチェックだが一応は良好な音質。ただしオリジナルの状態では、幻想交響曲は、ヒス・ノイズが多い上に受信障害によるパルス・ノイズが若干混ざるほか、高域の一部にディップ(周波数の落ち込み)があり、金管などが伸びきらずフォルティシモが物足りない印象があった。迫力あるミュンシュの演奏にとっては少々問題と言える。また「ベンヴェヌート・チェッリーニ」序曲も交響曲と同様の音質傾向。「トロイ人」は上記2作品よりは問題が少なかったが、ヒス・ノイズが多く少々ざらついた音質だった。
ディスク化に当たっては、3曲とも周波数レンジをFM放送の周波数上限15khzからCDの上限20khzへ拡大。幻想交響曲については、音質損ねないようにソフトウェアでヒス・ノイズとパルス・ノイズを低減、イコライジング等により高域の周波数バランスを適正化、ほかの2作品も同様にノイズ低減と周波数バランスの適正化を行った。
音質改善の結果、当時のメジャー・レーベルのステレオ・スタジオ録音と同等の音質を実現することが出来た。ただし幻想交響曲などは、いわゆる「きれいな音」ではない、尋常ならざる狂気を秘めたような音質が期待されるが、幸いオリジナル音源のレコーダーの録音レベル設定が最適(レベル・オーバー寸前)だったらしく、最大限の情報を記録してくれていたため、迫力ある音質を再現することが出来た。一般的な鑑賞にはまず不満は出ないだろう。
1962年の幻想交響曲は、ボストン・シンフォニー・ホールにおける定期演奏会から。3月30・31日2回公演の1日目(前日29日にオープン・リハーサルがあった)、金曜午後2時15分の開演で、前半に幻想交響曲、休憩を挟んで後半にドビュッシーの「海」、ラヴェルの「ダフニスとクロエ」第2組曲という、オール・フランス作品ながらヘビーなプログラム構成。前半だけでも相当なエネルギーを消耗しそうだが、聴衆にとってもタフなコンサートだったろう。
ミュンシュと言えば「幻想」という定番の作品だが、ボストン響(BSO)とは、常任指揮者就任2年目の1950年11月に最初に取り上げ、その後、1953年と1956年、1961年を除いて毎年演奏。常任指揮者退任後も1964年2月に客演で3回取り上げており、合計70回も演奏している。BSO後任の常任指揮者ラインスドルフがミュンシュ時代はレパートリーが偏りすぎていたと批判したが、確かにそれも理解できる。しかし、ミュンシュ本人の趣味もあったろうが、聴衆やオーケストラ側からの要望も多かったようだ。また驚くべきことは、1950年から客演で演奏した1964年まで、ミュンシュ以外に誰も「幻想」を指揮していないこと。ミュンシュ在任当時は、モントゥーやアンセルメなどフランス系指揮者の客演も多かったが、ミュンシュがほぼ毎年のように演奏していると、他の指揮者が入り込む余地はなかったのだろう。ちなみにミュンシュ以後に初めて「幻想」を演奏したのは1965年8月のマルティノンだった。
当ディスクの演奏が行われた1962年3月は、ミュンシュのBSO常任指揮者としての最終シーズンに当たり、4月に「幻想」を含むプログラムで国内ツアーと残りの定期演奏会を行い、その間の4月9日に米RCAビクターにスタジオ録音、8月のバークシャー・フェスティバルで常任時代最後の「幻想」を演奏している。ということで当ディスクの演奏は、言わばBSOとの「幻想」の最終形を示したものと考えられる。
1959年の「ベンヴェヌート・チェッリーニ」序曲は、同じくボストン・シンフォニー・ホールにおける定期演奏会から。2月27・28日の2回公演の2日目。前半冒頭に「ベンヴェヌート・チェッリーニ」序曲、続けてブラームスのセレナーデ第1番抜粋(プレミエ60020DFでディスク化済み)、休憩を挟んで後半にR・シュトラウスの「家庭交響曲」(こちらもプレミエ60067DFでディスク化済み)というややユニークなプログラム。ミュンシュが「ベンヴェヌート・チェッリーニ」序曲を取り上げたのは意外に遅く、当演奏前日の2月27日が最初で、その次はBSO常任指揮者退任後の1965年2月だった。この時は定期演奏会と国内ツアー含めて8回演奏している。ちなみに当時の常任指揮者ラインスドルフを差し置いて退任したミュンシュが国内ツアーを行うとは、ラインスドルフでは集客が期待できない。要するに人気がなかったと言うことだろうか。
1963年の「トロイ人」から第4幕「王の狩と嵐」もボストン・シンフォニー・ホールにおける定期演奏会から。1月25・26日の2回公演の2日目。前半にオネゲルの交響曲第2番、イベールの交響的楽章「ボストニアーナ」(世界初演)、休憩を挟んで後半に「王の狩と嵐」、続けてサン・サーンスの交響曲第3番というミュンシュらしいプログラム。イベールの「ボストニアーナ」は、ミュンシュがイベールに交響曲として委嘱したが、作曲家の死去によって1楽章のみの未完成作品となったもの。
ミュンシュは「王の狩と嵐」を早くから取り上げており、1952年と1953年の定期演奏会と国内ツアーで17回、1954年のバークシャー音楽祭で2回、1959年の定期演奏会と国内ツアーで9回、そして当ディスクの演奏を含む1963年に3回と、プログラムに組み込みやすかったのか、意外に多く演奏している。
シャルル・ミュンシュは、ベルリオーズの「幻想交響曲」を1949年仏コロンビアにフランス国立放送管(同一番号で7月ライブ録音と9月スタジオ録音の2種あるらしい)と、1954年と1962年米RCAビクターにBSOと、1966年ハンガリー・フンガロトンにハンガリー国立放送管と、1967年仏EMIにパリ管とスタジオ録音したほか、1954年、1960年3月と5月、1962年4月と12月、1963年6月と12月、1964年2月、1965年1月、1966年2月と7月、1967年11月にライブ録音していた。また、「ベンヴェヌート・チェッリーニ」序曲を1946年英デッカにパリ音楽院管と、1959年米RCAビクターにBSOとスタジオ録音したほか、1965年2月、1966年9月にライブ録音していた。また、「トロイ人」から第4幕「王の狩と嵐」を1949年英デッカにパリ音楽院管と、1959年米RCAビクターにBSOとスタジオ録音したほか、1963年2月にライブ録音していた。
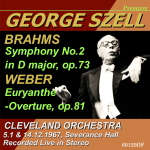
●優秀録音 セル/クリーヴランド管 ステレオ・ライブ
ブラームス交響曲第2番 ウェーバー「オイリアンテ」序曲
プレミエ60129DF
ブラームス 交響曲第2番
ウェーバー 歌劇「オイリアンテ」序曲
ジョージ・セル指揮クリーヴランド管弦楽団
1967年1月5日・12月14日、クリーヴランド・セヴェランス・ホール
ステレオ、ライブ
※セル/クリーヴランド管によるブラームス交響曲第2番とウェーバー「オイリアンテ」序曲のステレオ・ライブ録音。アメリカ人コレクターの提供音源で、いずれもFM放送のエアチェックと思われ、基本的には良好な音質。ただしオリジナルの状態は、交響曲では低域過剰でブーミーな一方、高域にピークがあり耳障り、第2・3楽章の一部に受信障害と思われるパルス・ノイズが混入、わずかにドロップアウト(音切れ)も存在した。また序曲は、ノイズはないものの強音は大きすぎ、弱音は小さすぎる(ダイナミックレンジが広すぎる)という問題があった。
ディスク化に当たっては、交響曲については、イコライジング等により高・低域の周波数バランスを改善、同時に周波数レンジをFM放送の上限15khzからCDの上限20khz程度まで拡大。パルス・ノイズについては、ソフトウェアによって音質を損ねずに除去、ドロップアウト解消。序曲は、コンプレッサーを慎重に使用することで家庭内での鑑賞に適切なダイナミックレンジを確保した。
以上の対策による結果、1960年代中期のメジャー・レーベルのスタジオ録音に匹敵する音質を実現することが出来た。なお交響曲は、おそらく収録時にホールトーン専用マイクの録音レベルが少々高かったのだろうか、若干残響が多めだが、一方で細かい音もよく捉えているおり解像度は十分に高く、この作品の性格にはふさわしい音質。序曲は、セル/クリーヴランド管によるライブ録音の典型的な音質で、歯切れが良くスピード感あふれるもの。いずれにしても一般的な鑑賞には不満のない状態。会場ノイズもほぼ皆無。
1967年というと、セル/クリーヴランド管の活動末期にさしかかった頃であり、1965年のヨーロッパ・ツアーでも高い評価を受け、世界最高峰のオーケストラの一つという名声を確立した時期にあたる。交響曲第2番は当演奏の翌日、1月6日に米コロンビアにスタジオ録音しており、レコーディングのリハーサルを兼ねた演奏でもある。ちなみに1966年4月7日録音とする別資料もあるが、ここではより信頼性の高い資料に従った。なお、海外の既出盤では第4楽章の演奏終了を待たずに聴衆の拍手が被さっていたという情報があるが、当時のクリーヴランド管の(冷静な?)聴衆にはそのような習慣はなかったと思われ(ミュンシュ/ボストン響の圧倒的な「爆演」ではよく見られた)、おそらく演奏直後に入るアナウンスを消すための対策と想像される。当演奏のオリジナル音源は、アナウンスは拍手が一定程度続いた後に入っており、既出盤とは異なった期日の放送であろう。
1月5日の演奏会は、5・7日の2回公演の定期演奏会の1日目。前半はシューベルトの「ロザムンデ」序曲、モーツァルトのピアノ協奏曲第22番(ペーター・フランクル独奏)、休憩を挟んで後半に交響曲第2番という、いかにもセルらしいオーソドックスな独墺系プログラム。交響曲の演奏は当然スタジオ録音と酷似しているが、マイク・セッティングが異なり、さらにライブという状況もあり、冷静なスタジオ録音と比べると、より感興豊かな印象。
一方、12月14日の演奏会は、14・16日の2回公演の定期演奏会の1日目。前半はオイリアンテ序曲、ブラームスのヴァイオリン協奏曲(ダヴィード・オイストラフ独奏)、休憩を挟んで後半は、オイストラフ指揮でチャイコフスキーの交響曲第5番という、やや変則的なプログラム。おそらくオイストラフが招聘に当たって、指揮もさせることを条件にしたと思われる。オイストラフは早期からヴァイオリンと並行して指揮活動も行っていたが、晩年は心臓を患っており、活動の中心を、身体に負担の大きいヴァイオリンから指揮へ移したかったのだろう。セルはオイストラフやギレリス、ロストロポーヴィチらと懇意にしており共演も多く(リヒテルがいないのが不思議だ)、また1967~1968年シーズンは、クリーヴランド管創立50周年記念シーズンに当たり、そのような祝祭の意味も兼ねた客演指揮となったと想像される。
「オイリアンテ」序曲はセルがクリーヴランド管とスタジオ録音を行わなかった作品。後述するように1952年にニューヨーク・フィルとスタジオ録音しているが、キャリア後期の演奏を知る貴重な録音でもある。
セルにとって、ブラームスはモーツァルトやベートーヴェンなどと並んでレパートリーの中心的存在。クリーブランド管の定期演奏会では、交響曲第2番は同管への音楽監督就任間もない1946年10月から、最後の演奏となった1969年5月までの24シーズンに13回(定期演奏会は2回公演なので実際の演奏は26回)取り上げており、しかも2年続くこともあるが、1シーズン空くと必ず取り上げるという几帳面さ。当然、同曲は客演指揮者も演奏した可能性があり、自身の好みというよりも、オーケストラ・トレーナーとしてブラームスは必須であるという認識で継続的にプログラミングしたのだろう。
セルは当ディスク以外にブラームスの交響曲第2番を1925年英パーロフォンにベルリン国立歌劇場管と、1967年米コロンビアにクリーヴランド管とスタジオ録音したほか、1958年ケルン放送響とライブ録音していた。また、ウェーバーの「オイリアンテ」序曲を1952年米コロンビアにニューヨーク・フィルとスタジオ録音していた。

●音質良好 ヴェラ・フランチェスキ モーツァルト ピアノ協奏曲第20番ほか
1953年・1955年ライブ
プレミエ60130DF
モーツァルト ピアノ協奏曲第20番
チャイコフスキー 協奏的幻想曲
ヴェラ・フランチェスキ(ピアノ)
ヴラディミール・ゴルシュマン指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
ピエール・モントゥー指揮ボストン交響楽団
1953年2月1日、ニューヨーク・カーネギー・ホール
1955年2月4日、ボストン・シンフォニー・ホール
モノラル、ライブ
※キャリア半ばで惜しくも早世したヴェラ・フランチェスキの貴重なライブ録音。アメリカ人コレクターからの提供音源で、オリジナルはいずれもエアチェックと思われるが、良好な受信環境の元、高品質な機材を使用して録音されたと想像され、放送局所有のオリジナル・テープに匹敵すると思われる高音質で、1950年代半ばの録音水準を上回る。ただし2曲とも若干高域寄りで低音不足、ヒスノイズも若干目立ったため、ディスク化に当たってはイコライジングでバランスを調整し、ソフトウェアで音質劣化を防ぎつつヒスノイズを低減した。結果として、鑑賞には不満のない不満のない状態とすることが出来た。
ヴェラ・フランチェスキ(1926~1966)はサンフランシスコ生まれのイタリア系アメリカ人ピアニスト。1936年に一家で両親の母国イタリアに戻ったため、1939年にローマの聖チェチーリア音楽院でカルロ・ゼッキやアルフレード・カゼッラに師事。在学中の1939年に13歳でパリでコンサート・デビュー、翌1940年にイタリア・ミラノでも公演を行った。なお、ニューヨーク・カーネギー・ホールの公演記録によると、1942年12月にニューヨーク・リトル・オーケストラ(現在も活動中の伝統ある室内管弦楽団)とも共演、モーツァルトのピアノ協奏曲第20番とホヴァネスのPrayerという作品を演奏しているというが、第二次世界大戦中、ドイツの潜水艦Uボートの攻撃にさらされる危険な大西洋を、演奏のためだけに往復できたのか疑問で、年代は1945年以降の誤りかも知れない(他の同姓同名の演奏家は確認できなかった)。
1947年以降は伊パーロフォンやチェトラにレコーディングも行った。ただし、スカルラッティやチマローザ、ガルッピ、ペルゴレージなどバロックや前古典派、またはイジノ・ロッビアーニやピック=マンジャガッリ、ヴァージル・トムソン、アブラム・チェイシンズといった当時の現代作品ばかりで、新人の若手演奏家がレパートリーを指定できたとは思えず、商業販売よりも教育・文化振興政策的な目的で録音された可能性もある。ただし前古典派作品については後年、米ウェストミンスター・レーベルに集中的にレコーディングしており、得意のレパートリーだったのだろう。
フランチェスキはこれらのレコーディングと同時期にアメリカに戻り、マンハッタン音楽院でハロルド・バウアーやカール・フリードベルクに短期間師事して修行を終えた。1948年にはモントゥー指揮サンフランシスコ響と初共演。モントゥーはフランチェスキの才能を評価し、その後は当ディスクに聴くようにボストン響における自身の公演でも共演した。
1953年の演奏会はニューヨーク・フィルの定期公演から。1月31日・2月1日2回公演の2日目。前記したニューヨーク・リトル・オーケストラとの公演の評判が良かったためだろうか、同じくモーツァルトのピアノ協奏曲第20番を演奏している。フランチェスキは、当時27歳とは思えない完成された演奏を行っており、テンポ設定や、ピアノを響かせすぎずオーケストラに溶け込ませる音作り、なめらかだが芯のあるフレージングなど、どことなくクララ・ハスキルを思い起こさせるスタイル。もちろんハスキルが残した同曲の最も早い時期の録音でもハスキル55歳の時であり、円熟度に明らかに差はあるが、ハスキルが若い頃はこのような演奏を行っていたのではないかと想像させるものがある。指揮のゴルシュマンは、アルトゥール・ルービンシュタインがレコーディングで指名したほど、協奏曲などの伴奏指揮に優れており、彼の巧みなサポートも演奏に貢献している。
1955年の演奏会はボストン交響楽団の定期公演から。2月4日・5日2回公演の2日目。ただし、2日にオープン・リハーサル、さらに1日に国内ツアーでロング・アイランド州プロヴィデンス、9日にニューヨーク・カーネギー・ホールでも公演を行っている。この時は1日のプロヴィデンス公演を除き、その他の公演はオール・チャイコフスキー・プログラムとして、前半にハムレット序曲、組曲モーツァルティアーナ、協奏的幻想曲、休憩を挟んで後半に交響曲第6番「悲愴」という意欲的な企画だった。通常のプログラミングであれば交響曲第6番以外に、ピアノ協奏曲第1番やヴァイオリン協奏曲、白鳥の湖などのバレエ組曲、「イタリア奇想曲」「ロミオとジュリエット」などで構成すれば、聴衆受けすると思うが、知名度は低くても、良い作品があることを知らしめるという啓蒙的発想だろう。
なかでも協奏的幻想曲は、現在でもほとんど演奏されない珍しい作品だが、近年は、広く演奏される価値がある作品との再評価が進んでいる。形式的にはピアノ協奏曲であり、少なくともピアノ協奏曲第2番よりは完成度が高いと言われている。フランチェスキもおそらくこの公演で初めて演奏したと思われるが、長らくレパートリーとしているかのような安定した演奏を繰り広げている。モントゥーが見抜いた才能故であろう。
フランチェスキは、前記チェトラや伊パーロフォン以外に米ウェストミンスターやRCAビクターにレコーディングを行っており、残した録音は決して少なくないが、なぜかレパートリーに片寄りがあり、クレメンティやケルビーニ、チマローザなど前古典派作品が多く、1965年頃RCAビクターにショパンのワルツ集全曲を録音した以外、いわゆるスタンダード・レパートリーの作品がない。
実は、ピアニストとしての評価も高まり本格的にレコーディング活動を開始した早々に白血病を発症。1966年に40歳の若さで亡くなってしまったことが原因である。冒頭に、キャリア半ばで惜しくも早世したと記したが、まさしく演奏家として円熟する前にキャリアが終わってしまった。その後も活動を継続していたら、国際的に名声を獲得する名ピアニストとなったに違いない。
フランチェスキの死にはもう一つ悲劇が続く。夫は4歳年下のイタリア人テノール歌手、ダニエーレ・バリオーニだったが、リリコ・スピント系の美声を持ち、同じ声質であるフランコ・コレッリの後継者と言われ大いに将来を嘱望されていた。イタリアの地方歌劇場でキャリアを積んだ後、1956年にニューヨーク・メトロポリタン歌劇場に出演、1957年にフランチェスキと結婚、その後も順調にキャリア・アップし、1966年3月ミラノ・スカラ座デビューを果たすが、その3か月後にフランチェスキを亡くし、衝撃のあまり演奏活動への意欲を失い、その後もステージへの出演は続けたが回数も減り、以前のようなパワフルな歌唱を聴くことはできなかった。フランチェスキの死はもう一人の名テノールの歌手生命も奪ったのだ。
ヴェラ・フランチェスキは、モーツァルトのピアノ協奏曲第20番、チャイコフスキーの協奏的幻想曲のスタジオ録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音である。
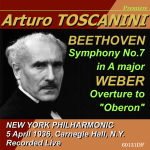
●世界初出か トスカニーニ/ニューヨーク・フィル 1936年ライブ
ベートーヴェン交響曲第7番ほか
プレミエ60131DF
ベートーヴェン 交響曲第7番
ウェーバー 歌劇「オベロン」序曲
アルトゥーロ・トスカニーニ指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
1936年4月5日、ニューヨーク・カーネギー・ホール
モノラル、ライブ
※今回初登場となるトスカニーニ指揮ニューヨーク・フィル(NYP)によるベートーヴェン交響曲第7番とウェーバー「オベロン」序曲の1936年ライブ録音。ベートーヴェンは米RCAビクターへの有名なスタジオ録音(同年4月9・10日)より4日前の演奏に当たる。最近公開された貴重な音源でアメリカ人コレクターからの提供。今までいかなるLP・CDにも復刻されていなかったと思われる。テープレコーダー実用化前の時代で、オリジナルはアセテート・ディスクに録音されており、演奏前後にアナウンスが入っていることから、コロンビア・ネットワーク(CBS)のラジオ放送を時差放送(時差のある地域への再放送)のために収録したものと思われる。CBSでは1935年から33回転16インチ・ディスクに20分程度録音可能なレコーダーを導入していたが、当音源は4分程度で音質やスクラッチ・ノイズが変化するため、旧式の12インチ78回転のディスク・レコーダーを使用していると思われ、しかも楽章ごとにディスクを替えて収録されている。ラジオ放送のエアチェックという可能性もあるが、家庭用録音機器が普及したのは1930年代末からであり、おそらくオリジナルの16インチ・ディスクから12インチ・ディスクにダビングされ、米国内の図書館または大学資料室などに保管されてきたものだろう。
肝心の音質だが、古いアセテート・ディスク特有の盛大なスクラッチ・ノイズとピッチの変動、一部ディスク損傷による音飛びが散見され、このままの状態では鑑賞に堪えるものではなかった。
ディスク化に当たっては、まずはスクラッチ・ノイズの低減を行ったが、幸い持続的で一定した音質?の素直なノイズ成分のため、大半はソフトウェアで低減または除去できた。ただし、強音など一部音割れしている箇所については、ノイズを完全に除去すると音質劣化が甚だしくなるため、敢えてノイズを残した箇所もある。ピッチについては、アセテート・ディスクを交換する度に変動しており(78回転レコーダーの調整不良だろう)、また音色も変化するため、改善には技術的に難易度が高く、ピッチは正常化できたものの、音色の統一については、過度に処理すると音質劣化の恐れもあるため、一定程度の統一に抑えた。音飛びはリピート部分のコピーなどで修復した。
以上の作業の結果、優秀とまでは言えないまでも、ノイズも低レベルで鑑賞に堪える音質まで改善することが出来た。もちろん1930年代中期の優れた音質の78回転SP録音には及ばないが、同時期のトスカニーニ/NYPによるライブ録音と同等以上の水準であり、この種の古い録音に慣れたリスナーであれば、大きなストレスなく演奏を楽しむことが出来ると思われる。
1936年4月5日は、1・3・5日と続いたNYPの定期演奏会3日目で、日曜日午後3時開演のマチネー。トスカニーニは、4月29日の公演をもってNYP常任指揮者を退任したため、退任直前の貴重な録音といえる。プログラムは、前半がウェーバー「オベロン」序曲、ベートーヴェン交響曲第7番、休憩を挟んで後半がマルトゥッチのノクターンとノヴェレッタ、デュカス「魔法使いの弟子」、最後にR・シュトラウス「死と変容」というもので、時代や地域に関連性や統一性のない、「ごった煮」的な典型的トスカニーニ・プログラム。好みの作品を並べただけという感じだが、第二次世界大戦前のコンサート・プログラムは、欧米各地の他の団体でも同様だったようだ。ちなみに現在のような統一性に配慮したコンサート・プログラミングは、1930年代にフルトヴェングラー/ベルリン・フィルが始めたと言われている。
ベートーヴェンの交響曲第7番は、当演奏会の4日後にスタジオ録音が行われたと先に記したが、後のカラヤンのように、レコーディングのためにリハーサルを兼ねてコンサート・プログラムを組んだというわけではなく、当時でも定期演奏会プログラムは前年シーズン中に発表されていたから、RCAビクターが演奏会の曲目に合わせてレコーディングを計画したというのが実態だろう。
当ディスクの演奏は当然、録音状態の差は別にしてスタジオ録音と酷似しているが、やはり全体の流れのスムーズさや、終楽章の圧倒的な推進力は当ディスクの演奏が勝る。当時の78回転SPレコードのスタジオ録音は、大曲の場合3~4分ごとに分割して録音する必要があったが、音溝を刻むワックス盤が脆弱なため工場への輸送や金属原盤製造の過程で破損することが多く、また製造枚数が一定限度を超えると、元となる原盤が摩滅して使用不能となるため、3~4分の同一箇所を数テイク演奏して予備として残す必要があった。このように繰り返して演奏することで、よく言えば冷静・客観的な、悪く言えば機械的(惰性的)演奏になる恐れがある。当ディスクの活力あふれるライブ演奏と比較すると、スタジオ録音は決して機械的演奏に陥らない名演には違いないが、やや表情の硬い証明写真のようにも感じる。当ディスクの録音こそが、1930年代のニューヨークの聴衆が実際に聴いていたトスカニーニの演奏だったのだろう。
NYPの演奏会記録を見ると、トスカニーニはベートーヴェンの交響曲第7番を1929年10月の定期演奏会で初めて取り上げ、1936年までに当演奏を含めて7シーズンに18回と、ツアーの演目も含むが、意外に多く演奏しており、その後1942年5月にも1回取り上げている。一方、「オベロン」序曲は1931年2月に初めて取り上げているが、1936年の当ディスクの演奏を含めても9回に留まるが、5シーズンという短い期間も影響しているだろう。
アルトゥーロ・トスカニーニは、ベートーヴェンの交響曲第7番を上記のように1936年米RCAビクターにNYPとスタジオ録音したほか、1951年にも同じくRCAビクターにNBC響とスタジオ録音、1935年BBC響(3種)、1939年・1951年NBC響とライブ録音していた。また、ウェーバーの「オベロン」序曲を1952年RCAビクターにNBC響とスタジオ録音したほか、1954年NBC響とライブ録音していた。

●優秀録音 セル/クリーヴランド管 ステレオ・ライブ
マーラー交響曲第6番「悲劇的」
プレミエ60132DF
マーラー 交響曲第6番「悲劇的」
ジョージ・セル指揮クリーヴランド管弦楽団
1967年10月12日、クリーヴランド・セヴェランス・ホール
ステレオ、ライブ
※セル/クリーヴランド管によるマーラー交響曲第6番のステレオ・ライブ録音。後で述べるが、セルが実演では、冷たく機械的な演奏を行っていたわけではなく、しかもマスタリングで演奏の印象が大きく変わる典型例となる録音である。音源はアメリカ人コレクターの提供で、FM放送の周波数上限15khzを超えて20khz近くまで高域が伸びており、ソフトウェアで周波数帯域を拡張した可能性もあるが、エアチェックではなく放送局保管音源の良質なコピーと思われる。ただし、放送局によるライブ録音時点もしくはアナログ・ダビング時に録音レベル設定を誤ったか、強音がレベル・オーバーしている箇所があった。しかしそれに起因する歪みは感じられず、基本的には極めて良好な音質。ディスク化に当たっては、ダイナミックレンジが広大で、弱音が小さすぎ強音が大きすぎたため、コンプレッサーでわずかに圧縮したほかは、あまり手を加えていない。1960年代中期のメジャー・レーベルのスタジオ録音とほぼ同等、十分に満足して鑑賞できる状態で、会場ノイズも極小。
10月12日は、12・14日に行われた定期演奏会の1日目。マーラーの交響曲第6番はクリーヴランド管における初演。第2楽章スケルツォ、第3楽章アンダンテの順による版を使用している。1967~1968年シーズンは同管の創立50周年シーズンに当たり、マーラー以外にも同管にとって多くの初レパートリーが演奏された。
ちなみに当録音で問題?となる点は、2日後の14日のライブ録音が米CBSコロンビアによってLP発売されていることであり、そこでいくつか疑問が生じてくる。コロンビア盤はセル死去後の1971年に追悼盤として発売されており、通常は表記されているプロデューサー名やエンジニア名も記載されていないことから、14日の演奏がLP発売を予定して録音されたわけではないことを示しており、コロンビア盤の音源も地元放送局WCLVが収録したと思われる。
しかし、当ディスクとコロンビア盤とは録音スタイルが対照的で、演奏の印象も大幅に異なる。当ディスクの録音はダイナミックレンジを大きく取り、低域・高域共に十分に伸ばし、オンマイクでダイレクトな生々しい音質だが、コロンビア盤はダイナミックレンジが狭く、低域・高域共に控えめでオフマイク気味の音質となっている。
WCLVが12日と14日でマイク・セッティングを大幅に変更したとは考えられないが、理由として考えられるのは、12日の演奏が前述したようにややレベルオーバー気味だったこと。ただし、それだけが理由であれば録音レベル設定を若干下げれば解決する問題であり、これほど大きく音質が変化する理由にはならない。
結果的に演奏の印象も大きく異なる。当ディスクの12日録音は、セルらしく精緻な演奏でありながらも、アグレッシブでパワフル、音楽用語で言えばエスプレッシーヴォ(表情豊か)な演奏だが、14日のコロンビア盤は、ダイナミックレンジを抑えているためもあり、客観的で冷めた、感情移入の乏しい、作品を外から眺めているような印象がある。かつて作曲家・評論家の諸井誠が、当盤について「演奏というより批評の産物」と記したが、良くも悪くもいわゆる「セル的」演奏となっている。
実は演奏そのものについても、12日と14日録音では第3楽章の演奏時間が大きく異なる。インターバルを除いた実質の演奏時間は、12日が15分28秒、14日が13分26秒と前者が2分も長い。12日録音は最初から遅めのテンポで始まり、中間部を過ぎる頃から更に遅くなっている。2回の公演で大きく演奏時間が異なるのは、クナッパーツブッシュやシューリヒトのような即興を好んだ指揮者によく見る例だが、セルのような厳格な指揮者の場合、当初から予定してテンポ設定を行ったとしか考えられず、12日の演奏を「反省して」14日のテンポを変更したとも考えられる
スタジオ録音の場合、必ず録音をプレイバックして演奏家に確認してもらい、発売承認を得ることが通例だが、セルはその際、演奏が「興奮・熱狂的」にではなく、理知的・客観的に響くことを要求したのかも知れない。理知的・客観的とは一般にセルのレコードに聴く典型的なイメージでもあり、それを認識していたコロンビアのスタッフが、セルの追悼盤としてマーラーの交響曲第6番をLP化する際に、2日間のWCLV録音を比較し、第3楽章のテンポが一定かつ速めで、より「セル的な」14日録音を選び、セルが要求したであろう音作りを実現すべく、ダイナミックレンジを大幅に圧縮、低域と高域をカットしてマスタリングしたように思える。ちなみに14日の音源のみでLP化したのではなく、一部の細かい演奏ミスなどを12日の録音で差し替えた可能性は高い。
当ディスクに聴く12日のライブは、20年ほど前に海外でCD化されたことがあったが、あるCDショップの説明では、「演奏はスタジオ録音とほぼ同一で、しかも音質は劣るため、敢えて購入する価値はない」とあったが、実際の録音を聴けば見当外れであることが分かる。
以前、セル/クリーヴランド管の1970年来日公演録音がCD化された際、ある評論家が「セルはダイナミックでもあったのだ!」と評したように、12日の録音がセル本来の演奏を示しているように考えられる。セルはレコードとして繰り返し聴かれる演奏と、ライブを別物として捉えていたか、ライブでは「理知的・客観的」な演奏に努めてはいても、必ずしもそうならなかった点で、新即物主義的と言われるセルだが本質的にはロマンチストだったようだ。
ジョージ・セルは当ディスク以外に、マーラーの交響曲第6番を、上記のように1967年米CBSコロンビアにライブ録音したほか、1969年ニューヨーク・フィルとライブ録音していた。
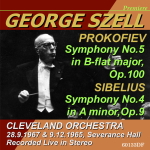
●優秀録音 セル/クリーヴランド管 ステレオ・ライブ
プロコフィエフ交響曲第5番、シベリウス交響曲第4番
プレミエ60133DF
プロコフィエフ 交響曲第5番
シベリウス 交響曲第4番
ジョージ・セル指揮クリーヴランド管弦楽団
1967年9月28日、1965年12月9日、クリーヴランド・セヴェランス・ホール
ステレオ、ライブ
※セル/クリーヴランド管によるプロコフィエフとシベリウスのステレオ・ライブ録音。アメリカ人コレクターの提供音源で、エアチェックとのことだが、FM放送の周波数上限15khzを超えて20khz近くまで高域が伸びており、ソフトウェアで周波数帯域を拡張した可能性もあるが、放送局保管音源のコピーの可能性もある。いずれにしても極めて優秀な音質で、1960年代半ば以降になると、アメリカでは家庭用レコーダーの性能が著しく向上し、受信状態の良いエアチェックと放送局保管音源との音質差は、2種の音源を厳密に比較しない限り判別が難しい。
ディスク化に当たっては、音質自体はほとんど問題ないため、微少なヒスノイズ低減、若干の周波数バランス調整、小音量と大音量差がやや大きいためコンプレッサーをわずかにかけた程度で、十分満足して鑑賞できる音質となった。おそらく同年代のメジャー・レコード会社のスタジオ録音と遜色ないレベルと思われる。
1967年9月28日のプロコフィエフは29・30日と続く定期演奏会初日(29日は追加公演)、冒頭にワーグナー「マイスタージンガー」第1幕への前奏曲、続いてドビュッシー「牧神の午後への前奏曲」、ウォルトン「管弦楽のためのパルティータ」、休憩を挟んで後半にプロコフィエフというプログラム。近・現代作品が多い中でワーグナーだけはやや異質のようだが、ドビュッシーがその初期にワーグナーの影響を受けていたという事実もあるので、プログラムとして筋は通っているようだ。ちなみにウォルトン作品はセルに献呈され、1958年にクリーヴランド管によって初演されている。
セルはプロコフィエフの交響曲第5番を早くから好んで取り上げ、1947年1月にプログラムに載せており、これはクーセヴィツキー/ボストン響によるアメリカ初演の2年後に当たる。その後も当ディスクの演奏以外に1951年3月、1953年1月、1954年10月、1959年3月・10月、1965年1月の定期演奏会で取り上げ、セルの死去によって実現しなかったが、1971年1月にもプログラムが組まれていた(代わりにクーベリックが指揮)。同曲はセルにとって定期演奏会の「定番」作品だったと言える。
一方、セルの音楽性にさらに合致すると思われる交響曲第1番「古典」は、1955年1月、1961年11月、1968年10月の3回に留まっており興味深い。さらにショスタコーヴィチに至っては、1963年10月にロストロポーヴィチを客演に迎えてチェロ協奏曲第1番を演奏した以外、全く演奏していない。セルによるショスタコーヴィチ交響曲第5番などが実現していたら、ムラヴィンスキーに匹敵する厳しい辛口の演奏となったと想像するが、セルの美意識と相容れない部分があったのだろう。
1965年12月9日のシベリウスは、9・11日定期演奏会2回公演の初日、シベリウス生誕100年を記念するオール・シベリウス・プログラムで、冒頭に「エン・サガ」(プレミエ60077DFで発売済み)、続いて交響曲第4番、ヴァイオリン協奏曲(クリスチャン・フェラス独奏)というもの。休憩がどこに入ったか分からない組み合わせだが交響曲の前だろうか。
セルはシベリウスの交響曲第2番を得意としており、来日公演でも取り上げているが、生誕100年記念演奏会に第2番ではなく、敢えて晦渋と言われる第4番を取り上げる点は、「教育的プログラム」をポリシーとするセルらしい。ちなみに定期演奏会記録を見ると、当演奏以外に1964年4月に取り上げており、また1966年1月にツアーで演奏しているが、さすがに頻繁というわけではなかったようだ。しかし、演奏の完成度の高さは、販売面は期待できなくとも正式なレコーディングを残すべきだったと思われる。
ジョージ・セルは、当ディスク以外にプロコフィエフの交響曲第5番を1959年米コロンビアにスタジオ録音したほか、1954年にライブ録音していた。また、シベリウス交響曲第4番はスタジオ録音を残さず、1966年にライブ録音していた。
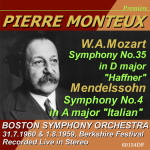
●優秀録音 モントゥー/ボストン響 ステレオ・ライブ
モーツァルト交響曲「ハフナー」、メンデルスゾーン「イタリア」
プレミエ60134DF
モーツァルト 交響曲第35番「ハフナー」
メンデルスゾーン 交響曲第4番「イタリア」
ピエール・モントゥー指揮ボストン交響楽団
1960年7月31日、1959年8月1日、タングルウッド・ミュージック・シェード
ステレオ、ライブ
※モントゥー/ボストン響(BSO)によるモーツァルト交響曲第35番とメンデルスゾーン交響曲第4番のステレオ・ライブ録音。アメリカ人コレクターによる提供音源。いずれもエアチェックと思われる。モーツァルトのオリジナル音源は、基本的には受信状態も良好で周波数レンジも広くノイズレスだが、録音当時のレコーダーのイコライザー不調かテープの経年変化のためか、中域が団子状態で混濁し高域が低下するなど、ややバランスが悪い音質。ただし素性は悪くないため、イコライジング等によりバランスを取り直し、FM放送の周波数上限15khzからCDの上限20khz程度までレンジを拡大、ヒスノイズを低減した結果、当時のメジャー・レーベルのスタジオ録音に匹敵する良好な音質へと改善できた。一方、メンデルスゾーンの音質は更に状態が良く、そのままの状態でも基本的には問題がなかったが、中低域が薄く力強さに欠けていたため、こちらも周波数レンジを拡大する一方、イコライジング等によりバランスを改善した。両者とも鑑賞には全く問題ない水準の音質と言える。
なお、BSOのFM放送を担当したボストンの放送局WGBHは、1959年頃からステレオでボストン響(BSO)の演奏会を収録しており、当ディスクの演奏も当然ステレオで録音・保存されたが、1960年代の社屋火災によって、1959年秋から60年夏までの演奏会のステレオ・テープが失われ、現在は火災を免れた同一演奏のモノラル・テープしか残っていない。当ディスクのモーツァルトはまさに失われたステレオ・テープの時期に当たり、貴重な音源と言える。
1960年7月31日のモーツァルトは、BSO恒例の夏のフェスティバル、バークシャー音楽祭におけるライブで、午後2時半開演のマチネー。前半にモーツァルト、休憩を挟んで後半にベートーヴェンの交響曲第9番というプログラム。ちなみにベートーヴェンは、当レーベル・プレミエ60042DFIIとして発売済みである。モントゥーとBSOの演奏会記録を見ると、モーツァルトは「フィガロ」や「魔笛」の序曲が圧倒的に多く、当ディスクに聴く交響曲は第35番は、1960年4月のBSO定期演奏会のみ。その他の交響曲もそれ以前の演奏は1952年4、5月の第41番まで遡る(こちらの録音もプレミエ60063DF発売済み)。さらに以前の演奏となると1924年4月、かつての常任指揮者時代の第28番に至る。
モントゥーの芸風とモーツァルトは相性が抜群と思われるが、モントゥーが第二次世界大戦後、BSOに頻繁に客演していた時代(1951~1963年に188回客演している)には、モーツァルトの交響曲は意外にも当時の常任指揮者シャルル・ミュンシュが取り上げることが多く、モントゥーの場合、プログラムの重複を避けるためオーケストラ側から依頼がなかったというのが実態だろう。
ちなみにモントゥーは最晩年の1964年に仏コンサート・ホール・ソサエティ(CHS、フランスにおけるレーベル名はG.I.D: Guilde
Internationale du
Disque)にハンブルク北ドイツ放送響を第35番と39番をレコーディングし、特に35番は名演との評価が高いが、ステレオのスタジオ録音にもかかわらず音質が冴えず、その点のみ批判の対象となっていた。これには原因があり、CHSは自前の録音チームを持たず、フリーランス・エンジニアや他社にレコーディングを外部委託することが通常だったが、モントゥーのモーツァルト(およびベートーヴェン交響曲第2番・4番、ベルリオーズ「幻想」)については、1930年代設立の老舗レーベル・デンマークのTONOに委託したものの、同レーベルは当時、シンフォニー・オーケストラのステレオ録音の経験がほぼ皆無だったらしい。結果として、ステレオと並行して録音したモノラルLPは無難な出来だったが、ステレオLPはナローレンジで混濁した音質という惨憺たる仕上がりとなった。近年、同音源を最新のリマスター技術で改善したCDも登場しており、かなり聴きやすくなってはいるが、根本的な改善には至っていない。その点で、音質の優れた当ディスクのモーツァルトは貴重な存在である。
一方、1959年8月1日のメンデルスゾーンも、同じくバークシャー音楽祭におけるライブで、午後8時半開演。前半の最初にメンデルスゾーン「イタリア」、同じくメンデルスゾーンのピアノ協奏曲第1番(ルドルフ・ゼルキン独奏)、休憩を挟んで後半にシューマンのマンフレッド序曲、同じくシューマンの序奏とアレグロ・アパッショナート(ルドルフ・ゼルキン独奏)、最後にワーグナー「トリスタンとイゾルデ」から前奏曲と愛の死という、少し変わった構成のプログラム。中間部に馴染みのない作品を置き、最初と最後はポピュラーな作品でまとめるという意図だろうか。
モントゥーにとってメンデルスゾーンの「イタリア」は、スタジオ録音を残していない極めて珍しいレパートリー。長いキャリアから膨大なレパートリーを持ち、それらを柔軟・自在にこなすモントゥーにとって不得意な作品というのは存在しないが、BSOの演奏家記録を見ると、当演奏以前には1921年3月、かつての常任指揮者時代に3回取り上げたのみ。メンデルスゾーンもモントゥーの芸風に合致する作曲家だが、こちらも前記のモーツァルトと同様に他の指揮者のプログラムとのバランスから、依頼が少なかったというのが実態だろう。
ピエール・モントゥーは、当ディスク以外にモーツァルトの交響曲第35番「ハフナー」を1964年仏コンサート・ホール・ソサエティにハンブルク北ドイツ放送響とスタジオ録音したほか、1946年と1962年にライブ録音していた。また、メンデルスゾーンの交響曲第4番「イタリア」はスタジオ録音を残さず、1947年にライブ録音していた。
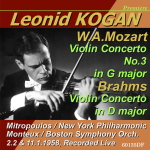
●音質良好 レオニード・コーガン アメリカ・デビュー・ライブ
モーツァルト ブラームス ヴァイオリン協奏曲
プレミエ60135DF
モーツァルト ヴァイオリン協奏曲第3番
ブラームス ヴァイオリン協奏曲
レオニード・コーガン(ヴァイオリン)
ディミトリ・ミトロプーロス指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
ピエール・モントゥー指揮ボストン交響楽団
1958年2月2日、ニューヨーク・カーネギー・ホール
1958年
1月11日、ボストン・シンフォニー・ホール
モノラル/ステレオ、ライブ
※旧ソ連の名ヴァイオリニスト、レオニード・コーガンによるアメリカ・デビュー時のモライブ録音。アメリカ人コレクターによる提供音源で、いずれもエアチェックとのこと。モーツァルトのオリジナル音源の音質は、1950年代末のニューヨーク・フィル(NYP)のライブ録音としては例外的に優秀な部類。1950年代後半~1960年代中期までのNYPのライブ録音は、カーネギー・ホールの記録用音源と思われるものが多く、ステージ上方に天吊りされた常設マイクによる収録で、音質に配慮したマイク・セッティングも行われておらず、しかも旧式の録音機材が使われていたと言われ、鈍く冴えない録音が目に付く。一方、当ディスクの音源は、コロンビア・ネットワーク(CBS)によるFMモノラル放送がオリジナルと思われ、良好な受信環境の元、高品質な録音機材によってエアチェックしたものと想像される。放送時のハムノイズが若干感じられるが、周波数レンジも広くバランスも良好で美しい音質。独奏ヴァイオリンをクローズアップし、オーケストラが後方にやや控えめに配置されるという古い録音スタイルだが、モノラル期のLPを聴き慣れたリスナーであれば満足して鑑賞できると思われる。ディスク化に当たっては、音質に悪影響を与えない範囲でハムノイズの低減を行い、大音量で再生しない限り聴こえない状態とすることが出来た。なお、同曲は海外で既出盤が存在し、こちらもハムノイズが乗っているので、同じ放送をエアチェックしたものと思われるが、ヒスノイズ過多で周波数レンジが狭く、当ディスクよりも古ぼけた音質であり、別のリスナーによるエアチェックだろう。
一方のブラームスは、地元ボストンの放送局WGBHによる最初期のステレオFM放送がオリジナル。アメリカでは高価ながら1951年からステレオ(正確にはバイノーラル)・テープ・レコーダーが市販されていたから、1958年当時、裕福なリスナーがステレオ・エアチェックを行っていても不思議ではない。非常に優秀な音質でステレオ初期のLPとほぼ同等の水準。ノイズレスで周波数レンジも広く安心して鑑賞できる。第1楽章冒頭、序奏部分の録音レベルが若干高く、ヴァイオリン独奏が入る頃から下がっていくため(録音エンジニアがその後のレベル・オーバーを抑えようとしたのだろう)、この部分のみボリューム調整および若干の周波数拡大を行った以外、ほとんど手を加えていない。両者とも会場ノイズは極小。
近年、再評価が著しいレオニード・コーガンだが、現役時代も10回のアメリカ公演、8回の日本公演を行うなど、先輩格のダヴィード・オイストラフと並びソ連を代表する大ヴァイオリニストとして高い人気を得ていた。また、レコーディングについてもソ連国内をもとより、1955年からは英コロンビアと契約を行うなど国外メジャーとのレコーディングも活発に行った。しかし晩年になると新世代の台頭もあり次第に地味な存在となっていったと言われる。また、オイストラフと比較すると、英仏コロンビアや米RCAに録音したLPもセールス的には今ひとつだったようだ(販売枚数が多くなかった結果、皮肉なことに現在の中古LP市場では価格が高騰している)。
ちなみに1958年ボストン響(BSO)とニューヨーク・フィル(NYP)への初共演後の再共演は、BSOは1960年3公演、1964年3公演、1975年5公演、NYPは1960年3公演、1976年4公演のみ。その他のアメリカのオーケストラとは1969年と1971年にはクリーヴランド管、1976年にはフィラデルフィア管と共演しているが、高い評価の割にはアメリカのメジャー・オーケストラとの共演もやや散発的だった。
オイストラフが豊麗な音色と濃厚な表現を特徴としているのに対し、コーガンは澄んだ音色とよりストレートでモダンな表現を特徴としており、しかも、高度な技巧を持ちながら、例えばハイフェッツのようにそれを前面に押し出すような演奏スタイルではなかった点で(コーガンのパガニーニ演奏はすさまじいものだったが)、没後は急速に注目度が低下した想像される。しかし現在の視点では、オイストラフよりも明らかに新しい世代に属する先進的演奏スタイルを持っており、現在では却って時流に近い形となることで、再評価が高まっているのは前記したとおりである。
当ディスクの録音はコーガンのアメリカ・デビュー時のライブ(なお当ディスクの演奏以外に、1月30・31日にNYPとラロ「スペイン交響曲」を演奏している)。日時的にはBSOとのブラームスが先で、当録音はBSO定期演奏会2回公演の2日目に当たる。午後8時30分開演でプログラムは、前半にワインガルトナー編曲によるベートーヴェン「大フーガ」、ドビュッシー「聖セバスチャンの殉教」抜粋2曲、R・シュトラウス「死と変容」、休憩を挟んで後半がブラームスのヴァイオリン協奏曲という、コーガンを主役とした構成。プログラム前半の途中、「死と変容」辺りから来場した聴衆が多かったかも知れない。
2月2日のNYPとの共演は、定期演奏会としては珍しい1回公演で日曜日午後3時開演、前半にモーツァルト「魔笛」序曲、ヴァイオリン協奏曲第3番、休憩を挟んで後半にベートーヴェンの交響曲第2番、レオノーレ序曲第2番という一風変わった構成。不思議なことに当日会場で配布されたブックレットには、交響曲第2番のみNYP自身によって録音される(た)との記載がある。実際には当ディスクに聴くようにコロンビア・ネットワークによってヴァイオリン協奏曲第3番が放送されており、おそらくNYPがついでに録音を依頼したのだろう。
レオニード・コーガンは、当ディスク以外に、モーツァルトのヴァイオリン協奏曲第3番を1955年英コロンビア、1959年仏コロンビア、1964年露メロディアにスタジオ録音。また、ブラームスのヴァイオリン協奏曲を1955年仏コロンビア、1959年英コロンビア、1967年露メロディアにスタジオ録音していた。

●優秀録音 ストコフスキー/フィラデルフィア管 ステレオ・ライブ
リムスキー・コルサコフ「シェエラザード」ほか
プレミエ60136DF
リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」
イッポリトフ・イワーノフ 組曲「コーカサスの風景」第1番
アンシェル・ブラシロウ(ヴァイオリン独奏)
レオポルド・ストコフスキー指揮フィラデルフィア管弦楽団
1962年2月6日、1963年2月8日、フィラデルフィア・アカデミー・オブ・ミュージック
ステレオ、ライブ
※ストコフスキー/フィラデルフィア管によるステレオ・ライブ。アメリカ人コレクターによる提供音源で、2曲ともFMラジオ放送のエアチェックだが、良好な受信環境の元、高品質な機器によって録音されたと思われ、音質は極めて良好。周波数レンジは広く、ヒス・ノイズなどの各種ノイズもほぼ皆無で、一般的な鑑賞には全く不満のないレベル。ディスク化に当たっては、FM放送の周波数上限15khzからCDの上限20khz程度までレンジを拡大した以外、特に手を加えていない。なお、シェエラザードには海外の既出盤が存在するが、ヒス・ノイズ低減のためにノイズ・リダクションを不適切にかけた結果、音質が低下したという批判があるとのことで、おそらく同一演奏の別ソースだろう。2曲とも会場ノイズはほぼ皆無。
1960年2月、ストコフスキーは1941年4月以来、約20年ぶりにフィラデルフィア管の指揮台に復帰した。ストコフスキーが同管を離れたのは運営や人事を巡る様々な理事会との対立があったとされるが、オーマンディが両者を巧みに取り持つことで、1969年まで60回もの客演が実現した。復帰当初は、限られたリハーサル時間のため、分厚い低域と艶やかな弦セクションを基本とするオーマンディ流サウンドの名残があったと言うが、当ディスクに聴く復帰3・4年目になるとストコフスキーがオーケストラを掌握し、独自のサウンドを実現しているようだ。弦セクションの美しさは相変わらずだが、全体にオーマンディ流の豊麗さよりも輝かしさが増しているように感じる。ちなみにシェエラザードのヴァイオリン独奏者アンシェル・ブラシロウは同管の著名なコンサート・マスター。
ストコフスキーはシェエラザードを5回スタジオ録音しているが、フィラデルフィア管とのステレオ録音を残さなかったのは、色彩的なオーケストレーションを特徴とする作品だけに至極残念だったと言わざるを得ない。ステレオで残っているロンドン響(1964年)とロイヤル・フィル(1975年)の録音もそれなりの価値があり、特にロンドン響とのデッカ録音は「フェイズ4」というマルチ・チャンネル録音の先駆けと言えるシステムが採用されているが、ここにフィラデルフィア管が参加していれば、更に絢爛たる演奏になったことは想像に難くない。
1960年前半、フィラデルフィア管の専属契約先は米CBSコロンビアであり、同社と英デッカは何らの提携関係もなかったが、両者は、当時デッカ専属のウィーン・フィルをCBSに貸し出す代わりにバーターとしてCBS専属のバーンスタインやセルをデッカが起用してスタジオ録音を行っており、同様の形式でフィラデルフィア管をレンタルする方法もあったはずだ。ただ、ストコフスキーへのギャランティは相当高額だったと想像され、デッカとしては、さらにコストはかけられなかったのかも知れない。結果としてライブながら、当ディスクの録音が良質なステレオ音質で残されたことは幸いだったと言える。
ちなみにストコフスキーによるシェエラザードの初演奏は1910年2月シンシナティ響、最後は1967年7月モンテカルロ国立歌劇場管との演奏で、58年間で計76回演奏している。毎年複数回演奏しているように思えるが、定期演奏会では2~3回の公演を行っていることを考慮すれば極端に多いわけではない。また、1968年以降1975年のコンサート活動引退まで同曲を取り上げなかった理由も不明だ。ただし、第3曲や第4曲のみも何回か演奏しており、好みのレパートリーだったことは確かだ。
一方、「コーカサスの風景」組曲第1番は、ストコフスキーが1909年パリ・コロンヌ管とのオーケストラ・デビュー・コンサートで演奏した記念すべき作品で、1924年までに10回演奏した記録がある。しかし、その後は当ディスクの録音までは第4曲「酋長の行列」などの演奏記録しか見当たらず、組曲第1番全4曲の演奏は39年ぶり。しかもその後も全4曲の再演は行っておらず、貴重な機会を捉えた録音である。
ストコフスキーは、リムスキー・コルサコフの「シェエラザード」を1927年と1934年米RCAビクターにフィラデルフィア管と、1951年英HMV/米RCAビクターにフィルハーモニア管と、1964年英デッカにロンドン響と、1975年米RCAビクターにロイヤル・フィルとスタジオ録音していた。一方、イッポリトフ・イワーノフの「コーカサスの風景」第1番全曲についてはスタジオ録音を残さず、第2曲を1925年米RCAビクターにフィラデルフィア管と、1947年米コロンビアにニューヨーク・フィルと、第4曲を1922年と1927年米RCAビクターにフィラデルフィア管と、1975年英パイにナショナル・フィルとスタジオ録音していた。

●音質良好 ミュンシュ/ボストン響
バルトーク「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」、ニールセン交響曲第5番 1958年・1953年ライブ
プレミエ60137DF
バルトーク「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」
ニールセン 交響曲第5番
シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団
1958年3月14日、1953年11月6日、ボストン・シンフォニー・ホール
モノラル ライブ
※ミュンシュ/ボストン響によるバルトークとニールセンのライブ。2作品ともミュンシュにとっては非常に珍しいレパートリー。アメリカ人コレクターからの提供音源で、両者ともエアチェックと思われるが音質は非常に良好。ノイズレスで周波数レンジも広く、バランスも申し分ない。バルトークのみ若干高域が下がり気味で、本作品に必要な高域のシャープさが不足していたためイコライジングでわずかに補正したが、いずれにしてもモノラルながら鑑賞する上で全く不満のないレベル。またニールセンは1953年録音とは思えない優秀録音で、5年後のバルトークは全く遜色のない音質。極めて良好な放送受信環境の元、良質でおそらく高価な録音機器を使用し、しかも今日まで録音テープが適正に保存されてきたと思われる。当時のアメリカ人リスナーの技術水準の高さには感心する。会場ノイズもほぼ皆無。
1958年のバルトークは3月14日の定期演奏会から。15日との2回公演の1日目。午後2時15分開演のマチネーで、前半冒頭、同年3月11日に死去したボストン・ヘラルド紙のコラムニスト・音楽評論家ルドルフ・F・エリーを追悼して、バッハ「マタイ受難曲」から第63曲、コラール「おお、血と傷にまみれた御頭よ」(当初のプログラムにはなく急遽演奏された)、続けてバルトーク、ラヴェルのピアノ協奏曲(ピアノ独奏ニコール・アンリオ=シュヴァイツァー)、休憩の後、後半にダンディ「フランスの山人の歌による交響曲」(ピアノ独奏は同じくニコール・アンリオ=シュヴァイツァー)というプログラム。ミュンシュお気に入りのアンリオ=シュヴァイツァーとの共演がメインの公演で、バルトークはあくまで前座的扱いのようだ。現在であればバルトークがメイン・プログラムとなると思われるが、当時の聴衆の好みを考慮すればこのような曲順が当然かも知れない。
1953年のニールセンは11月6日の定期演奏会から。7日との2回公演の1日目。こちらも午後2時15分開演のマチネーで、前半冒頭も11月4日に死去したエリザベス・スプレーグ・クーリッジ(パトロン兼慈善事業家としてアメリカ音楽界に多大な貢献があった)を追悼してバッハ「マタイ受難曲」から第62曲、コラール「いつしか私がこの世に別れを告げるとき、私から離れないでください」が演奏され、続けてシベリウス「フィンランディア」、ニールセン、休憩を挟んで後半は指揮者が交代、マルッティ・トゥルネン指揮によるクラミ「ヴィプネンの腹で」、マデトーヤ「サンポーの誘拐」、シベリウス「火の起源」(いずれもスロ・サーリツのバリトン、ヘルシンキ大学男声合唱団が共演)というフィンランド・プログラム、当時の欧米のオーケストラでは、新作初演などで作曲家自身が指揮をすることもあり、演奏会前半と後半で指揮者交代は珍しくなかったようだが、曲目は今日の目で見ても意欲的かつ挑戦的。当時の聴衆や批評家の反応を知りたいところだ。ミュンシュも後半のプログラムに配慮してニールセンを取り上げたと思われる。
先に述べたように、ミュンシュとボストン響にとってバルトークとニールセンは異色のレパートリー。ただし、バルトークについては、1951年に定期演奏会や国内ツアー、バークシャー音楽祭で計6回演奏しており、その後当ディスクの演奏を含めて、同様に定期演奏会や国内ツアー等で計6回演奏している。バルトークの他の作品については、「2つの映像」を1953年に8回、ヴィオラ協奏曲を1960・1961年に6回演奏しており、ミュンシュにとっては、頻繁には取り上げないものの重要視していた作曲家だったと思われる。現在と異なり1950年代のアメリカでは、バルトーク作品は同時代の現代音楽に近い存在であり、聴衆の評価や人気も確立していなかった。バルトークに師事したフリッツ・ライナーなどがレコーディングや演奏会で普及に努めた時代でもあり、ボストン響の聴衆があえてバルトーク作品を求めなかったという事情も想像され、それでもミュンシュは熱心に取り上げた方とも言える。一方のニールセンは確かに珍しいレパートリー。当ディスクに聴く1953年の定期演奏会で2回取り上げたのみ。ニールセン作品自体この時が唯一の演奏機会だった。
ミュンシュはかつてのパリ音楽院管首席指揮者時代(1938~1946年)に、「(当時の)現代音楽ばかり演奏している」と保守的な聴衆やオーケストラ側から不興を買い、より穏健なレパートリーを選ぶクリュイタンスに交代したという「実績」もあり、本来、現代音楽に対しては積極的な態度をとっていた。ボストン響常任指揮者時代にも現代作品を機会あるごとに取り上げているが、オーケストラの地元アメリカやミュンシュの出身国フランスの作品が多かったようだ。ただし意外な点は、ミュンシュの前任者クーセヴィツキーに関わりのある作品を避ける傾向があり、クーセヴィツキー財団が委嘱したムソルグスキー(ラヴェル編曲)「展覧会の絵」、バルトーク「管弦楽のための協奏曲」、メシアン「トゥーランガリラ交響曲」、ミヨーの交響曲第2番などは、少なくともボストン響とは演奏していない(例外はオネゲルの交響曲第1番とルーセルの交響曲第3番)。前任者のカラーを消そうという後任者の意思の表れとも思えるが、単純に「作品が好みではなかった」のかも知れない。ミュンシュはコンサート指揮者として広いレパートリーを持っていたように思われるが、ブラームスの交響曲第3番、チャイコフスキーの交響曲第5番などのポピュラー作品でもボストン響とは演奏しておらず、事情を知りたいところだ。
シャルル・ミュンシュは、当ディスク以外にバルトークの「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」、ニールセンの交響曲第5番のスタジオ録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音と思われる。
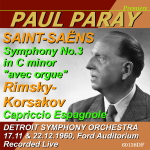
●音質良好 パレー/デトロイト響
サン・サーンス 交響曲第3番「オルガン付き」、リムスキー・コルサコフ「スペイン奇想曲」1960年ライブ
プレミエ60138DF
サン・サーンス 交響曲第3番「オルガン付き」
リムスキー・コルサコフ「スペイン奇想曲」
エルウッド・W・ヒル(オルガン)
ポール・パレー指揮デトロイト交響楽団
1960年11月17日、12月22日、デトロイト・フォード・オーディトリアム
モノラル ライブ
※パレー/デトロイト響によるサン・サーンスとリムスキー・コルサコフのライブ。2作品ともスタジオ録音を残している得意のレパートリーだが、ライブ録音は珍しい。アメリカ人コレクターからの提供音源で、両者ともエアチェックと思われる。音質はモノラルながら基本的に良好。ノイズレスで周波数レンジも広いが、オリジナルの状態では、サン・サーンスは低域不足でオルガンの低音がほとんど聞こえなかった。ただし、周波数バランスが悪いだけで、マイクは低音を捉えており、イコライジング等で補正することにより、迫力ある低音が再現された。また、わずかながらドロップアウトも存在したため補正を行った。一方、リムスキー・コルサコフは、逆に60khz以上の高域が低下しており、やや頼りない印象の音質。こちらもイコライジング等による補正でしっかりとした高域が甦った。以上の音質改善の結果、1960年のモノラル録音としては最上の音質を実現することができた。このままステレオ化しても十分通用するレベルで、一般的な鑑賞には不満がないと思われる。オーディオ的見地からはステレオでないことが惜しまれるが、再生時にサラウンドなどステレオ・プレゼンスを加えれば、より迫力ある演奏が楽しめるかも知れない。会場ノイズはほぼ皆無。
11月のサン・サーンスは定期演奏会から。前半に、ロッシーニの歌劇「絹のはしご」序曲、ピストンのヴァイオリン協奏曲第2番(ヴァイオリン独奏ジョセフ・フックス)、バッハ「狩のカンタータ」より第9曲アリア「羊は安らかに草をはみ」(地元デトロイトの音楽・演劇批評家ジェイ・ドロシー・キャラハンの引退を記念して演奏)、メンデルスゾーンの「真夏の夜の夢」からスケルツォ、休憩を挟んで後半がサン=サーンスというプログラム。メンデルスゾーンだけ余計な感じもするが、おそらくピストンの協奏曲が演奏時間22分前後と短く、後半のサン・サーンスも30分強ということで追加されたと想像する。サン・サーンスのオルガンを担当しているエルウッド・W・ヒルは、国際的に知名度が高い演奏家ではないが、ワシントンDCの大聖堂で演奏会を開催した記録があり、ミシガン州立大学でオルガン講師を務めるなど、アメリカ国内では中堅的ポジションに位置していたと考えられ、スター的存在ではないものの、当ディスクでも破綻のない堅実な演奏を聴かせている。
パレーの演奏は、当然3年前のスタジオ録音と酷似しているが、レコーディングを経験してオーケストラが作品に馴染んだか、またはライブのためか、柔軟性や自由度が増している感がある。
12月のリムスキー・コルサコフも定期演奏会からの1曲。前半にブラームスの交響曲第4番、休憩を挟んで後半にチャイコフスキーの「くるみ割り人形」組曲、ベルリオーズのオラトリオ「キリストの幼時」からトリオ、リムスキー=コルサコフというプログラム。現在とは順番が逆の構成だが、1960年頃までのコンサート・プログラムは前半が重く、後半は軽い曲目を置かれることが多く(聴衆に飽きさせない工夫と思われる)、最後は盛り上げてコンサート終了という形態。ちなみに今日のようなプログラム構成は1930年代中期のベルリン・フィルが徐々に始め、1960年代中期以降、世界的に普及したと言われる。逆に現在では、歌劇の序曲や「通俗的」といわれる管弦楽曲の演奏機会が通常の定期公演では激減しており、これはこれで問題かも知れない。パレーの演奏はさすがに老練かつ手慣れた印象で、このような通俗的作品を巧みにこなせる一流指揮者がいなくなったことも、演奏の機会が減った理由の一つだろう。
ポール・パレーはサン・サーンスの交響曲第3番を1957年米マーキュリーにデトロイト響とスタジオ録音したほか、1973年フランス国立フィルとライブ録音していた。また、リムスキー・コルサコフのスペイン奇想曲を1953年米マーキュリーにデトロイト響とスタジオ録音していた。
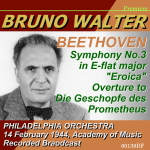
●ブルーノ・ワルター/フィラデルフィア管
ベートーヴェン交響曲第3番「英雄」、「プロメテウスの創造物」序曲 1944年放送ライブ
プレミエ 60139DF
ベートーヴェン 交響曲第3番「英雄」、「プロメテウスの創造物」序曲
ブルーノ・ワルター指揮フィラデルフィア管弦楽団
1944年2月14日、フィラデルフィア・アカデミー・オブ・ミュージック
モノラル 放送ライブ
※ブルーノ・ワルターが珍しくフィラデルフィア管を客演した際の記録で、アメリカ人コレクターからの提供音源。後述するように、今までライブ録音とされていたが、演奏会記録に記載されてないプログラムのため少々疑問があり、ライブ録音ではなく聴衆を入れずに行われた放送のための録音と思われる。テープ録音が実用化される以前に使用されていた、連続20分程度録音可能な33回転16インチ・アセテート・ディスク・レコーダーによる録音で、Armed
Forces Radio Service(米軍ラジオ放送、現在のAFN)によって全米各地および海外駐留の米軍向けに放送された。初出の海外盤(悪名?高きDisco
Archivia盤)ではコンサート・ライブと称されていたが、ライブに聴かれる楽章間の聴衆ノイズが聞こえず、拍手がカット?されるなど、ライブ録音とは思えない状態。オリジナル・ディスクから、楽章ごとに1枚のディスクにダビングして前後のノイズを消した可能性は否定できないが、当時の技術で、このように編集が可能だったのか疑問であり、元々聴衆はいなかったようだ。
音質自体は当時の標準レベルだが、ややナローレンジでアセテート盤特有のスクラッチ・ノイズが持続、会場の残響の乏しさから、硬めのドライな音質で、高音は歪み気味という、やや問題のある状態だった。ただし、欠落や音楽情報を阻害するような大きなノイズはなく、ディスク化に当たっては、スクラッチ・ノイズの大半を除去、イコライジングで周波数バランスの「暴れ」を補正、高域の周波数レンジを拡大することでドライな音質を緩和するなど、対策を行った結果、一応ストレスなく鑑賞できるレベルまで改善することができた。
ブルーノ・ワルターは1944年2月、フィラデルフィア管の2回の定期演奏会(各2公演)に客演した。記録によれば2月11・12日がモーツァルトの交響曲第40番、R・シュトラウス「死と変容」、ブラームスの交響曲第2番、18・19日がヘンデルの合奏協奏曲第6番、バーバーの交響曲第1番(改訂版初演)、ベートーヴェンの交響曲第3番というプログラム。ここには当ディスクに聴く「プロメテウスの創造物」序曲は含まれておらず、しかも、当オリジナル音源の冒頭には「All
Beethoven
program」とアナウンスがあり、序曲、交響曲の順で演奏が行われている。通常の演奏会としてはプログラムが短いので、ワルターがフィラデルフィア管客演時に、米軍ラジオ放送のために、2つの公演の間(14日と言われる)に録音セッションを組んだのだろう。ただし、12日の公演後に13日のみのリハーサルで録音が可能だったのか疑問はあるが、プログラムが2曲であり、録音が14日午後以降であれば、当日午前もリハーサル時間を取ることが可能で、無理ではないのかも知れない。
ワルターは、長いキャリアの中でアメリカ各地のオーケストラを指揮しているが、フィラデルフィア管については、意外にも1944年から1948年にかけて、定期演奏会とツアーを含めて6回(2回公演なので計12公演)指揮したに過ぎず意外に少ない。ただし同じく米東海岸のボストン響についても同様の状況で、1923年から1947年まで9回15公演指揮したのみだった。ワルターにとって、まずはニューヨーク・フィルが活動の中心であり、生活拠点だった西海岸のロサンゼルス・フィルなどがそれに次ぐ存在だったのだろう。一方、フィラデルフィア管やボストン響としても、当時はオーマンディやクーセヴィツキーが地元で好評を得ており、頻繁に大物のワルターを招く必要がなかったのかも知れない。
とは言うものの、レコード会社がワルターと名門フィラデルフィア管のコンビを見逃すはずはなく、米コロンビアは、1946年1月11・12日のワルター客演の際は、プログラムにあったベートーヴェン「田園」をレコーディング(1月10日・12日、12日は公演日だが?)、1947年2月28日、3月1日の客演の際は、プログラムにあったシューベルト「未完成」をレコーディング(3月2日)するなど、抜け目なく機会を捉えてビジネスに結びつけている。後年のカラヤンのように、レコーディングを前提にコンサート・プログラムを組んだというわけではなく、コンサート・プログラムに併せてレコーディングを組み込んだのだろう。
当ディスクに話を戻すと、ワルター/フィラデルフィア管に対する米軍ラジオ放送の放送用録音は、1944年2月14日のベートーヴェン以外にも実施され、直前の2月11・12日のコンサートで演奏されたブラームスの交響曲第2番に、実演では取り上げなかった悲劇的序曲とアメリカ国歌を加えたプログラムをコンサートの前後に録音し、後にプライベート・レーベルでCD化されている。こちらもライブと称されているが、聴衆を入れずに行われた放送用セッションだったと思われる。
いずれにしてもベテランのワルターは、さすがにどのオーケストラを指揮しても自らの刻印を記しており、当ディスクについても、以前からのロマン的柔和な表現に、渡米後、時代の趨勢に合わせて身に付けたスケールの大きさや客観性を加え、後年とほぼ同様の完成された「英雄」像を示していると言える。
ブルーノ・ワルターは、当ディスク以外にベートーヴェンの「英雄」を1941年と1949年米コロンビアにニューヨーク・フィルと、1958年同じく米コロンビアにコロンビア響とスタジオ録音したほか、1957年にライブ録音していた。また、「プロメテウスの創造物」序曲を1930年英HMVにブリティッシュ響とスタジオ録音したほか、1947年と1953年にライブ録音していた。

●高音質ステレオ録音 シャルル・ミュンシュ/ボストン響
ベートーヴェン交響曲第4番、第7番 1961年ライブ
プレミエ 60140DF
ベートーヴェン 交響曲第4番、第7番
シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団
1961年7月30日・8月6日、タングルウッド・ミュージック・シェード
ステレオ ライブ
※ミュンシュ/ボストン響(BSO)によるバークシャー音楽祭(現・タングルウッド音楽祭)におけるライブ。アメリカ人コレクターからの提供音源で、地元ボストンのラジオ局WGBHによるFM放送のエア・チェックと思われる。ちなみに第4番は、当レーベル既出60013DF(1959年8月7日録音)とは別演奏。2曲とも非常に優秀なステレオ録音で、ヒス・ノイズ、会場ノイズも皆無で、当時のメジャー・レコード会社のスタジオ録音に匹敵する音質。良好な受信環境の元、高価で高品質な機材を使用して録音したのだろう。特に第4番はバランスも良好で申し分ない状態。一方第7番は音質自体は優秀だが、オリジナルの状態ではやや低域過剰で、管やティンパニーが強い反面、弦が少々弱く、バランスが悪かった。2曲の録音日は1週間空いているが、その間に地元ボストンのラジオ局WGBHが大幅にマイク・セッティングを変更したとは考えられず、おそらく交響曲第4番を基準に設定したマイク・セッティングが、作品がよりスケールアップした第7番には、低域過剰などのバランスの悪さをもたらしたのだろう。ディスク化に当たっては、周波数バランス、管の飛び出しなどをイコライジング等によって改善を行った。強奏時の弦の弱さは完全には改善できなかったが、一般に会場での実演では、金管の強奏で弦がかき消される場合も多く、実際の演奏を聴いているバランスに近いと思われ、ティンパニーの強打なども含めてミュンシュのライブの凄さを生々しく伝えているとも言える。
また、ミュンシュによるベートーヴェンの交響曲第7番の録音は、RCAビクターへのスタジオ録音を含めて数種残されているが、BSOとのステレオ録音としては当録音が初登場と思われる。
7月30日の演奏会は、午後2時30分開演のマチネー。冒頭に交響曲第4番、続いてリストのピアノ協奏曲第2番(バイロン・ジャニス独奏)、休憩を挟んで後半に、ピストンの「ニューイングランドの3つの情景」、リストのピアノ協奏曲第1番(同じくジャニス独奏)という、バイロン・ジャニスをメインに据えたプログラム。ジャニスは1948年のデビュー以降、優れたピアニストとして評価されていたが、当録音の前年、米ソ文化交流にアメリカ人アーティストとして初めて参加し、国際的にも大きな注目を集めていた。
ミュンシュとBSOはベートーヴェンの交響曲第4番を1952~1953年シーズンから取り上げ、同シーズンに12回、1954~1955年シーズンに1回(バークシャー音楽祭)、1956~1957年シーズンに10回、1958~1959年シーズンに1回(バークシャー音楽祭)、1960~1961年シーズンに11回と1シーズンおきに演奏している。ベートーヴェンの交響曲としてはどちらかと言うと地味な存在だが、ミュンシュ好みのレパートリーだったようだ。ちなみに当演奏はBSOとの最後の演奏に当たる貴重な録音。
一方、8月6日の演奏会も午後2時30分開演のマチネー。こちらも冒頭に交響曲第7番、休憩を挟んで、バルトークのヴィオラ協奏曲(BSO首席ジョゼフ・ド・パスクアーレ独奏)、レスピーギの「ローマの松」(当レーベル60127DFでディスク化済み)というプログラム。交響曲第7番も「ローマの松」も“ミュンシュ向き”といえるレパートリーで、会場は大いに盛り上がったことだろう。
ミュンシュとBSOはベートーヴェンの交響曲第7番を、1949~1950年シーズンに14回、2シーズン空けて1952~1953年シーズンに9回、1954~1955年シーズンに13回、1955~1956年シーズンに4回、1957~1958年シーズンに8回、1958~1959年シーズンに2回(ツアーのみ)、1960~1961年シーズンに14回(オープンリハーサル1回を含む)とこちらも第4番に劣らず頻繁に取り上げている。オーケストラにとって、ベートーヴェンの交響曲が重要なレパートリーであることは当然だが、その点で、ミュンシュはフランス国籍ながらアルザス出身で(出生時はドイツ国籍)、フランス系・独墺系レパートリーの双方を、単に得意という以上に共感を持って演奏できる、ユニークな存在だったと言える。
いずれにしても当ディスクに聴くベートーヴェンの交響曲第7番は、録音の良さも相まって、ミュンシュ/BSOによるベスト・パフォーマンスと言っても過言ではない。
シャルル・ミュンシュは、ベートーヴェンの交響曲第4番のスタジオ録音を残さず、当ディスク以外に1957年(第1楽章のみ)、1959年、1961年、1964年にライブ録音していた。また、交響曲第7番を1949年に米RCAビクターにBSOとスタジオ録音したほか、1954年、1960年、1963年にライブ録音していた。

●音質良好 フリッツ・ライナー/シカゴ響
ヘンデル「メサイア」抜粋 1957年ライブ
プレミエ 60141DF
ヘンデル「メサイア」抜粋(第1部および第2部「ハレルヤ・コーラス」)
アデル・アディソン(ソプラノ)、ラッセル・オバーリン(カウンター・テノール)
デイヴィッド・ロイド(テノール)、ドナルド・グラム(バス・バリトン)
アポロ・ミュージカル・クラブ(ヘンリー・ヴェルド合唱指揮)
ギャヴィン・ウィリアムソン(チェンバロ)
フリッツ・ライナー指揮シカゴ交響楽団
1957年12月26日、シカゴ・オーケストラ・ホール
モノラル ライブ
※ライナー/シカゴ響(CSO)によるヘンデルの「メサイア」抜粋。アメリカ人コレクターからの提供音源で、地元ラジオ局WFMTまたはニューヨークのWBAI-FMによるFM放送のエア・チェックと思われる。実際の演奏でも全曲演奏されておらず、第1部の全曲に加えて第2部「ハレルヤ・コーラス」だけの演奏だった。オリジナル音源の音質は非常に良好、ノイズもなくモノラルとしては最良の部類でモノラル末期のメジャー・レコード会社のLPに匹敵。シカゴ響によるラジオ放送は放送用に編集されていると思われ、演奏ミスや顕著な会場ノイズは、リハーサル時や2回公演の場合、他日の録音などで修正しているようだ。これがライナーの要請だったのかは不明だが、演奏の完成度は極めて高い。
ただし、声楽と合唱、管弦楽の音量バランスが若干悪く、序曲の管弦楽のみ異常に大きく、次いで独唱が大きく、合唱の音量が小さい。これは録音ミスではなく当時求められていた録音スタイルと想像される。当時のラジオ放送をそのままディスク化することも一つの見識だが、このままでは終曲の「ハレルヤ・コーラス」があまりにも貧相で物足りない。合唱団員の数は少なくないと思われるため、実際に会場で鳴り響いていたであろう音量バランスを復元するため、各種調整を行った。結果として、ライナーの「メサイア」が正しい姿で甦り、十分に満足して鑑賞できるレベルになったと言える。
記録によるとライナー/CSOがヘンデルの「メサイア」を取り上げたのは、当録音の演奏のみで極めて貴重。26日と27日の2回公演だが、「メサイア」抜粋のみのプログラムで演奏時間70分程度と、通常の定期演奏会より短い。理由は不明だが、ラジオ放送の時間の都合かも知れない。
当時はバッハやヘンデルなどバロック期の作品をオーケストラに編曲して演奏することが頻繁に行われ、ライナーもしばしば取り上げていた。「メサイア」は全曲演奏に3時間を要する大曲だが、第二次世界大戦前からレコーディングが行われ、クリスマス・シーズンには各地のオーケストラが取り上げるなどポピュラーな作品だった。しかし、ライナーはシカゴ響音楽監督就任以前のシンシナティ響やビッツバーグ響音楽監督時代にも取り上げておらず、作品と彼の美学と一致しなかったのだろうか。ただしヴェルディの「レクイエム」をレコーディングしているように、独唱と合唱が加わる大規模声楽作品を嫌っていた訳ではないと想像される。
ちなみにシカゴ響定期公演では、ライナー以前にも「メサイア」全曲の演奏記録は見当たらず、ライナー以降は、1984年にゲオルグ・ショルティ、2004年にペーター・シュライヤー、2015年にベルナール・ラバディが全曲演奏しているのみ。ただしシカゴ響では、定期公演以外のクリスマス・シーズン特別演奏会として、CSO最初の演奏会からわずか2か月後の1891年に、当ディスクに聴くアポロ・ミュージカル・クラブ(現アポロ・コーラス)と共にCSO初の「メサイア」全曲が演奏されており、CSOとアポロ・ミュージカル・クラブによるメサイア全曲は、その後1964年まで70年間、ほぼ毎年演奏されたという。
以上の事情を考慮すると、敢えてライナーがCSOと「メサイア」全曲を指揮する必要はなかったとも言え、1957年については、実態は不明だが恒例の全曲演奏が行われず、ライナーが代わりに簡略版を演奏したとも考えられる。
独唱陣に触れると、それぞれ宗教音楽作品のベテランが揃っているが、女声アルトの代わりに、古楽復興の先駆者でカウンター・テノールのラッセル・オバーリンが起用されていることが当時としては画期的。ライナー自身が古楽に精通していたという記述はないから、毎年同曲の演奏会を担当していたスタッフの中に学術的に先進的な考え方の人間が存在したのだろう。また、ピアノではなくチェンバロ(ただしモダン・チェンバロ)が使用されていることも同様だ。
いずれにしてもフリッツ・ライナーによるヘンデル「メサイア」が、抜粋とは言え、良好な録音状態で残されたことは誠に幸いだったと言える。
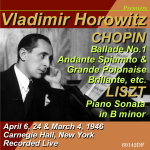
●ホロヴィッツ 1946年カーネギー・ホール・ライブ
ショパン バラード第1番、リスト ピアノ・ソナタほか
プレミエ 60142DF
ショパン
バラード第1番 ト短調 作品23
アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ 作品22
エチュード第3番 ホ長調 作品10の3「別れの曲」
エチュード第12番 ハ短調 作品10の12「革命」
マズルカ第26番 嬰ハ短調 作品41の1
マズルカ第27番 ホ短調 作品41の2
リスト
ピアノ・ソナタ ロ短調
ウラディミール・ホロヴィッツ(ピアノ)
1946年4月24日、4月6日(バラード第1番)、3月4日(リスト)
ニューヨーク・カーネギー・ホール
モノラル ライブ
※ホロヴィッツが真に「ホロヴィッツらしかった」全盛期のライブ。1946年3月から4月にかけて行われた三夜のリサイタルから。アメリカ人コレクターからの提供音源で、提供者の説明では、入手の経緯は少々複雑らしい。
オリジナルの音源は、ホロヴィッツ自身が録音サービス会社と個人契約を結び、1945年から6年間にわたりカーネギー・ホールで開催された22回の演奏会(リサイタルやオーケストラとの共演)を録音した16インチ33回転アセテート・ディスクで、ホロヴィッツが長年所有していたと言われる。レコード発売を前提としたものではなく、ホロヴィッツ自身の研究資料として録音したものと思われるが、貴重な音源という認識はなかったようで(数枚はホロヴィッツが誤って破損した)、数少ない弟子、マネージメント事務所の関係者やレコード会社、放送局の知人などに聴かせたり貸したりしていたという。後年、研究者の助言により、劣化が進むディスクから専門家の手によりテープにダビングされて保存し直され、最終的にはオリジナルのディスクも含めて米イェール大学に寄贈された。しかし、その間、このように音源が自由に外部に流出した結果、一部は早い時期からLP化されたり、中には放送に使用されたこともあったようだ。このように複数のルートで外部に出たディスクのコピー・テープがコレクターに渡ったらしく、それらが当ディスクの元となっている。
近年になって、この一連の録音から注目すべき演奏がソニー・BMGから正規音源としてセットでCD化されたが、当ディスクの音源はCDセットには含まれていない演奏である。含まれなかった理由は、演奏内容よりも、おそらくアセテート・ディスクの不良が大きく、当ディスクのオリジナル音源も、激しいスクラッチ・ノイズにより、このままでは商品化が困難な状態のものが大半だった。
ただし、ノイズを低減するソフトウェアを複数使用し、ノイズの状態や性質によってソフトウェアを使い分けたり、強音と弱音ではソフトウェアの効果が異なるため、音源を細かく分割してノイズを低減した後、再度結合するなど、音質を損ねないように細心の注意を払いながら様々な手法を試みることで、十分鑑賞に堪える音質へと改善することができた。大手のレコード会社では、費用対効果(人件費や機材と販売数量)を考慮すると、このような手間はかけられないのだろう。オリジナルの音源自体はプロのエンジニアによって録音されており、音質やバランスは良好で、ノイズのみ低減できれば、手を加える必要がないことも幸いした。結果として、ホロヴィッツ独特の最弱音と強音のダイナミックレンジの広大さ、低音の破壊的とも思える強打、テンポの極端な変動、さらには歌うような旋律など、ホロヴィッツのピアニズムを余すことなく再現できた。
先ほどホロヴィッツが1945年から6年間にわたりカーネギー・ホールで22回の演奏会を行ったと記したが、記録によると1946年には3回の演奏会を開催しており、当ディスクでは、その中からピックアップされている。16インチ33回転アセテート・ディスクは、連続20分程度録音が可能だが、当然ながら演奏会全体を収録するには複数枚(4~5枚か)のディスクが必要で、外部流出した音源も1回の演奏会単位ではなかったらしく、今回入手した音源のみでは、演奏会全体の再現はできなかった。
もっともホロヴィッツの演奏会(リサイタル)プログラムは、ソナタなどの大曲や、ある流派の作曲家を系統立って紹介するよりも、19世紀のサロン・コンサート風に様々な作曲家の小品を気ままに並べるという傾向が多く、CD化した場合、ホロヴィッツの演奏会を再現するという意味はあるが、繰り返し聴く場合には適当ではないとも思われる。
ちなみに、1946年3月4日のリサイタルは、スカルラッティのソナタ3曲、メンデルスゾーンの無言歌3曲、当ディスクに聴くリストのソナタ、休憩を挟んでカバレフスキーの24のプレリュードから10曲、ショパンのノクターン2曲とポロネーズ1曲、アンコールとしてドビュッシーの「子供の領分」から「人形へのセレナード」、シューマンの「トロイメライ」、モシュコフスキの15のエチュードから1曲、最後に定番のスーザ=ホロヴィッツ編「星条旗よ永遠なれ」という構成。
また4月6日は、ハイドンのソナタ、シューマンの幻想曲、プロコフィエフのトッカータ、休憩を挟んで、ドビュッシーのプレリュード第2巻とエチュードからそれぞれ2曲ずつ、当ディスクに聴くショパンのバラード第1番、マズルカ1曲、リスト=ホロヴィッツ編のメンデルスゾーンの結婚行進曲と変奏曲、アンコールとしてショパンのノクターンとワルツ、これも定番のホロヴィッツ編カルメン変奏曲という構成。
4月24日は、メンデルスゾーンの厳格な変奏曲、シューマンのアラベスク、プロコフィエフのソナタ第7番、休憩を挟んで、当ディスクに聴くショパンのアンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズほか5曲、リスト=ホロヴィッツ編のメンデルスゾーンの結婚行進曲と変奏曲、アンコールとして、スカルラッティのソナタ、シューマンの「トロイメライ」、カバレフスキーの24のプレリュードから1曲、ブラームスのワルツ、最後にスーザ=ホロヴィッツ編「星条旗よ永遠なれ」という構成。比較的ショパンをまとめて弾いている。また、上記3回のカーネギー・ホール公演の間に、3月24日にワシントンDC、4月4日にフィラデルフィアでリサイタル、4月18日と20日には、ボストン響の定期演奏会でラフマニノフのピアノ協奏曲第3番を演奏しており、多忙だが充実した演奏活動を行っていた。
ホロヴィッツは当時42歳。技術的にも音楽的にも一つの絶頂期を迎えていた時期。当ディスクでは、従来発表が困難だった音源が、大幅に改善された音質で公開されたことに意義がある。
ウラディミール・ホロヴィッツは当ディスク以外に、ショパンのバラード第1番を1947年米RCAビクターにスタジオ録音したほか、1965年、1968年(2種)、1976年(3種)、1981年、1982年にライブ録音。アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズを1945年米RCAビクターにスタジオ録音したほか1950年にライブ録音。エチュード第3番を1951年米RCAビクター、1972年米コロンビアにスタジオ録音。エチュード第12番を1963年と1972年米コロンビアにスタジオ録音。マズルカ第26番を1949年米RCAビクターにスタジオ録音。マズルカ第27番を1933年英HMV、1973年米コロンビアにスタジオ録音したほか1949年にライブ録音。リストのピアノ・ソナタを1932年英HMVにスタジオ録音したほか、1949年と1976年にライブ録音していた。
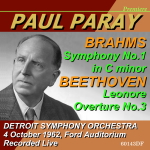
●音質良好 パレー/デトロイト響 1962年ライブ
ブラームス 交響曲第1番、ベートーヴェン レオノーレ序曲第3番
プレミエ 60143DF
ブラームス 交響曲第1番
ベートーヴェン レオノーレ序曲第3番
ポール・パレー指揮デトロイト交響楽団
1962年10月4日、デトロイト・フォード・オーディトリアム
モノラル ライブ
※ポール・パレー/デトロイト響(DSO)によるブラームスの交響曲第1番とベートーヴェンのレオノーレ序曲第3番。アメリカ人コレクターからの提供音源で、エアチェックとのことだが、受信ノイズもなく安定した音質であるため、放送局保管音源のコピーかも知れない。ただしオリジナルの状態は、ノイズがなく音質は良好ではあるものの、高域不足で中域ばかりが盛り上がったバランスの悪いもの。元々そのような音質なのかテープの経年劣化が原因かは不明だが、おそらく地元デトロイトの放送局WWJラジオによる録音スタイルによる可能性が高い。ポピュラー・ミュージック寄りの音作りに近く、当レーベルで発売済みのバルビローリ/ヒューストン響によるブラームスの交響曲第3番(プレミエ60119F)のオリジナル音源の音質も、中域主体の冴えない、よく似た状態で、当時アメリカの一部放送局によるオーケストラ録音の傾向だったようだ。ちなみに同時代のボストン響やシカゴ響、ニューヨーク・フィルの放送録音は基本的にフラット・バランスで、現代の感覚でも違和感のない音づくりとなっており、録音ポリシーの違いが興味深い。
ディスク化に当たっては、上記のような周波数バランスの改善と周波数帯域の拡大を行い、ポピュラー・ミュージックからシンフォニー・オーケストラ寄りのスタイルへと「変換」。音質は元から良好だったため、不満なく鑑賞できる音質へと改善することができた。会場ノイズはほぼ皆無。
1962年10月4日はDSOの定期公演で、1962~1963年シーズン開幕の演奏会。前半にベートーヴェンのレオノーレ序曲第3番、続いてR・シュトラウスの「死と変容」、アメリカの現代作曲家ジェームズ・コーンの「旅する異邦人」による変奏曲(初演)、おそらく休憩を挟んで後半にブラームスの交響曲第1番というプログラム。
当ディスクに聴くベートーヴェンのレオノーレ序曲第3番とブラームスの交響曲第1番は、パレーがスタジオ録音を残さなかった作品だが、いずれもポピュラーな有名作品で、DSOの音楽監督であるパレーとしては当然演奏会にかけるべきレパートリー。パレーの演奏も手慣れた印象だが、いずれも快速の「パレー・スタイル」。ただし、ブラームスでは第1楽章序奏を速めのテンポで終えた後、主部に入るところで急にテンポを落とし、遅めのテンポで第1楽章を終わるという意外な展開。そのためか第2楽章以降、全体としては快速だが、それほど速くは感じない。演奏表現として充実しているからだろう。なお、第2楽章終結部のヴァイオリン・ソロ演奏者は、当時DSOのコンサート・マスターだった名手ミッシャ・ミシャコフと思われる。
ポール・パレーは、ブラームスの交響曲第1番のスタジオ録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音と思われる。また、ベートーヴェンのレオノーレ序曲第3番もスタジオ録音を残さず、当ディスク以外に1961年にDSOとライブ録音していた。

●音質良好 パレー/デトロイト響 1960年ライブ
チャイコフスキー 交響曲第6番「悲愴」、フランク 交響詩「プシュケ」抜粋
プレミエ 60144DF
チャイコフスキー 交響曲第6番「悲愴」
フランク 交響詩「プシュケ」抜粋
ポール・パレー指揮デトロイト交響楽団
1960年10月6日、デトロイト・フォード・オーディトリアム
モノラル ライブ
※ポール・パレー/デトロイト響(DSO)によるチャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」とフランクの交響詩「プシュケ」抜粋。アメリカ人コレクターからの提供音源で、エアチェックとのことだが、受信ノイズもなく安定した音質であるため、放送局保管音源のコピーかも知れない。ただしオリジナルの状態は、ノイズがなく音質は良好ではあるものの、高域不足で中域ばかりが盛り上がったバランスの悪いもの。元々そのような音質なのかテープの経年劣化が原因かは不明だが、おそらく地元デトロイトの放送局WWJラジオによる録音スタイルによる可能性が高い。ポピュラー・ミュージック寄りの音作りに近く、当レーベルで発売済みのバルビローリ/ヒューストン響によるブラームスの交響曲第3番(プレミエ60119F)のオリジナル音源の音質も、中域主体の冴えない、よく似た状態で、当時アメリカの一部放送局によるオーケストラ録音の傾向だったようだ。ちなみに同時代のボストン響やシカゴ響、ニューヨーク・フィルの放送録音は基本的にフラット・バランスで、現代の感覚でも違和感のない音づくりとなっており、録音ポリシーの違いが興味深い。
ディスク化に当たっては、上記のような周波数バランスの改善と周波数帯域の拡大を行い、ポピュラー・ミュージックからシンフォニー・オーケストラ寄りのスタイルへと「変換」。音質は元から良好だったため、不満なく鑑賞できる音質へと改善することができた。会場ノイズはほぼ皆無。
1960年10月6日はDSOの定期公演で、1960~1961年シーズン開幕の演奏会。前半に冒頭にチャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」、続いてワーグナーの楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲、休憩を挟んで後半にフランクの交響詩「プシュケ」、最後にシャブリエの狂詩曲「スペイン」というプログラム。第二次世界大戦前まで主流だった「前半が重く後半が軽い」プログラムの典型で、1960年代初頭まではその残滓があったようだ。
ここで注目すべきは、パレーがスタジオ録音を残していないチャイコフスキーの「悲愴」。予想どおりというか快速のパレー調で、第1楽章や第4楽章など、通常の演奏であればロマンチックで濃厚な表現が多いが、パレーはそのような情緒的表現はすべて吹き飛ばした、ピリオド楽器演奏のような辛口の演奏。といっても表現が淡泊で物足りないわけではなく雄弁ともいうべきユニークなもの。スタイルは異なるがトスカニーニの演奏を思い起こさせる。ちなみにパレーは、当ディスクを含めチャイコフスキーの後期3大交響曲のライブ録音を残しており、演奏会では頻繁ではないもののしばしば取り上げていたようだ。一方のフランクはスタジオ録音も残しており、パレーにとって定番のレパートリー。同じく快速テンポだが、こちらの演奏はレコードで聴き慣れているためもあるが、極めて常識的・標準的演奏に聞こえる。フランス系作品ということでパレーの持つ音楽性と合致しているからだろう。演奏スタイルが国際化・無国籍化した現代とは異なり、指揮者がローカル・カラーを強く持っていた時代ならではの現象といえる。
ポール・パレーは、チャイコフスキーの交響曲第6番のスタジオ録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音と思われる。一方、フランクの「プシュケ」は1953年米マーキュリーにDSOとスタジオ録音したほか、1973年フランス国立放送フィルとライブ録音していた。
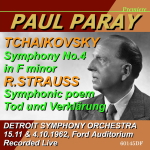
●音質良好 パレー/デトロイト響 チャイコフスキー 交響曲第4番、R・シュトラウス 交響詩「死と変容」 1962年ライブ
プレミエ 60145DF
チャイコフスキー 交響曲第4番
R・シュトラウス 交響詩「死と変容」
ポール・パレー指揮デトロイト交響楽団
1962年11月15日、10月4日、デトロイト・フォード・オーディトリアム
モノラル ライブ
※ポール・パレー/デトロイト響(DSO)によるチャイコフスキーの交響曲第4番とR・シュトラウスの交響詩「死と変容」。アメリカ人コレクターからの提供音源で、エアチェックとのことだが、受信ノイズもなく安定した音質であるため、放送局保管音源のコピーかも知れない。ただしオリジナルの状態は、ノイズがなく音質は良好ではあるものの、高域不足で中域ばかりが盛り上がったバランスの悪いもの。元々そのような音質なのかテープの経年劣化が原因かは不明だが、おそらく地元デトロイトの放送局WWJラジオによる録音スタイルによる可能性が高い。ポピュラー・ミュージック寄りの音作りに近く、当レーベルで発売済みのバルビローリ/ヒューストン響によるブラームスの交響曲第3番(プレミエ60119F)のオリジナル音源の音質も、中域主体の冴えない、よく似た状態で、当時アメリカの一部放送局によるオーケストラ録音の傾向だったようだ。ちなみに同時代のボストン響やシカゴ響、ニューヨーク・フィルの放送録音は基本的にフラット・バランスで、現代の感覚でも違和感のない音づくりとなっており、録音ポリシーの違いが興味深い。
またチャイコフスキーについては、オーボエなど木管のソロの音量が極端に小さいという問題もあった。ステージ上方のワンポイント・マイクのみで、その他の補助マイクが少ないか、または皆無だったのだろう。
ディスク化に当たっては、上記のような周波数バランスの改善と周波数帯域の拡大を行い、ポピュラー・ミュージックからシンフォニー・オーケストラ寄りのスタイルへと「変換」。木管のソロについては、個々の演奏部分について音量バランスを調整した。音質自体は元から良好だったため、不満なく鑑賞できる音質へと改善できた。会場ノイズはほぼ皆無。
11月15日はDSOの定期公演で午後8時30分の開演、前半に冒頭にワーグナーの歌劇「タンホイザー」序曲、続いてモーツァルトのフルートとハープのための協奏曲(独奏は、それぞれDSO首席のアルバート・ティプトンとイライゼ(またはエリゼー)・ヨッキー)、休憩を挟んで後半にチャイコフスキーの交響曲第4番というプログラム。
10月4日もDSOの定期公演で、1962~1963年シーズン開幕の演奏会。前半にベートーヴェンのレオノーレ序曲第3番、続いてR・シュトラウスの「死と変容」、アメリカの現代作曲家ジェームズ・コーンの「旅する異邦人」による変奏曲(初演)、おそらく休憩を挟んで後半にブラームスの交響曲第1番というプログラム。ちなみにベートーヴェンのレオノーレ序曲第3番とブラームスの交響曲第1番は当レーベル・プレミエ60143DFでディスク済みである。
10月の公演は、第二次世界大戦前まで主流だった「前半が重く後半が軽い」プログラムの典型だが、11月の公演は逆の形で現代風。デトロイトでは1960年代初頭にプログラミングの方針転換があり、当時はその端境期だったようだ。
当ディスクに聴くチャイコフスキーとR・シュトラウスは、いずれもパレーがスタジオ録音を残していない作品。既発売のブラームスの交響曲第1番やチャイコフスキーの「悲愴」も同じくスタジオ録音を残しておらず、貴重な録音と言えるが、ブラームスや「悲愴」はパレー独特のユニークな解釈が目立ち、かなり個性的な演奏と言えた。しかし当ディスクのチャイコフスキーとR・シュトラウスは、パレー独特の快速テンポも、若干速めという程度で違和感はなく、各所の表現も穏当な範囲に収まっている。しかしそれにもかかわらず凡庸(良く言えば堅実?)な演奏とはならない点はさすがにパレーであり、表面的には何もしていないように思えるが、聴き終えると充実した非常な名演であることが理解できる。エキセントリック・個性的な表現を行わなくても優れた演奏が出来ることは、巨匠指揮者たる所以かも知れない。少なくともDSOというアメリカのメジャー・オーケストラで10年以上にわたって常任指揮者を務めるには、数多のオーケストラ・スタンダード・レパートリーを単に個性的表現だけで乗り切ることは不可能だろう。
先にDSOをメジャー・オーケストラと表したが、パレーが常任指揮者に招かれる前は、1929年の大恐慌の影響を引きずり、1940 年代後半に財政破綻、1949
年には演奏会も中止となるなど崩壊状態だった。当時「ビッグ3」と言われた世界的自動車メーカーの本社・工場が存在する大産業都市でさえも、オーケストラ経営は厳しいことが理解できる。1951
年、地元化学メーカー経営者だったジョン・B・フォード・ジュニア(自動車メーカー・フォード家との関係は不明)がDSOの経営に関与。彼が中心となって「デトロイト・プラン」と称する再建計画を実施、主要自動車メーカーなどの製造業、金融機関など各社が、1955年までそれぞれ毎年1万ドルを支援することで、ようやくオーケストラ再建のめどが立った。この再建計画の一環として、1953年からオーケストラ再建を託されたのがパレーだった。パレーは1945年から1951
年にかけて、ボストン響、ニューヨーク・フィル、シンシナティ響、フィラデルフィア管、ピッツバーグ響、シカゴ響などに客演しており、おそらくその評判を聞いたDSOの理事会がパレーにアプローチしたのだろう。
パレーが常任指揮者に就任すると同時に楽員も増強され、ストック指揮シカゴ響、ストコフスキー指揮フィラデルフィア管、トスカニーニ指揮NBC響でコンサート・マスターを歴任した名手ミッシャ・ミシャコフを招聘するなど、オーケストラは急速に実力を向上させた。
1954年1月、DSOは北米東部、中部大西洋岸、南部の主要都市を巡り、ニューヨークのカーネギーホールでも演奏会を行った。1954年1月15日のコンサートは、ニューヨークの批評家に深い感銘を与え、指揮者とオーケストラ双方が賞賛を浴びた。ウェーバーの歌劇「魔弾の射手」序曲、ベートーベンの交響曲第7番、ワーグナーの楽劇「トリスタンとイゾルデ」から「前奏曲と愛の死」、デュリュフレの「舞曲」、ラヴェルのボレロなどが演奏されたが、作曲家・評論家のヴァージル・トムソンは、ヘラルド・トリビューン紙で次のように書いている。
「パレーは、決してオーケストラの音を無理強いしたり、バランスを崩したりしない。彼は、瞬間的な感情移入のために作品の壮大なラインを犠牲にすることはなかった。偉大な俳優のように、彼は小さな効果を捨てて、それぞれの作品を記念碑的で形あるものにした。オーケストラも、規律正しく統一されたソノリティで、素敵な響きを放っていた。この夜の音楽に心を奪われずにいられたのは、ポール・パレーのおかげだ。ベートーヴェンの第7番は、汚れが洗い流され、雄弁さを取り戻した。」
かつての常任指揮者・ガブリロヴィッチ時代からDSOを聴いてきたニューヨーク・タイムズ紙の有力な評論家オリン・ダウンズは、こんな評価を下している。
「パレーは、細部の明瞭さと完璧さ、格別に芸術的なフレージング、音色のバランス、アンサンブルの解釈における各セクションのまとまりにおいて特筆すべき成功を収め、我々がここ数日耳にした中で最も雄弁な作品解釈の一つであった。パレーがすでに多くのことを成し遂げているこのオーケストラは、自分の街で、そしてアメリカで侮れない交響楽団である。」
このようにして、デトロイト響は極めて短期間のうちに全米トップ・クラスのオーケストラへと成長した。
1955年、ポール・パレーはDSOとさらに2年契約を結び、1951年にオーケストラを復活させた「フォード・プラン」もさらに3年更新された。これはDSOの音楽的・財政的基盤が整ったことを意味した。パレーは「私の音楽人生の中で、これほど幸運で、これほど友好的な関係を築いたことはない。3年前にデトロイトに来た時に約束したことは、すべて忠実に実行されている。このような状況だからこそ、私はオーケストラ・ビルディングに全力を傾けることができるのだ。そして同じ条件の下で、この組織がますます優秀になる未来が見える」と語っている。パレーはDSO就任前のフランス時代、パリ・ラムルー管の音楽監督を務め、コロンヌ管などにもしばしば客演していたが、いずれの団体も自主運営で経営が苦しく、楽員はリハーサルを抜け出してアルバイトで収入補填することが日常茶飯事、パレー自身もスポンサー巡りを強いられた状況に比べると、DSOの安定的な運営は、別世界のように感じたことだろう。
DSOがパレー時代に急速に発展したことは、レパートリーを見ても理解できる。DSOには付属の合唱団が存在しなかったが、かつて存在していたプロの合唱団、ラッカム交響合唱団を再興。ガブリロヴィッチ以来途絶えていた、バッハの「マタイ受難曲」、ベルリオーズの「キリストの幼児」、フォーレの「レクイエム」を再演、そしてデトロイトで初めてベートーヴェンの交響曲第9番を終楽章を含めて全曲演奏するなど、合唱を必要とする主要作品がDSOで演奏可能となった。パレー以前にDSOでベートーヴェンの第9が全曲演奏されていなかったという点は、ある種驚きだ。DSOに対するパレーの貢献の大きさを象徴するものだろう
ポール・パレーは、チャイコフスキーの交響曲第4番、R・シュトラウスの交響詩「死と変容」のスタジオ録音を残さず、当ディスクがそれぞれ現在確認されている唯一の録音と思われる。
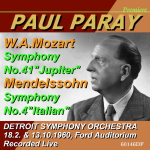
●音質良好 パレー/デトロイト響 モーツァルト 交響曲第41番「ジュピター」、メンデルスゾーン 交響曲第4番「イタリア」 1960年ライブ
プレミエ 60146DF
モーツァルト 交響曲第41番「ジュピター」
メンデルスゾーン 交響曲第4番「イタリア」
ポール・パレー指揮デトロイト交響楽団
1960年2月18日、10月13日、デトロイト・フォード・オーディトリアム
モノラル ライブ
※ポール・パレー/デトロイト響(DSO)によるモーツァルトの交響曲第41番「ジュピター」とメンデルスゾーンの交響曲第4番「イタリア」。アメリカ人コレクターからの提供音源で、エアチェックとのことだが、「イタリア」に関しては受信ノイズもなく安定した音質であるため、放送局保管音源のコピーかも知れない。「ジュピター」は確かにエアチェックらしく、高域がFM放送の上限15kHzで切れており、若干ノイズっぽい印象もある。ただし、致命的なノイズや欠落もなく、高域が不足した鈍い音質であることを除けば、それなりに安定した音質。一方「イタリア」は、こちらは高域不足というよりも低域が若干過剰で高域がマスクされた状態。それでも「ジュピター」より好条件と言える。
ディスク化に当たっては、「ジュピター」については、周波数帯域をCD上限の20kHz程度まで拡大、特に5kHz以上が不足していたため補正。低域も適度に調整。その他ドロップアウトの修正等々を行った結果、当時の水準を上回る良好な音質へと改善することができた。「イタリア」についても、周波数バランスの改善のほか、ドロップアウトの修正等々を行い、良好な音質へと改善することができた。2曲とも、一般的な鑑賞には差し支えないレベルの音質となっており、ストレスなく演奏を楽しむことができると思われる。いずれも会場ノイズはほぼ皆無。
2月18日はDSOの定期公演だが、エリザベート・シュヴァルツコップを特別ゲストに迎えた異例のプログラミング。前半冒頭にいきなりモーツァルトの「ジュピター」、続いてシュヴァルツコップの歌唱で、ヘンデルの歌劇「ジュリオ・チェーザレ」からアリア「汝のやさしい瞳を」、同じくヘンデルの合唱曲「ヘラクレス」からよりアリア「わが父よ」、おそらく休憩を挟んで後半にR・シュトラウスの歌劇「カプリッチョ」から「終景のモノローグ」という構成。ヘンデル以降がプログラム後半だった可能性もある。
10月13日もDSOの定期公演で、前半冒頭にメンデルスゾーンの「イタリア」、続いてバッハのブランデンブルク協奏曲第5番(グレン・グールドおよびDSOコンサート・マスターのミッシャ・ミシャコフとフルート首席のアルバート・ティプトン独奏)、おそらく休憩を挟んで後半に、ハワード・ハンソンの「セルゲイ・クーセヴィツキー追悼の悲歌」、ベートーヴェンのピアノ協奏曲第2番(グレン・グールド独奏)というプログラム。作品の時代も地域も統一性のない、第二次世界大戦前のプログラミングの名残を感じる。一応は、当時新進演奏家として大きな注目を集めていたグールドを中心とした構成らしい。グールドが演奏した2作品は海外でCD化されていた。
当ディスクに聴くモーツァルトの「ジュピター」とメンデルスゾーンの「イタリア」は、ポピュラーな作品ながら、いずれもパレーがスタジオ録音を残していない貴重な録音。同時発売のチャイコフスキーの交響曲第4番やR・シュトラウスの「死と変容」と同様、テンポが若干速めという程度で違和感はなく、各所の表現も妥当な範囲に収まっているが、2作品とも通常よりもスケールが大きい重厚なイメージに仕上がっている。特にメンデルスゾーンの「イタリア」は新古典主義的で軽快・軽妙な演奏が一般的だが、パレーは快速テンポながら、同時代のシューマンの交響曲にも比肩するロマン的深さを感じる点は、さすがに巨匠の芸というべきか。いずれにしても、指揮者がフランス人であることを全く感じさせないばかりか、パレーが作品の地域や時代を問わずあらゆるレパートリーに精通した指揮者だったことが理解できる。
1950年代の全米各地の有力オーケストラの大半は、ヨーロッパ出身の人間が常任指揮者や音楽監督を務めていたが、いずれの指揮者もレパートリーが広く、あらゆる作品を手際よく、しかも高度に仕上げる職人的技術に長けた者が多かった。というよりも。そのような能力を持った人間が求められていた。フランス出身のパレーやモントゥー、ミュンシュ(正確にはアルザス出身だが)も、自国フランス作品はもとより、独墺作品においても十分に説得力のある演奏が可能だった点で共通する。
ところで、パレー時代のDSOコンサート録音の大半は、1956年に完成した市の複合施設「シビック・センター」内のコンサート・ホール「ヘンリー&エドセル・フォード・オーディトリアム」におけるもの。このホールは、デトロイト市からの資金と、その名称のとおり自動車メーカーのフォード社、全国のリンカーン・マーキュリー車販売店、創業家のフォード家などからの多額の寄付により、570万ドルをかけてデトロイト川岸リヴァーフロントに建設された。パレーとDSOは、落成式から3日後の1956年10月18日、ベートーヴェンの「献堂式」序曲、パレー自作の「ジャンヌ・ダルク没後500年記念ミサ」を演奏した。
フォード・オーディトリアムはモダンなデザインと当時最新の設備を誇っていたが、残念ながらホールの音響については、完成当初から問題を抱えていた。高名な音楽評論家のハロルド・ショーンバーグはこのホールを「音響的な恐怖」と呼んだ。「いくつかの最初のコンサートに出席し、頭を振って立ち去った」「ホールには残響がなく、低音が聞こえず、音に暖かみがなかった」と記し、ホール設計の欠点を指摘した。
1957
年、エレノア・フォード(ヘンリー・フォードの一人息子エドセルの未亡人)が音響問題を解決するために資金提供を行い、ステージ上方・左右に音響反射板として機能する合板シェルが設置された。
ショーンバーグを含む多くの人が音響が改善されると信じたが根本的には解決されなかった。
1989年になって、DSOがかつて会場として使用していたオーケストラ・ホール(音響ははるかに良かった)が修復され、再び使用可能となったため、フォード・オーディトリアムはコンサート・ホールとして使用を終えた。
ホールの音響設計について、現在のような精密なコンピューター・シミュレーションが実用化される以前でもあり、それなりの音響理論は駆使されたものの、最終的には完成しなければ結果が分からず致し方ない面もあったと思うが、会場内写真を見ると、戦後のモダニズム建築の典型ともいえる装飾を排したシンプルなデザインのためか、コンサート・ホールとしては、ステージ周囲や客席の天井・側壁の音響処理が皆無。天井も内容積に比べるとやや低く、おそらく床も強固なコンクリート敷きで低音が響かず、残響も乏しいことが理解できる。一方、収容人員が2920人と比較的多いため、客席の位置によって響きが大きく異なることも想像される。おそらくヨーロッパの伝統的なコンサート・ホール設計者が見れば、綿密に調査するまでもなく、デッドな音響で問題が多いと感じただろう。
先にフォード・オーディトリアムは、当時最新の設備を誇っていたと述べたが、録音システムも同様であり、ステージ上で鳴っている直接音を収録する点については、ホールの音響が最悪でも問題はなく、結果としてパレー/DSOのライブ録音は、残響は乏しいものの音質自体は優れているものが多いことは幸運だった。また、これほど音響条件の悪い会場における演奏でも、パレー/DSOに対する評価が高まったことは、デトロイトの聴衆(や他地域の評論家)の審美眼が確かだったことの証明でもあろう。
パレーがDSO常任指揮者を退任する際のエピソードも興味深い。
1961年、75歳になったパレーは、1961~62年のシーズンを最後に常任指揮者の地位から退き、客演指揮の道に進むことを発表した。この決断にデトロイトの聴衆は猛反対し、DSOの経営陣に対して、パレーのさらに1年の留任を求める嘆願書が何百通も出された。やがて、新聞もこの運動を取り上げるようになったが、このような聴衆からの嘆願は異例のことであり、パレーがデトロイトに対して、地域社会だけでなくはるかに広い分野に貢献したことに対する評価の証しでもあった。
パレーは、デトロイトの聴衆から寄せられた要請に深く心を動かされ、1961~62年シーズンと、1962~63年のシーズンの最初の9週間を指揮することに同意した。最後のシーズンは、トーマス・シッパース、ヨーゼフ・クリップス、ヴェルナー・トルカノフスキー、シクステン・エールリンクといった共同指揮者とともに過ごし、エールリンクがDSOの常任指揮者の地位を継ぐことになった。
パレーのDSO常任指揮者としての最後のコンサートは、1962年3月30日に行われ、「フィデリオ」序曲、交響曲第1番・第9番というオール・ベートーヴェン・プログラムであった(前日29日のライブ録音がプレミエ60046DFとしてディスク化されている)。演奏に際し、聴衆はマエストロに惜別の意を表し、スタンディング・オベーションで迎え、涙ながらに送り出した。ジャーナリストのジョセフ・モスマンはデトロイト・ニュース紙に次のように書いている。
「音楽界の王が旅立ち、王家の別れを告げられた。コンサートが終わると、聴衆は立ち上がって拍手と歓声を上げ、照明が落とされ、コンサート・マスターのミッシャ・ミシャコフの合図でオーケストラが『オールド・ラング・サイン(蛍の光)』を演奏するまで、拍手は5分間も続いた。それは、デトロイトに音楽を与えてくれたパレーを大切に思う人々の、愛情や感謝の気持ちの表れであり、デトロイトに世界有数の交響楽団を育ててくれたパレーを大切に思う人々の、感動的な愛情表現であった。
デトロイトの聴衆は、パレーに別れを告げながらも、1962~63年シーズンのオープニング・コンサートに始まり、その後は客演指揮者として、パレーが定期的に戻ってくることを心待ちにした。パレーの客演は1968年まで続いた」。
ポール・パレーは、モーツァルトの交響曲第41番「ジュピター」とメンデルスゾーンの交響曲第4番「イタリア」のスタジオ録音を残さず、当ディスクがそれぞれ現在確認されている唯一の録音と思われる。

●ジネット・ヌヴー BS0・NYPライブ
プレミエ60147DF
ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲
ラヴェル ツィガーヌ
ジネット・ヌヴー(ヴァイオリン)
セルゲイ・クーセヴィツキー指揮ボストン交響楽団
シャルル・ミュンシュ指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
1947年12月23日、ボストン・シンフォニー・ホール
1949年1月2日、ニューヨーク・カーネギー・ホール
モノラル ライブレミエ
※航空機事故により惜しくも早世した名手ジネット・ヌヴーによるアメリカ公演ライブ。アメリカ人コレクターからの提供音源で、2曲とも音質がそれなりに良好で安定しているため、エアチェックではなく放送局保管音源のコピーと思われる。
1947年のベートーヴェンは連続20分程度録音可能なアセテートディスクによる収録。ディスク録音特有のスクラッチノイズはあったものの、ソフトな音質のノイズで容易に低減・除去しやすいタイプ。周波数レンジも比較的広かった。しかし低域過剰・高域不足でバランスが悪く、全体にくすんだ音質で演奏が貧相・地味に聴こえる。ソロヴァイオリンも音量レベルが極端に低く聴き取れない箇所もあった。
CD化に当たって、スクラッチノイズについてはソフトウェアにより音質を損ねることなく大半を除去。周波数バランスをイコライジング等で調整、周波数レンジも20khz程度まで仮想的に拡大。また、ソロヴァイオリンの音量レベルが低い箇所は適度に調整(ただし、こちらはヌヴーが強弱を意図的にコントロールしている可能性があるため控えめに処理)等を行った結果、1950年代半ばのモノラルLP程度まで音質が改善され、ヌヴーのヴァイオリンも輝きが増し、演奏の印象も一変した。
一方、1949年のラヴェルはテープによる録音。前年1948年にアンペックスから商用テープレコーダーが発売されており、早速導入したのだろう。1947年のベートーヴェンと比べると音質は格段に良く、フォーマットによる差は大きい。ただしこちらは逆に高域過剰・低域不足でバランスが悪かった。シャルル・ミュンシュの演奏(オーケストラ・バランス)自体がやや腰高な傾向があることは事実だが、これは極端過ぎる。CD化に当たっては、ベートーヴェンと同様に周波数バランスを調整、周波数レンジも20khz程度まで仮想的に拡大することにより、こちらも不満なく鑑賞できる音質とすることができた。
ジネット・ヌヴーは1937年に初めてアメリカ公演を行い、第二次世界大戦による中断の後、1947年に二度目のアメリカ公演を行った。1947年の公演は、すでにヨーロッパにおける名声が大西洋を越えて届いていたこともあり、アメリカのみならず南米も含む大規模な2か月間のツアーであった。当録音に聴くボストン響(BSO)との共演前の11月13・14日、ミュンシュ指揮ニューヨーク・フィル(NYP)とブラームスのヴァイオリン協奏曲を演奏しデビューを飾った。この公演について作曲家・評論家のヴァージル・トムソンは、「(ヌヴーは)若いヨーロッパのアーティストの中で、あらゆる観点から見て最高の存在。彼女は独自のリズムと激しさを持っており、興味深いアーティスト」と批評、ピアニスト・評論家のロバート・ベーガーはニューヨーク・ワールド・テレグラム紙に「内面性、熱情、力強さ、抒情性、音楽的知性の多くを備えたパリジェンヌ。背が高く、黒髪で威厳のある風貌。ローブをまとった従者のようで見る者を魅了する」と絶賛するなど、アメリカにおけるヌヴーの評価を絶対的なものとした。
当録音に聴く12月23日のBSOとの共演は10月24・25日のBSO定期演奏会に次ぐもので、これは元楽団員やその家族のための年金基金演奏会(pension
concert)として実施された1回のみの公演。プログラムはすべてベートーヴェン作品で前半に交響曲第7番、休憩を挟んでコリオラン序曲、最後にヴァイオリン協奏曲となっており明らかにヌヴーが中心の構成。当時の人気と評価の高さが窺える。ちなみにクーセヴィツキーはヌヴーとの共演後、「これほどの演奏は今後聴けないだろう」と語ったという。
ここで興味深いのは、10月24・25日のBSO定期演奏会とはヌヴーの「待遇」が異なること。10月の演奏会は、指揮は副指揮者のリチャード・バージン(バーギン)、プログラムは、冒頭にヘンリー・カウエルの交響曲第4番(世界初演)、続いてヌヴーの独奏でブラームスのヴァイオリン協奏曲、休憩を挟んでヒンデミットのシンフォニア・セレーナというもの。ブラームス以外は新作初演と渋い作品が並び、副指揮者が担当するという、ヌヴーのBSOデビュー公演としては少々地味な印象。アメリカのメジャー・オーケストラは前年シーズン中に翌シーズンの詳細なプログラムを決定するから、オーケストラ側がヌヴーの評価を留保したり、12月の年金基金演奏会で急遽プログラムを変更したりクーセヴィツキーが指揮台に上ったということは考えられず、どのような理由で10月のプログラムが組まれたのか知りたいところだ。
ちなみにここで聴くヌヴーのベートーヴェンは、マイク・セッティングの影響もあると思われるが、ハンス・ロスバウト指揮南西ドイツ放送響との共演録音と比べると強弱のレンジが広く、細かいテンポの変動も多いようだ。新即物主義スタイルの典型といえるロスバウトに対し、クーセヴィツキー(ロスバウトより20歳ほど年長)のロマン的演奏スタイルの影響とも想像されるが、ウィルヘルム・バックハウスの例に見るように、ヌヴーも共演指揮者の個性を生かしつつ演奏スタイルを自在に変化させていたのかも知れない。
一方、1949年1月2日のラヴェルはNYPの定期演奏会から。プログラムは前半がビゼーの「祖国」序曲と交響曲ハ長調、休憩を挟んでヌヴー独奏でショーソンの詩曲、ラヴェルのツィガーヌ、ダフニスとクロエ第2組曲というもので、ミュンシュお得意のフランス・プログラムにヌヴーが加わった形。前年1948年12月30・31日にもヌヴーが同じ作品で登場しており、こちらは「祖国」序曲が省かれ、ダフニスの代わりにオネゲルの交響曲第4番(アメリカ初演)という構成で、やや渋めのプログラム。ヌヴーの演奏は、以前から共演も多かったミュンシュとの相性も良く、まさしく水を得た魚状態。
ラヴェルの演奏を含む1949年のアメリカ・ツアーは前年10月から3か月にわたる長期ツアーで、全米20都市で約60回のコンサートを開いた。この中では、1949年1月6・7日にユージン・オーマンディ指揮シカゴ交響楽団とシベリウスのヴァイオリン協奏曲を演奏しており、共演したオーマンディはヌヴーについて「最も偉大な女性ヴァイオリニスト、そして私は現代の最も偉大な解釈者の一人とまで言いたい」と述べている(この演奏はライブ録音が残っている可能性がある)。
ヌヴーは1948年から49年にかけて行われた3回目のアメリカ・ツアー後、わずか10か月後の1949年10月には再びアメリカ・ツアーを計画、10月27日パリをエール・フランス機で出発したが、同機は翌28日にアゾレス諸島サンミゲル島に墜落、ヌヴーを含む乗客・乗員48名全員が死亡した。
ヌヴーと契約を交わしていた英HMV/コロンビアは、翌1950年にはブラームスのヴァイオリン・ソナタ(エトヴィン・フィッシャーのピアノ)、ベートーヴェンとチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲(カラヤン指揮)のレコーディングを予定していたが、残念ながらその機会は永久に失われた。なお、カラヤンとは1948年4月17日にウィーン・フィルとベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲を演奏しており、不完全ながら録音が残っている。また、実現しなかったブラームスのヴァイオリン・ソナタについては、ジョコンダ・デ・ヴィートが代役として起用されたといわれるが、実現は4年後と時期が離れており真偽は不明である。
ところで、ヌヴーは若くして国際的スターダムに上がり、レコーディングにも旺盛に取り組んだといえるが、例えばブラームスのヴァイオリン協奏曲のスタジオ録音とライブ録音の演奏を比較すれば、録音の善し悪しは別にしてライブ録音の方が明らかに活気に満ちており優れていると言わざるを得ない。ヌヴーが残したスタジオ録音はおそらく全て78回転SP(シェラック)録音であり、大曲の場合は作品を約4分ごとに分割し、その部分を3~4回程度繰り返して録音(音を刻むワックス盤が脆弱で数種のスペアを用意した)、それらを各パートごとに繰り返して全曲録音を完成させるというシステムだった。かつて日本の評論家がヌヴーの録音について「SP盤1面の後半になると演奏に生気が出て、ようやく集中力が増した頃に1面分の録音が終了する」印象があると述べていたが、これを見る限り、ヌヴーの演奏はもちろんスタジオ録音も優れてはいるが、その本来の姿はライブにあると言っても良いかも知れない。
ジネット・ヌヴーは、ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲のスタジオ録音を残さず、当ディスクの演奏の他、1949年のライブ録音が残されている。一方、ラヴェルのツィガーヌを1946年英コロンビアにピアノ伴奏版を録音していた。