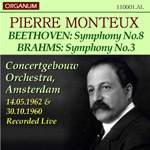
MENU PAGE → http://www.ne.jp/asahi/classical/disc/index2.html
ORGANUM(オルガヌム)
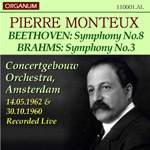
●モントゥー コンセルトヘボウ・ライブ ベートーヴェン交響曲第8番、ブラームス交響曲第3番
オルガヌム110001AL
ベートーヴェン 交響曲第8番
ブラームス 交響曲第3番
ピエール・モントゥー指揮コンセルトヘボウ管弦楽団
1962年5月14日、1960年10月30日、コンセルトヘボウ、 アムステルダム ライブ、モノラル
※モノラルながら音質良好。モントゥーはこのほかに、ベートーヴェンを1950年サンフランシスコ響、1959年ウィーン・フィルとスタジオ録音、また、1955年フランス国立放送管、1961年シカゴ響、1963年ロンドン響とライブ録音しており、ブラームスは、1956年にニューヨーク・フィル、1962年にBBCノーザン交響楽団とライブ録音していた。
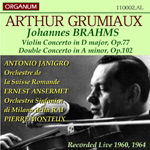
●グリュミオー ライブ ブラームス ヴァイオリン協奏曲、ヴァイオリンとチェロの二重協奏曲
オルガヌム110002AL
ブラームス ヴァイオリン協奏曲
ブラームス ヴァイオリンとチェロの二重協奏曲
アルチュール・グリュミオー(vl)、アントニオ・ヤニグロ(vc)
エルネスト・アンセルメ指揮スイス・ロマンド管弦楽団
ピエール・モントゥー指揮ミラノ・イタリア放送交響楽団
1960年1月27日、ヴィクトリア・ホール、ジュネーブ
1964年4月12日、ミラノ・ヴェルディ音楽院ホール
ライブ、モノラル
※2曲とも音質良好。グリュミオーはヴァイオリン協奏曲を1958年と1971年にスタジオ録音していた。アンセルメとは契約レコード会社が異なるためライブ録音ならではの共演。二重協奏曲はスタジオ録音を残さず、本録音が現在確認されている唯一の録音。ちなみに録音は1962年という資料もあるが、1964年が正しければ、モントゥー生涯最後の演奏会(の一つ)である。
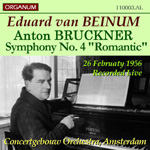
●ベイヌム/コンセルトヘボウのブルックナー交響曲第4番 1956年?ライブ
オルガヌム110003AL
ブルックナー 交響曲第4番「ロマンチック」(ハース版)
エドゥアルド・ファン・ベイヌム指揮コンセルトヘボウ管弦楽団
1956年2月26日?、コンセルトヘボウ、
アムステルダム ライブ モノラル
※現在確認されているベイヌム唯一の「ロマンチック」。ハース版による演奏。かつて海外盤で発売されていたものと同一の演奏だが、おそらく異なる音源からのCD化のため、既発盤にあった音量レベルの不自然な変動がなく、ドロップアウトも極小で十分鑑賞に堪えるようになった。また、録音年月日についてジャケットには1956年と表記されているが、1952年6月21日スヘフェニンヘン・クアハウス、または22日アムステルダム・コンセルトヘボウのいずれかが正しいようだ。ベイヌムはブルックナーの交響曲のうち、7番を1947年と1953年英デッカに、8番を1955年、9番を1956年蘭フィリップスにそれぞれスタジオ録音していたほか、5番を1959年、8番を1955年にライブ録音していた。。
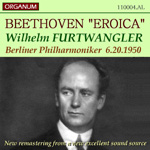
●高音質音源によるフルトヴェングラー/BPO ベートーヴェン「エロイカ」 1950年ライブ
オルガヌム110004AL
ベートーヴェン 交響曲第3番「英雄」
ウィルヘルム・フルトヴェングラー指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
1950年6月20日、ティタニア・パラスト、ベルリン ライブ モノラル
※音質は極めて良好。この演奏は、仏ターラや独アウディーテからも既出の有名な録音だが、当ディスクは、上記レーベルが独自のマスタリングを行う前のオリジナル音源から、音質劣化を避けるため一切の加工を行わずに制作されたか、または別の高音質音源を使用したと思われる。音質は生々しく、解像度も高いため細部をよく聞き取ることができ、フルトヴェングラーの音作りのすごさがよく分かる。楽章間の聴衆ノイズは収録されているが、ラジオ放送のためか拍手はカットされている。
1950年、フルトヴェングラーは64歳だったが、壮年期の活力を維持しており、熱いライブを繰り広げていた。演奏活動は多忙で、1月初めにはミュンヘン・フィル。その後1月下旬~2月はウィーン・フィル(VPO)とのコンサートとレコード録音。3月から4月初旬にミラノ・スカラ座で「リング」の上演指揮。4月中旬~5月にはブエノスアイレスのコロン劇場管。5月下旬にはロンドン・フィルハーモニア管、キルステン・フラグスタートと共演し、R・シュトラウス「4つの最後の歌」を世界初演。5月末~6月中旬まではベルリン・フィル(BPO)とドイツ各地とスイス、フランスへのツアー。その後ベルリンに戻り、当ディスクの演奏を含む17日から4日間のコンサートという超過密スケジュールで、健康状態が心配なほど。
当ディスクに聴く4日間公演最終日の20日はプログラムが異なり、ベルリン・フィルハーモニー協会会員のための特別演奏会として、ヘンデルの合奏協奏曲第10番、ブラームスのハイドン変奏曲、ヒンデミットの管弦楽のための協奏曲、ベートーヴェンの「英雄」が演奏された。
フルトヴェングラーによる「英雄」の録音は、ライブ録音も含めて現在11種ほど確認されている。録音順としては、1944年VPOとの放送録音(いわゆる「ウラニアのエロイカ」)、1949年英HMVへのVPOとのSPスタジオ録音、そして当録音となる。BPOと録音としては現在確認されている最も早期のもので、BPOとの共演中、最も充実した演奏という評価をされている。
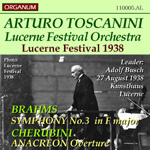
●トスカニーニ/1938年ルツェルン音楽祭ライブ ブラームス 交響曲第3番ほか
オルガヌム110005AL
ブラームス 交響曲第3番
ケルビーニ 歌劇「アナクレオン」序曲
アルトゥーロ・トスカニーニ指揮ルツェルン祝祭管弦楽団
1938年8月27日、ルツェルン・クンストハウス、ライブ モノラル
※1938年ルツェルン音楽祭における貴重なライブ録音。会場からの短波放送を外国(米英のいずれか?)の放送局が受信し、アセテート盤に記録したものと思われる。古いアセテート盤のスクラッチノイズや放送の電波状態の変動による一部の音質変化、混信によるノイズなどがある。当日は、上記の曲目に加えてモーツァルトの交響曲第40番、ワーグナー「マイスタージンガー」第1幕への前奏曲が演奏され、こちらも録音が残っているが、録音状態がさらに劣悪でCD化は断念、比較的状態の良い2曲のみ発売したという。ケルビーニはかつてLPが出ていた。
ジャケットの注意書きにもあるように、一般的な意味で録音状態は良好とは言い難いが、メンゲルベルクの第2次世界大戦中のアセテート盤によるライブ録音と同程度で、何とか鑑賞にたえる状態か。ケルビーニよりもブラームスの方が音質が安定していることが有り難い。そもそも録音が残っていたこと自体が奇跡的ともいえる。
1938年3月、ナチス・ドイツがオーストリアを併合した結果、同年夏に開催予定のザルツブルク音楽祭へ出演する機会を失ったユダヤ系や、ナチス政権に反発する音楽家が集まり、ルツェルン音楽祭が開催された。同地では以前から小規模な音楽祭が開催されていたが、ナチスに対抗するため一流演奏家が終結。国際的な音楽祭として再出発することになった。開催準備をすすめていたヴァイオリニストのアドルフ・ブッシュがトスカニーニに出演を依頼し、ブッシュがリーダーを務める祝祭管弦楽団を指揮した。管弦楽団は、ブッシュの弟ヘルマン(チェロ)やカール・ドクトール(ヴィオラ)らブッシュ四重奏団員のほか、ヴァイオリンのシュテフィ・ゲイエル、チェロのアウグスト・ヴェンツィンガー、アンリ・オネゲル、フルートのアンドレ・ペパンなど優秀なメンバーが揃った。この録音はトスカニーニによる2日目の演奏の模様。
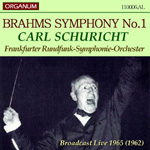
●シューリヒト ライブ ブラームス 交響曲第1番
オルガヌム110006AL
ブラームス 交響曲第1番
カール・シューリヒト指揮フランクフルト放送交響楽団
1965年または1962年3月22日もしくは23日録音、フランクフルト放送大ホール
ライブ モノラル
※録音年は確定していない。録音状態は1960年代前半の標準レベルだが、明快な音色で、シューリヒトの演奏スタイルにふさわしい録音。
20年ほど前にイタリアのマイナーレーベルで発売されたのみで、なぜか再発売されず、長らく入手不能だった。終楽章のコーダに欠落があることが原因とも言われるが、当盤ではリピート部分を使って違和感なく修正されている。
シューリヒトは同曲のスタジオ録音を残さず、当盤のほか1953年(スイス・ロマンド管)、1959年(フランス国立放送管)、1963年(シュツットガルト放送響)の3種のライブ録音が現在までに確認されている。
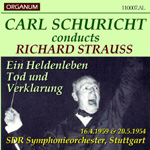
●シューリヒト ライブ 「英雄の生涯」「死と変容」
オルガヌム110007AL
R・シュトラウス 交響詩「英雄の生涯」、交響詩「死と変容」
カール・シューリヒト指揮シュツットガルト放送交響楽団
1959年4月16日、1954年5月20日録音 ライブ モノラル
※※「英雄の生涯」は、1950年代中頃のレコード用スタジオ録音と同等の好録音。会場ノイズが聞き取れないため、聴衆を入れずに行った放送のための演奏と思われる。「死と変容」は若干ヒスノイズが残るものの、当時の放送録音の水準を上回る。なお、ヒスノイズについては音質を損ねない範囲で低減されている。
シューリヒトは両曲ともスタジオ録音を残さず、上記録音が現在確認されている唯一の録音だが、独ヘンスラー・レーベルのシューリヒト・ライブ・シリーズにも含まれておらず、なぜかあまり注目されない演奏である。
ちなみにシューリヒトは、当録音以外に「英雄の生涯」を1936年(ベルリン・フィル)、1957年(パリ音楽院管)、1958年(ルツェルン祝祭管)の3回、「死と変容」を1928年(セント・ルイス響)、1930年(ドレスデン・フィル)、1933年、1937、1938年(いずれもハーグ・フィル)、1947年(ジェノヴァ歌劇場管)、1950年(ボローニャ歌劇場管)の7回取り上げた記録があるが、キャリアの長さから考えると演奏の機会は少なかったようだ。
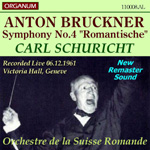
●シューリヒト 1961年ライブ ブルックナー 交響曲第4番「ロマンティック」
オルガヌム110008AL
ブルックナー 交響曲第4番
カール・シューリヒト指揮スイス・ロマンド管弦楽団
1961年12月6日、ヴィクトリア・ホール、ジュネーブ ライブ モノラル
※シューリヒトは同曲のスタジオ録音を残さず、現在確認されているのは1955年(シュツットガルト放送響)、1961年(本CD-R)の2種。端正な1955年録音に比べ、即興的なのが1961年録音といわれる。戦後スイスに住んだシューリヒトはアンセルメと親交を結び、たびたびスイス・ロマンド管に客演した。
今回のプレスから再マスタリングが行われてヒスノイズが大幅に低減、ドロップアウトも改善され、聴きやすくなった。
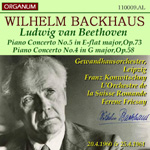
●バックハウス/コンヴィチュニー、フリッチャイ ライブ ベートーヴェン「皇帝」、4番
オルガヌム110009AL
ベートーヴェン ピアノ協奏曲第5番「皇帝」、ピアノ協奏曲第4番
ウィルヘルム・バックハウス(p)
フランツ・コンヴィチュニー指揮ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団
フェレンツ・フリッチャイ指揮スイス・ロマンド管弦楽団
1960年4月20日、コングレスハレ、ライプツィヒ
1961年4月25日、ヴィクトリア・ホール、ジュネーブ
ライブ モノラル
※モノラルながら2曲とも音質良好。バックハウスによる「皇帝」の録音は、スタジオ録音・ライブ録音含めて数多く残されているが、奔放で即興的なシューリヒト盤、力強く推進力に富むカイルベルト盤、落ち着いた格調の高さが印象的なコンヴィチュニー盤というように、バックハウスがそれぞれの指揮者の個性を活かしているようだ。共演者によって演奏スタイルを変えるという、芸風の幅広さや柔軟性が興味深い。第4番は、レコード会社による契約の影響でスタジオ録音が実現しなかったフリッチャイとの共演が注目される。
バックハウスは「皇帝」を、1927年独エレクトローラ(英HMV)に、1953年と1959年英デッカにスタジオ録音したほか、7種ほどのライブ録音が現在までに確認されている。第4番は、1929年から1930年にかけて英HMVに、1951年と1959年に英デッカにスタジオ録音したほか、現在までにライブ録音6種とテレビ放送用録画が1種確認されている。

●バックハウス/シューリヒト ライブ ブラームス ピアノ協奏曲第2番
オルガヌム110010AL
ブラームス ピアノ協奏曲第2番
ウィルヘルム・バックハウス(p)
カール・シューリヒト指揮ルガーノ・スイス・イタリア語放送管弦楽団
1958年5月23日、アポロ劇場、ルガーノ ライブ モノラル
※おそらくルガーノ音楽祭における録音。音質良好。両者は同曲を1952年デッカにスタジオ録音している。
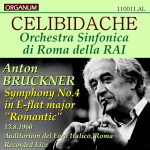
●チェリビダッケ/RAIローマ ライブ ブルックナー 交響曲第4番
オルガヌム110011AL
ブルックナー 交響曲第4番
セルジュ・チェリビダッケ指揮ローマ・イタリア放送(RAI)交響楽団
1960年3月18日、ローマ・イタリア放送オーディトリアム ライブ モノラル
1954年、当時ベルリン・フィル首席指揮者だったチェリビダッケは、終身指揮者フルトヴェングラー死去と後継カラヤンの就任により、首席指揮者の地位からほぼ「追放状態」で去ることとなった。その後は1972年に南ドイツ放送響(シュツットガルト放送響)首席客演指揮者に就任するまで、常任ポストを持たず、ヨーロッパや南米各地のオーケストラに客演を続けた。中でもRAI所属の4つのオーケストラ(トリノ、ミラノ、ローマ、ナポリ)への客演は多く、当録音もその際のもの。晩年のチェリビダッケはブルックナー演奏に定評があったが、現在残されている録音の大半は1970年代以降であり、1960年の当録音は、現在確認されているものの中では最古の部類に属する。ちなみにチェリビダッケによる最も早いブルックナー演奏の記録は1946年の交響曲第7番(ベルリン・フィル)といわれており(交響曲第4番の初演奏は1959年スカラ座管か?)、1970年以前は第7番と第4番のみ取り上げている。1971年以降、前記南ドイツ放送響への客演が増えるに従い、第4番と7番以外の交響曲がレパートリーに加わり、ブルックナー交響曲の演奏機会が急速に増えていったようだ。晩年チェリビダッケは「顧みれば私の人生は「ブルックナーすること」でした」と語ったが、ブルックナーの演奏経験が豊富なドイツのオーケストラと密接な関係を持つことで(南ドイツ放送響はシューリヒトとしばしばブルックナーを演奏していた)、彼が理想とする演奏が可能と考えたのではないか。
当録音は、その「理想」には遠い時代、非ドイツ系のイタリアの団体との演奏記録ではあるものの、管楽器の音色がやや明るいことを除けば意外なほど違和感のない、充実した演奏という印象がある。もちろん晩年のミュンヘン・フィルとの演奏に聴くような、極度に遅いテンポと精妙なアンサンブルによる円熟の境地に達した演奏とは異なるが、その反面、ブルックナーの演奏に不慣れで、しかも決して一流とはいえないオーケストラに対して、アンサンブルを適度に引き締めつつ巧みにリードしており、若干遅めのテンポ設定ながら(それでも晩年の演奏に比べればかなり速い)、個々の表現に良い意味での若々しさが感じられる。チェリビダッケは当時48歳、まだ壮年期だったのだ。
3月18日の演奏会は、おそらく前半にシューマンの交響曲第2番、休憩を挟んで後半にブルックナーというプログラム。冒頭に短い序曲などが演奏された可能性もある。当時のイタリアの聴衆にはなじみの薄い、かなり渋い曲目といえるが、営業的な収支を気にする必要がなく、幅広いレパートリーの紹介を使命とする公共放送局ならではのプログラム構成。チェリビダッケ自身の希望と放送局側方針との調整の結果、選択した曲目だったのだろう。
チェリビダッケによるブルックナー交響曲第4番の演奏機会は、ローマ・イタリア放送響との当録音後、1966年のスウェーデン放送響および南ドイツ放送響との公演まで空くことになり、チェリビダッケによる同曲初期の演奏例として貴重な存在といえる。
チェリビダッケはブルックナーの交響曲第4番を、当ディスクのほかに、1969年スウェーデン放送響、1973年南ドイツ放送響、1983年(3種?)・1988年・1989年(2種?)・1990年・1993年にそれぞれミュンヘン・フィルとライブ録音していた。
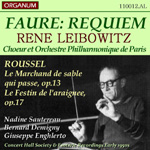
●レイボヴィッツ フォーレ レクイエム ルーセル「眠りの精」「蜘蛛の饗宴」
オルガヌム110012AL
フォーレ レクイエム
ルーセル 劇音楽「眠りの精」、交響的断章「蜘蛛の饗宴」
ナディーヌ・ソートロー(s)、ベルナール・ドミニ(br)
ルネ・レイボヴィッツ指揮パリ・フィルハーモニー管弦楽団・合唱団
1950年代録音(仏コンサートホール、米エソテリック原盤)モノラル
※レイボヴィッツはシェーンベルクに師事し作曲家としても活躍、リーダーズダイジェストのベートーヴェン交響曲全集やウィンドマシンを使って「演出」した「はげ山の一夜」などの録音で知られる。LP初期マイナーレーベルへの珍しい録音で、3曲ともレイボヴィッツ唯一の録音と思われる。復刻状態は良好だが、LPからの復刻のため、レクイエムにはわずかにスクラッチノイズあり。なお、音源として使用したLPはコンサートホール盤だが、オリジナル録音は米オーシャニック・レーベルのようだ。

●ジョコンダ・デ・ヴィート チャイコフスキー メンデルスゾーン 協奏曲
オルガヌム110013AL
チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲
メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲
ジョコンダ・デ・ヴィート(vl)
マリオ・ロッシ指揮トリノ・イタリア放送交響楽団
マルコム・サージェント指揮ロンドン交響楽団
1954年、トリノ・イタリア放送オーディトリアム ライブ
1951年11月5日、8日録音(英HMV原盤)
モノラル
※デ・ヴィートはチャイコフスキーはスタジオ録音を残さず、これは現在確認されている唯一の録音。マリオ・ロッシとは1942年のデビューコンサートでも共演していた。メンデルスゾーンは英HMVへのスタジオ録音。
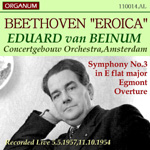
●ベイヌム ライブ ベートーヴェン交響曲第3番「英雄」
オルガヌム110014AL
ベートーヴェン 交響曲第3番「英雄」、エグモント序曲
エドアルド・ファン・ベイヌム指揮コンセルトヘボウ管弦楽団
1957年5月5日、コンセルトヘボウ、 アムステルダム(英雄)
1954年10月11日、国連本会議場、ニューヨーク(エグモント序曲)
ライブ モノラル
※2曲とも音質は比較的良好だが「英雄」は若干レベル変動がある。エグモント序曲はより安定している。ベイヌムは「英雄」のスタジオ録音を残しておらず、現在確認されているのは当演奏のみ。定期演奏会シーズン末期の特別演奏会におけるライブ。「英雄」はプログラムの前半で、後半はオランダの(当時の)現代作曲家アントン・ヴァン・デル・ホルストの「コロス(合唱隊)Ⅱ」と「夜」が演奏された。エグモント序曲の録音月日はジャケット表記は11月10日だが10月11日が正しい。1954年10月~12月にかけての北米公演の際のライブで、国連会場における演奏会は、オランダのクレフェンス元外相が同年、第9回国連総会議長に就任したことを記念したもの。この日はエグモント序曲に続き、ハイドンの交響曲第103番、ムソルグスキー「はげ山の一夜」、ラヴェル「ダフニスとクロエ」第2組曲というプログラムだった。
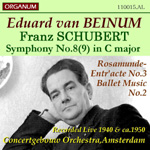
●ベイヌム ライブ シューベルト 交響曲第8(9)番「グレイト」ほか
オルガヌム110015AL
シューベルト
交響曲第8(9)番「グレイト」
エドアルド・ファン・ベイヌム指揮コンセルトヘボウ管弦楽団
1950年頃、1940年7月7日録音、コンセルトヘボウ、 アムステルダム
ライブ モノラル
※録音状態はそれぞれの年代の標準的レベルだが、特に鑑賞には問題ない音質。ベイヌムは交響曲第8(9)番「グレイト」のスタジオ録音を残しておらず、現在確認されているのはこの録音のみ。詳しい録音年月日は不明だが、残響の豊かさからコンセルトヘボウにおけるライブと思われる。演奏終了後に拍手が入るが、演奏途中の会場ノイズがほとんど聴き取れない不思議な録音。第二次世界大戦後、ベイヌムとコンセルトヘボウ管は同曲を1945、1948、1949、1958年の4回取り上げており、上記の演奏は、音質から推定すると1948年または1949年か。また会場がアムステルダムであれば48年は10月6日と7日、49年は5月20日に演奏会が行われた。一方、ロザムンデはメンゲルベルク在任時代、ベイヌム39歳時の記録。メンゲルベルクの影響が濃厚な演奏。録音月日は、ジャケット表記は4月4日だが、7月7日(サマーコンサートらしい)が正しいようだ。
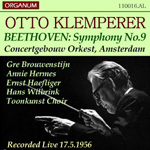
●クレンペラー/コンセルトヘボウ ライブ ベートーヴェン 交響曲第9番
オルガヌム110016AL
ベートーヴェン 交響曲第9番
グレ・ブラウエンステーン(s)、アニー・ヘルムズ(ms)、
エルンスト・ヘフリガー(t)、ハンス・ウィルブリンク(br)
トーンクンスト合唱団
オットー・クレンペラー指揮コンセルトヘボウ管弦楽団
1956年5月17日、コンセルトヘボウ、
アムステルダム ライブ モノラル
※モノラルながら録音は優秀。クレンペラーの「第9」録音はスタジオ、ライブ含め数種残されているが、コンセルトヘボウとの第9は,その後1964年のライブが発見され、当レーベルの110061として発売されている。
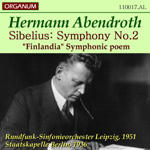
●アーベントロート シベリウス 交響曲第2番、フィンランディア
オルガヌム110017AL
シベリウス 交響曲第2番、交響詩「フィンランディア」
ヘルマン・アーベントロート指揮
ライプツィヒ放送交響楽団
ベルリン国立歌劇場管弦楽団
1951、1938年録音(米ウラニア、英パーロフォン原盤)モノラル
※交響曲第2番はLP初期のマイナーレーベル・米ウラニア原盤。当初は放送録音からのLP化と思われていたが、他レーベルからはLP復刻以外の再発売がないため、ウラニアによるオリジナル・スタジオ録音と推定される。同様の例としてゲルハルト・マンケ独奏、アーベントロート指揮によるブラームスのヴァイオリン協奏曲がある。「フィンランディア」はSP録音からの復刻。
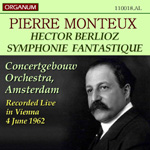
●モントゥー/コンセルトヘボウ ライブ ベルリオーズ 幻想交響曲
オルガヌム110018AL
ベルリオーズ 幻想交響曲
ピエール・モントゥー指揮コンセルトヘボウ管弦楽団
1962年6月4日、ウィーン・ムジークフェライン大ホール ライブ モノラル
※コンセルトヘボウ管によるウィーン芸術週間におけるライブ。モントゥーは1959年英デッカにウィーン・フィルと「幻想」をスタジオ録音したが、モントゥー夫人のドリスはその回想録で、デッカによる録音について、ウィーン・フィルには「強烈な幻覚と、熱っぽい想像力が生み出したこの曲に必要な気質を備えていなかったために、完全な大失敗を」したと語り、一方、ウィーンにおけるコンセルトヘボウとの演奏は、モントゥー自身も「この素晴らしいオランダのオーケストラが彼によくついて、この心をえぐるような悲しみと興奮のの音楽に指揮者の感情をを何倍にも表現してくれたことに大いに満足したしていた」という。ウィーンの聴衆に、曲のあるべき姿を正しく伝えることができたという思いがあったと思われる。
モントゥーによるベルリオーズの録音は、スタジオ、ライブ含め多く残されており、コンセルトヘボウとの録音も1948年と本CDの2種確認されている。
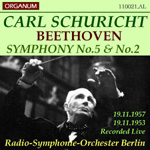
●シューリヒト/ベルリン放送響 ライブ ベートーヴェン 交響曲第5番 第2番
オルガヌム110019AL
ベートーヴェン 交響曲第5番 第2番
カール・シューリヒト指揮ベルリン放送交響楽団
1957年11月19日、1953年11月19日、ティタニア・パラスト、ベルリン
ライブ モノラル
※音質良好。シューリヒトは当録音以外に、5番を1949年英デッカ、1957年仏EMIにそれぞれパリ音楽院管とスタジオ録音していたほか、1953年シュツットガルト放送響、1955年ストラスブール市立管 1956年フランス国立放送管とライブ録音していた。2番は1947年英デッカにスイス・ロマンド管、1952年英デッカにウィーン・フィル、1958年仏EMIにパリ音楽院管とスタジオ録音していたほか、1957年スイス・ロマンド管とライブ録音していた。
●リヒテル 東欧ライブ 35歳時のチャイコフスキー ピアノ協奏曲第1番ほか
オルガヌム110020AL
チャイコフスキー ピアノ協奏曲第1番
バルトーク ピアノ協奏曲第2番
スビャトスラフ・リヒテル(p)
コンスタンティン・イワーノフ指揮ブルノ放送交響楽団
ヤーノシュ・フェレンチク指揮ハンガリー国立交響楽団
1950年5月25日、ブルノ・コミュニティ・ホール
1958年10月3日または6日、エルケル劇場、ブダペスト
ライブ モノラル
※リヒテルがチェコとハンガリーに客演した際のライブ録音。チャイコフスキーは数種残されている録音のうち、現在確認されている中で最も古い。リヒテル35歳の演奏。
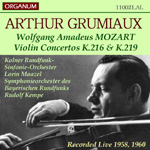
●グリュミオー ライブ モーツァルト ヴァイオリン協奏曲第3番、第5番
オルガヌム110021AL
モーツァルト ヴァイオリン協奏曲第3番、第5番
アルテュール・グリュミオー(vl)
ロリン・マゼール指揮ケルン放送交響楽団
ルドルフ・ケンペ指揮バイエルン放送交響楽団
1958年5月9日、ケルン放送大ホール
1960年9月11日、ヘルクレスザール、ミュンヘン
ライブ モノラル
※グリュミオー得意のモーツァルトだが、2度のスタジオ録音以外に、ライブ録音は本CD-Rを除けばほとんど紹介されていない。音質良好。
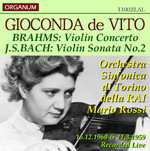
●新発見 デ・ヴィートとマリオ・ロッシのブラームス ヴァイオリン協奏曲
オルガヌム110022AL
バッハ 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第2番
ジョコンダ・デ・ヴィート(vl)
1960年12月16日、トリノ・イタリア放送オーディトリアム
1959年3月11日、ローマ・イタリア放送スタジオ
ライブ モノラル
※2曲とも音質良好。ブラームスは新発見と思われる。デ・ヴィートが翌1961年に若くして演奏活動から退いたため活動末期の記録。録音はソロ・ヴァイオリンをクローズアップし、オーケストラが背後に位置する古い手法だが、それだけにデ・ヴィートの演奏が細部まで聴き取れる。デ・ヴィートは、1923年のデビュー演奏会の際に、チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲でマリオ・ロッシと共演しており、古い間柄。バッハもヒスノイズが若干あるものの録音は良好。会場の遮音が悪く、演奏開始当初は、会場外の車の騒音などが入り込んでいるが(遅刻した聴衆を入れるため扉を開けていたか)、干渉の妨げになるほどではない。表記ではローマ・イタリア放送のスタジオとされているが、幹線道路に面した小ホールかも知れない。
デ・ヴィートはブラームスの協奏曲を、1941年独ポリドールにケンペン、1953年英HMVにシュワルツとスタジオ録音したほか、1951年にフリッチャイ、1952年にフルトヴェングラー、1956年にヨッフムとライブ録音していた。一方、バッハはスタジオ録音を残さず、本ライブが現在確認されている唯一の録音。
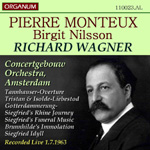
●音質一新 モントゥー/コンセルトヘボウ ライブ ワーグナー・コンサート
オルガヌム110023AL
ワーグナー
歌劇「タンホイザー」序曲
楽劇「トリスタンとイゾルデ」~愛の死
楽劇「神々の黄昏」から
夜明けとジークフリートのラインの旅
ジークフリートの死と葬送行進曲
ブリュンヒルデの自己犠牲
ジークフリート牧歌
ビルギット・ニルソン(s)
ピエール・モントゥー指揮コンセルトヘボウ管弦楽団
1963年7月1日、クアザール、クアハウス、スヘフェニンヘン ライブ モノラル
※毎年6~7月頃開催されるオランダ音楽祭のライブ録音。2曲目と6曲目はビルギット・ニルソンが共演。スヘフェニンヘンはオランダ有数のリゾート地。クアハウスは同地の高級ホテルで、クアザールはホテル付属のコンサートホールである。
今回のプレスから再マスタリングを行い、音質を一新させた。既発盤は低域過多・高音不足で、歪みも感じられたが、イコライジングや位相調整、ノイズ削減などにより、大幅な音質改善を実現。モントゥーらしい明晰なスタイルが再現され、演奏本来の姿がよみがえった。
モントゥーは、まだコロンヌ管弦楽団のヴィオラ奏者だった19世紀末頃、パリに客演した伝説的な大指揮者ハンス・リヒターとフェリックス・モットルの指揮の下、「神々の黄昏」と「トリスタンとイゾルデ」を演奏した。モントゥー夫人ドリスの著書によると、後年モントゥーは当時を回顧して「私は、忽ち熱心なワーグナー信者となった。私はいつの日かまたワーグナーの立派な指揮者たらんと決心し、この巨匠の作品を学ぶことを絶対にやめなかった。実際、私はそれらのほとんど大部分を暗譜している」と語っている。モントゥーが残したディスコグラフィからは想像できない言葉だが、彼自身、先の発言に加えて、「不幸にも私の名はピエール・モントゥーで、生まれながらのパリジャンだし、ケルン生まれのクラウス・シュミットではない。だから一般の人の頭は、私の生涯の大部分をベルリオーズ、フランク、ドビュッシー、ラヴェル、ロシアの曲、そしてストラヴィンスキーなどの音楽を演奏すべき使命を持った開拓者と思い込んでいる。」と嘆いている。
確かに1960年にベルリン・フィルがモントゥーを招聘した際も、プログラム前半こそベートーヴェンやR・シュトラウスだったが、サン=サーンスのヴァイオリン協奏曲をはさんで、後半はやはりストラヴィンスキー「ペトルーシュカ」であった。
幸いながら、長年関係を続けたコンセルトヘボウ管とオランダの聴衆は上記のような固定観念はなかったようで、このライブのようなオール・ワーグナー・プロが実現した。上記の著書によると、このオランダ音楽祭開催の頃は、モントゥーは、音楽通の間では「偉大なる古典主義者」と考えられ、「この演奏会は新聞でも聴衆からも広く賞賛され」「モントゥーにとっての勝利であった」という。モントゥーは、かつて常任だったサンフランシスコ響でも、ソプラノのヘレン・トラウベルを共演させた同様のコンサートを行っており、こちらは、プレミエ60074で聴くことができる。
モントゥーは、上記ライブのほか、「トリスタンとイゾルデ」から「愛の死」を1964年コンサートホールソサエティにハンブルク北ドイツ放送響とスタジオ録音したほか、1943年と1952年サンフランシスコ響とライブ録音、「神々の黄昏」から夜明けとジークフリートのラインの旅を1951年ボストン響および同年サンフランシスコ響とライブ録音、ジークフリートの死と葬送行進曲を1951年ボストン響とライブ録音、ジークフリート牧歌を1960年米RCAにサンフランシスコ響とスタジオ録音したほか、同年ロイヤル・フィルとライブ録音していたが、それ以外の曲目は、本ディスクのライブが現在確認されている唯一の演奏と思われる。
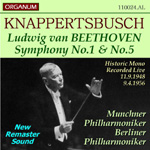
●クナッパーツブッシュ ライブ ベートーヴェン 交響曲第1番、第5番 1番は新発見
オルガヌム110024AL
ベートーヴェン 交響曲第1番、第5番
クナッパーツブッシュ指揮
ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
1948年9月11日、ミュンヘン大学講堂
1956年4月9日、ベルリン音楽大学講堂
ライブ モノラル
※交響曲第1番は当レーベルが2012年に初発売。クナッパーツブッシュは同曲を戦前に3度ほど演奏した記録があるが、戦後は、当演奏を含む9月11日と12日の2回のみしか取り上げなかったと思われる。5番はこのほかに1962年フランクフルト放送響とのライブ録音が残されている。
第1番のオリジナルの音質は良好とは言い難く、ハムノイズやヒスノイズが音楽全体を重く覆っており、演奏も鈍重な印象があったが、今回のプレスから音質改善が図られ、音質に配慮しつつ、これらのノイズが大幅に低減された。その結果、やせ気味で貧相に聞こえた弱音部に豊かなニュアンスが感じられるようになり、多くの既出盤と比べて演奏のイメージが変わった。また、各所のドロップアウトやクリックノイズも解消されている。一方、第5番もヒスノイズが多い音源だったが、こちらも改善されている。
クナッパーツブッシュは、ベートーヴェン交響曲第1番と5番のレコードのためのスタジオ録音を行わず、残されているのは上記を含むライブ録音のみである。
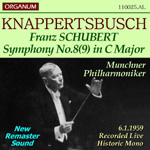
●クナッパーツブッシュ 1959年ライブ シューベルト 交響曲第8(9)番
オルガヌム110025AL
シューベルト 交響曲第8(9)番
ハンス・クナッパーツブッシュ指揮ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団
1959年1月6日、ミュンヘン・ドイツ博物館講堂 ライブ モノラル
※クナッパーツブッシュの同曲は1957年ウィーン・フィルとの録音がよく知られているが、これはその2年後の録音。57年録音は冒頭拍手が終わらないうちに演奏が始まっていたが、こちらは少し騒がしいものの一応は拍手が収まってスタート。録音はラジオ放送のエアチェックらしく、1959年録音としては少し落ちる。1950年代前半くらいのレベルか。それでもテープ録音でヒスノイズも少なく、安定したバランスの良い音質。今回のプレスから、若干音質が改善されたほか、楽章間に入っていたノイズも解消された。
●女流アニー・フィッシャー ライブ シューマン、モーツァルト ピアノ協奏曲
オルガヌム110026AL
シューマン ピアノ協奏曲
モーツァルト ピアノ協奏曲第22番
アニー・フィッシャー(p)
ヨゼフ・カイルベルト指揮ケルン放送交響楽団
オットー・クレンペラー指揮コンセルトヘボウ管弦楽団
1958年4月28日、ケルン放送第1ホール
1956年7月12日、コンセルトヘボウ、 アムステルダム
ライブ モノラル
※音質は、2曲とも当時のライブ録音の平均レベルだが、大きな問題はなく鑑賞に支障はない。特にシューマンは、海外の既出盤が過剰なノイズ除去と音質の加工により、違和感のあるサウンドになっているのに比べると、音質を損なわない範囲の適度なノイズ処理などにより、ナチュラルな仕上がりとなっている。
ハンガリーの名女流アニー・フィッシャーは、1950年代初頭からメロディアやスプラフォンなどにレコーディングを開始、1955年から英EMI(コロンビア)と契約し、国際的名声を高めていったが、上記CDのライブをちょうどその頃の録音である。
アニー・フィッシャーは上記CD以外に、シューマンの協奏曲を1960年英EMI(コロンビア)にクレンペラー/フィルハーモニア管とスタジオ録音したほか、1984年にネルソン/北ドイツ・ハンブルク放送響と、1985年にペリック/NHK響とライブ録音していた。またモーツァルトの協奏曲第22番を1958年英EMIにサヴァリッシュ/フィルハーモニア管とスタジオ録音していた。
当CDのシューマンの協奏曲は、2年後のクレンペラーとのスタジオ録音とは大きく異なるテンポ設定。アニー・フィッシャーは、スタジオ録音には慎重で、おびただしいテイクを重ねて編集したといわれるが、レコードとライブではスタイルが変わる演奏家だったようだ。
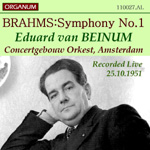
●ベイヌム ライブ ブラームス 交響曲第1番
オルガヌム110027AL
ブラームス 交響曲第1番
エドゥアルド・ファン・ベイヌム指揮コンセルトヘボウ管弦楽団
1951年10月25日、コンセルトヘボウ、
アムステルダム ライブ モノラル
※録音は、特に優秀というわけではないが、安定した音質で鑑賞に支障はない。定期演奏におけるライブで、前半にベートーヴェン「コリオラン序曲」、ヘンケマンスのヴァイオリン協奏曲(独奏テオ・オロフ)、後半にブラームスが演奏された。ベイヌムは同曲を英デッカ(2回)と蘭フィリップスにスタジオ録音している。本ライブは第2回目デッカ録音の直後の演奏。時期が近いスタジオとライブで相違があるのか興味深い。
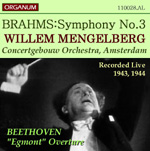
●メンゲルベルク 1944年ライブ ブラームス 交響曲第3番
オルガヌム110028AL
ブラームス 交響曲第3番
ベートーヴェン エグモント序曲
ウィレム・メンゲルベルク指揮コンセルトヘボウ管弦楽団
1944年2月27日、1943年4月29日、コンセルトヘボウ、
アムステルダム ライブ モノラル
※メンゲルベルクはブラームス交響曲第3番を英コロムビアに、エグモント序曲を同じく英コロムビア(2回)、米ビクターにそれぞれスタジオ録音している。ブラームスは現在確認されているメンゲルベルク最後の録音と思われる。戦中の彼のライブ録音は音質劣悪なものが多いが、これはディスク録音では避けられないスクラッチノイズはあるものの比較的良好。

●女流ヴァイオリニスト ブスターボのシベリウス、パガニーニ ヴァイオリン協奏曲ほか
オルガヌム110029AL
シベリウス ヴァイオリン協奏曲
パガニーニ ヴァイオリン協奏曲第1番(ウィルヘルミ編曲1楽章版)
サラサーテ ハバネラ 作品21、サパティアード 作品23
ファリャ(コハンスキ編曲)バレエ「恋は魔術師」 から パントマイム
スーク ブルレスケ 作品17の4
グィラ・ブスターボ(vl)
フリッツ・ツァウン指揮ベルリン国立管弦楽団
ウィルヘルム・シュローター(p)
1940~1941年頃録音(独エレクトローラ原盤)モノラル
※往年の女流ヴァイオリニスト、グィラ・ブスターボ(1916~2002年)の独エレクトローラへのSP録音をまとめた1枚。アメリカ出身ながらナチス政権下のドイツで演奏を行ったため、戦後は活動が制限された。録音も少なく、このほかの正規のスタジオ録音は戦前期に英EMIへのSP録音が若干ある程度。その才能を評価してヴォルフ・フェラーリが自身のヴァイオリン協奏曲(1943年作曲)を献呈した。

●フルトヴェングラー 戦中ライブ フランク交響曲 1945年録音
オルガヌム110030AL
フランク 交響曲ニ短調
ラヴェル ダフニスとクロエ第2組曲
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
1945年1月29日、ムジークフェライン大ホール、ウィーン
1944年3月22日または23日、ベルリン国立歌劇場
ライブ モノラル
※1945年録音のフランクは、第3楽章を中心にテープ劣化が甚だしく、音揺れが大きいことが知られている。本CD-Rは詳細不明だが、米VOX初期LPとオーストリア放送の保存テープから、状態の良い部分を編集したものと推定される。盤起こし特有のスクラッチノイズは皆無。良好な音質。ただし、第2楽章のわずかな音飛びは既出盤と同様。フルトヴェングラーがスイス亡命直前、戦中最後の演奏。ラヴェルは旧ソ連からの返還テープが音源。
●オイストラフ/アーベントロートの共演ライブ ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲
オルガヌム110031AL
ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ロマンス第1番
ダヴィード・オイストラフ(v)
ヘルマン・アーベントロート指揮ベルリン放送交響楽団
1950年3月13日、ベルリン国立歌劇場 ライブ モノラル
※オイストラフがロシア国外で演奏を始めた頃の演奏。オイストラフには同曲の数種の録音があるが、アーベントロートは現在確認されている唯一のレパートリー。
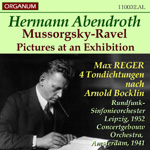
●アーベントロート ムソルグスキー「展覧会の絵」、レーガー「ベックリンによる4つの音詩」
オルガヌム110032AL
ムソルグスキー(ラヴェル編曲) 組曲「展覧会の絵」
レーガー ベックリンによる4つの音詩
ヘルマン・アーベントロート指揮
ライプツィヒ放送交響楽団
コンセルトヘボウ管弦楽団
1952年録音(米ウラニア原盤)
1941年2月20日、コンセルトヘボウ、
アムステルダム ライブ モノラル
※

●ムラヴィンスキー 1961年ベルゲン音楽祭ライブ ベートーヴェン「英雄」
モーツァルト 「フィガロの結婚」序曲
ベートーヴェン 交響曲第3番「英雄」
エフゲニー・ムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィルハーモニー交響楽団
1961年5月26日、6月2日、ベルゲン・コンサート・パレス ライブ モノラル
※ムラヴィンスキーのノルウェー・ベルゲン音楽祭ライブが復活。1990年代にイタリア・マイナーレーベルで発売されたのみで長らく入手不能だった。特に「英雄」は音質も向上。110034と併せて音楽祭公演全プログラムの約半分が聞ける。
●ムラヴィンスキー 1961年ベルゲン音楽祭ライブ チャイコフスキー 交響曲第5番
オルガヌム110034AL
チャイコフスキー 交響曲第5番
プロコフィエフ 「ロミオとジュリエット」組曲第2番
エフゲニー・ムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィルハーモニー交響楽団
1961年5月29日、ベルゲン・コンサート・パレス ライブ モノラル
※ムラヴィンスキーのノルウェー・ベルゲン音楽祭ライブが復活。1990年代にイタリア・マイナーレーベルで発売されたのみで長らく入手不能だった。音質良好。
●オッテルロー 1958年放送ライブ ブルックナー 交響曲第7番
オルガヌム110035AL
ブルックナー 交響曲第7番
ウィレム・ファン・オッテルロー指揮オランダ放送フィルハーモニー管弦楽団
1958年4月2日、ヒルヴェルスム、モノラル
※聴衆を入れない放送スタジオにおける録音と思われる。スタジオ録音だけに音質は良好。オッテルローは同曲を1954年に蘭フィリップスにスタジオ録音していた。
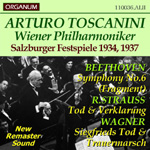
●音質大改善 トスカニーニ/ウィーン・フィル コンサートライブ 1934年・1937年ザルツブルク音楽祭
オルガヌム110036ALII
ベートーヴェン 交響曲第6番「田園」から第4、5楽章抜粋
R・シュトラウス 交響詩「死と変容」
ワーグナー 楽劇「神々の黄昏」から ジークフリートの死と葬送行進曲
アルトゥーロ・トスカニーニ指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
1937年8月24日、1934年8月26日(ワーグナー)、ザルツブルク祝祭劇場
ライブ モノラル
※戦前のザルツブルク音楽祭におけるトスカニーニとウィーン・フィルの貴重な記録。このコンビによるオペラ上演はCD化されているがコンサートは珍しい。田園は第4楽章の途中からフェイドインし最後まで録音。ほかの2曲は欠落なし。ベートーヴェンとR・シュトラウスはフォルテで若干の音割れ・ひずみあり、1934年録音のワーグナーは比較的安定している。
今回のプレスから、「田園」と「死と変容」については、音源は同一ながら音質改善が図られ、高域過多・低音不足のバランスの悪さが解消された。これにより単なる記録ではなく、ようやく音楽を鑑賞できるレベルとなった。古い録音ながら、トスカニーニやウィーン・フィルならではの特徴が聴き取れる。
オリジナルの音源は、おそらく「田園」と「死と変容」については、ザルツブルクからの短波による中継放送をアメリカの放送局(NBC?)が受信し、アセテート盤に記録したもの。「葬送行進曲」については、前2者よりも3年古いにもかかわらず、音質がわずかに良好な点から、会場でアセテート盤に収録されたものと思われる。いずれにしても、非常に初期のライブ録音の例である。
トスカニーニは、1934年からザルツブルク音楽祭に登場。1937年まで4年連続で参加した。1934年8月26日のコンサートは、ロッテ・レーマンと共演したオール・ワーグナー・プログラム。ファウスト序曲、ローエングリン第1幕と第3幕への前奏曲、タンホイザーから「歌の殿堂」、ジークフリートのラインの旅、ウェーゼンドンク歌曲集から3曲、ジークフリートの死と葬送行進曲、マイスタージンガー(第1幕への?)前奏曲というもの。1937年8月24日のコンサートは、ロッシーニ「アルジェのイタリア女」序曲、「田園」「死と変容」というプログラム。「死と変容」はトスカニーニが特に好んだ曲の一つであった。
1934年のザルツブルク音楽祭は、トスカニーニの他に、クレメンス・クラウス、ワルター、メンゲルベルク、ヴィットリオ・グイ、ワインガルトナーらが参加。1937年は、クナッパーツブッシュ、ワルター、ロジンスキ、フルトヴェングラーらが参加(この時、トスカニーニとフルトヴェングラーの間で一悶着が起こったことは有名)。1937年上演の歌劇やメンゲルベルクのライブなど、当ディスク以外にもいくつかの録音の存在が知られているが、さらに他の録音が発見されれば大きな注目を集めるだろう。
トスカニーニは、「田園」を1937年英HMVにBBC響、1952年米RCAにNBC響とスタジオ録音したほか、1938年、1939年、1941年にNBC響、1949年にミラノ・スカラ座管とライブ録音。また「死と変容」を1942年米RCAにフィラデルフィア管、1952年米RCAにNBC響とスタジオ録音したほか、1938年にハーグ・フィル、同じく1938年にNBC響、1946年にミラノ・スカラ座管、同じく1946年にNBC響とライブ録音。「ジークフリートの死と葬送行進曲」を1952年米RCAにNBC響とスタジオ録音したほか、1934年BBC響、1941年2月と5月NBC響、1945年ニューヨーク・フィル、1953年NBC響とライブ録音していた。
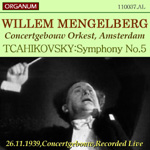
●メンゲルベルク 1939年ライブ チャイコフスキー 交響曲第5番
オルガヌム110037AL
チャイコフスキー 交響曲第5番
ウィレム・メンゲルベルク指揮コンセルトヘボウ管弦楽団
1939年11月26日、コンセルトヘボウ、
アムステルダム ライブ モノラル
※メンゲルベルクは同曲を1929年にコンセルトヘボウと、1940年にベルリン・フィルとスタジオ録音していた。本CD-Rは2回目の録音と近い時期にコンセルトヘボウを振ったライブ。第2楽章の一部が欠落していたため、1929年録音で補っているとのことだが、テンポやフレージングなど全く違和感がなく判別できない。アセテート盤録音のため若干ノイズあり。

●再発売・優秀新音源 推定:ピエール・モントゥー来日公演ライブ
1963年大阪国際フェスティバル ベートーヴェン ブラームス
オルガヌム110038ALIII
ベートーヴェン 交響曲第8番
ブラームス 交響曲第2番
ドビュッシー 「夜想曲」から「祭」
ピエール・モントゥー指揮ロンドン交響楽団
1963年4月15日、大阪フェスティバル・ホール(推定)
ライブ モノラル
※ピエール・モントゥー唯一の来日公演となった1963年大阪国際フェスティバルにおけるライブと推定される録音。英国人コレクター提供の音質良好な新音源による再発売。
当音源は2007年頃、当時日本国内で大量に流通していたライブ盤CD-Rレーベルの一つLanne
Historical
CollectionからLHC-7005として発売され一般に知られるようになった。LHC-7005は1963年4月22日録音との記載のみで録音会場は不明であったが、曲目のベートーヴェンとブラームスが4月15日のモントゥー大阪公演と一致するため、当盤の購入者などからモントゥー/ロンドン響(LSO)日本公演の録音に間違いないと「断定」され、今日まで様々なCD-Rレーベルから発売が繰り返されてきた。当レーベルでも、同一曲の他録音との比較からモントゥーの演奏には間違いないため、同様の表記で旧盤のディスクをカタログに掲載してきた。ちなみに4月22日はアンタル・ドラティが同響と名古屋市民会館で演奏している。
ただ、当録音が日本公演ライブという確実な根拠はなく、最近も同一録音が当初の表記4月22日ロンドン・ロイヤル・フェスティバル・ホールの公演であるとしてインターネット上にアップされている。このため真相を確認すべく調査したところ、懇意にしている英国人コレクターからいくつか情報が得られた。
LSO初の1963年日本公演は、NHKによってその多くがライブ録音されたが、LSOにとっても重要イベントと位置づけられ、英BBCが来日公演のドキュメンタリー・テレビ番組を制作、BBCにはNHK収録のライブ録音が提供され、公演後英国内で放送された。これら一連の放送のうち、モントゥーの公演が当時リスナーによってエアチェック録音され、欧米のエアチェック・コレクター間で「流通」したという。
ちなみにモントゥーとLSOは、ベートーヴェンについては1962年12月7日、ブラームスについては同年11月22日、それぞれロンドン・ロイヤル・フェスティバル・ホールで演奏しており。これらもBBCによって録音・放送された可能性があるが、ドビュッシー「祭」については演奏会記録に記載がなく、通常オーケストラの定期演奏会でアンコールを演奏することは考えられず、ドビュッシーは外国公演時などの演奏の可能性が高い。残されている音源は、ベートーヴェン、ブラームスとドビュッシーをまとめてエアチェックしており、すなわち一挙に放送されたことを意味する。またさらに演奏終了後、間合いを置かずすぐに拍手が始まっており、当時の英国の聴衆の慣習と異なり、日本の聴衆のかつての「流儀」だった点なども、日本公演説を補強する要素である。
録音日の相違については、オリジナルのエアチェック音源に既に4月22日公演と記載されていたらしく、BBCの放送時に誤ってアナウンスされたか、リスナーの記録ミスの可能性が高い。また、会場の大阪フェスティバル・ホールとロンドン・ロイヤル・フェスティバル・ホールを混同した可能性も指摘されている。
以上から、当演奏は日本公演ライブである可能性が極めて高いが、上記の理由のみでは決定的証拠にはなり得ず、当ディスクでは便宜上「推定」(presumed)と表記することとした。
このエアチェック録音が後のCD-Rの音源となったらしいが、1970年代以降、前記のように音源が愛好家の間でやりとりされてコピーが繰り返され、まだアナログ・コピーの時代だったため、コピーの度に徐々に音質が劣化、先のLHC-7005では、ナロー・レンジでドロップ・アウトやヒス・ノイズが多いばかりか、元がモノラルであるにもかかわらず、片チャンネルが位相反転して疑似ステレオのように聴こえるという惨憺たる音質となっていた。問い合わせ先の英国人コレクターによれば、音質に差のある7~8種ほどのコピーが存在しており、LHC-7005はその最終世代のコピーではないかという。
当レーベルの旧盤では、位相反転する前の世代の音源を使用していたが、必ずしも優秀録音とは言えなかった。今回初めて英国人コレクターから、オリジナルではないものの2~3世代目のコピーと思われる格段に音質の優れた音源を入手することが出来たため、改めて新装発売することとした。
新音源は、旧盤と同様にわずかにフラッターが感じられるが、高域の周波数レンジが8khzからFM放送規格上限の15khz程度まで拡大。レンジの拡大に伴い明快な音質となり、解像度も向上、併せてドロップアウトも解消し、ようやく1960年代中期の他のライブ録音と同等以上の音質となった。ヒスノイズも極小で不満なく鑑賞出来ると思われる。ディスク化に当たっては、最小限のノイズ処理、周波数バランスの調整のみ行った。
1963年、大阪国際フェスティバルに併せて初来日したロンドン響には、モントゥー、ショルティ、ドラティが同行し、モントゥーは4月13日(公演初日)、15日、19日の3公演を指揮した。ディスクには収録されていないが、15日の演奏会では冒頭にコリオラン序曲が演奏された。また前記のように「祭」はプログラムに予定がなく、アンコールだったと思われる。
オーケストラはその後、名古屋や東京公演を行ったが、モントゥーは、4月25日に予定されていたアムステルダム・コンセルトヘボウ定期演奏会客演のため離日し大阪のみの公演となった。モントゥーは翌1964年11月のロンドン響来日公演にも同行が予定されていたが、同年7月に死去したため果たされることはなかった。
モントゥーは、当時の日本において「春の祭典」や「ダフニスとクロエ」を初演したベテラン指揮者としてそれなりに知られてはいたものの、当時まだ現役だった他の巨匠指揮者に比べると地味な存在だった。しかし、実際の演奏を聴いた日本の聴衆や専門家は大きな感銘を受けたことで、従来の認識を一変、今日の高い評価が定まるきっかけとなった。
モントゥーは、上記曲目のうち、ベートーヴェンの交響曲第8番を、1950年米RCAにサンフランシスコ響と、1959年英デッカにウィーン・フィルとスタジオ録音したほか、1961年シカゴ響と、1962年コンセルトヘボウ管(オルガヌム110001ALとして発売済み)とライブ録音し、さらに2種類の未発表ライブ録音が確認されている。また、ブラームスの交響曲第2番を、1945年米RCAにサンフランシスコ響と、1959年英デッカにウィーン・フィルと、1962年蘭フィリップスにロンドン響とスタジオ録音したほか、1953年NBC響とライブ録音していた。ドビュッシーの「祭」については、1944年Vディスクにニューヨーク・フィルと、1955年米RCAにボストン響と、1961年英デッカにロンドン響とスタジオ録音したほか、1943年にニューヨーク・フィルとライブ録音していた。
●リヒテル ライブ 自身最速のチャイコフスキー ピアノ協奏曲第1番ほか
オルガヌム110039AL
チャイコフスキー ピアノ協奏曲第1番
リスト ピアノ協奏曲第2番、ハンガリー幻想曲
スビャトスラフ・リヒテル(p)
ボフダン・ヴォディチコ指揮クラクフ・フィルハーモニー管弦楽団
ヤーノシュ・フェレンチク指揮ハンガリー国立交響楽団
1954年11月12日、クラクフ・フィルハーモニック・ホール
1961年9月19日、27日、エルケル劇場、ブダペスト
ライブ モノラル
※リヒテルがポーランドとハンガリーに客演した際のライブ。1954年のチャイコフスキーは、当時の東欧の録音技術を考慮すれば良好な部類。西欧の基準では1940年代後半のレベルだが、テープ録音で破綻もなく、リヒテル壮年期の「凄さ」を実感できる音質。1961年のリストは、7年後の録音でもあり良好な音質。
リヒテルは1950年、チェコへ初めての国外演奏旅行を行ったが、亡命を警戒したソ連当局から西欧への演奏旅行は許可されず、1960年のフィンランド初訪問までの間、国外公演は旧共産圏各国のみであった。1954年のチャイコフスキーはポーランド公演の記録。2日前の11月10日にはワルシャワでリサイタルを行い、その際のショパンの録音が海外レーベルでCD化されている。1961年のリストは、9月にルーマニアとハンガリーをまわった際の記録。この年は7~8月に英国、10月にフランス(それぞれ初公演)と海外公演が続き、リヒテルが巨匠としての国際的評価を決定づけた時期の演奏。なお、ハンガリー幻想曲は、ブダペスト・フィルによる演奏とする資料もある。
リヒテルは上記CDのほかに、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番を、1954年アンチェル/チェコ・フィルとスプラフォンに、1958年ムラヴィンスキー/レニングラード・フィルとメロディアに、1962年カラヤン/ウィーン響と独グラモフォンにそれぞれスタジオ録音していたほか、1950年イワーノフ/ブルノ放送響(当レーベル・オルガヌム110020ALでCD化)、1957年ラクリン/ソビエト国立響、1968年コンドラシン/ソビエト国立響とライブ録音していた。また、リストのピアノ協奏曲第2番を、1961年コンドラシン/ロンドン響と蘭フィリップス(本来の制作主体は米マーキュリーか)にスタジオ録音していたほか、この録音の直前に同じ共演者とライブ録音していた。ハンガリー幻想曲は、ピアノ協奏曲第2番と同じ演奏会のライブが残されている。当CDのチャイコフスキーの演奏は、数種あるリヒテルの録音の中でおそらく最速の演奏と思われる。
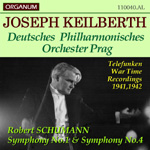
●カイルベルト/プラハ・ドイツ・フィルの戦中録音 シューマン 交響曲第1番、第4番
オルガヌム110040AL
シューマン 交響曲第1番、交響曲第4番
ヨゼフ・カイルベルト指揮プラハ・ドイツ・フィルハーモニー管弦楽団
1941、1942年、ルドルフィヌム、プラハ(独テレフンケン原盤) モノラル
※78回転SPから復刻。カイルベルトの戦前・戦中の録音は、LP初期に米キャピトルからレーガー作品など一部が発売されていたが、シューマンは初復刻か。戦後、同曲をスタジオ再録音していない。プラハ・ドイツ・フィルはチェコ・プラハに本拠を置いたドイツ人主体の団体。戦後、ドイツに移りバンベルク交響楽団に改組されたが、カイルベルトはその後も密接な関係を続けた。旧組織時代の録音は珍しい。
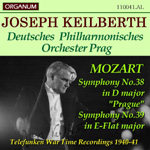
●カイルベルト/プラハ・ドイツ・フィルの戦中録音 モーツァルト 交響曲第38番、39番
オルガヌム110041AL
モーツァルト 交響曲第38番、第39番
ヨゼフ・カイルベルト指揮プラハ・ドイツ・フィルハーモニー管弦楽団
1941年6月17日、1940年1月1日、ルドルフィヌム、プラハ
(独テレフンケン原盤)モノラル
※独テレフンケン78回転SPから復刻。録音・復刻状態良好。第二次世界大戦中、カイルベルト32~33歳時の録音。2曲とも初復刻と思われる。カイルベルトは2曲とも1960年バンベルク響とテレフンケンに再録音していたほか、38番を1963年にバンベルク響とライブ録音、39番を1959年にバンベルク響と、1966年にバイエルン放送響とライブ録音していた。プラハ・ドイツ・フィルはチェコ・プラハに本拠を置いたドイツ人主体の団体。戦後、ドイツに移りバンベルク交響楽団に改組されたため、同じ団体で2回スタジオ録音していたことになる。
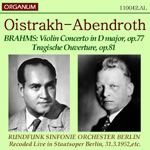
●オイストラフ/アーベントロートの共演ライブ ブラームス ヴァイオリン協奏曲
オルガヌム110042AL
ブラームス ヴァイオリン協奏曲 悲劇的序曲
ダヴィード・オイストラフ(v)
ヘルマン・アーベントロート指揮ベルリン放送交響楽団、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管
1952年3月13日、ベルリン国立歌劇場
1945年3月26日、ライプツィヒ・コンコルディアザール
(ライブおよび放送録音)モノラル
※モノラルながら音質良好。協奏曲はオイストラフ得意のレパートリーだが、最初のスタジオ録音(露メロディア、コンドラシン指揮)とほぼ同時期のライブ。アーベントロートはゲルハルト・マンケとの録音も残っている(1949年米ウラニア)。悲劇的序曲は、第2次世界大戦終結直前、旧ゲヴァントハウスが空襲で破壊され、被害を免れた映画館などで演奏を行っていた頃、おそらく聴衆を入れずに行った放送のための演奏録音。

●シューベルト 交響曲第7(8)番「未完成」、ベートーヴェン 交響曲第7番
オルガヌム110043AL
シューベルト 交響曲第7(8)番「未完成」
ベートーヴェン 交響曲第7番
ハンス・クナッパーツブッシュ指揮
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団
1949年3月7日、ムジークフェライン大ホール、ウィーン
1948年12月25日、ミュンヘン大学講堂
(放送録音及びライブ録音)モノラル
※2曲とも古い録音だがバランスは悪くない。シューベルトはムジークフェライン大ホールで聴衆を入れずに行われた放送録音。ベートーヴェンは近年発見されたものだが、クナッパーツブッシュの指揮ではないとの説もある疑惑の演奏。
クナッパーツブッシュは「未完成」をこのほかに1950年にベルリン・フィル、1958年にバイエルン国立管とライブ録音。ベートーヴェンは、このほかに1929年独エレクトローラにベルリン国立歌劇場管とスタジオ録音、1954年ウィーン・フィルとライブ録音していた。

●クララ・ハスキルの初期貴重録音 ポリドール&コンサートホール・レコーディング
オルガヌム110044AL
ブラームス ピアノ五重奏曲
ペシェッティ ソナタ ハ短調
ソレール ソナタ ニ長調
ハイドン アンダンテと変奏 ヘ短調
シューマン アベッグ変奏曲
クララ・ハスキル(pf)
ウィンタートゥール四重奏団(ペーター・リバール、クレメンス・ダヒンデンほか)
1949(ブラームス)、1934、1935、1938年録音(仏コンサートホール、独ポリドール原盤)モノラル
※ハスキルの初期録音集。研究家マイケル・グレイの調査によると、従来、初録音とされていた1934年のペシェッティ、ハイドン、ソレールのうち、実際にはハイドン以外は未発売となり、翌1935年再録音のテイクが発売されたという。また、ポリドールからは上記以外に、スカルラッティのソナタとグラウン(Johann
Gottlieb
Graun)のジーグを組み合わせた1枚が発売された。ブラームスの五重奏曲は戦後、コンサートホールソサエティへの録音。四重奏団の本拠地ウィンタートゥールではなく、なぜかチューリヒで録音されている。リバールやダヒンデンなど、同時期のウェストミンスターへの録音と共演者が重複しており、両レーベルが何らかの協力関係にあったことがうかがわせる。ノイズもなく良好な復刻。
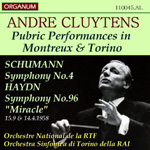
●クリュイタンスのライブ シューマン交響曲第4番、ハイドン交響曲第96番
オルガヌム110045AL
シューマン 交響曲第4番
ハイドン 交響曲第96番「奇跡」
アンドレ・クリュイタンス指揮
フランス国立放送管弦楽団、トリノ・イタリア放送交響楽団
1958年9月15日、パビリオン大ホール、モントルー
1958年4月14日、トリノ・イタリア放送オーディトリアム
ライブ モノラル
※モノラルながら音質良好。シューマンはモントルー音楽祭におけるライブ。クリュイタンスは、シューマンを1950年フランス国立放送管、ハイドンを1955年パリ音楽院管と、それぞれ仏コロンビアにスタジオ録音、またハイドンは1958年3月(本録音の1か月前)ベルリン・フィルとライブ録音していた。2曲ともクリュイタンス得意の曲目。日本では、クリュイタンスはラヴェルなどフランス音楽の大家というイメージがあるが、実演では、ワーグナーも含めてドイツ系作品も重要なレパートリーだった。

●クリュイタンス「プラハの春」音楽祭ライブ ベルリオーズ「幻想」
オルガヌム110046AL
ベルリオーズ 幻想交響曲
アンドレ・クリュイタンス指揮チェコ・フィルハーモニー管弦楽団
1955年5月30日、スメタナ・ホール、プラハ
ライブ モノラル
※モノラルながら音質良好。1955年「プラハの春」音楽祭におけるライブ。当日はプログラム前半に、ラヴェルのスペイン狂詩曲、ジャンヌ・マリー・ダレのソロでシューマンのピアノ協奏曲が演奏された。クリュイタンスは、「幻想」を1955年10月(本録音から5か月後)フランス国立放送管と仏コロンビアに、1958年フィルハーモニア管と英コロンビアにスタジオ録音。1955年11月ケルン放送響、1964年パリ音楽院管とライブ録音(有名な来日公演)していた。
クリュイタンスは1955年5月の「プラハの春」音楽祭出演後、7月にはバイロイト音楽祭に登場。翌1956年にはウィーン・フィルと北米公演を行うなど、国際的名声を高める充実期にあった。
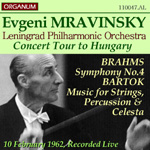
●ムラヴィンスキー 1962年ブダペスト・ライブ ブラームス交響曲第4番、バルトーク「弦楽器、打楽器、チェレスタ」
オルガヌム110047AL
ブラームス 交響曲第4番
バルトーク 弦楽器、打楽器、チェレスタのための音楽
ベルリオーズ 劇的物語「ファウストの劫罰」から「妖精の踊り」
グラズノフ 舞踊音楽「ライモンダ」作品57から第3幕への前奏曲
グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
エフゲニー・ムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団
1962年2月10日、フランツ・リスト音楽院、ブダペスト ライブ
ムラヴィンスキーは、上記録音のほかにブラームスを1940~41年(1~3楽章のみ)、1954年、1961年、1973年に、またバルトークを1965年、1967年、1971年にそれぞれライブ録音していた。
ムラヴィンスキー/レニングラード・フィルは、1962年1月から2月にかけて、ハンガリー各地で5回のコンサートを行った。本録音はその最終公演で、実際にはバルトーク、ブラームスの順で演奏された。小品の3曲はアンコール。当時のフルシチョフ政権による国際的な緊張緩和策(「雪解け」)の影響もあり、ムラヴィンスキーと同フィルは、1960年にイギリス、フランスなど西欧各国、1961年に北欧、1962年10~11月に北米と、活発な海外公演を行っていた。オルガヌム10033AL、10034ALにあるベートーヴェン「エロイカ」やチャイコフスキー交響曲第5番のライブ録音(ベルゲン音楽祭)も、これらのツアーの遺産である。
バルトーク作品は、彼らが1961年にソ連初演を行ったが、1カ月間の徹底したリハーサルを行い、以降、得意のレパートリーとなったという。
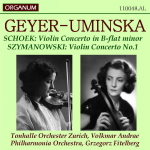
●ゲイエルとウミンスカ 女流バイオリニストの稀少な協奏曲録音 シェック&シマノフスキ
オルガヌム110048AL
オットマール・シェック ヴァイオリン協奏曲“幻想曲風”
シュテフィ・ゲイエル(vl)
フォルクマール・アンドレーエ指揮チューリヒ・トーンハレ管弦楽団
1947年2月6日、トーンハレ、チューリヒ ライブ モノラル
カロル・シマノフスキ ヴァイオリン協奏曲第1番
エウゲニア・ウミンスカ(vl)
グジェゴシュ・フィテルベルク指揮フィルハーモニア管弦楽団
1945年12月27日、アビーロード第1スタジオ、ロンドン(英パーロフォン原盤)モノラル
※シュテフィ・ゲイエル(またはガイヤー)(1888~1956年)はハンガリー出身でフバイに師事。美貌で知られ、彼女に好意を寄せていたバルトークは協奏曲第1番を贈ったが、同様にスイスの作曲家シェック(1886~1957年)も協奏曲を献呈(二人ともフラれた!)。作品(1910年作曲)は、後期ロマン派風の親しみやすいもの。指揮のアンドレーエはスイスのベテラン。孫のマルクも指揮者として知られる。この録音はゲイエル晩年のライブだが、技術の衰えもなく、録音状態も年代を考慮すれば良好。
エウゲニア・ウミンスカ(1910~1980年)はポーランド出身。パリでエネスコに師事。指揮のフィテルベルクとともにシマノフスキ作品の理解者として紹介に尽力した。この録音は英パーロフォンへのスタジオ録音。別資料では1948年録音というデータもあるが、いずれにしても同曲初のスタジオ録音と思われる。
ウミンスカとフィテルベルクは同曲を、1951年ポーランド・ムザにポーランド放送管弦楽団と再録音していた。
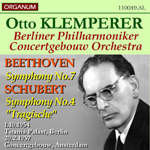
●クレンペラー/ベルリン・フィル、コンセルトヘボウのライブ ベートーヴェンほか
オルガヌム110049AL
ベートーヴェン:交響曲第7番
シューベルト:交響曲第4番「悲劇的」
オットー・クレンペラー指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、コンセルトヘボウ管弦楽団
1954年10月1日、ティアニア・パラスト、ベルリン
1957年2月20日、コンセルトヘボウ、
アムステルダム
ライブ
1954年のクレンペラーとベルリン・フィルとの共演は、1948年9月以来だったが、この年は彼にとって節目となる年となった。1947年に亡命先のアメリカからヨーロッパへ帰還後は、ハンガリー国立歌劇場音楽監督の地位や米ヴォックス・レーベルとの契約が長続きせず、1951年にモントリオール空港でタラップから転落して重傷、しかも亡命による無国籍状態が続くなど不安定な状況だったが、1954年にドイツの旅券を得て国籍問題に解決の目処が立ち(後にスイス国籍を取得)、ベルリン・フィル客演4日後の10月5日から英EMIとの長期にわたるレコーディングを開始するなど、活動を本格化させていた。なお、この演奏会ではベートーヴェンのほか、ブラームスのハイドン変奏曲、ストラヴィンスキーのペトルーシュカ組曲が演奏された。
コンセルトヘボウとのライブはベイヌム常任時代の記録。同オケとは相性が良かったようで1950年代に頻繁に客演、ベートーヴェンの交響曲の大半を演奏したほか、数多くのレパートリーを手がけていた。
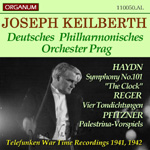
●カイルベルト/プラハ・ドイツ・フィルの戦中録音 ハイドン、レーガー、プフィッツナー
オルガヌム110050AL
ハイドン 交響曲第101番「時計」
レーガー ベックリンによる4つの音詩
プフィッツナー 歌劇「パレストリーナ」から3つの前奏曲
ヨゼフ・カイルベルト指揮プラハ・ドイツ・フィルハーモニー管弦楽団
1941年8月16日、1942年12月20、21日、ルドルフィヌム、プラハ
(独テレフンケン原盤)モノラル
※独テレフンケン78回転SPから復刻。録音・復刻状態良好。カイルベルトの第二次世界大戦中の録音。プラハ・ドイツ・フィルはチェコ・プラハに本拠を置いたドイツ人主体の団体。戦後、ドイツに移りバンベルク交響楽団に改組された。レーガーの作品はアーベントロートなども取り上げており、当時人気があったようだ。ワーグナーとブラームスの折衷?のような後期ロマン派的作風。
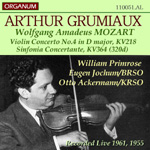
●グリュミオー ライブ モーツァルト ヴァイオリン協奏曲第4番、協奏交響曲
オルガヌム110051AL
モーツァルト ヴァイオリン協奏曲第4番
モーツァルト ヴァイオリンとヴィオラの協奏交響曲
アルチュール・グリュミオー(vl)、ウィリアム・プリムローズ(va)
オイゲン・ヨッフム指揮バイエルン放送交響楽団
オットー・アッカーマン指揮ケルン放送交響楽団
1961年6月23日、ヴュルツブルク宮殿王の間
1955年1月22日、ケルン放送大ホール
ライブ モノラル
※2曲とも録音良好。特に協奏曲は会場の音響の良さによるためか、非常に美しい録音。協奏曲は、ヴュルツブルクで毎年初夏に開催されるモーツァルト音楽祭におけるライブ。グリュミオーは、協奏曲第4番を1953年と1962年にスタジオ録音。協奏交響曲を1962年にスタジオ録音していた。
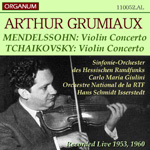
●グリュミオー ライブ メンデルスゾーン、チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲
オルガヌム110052AL
メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲
チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲
アルチュール・グリュミオー(vl)
カルロ・マリア・ジュリーニ指揮ヘッセン(フランクフルト)放送交響楽団
ハンス・シュミット・イッセルシュテット指揮フランス国立放送管弦楽団
1953年2月、ヘッセン放送大ホール、フランクフルト
1960年2月18日、シャンゼリゼ劇場、パリ
ライブ モノラル/ステレオ
※2曲とも録音良好。チャイコフスキーはステレオ録音。グリュミオーはメンデルスゾーンを1953年、1960年、1972年と3回スタジオ録音したほか、1946年に英コロンビアにスタジオ録音したが、未発売に終わったといわれる。またチャイコフスキーを1956年、1960年、1975年にスタジオ録音していた。
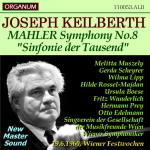
●新優秀音源 カイルベルトのマーラー交響曲第8番 1960年ウィーン芸術週間ライブ
オルガヌム110053ALII
マーラー 交響曲第8番
メリッタ・ムセリ、ゲルダ・シャイラー、ウィルマ・リップ(ソプラノ)、ヒルデ・レッセル=マイダン、ウルズラ・ベーゼ(コントラルト)、フリッツ・ヴンダーリヒ(テノール)、ヘルマン・プライ(バリトン)、オットー・エーデルマン(バス)、フランツ・シュッツ(オルガン)
ウィーン楽友協会合唱団
ヨゼフ・カイルベルト指揮ウィーン交響楽団
1960年6月19日、ウィーン・ムジークフェラインザール
ライブ モノラル
※1960年ウィーン芸術週間におけるマーラー生誕100年を記念するライブ。今回、新たな音源を英国人コレクターから入手。旧盤に比べて大幅な音質改善に成功した。旧盤はオーストリア人コレクター所有によるオーストリア国営放送(ORF)と思われるAM放送のエアチェック音源だったが。新音源は同じくエアチェックながら、放送局間の交換音源として英国で放送されたBBCのモノラルFM放送を良好な受信環境の元、高品質なレコーダーで録音したもの。格段に音質が良く、ディスク化に当たっては、若干の周波数レンジ拡大、ヒスノイズの低減、ダイナミックレンジの調整等を行ったが、低域が豊かで高域もクリアに伸び、しかもノイズレスで、この作品らしいスケールの大きさを実感できる。モノラルながら鑑賞に当たっては全く不満のない状態。
ちなみに、ORFは同年のウィーン芸術週間の音源を保存していないらしく、この年の芸術週間で行われたクレンペラー/フィルハーモニア管によるベートーヴェン交響曲全曲演奏会、ワルターによるウィーン・フィルとの「告別」演奏会、ホーレンシュタインによるマーラーの交響曲第9番(オルガヌム110079ALでディスク化済み)、カラヤンによる「大地の歌」(いずれもウィーン響)、シューリヒト/ウィーン・フィルによるブルックナー交響曲第9番といった貴重な演奏も、現在まで一部がエアチェック音源やフランス国立放送が保管していた音源がCD化されたに過ぎない。
カイルベルトはマーラーの交響曲のスタジオ録音を残さず、この他に1番と大地の歌のライブ録音が現在までに確認されているのみだが、当ディスクに聴く第8番のような合唱を伴う巨大な作品では、長年の歌劇場経験で鍛えたが統率力が冴えているようだ。独唱者も豪華な顔ぶれで特に男声は強力。早世した名テノール、ヴンダーリヒの歌唱も注目される。
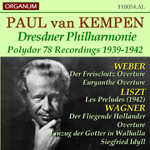
●ケンペン/ドレスデン・フィル ウェーバー、リスト、ワーグナー名曲集
オルガヌム110054AL
ウェーバー
歌劇「魔弾の射手」序曲
歌劇「オイリアンテ」序曲
リスト
交響詩「レ・プレリュード(前奏曲)」
ワーグナー
歌劇「さまよえるオランダ人」序曲
楽劇「ラインの黄金」から、「ヴァルハラ城への神々の入場」
ジークフリート牧歌
パウル・ファン・ケンペン指揮ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団
1939~1942年録音
(独ポリドール原盤) モノラル
※オランダの名匠ケンペンによる独ポリドールへのSP録音。多くが初復刻と思われる。音質良好。リストのみ第2次世界大戦下の物資不足の影響か、前半部分にサーフェイスノイズがやや多いが、ソフトな音質のノイズであるため、鑑賞への影響は少ない。
ケンペンは1934~1942年に同オケの音楽監督を務めており、ポリドールに当時としては大量の録音を残したが、ジョコンダ・デ・ヴィートとの共演盤を除いて、LPやCDに復刻されているものはあまり多くない。ちなみにリストの「前奏曲」は、2度録音したうちの2回目の録音。最初の録音は、ナチス政権によるラジオ宣伝放送やニュース映画のテーマ曲などに使用されたいわく付きの演奏。
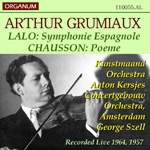
●グリュミオー ライブ ラロ スペイン交響曲、ショーソン 詩曲
オルガヌム110055AL
ラロ スペイン交響曲
ショーソン 詩曲
アルテュール・グリュミオー(ヴァイオリン)
アントン・ケルシス指揮クンストマンド管弦楽団
ジョージ・セル指揮コンセルトヘボウ管弦楽団
1964年2月2日、1957年11月28日、アムステルダム
ライブ モノラル
※2曲とも音質良好。1957年のショーソンは年代の水準を上回る音質。グリュミオー得意のフランス作品で、ラロは1954年と1963年、ショーソンは1954年と1966年、それぞれ2回ずつ蘭フィリップスにスタジオ録音していた。
クンストマンド(=芸術月間)管は、日本では馴染みがないが、1953年設立された団体で、1969年にアムステルダム・フィルと改称、さらに1985年に他団体と統合し、現在はネーデルランド・フィルの名で活動している。指揮者ケルシス(イシュトヴァン・ケルテスとは別人)は同オケの主席指揮者を長く務めた。
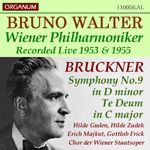
●ワルター/ウィーン・フィル ブルックナー交響曲第9番 1953年ライブ
オルガヌム110056AL
ブルックナー 交響曲第9番、テ・デウム
ヒルデ・ギューデン(ソプラノ)、ヒルデ・ツァーデク(メゾソプラノ)
エーリヒ・マイクト(テノール)、ゴットローブ・フリック(バス)
ウィーン国立歌劇場合唱団
ブルーノ・ワルター指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
1953年8月20日、ザルツブルク祝祭劇場
1955年11月13日、ウィーン国立歌劇場
ライブ、モノラル
※2曲とも特に優秀というわけではないが、良好で安定した音質。交響曲は既出盤よりヒスノイズが低減、潤いのあるウィーン・フィルらしい音色が再現されている。
交響曲はザルツブルク音楽祭におけるライブ。公演2日目の録音で、前半はベートーヴェン交響曲第2番が演奏された。テ・デウムは、ウィーン国立歌劇場再建記念公演におけるライブ。後半はベートーヴェン交響曲第9番が演奏された。
ワルターは亡命と第2次世界大戦による中断を経て、1947年にウィーン・フィルと再会、1960年までしばしば指揮台に上ったが、ブルックナーを取り上げることは少なく、交響曲は9番を1953年ザルツブルク音楽祭で2回、テ・デウムを1948年と1955年に演奏したのみであった。
ブルックナー自身は、交響曲第9番の未完成の第4楽章に代えて、テ・デウムを演奏するように示唆したと言われるが、実際にワルターは、1931年のウィーン・フィルとの演奏会で、この曲順でプログラムを構成していた。
ワルターは交響曲第9番を、1959年米CBSにコロンビア響とスタジオ録音していたほか、1946年、1953年、1957年にニューヨーク・フィル、1948年にフィラデルフィア管とライブ録音。テ・デウムを1937年にウィーン・フィル、1953年にニューヨーク・フィルとライブ録音していた。
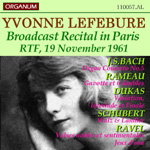
●イヴォンヌ・ルフェビュール 1961年放送ライブ バッハ、デュカ、シューベルト、ラヴェルほか
オルガヌム110057AL
バッハ(ヴィヴァルディ原曲) オルガン協奏曲第5番
ラモー ガヴォットと6つのドゥーブル(変奏)
デュカ ラモーの主題による変奏曲、間奏曲とフィナーレ
シューベルト(イヴォンヌ・ルフェビュール編) 12のワルツとレントラー
ラヴェル 高雅にして感傷的なワルツ、
水の戯れ
イヴォンヌ・ルフェビュール(ピアノ)
1961年11月19日、フランス国立放送スタジオ、パリ
モノラル
※イヴォンヌ・ルフェビュール(1898~1986年)は、フランスの女流ピアニスト。パリ音楽院でコルトーらに学び、フランス音楽のみならず、ベートーヴェンをはじめとするドイツ音楽にも定評があった。日本では、フルトヴェングラーと共演したモーツァルトのライブ録音や、晩年のソルスティスやfyなど仏レーベルへの録音で知られる。
この録音は、ルフェビュール60歳代中頃の放送用スタジオ録音。聴衆を入れずに収録したもので、モノラルながらノイズもなく良好な音質。ラモー~デュカ(ラモー作品を主題としている)、シューベルト(「感傷的なワルツ」を含む)~ラヴェルへと、それぞれ関連させながら、バロック期から近代まで、音楽の歴史を辿る巧みなプログラム構成。シューベルトは、ルフェビュールが様々なワルツや舞曲集から12曲(実際は14曲)を選び、シューマンに見られるような組曲形式にまとめたもの。プログラムの一部は後年、上記レーベルにスタジオ録音している。
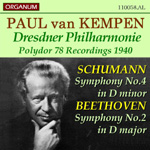
●ケンペン/シューマン交響曲第4番 ベートーヴェン交響曲第2番 ドレスデン・フィル 1940年独ポリドール録音
オルガヌム110058AL
シューマン 交響曲第4番
ベートーヴェン 交響曲第2番
パウル・ファン・ケンペン指揮ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団
1940年5月25日、4月7日録音(独ポリドール録音)モノラル
※独ポリドールによる第2世界大戦中のスタジオ録音。音質良好。78回転盤からの復刻のため、若干のサーフェイスノイズはあるが、レベルも低くソフトな音質のノイズであり、鑑賞への影響はほとんどない。
2曲ともオランダの巨匠ケンペン唯一の録音。ベートーヴェンの交響曲については、第2番以外に、蘭フィリップスほかに3、5、7、8番の録音が残されているが、シューマンの交響曲は上記4番のみで大変珍しい。
ケンペンは1934~1942年に同オケの音楽監督を務めており、当時はドイツ国籍を取得。独ポリドールには小品を中心に多くの録音を残した。しかし戦後オランダに復帰後は、この時期のドイツ国内の活動によってナチスへとの関係が取りざたされ、批判の対象となった。
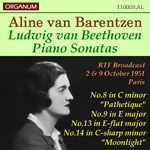
●アリーヌ・ヴァン・バレンツェン 放送ライブ ベートーヴェン「悲愴」「月光」ほか
オルガヌム110059AL
ベートーヴェン ピアノ・ソナタ第8番「悲愴」、第9番、第13番、第14番「月光」
アリーヌ・ヴァン・バレンツェン(p)
1951年10月2日(第8番、9番)、9日(第13番、14番)
フランス国立放送スタジオ、パリ
モノラル
アリーヌ・ヴァン・バレンツェン(1897~1981年)はアメリカ出身の女流ピアニスト(姓から推測するとオランダ系か)。幼少時に母とともにフランスに移住し、パリ音楽院でマルグリット・ロンなどに学んだ後、ベルリンでドホナーニ、ウィーンでレシェティツキにも師事した。その後はパリを中心に活動し1927年にはヴィラ=ロボスのショーロス第8番初演に参加するなど同時代の作曲家と交流。1930年代初頭にフランス国籍を取得した後は終生パリに住んだ。このような経歴から、フランス音楽のみならず様々な地域の作品も得意とした。ベートーヴェンのピアノ・ソナタはレコーディングの重要なレパートリーであり、演奏スタイルは、パリ音楽院出身の女流ピアニストというイメージとは異なる猪突猛進型。同じレシェティツキ門下の兄弟子シュナーベルを想起させるスタイル。
この演奏は、フランス国立放送(RTF)によるラジオ放送用スタジオ録音で、聴衆を入れずに収録したもの。アセテート盤に記録されており、ところどころ少しスクラッチノイズが入るが、鑑賞を妨げるような大きなノイズは音質を損なわない範囲でカットされている。バレンツェンの打鍵が強すぎるためかフォルテにも少し濁りがあるが、音質自体は、1950年代初頭という時代を考慮すれば妥当で鑑賞に堪えるレベル。録音ディスクの保存状態の差(?)により、8番・9番の方がノイズが少ない。
バレンツェンは、第8番と14番を仏EMI(VSM)に1947~1948年、1953年、1959年と3回スタジオ録音したほか、1959年にライブ録音していた。78回転SP、モノラルLP、ステレオLPと録音技術が進歩する10年ほどの間に、同一レーベルに再録音を繰り返していることは異例だが、それだけ高く評価されていたようだ。第9番と13番は、本CDが現在確認されている唯一の録音と思われる。
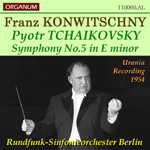
●コンヴィチュニー チャイコフスキー交響曲第5番 ウラニアLP復刻
オルガヌム110060AL
チャイコフスキー 交響曲第5番
フランツ・コンヴィチュニー指揮ベルリン放送交響楽団
1954年、ベルリン
米ウラニア原盤
モノラル
LP初期のマイナーレーベル・米ウラニアのLPから復刻。ウラニアは、フルトヴェングラーのエロイカなど、放送局由来の音源を使用した例が多いが、コンヴィチュニーのいくつかの録音は、おそらく正規のスタジオ録音と思われる(ほかにアルプス交響曲、ワーグナー序曲集、「リング」抜粋などが知られている)。
録音状態は当時の水準を超える高音質で、優れた録音機材を使用していたようだ。LP復刻によるノイズはわずかに残っているが、持続的なものではなく鑑賞に支障はない。
コンヴィチュニーは1949年からライプツィヒ・ゲヴァントハウス管、1953年からシュターツカペレ・ドレスデンの首席指揮者を兼務していたが、ベルリン国立歌劇場をはじめとして、ベルリンにも頻繁に来演していた。ちなみに当盤のベルリン放送響は、1923年に設立され、第二次世界大戦後は東ベルリンに本拠をおいた楽団。フリッチャイが指揮した西ベルリンの同名のオケ(旧称RIAS交響楽団)とは別団体。
コンヴィチュニーは、当盤以外にチャイコフスキーの交響曲のスタジオ録音を残さず、第4番について1953年シュターツカペレ・ドレスデン、1960年シュターツカペレ・ベルリンとのライブ録音が確認されているのみ。
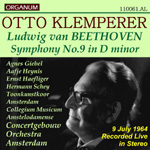
●クレンペラー/コンセルトヘボウ ステレオ・ライブ ベートーヴェン 交響曲第9番
オルガヌム110061AL
ベートーヴェン 交響曲第9番
アグネス・ギーベル(ソプラノ)、アーフェ・ヘイニス(アルト)
エルンスト・ヘフリガー(テノール)、ヘルマン・シャイ(バス・バリトン)
アムステルダム・トーンクンスト合唱団
コレギウム・ムジクム・アムステルダメンセ
オットー・クレンペラー指揮コンセルトヘボウ管弦楽団
1964年7月9日、コンセルトヘボウ、アムステルダム
ステレオ ライブ
※録音状態は良好。当時一般化していたステレオLPと比べると、もう少し広がりがほしい印象だが、ヨーロッパの放送現場でステレオ録音が導入され始めた時期であり、サウンド・エンジニアがステレオのマイクセッティングに不慣れだったためかも知れない。それでもモノラルに比べれば格段に分離が良く十分鑑賞に堪える。また会場ノイズも少なく、コンセルトヘボウの響きがよく捉えられている。
クレンペラーは第2次世界大戦後、頻繁にコンセルトヘボウ管弦楽団に客演したが、特にベートーヴェンの交響曲については、1955~1956年の全曲演奏会を含め数多く取り上げた。この演奏は毎年7月に開催されているオランダ音楽祭におけるライブで、公演の前半には、交響曲第1番が演奏された。コンセルトヘボウ管弦楽団にとっては、1964年はハイティンクとヨッフムによる二人常任体制最後の年であった。
クレンペラーは、ベートーヴェンの第9を1957年英コロンビアにフィルハーモニア管とスタジオ録音していたほか、1956年コンセルトヘボウ管弦楽団、1957年フィルハーモニア管、1958年ケルン放送響、1960年と1961年フィルハーモニア管、1964年と1970年ニュー・フィルハーモニア管とライブ録音していた。
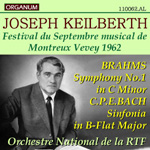
●カイルベルト ライブ ブラームス交響曲第1番ほか
オルガヌム110062AL
ブラームス 交響曲第1番
カール・フィリップ・エマヌエル・バッハ シンフォニア 変ロ長調
ヨゼフ・カイルベルト指揮フランス国立放送管弦楽団
1962年9月25日、モントルー・パビリオン大ホール
モノラル、ライブ
※2曲ともスイスのモントルーで開催された9月音楽祭におけるライブ。モノラルながら音質良好。会場ノイズも極小。ただしオリジナル音源は低音不足で高音にピークがあるほか、バッハの一部に混信があるなど問題が多く、イコライジングによる補正と最小限のノイズ処理を行ったという。結果的には、補正の不自然さもなく、カイルベルトらしい堂々たる演奏が再現されている。
カイルベルトとフランス国立放送管の組み合わせは意外に思えるが、同時発売のザルツブルク音楽祭ライブに見るようにしばしば共演していた。フランス国立放送管もシューリヒトなどドイツ系指揮者との共演も多く、また、さまざまなレパートリーへの対応が要求される放送オーケストラの柔軟性も相まって、このCDに聴くように違和感なく対応しているようだ。一部の木管楽器の音色が明るい点などにラテン系の団体らしさを感じる。
当日の演奏は、前半に、C・P・E・バッハのシンフォニアとバックハウス独奏によるベートーヴェンのピアノ協奏曲第3番が演奏され、休憩の後、ブラームスが演奏された。なお、バックハウスによるベートーヴェンも近日CD化予定。
カイルベルトは、ブラームスの交響曲第1番を1951年独テレフンケンにベルリン・フィルとスタジオ録音していたほか、1968年NHK交響楽団とライブ録音していた。C・P・E・バッハのシンフォニアはスタジオ録音を残さず、上記ライブが現在確認されている唯一の録音と思われる。今日のピリオド楽器による演奏に比べて、モダン楽器による重厚な演奏は、まったく異なる曲を聴いているような印象。
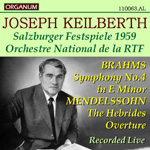
●カイルベルト ライブ ブラームス交響曲第4番ほか
オルガヌム110063AL
ブラームス 交響曲第4番
メンデルスゾーン 序曲「フィンガルの洞窟」
ヨゼフ・カイルベルト指揮フランス国立放送管弦楽団
1959年8月9日、ザルツブルク祝祭劇場
モノラル、ライブ
※2曲ともザルツブルク音楽祭におけるライブ。モノラルながら音質良好。わずかにヒスノイズがあるが、鑑賞の妨げになるものではない。ザルツブルク祝祭劇場らしい音響が再現されている。会場ノイズも微少。正規音源によるザルツブルク音楽祭ライブCDの多くが、過剰なノイズカットにより無機質な音色に変質していることに比べると、このCDでは「漂白」されていないオリジナル音源の良さが残されている。
カイルベルトとフランス国立放送管の演奏は、同時発売のモントルー9月音楽祭ライブと同様に違和感なく、演奏を聴く限りフランスの団体とは分からない。当日の演奏は、前半に「フィンガルの洞窟」とウォルフガング・シュナイダーハンの独奏でフランク・マルタンのヴァイオリン協奏曲が演奏され、休憩の後、ブラームスが演奏された。
カイルベルトは、ブラームスの交響曲第4番を1960年独テレフンケンにハンブルク国立フィルとスタジオ録音していたほか、1968年バンベルク交響楽団とライブ録音していた。また「フィンガルの洞窟」を1967年独テレフンケンにベルリン・フィルとスタジオ録音していた。
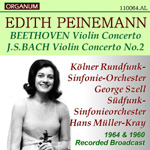
●エディット・パイネマン ベートーヴェン、バッハ ヴァイオリン協奏曲
オルガヌム110064AL
ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲
バッハ ヴァイオリン協奏曲第2番
エディット・パイネマン(ヴァイオリン)
ジョージ・セル指揮ケルン放送交響楽団
ハンス・ミュラー=クライ指揮シュツットガルト放送交響楽団
1964年6月11日、ケルン放送大ホール
1960年10月11日、シュツットガルト・ヴィラ・ベルク・ホール
放送スタジオライブ モノラル
※2曲とも聴衆を入れずに収録した放送のための演奏で、当時の西ドイツの放送録音らしく、派手さはないが堅実でノイズもない安定した録音。年代が新しいベートーヴェンは特に音質良好で、左右チャンネルが分離すればそのままステレオ録音として通用する。一方、1960年録音のバッハは、ベートーヴェンに比べて周波数レンジが狭いが、こちらも年代を考慮すれば好録音。
エディット・パイネマンは、1934年生まれのドイツのヴァイオリニスト。マックス・ロスタルに師事した後、1953年にミュンヘン国際コンクールで上位入賞後、1962年にアメリカ・デビュー、その後はザルツブルク音楽祭にも出演、1972年にはミュンヘン・フィルに同行して来日している。このように欧米を中心に広く活躍したが、正規のレコード録音は極めて少なく、1966年録音のドヴォルザークのヴァイオリン協奏曲+ラヴェルのツィガーヌ(独グラモフォン)、および1965年録音のシュワルツコップとジョージ・セルによるR・シュトラウス「4つの最後の歌」第3曲におけるヴァイオリン・ソロ(英EMI)以外には、マイナーレーベルにブラームスのヴァイオリン・ソナタ、レーガーのヴァイオリン協奏曲があるだけといわれており、今回のベートーヴェンとバッハの放送録音は貴重。
女流ヴァイオリニストというと、ヌヴーやキョンファ・チョンのように情熱的であったり、ボベスコのように優美・典雅な演奏イメージがあるが、パイネマンは、極めて理知的で引き締まった均整美あふれる演奏スタイルといえる(同じくドイツ生まれで2歳年長のラウテンバッハーに近いか)。
ベートーヴェンの伴奏を務めるジョージ・セルは、おそらく自らの音楽性との共通点を見出したのであろう。彼女のアメリカ・デビュー時の演奏を聴き、クリーヴランド管やニューヨーク・フィル、コンセルトヘボウ管への招聘を推薦し、公演の際には様々な助言を与えるのみならず(これはすべての共演者に行っていたようだが)、グアルネリの銘器を購入するため資金提供者を募るなど、さまざまな援助を行ったという。上記英EMIへのR・シュトラウス「4つの最後の歌」は正規録音における唯一の共演だが、セルが参加を推薦した可能性がある。ちなみにライブでは、1964年11月(コンセルトヘボウ管、ベートーヴェンの協奏曲、当録音の5か月後)、1965年1月クリーヴランド管(同じくベートーヴェンの協奏曲)、1967年同管(バルトーク協奏曲第2番)、1970年ニューヨーク・フィル(モーツァルト協奏曲第5番)に共演記録が確認されている。
バッハの伴奏を務めるミュラー・クライ(1908~1969)は、ドイツ・エッセン生まれで、1948年から死去するまでシュツットガルト放送響(当時の名称は南ドイツ放送響)の首席指揮者を務めた。シューリヒトやチェリビダッケらが同響を客演した当時、普段この楽団を支えていたのはミュラー・クライであったことになる。
前述のように、パイネマンは2曲のレコード録音を残しておらず、上記CDが現在確認されている唯一の録音。セルはベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲を、1934年英コロンビアにフーベルマンとスタジオ録音したほか、1967年にモリーニとライブ録音していた。
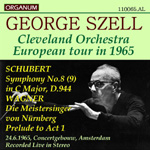
●セル/クリーヴランド管 ステレオ・ライブ シューベルト 交響曲第8(9)番ほか
オルガヌム110065AL
シューベルト 交響曲第8(9)番「グレイト」
ワーグナー 「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲
ジョージ・セル指揮クリーヴランド管弦楽団
1965年6月24日
コンセルトヘボウ、アムステルダム
ライブ ステレオ
※2曲とも優秀なステレオ・ライブ録音。コンセルトヘボウの美しい残響が印象的。聴き始めは、音が遠く感じ、解像度が低いように感じるが、細かい音も良く捉えており、コンセルトヘボウの客席から聴くイメージに似ている。直接音が中心だった1960年代の大手レコード会社の標準的な録音スタイルよりも、ホール全体の響きを捉える現在の傾向に近いも知れない。
1965年春から夏にかけて、セルとクリーヴランド管は1957年以来二度目となるヨーロッパ公演を行った。この公演では米国務省の支援を受けて初めてソ連を訪問、サンクトペテルブルクやキエフ、ジョージア(グルジア)、アルメニア各地で公演が行われたが(サンクトペテルブルクのライブは「Aurora」レーベルで発売予定)、上記の演奏は、ソ連各地を訪問後、アムステルダムで行われた演奏会のライブ録音。演奏会では、上記の2曲に加えて、ジョン・ブラウニング独奏によるバーバーのピアノ協奏曲も演奏された。
セルは、しばしばコンセルトヘボウ管の指揮台に立ったが、クリーヴランド管による1965年のアムステルダム公演は、オランダの聴衆に対して、長年セルが育成してきた同管が、コンセルトヘボウ管と同レベルの世界最高水準のオーケストラであることを示す機会となった。普段は機能美を強く感じるクリーヴランド管だが、この演奏では、コンセルトヘボウの深い残響のためか、ヨーロッパの伝統的なオーケストラと同様の趣を見せているように思える。
セルは、シューベルトの「グレイト」を、いずれもクリーヴランド管と1957年米CBS、1970年英EMIにスタジオ録音したほか、1957年、1968年、1970年にライブ録音していた。また、「マイスタージンガー」第一幕への前奏曲は、ニューヨーク・フィルと1954年米CBSに、クリーヴランド管と1962年に米CBSにスタジオ録音したほか、1968年にクリーヴランド管とライブ録音していた。

●バックハウス カイルベルト ライブ ベートーヴェン協奏曲第3番、第5番「皇帝」
オルガヌム110066AL
ベートーヴェン ピアノ協奏曲第3番、第5番「皇帝」
ウィルヘルム・バックハウス
ヨゼフ・カイルベルト指揮フランス国立放送管弦楽団
シュツットガルト(南ドイツ)放送交響楽団
1965年9月25日、3月15日
モントルー展示館大ホール、
シュツットガルト・ヴィラ・ベルク・スタジオ
ライブ モノラル
※2曲とも特に優秀というわけではないが、十分鑑賞に堪える音質。ただし、第3番はフランス国立放送、第5番は南ドイツ放送による録音で、オリジナルの音質の傾向はそれぞれ異なっていたようだ。第3番は、オリジナルはやや低音不足で高音にピークがあり、解像度は比較的良い方だが、潤いのないドライな音質。また、録音済みテープを上書きして使用しており、弱音部で前の録音(会話?)がかすかに聞こえていた。これらをマスタリングにより、鑑賞に堪える状態まで改善したという。また第5番のオリジナルの状態は、第3番とは対照的に中低域が過剰で濁りがあり、解像度も不足していた。こちらもイコライジング等により見通しの良いクリアな音質に改善したという。両者の録音スタイルの違いにはフランス人とドイツ人の感性の違いを感じる。
第3番はモントルー音楽祭におけるライブで、同時に演奏されたカイルベルト指揮によるC・P・E・バッハのシンフォニアとブラームス交響曲第1番は、オルガヌム110062でCD化されている。第5番は、南ドイツ放送による聴衆を入れたスタジオ・ライブ録音。プログラム後半は、カイルベルト指揮でブラームス交響曲第4番が演奏された。ちなみに第5番は、かつてクナッパーツブッシュ指揮ベルリン・フィルと偽ってLP発売された演奏。今日では、カイルベルトとクナッパーツブッシュは演奏スタイルが大きく異なるという認識だが、LP発売当時は、専門家でも知識や情報が不足し、演奏に疑念を持つ者はいなかった。カイルベルトの個性に影響されたためか、バックハウスが数多く残した「皇帝」の録音の中でも、最も推進力に富んだ、充実した演奏といえる。
1962年と言えば、バックハウスはすでに78歳の高齢だったが、この年も精力的に活動。3月にシュツットガルトでカイルベルトと共演後、5月にはウィーン芸術週間、7月にはザルツブルク音楽祭に登場、9月にはモントルー音楽祭で再びカイルベルトと共演している。
バックハウス自身は、ベートーヴェンのピアノ協奏曲のうち、最も好んで演奏したのは第4番で、第5番をあまり好んでいなかったようだ。しかし、後述するようにライブも含めて10種もの録音が残ったのは、人気曲で要望が多かったからだろう。
バックハウスは上記CDのほかに、ピアノ協奏曲第3番を1950年と1959年英デッカにスタジオ録音したほか、1960年にライブ録音していた。また、「皇帝」を、1927年独エレクトローラ(英HMV)に、1953年と1959年英デッカにスタジオ録音したほか、1954年、1956年、1959年、1960年、1961年、1963年にそれぞれライブ録音していた。
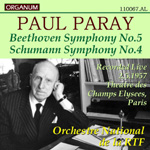
●ポール・パレー フランス国立管ライブ ベートーヴェン5番、シューマン4番
オルガヌム110067AL
ベートーヴェン 交響曲第5番
シューマン 交響曲第4番
ポール・パレー指揮フランス国立放送管弦楽団
1957年5月2日録音、パリ・シャンゼリゼ劇場
ライブ、モノラル
※モノラルながら音質良好。1957年当時のヨーロッパの放送局によるライブ録音としては標準的な音質で、特に優秀というわけではないが、会場ノイズもなく十分鑑賞に堪えるレベル。一般にフランス国立放送のオーケストラ録音というと、解像度が高くて生々しく、分析的に聴くには適しているものの、低音不足で高音にピークがあり、各楽音がブレンドしない乾いた音質で、音を楽しむまでには至らない場合が多い。しかし、このCDの録音は、珍しくも中低音が充実しており、オーケストラをマスとして捉えた、ドイツの放送局のような録音スタイル。そのせいかオーケストラもフランスらしさよりドイツのオケのような趣があるが、それは、ポール・パレーの演奏も寄与していると思われ、1950年代のパリで、フランス人によってこれほどの充実したベートーヴェンが演奏されていたという証拠でもある。オリジナル録音は、前述のように中低音が豊かな反面、逆に高音が不足していたため、イコライジングで補正している。
演奏は、パリ・シャンゼリゼ劇場におけるフランス国立放送管定期演奏会のライブ録音だが、当日は、上記2曲の前にハイドンの交響曲第96番が演奏された。ハイドンとシューマンの2曲は、いずれも米マーキュリーにスタジオ録音しており、得意のレパートリーであったことが分かる。
ポール・パレーは上記のように、シューマンの交響曲第4番を1953年米マーキュリーにデトロイト響とスタジオ録音していたが、ベートーヴェンの交響曲第5番はスタジオ録音を残さず、1959年デトロイト響とのライブ録音が残されているのみである(この録音はプレミエ60059としてCD化済み)。
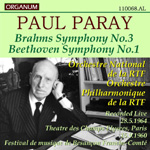
●ポール・パレー フランス国立管ほかライブ ブラームス3番、ベートーヴェン1番
オルガヌム110068AL
ブラームス 交響曲第3番
ベートーヴェン 交響曲第1番
ポール・パレー指揮フランス国立放送管弦楽団、フランス放送フィルハーモニー管弦楽団
1964年5月28日、パリ・シャンゼリゼ劇場
1960年9月15日、ブザンソン・グラン・クルサール
ライブ、ステレオ/モノラル
※2曲とも録音優秀。ブラームスはステレオ録音。エンジニアが一切のイコライジングを行わず、すべての楽器が前に出てくるような奔放な録音。パレーの演奏自体が奔放なのかも知れない。メジャーレーベルのレコード会社のような練り上げた録音とは対照的で、新鮮で刺激的である。ライブ録音のため、マイクセッティングに制限があったと思われ、バランスが少し悪い箇所も見受けられるが、優秀録音といえる。ベートーヴェンはモノラルだが、フランスの放送局へステレオ機材導入が開始された時期と重なっており、音質は非常に良い。全体のバランスなどは、ステレオのブラームスよりもまとまりが良いようだ。いずれも会場ノイズはほとんど聞こえない。
ブラームスはパリ・シャンゼリゼ劇場におけるフランス国立放送管の定期演奏会、ジャケット表記はおそらく放送日で、実際は5月12日のようだ。この日のプログラムは、ブラームス、ラヴェルのスペイン狂詩曲、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番(バイロン・ジャニス独奏)というもの。ラヴェルが第1曲、ブラームスが第2曲だったかも知れないが、バイロン・ジャニスのチャイコフスキーがメイン・プログラム。一方、ベートーヴェンはブザンソン音楽祭からのライブ。オーケストラは珍しく「第二オケ」のフランス放送フィルハーモニー管。よく知られているように、この音楽祭では指揮者コンクールが開催され、この録音の前年1959年には小澤征爾が優勝している。こちらのプログラムは、ベートーヴェンのレオノーレ序曲第1番に続き交響曲第1番。休憩をはさんでクロード・パスカルのチェロ協奏曲(アンドレ・ナヴァラ独奏、世界初演)、フォーレのペレアスとメリザンド組曲、最後にシャブリエの狂詩曲スペイン(アンコールか?)という、今日の我々から見るといささか妙な組み合わせ。クラシックな独墺音楽と自国作品というカップリングがフランスらしいともいえる。
パレーは、ブラームス交響曲第3番のスタジオ録音を残さず、上記のライブが現在確認されている唯一の録音。ベートーヴェン交響曲第1番は1959年米マーキュリーにデトロイト響とスタジオ録音していた。
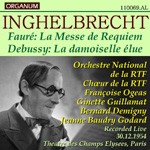
●アンゲルブレシュト ライブ フォーレ「レクイエム」 ドビュッシー「選ばれし乙女」
オルガヌム110069AL
フォーレ「レクイエム」
ドビュッシー カンタータ「選ばれし乙女」
フランソワーズ・オジュア(ソプラノ)
ジネット・ギヤマ(メゾ・ソプラノ)(「選ばれし乙女」語り手)
ベルナール・ドゥミニ(バリトン)
ジャンヌ・ボドリー・ゴダール(オルガン)
マルセル・ブリクロ(合唱指揮)
デジレ・エミール・アンゲルブレシュト指揮フランス国立放送管弦楽団・合唱団
1954年12月30日、パリ・シャンゼリゼ劇場
ライブ、モノラル
※録音状態良好。1950年代半ばのテープ録音で極めてクリアな音質。フォーレの第4曲に微細な電気的ノイズ(ほとんど聞こえない)、第7曲に1カ所瞬間的で微細なワウ(音程の変動)、ドビュッシーに数カ所こちらも微細なポップ(クリック)ノイズがあり、いずれも録音テープの経年変化によると思われるが、鑑賞には全く支障がないと言えるレベル。
この時代のフランス国立放送による録音の特徴として、またシャンゼリゼ劇場の音響特性も相まって、残響が乏しく、解像度は高いが各楽音があまりブレンドしない傾向がある(オンマイクで楽器との距離が近いのだろう)。これらはドイツ系の音楽ではマイナス要素が大きいが、なぜか本CDのフォーレやドビュッシーではプラスに働いているようで、違和感なく音楽を楽しむことが出来る。やや曖昧模糊とした音響の作品には相性が良いのかも知れない。
アンゲルブレシュトは1955年1~2月、仏デュクレテ・トムソンにフォーレの「レクイエム」を録音し、歴史的名盤と評価されているが、本CDはその直前に同じキャストで行われたライブ録音である(ただしデュクレテ・トムソンによる録音会場はパリ・サン・ロシュ教会)。フランス国立放送管の定期演奏会の機会を捉えてスタジオ録音を行ったのだろう。
ちなみに当日の公演は、第1曲目にモーツァルトの交響曲第40番、続いてドビュッシー、休憩を挟んでフォーレというプログラムであった。アンゲルブレシュトのモーツァルトは珍しいが、彼は1934年~1946年と1951~1958年にフランス国立放送管の首席指揮者を務めており、放送オーケストラの使命として、幅広いレパートリーの作品を取り上げたようだ。ちなみにこの日のモーツァルトは「残念ながらCD発売できる状態の演奏ではない」とのこと。
アンゲルブレシュトは前述のように、フォーレの「レクイエム」を1955年仏デュクレテ・トムソンにシャンゼリゼ劇場管(フランス国立放送管の変名)と、またドビュッシーの「選ばれた乙女」を1953年に同じレーベルとオーケストラでスタジオ録音したほか、「選ばれた乙女」を1957年と1962年にライブ録音していた(いずれもオケはフランス国立放送管)。

●バルビローリ 1965年プロムス・ライブ ベートーヴェン「英雄」
オルガヌム110070AL
ベートーヴェン 交響曲第3番「英雄」
エグモント序曲
サー・ジョン・バルビローリ指揮ハレ管弦楽団
1965年7月30日、ロンドン・ロイヤル・アルバート・ホール
1966年12月1日、マンチェスター・フリー・トレード・ホール
モノラル、ライブ
※「英雄」は、BBCプロムナード・コンサート(プロムス)、エグモント序曲は、ハレ管の本拠地における定期演奏会のライブ。「英雄」はおそらく初出。エグモント序曲はかつて海外盤で発売されていたと思われる。
年代的にはステレオ録音が普及していた頃だが、残念ながら両曲ともモノラル。AMラジオ放送などのために、ヨーロッパの放送現場では、ステレオ録音と平行して1970年代までモノラル収録が行われていたようだ。
ただし「英雄」の録音状態は良好だがやや特殊な音響。第1楽章冒頭の2回の主和音に深く長い残響が付いているなど、円柱形の構造を持つロイヤル・アルバート・ホールの音響を忠実に収録したような録音。直接音中心だった当時の放送録音と異なるスタイルで、ホールやオーケストラ自身による記録用録音かも知れない。それでも残響が長めの割には、ソロ楽器などの細かい音もよく拾っているため、演奏の善し悪しを判断し音楽を楽しむには問題ないレベル。ただしオリジナルの音源は、低音過剰な上、高音にピークがあって聴きずらく、また演奏の正しい姿を伝える状態ではなかったため、大幅なイコライジングにより補正を行ったとしている。1階フロアが立ち席でお祭り騒ぎのイメージが強いプロムスだが、会場ノイズはほとんど聞こえない。騒がしいのはラスト・ナイトのみか。
エグモント序曲は、「英雄」に比べると、直接音主体のオーソドックな放送録音スタイル。1966年としてはやや古い感じで(1960年代初頭くらいか)、古い録音機材が使われていたのかも知れない。こちらも鑑賞には不足のないレベルとなっている。
バルビローリは、1965年のプロムスには4回登場。7月30日の公演は、ハイドンの交響曲第83番「めんどり」、「英雄」、ニルセンの交響曲第4番「不滅」というもの。「英雄」までが前半で「不滅」が後半と思われるが、休憩時間の配分が難しいプログラム。
バルビローリにとってベートーヴェンの交響曲は、1、3、8番しか正式なレコーディングを残しておらず、中心的なレパートリーではなかったような印象があるが、ハレ管やニューヨーク・フィルの常任時代の演奏会記録を見ると、多数回ではないものの、第9番を含めておそらく交響曲全曲を取り上げており、海外情報が乏しかった日本人の誤解らしい。なかでも「英雄」は比較的演奏回数が多かった。
バルビローリは、上記のほかに、ベートーヴェンの「英雄」を1967年、エグモント序曲を1949年、それぞれ英HMVにハレ管とスタジオ録音していた。
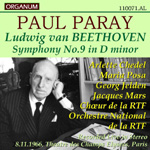
●パレー フランス国立管ステレオライブ ベートーヴェン第9
オルガヌム110071AL
ベートーヴェン 交響曲第9番「合唱付き」
アリエット・シェデル(ソプラノ)
マリア・ポーザ(アルト)
ゲオルク・イェルデン(テノール)、
ジャック・マルス(バス・バリトン)
ポール・パレー指揮フランス国立放送管弦楽団・合唱団
1966年11月8日録音、パリ・シャンゼリゼ劇場
ライブ、ステレオ
※輸入新品CD-R。優秀なステレオ録音。フランス国立放送は1960年頃からステレオ録音を導入し始めたが、それから数年経った時期の録音。若干低音が軽いイメージだが、演奏の傾向によるものかも知れない、いずれにしても当時の放送録音としては十分に高音質で鑑賞には全く問題ない。会場ノイズもほとんど聞こえない。
当日は第9に加え、前半に交響曲第1番が演奏された。11月にベートーヴェン第9を演奏するというのは、日本の「クラシック業界」から見ると中途半端なイメージもあるが、ドイツの一部地域を除き欧米では年末に第9を演奏したり放送する習慣はなく、一方では何らかの祝典や記念として演奏されることが多いようだ。
パレーは第二次世界大戦前から仏コロンビアなどに度々レコーディングを行い、戦後は常任となったデトロイト響と米マーキュリーに大量の録音を残した。しかし、1963年のデトロイト響退任後、1979年に死去するまでの10数年間は極端にレコーディングが少なくなり、放送ライブ以外の正式なスタジオ(セッション)録音は、仏コンサートホールソサエティや仏エラートへの数枚に過ぎない。理由は不明だが、パレーほどの大物にレコード会社から録音の依頼がないわけはなく、マーキュリーへの大量録音でレコーディングは「卒業」したと本人が思ったか、演奏会の指揮以外には作曲活動に力を入れたいと考えたか。パレーはフランス国立放送管とは、終生密接な関係を続けており、放送オーケストラの特徴として、演奏会の大半は録音されているため、このCDのように、パレーによる未発表録音の発掘が期待される。
1966年録音のベートーヴェン第9は、そのようなレコーディング空白期の演奏。パレーのベートーヴェンというと「田園」の超高速テンポが有名だが、この演奏では速めながら「田園」ほど極端なテンポではないようだ。フランス国立放送管は、前年の1965年にもシューリヒト指揮で同曲を演奏しており、ドイツ系レパートリーにも全く違和感なく対応している。
パレーは、ベートーヴェン交響曲第9番のスタジオ録音を残さず、1962年デトロイト響とのライブ録音が残されている(この録音はプレミエ60046としてCD化済み)。
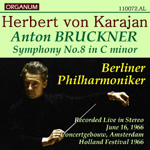
●カラヤン/BPO ブルックナー8番 1966年オランダ音楽祭ライブ
オルガヌム110072AL
ブルックナー 交響曲第8番(ハース版)
ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
1966年6月16日録音、アムステルダム・コンセルトヘボウ
ライブ、ステレオ
※優秀なステレオ録音。コンセルトヘボウの深い残響が美しくバランスも申し分ない。会場ノイズも極少。オランダの放送局AVROは1964年頃からステレオ収録を導入しており、2年ほどキャリアを積んだ当録音では技術的に完成の域に達している。当時のフィリップス・レーベルなどのコンセルトヘボウにおけるセッション録音に比べると、ホールトーンがより豊かで実際に客席で聴いているような感覚。
1966年のカラヤンは57~58歳の働き盛り。1月~3月にベルリン・フィル定期演奏会に登場。4月~5月に同フィルとともに2度目の来日公演を行い、5月2日には東京でブルックナー交響曲第8番を演奏。離日後、5月末にはプラハの春音楽祭、6月にオランダ音楽祭に出演。6月15日と16日の2回の公演で2日目のプログラムがこのCDの録音である。その3日後、19日から3日間はフランスのシャルトルとパリで公演を行い、その後カラヤンのみ7月~8月にウィーン・フィルとともにザルツブルク音楽祭に出演、9月からはベルリン・フィルの1966~1967年シーズンの定期演奏会が開幕という超ハードスケジュールの日々であった。
カラヤンはブルックナーの交響曲第8番を、1957年英コロンビア、1975年と1988年独グラモフォンにそれぞれベルリン・フィルとスタジオ録音(1988年録音は独ソニーがビデオ収録)、1979年独グラモフォンにウィーン・フィルとビデオ収録したほか、1944年にベルリン国立歌劇場管、1957年(4月と7月の2種)と1965年にウィーン・フィル、1966年5月、1967年、1974年(11月5日と11日の2種)、1975年にベルリン・フィル、1978年、1986年、1989年ウィーン・フィルとライブ録音していた。
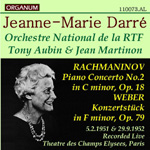
●ジャンヌ=マリー・ダレ ラフマニノフ ピアノ協奏曲第2番 ウェーバー コンツェルトシュトゥック 1951年、1952年ライブ
オルガヌム110073AL
ラフマニノフ ピアノ協奏曲第2番
ウェーバー コンツェルトシュトゥック(ピアノ小協奏曲)
ジャンヌ=マリー・ダレ(ピアノ)
トニー・オーバン、ジャン・マルティノン指揮
フランス国立放送管弦楽団
1951年2月5日、1952年9月29日録音、パリ・シャンゼリゼ劇場
ライブ、モノラル
※ラフマニノフは、特に優秀というわけではないが安定した年代相応の音質。同年代のライブ録音に親しんでいる鑑賞者であれば全く問題ないレベル。一方、1年後のウェーバーは、年代を考慮すると非常に優れた音質。マイクセッティング等の条件がよほど良好だったのだろう。1960年代前半のライブ録音と同等レベル。ただし、2曲ともヒスノイズやドロップアウトなど、古い録音に頻出する瑕疵が散見されたため、慎重なマスタリングにより、音質を損ねることなく解消している。
2曲ともフランス国立放送管定期演奏会のライブで、拍手はカットされているか、またはもともと拍手がされていない可能性がある。フランス国立放送管は放送オケの常として、演奏会と合わせてラジオ放送のためのライブ録音が行われていたが、1950年代初頭には、通常の演奏会とは異なり、ステージ上で司会者(アナウンサー)の挨拶に続き、専門家による曲目解説、そして司会者の曲目・演奏者の紹介後、演奏開始、演奏終了後、場合によっては聴衆に拍手をさせずに再び司会者が曲目の紹介するといった手順で進められたこともあったようだ。現代の我々は、演奏を収録後、アフレコでナレーションなどを追加するか、生中継でも会場の別室で放送のためのアナウンスを行うことが常識だが、当時は、演奏会自体を番組として放送していたのだろう。聴衆は言わば放送見学者の扱いだったわけである。
ジャンヌ=マリー・ダレ(1905~1999年)は、フランス生まれの女流。いわゆるグラン・ダーム(grande
dame、貴婦人・名声のある女性の意)といわれるフランス系女流ピアニストの一人。例外もあるが19世紀末~20世紀前半にパリ音楽院などでフランス流の教育を受け、長年パリを中心に演奏や教育活動を行った人たちを指し、マルグリット・ロンが代表格であり、当レーベル既発売のイヴォンヌ・ルフェビュールなどもその一人である。一般にフランス系女流というと、優美で典雅なサロン的演奏スタイルと思われがちだが、実際は異なり、時代背景も影響して、多くは過剰な情緒を排した即物的・新古典主義的で、現代的・客観的な演奏スタイルが主流であるようだ。ただし、そのような表現の中に、洗練されたロマン的要素がうかがえる点も魅力とされる。ジャンヌ=マリー・ダレはパリ音楽院でイシドール・フィリップ、マルグリット・ロンに師事。パリを中心に演奏・教育活動を行い、フランス国立放送管とも度々共演した。
ジャンヌ=マリー・ダレは、日本では仏EMIパテに録音したサン=サーンスのピアノ協奏曲全集、米ヴァンガードに録音したショパンやリストの独奏曲で知られているが、ラフマニノフは意外な曲目。しかし、コンサートピアニストとしては当然のレパートリーであり、難曲として知られるサン=サーンスの協奏曲を得意としていれば、技術的には十分対応可能であり、我々日本人の情報不足であろう。指揮のトニー・オーバン(1907~1981年)は、日本では、作曲家の黛敏郎がパリ音楽院留学した際の担当教授であったこと(黛は教育内容に反発して退学した)、ラヴェルの弟子で作曲家・評論家のロラン・マニュエルの対談集「音楽の楽しみ」で、議論を仕掛けてくる血気盛んな作曲家・教育者として紹介されたことくらいしか知られていないが、1945~1960年までフランス国立放送(四つのオケが所属)の指揮者を務め、コンサート以外に放送のための珍しいオペラ録音など積極的に指揮活動を行っていた。そのオペラ録音の一部は、1980年代に仏ブール(Bourg)レーベルでLP・CD化されていた。一方のウェーバーは、ジャンヌ=マリー・ダレの演奏スタイルにふさわしいレパートリー。ロベール・カザドシュも好んで演奏しており、フランスのピアニストに好まれていたようだ。指揮のジャン・マルティノンについては説明不要だろう。
ジャンヌ=マリー・ダレは、上記2曲ともスタジオ録音を行わず、当盤が現在確認されている唯一の録音である。
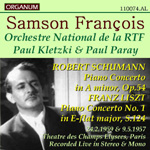
●サンソン・フランソワ ライブ シューマン ピアノ協奏曲 リスト ピアノ協奏曲第1番 1959年、1957年ライブ
オルガヌム110074AL
シューマン ピアノ協奏曲
リスト ピアノ協奏曲第1番
サンソン・フランソワ(ピアノ)
パウル・クレツキ、ポール・パレー指揮
フランス国立放送管弦楽団
1959年2月24日、1957年5月9日録音、パリ・シャンゼリゼ劇場
ライブ、ステレオ/モノラル
※シューマンはステレオ録音。おそらくフランス国立放送によるステレオ収録の最初期の一例と思われ、マイクセッティングが未熟のためか、左右のセパレーションが弱く広がりにやや欠ける。ただし音質自体はそれほど悪くなく年代相応、バランスも良好でノイズも極小。音楽を鑑賞するためには問題ない。その2年前に収録されたリストは当然モノラルだが、技術的に安定しているせいか、音質自体はこちらの方が良好。ただし、両者の録音の印象は、シューマンとリストのオーケストレーションの違いによる響きの違いによるかも知れない。
早世した天才ピアニスト、サンソン・フランソワによるライブ録音は近年少しずつ発掘されてきているが、シューマンはクレツキ指揮によるフランス国立放送管定期演奏会のライブ録音。この日の演奏会は、ベートーヴェンのレオノーレ序曲第3番に続いてシューマンの協奏曲、休憩の後、ブラームスの交響曲第1番というドイツ作品プログラムからの1曲。シューマンは、前年1958年6月に行われた仏コロンビアによるスタジオ録音と同じコンビによる再演に当たるが、フランソワによるシューマンの協奏曲は当時人気が高かったらしく、仏コロンビアによるスタジオ録音の前年、1957年9月にはモントルー音楽祭でミュンシュと、当演奏の2カ月後の4月には再びパリでジュリーニと演奏している。パレーと共演したリストの協奏曲も同じくフランス国立放送管定期のライブで、ラヴェルの「ボレロ」、ドビュッシーの「海」、リストの協奏曲、プロコフィエフの古典交響曲という「名曲コンサート」からの1曲。リストもフランソワ得意のレパートリーで1956年初来日時にも演奏している。
サンソン・フランソワはシューマンの協奏曲を、上記のように1958年仏コロンビアにクレツキ指揮フランス国立放送管とスタジオ録音したほか、1957年にミュンシュ指揮フランス国立放送管と、1959年にジュリーニ指揮フランス国立放送管とライブ録音していた。また、リストの協奏曲第1番を、1954年仏コロンビアにツィピーヌ指揮パリ音楽院管と、1960年同じく仏コロンビアにシルヴェストリ指揮フィルハーモニア管とスタジオ録音したほか、1956年上田仁指揮東京交響楽団とライブ録音していた。
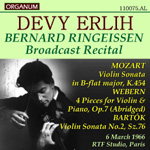
●ドヴィ・エルリ 1966年放送リサイタル モーツァルト、ウェーベルン、バルトーク
オルガヌム110075AL
モーツァルト ヴァイオリン・ソナタ第40番変ロ長調 K.454
ウェーベルン ヴァイオリンとピアノのための4つの小品 作品7(3曲抜粋)
バルトーク ヴァイオリン・ソナタ第2番 Sz.76
ドヴィ・エルリ(ヴァイオリン)、ベルナール・リンガイセン(ピアノ)
1966年3月6日、フランス国立放送スタジオ、パリ
モノラル
※聴衆を入れずに行われた放送のためのスタジオ・ライブ。音質良好。1960年代中盤ともなると放送局の録音技術も進歩し、モノラルではあるが、現代の水準から見ても(聴いても)違和感なく音楽を鑑賞出来るレベルとなっている。ヴァイオリンとピアノという編成が小さいことも有利に働いている。
ウェーベルンの4つの小品は、第1曲(Sehr
langsam~非常にゆっくりと)を除く3曲を演奏。オリジナル音源にあるアナウンサーの曲目紹介では第1曲にも言及しているが、実際の演奏は第2曲から始まっている。演奏されなかったのか録音に失敗したのか不明だが、チューニングを繰り返しているような曲想で1分ほどと短いため、編集段階でエンジニアが誤って削除した可能性もある。
ドヴィ・エルリ(1928~2012年)(デヴィ・エルリとの表記もある。フランス国立放送のアナウンサーの発音はこちらに近い)はフランス・パリ生まれのヴァイオリニスト、パリ音楽院でジュール・ブーシュリに学び、1955年ロン=ティボー国際音楽コンクールで優勝、直後の1956年に初来日。1982年にはパリ音楽院の教授に就任、1980年代後半からは桐朋学園に客員教授として赴任するなど、後進の指導にも尽力した。レコーディングは1950年代~60年代前半に仏デュクレテ・トムソンやクラブ・ディスク・フランスを中心に、協奏曲や室内楽などの録音が活発に行われた。1990年には日本のフォンテックに現代作品を録音している。
レコーディングも数多く、来日して教育も行い、晩年に至るまで演奏活動も続けていたが、なぜか日本では長らく幻の演奏家扱いされていた。1970年代~1980年代にはレコードが廃盤で入手不能が続く一方、海外情報や音楽教育分野には関心が乏しかった音楽愛好家や中古レコード業界が作り出した神話だったのかも知れない。
「幻」扱いされたためかは不明だが、エルリほど日本での評価が極端に分かれる人もいないようだ。技術的な正確さや楽曲の正しい表現を重視する立場の専門家からは粗雑で緻密さに欠ける演奏と評される一方、立場の異なる評論家や愛好家からは自由奔放で情熱的、即興的なセンスの良さを評価されている。評価の揺れは、1956年の初来日時も同様だったらしく、フランス的ニュアンスに富んだ演奏ではなく、「(当時の)現代的にバリバリと技巧的に弾くスタイル」(レコード芸術誌)と評されたが、おそらく当時の日本で評価が高かったハイフェッツやオイストラフ、さらには往年のクライスラーやティボーらとも異なる演奏スタイルであるため、どのように評価すべきか戸惑いが感じられる。おそらく違和感を覚えながらもロン=ティボー国際音楽コンクール優勝者という経歴から、権威に弱かった当時の批評家としては、低評価したくともしずらい状況だったのだろう。様々な演奏スタイルが並立する現在、ようやくエルリの演奏を正しく認識出来るようになったと言えるかも知れない。
エルリは上記ディスクの作品のうち、ウェーベルンのヴァイオリンとピアノのための4つの小品を1980年にライブ録音していたが、その他の作品は、上記ディスクが唯一の録音と思われる。
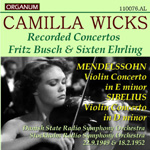
●カミラ・ウィックス メンデルスゾーン、シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ライブ&キャピトル・スタジオ録音
オルガヌム110076AL
メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲ホ短調 作品64
シベリウス ヴァイオリン協奏曲ニ短調 作品47
カミラ・ウィックス(ヴァイオリン)
フリッツ・ブッシュ指揮デンマーク国立放送交響楽団
シクステン・エールリンク指揮ストックホルム放送交響楽団
1949年9月22日、コペンハーゲン・デンマーク放送コンサートホール
1952年2月18日、ストックホルム・王立音楽院ホール
モノラル・ライブ&米キャピトルLP復刻
※メンデルスゾーンはアセテート盤に収録された放送ライブ。録音年代を考えれば音質良好。1949年と言えばヨーロッパの放送局ではテープ録音が導入され始めた時期だが、イタリアやスイスの放送局などで行われていたように、テープに録音して放送した後、録音テープを消去して再使用するため、保存用にアセテート盤にダビングしたものかも知れない。ややくすんだ音質でもう少しクリアに響くと申し分ないのだが、ディスク由来のスクラッチノイズは非常に低く、ソロヴァイオリンは明確に捉えられているので、十分鑑賞に堪える状態。CD化に際しては、オリジナル音源そのままではなく、ノイズ低減や音質改善等を行っている。
シベリウスは有名な米キャピトル録音。使用したLPの番号が記載されているが、スクラッチノイズが皆無で良質な復刻。キャピトルはLP初期からハイファイ録音で知られており、音質は良好。
カミラ・ウィックスは1951年に結婚後、両親の出身国ノルウェーに移住しているが(後年米国に戻った)、それ以前から北欧各国に客演することも多く、メンデルスゾーンはその際の録音である。聴衆を入れたライブであるが会場ノイズはほとんど聞こえない。戦後の録音が少ないフリッツ・ブッシュの貴重な記録でもある。
シベリウスは1952年録音であるから、ウィックスのノルウェー移住後ということになる。ウィックスの証言では、リハーサルを行う時間がほとんど持てない中で行われたと言われるが、得意の曲目で、同曲をプログラムに組み込んだコンサートツアーを終えた直後でもあったため、ツアーにも同行した指揮のエールリンクとのコンビネーションも問題なく録音が行われたという。
当時の米国レコード会社によるヨーロッパ出張録音は、ウェストミンスター・レーベルなどでは、簡単な音出しでマイクセッティングを完了後、リハーサルなしにいきなり録音開始、録音後はプレイバックによる演奏家の承認も省略し、ギャラを現金(終戦直後は食料現物)で支払って終了という、ライブ一発録りと変わらないような荒っぽい録音さえ行われていたから、上記のエピソードは事実だろう。
ウィックスは、メンデルスゾーンの協奏曲のスタジオ録音を残さず、上記ライブが現在確認されている唯一の録音。シベリウスの協奏曲も上記キャピトル録音が唯一の確認されている録音である。
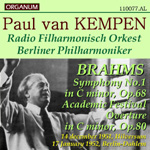
●パウル・ファン・ケンペン ブラームス交響曲第1番ほか オランダ放送フィル 1951年放送ライブ
オルガヌム110077AL
ブラームス 交響曲 第1番ハ短調作品68
大学祝典序曲
パウル・ファン・ケンペン指揮
オランダ放送フィルハーモニー管弦楽団、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
1951年12月14日、ヒルヴェルサム・オランダ放送スタジオ
1952年1月17日、ベルリン・イエス・キリスト教会
モノラル・放送ライブ&ドイツ・グラモフォンLP復刻
※交響曲は聴衆を入れずに行われた放送のための録音。アセテート盤による録音であり、同年代のテープによる録音には及ばないものの十分鑑賞に堪えるレベル。スクラッチノイズも極小。大学祝典序曲はDGGの10インチLPからの復刻で、こちらもスクラッチノイズは皆無で良好な状態。
ベートーヴェンなどドイツ音楽を得意としたケンペンは、ブラームスの管弦楽曲や協奏曲は録音しているものの、なぜか交響曲の録音を残していなかったため、注目すべき演奏と言える。おそらく初CD化。
ケンペンは1949年から1955年に亡くなるまでオランダ放送フィルの首席を務めており、交響曲は就任2年目の録音。当時の同フィルは設立4年目だったが、ケンペンの優れた指導により急速に実力を向上させ、当盤では、若干の瑕疵はあるものの堂々たる演奏を披露している。
ケンペンは1932年にドイツ国籍を取得し、1933年に指揮者としてデビュー後はドイツを中心に活動し、第二次世界大戦中にドイツ軍の慰問演奏会を行ったことから、戦後、ナチスへの協力の疑いを持たれた(その後疑いは晴れた)。
ケンペンの実力を持ってすれば、コンセルトヘボウ管への客演を頻繁に行っても不思議でなかったが、このようなナチス政権とのかかわりが問題視され、オランダ復帰後の1951年1月27日(当録音の年だ)、コンセルトヘボウ管にベイヌムの代役として客演した際(曲目はヴェルディ「レクイエム」)、ケンペンが登場した途端に聴衆から激しいヤジや怒号が飛び、当日の演奏会は何とか終えたものの、翌28日は楽員62名が出演を拒否し、演奏会は中止となった。蘭フィリップスへのレコーディングでは、その後もケンペンとコンセルトヘボウ管の共演が続けられたが、演奏会への登場が一度限りとなったことは残念なことであった。
このようなケンペンにとって、聴衆を入れずに演奏可能な放送オーケストラの指揮が出来たことは幸いであった。また、オランダ放送や政府もナチスへの関与の嫌疑がないことと、その実力を認めていた証でもあろう。
ケンペンは上記ディスク以外にブラームスの交響曲の録音を残しておらず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音。大学祝典序曲も上記DGG録音が唯一と思われる。
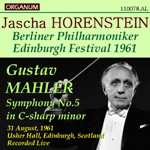
●ホーレンシュタイン/ベルリン・フィル マーラー 交響曲第5番、1961年ライブ
オルガヌム110078AL
マーラー 交響曲第5番
ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
1961年8月31日、エジンバラ・アッシャー・ホール
ライブ、モノラル
※スコットランドのエジンバラ音楽祭におけるライブ。BBCによる中継放送が行われており、マイクセッティングなどはプロの手によるものであるが、オリジナルテープが失われたらしく、従来は音質に難のあるエアチェック録音しか存在しなかった。しかし最近になって、多少は良好な音源が発見されたため、これを元にディスク化することとした。
とはいうものの、弱音はテープノイズに埋もれ、強音は荒れ気味で、高音はヒステリック、低音はブーミーという、古いライブ録音に見られる問題点が数多くあったため、マスタリングで改善を図った結果、ようやく鑑賞に堪える音質となった。幸いなことに欠落や大きなノイズなど重大な破綻はない。同一音源を元とした海外既出盤などでは、さらにイコライジングを積極的に行い、残響を付加した例も見られるが、ホーレンシュタインの演奏意図に反するおそれもあるため、当CDでは、修正は鑑賞に支障のある場合に限定している。
ホーレンシュタインは、巨匠指揮者の一人に数えられているものの来日せず、キャリア後半は特定のオーケストラの常任などを務めず、またレコーディングが体系的に行われず、複数以上のレコード会社に分散したことなどから、日本では根強い支持者がいるもののやや地味な存在である。また、旧ロシア帝国(現ウクライナ)のキエフ出身で名前もロシア系指揮者というイメージが強い一方、レパートリーの中心が特にロシア系作品ではないことも影響しているかも知れない。
実際のホーレンシュタインは、8歳で家族とともにロシアを離れ、1911年からウィーン・アカデミーで音楽教育を受け、1920年にベルリン・フィルでフルトヴェングラーの助手となり、1928年にはデュッセルドルフ歌劇場の首席指揮者を務めるなど、その経歴は、伝統的な独墺系指揮者の典型である。その後、ユダヤ系であることからナチスを逃れてアメリカに亡命することになるが、これらはワルターやクレンペラーなどの経歴と重なる。
ホーレンシュタインは、1928年にブルックナーの交響曲第7番をレコーディング(史上2番目)、1927年にベルリン・フィルとマーラーの5番を演奏会で取り上げており、早くからブルックナーとマーラーのスペシャリスト(本人も自称した)として知られた。
1961年のエジンバラ音楽祭にはベルリン・フィルが出演。8月25日と26日はカラヤン、28日はルドルフ・ケンペ、30日と31日にはホーレンシュタインが指揮した。31日のプログラムは、前半にヤナーチェクの「タラス・ブーリバ」、後半にマーラーの交響曲第5番が演奏された。当初、この両日はラファエル・クーベリックが予定されていたと言われるが、ヤナーチェクとマーラーという組み合わせは、いかにもクーベリックらしい曲目で、ホーレンシュタインはプログラムをそのまま引き継いだのだろう。
マーラーをレパートリーにする以前のカラヤンが首席指揮者を務めていた当時のベルリン・フィルにとって、マーラーの交響曲はほとんど未知のレパートリーであったといわれるが、頻度は少ないものの、客演指揮者によって時々は取り上げられていたようだ。エジンバラ音楽祭におけるホーレンシュタインの演奏もその一例であり、定期演奏会ではない国外の音楽祭に不慣れなプログラムを組むことはあり得ないから、オーケストラ側もそれなりの実績と自信を持っていたようで、不自然な箇所を感じさせない確固たる演奏となっている。ホーレンシュタインも、客演という限られた時間内に指揮者独自の個性を刻印している点で、キャリアの後半をフリーランスで活動した老巧さが感じられる。
ホーレンシュタインはマーラーの交響曲第5番のスタジオ録音を残さず、上記ディスクのほか、1969年イエーテボリ響のライブ(未CD化)が残されている。

●ホーレンシュタイン/ウィーン響 マーラー 交響曲第9番、1960年ライブほか
オルガヌム110079AL
マーラー 交響曲第9番
シュレーカー あるドラマへの前奏曲
ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮ウィーン交響楽団、BBC交響楽団
1960年6月22日、ウィーン・コンツェルトハウス
1957年11月16日、ロンドン・BBCメイダ・ヴェール・スタジオ
ライブ/放送スタジオ・ライブ、モノラル
※2枚組。マーラーはウィーン芸術週間におけるライブ、シュレーカーはBBC放送スタジオにおける放送録音。マーラーは、特に優秀というわけではないが安定した音質でバランスも良く、1960年当時の録音水準を上回る。ただし、テープの一部劣化によるドロップアウトが散見されたため、こちらは鑑賞の妨げとならないように補修してある。一方、シュレーカーのオリジナル音源は、使用した録音機材が旧式だったためかは不明だが、スタジオにおける放送録音という割には少々古く、1950年代前半といったレベル。このためイコライジング等により見通しを良くし、高域を補正、ダイナミックレンジを広げるなどの音質改善を図った結果、鑑賞に堪える状態となった。
ホーレンシュタインは、巨匠指揮者の一人に数えられているものの来日せず、キャリア後半は特定のオーケストラの常任などを務めず、またレコーディングが体系的に行われず、複数以上のレコード会社に分散したことなどから、日本では根強い支持者がいるもののやや地味な存在である。また、旧ロシア帝国(現ウクライナ)のキエフ出身で名前もロシア系指揮者というイメージが強い一方、レパートリーの中心が特にロシア系作品ではないことも影響しているかも知れない。
実際のホーレンシュタインは、8歳で家族とともにロシアを離れ、1911年からウィーン・アカデミーで音楽教育を受け、1920年にベルリン・フィルでフルトヴェングラーの助手となり、1928年にはデュッセルドルフ歌劇場の首席指揮者を務めるなど、その経歴は、伝統的な独墺系指揮者の典型である。その後、ユダヤ系であることからナチスを逃れてアメリカに亡命することになるが、これらはワルターやクレンペラーなどの経歴と重なる。
ホーレンシュタインは、1928年にブルックナーの交響曲第7番をレコーディング(史上2番目)、1927年にベルリン・フィルとマーラーの5番を演奏会で取り上げており、早くからブルックナーとマーラーのスペシャリスト(本人も自称した)として知られた。
1960年のウィーン芸術週間ではマーラー生誕百年記念祭が行われ、ホーレンシュタインによるマーラーの交響曲第9番のほか、ブルーノ・ワルターによる第4番、カイルベルトによる第8番、カラヤンによる「大地の歌」が演奏され、また、シューリヒト/ウィーン・フィルによるブルックナー交響曲第9番、クレンペラー/フィルハーモニア管によるベートーヴェン交響曲全曲演奏も行われ、当時の豊かな音楽事情を伺い知ることが出来る。一方でウィーン響は、6月19日に第8番、22日に当ディスクに聴く第9番を演奏するというハードワークだった。
ホーレンシュタインとウィーン響は、LP初期に米ヴォックスにブルックナーの交響曲第8番や9番、マーラーの交響曲9番などを録音していたが(レコードではウィーン・プロ・ムジカ管と表記)、欧米における評価は、オーケストラの貧弱さ・非力さに対する批判が多かった。しかし、この録音で聴く限り、パワフルというわけではないが決して非力な印象はなく、充実した演奏を繰り広げている。批判は米ヴォックスの貧しい録音によるものか、または1948年から1960年までカラヤンが音楽監督を務めており、オーケストラが実力を向上させたことが関係しているかも知れない。
一方、シュレーカーはホーレンシュタインならではのレパートリー。シュレーカーは近年再評価されつつあるが、ナチス政権によって「退廃音楽」として排斥され、作曲家自身が1934年に亡くなったこともあり、当演奏が録音された1950年代当時は忘れられた存在であった。ホーレンシュタインはウィーン・アカデミーでシュレーカーから作曲指導を受けており、マーラー以降の重要な作曲家として関心を持ち続けていたのだろう。
ホーレンシュタインは、マーラーの交響曲第9番を上記録音のほか、前述のように1952年米ヴォックスにウィーン響とスタジオ録音したほか、1966年4月と9月にロンドン響、1967年フランス国立放送管、1969年ロンドン響、1969年アメリカ響とライブ録音していた。

●クナッパーツブッシュ/ミュンヘン・フィル ブルックナー交響曲第8番 1963年ライブほか
オルガヌム110080AL
ブルックナー 交響曲第8番(1892年シャルク改訂版)
R・シュトラウス 交響詩「死と変容」
ハンス・クナッパーツブッシュ指揮
ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団、シュターツカペレ・ドレスデン
1963年1月24日、ミュンヘン・ヘルクレス・ザール
1959年11月28日、ドレスデン・州立劇場
ライブ、モノラル
※2枚組。22曲ともモノラルながら優秀録音で、録音年代の水準を上回り、安心して音楽を鑑賞できるレベル。ブルックナーは特に音質良好で、おそらくオリジナルに近いと思われる音源からのディスク化。シュトラウスは、ブルックナーとは会場の音響特性が異なるものの、音楽を問題なく楽しめるレベル。ゼンパーオーパーが第二次世界大戦中の連合軍による空襲で焼失後、ドレスデン歌劇場を仮小屋として州立劇場で公演を続けていた時代の記録である。こちらも会場ノイズは極小。。
1963年1月、クナッパーツブッシュは6日にミュンヘン・フィルとコンサート、9日と14日にミュンヘン(バイエルン)国立歌劇場でオペラ公演の後、23日と24日の2日、再びミュンヘン・フィルを指揮、当ディスクに聴くブルックナーを演奏した。公演前後(直後?)に、米ウェストミンスター・レーベルに同曲を録音しており、レコーディングのリハーサルを兼ねたコンサートであった。レコーディングと当盤の演奏は当然酷似しているが、ウェストミンスター録音はステレオとは言え、当時一部で流行した残響を排したドライな音質であるのに対して、当録音はライブ録音ながら、自然な潤いのある音質がブルックナーにふさわしい。クナッパーツブッシュにとっては、同曲の最後の演奏機会となった。
R・シュトラウスは、1959年11月末、なぜか1公演だけのためにドレスデンに客演した際の録音。当日は、ハイドン交響曲第88番、R・シュトラウス「死と変容」、ブラームス交響曲第2番というプログラム。クナッパーツブッシュは11月14日から22日まで、ベルリン国立歌劇場で「ニーベルングの指輪」全曲を指揮しており、そのままドレスデンに移動したのだろう。当時クナッパーツブッシュは71歳前後だったが、まだまだ活発に演奏活動を行っていた。
R・シュトラウス自身は、スカートという19世紀後半ドイツで大流行したカードゲームを好み、クナッパーツブッシュも相手をしたが、シュトラウスのことを「豚のような奴だった」と罵っている。シュトラウスは、作曲や演奏収入を妻のパウリーネに管理されていたため、賭けゲームで自身の小遣い稼ぎをしていたらしく、金に汚いことから、トスカニーニも「作曲家としてのシュトラウスには帽子を取るが、人としてのシュトラウスには何度も帽子を被る」と語っている。同僚や世代の近い者からの評判は今ひとつだったようだが、クナッパーツブッシュは罵りながら、当演奏の後も「死と変容」を1962年と1964年の2回、最晩年まで演奏会で取り上げており、作品自体は評価していたようだ。
クナッパーツブッシュは、当ディスクの演奏のほかに、上記のように1963年米ウェストミンスターにミュンヘン・フィルをスタジオ録音したほか、1951年ベルリン・フィル、1955年バイエルン国立管、1961年ウィーン・フィルとライブ録音していた。また「死と変容」を1956年英デッカにパリ音楽院管とスタジオ録音したほか、1962年ウィーン・フィル、1964年ミュンヘン・フィルとライブ録音していた。
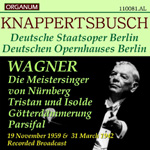
●クナッパーツブッシュ/シュターツカペレ・ベルリンほか ワーグナー名曲集 1959年・1942年放送ライブ
オルガヌム110081AL
ワーグナー
ニュルンベルクのマイスタージンガー 第1幕への前奏曲
トリスタンとイゾルデ 第1幕への前奏曲と愛の死
神々の黄昏 ジークフリートのラインへの旅
神々の黄昏 ジークフリートの死と葬送行進曲
パルシファル 第1幕への前奏曲
パルシファル 第3幕への前奏曲
ハンス・クナッパーツブッシュ指揮
シュターツカペレ・ベルリン、ベルリン・ドイツ歌劇場管
1959年11月19日、1942年3月31日
放送スタジオライブ、モノラル
※パルシファルの2つの前奏曲のみ1942年ベルリン・ドイツ歌劇場管録音。1959年・1942年録音ともに音質優秀で当時の平均を上回る。両者とも聴衆を入れずに行われた放送のための録音で、マイクセッティング等の制約もなく、好条件の下に録音されたものと思われる。ただし1959年録音の既出盤は、低域が弱く、高音にピークがあるなどやや腰高な印象。一方、当ディスクの音源は低音が厚く豊かで、クナッパーツブッシュらしい堂々たる演奏が再現されている。おそらく当盤の方がオリジナルに近いのではないか。一方、1942年録音は、旧ドイツ帝国放送による初期のテープ録音。マグネトフォンと呼ばれるAEG社製レコーダーによると思われるが、特に第1幕への前奏曲は優秀で、第二次世界大戦後1950年代の録音に匹敵する。同時に録音された第3幕への前奏曲はなぜかやや古く感じるが、おそらくテープの保存状態の差によるものだろう。
クナッパーツブッシュは1959年11月14日から22日まで、ベルリン国立歌劇場で「ニーベルングの指輪」全曲を指揮した。14日「ラインの黄金」、16日「ワルキューレ」、18日「ジークフリート」、22日「神々の黄昏」というスケジュールで、上記ワーグナー録音は上演期間中の19日に行われた。録音会場は不明だが、上演の合間で、楽器の輸送などの手間を考えると、「指輪」公演と同じくベルリン国立歌劇場で録音された可能性が高い。
一方、1942年録音は、ラジオ放送用に収録されたパルシファル第3幕全曲の一部で、オペラ全曲に連結する第3幕への前奏曲はもちろんのこと、第1幕への前奏曲も演奏会用のコーダが付属せず、唐突に終結する。第3幕のみの録音であるにもかかわらず、第1幕への前奏曲が単独で録音されているのは不自然だが、放送のオープニングテーマなどに使用するためだったかも知れない。フェイドアウトして使うことを前提とすればコーダがないことも理解できる。録音会場は不明だが、ベルリン・ドイツ歌劇場管の本拠地ドイツ歌劇場ではなく、おそらくベルリンの帝国放送局内のスタジオ(Haus
des Rundfunks)であろう。
スタジオ録音やライブ録音を問わず、クナッパーツブッシュはこれらワーグナーの管弦楽抜粋等を数多く録音しているが、当ディスクは、ウィーン・フィルによるスタジオ録音を除けば、ワーグナー作品の上演に精通した歌劇場のオーケストラを起用した録音として、そして音質・演奏ともに最も充実したものとして貴重な存在である。
ちなみにオーケストラ名は、当解説ではそれぞれシュターツカペレ・ベルリン、ベルリン・ドイツ歌劇場管と表記しているが、前者については、歌劇上演ではジャケット表記にあるようにベルリン・ドイツ国立歌劇場管、オーケストラ単独の公演の場合はシュターツカペレ・ベルリン(ベルリン国立管)となり、当ディスクのように歌劇上演の間に上演作品の抜粋をおそらく歌劇場内で演奏・録音した場合はやや複雑となる。ちなみにベルリン・ドイツ歌劇場は、後のベルリン・ドイツ・オペラと同一団体だが、原語表記では前者はDeutsches
Opernhaus、後者はDeutsche Oper Berlinとなり、こちらも微妙に異なる。
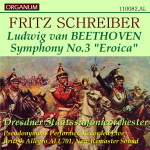
●フリッツ・シュライバー? ベートーヴェン 交響曲第3番「エロイカ」ライブ
オルガヌム110082AL
ベートーヴェン 交響曲第3番「エロイカ」
フリッツ・シュライバー?指揮
ドレスデン国立管弦楽団?
英アレグロLP ALL701から復刻
1940年代中盤~1950年頃録音
ライブ、モノラル
かつてフルトヴェングラーによる指揮ではないかと噂された有名な(悪名高い?)LPからの復刻。指揮者は偽名。オーケストラは実在するが、おそらく実際の演奏は異なる団体。以前からしばしばCD-R化されてきているが、従来はLPの忠実な復刻というレベルに留まっていた。当ディスクでは、LP化される以前のオリジナルの録音・演奏を追求するべく、音質を改善して復刻した。
英アレグロ(Allegro)のオリジナルLPは中低域過剰でヌケが悪く、中高域にディップ(周波数の落ち込み)があるなど、バランスが悪かったため、イコライジングで修正し、LPのサーフェイス・ノイズを軽く除去した結果。熱演であることに変わりはないが、ややすっきりと見通しの良い印象に変化。フルトヴェングラーと見なされたようなデモーニッシュなイメージはやや後退し、個性的・積極的ではありつつも。良い意味での常識的な範囲の名演となった。
最近判明した新事実によれば、今まで英アレグロ盤のオリジナルは米アレグロ3113(1954年初出)と言われていたが、1951年に米アレグロの前身レーベルであるロイヤル(Royale)から、1218という番号でFranz
R.Friedl指揮Berlin Symphony
Orchestraによる演奏として発売されており(指揮者名はこちらも偽名)、各楽章の会場ノイズが一致することから、英アレグロ=ロイヤル(=米アレグロ)が同一演奏であることが分かった。
これにより、英アレグロは初出の米アレグロ盤と同一演奏ではないという説は否定され、また、一部中古盤ショップが主張したシルヴェストリ指揮ベルリン・フィル(1960年録音)による演奏という説も併せて否定された。
ところでロイヤル1218盤の演奏は、英アレグロ盤と比較するとかなり印象が異なる。1950年代初頭、LP初期のアメリカでは、コロンビアやRCAなど大手レコード会社の以外にも中小のレコードプレス会社が数多くあり、技術水準にもばらつきがあったとされる。廉価盤として販売されたロイヤル盤も一流とはいえない会社によって製造されたと思われ、製盤技術の低さをカバーするため(=針飛びを防ぐため)ダイナミックレンジを抑え、低域をカットした中高域中心のナローレンジな音作りとなっている。低域が控えめなせいもあり、優れた演奏ではあるが、英アレグロ盤よりも軽量級の印象。また、レコードの材質が悪くノイズやひずみが多いためか、余裕のないヒステリックな演奏として聞こえ、演奏の印象を悪くしている。
これに対して英アレグロ盤は、LP製造技術が安定期に入った1964年の発売だけに盤質は一定水準を保っており、マスターテープの情報を十分に伝えていると思われる。ただし、英アレグロ盤の特徴的といえる過剰な低域がオリジナルマスターによるものか、英アレグロがイコライジングで「演出」したものかは不明だが、オリジナルマスターの録音の古さを補うため、敢えて補正(演出)を行った可能性が高い。
米ロイヤル/アレグロ盤発売当時は、アメリカの多くのマイナーレコード会社が競ってドイツなどの放送局から録音テープを買い付ける一方、演奏家による権利の許諾を逃れるために架空の演奏家名を付けたLPを発売していた。米ロイヤル/アレグロ盤も、発売されたほぼすべてが偽名の演奏家によるものだが、アメリカの研究者Ernst
A. Lumpeによって、多くの盤の実際の演奏家が特定され、大半が第二次世界大戦中から戦後にかけてのドイツの放送局由来の音源であることが判明している。
先の演出過剰が推測されるとはいえ、かなり優れた指揮者による演奏であることになる。1940年代半ば~1950年頃にドイツで活動した指揮者は数多い一方、有能でも正式なレコード録音を行わなかった者も多く、ドイツの放送局から英アレグロ盤と同一演奏の音源が発見されない限り、演奏家の特定は困難である。
現時点でほぼ推定できることは、第二次世界大戦中~1950年初頭までの放送局によるライブ録音。オーケストラは不明だが、ドイツ各地の団体であることは確実。指揮者は二流ではなく、ライブでは時に豹変する熱演タイプ(アーベントロート、若き日のチェリビダッケ、シェルヘン、ベーム?など・・・・)といったところであろうか。

●マタチッチ 音質良好ステレオ・ライブ ベートーヴェン「田園」ナポリ・スカルラッティ管
オルガヌム110083AL
ベートーヴェン 交響曲第6番「田園」、エグモント序曲
ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮ナポリ・イタリア放送スカルラッティ管弦楽団
1962年2月13日(田園)、1961年1月4日(エグモント序曲)
ナポリ音楽院大ホール
ライブ、ステレオ/モノラル
「田園」はステレオ、エグモント序曲はモノラル。いずれもライブ録音だが音質は良好。特にステレオの「田園」は優秀。音はつややかでステレオの分離も良好。バランスも申し分なく会場ノイズもほぼ皆無。エグモントもモノラルながら鑑賞に全く問題ないレベル。こちらも会場ノイズはほぼ皆無。イタリア放送では、ラジオ番組収録の際の聴衆には「風邪を引いていないこと、咳をしないこと」を条件に観覧させていたと言われ、当演奏でも楽章間で咳払いをする聴衆に周囲の者が「シーッ」と注意している。イタリアのオペラハウスでもよく見かける光景だ。
一般にイタリア放送(RAI)の録音は、ミケランジェリの協奏曲ライブ録音などに聴くように、レンジの狭い貧相でひからびた音質か、リミッターをかけすぎたり、管弦楽各セクションのマイクバランスが悪いものが少なくない。声楽は意外に良好であることが多く、やはりオペラの国でオーケストラの国ではないのだろう。特にナポリのスカルラッティ管の放送録音は問題が多いが、当CDに聴くマタチッチの録音は奇跡的ともいえる優秀録音。スカルラッティ管は小編成の室内管弦楽団で、会場のナポリ音楽院は大ホールとは言うもののステージは狭く、演奏者は50~60人程度と思われるが、マタチッチの演奏を聴く限り少人数であることのハンディキャップは感じられず、十分な音量を保ち、充実した演奏を繰り広げている。モノラルのエグモント序曲は「田園」よりもさらに重厚な演奏を行っており、マタチッチのマジックかもしれない。イタリア放送はステレオ録音の導入が早く、1960年頃のミラノから始まり、ナポリでは1961年頃から稼働し始めたと思われ、当CDの2曲はその移行期に当たるが、ステレオ導入当初の「田園」でも、すでにステレオ用マイクセッティングは確立されていたようだ。ただし、「田園」の原テープは(おそらく)コピーの際に誤って左右チャンネルを逆に記録しており修正。また、セッティングがオンマイク過ぎるため、各セクションがブレンドするように若干距離を空ける調整を行っている。エグモント序曲は、劇音楽全曲演奏からの抜粋である。
マタチッチは当時61~62歳の働き盛り。1950年代後半からドレスデンやベルリンなど東独の歌劇場にしばしば客演を行い、1959年にはバイロイトで「ローエングリン」を指揮、1961年にはフランクフルト歌劇場の首席指揮者に就任、同年ローマ歌劇場でワーグナー「リング」を指揮するなど、充実した活動を行っていた。イタリア各地の放送オケへの客演も頻繁に行われ、ナポリにおける当演奏もその一環であろう。後年のようなスケールの巨大さはないものの、決して一流とはいえないスカルラッティ管の弱点を巧みにカバーし(ホルンがいささか頼りないが)、上質なオケであるかのように変身させ、マタチッチ独自の刻印を押した演奏を行っている。
マタチッチは「田園」を1967年NHK交響楽団、1982年ローザンヌ室内管弦楽団とライブ録音していたが、「エグモント序曲」は当CDが唯一の録音と思われる。
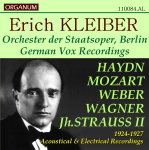
●エーリヒ・クライバー ドイツ・フォックス録音集1924-1927
オルガヌム110084AL
CD1
ハイドン 交響曲第100番「軍隊」
モーツァルト 管楽セレナーデ第11番
CD2
ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」第1幕序曲、第3幕序曲
ワーグナー 歌劇「タンホイザー」序曲、楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲
ヨハン・シュトラウス2世 ワルツ「美しき青きドナウ」
エーリヒ・クライバー指揮ベルリン国立歌劇場管弦楽団、ベルリン国立歌劇場管弦楽団管楽八重奏団(M.Balnemones、O.Brandt、L.Kohl、P.Rembt、L.Scherwein、G.Schreiber、A.Stengl、
G.Zell)
1927年8月(ハイドン)、1924年12月(モーツァルト)、1926年7月(ウェーバー)、1927年4月(タンホイザー)、1926年1月(マイスタージンガー)、1925年5~7月(シュトラウス)、ベルリン
モノラル
CD-R2枚組。カルロス・クライバーの父、エーリヒの初期録音集。78回転SP(シェラック盤)からの復刻。マイクロフォンを使用したいわゆる電気式録音は1925年頃に実用化されたが、当CDにはそれ以前の録音方式であるアコースティック(ラッパ)録音も含み、1924年のモーツァルト、1925年のシュトラウスがそれに当たる。
独フォックスは1921年から1929年まで存続したレコード・レーベル。クラシックからポピュラーまで幅広く録音を行ったが、小規模で経営は不安定だったらしく世界恐慌発生以前に破産し活動を停止してしまった。VOXとはラテン語で声・音の意味で、第二次世界大戦後、アメリカで設立された同名のレーベルとは無関係である。
同社は、一説には1924年に世界初の電気式録音レコードを発売したとも言われているが、当CDのモーツァルトなどは該当しないと思われる。また電気式録音といっても米ウェスタンエレクトリックが開発した、今日でも一般的なマイクロフォンによるシステムではなく、同時期に米ブランズウィックが開発した「ライト・レイ」方式と思われる(音の変化を光源が捉え、音による光の揺らぎ?を音溝に記録する。フルトヴェングラーの第1回録音の「運命」もこのシステムが使用された)。
1920年代当時のメジャーレーベルHMVやコロンビア、同じドイツのポリドールなどと比較すると、同社の録音技術水準や、今日残っている限りのシェラック盤の質は良好とは言い難く、CD復刻は困難を極めた。電気式録音初期のウェーバーとワーグナーの4曲はサーフェイス(スクラッチ)ノイズが多く、強音で音割れやひずみが発生する上、バランスが悪く低音不足という貧弱な音質。ノイズ処理とイコライジングによる補正を入念に行った結果、一応はクライバーの演奏意図は聴き取れるレベルとなった。一方、アコースティック録音のモーツァルトとシュトラウスは、旧方式の限界はあるが技術的に安定期にあり、悪い(古い)ながらも安心して音楽を楽しめる。モーツァルトは弦を伴わない管楽器のアンサンブルというアコースティック録音向きの編成であることも有利に働いている。シュトラウスも予想外によく録れている。ハイドンについては、他の録音とは一線を画す良好な音質。といっても1927年としてはやや物足りないが、同年4月のタンホイザー録音後、7月のハイドン録音までの間に新たな録音機材が導入されたものと思われ、ようやく当時の録音水準の末席に追いついた感がある。なお、シェラック盤4面に収めるためか、残念ながら第1楽章の序奏部がカットされ主部から開始されている。SP時代にしばしば行われた悪癖である。モーツァルト、シュトラウス、ハイドンはいずれもサーフェイスノイズが盛大だったため、鑑賞の妨げにならない程度に軽減した。
エーリヒ・クライバーは、録音当時30歳代の若さでベルリン国立歌劇場の音楽監督の地位にあり、ベルリン・フィルの常任指揮者フルトヴェングラーと並ぶベルリン音楽界を代表する存在であった。ちなみに当時ブルーノ・ワルターは格下の市立歌劇場音楽監督、クレンペラーは国立歌劇場の第二歌劇場ともいえるクロール劇場の音楽監督に過ぎず、クライバーの名声の高さがうかがわれる。
1923年から27年の間、クライバーとベルリン国立歌劇場管はフォックス・レーベルにシェラック盤50面(25枚)ほどの録音を残したが、LPやCDに復刻されたものは少ない。録音技術の低さ、盤質の悪さなど、現代の鑑賞に堪える商品としては問題が多いからであろう。また、(フォックスとの契約終了後?)1927年からはポリドール(ドイツ・グラモフォン)とのレコーディングが開始され、良好な音質の録音が残されたこともある。しかし、フォックスには再録音されなかったレパートリーも多く含むため、当CDは貴重といえる。
ちなみにクライバーに師事した近衛秀麿は、1935年新交響楽団と日本コロムビアに「青きドナウ」を録音した際、見学していた野村あらえびすに、緩やかなテンポについて「どうです。クライバーに似てるでしょう?」と語ったという。近衛はフォックス盤を購入して参考にしたとのことだが、当CDの同曲がそれに当たる。
クライバーは1931年、「青きドナウ」をベルリン・フィルと独テレフンケンにスタジオ録音したが、それ以外の当CDの曲目は唯一の録音である。

●ムラヴィンスキー/チェコ・フィル ライブ チャイコフスキー 交響曲第4番ほか
オルガヌム110085AL
チャイコフスキー 交響曲第4番
ベートーヴェン 交響曲第4番
エフゲニー・ムラヴィンスキー指揮チェコ・フィルハーモニー管弦楽団
レニングラード・フィルハーモニー交響楽団
1957年6月3日、1955年6月3日、プラハ・スメタナ・ホール
モノラル ライブ
※2曲とも「プラハの春」音楽祭におけるライブ。放送局由来と思われる音源であるためか、2曲とも年代の水準を超える良好な音質。2年古い1955年のベートーヴェンの方がより良好に感じるが、マイクセッティングの相違により残響がやや多めに入っているからであろう。いずれにしても鑑賞には全く問題ないレベル。会場ノイズもほとんどない。
ムラヴィンスキーは、1946年以降6回にわたって「プラハの春音楽祭」で公演を行ったが、当然ながら大半はレニングラード・フィルと同行しており。チェコ・フィルとのチャイコフスキーの録音は、ロシア(当時はソ連)以外のオーケストラを指揮した希少な例。ムラヴィンスキーは1946年、1947年と当ディスクの1957年にチェコ・フィルと共演しており、おそらくムラヴィンスキーが振った唯一の外国オーケストラと思われる。
1957年のプログラムは、5月30日に続く同一曲目の公演で、ムソルグスキーのホヴァンシチナ前奏曲、ダヴィード・オイストラフ独奏でショスタコーヴィチのヴァイオリン協奏曲第1番、休憩を挟んでチャイコフスキーというもの。チャイコフスキーの交響曲第4番については、ムラヴィンスキーは1950年代後半から同曲を自らのレパートリーから外しつつあり、この点でも貴重である。1955年は、前半にベートーヴェン、後半はショスタコーヴィチの交響曲第10番という典型的な「ムラヴィンスキー・プログラム」。
ちなみに1960年にムラヴィンスキーがドイツ・グラモフォン(DG)に同曲を含むチャイコフスキーの後期交響曲3曲をスタジオ録音した際、日本グラモフォン(ポリドール)による後期交響曲3曲LPセットの発売予告広告には「引き続き交響曲第1番~3番も録音予定」とうたわれており、DGには交響曲全集とする計画があったと思われる。しかし、上記のような事情があった第4番を録音させた上に、ムラヴィンスキー自身1940年代中期以降取り上げていない第1番~3番も録音させることは(そもそも第3番は演奏した記録がない)、当時のレコード会社(とソ連政府?)の強大な力を持ってしても不可能だったようだ。
ムラヴィンスキーは当ディスク以外に、チャイコフスキーの交響曲第4番を1957年露メロディアに、1960年DGにスタジオ録音していたほか、1959年にソビエト国立響とライブ録音していた(アウローラMK.30003として発売済み)。また、ベートーヴェンの交響曲第4番を1949年メロディアにスタジオ録音したほか、1972年、1973年4月、1973年5月にライブ録音していた。

●リュセット・デカーヴ 仏グラモフォンほかSP復刻
ファリャ「スペインの庭の夜」、シャブリエ、ドビュッシー、ラヴェルほか
オルガヌム110086AL
ファリャ 交響的印象「スペインの庭の夜」
シャブリエ 「気まぐれなブーレ」
ドビュッシー 「前奏曲集第2巻」から第12曲「花火」
ラヴェル 「水の戯れ」、組曲「鏡」から「道化師の朝の歌」
ピエルネ 演奏会用練習曲
リュセット・デカーヴ(ピアノ)
ウージェーヌ・ビゴー指揮パリ音楽院管弦楽団(ファリャ)
1939~1946年、パリ・アルベール・スタジオ
仏EMI(ディスク・グラモフォン、VSM)録音
モノラル
※フランスの名女流リュセット・デカーヴによる戦前・戦後期の78回転SP録音集。おそらく大半が初復刻と思われる。1939年録音のファリャはわずかにスクラッチノイズが残るが、低レベルでソフトな音質のノイズであるため鑑賞に支障はないだろう。ただ、オリジナル録音は、ピアノはクリアに録れているものの、管弦楽についてはやや不明瞭であまり優秀といえず、78回転のシェラック盤では、ファリャの印象主義的で微妙な音色を収録するには限界があったようだ。一方、シャブリエほかのピアノ独奏曲はほとんどノイズレスで、当時としては優秀録音といえる。第二次世界大戦を挟んだ時期でもあり、特に戦中や終戦直後はシェラックなどの原材料不足や品質低下があったと言われるが、さすがにメジャーレーベルの技術力と品質の高さを感じさせる。
なお、ファリャの「スペインの庭の夜」は、現代の日本では頻繁に演奏される作品ではないが、第二次世界大戦前後のフランスでは人気曲だったらしく、ハスキル、カサドシュ、ノヴァエス、ブランカール、レリア・グッソー、イヴォンヌ・ロリオなどパリ音楽院出身の多くのピアニストが録音を残している。ちなみに同作品の初レコーディングは1928年仏VSMによるアリーヌ・ヴァン・バレンツェン、ピエロ・コッポラ指揮盤らしく、次いで1929年スペイン・コロンビアによるエルネスト・アルフテル(ファリャの弟子)、マヌエル・ナバーロ指揮盤、デカーヴ盤はそれに次ぐ録音と思われる。
リュセット・デカーヴ(1906~1993)はパリ出身。芸術家との交流も多い家庭で育ち、パリ音楽院でマルグリット・ロンやイーヴ・ナットに師事。1923年にプルミエ・プリを獲得後は同音楽院で教育に携わり、数多くの著名演奏家を輩出した。また演奏家としては同時代の作品紹介に力を注ぎ、プロコフィエフのピアノ協奏曲第3番フランス初演、ジョリヴェのピアノ協奏曲(いわゆる赤道コンチェルト)世界初演など、多くの新作紹介を行った。
パリ音楽院出身の女流ピアニストということで、グラン・ダーム(grande
dame、貴婦人・名声のある女性の意)といわれるフランス系女流ピアニストの一人になぞらえられるが、当然ながら様々なタイプの者がおり、デカーヴは教育と同時代作品の紹介に活動の中心があった点で、敢えて言えばマルセル・メイエル(6人組の女神と言われた)やイヴォンヌ・ロリオ(メシアン夫人)に近い存在かもしれない。
レコーディングは多いとはいえないが、1920年代(10歳代半ば)に行ったヴァイオリン小品のピアノ伴奏がおそらく初録音と思われ、その後、LPモノラル期の1950年代半ばまで断続的に行った。ただし、室内楽・歌曲の伴奏や戦後まもなくフランス・デッカに録音したシューマン「子供の情景」、モーツァルト生誕200年記念として仏パテが企画した「パリのモーツァルト」に収めた変奏曲変ホ長調K.354を除けば、多くがフランス系の近現代作品が大半であることは、上記の演奏活動と同様だ。
同時代の作品の初演は過去の演奏例がないため、作曲家本人から助言が得られるとはいえ、作品の本質を的確に把握する能力が求められる。ファリャの作品についても1916年の初演から23年後の録音であり、現代に例えれば1990年代の作品ということになるが、1939年当時、デカーヴは今日の視点でも違和感のない演奏を行っていたことが分かる。
日本ではSP期に当ディスクのファリャ、LP初期にデュクレテ・トムソン原盤でジョリヴェのピアノ協奏曲が発売されていたが、ジョリヴェは初演時の賛否両論によって話題となったものの、演奏家には注目されずに終わり、その後は、エラート原盤によるラヴェルのピアノ三重奏曲が、デカーヴを聴くことができる唯一のLPであった。
近年では、一般に初版・初期プレス中古LPの評価が高まるにつれて、デカーヴが1950年代に仏ヴェルサイユ・レーベルに録音したルーセルやオネゲルのピアノ曲集が高価に取引されるなど、知名度も高まり再評価されつつある。
デカーヴは、上記ディスク以外に、ファリャの「スペインの庭の夜」を当録音の3か月前、1939年3月にも録音したが未発売に終わっている(原盤トラブルか演奏家による発売不承認だろう)。また、その他のピアノ作品はおそらく唯一の録音と思われる。
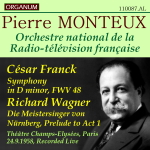
●モントゥー/フランス国立放送管ライブ
フランク 交響曲、ワーグナー マイスタージンガー前奏曲
オルガヌム110087AL
フランク 交響曲 ニ短調
ワーグナー ニュルンベルクのマイスタージンガー 第1幕への前奏曲
ピエール・モントゥー指揮フランス国立放送管弦楽団
1958年9月24日、パリ・シャンゼリゼ劇場
モノラル ライブ
※フランス国立放送によるライブ録音。フランクはモントゥーが数度のレコーディングを行った得意のレパートリーだが、当ディスクはフランスのオーケストラを指揮したおそらく唯一の録音である。既出の海外盤CDよりもオリジナルに近い音源を使用することで音質が向上し、より生々しく臨場感がある。ただし、ラジオ放送用にダイナミックレンジが圧縮されており、フォルティッシモが抑えられて弱音と強音の差が小さく、いささか迫力不足だったため、フランクではレベル拡大などの調整を行っている。一方、ワーグナーは、同じ日の演奏会であるからマイクセッティングに大きな違いはないと思われるが、フランクに比べてバランスが悪く、金管が突出気味で騒がしい一方、各セクション同士がブレンドせずにばらばらに鳴っている感があったため、イコライジングでバランスを取り直した結果、ようやくワーグナーらしい音楽が聴けるようになった。
一般に当時のフランス国立放送の録音スタイルとして、マイクが楽器に近く、解像度は高い反面、残響は少なめでドライな音質となる傾向がある。結果としてフランクやフォーレ、ドビュッシーなど自国作品の録音には適しているようだが、ワーグナーを始めとするドイツ系作品にはマスとしての響きが乏しく違和感がある。フランク本人は、ワーグナーなどドイツ音楽の影響が大きかったはずだが、作品自体はあくまでラテン的・フランス的であるということが、録音を通しても理解できるところが興味深い。
モントゥー自身はベートーヴェンやブラームス、ワーグナーを好んでおり、ドイツ的ともいえるオーソドックスな演奏を行っているはずだが、録音スタイルによってこれほどまでに印象が変わるという好例(悪例?)だ。
当日の演奏会は、マイスタージンガー前奏曲、フランクの交響曲、おそらく休憩を挟んでロベール・カサドシュ独奏でモーツァルトのピアノ協奏曲第24番、エルガー「エニグマ」変奏曲という、やや長めのプログラム。「エニグマ」はモントゥーお気に入りのレパートリーだが、当時のフランスではまだなじみが薄い作品だっただろう。
フランス出身のモントゥーだが、1935年のパリ交響楽団常任指揮者退任後は、生涯フランスのオーケストラにポジションを得ることはなかった。サンフランシスコ響音楽監督やコンセルトヘボウ第一指揮者の仕事が多忙な理由もあっただろうが、フランスでは多くのオーケストラの経営が不安定で楽員が固定せず(先のパリ交響楽団も経営難で活動停止した)、3回のリハーサルに3人の奏者が交代で参加するような慣習?(アルバイトに行っているのだ)も日常的で、1956年、モントゥーとパリ音楽院管弦楽団が英デッカにストラヴィンスキーの三大バレエをレコーディングした際も、録音終了後、モントゥーはデッカのプロデューサー・ジョン・カルショウに「次にレコーディングするときは、できればウィーンがロンドンのオーケストラにしていただきたい」と希望を述べたという。クリュイタンスやミュンシュであればフランスのオーケストラの現状に、鷹揚(いい加減?)に対応したかもしれないが、モントゥーは我慢がならなかったのだろう。
そのような状況の中でフランス国立放送管弦楽団は、モントゥーが唯一許容できるフランスのオーケストラだったようで、頻繁に客演を繰り返した。当時のパリでは、フランス国立放送管は、オペラ座管弦楽団を除けば唯一の公営オーケストラであり(パリ音楽院管弦楽団も音楽院楽友協会という半官半民のような不安定な団体が運営)、放送オーケストラという性格から、あらゆるレパートリーにも対応できる柔軟性も備えていたと思われる。ただし、指揮者陣にはアンゲルブレシュトやローザンタールほか、トニー・オーバン、モーリス・ル・ルーなどベテランから中堅・若手がひしめいており、さすがのモントゥーも割り込む余地が(その気も)なかったかもしれない。
モントゥーは上記録音のほかに、フランクの交響曲を1941年と1950年サンフランシスコ響と米RCAに、1961年シカゴ響と同じく米RCAにスタジオ録音したほか、1943年ニューヨーク・フィル、1946年サンフランシスコ響とライブ録音していた。また、マイスタージンガー第1幕への前奏曲を1947年サンフランシスコ響、1963年ロンドン響とライブ録音していた。
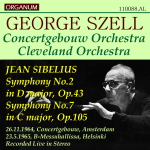
●セル/コンセルトヘボウ管、クリーヴランド管 高音質ステレオ・ライブ
シベリウス 交響曲第2番・第7番
オルガヌム110088AL
シベリウス 交響曲第2番、第7番
ジョージ・セル指揮
コンセルトヘボウ管弦楽団(第2番)、クリーヴランド管弦楽団(第7番)
1964年11月26日、アムステルダム・コンセルトヘボウ
1965年5月23日、ヘルシンキ・Bエキシビション・ホール
ステレオ ライブ
※2曲とも非常に優れた音質のステレオ・ライブ録音。それぞれ放送局保管音源からのディスク化。第2番はオランダ公共放送VARAによる収録。放送におけるコンセルトヘボウ管のステレオ収録は1964年初頭からスタートしたようだが、同年7月に収録されたクレンペラー指揮のベートーヴェン第9録音(オルガヌム110061で発売済み)に比べると、ステレオ・セパレーションの明確化やダイナミックレンジの拡大など、わずか4か月の間に長足の進歩を遂げている。試行錯誤中の偶然の成功例かもしれないが、当時のメジャーレーベルのレコード録音に匹敵する高音質である。もちろん正規のスタジオ録音に比べてマイクセッティングに制約があり、やや音像が遠い感じもあるが、豊かな残響を取り込む一方で細かい音もよく拾っており、当時のオランダ・フィリップスなどの録音よりも、コンセルトヘボウの音響の特徴をよく捉えている。実際の客席で聴く音響に近いかもしれない。会場ノイズは極小。なお、オリジナル音源はオーケストラの広大なダイナミックレンジを忠実に収録しており、弱音と強音の差が甚だしいため、当ディスクでは家庭での鑑賞を考慮し、わずかではあるがコンプレッサーでレンジを圧縮した。一方、第7番はフィンランド国営放送による収録。録音会場は、さすがにコンセルトヘボウほど優れた音響特性は持っていないが、1965年という年代の前提がなくても十分に優秀な音質。バランスも申し分ない。当時は西ドイツでも放送録音は依然としてモノラルが主流であり、フィンランド国営放送は技術的に進んでいたようだ。こちらも会場ノイズはほとんど聞こえない。
セルは、コンセルトヘボウ管には1936年以降、特に1950年代を中心に頻繁に客演を行い、計103回も共演した。シベリウスの交響曲第2番は、1964年11月25・26・28日に行われた定期演奏会2日目の録音。プログラムは、前半にオランダの作曲家ヘンケマンスのBarcarola
fantastica(幻想的舟歌?)、クリフォード・カーゾン独奏によるベートーヴェンのピアノ協奏曲第4番、後半に交響曲第2番というもの。ジョージ・セルは早くからシベリウスの交響曲を取り上げていたが、正規録音として残っているのは、同年11月オランダ・フィリップスに入れた交響曲第2番のみであり、当ディスクは、そのためのリハーサルも兼ねた演奏だったと思われ、当演奏会直後にレコーディングが行われたようだ。セルとコンセルトヘボウ管は、英デッカやオランダ・フィリップスに正規録音をかなりまとめて残しているが、シベリウスの交響曲第2番の録音はなぜか地味な存在で注目されることが少ない。セルとコンセルトヘボウ管が互いの特性を消し合っているような印象があるとも言われるが、精緻かつダイナミックな当ディスクの録音がLPとして発売されていれば、そのような評価を受けることもなかったのではないだろうか。
一方、第7番は、クリーヴランド管のヨーロッパ・ツアーの際の録音。5月19日サンクトペテルブルク(レニングラード)、6月24日コンセルトヘボウにおけるライブは、すでにアウローラMK30009、オルガヌム110065で発売済みであり、第7番はソ連公演直後の演奏ということになる。セルはシベリウスの交響曲第2番を得意としており、クリーヴランド管の定期演奏会やその他のオーケストラへの客演の際にも頻繁に演奏している一方、第7番は、クリーヴランド管の定期演奏会では1948年から1949年にかけて集中的に3回6公演で演奏しており、当時はお気に入りの作品だったようだが、それ以降は1965年3月に3回演奏したのみで、これはヘルシンキ公演のための予習だったのだろう。
セルは上記録音のほかに、シベリウスの交響曲第2番を前述のように1965年コンセルトヘボウ管とオランダ・フィリップスにスタジオ録音したほか、1966年と1970年クリーヴランド管とライブ録音していた。また、第7番は、上記ディスクが現在確認されている唯一の録音である。

●モニク・ドゥ・ラ・ブリュショルリ スタジオ・ライブ
ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲、サンサーンス ピアノ協奏曲第5番
オルガヌム110089AL
ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲
サン=サーンス ピアノ協奏曲第5番「エジプト風」
モニク・ドゥ・ラ・ブリュショルリ(ピアノ)
ミシェル・プラッソン、ジャン・バティスト・マリ指揮フランス国立放送管弦楽団
1966年2月24・25日、1965年5月23日
パリ・メゾン・ド・ラ・ラジオ(フランス国立放送ラジオ・フランス・スタジオ)
モノラル/ステレオ スタジオ・ライブ
※ドイツの高名な音楽評論家ヨアヒム・カイザーが著書で「彼女はヴァルキューレとなり、グランド・ピアノは軍馬となり、いまオクターヴ征討の戦いに進発する」と言わしめた超絶技巧の名手モニク・ドゥ・ラ・ブリュショルリによる貴重な録音。会場はラジオ・フランスの客席付き大型スタジオ(オーディトリアム)だが、会場ノイズや拍手がないため、聴衆を入れずに行った放送録音と思われる。適切なマイクセッティングを行っているらしく2曲とも音質は極めて良好。会場がクラシック専用のコンサートホールではないため残響は少ないが、良い意味でダイレクトな生々しさがある。ただ、録音年が新しいラフマニノフはなぜかモノラル収録となっている。当時フランス国立放送の演奏録音はステレオ収録が通常であったと思われるが、おそらくステレオテープとは別にAMラジオ放送用のモノラルテープを作ることがあり、こちらが今日まで保存され。残念ながらステレオテープは破損または紛失したか、未発見と思われる。日本のNHKなどでも収録当時はステレオ録音されていたにもかかわらず、現在モノラルテープしか残っていない例があるから、同様のパターンであろう。ただし、ラフマニノフはモノラルであっても、十分に良好な音質を保っており、鑑賞には全く問題ない。ラフマニノフの録音日が2日にわたっているが、これはピアノが参加しない他のプログラムの収録日も含んでいるためで、おそらくラフマニノフは24日だろう。なお、テープの経年劣化により、微細なノイズがあったため、音質に影響を与えない範囲で慎重に低減した。
モニク・ドゥ・ラ・ブリュショルリは、レコーディングが少なく、1966年にただ一度来日したものの、ロシアやドイツ系ピアニズムが主流だった当時の日本ではあまり注目されず、その後は先のヨアヒム・カイザーの評価ばかりが引用されるのみで、日本の音楽ファンにとっては演奏の実態が十分に知られているとはいえなかった。わずかに1950年代米VOX録音のラフマニノフ(当CDと同じパガニーニ狂詩曲)、チャイコフスキーやブラームスの協奏曲にその片鱗を伺うことができるが、いささか録音が古く、ステレオ期に入った1960年代のモーツァルトやベートーヴェンの協奏曲(オイロディスク録音)では、音楽性の高さは理解できるものの「ヴァルキューレ」というイメージからは遠かった。
当ディスクに収められた2曲はいずれも高度な技巧(とともに音楽性)を要する作品であり、良好な録音とも併せて、モニク・ドゥ・ラ・ブリュショルリに対する理解を深める一助になると期待される。なお、二人の指揮者のうちプラッソンは当時33歳、1962年にブザンソン国際指揮者コンクールで優勝後、1965年にフランス北東部メス市歌劇場音楽監督、3年後の1968年にはトゥールーズ・キャピトル劇場音楽監督就任という伸び盛りの時代、マリは43歳の充実期、ラムルー管の常任指揮者を務めていた。二人とも巧みにサポートしている。
モニク・ドゥ・ラ・ブリュショルリは、当ディスク以外に、ラフマニノフのパガニーニの主題による狂詩曲を1956年米VOXにスタジオ録音したほか、サンサーンスのピアノ協奏曲第5番を1963年にライブ録音していた。
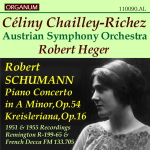
●セリニ・シャイエ・リシェ シューマン ピアノ協奏曲、クライスレリアーナ
米レミントン、仏デッカLP復刻
オルガヌム110090AL
シューマン ピアノ協奏曲、クライスレリアーナ
セリニ・シャイエ・リシェ(ピアノ)
ロベルト・ヘーガー指揮オーストリア交響楽団(トンキュンストラー管弦楽団)
1951年ウィーン、1955年7月、パリ
レミントンR199-65、フランス・デッカFM133.775から復刻
モノラル
※おそらく日本ではジョルジュ・エネスコの伴奏者としてのみ知られるフランスの女流ピアニスト、セリニ・シャイエ・リシェの数少ないソロLP録音の復刻。ピアノ協奏曲の音源であるレミントンはLP初期の廉価盤レーベルとして知られ、コスト削減のため耐久性の低い材料を使用し(ウェブスターライトという塩化ビニール。シェラックを混ぜたという一部の解説は誤り)、しかも自社工場の製造技術も一流とは言い難かったため、現存しているLPは、ノイズが多い劣悪なコンディションの盤が大半を占めている。しかし、当ディスクの復刻に使用したLPは奇跡的に良好な状態を保っており、若干のサーフェイスノイズを軽く除去したのみでオリジナル音源情報の多くを引き出すことができた。ただし、オリジナル音源は低域が過剰で、音量レベルの変動もあったため、バランスを取り直すなど改善を図った。なお、オリジナルの音質は良好で、鑑賞上それほど不満はないが、1951年という年代を考慮すると、レコード会社によるスタジオ(セッション)録音であれば、もう少しクリアに録れているはずであり、放送局による録音に近い音質。後述するように、当録音はレミントンのエンジニアによるオリジナル録音ではなく、オーストリア放送(ORF)収録の放送録音を買い取ったといわれるから、オリジナル音源のバランスなどが悪い点はそのためかもしれない。一方、クライスレリアーナは録音年を1954年11月とする資料もあるが、英デッカのフランス支社による録音。英デッカ本家のハイファイ録音とは異なるようだが、復刻状態も良好でノイズもなく、鑑賞には全く問題ないレベル。ガヴォーのピアノを使用しており、スタインウェイの響きに慣れた今日の我々にはやや異質な印象があるが、古雅と表現すべきピリオド楽器に近いイメージか。若干高域が不足気味だったため見かけ上周波数帯域を拡大している。
セリニ・シャイエ・リシェ(1884~1973)は、フランスのリールで音楽一家の家系に生まれ、地元の音楽院を経てパリ音楽院でラウル・プーニョなどに学び、プリミエ・プリを獲得して卒業。その後は演奏活動の傍ら、母校やエコール・ノルマルで教えた。また1908年にヴァイオリニストのマルセル・シャイエと結婚。シャイエ=リシェ五重奏団としても活動し、ヨーロッパ諸国はもとより南米へもツアーを行った。ちなみに彼らの長子は後の作曲家・音楽学者のジャック・シャイエ、末子はヴァイオリニスト・教師のマリー・テレーズ・シャイエである。ジョルジュ・エネスコとは1926年に初めて共演し、その後1950年代に入り、レミントンやデッカにシューマンやバッハなどの録音を行った。これらの一連の録音は、エネスコの演奏を後世に残すため、セリニ・シャイエ・リシェが引退間際のエネスコに強く勧めて実現したといわれる。
セリニ・シャイエ・リシェの録音は多くないが、第二次世界大戦前に数点、戦後は先のエネスコの共演を中心として、レミントンのほかフランス・デッカ、フランス・コロンビアなどに十数点は残されているようだ。多くは戦後の1950年代前半から半ばに集中しており、当ディスクのクライスレリアーナは、彼女の最後の録音の一つと思われる。一方、ピアノ協奏曲は先述のように、ORFが聴衆を入れずに行った放送録音といわれる。レミントンのプロデューサーがエネスコの録音をきっかけに、セリニ・シャイエ・リシェの実力を評価し、本人の許可を得てLP化したのだろう。なお、オーケストラの実体はトンキュンストラー管弦楽団といわれているが、オーストリア交響楽団とは、レミントンが自身のスタジオ録音でトンキュンストラー管を使用した際の変名であり、ORFによる当録音が同様であるかは不明。ウィーン国立歌劇場のピックアップメンバー(実態はフォルクスオーパー)や、ウィーン交響楽団などの可能性も捨てきれない。会場も不明だが、ムジークフェラインではなく、コンツェルトハウス辺りだろうか。老練な指揮者ロベルト・ヘーガーについては説明不要だろう。
セリニ・シャイエ・リシェによるシューマンのピアノ協奏曲とクライスレリアーナは、当ディスクが現在確認されている唯一の録音と思われる。

●アリーヌ・ヴァン・バレンツェン 1960年スタジオ・リサイタル
ベートーヴェン、シューマン、ドビュッシー
オルガヌム110091AL
ベートーヴェン ピアノ・ソナタ第12番「葬送」
シューマン 交響的練習曲
ドビュッシー「子供の領分」
アリーヌ・ヴァン・バレンツェン(ピアノ)
1960年6月21日、パリ・フランス国立放送スタジオ
モノラル
※近年日本でも認知度が高まってきたアリーヌ・ヴァン・バレンツェンによるスタジオ・ライブ録音。ラジオ放送用に聴衆を入れずに行われたもので、マイクセッティングの制約もないため、モノラルながら当時としては極上の音質。このままステレオ化すれば1960年代初頭のメジャーレーベルLP録音と同等の水準で、鑑賞には全く不満はない。一部に録音テープの経年劣化による微細なノイズが生じていたため、音質を損ねることなく低減した。
バレンツェンは、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ演奏が高く評価され、1950年代前半にフランス国立放送(RTF)によりソナタ全曲を録音・放送したが、当ディスクの録音はそれとは別の機会に行われたものである。ちなみにバレンツェンは仏EMI(VSM)というメジャ・レーベルと録音契約を結んだにもかかわらず、ソナタ全曲のレコーディングは行わず、当ディスクの第12番も正式なレコード録音を行わなかった作品である。
バレンツェンはベートーヴェンばかり弾いていたわけではなく、コンサート・ピアニストしての基本的レパートリーは網羅しており、さらにフランス楽派のピアニストしてドビュッシーのほかフランス作品も重要なレパートリーであった。当録音のシューマンやドビュッシーはその一例である。また、ヴィラ・ロボスなど当時の現代作品の初演なども手がけており、若干の録音も残している。
なお、バレンツェンは1960年代末まで演奏活動を行ったが、メジャーレーベルのレコードビジネスからは若干距離を置いていた感があり、レコーディングは皆無ではないものの散発的である。おそらくピアニストとしての評価とは別に、レコード会社のスターシステムに組み込まれていたか否かの違いであり、そのためには海外公演を頻繁に行い、かつレコード大消費地アメリカで人気があるかどうかが重要であった。1960年代以降、ロベール・カサドシュ、サンソン・フランソワやアルド・チッコリーニ、(ハンガリー系だが)ジョルジュ・シフラなどがこれに組み込まれ、パリ音楽院で教育に力を注ぎ、演奏活動を制限したペルルミュテール(1950年代にはまとまった録音はあるが)やイヴォンヌ・ルフェビュールなどが外される結果となったが、バレンツェンもその一人なのだろう。
アリーヌ・ヴァン・バレンツェンは、上記のようにベートーヴェンのピアノ・ソナタ第12番のスタジオ録音を残さず、放送用ライブ録音が残っているとされる。シューマンの交響的練習曲とドビュッシーの子供の領分も当ディスクが現在確認されている唯一の録音と思われる。
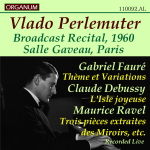
●ヴラド・ペルルミュテール 1960年パリ・サル・ガヴォー・ライブ
フォーレ、ドビュッシー、ラヴェル
オルガヌム110092AL
フォーレ 主題と変奏
ドビュッシー「喜びの島」
ラヴェル 「鏡」から「悲しげな鳥たち」「海原の小舟」「道化師の朝の歌」、「クープランの墓」から「トッカータ」
ヴラド・ペルルミュテール(ピアノ)
1960年1月16日、パリ・サル・ガヴォー
モノラル ライブ
※ラヴェルから自作の奏法について直接教えを受け、パリ音楽院で長らく教育にも携わったペルルミュテール壮年期のライブ録音。フランス国立放送の持つラジオチャンネルの一つ「パリ・インテル」(1960年頃にはフランス・インテルと改称か)による聴衆を入れた公開録音で、音源はエアチェックと思われるが、高品質な機材を使用したためかモノラルながら音質は極めて良好。いわゆるハイファイ的な派手な録音ではなく、素直で堅実な録音だが、ノイズもなくバランスも問題ないため、鑑賞には全く不満はない。
当日のプログラムは、ペルルミュテール単独のリサイタルではなく、前半にソプラノのジャニーヌ・ミショーを迎えて、ラヴェル、カントルーブ、プーランク、ビゼーの歌曲が披露され(伴奏もペルルミュテール)、後半に当ディスクに聴くプログラムが演奏された。リサイタルとして異例に短いのはこのような理由による。なお、「クープランの墓」から「トッカータ」は、予定にはなかったようでアンコールと思われる。
当時ペルルミュテールは55歳。音楽的にも技術的にも円熟期にあり、1951年からパリ音楽院で携わる傍ら、演奏活動も積極的に行い、当公開録音の前年12月にはシャンゼリゼ劇場でリサイタル、当録音の2日後にはスイス・ローザンヌでローザンヌ室内管弦楽団と共演。レコーディングも同年からコンサートホールソサエティと契約し、ショパンを始め録音を開始するなど、活発な活動を行っていた。
ペルルミュテールは、1930年代からレコーディング歴があるが、まとまった録音はなぜか1950年代と70年代以降に集中している。1950年代には米ヴォックスにモーツァルトのソナタ全集やラヴェルのピアノ曲全集などを録音したが、当時のヴォックスの貧弱な録音では、ペルルミュテールの美点を十分に伝えているとは言い難い(ペルルミュテール録音に限らず、当時のヴォックスのヨーロッパ出張録音は総じて問題が多い)。一方、1970年代以降は英ニンバスにラヴェルのピアノ曲全集の再録音やショパンの主要曲を録音しており、若干残響が多めながら、年代が新しいだけに美しい音質で、音楽的にも味わい深い名演にであるものの、技術的には万全とはいえず、録音時期が数年早ければという感がある。
1960年代の充実期の録音は、上記のコンサートホールソサエティのLP5点分のみであり、この時期に録音を多く残さなかった理由は不明だが、ペルルミュテール本人は1977年にパリ音楽院の教授職を退いた際、これで演奏活動に時間を割けると述べているところから、単に多忙であったということが理由であろう。また、レコード会社自身も、スター性を重視し、かつレコーディングに協力的な演奏家を優遇したという事情もあると思われる。それだけに当ディスクに聴く1960年代初頭のライブ録音は貴重な存在といえる。
ペルルミュテールは、フォーレの主題と変奏を1972年にデンオン、1982年にニンバスに録音。ラヴェルの「鏡」から「悲しげな鳥たち」「海原の小舟」「道化師の朝の歌」と「クープランの墓」から「トッカータ」を1954年ヴォックス、1973年ニンバスに録音したほか、ドビュッシーの「喜びの島」を1961年にライブ録音、「トッカータ」を1968年BBCに放送録音していた。
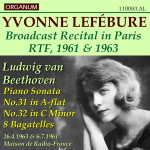
●イヴォンヌ・ルフェビュール スタジオ・ライブ 1961年、1963年
ベートーヴェン ピアノ・ソナタ第31番、32番ほか
オルガヌム110093AL
ベートーヴェン
ピアノ・ソナタ第31番、第32番
8つのバガテル 作品33、作品119から
イヴォンヌ・ルフェビュール(ピアノ)
1963年4月26日、1961年7月6日、パリ・ラジオ・フランス・スタジオ
モノラル 放送ライブ
※フランスのベテラン女流・イヴォンヌ・ルフェビュールによる放送ライブ録音。かつて日本では「フルトヴェングラーと共演したピアニスト」としか認識されていなかったが、その後フランスのFYやソルスティス・レーベルから新録音が登場することによって徐々に評価が高まり、今日では良きフランス流派の伝統を受け付いた名ピアニストとしての地位を確立している。ルフェビュールは自国作品のみならずベートーヴェンも得意としており、後期のピアノ・ソナタは複数のレコーディングが残っている。当ディスクの音源はフランス国立放送が聴衆を入れずに行った放送用スタジオ録音。いずれも音質は良好でノイズもなく鑑賞に全く問題ない。なお、1963年録音の第31番はビデオ収録されたテープを音源としており、オーディオ・テープに録音された1961年録音の第32番とバガテルの方が周波数レンジもやや広く、こちらがより新しい録音のように感じる。ただその差はわずかで、音の録り方(スタイル)は同一であるため違和感はないだろう。いずれの録音もドルビー・ノイズ・リダクション普及以前のためテープ・ヒスノイズがあり、音質を損ねない範囲で低減している。
録音会場はラジオ・フランスのスタジオ(メゾン・ラジオ・フランス)とされているが、第31番についてはテレビ放送用にビデオ収録されているので、フランス国立放送(RTF)スタジオと表記する方が正確かもしれない。ちなみに第31番では、ルフェビュールの「鼻歌」がわずかに聞こえる。グレン・グールドやトスカニーニほど極端なものではないが、興に乗っているようだ。
イヴォンヌ・ルフェビュールは、ベートーヴェン作品には一家言を持っており、レクチャーの模様を収録したビデオなども残っている。フランスでは、ベートーヴェンのソナタ全集を録音したイヴ・ナットや、モーツァルトのソナタ全集を録音したヴラド・ペルルミュテール、シューマンのソロ作品全集を録音したレーヌ・ジャノリの例に見るように、独墺作品の解釈や奏法についても、パリ音楽院やエコール・ノルマルなどを中心に長い伝統を持っているが、ドイツ系流派が主流だった日本では理解が進まず(井口基成の先生だったイヴ・ナットという例外はあるが)、近年、ようやくルフェビュールも含めて、フランス流のベートーヴェン演奏についても評価が定着しつつあるといえる。
なお、当ディスクのバガテルは、ルフェビュールが適宜選択し、シューマンなどロマン派の性格的小品集のように仕立てて演奏している。ルフェビュールはシューベルトのレントラーなどの小品でも同様の手法でまとめて録音も残しているが(オルガヌム110057ALで聴くことができる)、作品を単に番号順に演奏しない作・編曲的発想、または今世紀前半まで残っていた、作品を神聖視せず自由に解釈する慣習によるものだろう。
ルフェビュールは、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ第31番を1955年仏VSM、1977年仏ソルスティスにスタジオ録音。第32番を1977年仏ソルスティスにスタジオ録音したほか、1959年に放送録音していた(当ディスクと同一録音の可能性あり)。バガテルは当ディスクが現在確認されてる唯一の録音と思われる。

●イヴォンヌ・ルフェビュール スタジオ・ライブ
モーツァルト ピアノ協奏曲第20番、シューマン ピアノ協奏曲
オルガヌム110094AL
モーツァルト ピアノ協奏曲第20番
シューマン ピアノ協奏曲
イヴォンヌ・ルフェビュール(ピアノ)
ピエール・デルヴォー指揮パリ放送交響楽団、フランス国立放送管弦楽団
1958年1月25日、1955年4月4日、パリ・ラジオ・フランス・スタジオ
モノラル 放送ライブ
※名女流イヴォンヌ・ルフェビュールによる、聴衆を入れずに行われたラジオ放送用録音。1958年のモーツァルトは年代相応の録音状態。モノラル・テープ録音技術の安定期に入っており、特に優秀録音というわけではないが、ピアノと管弦楽のバランスも良好で鑑賞には全く問題ない。シューマンはモーツァルトよりも3年前の録音だが幾分古い印象。両者はわずか3年の差だが、この時代の録音技術の進歩の早さを感じる。ただ放送局による正規の録音であるため必要な情報はしっかり記録されており、聴きづらさもない。フルトヴェングラー晩年のライブ録音の平均的音質に近く、十分鑑賞に堪えるレベル。ただ、低域が過剰でヒスノイズも多かったため、バランスを取り直すなど、音質を損ねない範囲の調整を行っている。
モーツァルトのニ短調協奏曲は、1954年5月スイス・ルガーノにおけるフルトヴェングラーとの共演した録音が有名だが、当ディスクの録音はその4年後の録音。ルガーノの公演は急病のエトヴィン・フィッシャーの代役としての出演要請であったとわれるが、1951年にはペルピニャン音楽祭でもカザルス指揮で演奏しているなど、ルフェビュールにとっては急な演奏依頼でも対応可能なレパートリーでもあったようだ。シューマンの協奏曲も複数の放送またはライブ録音が残されており、いずれの作品も、コンサート・ピアニストとしては当然のレパートリーであるともいえる。ちなみにシューマンでは第2楽章から3楽章への移行部にティンパニが追加されているが、現在確認されている指揮者が異なるルフェビュールによる3種の録音とも追加がある。他の演奏家の事例はあるのだろうか。
なお、モーツァルトの伴奏を務めているパリ放送交響楽団は、現在のフランス放送フィルハーモニー管弦楽団であり、フランス国立放送管弦楽団とは別団体。1937年の設立から1960年までは、Orchestre
Radio-symphonique de la Radiodiffusion-télévision Française または Orchestre Radio
Symphonique de Parisのいずれかの名称を使用していた。
指揮のピエール・デルヴォーは、1956年にはパリ・オペラ座の常任指揮者となり、1950年代末にはメジャーレーベルのEMIとレコーディング契約するなど、1960年代後半頃までフランスで最も勢いのあった指揮者の一人。なぜかその後はあまり良いポストに恵まれず、フランスの地方オーケストラでの活動が中心となり、意外に地味な存在としてキャリアを終えている。エコール・ノルマルにおける教育活動に注力したためかもしれない。
教育活動に注力したといえばルフェビュールも同様であり、長らくパリ音楽院で教授を務めていたが、メジャーレーベルVSM(仏EMI)との録音契約は1950年代中頃で終了し、1960年代はおそらくレコーディング契約なし。1970年代からはマイナーレーベルのFYやソルスティスと契約したが、当ディスクに聴くような協奏曲は放送録音を転用してCD化し、正式なスタジオ(セッション)録音を残さなかった。小規模レーベルではレコーディングのためにオーケストラを雇う予算がなかったのだろう。
ルフェビュールは、モーツァルトのピアノ協奏曲第20番のスタジオ録音を残さず、当ディスク以外に前記1951年と1954年にライブ録音していた。また、シューマンのピアノ協奏曲もスタジオ録音を残さず、当ディスク以外に1964年と1970年にライブ録音していた。

●マルセル・メイエ スタジオ・ライブ
ファリャ「スペインの庭の夜」、R・シュトラウス「ブルレスケ」
オルガヌム110095AL
ファリャ 交響的印象「スペインの庭の夜」
R・シュトラウス ピアノと管弦楽のための「ブルレスケ」
マルセル・メイエ(ピアノ)
マリオ・ロッシ指揮トリノ・イタリア放送交響楽団
1958年5月12日、トリノ・イタリア放送オーディトリアム
モノラル 放送ライブ
※若き日にサティやコクトーと親交を結び、プーランクやミヨー、オネゲルらの作品をいち早く紹介、「6人組のミューズ」とも称されたマルセル・メイエ(メイエル)晩年の放送録音。2曲ともトリノ・イタリア放送(RAI)が観客席付きのホールで聴衆を入れずに行ったもので、当時のRAIの録音としては最良の音質。解像度が高く明晰・クリアな音質でバランスも良好で鑑賞には全く不満がない。会場は残響が乏しくドライな音響のようだが、作品の性格とマッチしておりプラスに働いている。ただ、「ブルレスケ」は高域にピークがあり耳障りな一方で、やや低域不足だったためイコライジングにより改善している。
マルセル・メイエは当録音の6か月後の11月17日、パリの姉の家を訪問中に心臓発作を起こし(ピアノを弾いていたという情報も)、同夜61歳で亡くなるが、当時ディミトリ・ミトロプーロスと初の北米ツアーを計画しており、現役のままの急死であった。このような事情からも、当ディスクに聴く演奏は「晩年」をみじんも感じさせない溌剌たるもので、ピアノと管弦楽による協奏曲的作品のユニークな組み合わせも、近現代作品の紹介に努めたマルセル・メイエの面目躍如たるプログラム。2曲とも得意の作品だったらしく、「スペインの庭の夜」は戦前派フランス系の多くのピアニストが好んだ作品。一方「ブルレスケ」は現代の演奏会でも珍しい作品だが、メイエは1930年代に作曲家シュトラウス自身の指揮で演奏し、1943年にはクリュイタンス指揮でスタジオ録音も残している。メイエは前述のようにサティや6人組、ソーゲやトマジら「アルクイユ派」とも親しく、反ロマン主義的な思潮のポジションにある。反面R・シュトラウスは本来ドイツ・ロマン派本流の作曲家で、「ブルレスケ」もブラームスの影響下に作曲されたと本人は語っているものの、作品自体は新古典主義的な仕上がりとなっており、メイエとの相性が良かったのだろう。
マルセル・メイエは、近現代作品またはバッハやスカルラッティ、ラモーなどバロック(フランス流に言う古典派)作品ばかり演奏していたように思われがちだが、モーツァルトの協奏曲の録音も残しており、ショパンやシューマンの演奏でも定評があった。近年にはベートーヴェンの「皇帝」のライブ録音も発掘されている。海外情報が乏しく、レコーディング・レパートリーのみから想像した日本人の誤解であろう。
ちなみに日本におけるメイエの評価は、第二次世界大戦前のSPレコード期にはほぼ無名で、戦後は1960年前後にディスコフィル・フランセ原盤の国内盤LPが少数発売されたが、ドイツ流派を信奉する一方、フランス流ピアニズムに理解のない一部の評論家にことごとく酷評を浴びたため(クララ・ハスキルなども同様であった)早々に廃盤となり、長らくメイエはサティや6人組との関連で名前のみ一部で知られる存在だった。再評価が始まったのは、海外で復刻CDが再発売され、一方で初期プレスの中古LPが注目されるようになった1980年代後半頃からと思われる。
指揮者のマリオ・ロッシは、1946年から1969年まで20年以上トリノ・イタリア放送交響楽団の首席指揮者を務めたベテラン。当時は米ヴァンガード・レーベルなどに盛んにレコーディングするなど国際的にも知名度を向上させつつあった。トリノ・イタリア放送交響楽団はロッシの尽力により、ローマ、ミラノ、ナポリと4団体あったイタリア放送の交響楽団の中で最も優れていると言われ、1994年に4団体が整理・合併してRAI国立交響楽団となった際も、トリノが中心となって再編成された。
マルセル・メイエは、ファリャの「スペインの庭の夜」のスタジオ録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音。R・シュトラウスの「ブルレスケ」は前述のように1943年仏VSMにスタジオ録音を行っていた。
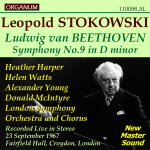
●ストコフスキー/ロンドン響 高音質ステレオ・ライブ
ベートーヴェン 交響曲第9番
オルガヌム110096AL
ベートーヴェン 交響曲第9番「合唱付き」
ヘザー・ハーパー(ソプラノ)
ヘレン・ワッツ(アルト)
アレグザンダー・ヤング(テノール)
ドナルド・マッキンタイア(バス)
チェルシー・オペラ・グループ団員
ロンドン交響楽団合唱団
ジョン・オールディス(合唱指揮)
レオポルド・ストコフスキー指揮ロンドン交響楽団
1967年9月23日、ロンドン・クロイドン・フェアフィールド・ホール
ステレオ ライブ
※英国人コレクターのプライベート・アーカイブからディスク化。従来、同一演奏のモノラル音源がCD化されていたが、貧しい音質で海外のディスコグラフィでも「relatively
poor
sound」(比較的悪い音)と奥ゆかしく?表現されていた。一方、当ディスクはそれとは全く異なる出所の音源で、すばらしく高音質なステレオ録音。BBCのラジオ放送をエアチェックしたと思われるが、良好な受信状態のもとで高品質な機材を使用して録音したらしく、ノイズレスで周波数レンジは広くバランスも申し分ない。1960年代後半のエアチェック録音の水準を上回る高音質。若干のヒスノイズは低減した。当日、第9の前に演奏されたマイスタージンガー前奏曲がBBCのオリジナル音源を使用してCD化されているが、それとほぼ同一レベルの音質であり、当演奏もBBC音源のコピーである可能性は捨てきれない。
ストコフスキーは、当演奏の2日前の9月20・21日に、英デッカに第9のスタジオ(セッション)録音を行っているが、通常はリハーサルを兼ねてコンサートを行い、その後レコーディングという例が多いが、これはその逆という珍しいパターン。録音会場(キングズウェイ・ホール)やストコフスキー本人のスケジュールなどによるものであろう。ちなみにLPの発売は3年後の1970年であった。LPは「フェイズ4」というアンペックスの4トラック・レコーダーとマルチマイクを使用した、やや派手な録音が売り物だったが、当録音はBBCによるまっとう?な録音であり、両者の比較も興味深い。
なお、当時ストコフスキーは85歳の高齢ながら依然として活発な活動を行っていた。当演奏会についても第9のみではなく、前半にワーグナーのマイスタージンガーからの抜粋(ストコフスキー編曲による組曲?)を演奏しており、一部は前述のように正規音源からCD化されている。また当演奏の2年前には来日して日本フィルと読売日響を指揮しており、当時のインタビュー記事では、影響を受けた指揮者を問われて即座にハンス・リヒターと回答。リヒターは1911年に引退して録音も残しておらず、現代の我々は確認する術もないが、当時としては楽譜に忠実、インテンポで客観的な演奏を行ったと伝えられている。ストコフスキーの芸風とは対照的に思われるものの、一方でリヒターはリハーサルの手際が良く、オーケストラ・コントロールに長けていたと言われており、こちらの部分で影響を受けたのかもしれない。
ストコフスキーは、ベートーヴェンの第9を1934年米ビクターにフィラデルフィア管弦楽団と、1967年前述のように英デッカにロンドン交響楽団とスタジオ録音したほか、1967年、1970年、1972年にアメリカ交響楽団とライブ録音していた。
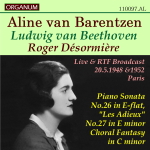
●アリーヌ・ヴァン・バレンツェン 1952年スタジオ・ライブ&1948年コンサート・ライブ
ベートーヴェン ピアノ・ソナタ「告別」、合唱幻想曲ほか
オルガヌム110097AL
ベートーヴェン
ピアノ・ソナタ第26番「告別」
ピアノ・ソナタ第27番
合唱幻想曲
アリーヌ・ヴァン・バレンツェン(ピアノ)
フランス国立放送合唱団
ルネ・アリックス(合唱指揮)
ロジェ・デゾルミエール指揮フランス国立放送管弦楽団
1952年、パリ・ラジオ・フランス・スタジオ
1948年5月20日、パリ・シャンゼリゼ劇場
モノラル 放送ライブおよびコンサート・ライブ
※近年日本でも評価が高まってきたアリーヌ・ヴァン・バレンツェンによるスタジオ・ライブとコンサート・ライブ録音。2曲のピアノ・ソナタは、1951年から52年頃にかけて、ラジオ放送用に聴衆を入れずに収録されたピアノ・ソナタ全曲の一部で、第8番、第9番、第13番、第14番はオルガヌム110059ALで発売済みである。当ディスクの2曲は、詳しい録音日時は不明ながら1952年とされている。1950年代初頭には、フランス国立放送ではテープレコーダーを導入していたはずであり、オリジナルはテープ録音だったと思われる。ただし、当時の放送局では高価だったオーディオ・テープを再利用するため、テープ音源を放送後、(より安価な)アセテート盤にダビングして保存されることが一般的であった。バレンツェンによるベートーヴェン・ソナタ全曲も同様の形で今日まで残されることとなったが、残念なことにアセテート盤の品質またはその後の保存環境に問題があったか、先に発売された4曲と同様、当ディスクの2曲もノイズだらけで、そのままの状態ではディスク化困難な状態だった。ただし、2曲に関しては、幸いなことに比較的単純なスクラッチノイズ(パチパチ音)が多数であったため、音質を損ねることなく大半を除去することが可能であり、一部に微細なノイズが残った箇所があるものの、ようやく鑑賞に堪える音質となった。状態の悪いアセテート盤からの復刻でもあり、ナローレンジで古びた音ではあるが、大きなストレスなく演奏を楽しむことが出来る。
合唱幻想曲はピアノと管弦楽、独唱、合唱という特異な編成の曲であるため、演奏される機会は極めて少ないが、近年アルゲリッチと小澤征爾が演奏したことで知る人も増えた。オリジナル音源は、意外にノイズが少ないためテープ録音と思われ、先のピアノ・ソナタとは異なり、後述するように特別な演奏会だったためテープを再利用せずにそのまま保存したのであろう。ただし、当時のドイツなどの録音に比べると若干見劣りする音質で、第二次世界大戦中のフルトヴェングラーのライブ録音と同程度。元来フランス国立放送が収録したものでもあり、一応はマイクセッティング等も適正で、幸いバレンツェンのピアノもクリアに録らえられているなど、聞こえるべき音はしっかりと収録されており、情報量は不足していない。ディスク化に当たっては、ヒスノイズ低減のほか、イコライジングによるバランスの改善、周波数レンジの見かけ上の拡大などを行い、鑑賞に堪える音質とした。
バレンツェンはベートーヴェンを得意としており、上記のようにピアノ・ソナタ全曲をフランス国立放送のラジオ・フランスに放送収録したが、正式なレコード録音は限られており、8、14、18、21、23、26番と中期までのソナタのみで、協奏曲の録音も残さなかった。ラジオ・フランスのソナタ全曲を含め、今後は埋もれた録音の発掘が望まれる。
合唱幻想曲を含む1948年の演奏会は、フランスの2月革命100周年を記念して行われた演奏会のライブ録音。独唱者名は不明だが、合唱団のメンバーと思われる。祝祭コンサートならではの盛りだくさんの内容で、国歌ラ・マルセイエーズに始まり、マニャール「正義への賛歌」、ミヨーの交響曲第4番(初演。これのみ作曲者ミヨー指揮)、「ジロンダンの歌」(フランス第二共和政国歌)、ベルリオーズ「万人の聖堂」、ベートーヴェン「合唱幻想曲」、ベルリオーズ「葬送と勝利の大交響曲」(抜粋)というプログラム。このような祝典コンサートの場合、「合唱幻想曲」の代わりに交響曲第9番の終楽章を演奏しても良さそうだが、最後の演奏プログラムをベルリオーズ「葬送と勝利の大交響曲」とするために、第9よりも多少「軽め」の曲目を選んだのだろうか。結果として、幸運にもバレンツェンの独奏が聴けることになった。
アリーヌ・ヴァン・バレンツェンは当ディスク以外にベートーヴェンのピアノ・ソナタ第26番を1952年仏VSMにスタジオ録音していた。他の曲は当ディスクが現在確認されている唯一の録音と思われる。

●イヴォンヌ・ルフェビュール スタジオ&コンサート・ライブ 1964年、1959年
シューマン ピアノ協奏曲、ベートーヴェン ピアノ協奏曲第4番
オルガヌム110098AL
シューマン ピアノ協奏曲
ベートーヴェン ピアノ協奏曲第4番
イヴォンヌ・ルフェビュール(ピアノ)
ジョルジュ・セバスティアン、スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ指揮
フランス国立放送管弦楽団
1964年2月14日、パリ・ラジオ・フランス・スタジオ
1959年12月1日、パリ・シャンゼリゼ劇場
モノラル/ステレオ スタジオ&コンサート・ライブ
※フランスのベテラン女流・イヴォンヌ・ルフェビュールによるライブ録音。シューマンは、オルガヌム110094ALでディスク化された同一曲の9年後の演奏。会場はラジオ・フランスの客席付き大型スタジオ(オーディトリアム)で聴衆を入れた公開収録。1960年代中期ともなると音質も安定していると思いがちだが、オリジナル音源はかなり問題の多い音質。当時、フランス国立放送ではステレオ収録が通常であったと思われるが、なぜかモノラル。おそらくステレオ/モノラルの端境期で放送により両者を使い分けていたか、FM放送用のステレオテープが失われたか破損し、AM放送用のモノラルテープが今日まで保存されたのであろう。しかし、それにも増して問題なのがバランスで、音質自体は良好だが、極端に高域が強調され低音が不足、また弱音と強音の差が甚だしいなど、このまま放送に使用したのか疑問に思われるひどい状態。録音スタジオであるから、オーケストラのマイクセッティングには定型があると思われ、各オーケストラ・パートの音もしっかり録れているため、その点は問題ない。おそらくレコーダーのイコライザー不調など機器のトラブルではないだろうか。当時この音質で放送を聴いたリスナーはどう感じただろうか。
ディスク化に当たっては、イコライジングによる高低域バランスの改善、弱音と強音の調整など、様々な手当の結果、ようやくまともに音楽を鑑賞できる状態となった。年代的にはテープ録音の完成期であるため音質は悪くなく、モノラルながら当時の水準を上回るレベルとなった。
一方ベートーヴェンは、シューマンよりも5年前の録音だが、こちらは優秀なステレオ録音。フランス国立放送は、シャンゼリゼ劇場におけるフランス国立放送管のライブ収録の際、先行実験的にステレオ録音を行っていたようで、アンドレ・シャルランなどが協力していたのかもしれない。実に美しい音質だが、ソロ演奏をピックアップし、伴奏をボリューム小さめに配した古いスタイルを引きずっており、第3楽章のオーケストラ強奏などは明らかに迫力不足。ディスク化に当たっては、ピアノとオーケストラのボリュームバランスを改善した。2曲とも会場ノイズは極小。
イヴォンヌ・ルフェビュールは、シューマンのピアノ協奏曲のスタジオ録音を残さなかったが、当ディスク以外に1955年と1970年に放送録音を残しており、3者を比較すると徐々に演奏の自由度が増している感があり、特に1955年録音とその後2種の差が大きい。1970年録音はステレオ録音のため音質が最も良好で、ポール・パレーの巧みなサポートで完成度が高い一方、パレーが巧みすぎて?ルフェビュールの自由度が目立たない感もある。その点、当ディスクの演奏は録音に問題があったが、演奏自体も興味深い。事前のリハーサルが不十分だったのか、それともルフェビュールが即興的に打ち合わせにない弾き方をしたのかは不明だが、当初はピアノと管弦楽がずれ気味に展開していく。指揮のセバスティアンはハンガリー出身のベテランで、パリ・オペラ座の首席指揮者を務めるなど、伴奏指揮は慣れているはずだが、ルフェビュールのピアノを慌てて追いかけている感がある(それが伝染したかオーボエが飛び出している箇所もある)。それでも第2楽章辺りから落ち着き、最終的には見事にまとめており、聴衆も大歓声。演奏の完成度としては問題があるかもしれないが、ルフェビュールのピアノの自在さを聴くには好適?とも言える。なお、他の2種の録音と同様に第2楽章から3楽章への移行部にティンパニが追加されている。例によって、かすかにルフェビュールの鼻歌が聞こえる。
ベートーヴェンは、現在確認されているルフェビュール唯一の協奏曲録音。ルフェビュールの実力を持ってすれば「皇帝」の演奏も不可能ではなく、第4番以外の協奏曲録音の発掘も期待したい。指揮は当時「駆け出しの新人」だったスクロヴァチェフスキ。1956年にローマの国際指揮者コンクールに優勝後、当録音の前年1958年にはジョージ・セルに招かれ、クリーブランド管弦楽団を指揮してアメリカデビューしたばかりだったが、翌1960年からはミネアポリスの音楽監督に就任するなど、駆け出しながら既に実力は一流であった。当ディスクでも、合わせにくいと言われる第4番の伴奏を破綻なく務めている。ただし、当時スクロヴァチェフスキのデビューレコードを聴いた日本の音楽評論の重鎮は「無味乾燥」と酷評。ブルーノ・ワルターやフルトヴェングラーなどロマン的演奏を理想としていた日本の評論家にとっては、その演奏スタイルは到底理解不能だったのだろう。
ルフェビュールは、当ディスク以外に、上記のようにシューマンのピアノ協奏曲を1955年と1970年にライブ録音していた。ベートーヴェンのピアノ協奏曲第4番も上記のように当ディスクが現在確認されている唯一の録音。
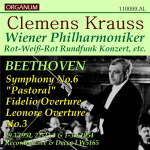
●クレメンス・クラウス/ウィーン・フィル
ベートーヴェン 交響曲第6番「田園」、フィデリオ序曲、レオノーレ序曲第3番
ライブおよびデッカLP復刻
オルガヌム110099AL
ベートーヴェン 交響曲第6番「田園」、フィデリオ序曲、レオノーレ序曲第3番
クレメンス・クラウス指揮ウィーン・フィル
1952年3月29日、1954年3月22・23日、4月1~3日
ウィーン・ムジークフェラインザール
モノラル ライブおよび英デッカLW5165から復刻
※「田園」はライブ録音。序曲は英デッカ10インチLPから復刻。「田園」は、第二次世界大戦後ウィーンを含む地域を管理していたアメリカ占領軍の放送局ロート・ヴァイス・ロートによる録音。通常の定期演奏会ではなく、ロート・ヴァイス・ロート放送コンサート(Rot-Weiß-Rot
Rundfunk
Konzert)と銘打った、聴衆を入れて行った放送のため公開録音である。終戦後7年を経て録音技術も安定してきており、物資も技術も充実していた米軍放送局の録音だけに、当時の水準を超える良好な音質。会場ノイズも少なく、モノラルながら音楽を鑑賞する上で全く問題ない。ただし、第2楽章までと第3楽章以降でそれぞれ別のレコーダーを使用しているらしく、オリジナルの音源は、録音レベルの設定が若干異なるようだ。第2楽章までは録音レベルが若干低く、第3楽章からいきなりレベルが高くなり、第4楽章「嵐」では、強奏でレベルオーバーを避けるためエンジニアが(慌てて?)レベルを下げたと思われる箇所がある。今回のディスク化に当たっては、ヒスノイズの低減のほか、前半と後半の音量レベルを揃えることと、先のエンジニアによる不自然なレベル調整を修正する作業を行った。英デッカの10インチLPから復刻した序曲はスクラッチノイズもなく、こちらも良好な音質。ただし録音会場が有名なゾフィエンザールに移る前の録音であり、残響が豊かで中域が膨らんだムジークフェライン独特の音響のため、英デッカからイメージされるシャープでクリアな音質ではなく、EMI系のようなナチュラルな音質。
3月29日の演奏会は、通常の定期公演よりも短く、最初にエグモント序曲、次いで「田園」、最後になぜかエネスコのルーマニア狂詩曲第1番というプログラム。定期会員向けではない、広く一般向けの放送コンサートだけに最後は盛り上げようという演出か。
ちなみにクレメンス・クラウスはウィーン・フィルの常任指揮者を長く務め、同フィルを数多く指揮しているが、「田園」については、1931年に1公演、1944年に4公演、1945年に1公演、1950年に1公演。当ディスクの公演の後、1952年11月のロンドン公演で指揮したのみであまり多くはなく、それだけに当ディスクのライブ録音は貴重である。
クレメンス・クラウスというと、典型的なウィーン・スタイルの演奏を行う指揮者と言われているが、こちらも典型的なウィーン・スタイルの演奏として評価が高い、ブルーノ・ワルター指揮ウィーン・フィルによる1936年録音の78回転SP盤と比較すると、中庸なテンポで情緒纏綿、ロマンチックなワルター盤に対し、速めのテンポですっきりとまとめたクラウスは、都会風のしゃれた洗練さを感じさせ、ウィーン・スタイルと言っても多様であることが分かる。またクラウスはワルターより17歳若く、世代の相違もあろう。
余白に収めた序曲は、今日ではほとんど忘れられた録音。ほぼ同時期にレオノーレ第1番と2番も録音された。そもそもクラウスは二人のシュトラウス(ヨハンを含むワルツ王一家とリヒャルト)の録音ばかりが注目され、近年バイロイトのライブ録音が発掘されることで、ようやくワーグナー指揮者としても評価されつつあるが、第二次世界大戦後に限っても、英デッカ以外に独テレフンケン、米ヴォックスも含めれば、かなり多くのレパートリーの録音を残している。彼は本質的にオペラ指揮者であり、コンサート指揮者ではなかったようだが、残された録音の再評価は今後に期待したい。
クレメンス・クラウスは、当ディスク以外に「田園」のスタジオ録音を行わず、フィデリオ序曲とレオノーレ序曲第3番も英デッカに入れた当ディスクの録音が唯一と思われる。
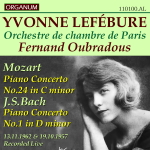
●イヴォンヌ・ルフェビュール スタジオ・ライブ
モーツァルト ピアノ協奏曲第24番、バッハ ピアノ協奏曲第1番
オルガヌム110100AL
モーツァルト ピアノ協奏曲第24番
バッハ ピアノ協奏曲第1番
イヴォンヌ・ルフェビュール(ピアノ)
フェルナン・ウーブラドゥ指揮パリ室内管弦楽団、室内管弦楽団
1962年11月13日、パリ・ラジオ・フランス・スタジオ
1957年10月19日、パリ・サル・ガヴォー
モノラル ライブ
※フランスのベテラン女流イヴォンヌ・ルフェビュールによるライブ録音。1962年録音のモーツァルトは、ラジオ・フランスの客席付き大型スタジオ(オーディトリアム)で聴衆を入れた公開収録。モノラル・テープ録音の末期に当たり技術的に成熟しており、ピアノと管弦楽のバランスも良好で鑑賞には全く問題ない。ややマイクがピアノに近く、もう少し膨らみがほしい気もするが、しばしばマイクが楽器に近い(近すぎる?)のはフランス国立放送の録音スタイルの一つだ。ディスク化に当たっては、ピアノの音の硬さを若干和らげるように調整を図った。バッハはモーツァルトより5年前のサル・ガヴォーにおけるライブ。モーツァルトよりも条件が悪いと思われるが音質はほぼ同等で、優秀なエンジニアが担当したのだろうか、ピアノの録り方などはこちらの方が良好。アンドレ・シャルラン辺りが関係しているのかもしれない。いずれも会場ノイズは極小。
イヴォンヌ・ルフェビュールにとってモーツァルトの協奏曲は重要なレパートリーの一つ。第20番ニ短調はフルトヴェングラーとの共演を含め、3種の録音が知られているが、24番ハ短調は当ディスクが現在確認されている唯一の録音。おそらく実演では他のモーツァルトの協奏曲も演奏したと思われるが、残念ながら現状では録音は発見されていない(第20番の未発表録音が1種あるらしい)。バッハもルフェビュールの重要なレパートリー。1950年代に仏VSM、晩年の1970年末にも仏ソルスティスに作品集をレコーディングしていたが、協奏曲のスタジオ録音は残さなかった。
ルフェビュールが20年遅く生まれ、パリ音楽院の教授職に就かなければ、1960年代には40歳代で活発にコンサート活動を行い、フランス・パテEMIやエラート辺りからモーツァルト・ベートーヴェンの協奏曲やソナタ、ショパンやドビュッシー、ラヴェルの諸作品のレコードが続々と発売されていたかもしれず、ちょうどルフェビュールの教え子(サンソン・フランソワ、イモージェン・クーパーなど)のようなキャリアをたどった可能性もあるが、それは本人が望んだものではなかったかもしれない。
伴奏を務めているパリ室内管弦楽団と室内管弦楽団はおそらく同一団体。いずれもファゴット(フランス風にバソンと言うべきか)奏者で指揮者のフェルナン・ウーブラドゥが創設、ウーブラドゥ室内管弦楽団とも呼ばれた団体であろう。メンバーが固定した常設の楽団ではなく、オペラ座やフランス国立放送管、パリ音楽院管などからのピックアップメンバーが演奏会の度に集まって活動していたと思われる。ただ、常設ではないとはいえ名手揃いで、1950年代~1960年代前半にはレコーディングやコンサートを活発に行っており、当ディスクでもウーブラドゥの巧みな指揮もあってか、充実した演奏を繰り広げている。
ルフェビュールは、上記のようにモーツァルトのピアノ協奏曲第24番とバッハのピアノ協奏曲第1番のスタジオ録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音と思われる。
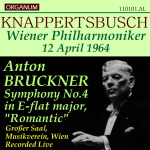
●クナッパーツブッシュ/ウィーン・フィル 音質良好1964年ライブ
ブルックナー交響曲第4番「ロマンチック」
オルガヌム110101AL
ブルックナー 交響曲第4番「ロマンチック」(改訂版)
ハンス・クナッパーツブッシュ指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
1964年4月12日、ウィーン・ムジークフェライン大ホール
モノラル ライブ
※クナッパーツブッシュ最晩年のライブ。歌劇を除けば生涯最後の演奏会となったもので、ウィーン・フィル定期演奏会における録音。アメリカ人コレクター所有テープからのディスク化。当録音は従来から様々なレーベルでCD発売されているにもかかわらず、現状では放送局由来の正規音源によるディスクが未発売という状況にある。収録を行ったであろうオーストリア放送協会(ORF)自身が紛失などにより音源を所有していないか、所有音源に何らかの不備があるのかも知れない。ちなみに第1楽章冒頭でホルンのミスがあるが、これが大きな原因とは考えられない。
当ディスクの音源はエアチェックと思われるが、当時のヨーロッパ(特にオーストリア)の標準的なエアチェック録音を上回る音質。想像ではあるが、欧米の放送局間における交換音源として、ORF由来の音源をアメリカのラジオ局が放送し、それをエアチェック録音したものではないだろうか。
このようにオリジナル音源の音質自体は良好だが、ディスク化に当たっては、ややハイ上がりのバランスのため、イコライジングで調整し、弱音がヒスノイズに埋もれがちだったため、音質を損ねない範囲でノイズを若干低減、放送のために強音にリミッターがかかっていたため、ダイナミックレンジをわずかに広げる処理を行った。結果的に、ストレスなく十分に音楽を鑑賞できる音質となった。なお、前記のホルンのミスは微細なものであり修正していない。
ウィーン・フィルの定期演奏会は公開ゲネプロ1日、本演1日の2回公演だが、当ディスクに聴く本演4月12日は午前11時開演のマチネー(夜は歌劇公演を担当するウィーン・フィルならではの伝統)、プログラムは、ブラームス「ハイドン変奏曲」とブルックナーというもので、「ハイドン変奏曲」の録音も残っている可能性がある。クナッパーツブッシュは当時76歳、椅子に座っての指揮だったと思われるが、当演奏会後、6月にミュンヘンで「ウィンザーの陽気な女房」を1回、7月にもミュンヘンで「フィデリオ」を1回、さらに7月から8月にかけてバイロイトで「パルシファル」を4回指揮しており(これが生涯最後の指揮)、演奏自体に特に衰えは感じず、若干遅めのテンポで、クナッパーツブッシュのブルックナーの完成形を聴くことができる。例によって細かいリハーサルは行っていないと思われるが、指示を入れたオリジナルのパート譜を楽員に事前に配り、楽員にそれを深く理解させることでリハーサル不足を補い、クナッパーツブッシュ独自の演奏を実現したと言われている。ベテラン揃いのウィーン・フィルの楽員だからこそ可能だったとも言えるが、ゼロベースからリハーサルを進めていく現代の指揮者よりも、却って合理的な練習方法かも知れない。ちなみに近年ではスクロヴァチェフスキが同様のスタイルを採っていた。
クナッパーツブッシュが初めてウィーン・フィルを指揮したのは、1929年8月のザルツブルク音楽祭で41歳の時。最近の若手スター指揮者に比べるとかなり遅いウィーン・フィル・デビューだったことになる。またウィーン・フィルとブルックナーの交響曲第4番を初めて指揮したのは1934年11月で、クナッパーツブッシュにとっても交響曲第4番の初指揮だったという。その後は1939年12月、1941年2月、1944年1月、1948年9月、1954年10月と、1964年を含めて7回ほどの演奏機会があった(複数回公演を含むので実際は10数回)。意外に少ないように思われるが、そもそもウィーン・フィルのメンバーは国立歌劇場管弦楽団としての演奏活動が優先され、ウィーン・フィルとしては年10回程度の定期演奏会と夏のザルツブルク音楽祭、それに当時はそれほど多くはなかったツアーに限られており、その点を考慮すると決して少なくない回数と言える。
クナッパーツブッシュは、当ディスク以外にブルックナーの交響曲第4番を、1955年英デッカにウィーン・フィルとスタジオ録音したほか、1944年にベルリン・フィルとライブ録音していた。
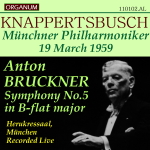
●クナッパーツブッシュ/ミュンヘン・フィル 高音質1959年ライブ
ブルックナー交響曲第5番
オルガヌム110102AL
ブルックナー 交響曲第5番(改訂版)
ハンス・クナッパーツブッシュ指揮ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団
1959年3月19日、ミュンヘン・ヘルクレスザール
モノラル ライブ
※クナッパーツブッシュとミュンヘン・フィルのライブ。10年以上前にバイエルン放送提供の正規音源による国内盤CDが発売されていたが、当ディスクの音源はアメリカ人コレクターの個人所有テープのデジタルコピー。オリジナルは「Reel
to Reel 15Ips (38cm)
Master」とのこと。これは一般に放送局やレコード会社所有のマスターテープのコピーを指すが、門外不出ではないらしく海外のオークションサイトでは数多く出品されている(放送局が不要のテープを売却処分する場合もあるようだ)。当録音はアメリカ国内でコピーされたと言われ、バイエルン放送の音源がアメリカの放送局(ラジオ局)またはVOA(ヴォイス・オブ・アメリカ)などに供給され、その関係者?がコピーしたものと思われる。
オリジナルマスターのコピー(正確にはコピーテープの再コピー)だけに音質は優秀で、既出の国内盤と酷似しているが、ダイナミックレンジやや圧縮されていたり、高音が強調されているなど、コピーに伴うものかアメリカ国内で放送するためかは不明だが、微妙に異なるところもある。ディスク化に当たっては、ヒスノイズ低減のほか、ダイナミックレンジの再拡張、高低音バランスの改善などを行った。いずれにしても音楽を鑑賞する上では全く問題なく、モノラルながら高水準の音質となっている。
当録音はミュンヘン・フィル定期演奏会から。2回公演の2日目でプログラムはブルックナー1曲のみ。当時クナッパーツブッシュは71歳。大病する直前だが活発に演奏活動を行っていた。18日前の3月1日にはミラノ・スカラ座で「さまよえるオランダ人」を指揮(ライブ録音が残っていても不思議ではない)、3月24日にはバイエルン国立歌劇場で同じく「オランダ人」、引き続き同歌劇場で4月1日には「ウィンザーの陽気な女房」、7日には「フィデリオ」、17日にはパリ・オペラ座で「ローエングリン」を指揮と、意外なほどヨーロッパ各地を巡っている。「ほとんどドイツ国内に留まって活動している」というかつての紹介記事は、単なる情報不足と憶測だったのだろう。それでもミュンヘン・フィルはクナッパーツブッシュが最も多く指揮した団体の一つに違いなく、両者の初共演は1923年にさかのぼり、最後は1964年だった。ブルックナーの交響曲第5番については、意外にも1954年6月ミュンヘン・フィル定期演奏会で初めて指揮したと思われ、1957年1月ウィーン・フィル定期演奏会が2回目、当録音が3回目で最後の演奏機会であった。クナッパーツブッシュというと、ワーグナーとブルックナーの大家と言われ、ブルックナーの交響曲を数多く指揮したという印象があるが、第5番に限っては例外で、英デッカにレコーディングを行ったのは偶然だったかも知れない。その意味では当ライブ録音が優秀な音質で残されたことは幸運と言える。
ちなみに疑問となるのは、当演奏は改訂版によっているが、クナッパーツブッシュが1954年に初めて指揮した時点でも、すでに原典版であるハース版(1935年)、ノヴァーク版(1951年)の発表後であり、改訂版を使用した理由が少々理解できない。おそらく第5番以外の4番や8番を以前から改訂版で演奏しており、5番の改訂版使用についても自然の成り行きだったとも考えられるが、4番や8番とともに5番も、ハース版が出版された1935年以前から改訂版を元に研究し、演奏の準備を進めていたのではないだろうか。そして、ようやく演奏会で披露できると判断し、その機会を得たのが1954年頃だったと考えることもできる。断続的ではあろうが、少なくとも20年間準備を行っていたということになり、時間をかけて作品への理解を深めていったのだろう。「原典版には興味がなかった。新作を勉強するのが嫌いだった」というクナッパーツブッシュに対する評価は的外れではないが、演奏記録を参照すると別の事実が見えてくる。フルトヴェングラーによる交響曲第8番のように、演奏の度に使用する版が異なっていた例とは対照的である(こちらも理由はよく分からないが)。
クナッパーツブッシュは上記のように、当ディスク以外にブルックナーの交響曲第5番を、1955年英デッカにウィーン・フィルとスタジオ録音していた。
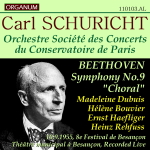
●シューリヒト/パリ音楽院管 1955年ライブ
ベートーヴェン交響曲第9番
オルガヌム110103AL
ベートーヴェン 交響曲第9番「合唱付き」
マドレーヌ・デュビュイ(ソプラノ)
エレーヌ・ブーヴィエ(アルト)
エルンスト・ヘフリガー(テノール)
ハインツ・レーフス(バス)
モントルー音楽祭合唱団
ロベール・メルムー(合唱指揮)
カール・シューリヒト指揮パリ音楽院管弦楽団
1955年9月10日、ブザンソン市立劇場
モノラル ライブ
※第8回ブザンソン音楽祭のライブ。フランス国立放送(RTF)による放送録音のコピーと思われ、英国人コレクター所有の音源からのディスク化。放送自体は生中継だった可能性があり、その範囲では問題なかったとも思われるが、残された録音は独唱・合唱がレベルオーバーで歪みや音割れが多く明らかに失敗。レコーダーの録音レベル設定を誤ったのだろう。オーケストラのみの録音は1950年代中頃の水準を維持しており、RTF録音の難点である残響ゼロで各セクションがブレンドせずにばらばらに響くようなこともなく、適度なホールトーンも入っており及第点と言える状態だった。今回のディスク化に当たっては、歪み・音割れが多い声楽部分をイコライジングやレベル調整、慎重なノイズ処理等々で聴きやすくし、限界はあるものの、オリジナルの状態からはかなり改善できた。ただし、若干の音割れや合唱が飽和している箇所は一部残った。一方、第1楽章のレベル変動(音量が一定時間上下する)は解消、その他のドロップアウト・音飛びも修正、一応は鑑賞に堪える状態することができた。
フランス東部の古都・ブザンソンで開催される音楽祭に、シューリヒトは1950年から1963年まで6回参加した。オーケストラはフランス国立放送管弦楽団とパリ音楽院管弦楽団のいずれかで、1955年はパリ音楽院管とベートーヴェンのエグモント序曲と第9を指揮した。当時フランスではシューリヒト指揮によるベートーヴェンの第9が大変人気があったという。ドイツ・オーストリアではシューリヒトにブルックナーの演奏依頼が多かったことと併せると、シューリヒトに求めたレパートリーが地域によって異なるのが興味深い。また合唱団はパリから呼ばずにスイスのモントルー音楽祭の合唱団が務めている。同合唱団は、前年のモントルー音楽祭でシューリヒト指揮でベートーヴェン第9を演奏しており、経験のある団体を選定したのかも知れない。ちなみにモントルー音楽祭も同月から始まり、シューリヒトも当演奏の4日後には出演している。当時シューリヒトは75歳だったが、元気に演奏活動を行っており、モントルーで9月21日まで3回の演奏会後、27日にはシュツットガルトへ行き南ドイツ放送響を指揮、10月6日と13日にはコペンハーゲンでデンマーク国立放送響を指揮するなど、ヨーロッパ各地のオーケストラを活発に客演指揮していた
シューリヒトとパリ音楽院管はなぜか相性が良く、英デッカや仏HMV(VSM、パテ・マルコーニ)に多くのスタジオ録音を残しているが、実演でも1949年の初指揮以来1961年まで約50回共演し、ライブ録音も残されているはずだが、なぜかLP・CD化されることがなく、当ディスクはその珍しい1枚。パリ音楽院管は気まぐれな性格のオーケストラで、凡庸な指揮者の時は演奏も低レベルだが、優れた指揮者の手にかかると見違えるような素晴らしい演奏を繰り広げたと言われる。ウィーン・フィルと似ているところもあり、スコアを重視し、厳格さや正確さを求める指揮者(ヴァントやショルティなど)とは相性が合わず、楽員の自発性を重んじ、即興性を好む指揮者には合うと言える(ミュンシュはその好例)。シューリヒトもその一人であり、当ディスクの演奏も楽章間の間合いがほとんどなく(独唱者は最初からステージにいたのだろうか)、速めのテンポで一気呵成に進むというまさしくシューリヒト・スタイル。
シューリヒトは、当ディスク以外にベートーヴェンの交響曲第9番を、上記のように1958年仏HMVにパリ音楽院管とスタジオ録音したほか、1954年と1965年にフランス国立放送管、1961年シュツットガルト放送響とライブ録音していた。
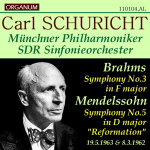
●優秀新音源 シューリヒト/ミュンヘン・フィル、シュトゥットガルト放送響
ブラームス 交響曲第3番、メンデルスゾーン 交響曲第5番「宗教改革」 1963・1962年放送ライブ
オルガヌム110104AL
ブラームス 交響曲第3番
メンデルスゾーン 交響曲第5番「宗教改革」
カール・シューリヒト指揮
ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団
シュトゥットガルト放送(SDR)交響楽団
1963年5月19日、ミュンヘン・ヘルクレスザール
1962年3月8日、シュトゥットガルト・リーダーハレ
モノラル 放送ライブ
※シューリヒトによるブラームスとメンデルスゾーンのライブと放送録音。ドイツ在住のロシア人コレクターからの提供音源。エアチェックではなく放送局保管テープのコピーと思われる。両者とも比較的珍しい音源で、ブラームスはおそらく1990年代初頭の伊メロドラム・レーベルCDが初出。その後は同ディスクのコピーと思われるCDやCD-Rが出ていたが、いずれも高域不足で解像度が低く、混濁気味の音質で1963年録音としては物足りないものだった。一方、当ディスクのオリジナル音源の音質はまるで別物。バイエルン放送による録音と思われるが、高域が伸び解像度も高い鮮明な音質。あまりにも異なる音質のため別演奏のように聞こえるが、各楽章の演奏時間やわずかな会場ノイズも同一で確かに同じ演奏である。バイエルン放送提供の正規音源による他の市販CDと同水準で、鑑賞には全く問題ない。また会場ノイズもほとんどない。一方、メンデルスゾーンは、南ドイツ放送(SDR)が聴衆を入れずに収録した放送録音。こちらも解像度が高く優秀な音質。やや低域不足で高域寄りのバランスだったため、ディスク化に当たってはイコライジングによる若干の調整を行った。こちらも十分鑑賞に堪える。
ブラームスの演奏はミステリアスな録音。記載漏れの可能性はあるものの、現状では演奏会記録に見当たらず、当日の他の演奏曲目も不明。会場ノイズも第1、第2楽章にそれぞれ一回ずつ微弱な咳払いらしき音が聞こえるのみで異常に静か。残念ながら各楽章間のインターバルがカットされているため不明だが、聴衆を入れずに行った放送のための録音のようにも思える。また演奏終了後の拍手があるが、別演奏から付け足された可能性もある。これは初出のメロドラム盤も同様である。
意外なことだが、シューリヒトは長い経歴において、ミュンヘンでは1958~1963年に5回指揮したのみ(仲が悪かったと言われるクナッパーツブッシュの牙城だったことが理由か)。そのうち2回はバイエルン放送響、3回はミュンヘン・フィルだったが、いずれも曲目が異なり当演奏は該当しない。
このような場合、フルトヴェングラーの例に見るように、指揮者やオーケストラ表記が正しいかどうかが問題となるが、当演奏自体は、シューリヒトの他に2種ある同曲の録音と同様、「雑にならない限度いっぱいの一筆書きスタイル」という特徴から、シューリヒトの演奏と判断するのが妥当であろう。オーケストラについては、ヘルクレスザールにおけるバイエルン放送による録音の特徴が共通しており、同放送が管轄する地域のオーケストラと推定できる(主要オケとしてバイエルン放送響、ミュンヘン放送管、ミュンヘン・フィル、バイエルン国立管など)。
ちなみに同曲の第4楽章216小節4拍目、217小節1拍目で、ティンパニがそれぞれcとfを叩いており、これは第二次世界大戦前からの古い伝統を持つオーケストラではよく見られた改変と思われるが、シューリヒト自身は南西ドイツ放送響とのスタジオ録音やシュトゥットガルト放送響との放送録音では行っていない。両オケとも、またバイエルン放送響も戦後の設立であり、あくまで推測だが、オーケストラはミュンヘン・フィル(1893年設立)で間違いないだろう。
これらの状況を総合すると、放送オーケストラではないミュンヘン・フィルが純粋な放送のための録音を行うことは通常はあまりないが、バイエルン放送所属の2楽団のスケジュールの都合等何らかの事情から、ミュンヘン・フィルが起用された放送録音と推定され、会場ノイズが異常に少ないもののわずかながら聞こえる点は、聴衆を入れた公開録音だったと思われる(公開録音の場合、聴衆には静粛を要請されることが多かった)。
シューリヒトの当演奏前後の演奏記録を見ると、5月14日にパリでフランス国立放送管を指揮後、7月3日に仏リヨンで再び同国立放送管を指揮している。この間2か月近く空いており、5月15日以降にパリからミュンヘンに移動して17・18日にリハーサル、19日に当演奏というスケジュールは不可能ではない。当時シューリヒトは82歳と高齢だったが、同年10月28日にはスイス・ルツェルンでブルックナー交響曲第9番ほかを指揮、2日後の31日にパリでベートーヴェン交響曲第9番を指揮するというハードワークをこなしており、まだまだ元気だった。
一方、メンデルスゾーンは聴衆を入れずに行われた純粋な放送録音。2月20日にパリでフランス国立放送管と放送録音を行った後、3月3・4日にウィーンでウィーン・フィルを指揮、7日までにシュトゥットガルトに入り当ディスクの録音を行ったと思われる。その後は18日にフィレンツェで演奏会が予定されていたが、これはキャンセルされ、22・23日にフランクフルトでヘッセン放送響を指揮するという、多忙な客演活動を行っていた。
「宗教改革」はシューリヒトにとっては極めて珍しいレパートリーで、演奏会記録にも記載がない(記録に残るメンデルスゾーンの交響曲は第4番のみ)。オーケストラが指揮者を客演に招く場合、指揮者が提出したレパートリー一覧から、オーケストラ側が選定して依頼することが多いから、シュトゥットガルト放送響が同曲の演奏を求めたのだろう。ちなみにシューリヒト自身は「ブルックナーばかり演奏するのはそういう依頼が多いから。本当は現代音楽(!!)が好きだ」と語っていたという。
「宗教改革」は日本ではあまり人気のある作品とは言えないが、シューリヒトのような魅力的な演奏が聴ければ人気作品となるのではないだろうか。
シューリヒトは当ディスク以外に、ブラームスの交響曲第3番を1962年コンサートホールソサエティに南西ドイツ放送響とスタジオ録音したほか、1954年にシュトゥットガルト放送響と放送録音していた。メンデルスゾーンの「宗教改革」は当ディスクが現在確認されている唯一の録音と思われる。
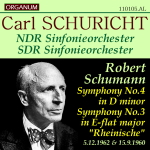
●音質良好 シューリヒト/ハンブルク北ドイツ放送響、シュトゥットガルト放送響
シューマン 交響曲第4番、第3番「ライン」 1962・1960年放送ライブ
オルガヌム110105AL
シューマン 交響曲第4番、第3番「ライン」
カール・シューリヒト指揮
ハンブルク北ドイツ放送(NDR)交響楽団
シュトゥットガルト放送(SDR)交響楽団
1962年12月6日、ハンブルク・ムジークハレ
1960年9月15日、シュトゥットガルト・リーダーハレ
モノラル 放送ライブ
※シューリヒトによるシューマンの交響曲2曲。ドイツ在住のロシア人コレクターからの提供音源。エアチェックではなく放送局保管テープのコピーと思われる。2曲とも聴衆を入れずに行った放送のための録音で、第4番については、北ドイツ放送(NDR)のアーカイブが音源の出所と言われる既出盤があるが(ただし12月5日録音とされている)、複数の購入者のレビューでは、「録音にやや難」「短波放送のラジオをエアチェックしたみたいな音質」と散々な評価がされていた。該当盤の音質がレビューどおりかどうかは不明だが、当ディスクのオリジナル音源の音質はそのようなことはなく、1960年代初頭のドイツの放送局録音としては平均以上の水準にある。聴衆を入れていないためマイクセッティングの自由度が高いという好条件もあり、周波数バランスや解像度などにも不満がない。聴衆がいない分、残響がやや多く、高域が強く出ていたためイコライジングで若干調整したのみで、十分鑑賞に堪える音質となっている。興味深いのは、交響曲第4番(改訂版)は、4楽章を休みなく続けて演奏するように指定されているが、オリジナルの音源は第1・第2楽章が終わるとそれぞれ10数秒のインターバルが設けられていたこと。おそらくレコーダーの切り替えやテープの掛け替え等、放送局側の都合によるものと想像されるが、実際には、余白部分は編集でカットされて放送されたと思われる。そのままディスク化しても放送録音現場のドキュメントとしては面白いが、家庭での繰り返しの鑑賞を考慮して、当ディスクでも同様の編集でカットしている。なお、録音日表記の疑問については後記する。
一方、第3番「ライン」も南ドイツ放送(SDR)の正規音源を元にした既出盤があるが、疑似ステレオ風の残響が付加されるなど余計な編集が加えられており、却って本来の良好な音質を損なっていた。当ディスクのオリジナル音源は、幸い未編集状態で、ほとんど手を加える必要がない良好な音質。ただし、若干高域不足で、楽章ごとに若干録音レベル(音量)に差があり(複数のレコーダーを使用した際の弊害)、一部では楽章の途中でもレベル変動があったため、イコライジング等で慎重に調整した。
ちなみにNDRとSDRの両放送局録音を比較すると、高域がシャープで解像度が高く寒色系のNDR録音、中低域が豊かで暖色系のSDR録音と、北と南で録音傾向が異なる点が興味深い。ただし、これは北と南の地域的な違いよりも録音会場の音響特性によるものが大きいと思われる。
シューマンの交響曲第4番は12月6日録音とされているが、12月5日・6日に2回公演が行われており、メンデルスゾーンのカンタータ「最初のワルプルギスの夜」、ウェーバー「オイリアンテ」序曲、そして交響曲第4番という通常の演奏会であり、両日とも聴衆が入った公演である。当ディスクに聴く会場ノイズが全くなく、楽章間に異常に長いインターバルがある録音は、明らかに聴衆を入れたライブ録音ではない。おそらく公演日前のリハーサルの際か、公演当日の演奏前後に録音されたと推測される。NDRでは当公演の20日後の26日もシューリヒト指揮でフンパーディンクの「ヘンゼルとグレーテル」の公演を行っているが(シューリヒトの貴重な歌劇公演だ)、こちらも残されている録音は明らかに聴衆がいない純粋な放送録音である。当時のNDRでは、放送のための録音と演奏会を分けていたのだろう。
ちなみにシューリヒトはシューマンの交響曲の演奏回数については第2番が突出して多く、次いで第3番、第4番(第1番はなし)という状況で、第4番は1924年ウィースバーデンにおける初指揮を含めても、わずか9回しか取り上げていない(実際には複数回公演があるため12回)。その最後の公演が当演奏という貴重な録音である。
交響曲第3番は、2種の正規スタジオ録音を行うなど第4番よりも若干演奏回数が多く、1918年ウィースバーデンで初指揮の後、生涯を通じて16回(22公演)を数える。長い経歴を考えると意外に少ないように思えるが、これはシューマンの交響曲が20世紀前半まではあまり評価されず、その後、徐々に注目され再評価されるようになった経緯もあるだろう。シューリヒトの演奏回数も、第二次世界大戦前はあまり多くなく、大半は戦後に集中、特に1950年代から急増している。
第3番も先の第4番と同様、SDRによって9月14日と15日に聴衆を入れて公演が行われている。プログラムは、シュテルツェルの合奏協奏曲、ブルッフのヴァイオリン協奏曲第1番(ハンスハインツ・シュネーベルガー独奏、偶然だが1961年までNDR響のコンサートマスターだった)、シューマンのマンフレッド序曲、交響曲第3番というもの。当ディスクの録音は15日の公演前後(おそらく当日の日中)に放送用に録音されたのだろう。
1940年代後半、SDRは放送響のレベルアップのため、シューリヒトに首席客演指揮者の地位を打診したが、当時60歳を過ぎていたシューリヒトは自由な活動を望んで固辞し、より緩やかな関係であれば協力できると応えたという。当ディスクに聴くように、演奏会以外に、放送録音のための演奏まで常時要求されることは負担が大きかったろう。
シューリヒトは、シューマンの交響曲第4番のスタジオ録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音。交響曲第3番は当ディスク以外に、1952年英デッカにパリ音楽院管、1960年コンサートホールソサエティにシュトゥットガルト放送響とスタジオ録音したほか、1955年にスイス・ロマンド管弦楽団とライブ録音していた。

●優秀新音源 ヨハンナ・マルツィ
ベートーヴェン、メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 1954年ライブ
オルガヌム110106AL
ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲
メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲
ヨハンナ・マルツィ(ヴァイオリン)
オトマール・ヌッシオ指揮ルガーノ・スイス・イタリア語放送管弦楽団
オットー・クレンペラー指揮ハーグ・レジデンティ・フィルハーモニー管弦楽団
1954年5月22日、ルガーノ・テアトロ・クアザール(テアトロ・アポロ)
1954年6月26日、アムステルダム・コンセルトヘボウ
モノラル ライブ
※近年急速に再評価が進んでいるハンガリーの女流ヴァイオリニスト、ヨハンナ・マルツィによるベートーヴェンとメンデルスゾーンの協奏曲。それぞれスイス・ルガーノ音楽祭とハーグ・フィルのアムステルダム公演におけるライブ録音。ドイツ在住のロシア人コレクターからの提供音源で、エアチェックではなく放送局保管テープのコピーと思われる。
ベートーヴェンは10年ほど前から海外で既出盤が存在するが、どういう訳かソロヴァイオリンが硬く歪みが多い音質で、マルツィ独特の美音がほとんど聴き取れない残念な音質だった。スイス・イタリア語放送の録音は優秀なものが多く、既出盤は劣化したコピー音源を使用し、さらに劣化した音質を改善するための調整がうまくいかなかったのかも知れない。
当ディスクの音源は、幸いオリジナルの状態でも十分に音質優秀でバランスも良好。マルツィらしい高音の繊細な美音が見事に再現されており、初めて演奏の本来の姿が現れたといえる。良好な音質の一方でオーケストラの非力さが露わになった感もあるが、これは指揮者の責任かも知れない。若干低域が不足気味だったため、わずかにイコライジングで補正したほか、音質を損ねない範囲でヒスノイズの低減を行った。
一方、メンデルスゾーンもいくつかの既出盤があるが、こちらも音質があまり良くないと言われている。本来1950年代中期のオランダの放送局録音は決して低レベルではなく、こちらも既出盤は劣化したコピーかエアチェック音源が使用されたのだろう。当ディスクの音源は、別系統のものと思われ、特別に優秀というわけではないが、1950年代中期の放送録音の水準を上回る音質で、ストレスなく十分に鑑賞に堪える音質である。オーケストラの音量が大きすぎ、ソロヴァイオリンのそれが小さかったため、バランスを若干改善している。なお、一部の資料では6月23日ハーグにおける録音という記載もあるが、より信頼できる資料データに従った。
当ディスクの録音された1954年前後は、ヨハンナ・マルツィが最も活発にレコーディングを行っていた時期に当たる。1952年から1953年にかけてドイツ・グラモフォンにモーツァルトの協奏曲第4番とソナタK.376、ベートーヴェンのソナタ第8番、ドヴォルザークの協奏曲を録音後、翌1954年から英コロンビアとレコーディングを開始、2月15~17日にブラームスの協奏曲、5月1日と6月1~3日にバッハの無伴奏ソナタ第3番、6月9・10日にモーツァルトの協奏曲第3番、メンデルスゾーンの協奏曲(ただし、後者は当時マルツィが発売を承認せず、後年CD化)、7月24・26日にバッハのパルティータ第2番を録音している。このように多忙なレコーディングの合間を縫って、5月に開催されたスイス・ルガーノ音楽祭に参加したことになる。なお、22日という日付は不確定という情報もある(放送日かも知れない)。ちなみにこの年のルガーノ音楽祭では15日にフルトヴェングラーとベルリン・フィルの公演が行われており、ベートーヴェン「田園」、モーツァルトのピアノ協奏曲第20番(イヴォンヌ・ルフェビュール独奏)ほかが演奏されている。マルツィのベートーヴェンとともに当時は当たり前の公演だったかも知れないが、現代の我々から見れば、当時のヨーロッパは何とも豊かな音楽文化に恵まれていたことだろう。
なお、ベートーヴェンの協奏曲の指揮者オトマール・ヌッシオは、イタリア出身の元フルート奏者で、1938年から1968年の長きにわたってスイス・イタリア語放送管弦楽団の首席指揮者を務めた。30年間も主席の地位にあったと言うことは、凡庸な指揮者では到底務まらず、先にオーケストラが非力と表現したが、当時は育成途上にあったのだろう。
メンデルスゾーンは、マルツィが最も得意としたレパートリーの一つでもあり、当ディスクの録音4月前の1月にもケルンでシュミット=イッセルシュテットと放送録音を残している。前述のようにマルツィは同曲を1954年にスタジオ録音したにもかかわらず発売を承認せず、1955年に再録音を行い、こちらが発売されている。得意なレパートリーを完全な形で残したいという意思の表れであろうが、1回目の録音は指揮者との齟齬があったのかも知れない。ちなみに当ディスクの録音はクレンペラーがハーグ・フィルに客演した最後の公演でもあった。
ヨハンナ・マルツィは、ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲のスタジオ録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音。また、メンデルスゾーンの協奏曲は、上記のように、1954年と1955年英コロンビアにスタジオ録音したほか、1954年にライブ録音していた。

●高音質ステレオ・ライブ ケルテス/ロンドン響
シューベルト「未完成」、ドヴォルザーク 交響曲第6番 1966年BBCプロムス・ライブ
オルガヌム110107AL
シューベルト 交響曲第7(8)番「未完成」
ドヴォルザーク 交響曲第6番
イシュトヴァン・ケルテス指揮ロンドン交響楽団
1966年9月1日、ロンドン・ロイヤル・アルバート・ホール
ステレオ ライブ
※将来を嘱望されながら水難事故で早世したイシュトヴァン・ケルテスのBBCプロムナード・コンサートにおける貴重なライブ録音。英国人コレクター所有のエアチェック音源をディスク化したもの。オリジナル音源の音質は、エアチェックとしては最高レベルの高音質で、わずかにヒスノイズが残るほかはノイズレスで、周波数レンジも広く、バランスも良好。BBC所有のマスターテープにも遜色ないのでないかと思われほど。いずれにしても鑑賞上全く不満がない。ディスク化に当たっては、ダイナミックレンジが広大すぎて、家庭でピアニッシモが聞こえるように音量を調整するとフォルティッシモが近所迷惑になるほど過大になるため、コンプレッサーで若干音量を調整しているが、それ以外には手を加えていない。会場ノイズもほとんど皆無で、立ち見の低料金ながら聴衆のマナーの良さは特筆すべきもの。
ケルテスは、1965年から1968年までロンドン響(LSO)の首席指揮者を務めており、BBCプロムナード・コンサート(プロムス)には1965年と1966年に計3回出演した。1966年には2回出演し、そのうちの1回が当ディスクの録音。当日のプログラムは、シューベルト「未完成」、LSOの首席奏者たちが参加したモーツァルトの協奏交響曲K.297B、ドヴォルザークの交響曲第6番というもの。シューベルトとドヴォルザークの交響曲については、それぞれ1962年~1971年と、1963年~1966年にかけて交響曲全集をレコーディングしており、得意とする曲目。モーツァルトも、K.297Bのレコーディングこそ残さなかったものの多くの作品を録音しており同様に得意としていた。
ここでは、後半のメイン・プログラムにドヴォルザークの交響曲第6番を置いたことが興味深い。ドヴォルザークの交響曲は、作曲家の母国チェコは例外だが、国際的には長らく9番と8番ばかりが演奏され、時折7番が加わる程度。6番や5番以前の作品を聴く機会は現在でも多くはない。ドヴォルザークの中期までの交響曲に対する一般的評価は、若書きの発展途上作品というものだが、ケルテスの演奏を聴くと非常に魅力的な曲に思える。演奏次第では、メイン・プログラムとする価値がある作品だということを主張したかったのかもしれない。実際、演奏終了後は大歓声が上がっている。
ただし、ケルテスはロンドンの聴衆にあまり人気がなく、彼のLSO首席指揮者在任中は観客減少に見舞われ、1968年立て直しのためアンドレ・プレヴィンに交代することになったという。しかし、実際には、ケルテスがプログラム決定や客演奏者の選定等、演奏分野の全権限をLSOに求めたことが要因だったとも言われる。かつてフリッチャイがヒューストン響の常任指揮者在任中、楽員の選任権限や新しいコンサートホールの建設(!)要求を行った結果、退任したエピソードを想起させる。ハンガリー出身の指揮者には、セルやライナーと同様、オーケストラを完全に掌握しようという発想があるのかも知れない。
イシュトヴァン・ケルテスは、当ディスク以外にシューベルトの「未完成」を1963年英デッカにウィーン・フィルとスタジオ録音。ドヴォルザークの交響曲第6番を1965年英デッカにLSOとスタジオ録音していた。
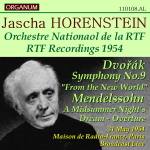
●音質にやや問題あり ホーレンシュタイン/フランス国立放送管 1954年放送ライブ
ドヴォルザーク「新世界から」、メンデルスゾーン「真夏の夜の夢」序曲
オルガヌム110108AL
メンデルスゾーン 劇音楽「真夏の夜の夢」序曲
ドヴォルザーク 交響曲第9番「新世界から」
ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮フランス国立放送管弦楽団
1954年5月31日、パリ・ラジオ・フランス・スタジオ
モノラル ライブ
※ホーレンシュタインとフランス国立放送管による、聴衆を入れたラジオ放送用スタジオ・ライブ。英国人コレクター所有の音源からのディスク化で、オリジナルは放送局所有テープのコピーと思われ、十数年前に海外で発売された同管とのCD9枚組セットには含まれていなかった演奏である。2曲とも基本的には1950年代中期の録音水準を上回り、フランス国立放送録音の欠点である残響に乏しくドライな傾向も少なく、音質自体は良好な状態にある。しかし、ドヴォルザークについては問題があり、一部にテープトラブルと思われるノイズが混入していることに加え、ワウ・フラッターのフラッター(極めて短い周期の音揺れ)がいくつか感じられること。弦楽器のトレモロ部分やフォルテのアタック部分、金管(特にトランペット)の強奏部分に影響が出ているようだ。ただし、その状態が常に続くわけではなく、しかもフラッターが目立ちやすい木管のソロなどでは発生していない。おそらく録音時のトラブルではあれば放送には使用できず、その後音源の保管も行われなかったと思われ、原因はテープの保存環境の不備による経年劣化だろう。前出の9枚組セットから外されたのは、このような音質が理由だったと思われる。ただし、メンデルスゾーンの録音は全く問題ないので、こちらがセットに含まれなかった理由は不明である。
ディスク化に当たっては、音質を損ねないように配慮しつつ、上記ドヴォルザークのフォルテのアタック部分、金管強奏時の歪みを低減すること、テープトラブルによるノイズを除去すること等の改善を行った。一方、一部残ったフラッターは、改善を試みると却って音質劣化の恐れがあるため手を加えなかった。総じてこの種の古いライブ録音を聴きなれたリスナーであれば、鑑賞する上で決定的な障害とはならないと考え、許容いただくことにした。
当日の演奏会は、最初にメンデルスゾーン、次いでシェーンベルクの「浄められた夜」、おそらく休憩を挟んでドヴォルザークというプログラム。興味深いのは楽章間の会場ノイズなどから聴衆がいることは明らかだが、演奏終了後の拍手がないこと。ごく普通のコンサートのように思えるが、前述のように本来の目的はラジオ放送のための録音で、聴衆はあくまでスタジオ見学者の扱いなのだろう(トスカニーニ/NBC響のコンサートも応募による抽選だったことと似ているが、こちらは拍手は許されていた)。
ホーレンシュタインは1933年、当時のナチス政権によりデュッセルドルフ歌劇場音楽監督の地位を追われ、ヨーロッパ各地を転々とした後アメリカに亡命。1949年にヨーロッパに戻った後は、特定の歌劇場やオーケストラのポストを得ることなく客演活動に専念した。ヨーロッパの場合、歌劇場やオーケストラは運営の少なからず部分を政府の援助(予算)に頼ることが多く、音楽監督や常任指揮者の地位にある者は経営にも関与するため、否応なく政府や官僚との関係が深まることになる(アメリカではその代わりに富裕層や企業経営者などスポンサーとの付き合いが重要になる)。ナチス政権による追放を経験したホーレンシュタインにとって、政府や政権と関わることを嫌ったため客演活動に専念したのかも知れない。
客演は、純粋に演奏活動を行うためには好都合だが、逆に特定の歌劇場やオーケストラとの結びつきは弱くなり、限られたリハーサル時間で手際よく(悪い意味では手っ取り早く)演奏会にかけられる状態にまで仕上げる必要があり、長期的なビジョンで自らの演奏芸術を深めるといったには不向きであり、発展途上の若手指揮者が採るべきキャリアではない。幸いホーレンシュタインは、デュッセルドルフ時代に音楽家として完成していたようで、客演活動に必要なレパートリーや効率的なリハーサルの進め方など、十分に体得していたのだろう(往年の巨匠指揮者と言われる人たちは、もれなく地方の歌劇場やオーケストラで修行するなど、同様のキャリアを経験している)。当演奏に聴くメンデルスゾーンとドヴォルザークについては、オーケストラも手慣れたレパートリーであり、難なくそつのない演奏は可能だと思われるが、ホーレンシュタインは、メンデルスゾーンでは、初期ロマン派という枠をはみ出さない範囲でスケールの大きな演奏を、また、ドヴォルザークでは特にスラヴ的な民族性を強調することもなく(彼の父親はロシア人でスラヴ系だ)、速めのテンポでアグレッシブな表現な演奏を進めており、客演指揮を超えた存在感を示していると言える。
ホーレンシュタインは当ディスク以外に、メンデルスゾーンの「真夏の夜の夢」序曲の録音を残さず、当演奏が現在確認されている唯一の録音である。一方、ドヴォルザークの交響曲第9番は、1952年米ヴォックスにウィーン響と、1962年米リーダーズ・ダイジェストにロイヤル・フィルとスタジオ録音していた。

●ホーレンシュタイン/ロンドン響 1961年放送ライブ
ブルックナー交響曲第6番
オルガヌム110109AL
ブルックナー 交響曲第6番(ハース版)
ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮ロンドン交響楽団
1961年11月21日、ロンドン・BBCマイダ・ヴェイル・スタジオ
モノラル ライブ
※ホーレンシュタインとロンドン交響楽団(LSO)による、聴衆を入れずに行われたラジオ放送用スタジオ・ライブ。英国人コレクター所有の音源からのディスク化で、オリジナルはエアチェック録音。テープトラブルと思われるノイズはあるが、エアチェックとしては年代の水準を上回る良好な音質。ちなみにBBCのオリジナル・テープは残念ながら放送後消去(再利用)されて存在しない。当演奏は国内外でCD-R等による数種の既出盤が存在するが、代表的な海外盤は、疑似ステレオ化されており、オリジナルと比べると演奏の印象が異なるようだ。音質は改善されているものの残響が付加されるなど、演出過剰の「やり過ぎ」といえる。一方、その他の既出盤は随所に散見されるノイズ等が未処理で、こちらは「手抜き」といえる。今回ディスク化に当たっては、あくまでモノラルのまま、耳障りなノイズについては、音質を損なうことなく除去することに努め、また、明らかに低域過剰でブーミーだったため、周波数バランスを調整し、中低域の混濁を解消、その結果、見通しの良い本来の演奏がよみがえった。
ホーレンシュタインは、1922年ウィーン響とのデビュー・コンサートでマーラーの交響曲第1番を指揮、1928年独ポリドールにベルリン・フィルとブルックナーの交響曲第7番を録音するなど、若い頃からブルックナーとマーラーを得意としており、演奏依頼も多かったようだ。ただし、当ディスクの第6番は、ブルックナー中期以降の作品の中では不人気で、当録音も1961年に行われたが実際に放送されたのは3年後の1964年。BBC自身も保存すべき音源とは認識しなかったためか、前述のように放送後のテープは消去されてしまった。このように散々な状況ではあったが、奇特なリスナーによってエアチェックされ音源が保管されていたことは幸いであった。
ホーレンシュタインは、前述のように1928年に早くもベルリン・フィルとブルックナーの交響曲第7番をスタジオ録音。第二次世界大戦後も、1955年と1953年米ヴォックスにそれぞれ第8番と9番をスタジオ録音するが(米ヴォックスはチャレンジングなレコーディング・レパートリーを開拓していた)、1950年末に米ヴォックスとの契約終了後、ブルックナーのレコーディングは途絶えてしまう。1960年代以降、ホーレンシュタインは米リーダーズ・ダイジェストや英EMI、英ユニコーンなどとレコーディングを行っているが、リーダーズ・ダイジェストはポピュラー名曲が主体で、EMIは大御所クレンペラーが専属契約を結んでおり、ホーレンシュタインがブルックナーを録音する機会はなかった。ちなみに、クレンペラーも交響曲第6番のレコーディングを度々希望していたが、プロデューサーのウォルター・レッグに売れ行きが見込めないと拒まれ、レッグ引退後にようやく録音にこぎ着けたというエピソードが残っている。結局、EMIとユニコーンには、もう一つの得意のレパートリーであるマーラーを数曲録音したのみとなり、今日聴くことができるホーレンシュタインのブルックナーは、大半が放送やライブ録音という状態となっている。
マーラーの再評価が1960年代後半から始まった一方、ブルックナーについては、本国ドイツ・オーストリア以外では再評価が1970年代以降と遅れた。1973年に75歳で亡くなったホーレンシュタインがさらに5年でも長生きすれば、ブルックナーの新たなスタジオ録音が実現していたに違いない。
ホーレンシュタインは当ディスク以外に、ブルックナー交響曲第6番を1968年にイエーテボリ響とライブ録音していた。

●マグダ・タリアフェロ 1955・1958年パリ・ライブ
モーツァルト ピアノ協奏曲第26番、サン=サーンス ピアノ協奏曲第5番
オルガヌム110110AL
モーツァルト ピアノ協奏曲第26番「戴冠式」
サン=サーンス ピアノ協奏曲第5番「エジプト風」
マグダ・タリアフェロ(ピアノ)
フェルナン・ウーブラドゥ指揮パリ室内楽演奏協会管弦楽団
ポール・パレー指揮フランス国立放送管弦楽団
1955年3月27日、パリ・サル・ガヴォー
1958年4月21日、パリ・シャンゼリゼ劇場
モノラル ライブ
※往年の名女流ピアニスト、マグダ・タリアフェロによる協奏曲のライブ。いずれもフランス国立放送による収録で、英国人コレクターからの提供音源。エアチェックではなく、放送局(またはINA=国立視聴覚研究所)保管音源のコピーと思われる。1955年のモーツァルトは年代相応の録音。特に優秀というわけではないが、ピアノはクリアに録れており、オーケストラは小編成ということもあり解像度も十分。ピアノとオーケストラのバランスも良く、音楽を鑑賞する上で不満はない。一方サン=サーンスは、年代の水準を上回る優秀録音で1960年代中頃の録音に匹敵。このままステレオ化しても十分通用する音質。シャンゼリゼ劇場におけるフランス国立放送管による録音の中は、時折、驚くほど優れた録音があるが当録音もその一例。名録音エンジニアのアンドレ・シャルラン辺りが協力していたのかも知れない。
マグダ・タリアフェロは、第二次世界大戦前から多くのレコーディングを行っており、古くからの音楽愛好家には説明を要しないほど著名な存在。パリ音楽院を中心とするフランス流派の教育を受けた女流ピアニスト=いわゆるグラン・ダーム(grande
dame、貴婦人・名声のある女性の意)の代表格といえる。ギオマール・ノヴァエスとはブラジル出身で2歳違い、パリ音楽院で学んだということで共通点も多いが、米ヴォックス・レーベルに大量の録音を行うなど、アメリカでの活動が活発だったノヴァエスに対し、タリアフェロはパリ音楽院で教えるなど、パリ(と故郷ブラジル)が活動の中心だった。当ディスクに聴くモーツァルトとサン=サーンスの協奏曲はそれぞれスタジオ録音を残しており、得意とするレパートリー。現代の日本からは想像できないが、サン=サーンスのピアノ協奏曲5曲は、古くからのフランス系ピアニストにとっては、ベートーヴェンの協奏曲5曲と同格の重要なレパートリーで、コンサートでも頻繁に演奏されていたようだ。ただし、タリアフェロはモーツァルトとサン=サーンスばかりではなく、パリでベートーヴェンの協奏曲全曲演奏会で好評を得たり、米カーネギーホール・デビューの際にはシューマンの協奏曲を演奏するなど、これらの作品も得意としていたという。
先に第二次世界大戦前から活発にレコーディングを行ったと記したが、戦後も1960年代初頭までは仏デュクレテ・トムソン、蘭フィリップス、仏コロンビアなどに断続的に録音を行った。ただし、1962年に仏エラートにフランス作品のリサイタル盤を録音後は、80歳になって1972年母国のブラジル・エンジェルにヴィラ・ロボスとショパンの作品集をレコーディングするまで10年ほど空き、その後は、ブラジル・ロンドンやブラジル・コパカバーナ(これはライブ盤)など自国レーベルを中心に録音活動を続け、ラスト・レコーディングは88歳時の米(独?)CBSへの連弾集であった。タリアフェロは1960年代以降もパリを中心に演奏活動を頻繁に行っており、ステレオLPが登場したレコード産業の興隆期になぜかレコーディングの機会がなかったが、1960年代初頭のフランスでは、マイナー・レーベルの淘汰が進む一方、メジャー・レーベルが巨大アメリカ市場を意識したスター・システムを確立しつつあった時期でもあった。このためメジャー・レーベルは、アメリカで人気があり、若く元気で頻繁に演奏旅行が可能で、しかもレコーディングに協力的な演奏家を重用した。当時70歳を迎え、パリ音楽院教授としての教育活動に一定期間縛られ、1940年代以降アメリカではコンサートを行っていなかったタリアフェロにとって、メジャー・レーベルの「営業方針」と合わなかったことが、録音から遠ざかった大きな理由かも知れない。これは、ヴラド・ペルルミュテールやイヴォンヌ・ルフェビュール、マルセル・シャンピなどパリ音楽院で教えていた他の名ピアニストにも共通していた。
なお、モーツァルトの伴奏を担当するウーブラドゥ指揮のオーケストラ名は、ウーブラドゥ室内管弦楽団、パリ室内管弦楽団、単に室内管弦楽団と称されるなど様々だが、実態はウーブラドゥが主催する同一団体。専属奏者はおらず、ウーブラドゥが演奏会の度にフリーランスやパリ音楽院管、フランス国立放送管、パリ・オペラ座管などの演奏者を集めて編成していたと思われる。ただし、各パートのトップなど何人かはレギュラーメンバーで、優秀な奏者が揃っていたようだ。
マグダ・タリアフェロは前述のように、モーツァルトのピアノ協奏曲第26番を1930年仏デッカに、サン=サーンスのピアノ協奏曲第5番を1953~1954年蘭フィリップスにスタジオ録音していた。
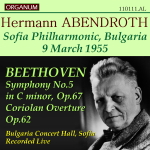
●アーベントロート/ソフィア・フィル 1955年ブルガリア・ライブ
ベートーヴェン交響曲第5番、コリオラン序曲
オルガヌム110111AL
ベートーヴェン 交響曲第5番、コリオラン序曲
ヘルマン・アーベントロート指揮ソフィア・フィルハーモニー管弦楽団
1955年3月9日、ブルガリア・コンサート・ホール、ソフィア
モノラル ライブ
※巨匠アーベントロートがブルガリアのソフィア・フィルを客演した際のライブ録音。ドイツ在住のロシア人コレクターによる提供音源。オリジナルはブルガリア国営放送によってラジオ放送用にテープ録音されたもので、提供音源は放送局保管音源のコピーと思われる。1955年当時のブルガリア国営放送の録音技術水準は不明だが、当録音は優秀とは言えないものの決して貧弱な音質ではなく、1940年代末~1950年代初頭のドイツの放送録音と同等で、ノイズレスでバランスも良く、少なくともアーベントロートの解釈を十分理解でき、鑑賞上の不満はない。第二次世界大戦後ブルガリアが社会主義化され、ソ連や録音技術では先進的だった東独、チェコなどから録音機器や技術を導入したと想像される。なお、おそらく放送のために拍手がカットされているほか、会場ノイズはわずかに数カ所聞こえるが、微少な音で鑑賞の妨げにはならない。
なお、当音源は20年?ほど前にブルガリアのレーベルによってCD化されているが、サラウンドステレオ的な残響(というよりは過大なエコー)が付加された異様なサウンドだった。幸い当ディスクの提供音源にはそのような不自然な残響はなかったが、厳密に聴くと微少な残響が付加されていた。第二次世界大戦の結果、旧ソ連が戦利品としてドイツ帝国放送からフルトヴェングラーの演奏を含む大量の録音テープを押収。その後、1987年にオリジナルではないコピーテープ20本が自由ベルリン放送に返還された際、多くのテープに残響が付加されていたことはよく知られている。おそらくラジオ放送を行う際に、古い録音を聞きやすくするため放送局が付加したと思われるが、アーベントロートによる当演奏も、ソ連の放送技術の影響下で同様の措置が執られたと想像される。
今回のディスク化に当たっては、録音会場のオリジナルの残響と後に付加された残響を切り分けることは困難なため、若干残響の長さを切り詰めることで、より原音に近づけるべく処理を行った。
アーベントロートは第二次世界大戦後、社会主義化された東独のライプツィヒを中心に活動した結果、コンヴィチュニーとともに同国を代表する指揮者として、ソ連や東欧諸国などへの客演を盛んに行った。近年もポーランド訪問時のベートーヴェン交響曲第7番などの珍しい録音がCD化されており、当ディスクに聴く第5番も、第二次世界大戦前にスタジオ録音を行っているが、戦後に限ると現在確認されている唯一の録音である(未発表録音が一種あるようだが詳細不明)。ソフィア・フィルはブルガリアを代表するオーケストラではあるものの、国際的には決して一流の団体とは言えず、ホルンなどに技術的なほころびも目立つが、ブルガリアは大歌手などの有名演奏家を輩出した音楽的伝統があり、オーケストラについてもアーベントロートの演奏意図を十分に理解し対応する音楽性を持っていると言える。なお、当ディスクのプログラムでは一回の演奏会としてはやや短く、おそらくコリオラン序曲の後に、協奏曲など1作品が演奏されたと思われる。こちらの発掘も期待したい。
アーベントロートというと、ライプツィヒ放送響とバイエルン放送響を指揮した2種のブラームス交響曲第1番の「怪演」により、破天荒な解釈を行う指揮者というイメージが強いが、ベートーヴェン交響曲第9番の数種の録音に聴くように、多くの場合、剛直かつスケールが大きいドイツの巨匠指揮者の典型と言える。当ディスクに聴く2曲も、亡くなる前年ではあるが、脳卒中による急死だったため、当ディスクでも幾分速めのテンポで剛直な演奏を行っており衰えは感じない。
アーベントロートは、当ディスク以外にベートーヴェンの交響曲第5番を1937年独オデオンにベルリン・フィルとスタジオ録音したほか、コリオラン序曲を1949年にライプツィヒ放送響と放送録音していた。

●マグダ・タリアフェロ/1957・1955年パリ・シャンゼリゼ劇場リサイタル
シューマン「謝肉祭」、ショパン「バラード第4番」ほか
オルガヌム110112AL
シューマン「謝肉祭」
ショパン バラード第4番、マズルカ第15番、華麗なる大ポロネーズ
ドビュッシー「月の光」
ラヴェル「道化師の朝の歌」
マグダ・タリアフェロ(ピアノ)
1957年6月5日、1955年2月28日、パリ・シャンゼリゼ劇場
モノラル ライブ
※往年の名女流ピアニスト、マグダ・タリアフェロによるパリ・シャンゼリゼ劇場におけるリサイタルのライブ。英国人コレクターからの提供音源。シューマンとショパンが1957年、ドビュッシーとラヴェルが1955年の収録で、前者はフランス国立放送の保管テープのコピーと思われるが、後者はエアチェックのようだ。両者ともリサイタル全曲の録音が残されているどうかは不明。なお、「華麗なる大ポロネーズ」は前半の「アンダンテ・スピアナート」を欠いた形で演奏されたようだ。
シューマンとショパンのオリジナル音源の音質は、当時のフランス国立放送の録音傾向が良くも悪くも表されたもので、ノイズもなく解像度はそれなりに高いが、ドライで潤いというかデリカシーに欠け、しかも使用ピアノはスタインウェイと言われているにもかかわらず、高域不足で同社製ピアノらしい輝かしさもなく、特にショパンにはふさわしくない音質。ディスク化に当たっては、周波数帯域を拡大し、イコライジングによって周波数バランスを調整するなど音質改善を図った結果、本来の演奏の姿がよみがえった。また、バラード第4番には、客席からファスナー?を開閉するような原因不明のノイズが4カ所あったが、音量が小さく目立たない1カ所を除き、音質を損ねることなく除去した。
一方、1955年録音のオリジナル音源の音質は、1955年のエアチェックとしてもやや物足りない音質。受信状態は悪くなかったようだが録音機材が貧弱だったためか、やや濁った音質で強音では割れ気味。ただし適度に残響を含み、1957年録音よりも周波数バランスが良く、ライブ演奏らしい雰囲気は豊か。ディスク化に当たっては、ピアノ音をクリアにして明確化すること。割れ気味の強音の改善を行った。オリジナルの音質の限界もあり、劇的な改善は果たせなかったが、一応は鑑賞に堪える状態となった。
なお、1957年録音はタリアフェロの故国ブラジルで限定発売された書籍の付録CD?に収録、1955年録音もかつてブラジルでCD化されていたが、いずれも当ディスク化のような音質改善は行われていないと思われる。
当録音の1955~1957年は、タリアフェロが62歳から64歳にかけての円熟期。1955年にはショパン・コンクールの審査員に選出、1957年にはザルツブルク・モーツァルテウム音楽院の講師に招聘、パリではマグダ・タリアフェロ国際ピアノコンクールが開催されるなど、パリ音楽院における教育活動を併せて多方面で活躍していたが、演奏活動についても、毎年シャンゼリゼ劇場でリサイタルを行い、フランス国立放送管ほかパリのオーケストラと共演するなど、充実した日々を送っていた。
詳しい曲目は不明だが、1957年のリサイタルは、ベートーヴェン、シューマン、ショパン作品を、1955年は、シューベルト、ブラームス、モンポウ、グラナドス、ドビュッシー、ラヴェル作品が演奏された。おそらくレコーディングも行った得意の曲目を取り上げたものと思われるが、当ディスクの曲目でも「華麗なる大ポロネーズ」「道化師の朝の歌」以外はスタジオ録音を残している(有名曲「道化師の朝の歌」のスタジオ録音が存在しないのは意外だ)。当ディスクには含まれていないが、リサイタルでグラナドスやモンポウを取り上げている点は、今日の日本のコンサート・プログラムとは時代や文化的背景の相違を感じる。
毎度のことながら、パリで活躍したフランス系女流ピアニスト(タリアフェロはブラジル生まれながら両親はフランス人)というと、典雅・優美というイメージを持ちやすいが、当ディスクに聴く「謝肉祭」などは、不要な情緒を排した極めて即物的・ピアニスティックな演奏。それにもかかわらず無味乾燥には陥らないという、巧みなバランスを保っており、指が早く回るだけの若手演奏家とは異なる老練さを感じる。
ちなみにタリアフェロは、第二次世界大戦前78回転SPレコード時代の日本でも人気があり、当時「清新な演奏を行う」という評価を得ていたようだ。
マグダ・タリアフェロは当ディスク以外に、シューマンの「謝肉祭」を1953年蘭フィリップス、マズルカ第15番を1972年ブラジル・エンジェル、ドビュッシーの「月の光」を1951年仏デュクレテ・トムソンにそれぞれスタジオ録音したほか、シューマンの「謝肉祭」とショパンのバラード第4番を1979年にライブ録音していた。
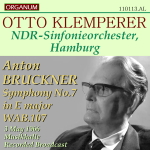
●優秀録音 クレンペラー/ハンブルク北ドイツ放送響
ブルックナー交響曲第7番 1966年放送ライブ
オルガヌム110113AL
ブルックナー 交響曲第7番(ノヴァーク版)
オットー・クレンペラー指揮ハンブルク北ドイツ放送交響楽団
1966年5月3日、ハンブルク・ムジークハレ
モノラル スタジオ放送ライブ
※クレンペラー/ハンブルク北ドイツ(NDR)放送響によるブルックナー交響曲第7番。ドイツ在住ロシア人コレクターからの提供音源。エアチェックではなく、放送局保管音源のコピーと思われる。1966年というと、英BBCやフランス国立放送などはステレオ録音を幅広く導入していた時期だが、当録音はモノラル。ドイツ(当時は西ドイツ)の放送局は、なぜかステレオ放送の導入が1967~1968年頃と遅れた。ドイツは、1930年代末にテープレコーダーを実用化し、第二次世界大戦中の1940年代には実験的にステレオ録音が試みられており技術的には進んでいたはずだが、放送規格の決定や設備の導入・更新、聴取者の要望の有無など、様々な理由があったと思われる。
ただし、当録音はモノラルではあるものの音質は極めて優秀。聴衆を入れずに行われた放送のための録音で、当然ながら会場ノイズは皆無。マイクセッティングの制約もなかったためかバランスも申し分なく、このままの音質でステレオ化すれば1970年代の録音としても通用する水準。左右へのステレオ的広がりに乏しいだけで、鑑賞には全く不都合はない。
なお、当音源は10数年前に海外盤CDが出ているが、音質的にはあまり評価されたかったようだ。当音源もオリジナルの状態では、ヒスノイズがやや目立っていたが、既出盤はヒスノイズと併せて高域の音楽部分を削ってしまい、高域不足の冴えない音質となったと想像する。今回ディスク化に当たっては、高域の音楽成分を欠落を防ぎつつ慎重にヒスノイズのみを低減した。また、既出盤は第3楽章中間部にノイズと音飛びが発生していたが、当音源には存在せず、おそらく当音源と既出盤は出所が異なるようだ(既出盤の音源はNDRが出所らしいが、当ディスクの音源の出所は南ドイツ放送所有のコピーテープと推測される)。本家NDRが所有するオリジナル・テープは経年劣化で痛んだのだろう。
クレンペラーは1966年、当ディスクの録音時は80歳だったが(直後の5月14日に81歳になった)、1月から2月にかけてニュー・フィルハーモニア管と英EMIにレコーディング(イェフディ・メニューイン独奏でベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲)および同管とコンサート、3月にはケルン放送響、4月にはバイエルン放送響、5月にはNDR(当ディスクの録音)、同月ベルリン・フィルとコンサート、6月から7月にかけてニュー・フィルハーモニア管と英EMIにレコーディング(モーツァルトの歌劇「ドン・ジョヴァンニ」全曲)と、高齢とは思えない旺盛な演奏活動を行っていた。
NDRへの客演では、ブルックナーのほかにモーツァルトの交響曲第40番も録音されたが、クレンペラーにとってはNDRとの最後の共演となった。また、ブルックナーの交響曲第7番についても現在7種確認されているクレンペラーの録音のうち、最後の録音である。ただし、最後の録音であっても演奏時間が最も長く、テンポが遅くなるわけでもないところがクレンペラーらしいところで、使用する版の違いもあるが7種のうちでは4番目の演奏時間となっている。当ディスクの録音の価値は、シュミット=イッセルシュットによって鍛えられたドイツのオーケストラとの演奏が、好条件の録音環境の元で優秀な音質で残されたことにある。
クレンペラーは、1954年に英EMI(コロンビア)と録音契約を締結後、幾度となくブルックナーの録音を希望したが、当時プロデューサーだったウォルター・レッグに「今はまだその時期ではない」と拒まれ続けた。当時は独墺圏(とオランダ)を除けば、ヨーロッパ各国さらには巨大レコード市場のアメリカではブルックナーへの理解が進んでおらず、売り上げの見込みが立たないことが大きな理由だったが、交響曲第7番に関しては例外的に、1960年という比較的早い時期にスタジオ録音が実現している。アメリカのメジャー・オーケストラでも第4番と第7番だけは、かろうじてレパートリーとして定着しており、そのような理由から録音が実現したのだろう(米CBSコロンビアがブルーノ・ワルター/コロンビア響で実現したブルックナー録音も第4番と第7番、第9番だった)。
クレンペラーはブルックナーの交響曲第7番を、前記のように1960年フィルハーモニア管と英EMIにスタジオ録音したほか、1955年BBC響、1956年バイエルン放送響、1958年ウィーン響、同じく1958年ベルリン・フィル、1965年ニュー・フィルハーモニア管とライブ録音していた。
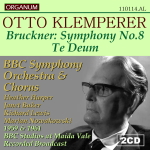
●音質良好新音源 クレンペラー/BBC響ほか
ブルックナー交響曲第8番、テ・デウム 1959年・1961年放送ライブ
オルガヌム110114AL
ブルックナー 交響曲第8番(ハース版)、テ・デウム
ヘザー・ハーパー(ソプラノ)、ジャネット・ベーカー(メゾ・ソプラノ)
リチャード・ルイス(テノール)、マリアン・ノヴァコフスキ(バス)
オットー・クレンペラー指揮BBC交響楽団・合唱団
1959年10~12月頃、1961年1月12日、ロンドン・BBCマイダ・ヴェイル・スタジオ
モノラル スタジオ放送ライブ
※2枚組。クレンペラー/BBC響ほかによるブルックナー交響曲第8番とテ・デウム。英国人コレクターからの提供音源。2曲とも英BBC放送のエアチェックと思われる。2曲とも聴衆を入れずに行われた放送のための録音で、交響曲第8番については後述するが、今まで1964年2月2日録音としてディスク化されていた音源。ただし、既出盤はヒスノイズが非常に多く、ドロップアウト(音飛び、音切れ)が頻発、録音テープの劣化によるポップノイズが散見されるなど、鑑賞に堪える音質ではなかった。当ディスクの音源は他のリスナーによる別音源か、既出盤音源の数世代前のコピー元オリジナルまたはそれに近い音源と思われ、わずかにヒスノイズが残るもののドロップアウトもなく、1950年代末の放送録音の水準を上回る良好な音質。ストレスなく音楽を楽しめる。先に1964年録音と誤記されていたと述べたが、1964年に放送が行われエアチェックされたらしく、当時は、高価ではあるものの家庭用の高性能テープレコーダーが普及していた時代であり、BBCの好録音に加え、高音質の音源が残された理由も理解できる。ディスク化に当たっては、第1・第2楽章に比べて第3・第4楽章の録音レベルが高かったため(長大な作品だけに2台のレコーダーで録音したのだろう)、音量を揃えたほか、周波数レンジを若干拡大し高音域を伸ばす作業を行った。テ・デウムは交響曲を上回る良好な音質で、交響曲よりも2年後の録音という技術の進歩を感じる。ディスク化に当たってはほとんど手を加える必要もなく、ヒスノイズを若干低減する処理のみ行った。両者ともBBCの録音であるから、派手さのない堅実な録音ではあるが、情報量は豊富で手慣れた職人的巧さを感じる。
クレンペラーは1958年10月、チューリヒの自宅で寝タバコによりシーツが燃えて大やけどを負った。一時は重体となるほどで、同年予定されていたバイロイト音楽祭(「マイスタージンガー」)やオランダ音楽祭(「トリスタンとイゾルデ」)など重要公演を含むすべての公演のキャンセルを余儀なくされた。皮膚移植を繰り返すなどの治療の結果、翌1959年7月頃にはようやく回復し、9月のルツェルン音楽祭に出演し約1年ぶりに指揮台に復帰。10月1日からは英EMIにフィルハーモニア管とモーツァルトの「ドン・ジョヴァンニ」のレコーディングを開始、ただし、直後に一時的に体調が悪化(急性良性心膜炎と言われる)、一部録音したのみで4日で降板(ジュリーニが代役でレコーディング)。短期間の療養後、22日から29日かけてフィルハーモニア管とベートーヴェンの交響曲第5番、第3番、序曲をレコーディング。11月にはロイヤル・フェスティバル・ホールでベートーヴェン・フェスティバルが開催され、クレンペラーは交響曲全曲のほか、序曲や3曲のピアノ協奏曲、ヴァイオリン協奏曲など全8回のコンサートを指揮している。
当ディスクに聴くブルックナーの交響曲第8番は、1959年のBBCによる放送録音だが、録音月日が特定されておらず、上記クレンペラーの行動記録(+療養期間)から推測すると、ロンドン滞在時期の10月以降の録音と思われる。ただし、10月は病気やレコーディングで余裕がなく、11月以降がより正確かも知れない。
なお疑問点として、当録音含めて現在3種確認されているクレンペラーによる交響曲第8番の録音について、1957年ケルン放送響への客演と、1970年英EMIへのスタジオ録音ではノヴァーク版を使用しており、ケルン放送響への客演2年後の当録音のみハース版を使用していること。理由は不明だが、もしかすると録音年は1959年ではなく1957年以前である可能性もある。一方で、レジナルド・グッドールが1969年にBBC響と同曲を演奏した際もハース版を使用する一方、1971年に第7番、1974年に第9番を同響と演奏した際にはノヴァーク版を使用しており、BBC響側の当時の事情(パート譜を用意できなかったとは考えられないが)があるかも知れない。いずれにしても今後の調査・研究が待たれる。
クレンペラーは、英EMIと長期のレコーディング契約を締結後、当初からブルックナーの録音を希望したが、プロデューサーのウォルター・レッグに、ブルックナーに対する理解が遅れていた(要は人気がない)英米市場における販売面のリスクを理由に拒まれた。結果的には1960年に第7番の録音が実現、1970年までに第4番から第9番まで主要作品の録音を残すことが出来たが、希望が叶わない1950年代には「放送であれば英国で演奏も録音もできる」と考えたか、BBC響とは1955年に第7番、前述のように録音年にやや疑問はあるが1959年に当ディスクに聴く第8番、1961年第6番を録音。この第6番と同じ日に当ディスク収録のテ・デウムも録音された。言わば英国におけるブルックナー不遇の時期の演奏・録音と言える。
クレンペラーは前述のように、当ディスク以外にブルックナーの交響曲第8番を1970年英EMIにスタジオ録音したほか、1957年にケルン放送響と放送録音していた。一方、テ・デウムはスタジオ録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音である。
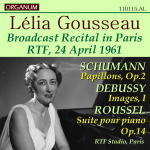
●レリア・グソー スタジオ・ライブ 1961年
シューマン、ドビュッシー、ルーセル
オルガヌム110115AL
シューマン「蝶々(パピヨン)」
ドビュッシー「映像第1集」
ルーセル ピアノのための組曲
レリア・グソー(ピアノ)
1961年4月26日、パリ・RTF(ラジオ・フランス)・スタジオ
モノラル スタジオ放送ライブ
※フランスの女流レリア・グソーによる放送スタジオ・ライブ。英国人コレクターからの提供音源だが、エアチェックではなく放送局保管音源のコピーと思われる。フランス国立放送パリ・アンテルがラジオ放送用に聴衆を入れずに録音したもので、聴衆がいないためマイクセッティングの制約もなく、モノラルながら当時としては極上の音質。バランスも良好で、このままステレオ化すれば1960年代初頭のメジャー・レコードのLP録音と同等の水準。鑑賞する上で全く不満はない。ディスク化に当たっては、シューマンのみ録音レベルが高いため調整したほか、曲間の一部に録音テープの経年劣化による微細なノイズが生じていたため、音質を損ねることなく低減した。
レリア・グソー(1909~1997)は、音楽家の両親の元にパリで生まれ、9歳でパリ音楽院に入学、16歳からラザール・レヴィのクラスで学び、1925年にプルミエ・プリを獲得後、演奏活動を開始。その間、1937年の第3回ショパン・コンクールで第12位入賞(原智恵子が参加した年でもある。第1位はヤコフ・ザークだったが上位をロシア・東欧系が占め、モニク・ドゥ・ラ・ブリュショルリでさえ第7位と、フランス系ピアニストには辛い順位付けだった)。第二次世界大戦後の1952年には初のアメリカ公演を行い、ニューヨーク・フィルやボストン響などと共演、さらには南アフリカやモロッコ、アルジェリア、トルコで公演するなど、1950年代には欧米を中心に幅広く演奏活動を行った。レコーディングも多くはないが、1950年代に蘭フィリップスや独テレフンケン、仏ヴェガなどに録音を残している。コンサート・ピアニストとしてのレパートリーは広く、コンクールに参加したショパンをはじめ、当ディスクに聴くシューマン(フィラデルフィア管と協奏曲で共演)、ベートーヴェン(ボストン響と「皇帝」で共演)、ブラームス(近年協奏曲第1番の放送ライブがCD化された)などスタンダードな作品から、当然ながら自国フランスの作品、テレフンケンに録音したファリャなども含まれていた。
ただし、グソーは1960年代に入ると1961年から1978年までパリ音楽院、その後はエコール・ノルマルで教育に携わるなど、演奏よりも教育活動の比重が増していった。20世紀初頭前後生まれのフランス出身ピアニストの多くのキャリアに見られる傾向で、50歳代を過ぎる頃から後進の育成に関心が移るのかも知れない。その結果、グソーについて言えば、録音技術が向上し、レコード産業が隆盛を極めた1960年代以降のLP発売を前提としたスタジオ録音が乏しく(というよりもおそらく皆無)、レコードのみで情報を得ていた日本の音楽愛好家にとっては、ほとんど未知の存在となってしまったと言える(未確認だがテレフンケン録音が日本で発売されていたという情報もある)。その一方で、グソーはパリ音楽院で木村かをり(故・岩城宏之夫人)を教えるなど、フランスで学んだ日本人ピアニストにとっては親しい存在だったようだ(グソーの主な教え子にはアンヌ・ケフェレック、エミール・ナウモフ、パスカル・ドヴォワイヨンなどがいる)。
また、主催者など詳細は不明だが、グソーは1939年にルーセル賞を受賞するなど、ルーセルを主要レパートリーとしており、先のフィリップス録音ではピアノ協奏曲を録音したほか、仏マイナーレーベルにルーセル作品のみのLPを1枚録音している。当ディスクでもルーセル作品をリサイタルの最後に置くなど、重要視していることが理解できる。ルーセルというと、日本では印象派期の作品「蜘蛛の饗宴」ばかりが有名で、それに新古典期の「バッカスとアリアーヌ」、やや晦渋な交響曲が知られるのみであり、人気がある作曲家とは言えないが、当ディスクに聴くグソーのような自信に満ち、しかも手慣れた演奏を聴くと、ルーセルに対する評価も変わってくるように感じる。
レリア・グソーは当ディスク以外に、ルーセルの組曲を1950年代中頃仏プレイヤードにスタジオ録音していた。一方、シューマン「蝶々」とドビュッシー「映像第1集」は当ディスクが現在確認されている唯一の録音と思われる。

●画期的音質改善
フルトヴェングラー/ベルリン・フィル 1954年トリノ・ライブ
ブラームス交響曲第3番、ワーグナー「トリスタンとイゾルデ」ほか
オルガヌム110116AL
ブラームス 交響曲第3番
ワーグナー 楽劇「トリスタンとイゾルデ」から
第1幕への前奏曲と「愛の死」
ウェーバー 歌劇「オイリアンテ」序曲
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
1954年5月14日、トリノ・イタリア放送協会オーディトリアム
モノラル ライブ
※フルトヴェングラー/ベルリン・フィルによる1954年トリノ公演のライブ録音。アメリカ人コレクターからの提供音源。演奏会はイタリア放送協会(RAI)によってテープ収録されたが、ラジオ放送終了後、当時は高価だった録音テープを再利用するため、「パデローニ」(Padelloni=フライパン、鍋、皿という意味)と呼ばれる33・1/3回転のアセテート・ディスクにダビングして保存された。パデローニは、RAIがイタリア国内の電機メーカーと協力の上1940年代に開発したアセテート・ディスク・レコーダーで、ディスク・サイスは不明だがおそらく16インチ程度(LPの2倍の大きさだったという情報もあるが誇張と思われる)、センター・スタートで連続15分程度の録音が可能だった。テープレコーダー導入以前、15分以上録音する場合は2台のレコーダーで2分間ほど重複して録音し、放送する際には1000分の1秒単位で連結ポイントを探り出して連続再生したというが、大変な労力だったろう。テープレコーダー導入後は、前述したようにテープ音源のバックアップや保存のために活用され、1950年代末まで稼働していた。
5月14日のコンサートは、ウェーバー「オイリアンテ序曲」に始まり、ブラームスの交響曲第3番、休憩を挟んで、当ディスクには含まれないがR・シュトラウス「ティル・オイゲンシュピーゲルの愉快ないたずら」、ワーグナー「トリスタンとイゾルデ」「第1幕への前奏曲と愛の死」、アンコールとして「タンホイザー序曲」が演奏された(アンコールは録音が残っていないらしい)。
当演奏は、パデローニから復刻したブラームスが1975年米ディスココープによりLPとして発売されて以降、その他も曲も含め、様々なレーベルによってLP・CD化されたが、いずれも音質に難ありという評価だった。その後1999年に仏ターラが「正規盤」と称するCDを発売、これが最も音質良好と評価されてきた。
ただし、ターラ盤にはなぜかRAIのロゴマークがなく、正規にライセンスを得た旨の記載もないため、RAIの関係者が私的に音源を提供したと推察され、音質自体も以前のLP・CDと比較して鮮明さは増しているものの、特にブラームスは高域が強調されたヒステリックな音質で、一部の既出盤の方が聴きやすいとの意見もあった。おそらくターラ盤は新たに音源を入手したものの、パデローニに刻まれた情報を忠実に再現したに留まるものだったと想像される。これは一つの見識で批判されるものではないが、元々音質が良くないパデローニの性能の限界と、音源のディスク自体、ターラ盤発売当時でも40年以上の時間を経て劣化を否定できない上(アセテート・ディスクは経年劣化が早い)、1950年代中頃のRAIの録音技術も決して上等とは言えず、フルトヴェングラーの演奏を正しく記録できていたのか、はなはだ疑問があった。
当ディスクの音源は、アメリカ人コレクターから提供された段階で既にリマスターが施されていた。姉妹レーベル・プレミエPR60095で発売したジョルジュ・エネスコのバッハ無伴奏ソナタ・パルティータをオリジナルLPから復刻したエンジニアがリマスターを行ったとのことで、RAI関係者またはイタリア人コレクターから、ターラと同レベルの音質の音源を入手、フルトヴェングラーによる同曲の他の演奏録音を参考とした上で周波数バランスを調整、さらに10khz前後までしか伸びていなかった高域を15khz程度まで拡張(FM放送並みの帯域が確保できる)。元の音源はデッドで残響ゼロだったが、会場であるトリノ・イタリア放送協会オーディトリアムの音響特性を考慮し、想定できる残響をごくわずかに付加したとしている。ちなみに同オーディトリアムは1952年に完成した当時最新のホールであり、会場の写真を見ると、ステージに音響を遮るような額縁がなく、天井の高さも十分にあり、収容人数は1600名程度と小ぶりだが(ウィーンのムジークフェラインも1700席弱と大差ない)、豊かとは言えないまでも適度な響きは期待できそうだ。オリジナル音源の残響ゼロは、RAIによる直接音主体のマイクセッティングが原因と思われ、英デッカのように残響を収録するための専用マイクを天井から吊るすというアイデアはRAIにはなかったらしい。その他リミッターによって制限されていた強音を復活させるなどダイナミックにも細かい調整を行ったようだ。
以上のような音質改善の結果、あらゆる既出盤とは一線を画した素晴らしい音響が再現されることとなった。豊かな低音の上に充実した中音と輝かしい高音がバランス良く響き、当時の会場ではこのような音楽が鳴り響いていただろうと確かに感じられ、演奏本来の姿がよみがえった感がある。晩年のフルトヴェングラーは枯れた演奏が多いと言われるが、当ディスクの演奏は例外で、円熟しつつも全盛時の「熱さ」が感じられる。
当ディスクに聴くブラームス交響曲第3番は、現在確認されているフルトヴェングラーによる3つの録音の中では注目度が最も低いが、画期的に音質を改善した当ディスクによって、その位置づけが変わるかも知れない。
なお、放送のための録音を前提にしているため、RAIの「お約束」により聴衆は風邪を引いていないこと、演奏中は静粛にしていることを条件に入場が許されており、会場ノイズはほとんど皆無で、演奏後の拍手も静かで控えめ。
1954年4月、フルトヴェングラーとベルリン・フィルは、25~27日のベルリンにおける定期公演を終えた後、ツアーに出発。翌28日ハノーファー、29日ビーレフェルト、30日ケルンと連日公演をこなし、2日空けて5月3・4日パリ(4日のオペラ座における録音が残っている)、5日リヨン、6日スイス・ジュネーヴ、7日ローザンヌ、8・9日イタリア・ミラノ、10日フィレンツェ、11日ペルージャ、12日ローマ、14日トリノ(当ディスクの演奏)、15日スイス・ルガーノ(「田園」他の録音が残っている)、16日チューリヒ、17日ドイツ・フライブルク、18日バーデン・バーデン、19日カールスルーエ、20日マンハイム、21日カッセルでツアーが終了し、23~25日ベルリンで定期演奏会と、殺人的とも言えるスケジュールをこなしている。健康状態が心配になるが(実際無理があったろう)、後任のカラヤンも似たようなスケジュールでツアーを実施していたから、ベルリン・フィルの常任指揮者には、これほどのハードスケジュールが求められていたと言える。それでも残された演奏は当ディスクに聴くように見事なものであり、多忙であっても高水準の演奏を提供していたことが理解できる。一方で、これほど各地で演奏しているにもかかわらず、残されたライブ録音が少ないことは理解できないが、今日と異なり、放送を前提としない限り演奏を録音することはなかったのだろう。
フルトヴェングラーは当ディスク以外にブラームスの交響曲第3番を、上記のように1949年と1954年4月にライブ録音していた。また、ワーグナー「トリスタンとイゾルデ」「第1幕への前奏曲と愛の死」を、楽劇の全曲や抜粋録音を除けば、1930年ベルリン・フィルと独ポリドールに、1938年同じくベルリン・フィルと英HMVにスタジオ録音したほか、1942年ベルリン・フィル、同じく1942年ストックホルム・フィル、1950年フィルハーモニア管、1954年4月ベルリン・フィルとライブ録音していた。また、ウェーバーのオイリアンテ序曲を1954年ウィーン・フィルと英HMVにスタジオ録音したほか、1954年5月4日ライブ録音していた。

●優秀録音 アルヘンタ/フランス国立放送管、ファリャ名曲集 1957年パリ・ライブ
7つのスペイン民謡、恋は魔術師、スペインの庭の夜ほか
オルガヌム110117AL
ファリャ
歌劇「はかなき人生」から 序奏とサルーのアリア「笑うものたち万歳!」
7つのスペイン民謡(管弦楽編曲:エルネスト・アルフテル)
バレエ「恋は魔術師」組曲
交響的印象「スペインの庭の夜」
バレエ「三角帽子」から 近所の人たちの踊り、粉屋の踊り、終幕の踊り
テレサ・ベルガンサ(メゾ・ソプラノ)
ゴンサロ・ソリアーノ(ピアノ)
アタウルフォ・アルヘンタ指揮フランス国立放送管弦楽団
1957年2月21日、パリ・シャンゼリゼ劇場
モノラル、ライブ
※2枚組。当時スペイン指揮者界の第一人者と言われたアタウルフォ・アルヘンタによるファリャ・プログラム。ファリャ没後10年を記念したコンサートで、アルヘンタが不慮の事故により44歳で早世する約11か月前の貴重なライブ録音である。音源は英国人コレクターからの提供、後述するように極めて音質優秀で、エアチェックではなく放送局保存音源の良質なコピーと思われる。コンサート・プログラムの一部は既出盤が存在するが、全曲のディスク化はおそらく初めて。また、既出盤は実際のプログラムとは異なる曲順だったが、当ディスクには実際のプログラム順に収められている。
音質はモノラルながら極めて優秀。1957年という年代の水準を上回り、1960年代半ば頃のレベルに匹敵。フランス国立放送特有の録音傾向で、残響が少なく、オンマイクの直接音主体の録音だが(シャンゼリゼ劇場のドライな音響特性も影響している)、色彩的なファリャの作品には極めて相性が良く効果的。叩き付けるようなリズムや強烈なアクセントを持った演奏を見事に捉えており、優秀なエンジニア(アンドレ・シャルラン?)が関与したと想像される。同じ演奏をウィーンのムジークフェラインなど残響豊かなホールにおいてオフマイクで録音したら、演奏の魅力の大半は失われてしまっただろう。聴衆は大いに盛り上がっていたと思われるが、会場ノイズは意外にもほとんど聞こえない。
ファリャ没後10年(正確には11年)を記念したコンサートがパリで開催されたのは、ファリャがフランスで高い評価を得たことが大きな理由と思われる(その高い評価が故国スペインに伝わって一躍注目された)。プログラムは、ファリャの代表作を網羅したもので、特にアンダルシア風の民族的要素の強い人気作品を集めている。「7つのスペイン民謡」の原曲はピアノ伴奏だが、ファリャの弟子エルネスト・アルフテルによる管弦楽編曲版で演奏されている。現在の視点で見れば、中期以降のチェンバロ(クラヴサン)協奏曲や「ペドロ親方の人形芝居」の抜粋などを含めてもよい気がするが、聴衆の「盛り上がり」には欠けるだろう。その点では、演奏時間の都合によるものか、最高傑作である「三角帽子」から3曲しか演奏されていないのは残念である。
出演者は、当時のスペイン作品演奏家の“ベストキャスト”と言えるもので、指揮のアルヘンタをはじめ、当時23歳ながら同年7月にはエクス・アン・プロヴァンス音楽祭に出演して大好評を博し、ミラノ・スカラ座1957~1958年シーズンにデビューするなど、期待の新人として人気急上昇中だったベルガンサ、スペイン・ピアノ界の第一人者ソリアーノという名手揃い。敢えて言えば「7つのスペイン民謡」にビクトリア・デ・ロス・アンヘレスの起用も考えられなくはないが、アルヘンタによるスペインの民族性豊かな演奏スタイルを考えると、ロス・アンヘレスの歌唱は上品すぎたかも知れず、ここではベルガンサの方がふさわしい。
アルヘンタは「スペイン音楽のスペシャリスト」のように形容されることが多いが、ドイツ留学した際にはカール・シューリヒトに師事しており、指揮者として当然求められる幅広いレパートリーの持ち主だった。英デッカにベルリオーズやチャイコフスキー、リスト(ファウスト交響曲という珍しい作品)、ドビュッシー、仏クラブ・ディスク・デュ・フランスにシューベルトやラヴェルなどのスタジオ録音を行い、ライブだがハイドンやベートーヴェン、メンデルスゾーン、ブラームス、R・シュトラウス、さらにはストラヴィンスキーなどの録音を残している。いずれも高水準なレベルの演奏で、さらに経験と年齢を重ねていけば巨匠と呼ばれる存在になったことは間違いない。しかし、スペイン音楽や(リムスキー・コルサコフやシャブリエなどの)スペイン風作品の演奏があまりにも素晴らしかったため、そちらにばかり注目が集まったことは、ある意味不幸なことであった。これはビクトリア・デ・ロス・アンヘレスやアリシア・デ・ラローチャに対する評価と通じるものがあり、ロス・アンヘレスのシューベルトやフランス系歌曲がどれほど優れていても、ラローチャのモーツァルトやシューマンがいかに素晴らしくても、聴衆はアルベニスやグラナドス、ファリャの演奏の方に喝采したことと同様である。
もちろんスペイン人演奏家が必ずしもスペイン作品の演奏に優れているわけではないが、スペイン人以外を含めて、アルヘンタ亡き後、彼のようにファリャ作品の芸術性とスペインの民族性を巧みに両立させた指揮者はおらず、今日まで、ファリャを含めてスペインの管弦楽作品に関して彼を凌ぐ演奏を成し遂げた指揮者はいない(フリューベック・デ・ブルゴスが後継者と言われた時期もあったが・・・)。誠に貴重なドキュメントと言える。
アルヘンタは、当ディスク以外に「恋は魔術師」組曲を1951年仏コロンビアにパリ音楽院管と、「スペインの庭の夜」を1957年スペイン・コロンビアにソリアーノおよびスペイン国立管と、「三角帽子」組曲を1958年スペイン・コロンビアにスペイン国立管とスタジオ録音したほか、「恋は魔術師」組曲を1957年スイス・ロマンド管と、「三角帽子」抜粋を1954年ウィーン響とライブ録音していた。その他の作品は当ディスクが現在確認されている唯一の録音と思われる。

●優秀録音 ジャニーヌ・アンドラード
シベリウス、サン=サーンス ヴァイオリン協奏曲 1962年・1966年スタジオ・ライブ
オルガヌム110118AL
シベリウス ヴァイオリン協奏曲
サン=サーンス ヴァイオリン協奏曲第3番
ジャニーヌ・アンドラード(ヴァイオリン)
アンドレ・ジラール指揮フランス国立放送管弦楽団
ジョルジュ・ツィピーヌ指揮フランス国立放送フィルハーモニー管弦楽団
1962年2月24日、1966年7月6日、パリ・メゾン・ド・ラジオ・フランス(RTF)
モノラル/ステレオ、放送ライブ
※ジャニーヌ・アンドラードによる聴衆を入れずに行われた放送スタジオ・ライブ録音。音源は英国人コレクターからの提供、エアチェックではなく放送局保存音源の良質なコピーと思われる。サン=サーンスはステレオ録音。2曲とも音質良好。シベリウスはモノラルながら1962年の平均を上回る音質。オンマイク過ぎて残響がほとんどないというフランス国立放送(RTF)録音の欠点もなく、適度な距離のマイクセッティングで違和感のないもの。シャープで解像度の高い録音はシベリウスの作品に適している。ソロ・ヴァイオリンをクローズアップした昔ながらの録音スタイルだが、それほど極端ではなく、オーケストラとのバランスも許容範囲。1966年のサン=サーンスも同一傾向の録音だが、ステレオ化されたことで余裕が生まれ、色のパレットが増えたイメージでサン=サーンス作品にふさわしい録音スタイル。ただしモノラルよりもマイクセッティングが難しいためか、ソロ・ヴァイオリンとオーケストラのバランスが若干悪い箇所もある。しかし、これは微細に粗探しを行った結果であり、いずれにしても一般的な鑑賞にはまったく問題ない。
ジャニーヌ・アンドラードについて、少なくとも日本国内における評価は、パリ音楽院でジュール・ブーシェリに師事した一連の女流ヴァイオリニスト(ジャンヌ・ゴーティエ、ドゥニーズ・ソリアーノ、ローラ・ボベスコ、ジネット・ヌヴー、ミシェル・オークレール)の中では地味な存在で、レコーディングも少なく、また、その少ない録音を聞く限り、技術的にもやや弱いという評価があった。従来入手可能だった録音は、廉価盤LPとして発売されたブラームスとチャイコフスキーの協奏曲(米MGMレコードが、おそらく予算の制約から十分な事前準備やリハーサルを行う余裕もなく短時間で録音したものの、同社がレコード事業から撤退したため未発売となり、同社のプロデューサーだったポール・ラザールが音源を買い取り、様々なマイナーレーベルに投げ売りしたものという)、10数年前にCD化されたチェコ・スプラフォン録音の小品集、これも同じ頃にCD化された旧東独エテルナ録音のモーツァルトの協奏曲程度で、いずれもアンドラードの本来の姿を伝えるものではなかったようだ。稀少な録音としては、デンマーク盤のみ存在すると言われる独デッカ(実際の録音はフィンランドのMusiikki-Fazer社、独デッカは提携販売のみ)録音のシベリウスのヴァイオリン協奏曲があるが、こちらも多くの名盤に伍するような存在ではないと言われている。これらレコードにおける低評価は、おそらく準備不足や共演者に恵まれなかったことが原因であるようにも思われるが、ここで興味深いのは、録音がすべてフランス以外のレーベルであること(ドイツで評価が高かったと言われる)。また、協奏曲が大半で小品集を除けば室内楽がないこと。実演に接する機会が少なく(アンドラードは1954年に一度だけ来日しているが)、録音のみで評価される日本では、自国フランス作品の録音もなく、また契約レコード会社が固定せず、散発的に廉価盤のLPやCDが発売される状況では、ある意味評価以前の状況だったかも知れない。
アンドラードの評価が改まったのは、近年になってライブや放送録音が海外レーベルによってCD復刻され始めたことが大きい。ベートーヴェンやフランク、フォーレなどのソナタに聴く、しなやかではありつつも、安定した技術に支えられた確固たる演奏は、従来のアンドラードのイメージを変えることとなった。当ディスクのシベリウスに聴くようなスケールが大きく充実した演奏も、女流という先入観を打ち消すものであり、技術的な弱さも感じさせない。サン=サーンスは曲想や録音のせいもあって、若干従来のアンドラード像に近いが、それでも余分な情緒を排した客観的で緻密な演奏は、まぎれもなく一流の演奏家だったことを示している。ただし残念なことに、円熟期の1972年に54歳で脳卒中に襲われて右半身が麻痺し、引退を余儀なくされたため、その演奏芸術の完成を見ることは出来なかった。アンドラードはヨーロッパのみならず南米や南アフリカなど、幅広く演奏活動を行っており、今後も録音の発掘を期待したい。
指揮のアンドレ・ジラール(1913~1987)は日本ではなじみが薄いが、パリ交響楽団(モントゥーが常任だったが経営難で解散した)やパリ音楽院管弦楽団のヴァイオリニスト出身で、第二次世界大戦後フランス各地のバレエ団、モロッコ放送、ボルドー歌劇場などの指揮者のポストを経て、1950年代後半からRTF所属のオーケストラ4団体の指揮者陣に加わった。シベリウスの録音はその当時のものである。1964年から1974年までRTF室内管弦楽団を指揮、1976年から1978年までロワール・フィルの音楽監督を務めた。地味なキャリアの指揮者で、現場たたき上げの手堅い職人というイメージだが、シベリウスでは積極的にアンドラードをサポートしており、有能な指揮者だったことが想像される。一方のジョルジュ・ツィピーヌ(1907~1987)は、フランス系作品に親しんだベテランのレコード愛好家にはなじみ深い名前。フランス近代の作品や6人組、特にオネゲルの録音が多く、初演も数多く出がけたようだが、実はパリ生まれのユダヤ系ロシア人で本名はジョルジュ・サムイロヴィチ・ツィピンとのこと。国際都市パリならでは特徴と言えよう。サン=サーンス録音当時は、仏EMIなどへのレコーディングも一段落し、RTFの仕事が多かったようだ。
なお、フランス国立放送フィルはRTF所属の4オーケストラのうちの第2オケ。当時はRTF傘下のラジオ・フランスが管理・運営しており、RTF直属のフランス国立放送管とは微妙に運営主体が異なる(現在は両者ともラジオ・フランスが運営している)。
アンドラードは、当ディスク以外に前記のようにシベリウスのヴァイオリン協奏曲を1959年フィンランドMusiikki-Fazerにスタジオ録音していた。サン=サーンスのヴァイオリン協奏曲第3番は、当ディスクが現在確認されている唯一の録音と思われる。
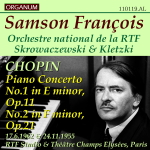
●優秀録音 サンソン・フランソワ ショパン ピアノ協奏曲第1番・第2番
1962年・1955年ライブ
オルガヌム110119AL
ショパン ピアノ協奏曲第1番
ショパン ピアノ協奏曲第2番
サンソン・フランソワ(ピアノ)
スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ、パウル・クレツキ指揮フランス国立放送管弦楽団
1962年6月17日、パリ・フランス国立放送(RTF)スタジオ
1955年11月24日、パリ・シャンゼリゼ劇場
モノラル、放送ライブ/コンサート・ライブ
※サンソン・フランソワによるショパンのピアノ協奏曲2曲。第1番はフランス国立放送(RTF)のスタジオにおけるテレビ放送のための収録で、少数ながらスタジオ内に聴衆(見学者?)がいるようだ。表記の録音日は、放送日であり収録日ではないと言われているが、生放送だった可能性も否定できない。第2番はラジオ放送を前提としつつも、聴衆を入れた通常のコンサートのライブ録音。2曲とも音源は英国人コレクターからの提供、エアチェックではなく放送局保存音源の良質なコピーと思われる。第1番は海外でDVD化された演奏と同一だが、同じマイクラインながら、ラジオ放送用に音声のみテープレコーダーで別録りされたものが当ディスクの音源らしく、当ディスクの音源はDVDよりも高域が伸びているせいか、DVDではオーケストラと混濁気味だった独奏ピアノがより明確に聴こえる。ただ、テレビ放送用のため目障りにならないようにマイクの数を制限しているためか、オーケストラの解像度が若干低いが許容範囲であろう。もちろんフランソワのピアノを聴く分には問題ない。第2番は第1番よりも7年古く条件も悪いはずのライブ録音だが、ややソリッド(堅め)な音質ながらバランスも問題なく、1950年代半ばの録音水準を上回る十分に良好と言える音質。両者とも会場ノイズも極めて少ない。第1番は拍手なし。
フランソワは、ショパンのピアノ協奏曲第1番を1954年と1965年にスタジオ録音しているが、当ディスクの録音年はその中間に当たるもの。「フランソワとしては」という条件付きで端正だった旧録音や自由奔放・気まま・やりたい放題だった再録音と比較すると、ピアノ独奏自体は当然再録音のスタイルに近くなっているが、スクロヴァチェフスキが巧みにサポートしているためか、表面的には意外にまともな演奏に聴こえる。再録音のモンテカルロ歌劇場管より柔軟性と対応力に長けたフランス国立放送管の貢献も大きいか。独奏者の個性を十分に生かしつつ、指揮とオーケストラが演奏の崩壊を防いでいるようだ。スクロヴァチェフスキは当時41歳の中堅ながら、その実力は高く評価されていた。1960年からミネアポリス(ミネソタ)響の音楽監督を務めていたが、かつてフランス留学の経験もあり作曲家としてもパリで活動したため、当時はフランス国立放送管を指揮する機会も多かったようだ。一方、第2番は1958年と1965年にスタジオ録音しており、当ディスクの演奏はそれ以前の録音である。フランソワにとっては第2番の方が相性が良いと思われ、1958年録音でもかなり自由に演奏しているが、ここではライブと言うことで自由度が増しているようだ。指揮のクレツキはフランソワに翻弄されることなく老練にサポートしている。
元来、第1番よりも先に作曲された第2番は、第1番よりも演奏の解釈の幅が広いらしく、そのためか、コルトーやハスキル、マルグリット・ロンなどフランス流派のピアニストは、第1番ではなく好んで第2番のみレコーディングを残していることが多い。
ちなみに1955年のシャンゼリゼ劇場におけるコンサートは、最初にチャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」、ショパンのピアノ協奏曲第2番、スクリャービンの交響曲第4番「法悦の詩」という、意欲的というか曲順もバラバラの組み合わせ。パウル・クレツキ得意のロシア作品に、フランソワのレパートリーを追加した形と思われるが、それであればフランソワが好んだプロコフィエフのピアノ協奏曲でもよかった気もする。統一感のあるコンサート・プログラム構成は、1930年代のドイツで始まったとされ、欧米全体に広まったのは1950年代後半と言われるから、当時のパリでは第二次世界大戦前からの習慣が残っていたのだろう。
フランソワというと酒と煙草とジャズを愛し、退廃的な日常を送り、神がかり的な素晴らしい演奏をしたかと思えば惨憺たる演奏をするなど、気まぐれで出来不出来が激しかったというイメージがあるが、記録を見ると海外公演(3回来日している)やソロ・リサイタルを含む多くの演奏会に出演、オーケストラとの共演も多く、さらに膨大なレコーディングを行っている点を考えると、演奏の出来そのものは別として、強いプロ意識を持った誠実な演奏家という見方も出来る(キャンセル魔のミケランジェリは別の意味で音楽に「誠実」だったが)。ちなみに1967年に来日した際、当時の東芝音楽工業へレコーディングを行ったが、事前のテスト録音のプレイバックを聴いて「マイクが近すぎるので距離を空け、響きを多く入れるように」等々と細かく注文を出すなど、自らの仕事には熱心に取り組んでいたことがうかがえる。フランソワに対する評価は、ジャーナリズムによって面白おかしく誇張された部分も多いと考えられる。
サンソン・フランソワは、上記のようにショパンのピアノ協奏曲第1番を1955年と1965年、第2番を1958年と1965年それぞれ仏コロンビアにスタジオ録音していた。
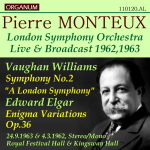
●ピエール・モントゥー/ロンドン響
ヴォーン・ウィリアムズ ロンドン交響曲、エルガー エニグマ変奏曲
1963年・1962年ステレオ・コンサート・ライブ/モノラル放送ライブ
オルガヌム110120AL
ヴォーン・ウィリアムズ 交響曲第2番「ロンドン交響曲」
エルガー エニグマ変奏曲
ピエール・モントゥー指揮ロンドン交響楽団
1963年9月24日、ロンドン・ロイヤル・フェスティバル・ホール
1962年3月4日、ロンドン・キングズウェイ・ホール
ステレオ/モノラル、コンサート・ライブ/放送ライブ
※名コンビと言われたモントゥー/ロンドン響(LSO)によるオール・ブリティッシュ・プログラム。英国人コレクターによる提供音源。いずれもエアチェックとのことだが、エルガーについては放送局保管音源のコピーの可能性もある。ヴォーン・ウィリアムズは幸いステレオ録音だが、当時エアチェックを行ったリスナーのFM放送受信環境が万全ではなかったのか、オリジナルの音質自体はそれほど悪くないが、弱いパルス性のノイズが随所に混ざり、時折、音が崩れるような大きなノイズが入るという状態で、さらに低音過多と高音不足、ピアニシモは小さすぎ、フォルティシモは大きすぎるというバランスの悪さなど、鑑賞にはかなり忍耐が求められる音源だった。
このため、ディスク化に当たっては、音質を損ねないように細心の注意を払いながら、パルス性ノイズと大きなノイズそれぞれについて、フィルターは音質低下の原因となるため使用せず、複数のソフトウェアで除去・低減し、イコライジングで周波数バランスを調整、コンプレッサーを必要最小限使用して弱音と強音のバランスを改善するなど、様々な手を加えることでようやく一般的な鑑賞に堪える音質となった。結果としては、1960年代初頭のステレオ・ライブ録音としては良好な音質と評価して差し支えない水準。会場ノイズも極小。
一方のエルガーは、モノラルながらエアチェックとは思えない高音質で、エアチェックではなく放送局保管音源のコピーの可能性が大きい。後述するが、録音専用スタジオで聴衆を入れずに録音されているため、マイクセッティングの制約がないなど条件が良く、このままステレオ化すれば1960年代のメジャー・レーベルのスタジオ録音に匹敵する水準。ディスク化に当たっても、若干ダイナミックレンジを調整した以外、ほとんど手を加える必要がなかった。
モントゥーは1958年LSOに初めて客演以降、徐々に客演回数が増え、1961年85歳の時に首席指揮者に就任。1964年死去するまでその地位にあった。当時のLSOはコンサート・マスターにエリック・グリューエンバーグ、第2ヴァイオリン首席にネヴィル・マリナー、ホルン首席にバリー・タックウェルが在籍するなど、優秀な奏者が揃った黄金時代だった。
ちなみにモントゥーの英国音楽への興味はLSO客演以前からあったらしく、当ディスクに聴くヴォーン・ウィリアムズの「ロンドン交響曲」については、なんとボストン響音楽監督時代の1921年に2回4公演、1923年に2回3公演取り上げている。作曲されたのは1912年だが、正式な初版譜が出版されるのは1928年であり、暫定的な総譜を元に演奏したのだろう。現代音楽の演奏に貪欲だった若き日のモントゥー(それでも40歳代だが)の面目躍如たるものがある。「ロンドン交響曲」は、言うまでもなく英国系指揮者のレコーディングが多くを占めるが、モントゥーの演奏はやや異なり、弱音部など不明確になりやすい音型を明確化し、不協和音をできる限り協和音に聞こえるように響かせるなど、より古典的な解釈を行っている。ラヴェルやストラヴィンスキーなど(当時の)現代音楽の初演を数多く手がけたモントゥーは、保守的な聴衆の理解を助ける工夫をしていたのだろう。LSOとの「ロンドン交響曲」の演奏は、当ディスクに聴く1963年の1公演のみであり、貴重な機会の録音が残されたことになる。
1963年の演奏はLSO定期演奏会における録音で、前半にウェーバーのジャベル序曲、アイザック・スターン独奏でシベリウスのヴァイオリン協奏曲、休憩を挟んで後半に「ロンドン交響曲」というプログラム。ウェーバーのジャベル序曲はかつて海外でCD化されていた。
一方、エルガー「エニグマ変奏曲」は、判明している限りでは1950年にコンセルトヘボウ管で取り上げており、こちらもLSO客演以前である。ちなみに同曲については、後述するように正式なスタジオ録音を行ったほか、他の楽団を含め度々演奏するなど、モントゥーお気に入りの作品だった(来日公演でも取り上げた)。なお、当ディスクの演奏は、BBCによる放送のための録音であるものの、BBC自身が保有するマイダ・ヴェイル・スタジオではなく、キングズウェイ・ホールで録音されている。同ホールは、EMIやデッカなど英国のメジャー・レーベルがレコーディングに多用した有名な録音スタジオ。元は教会で内外観とも荒れた廃墟のような建物だが、適度な残響がありながらクリアな音響がレコーディングに最適とされた。おそらくマイダ・ヴェイル・スタジオが改修工事などで使用できず、その間、同ホールを借りたのだろう。1950年代末にはステレオ録音を導入していたBBCだが、残念ながら当録音はモノラルで、おそらくAM放送用の録音だったと思われる。BBCでは1970年頃まで目的別にステレオとモノラル併用で録音を行っていた。
ピエール・モントゥーはヴォーン・ウィリアムズの「ロンドン交響曲」のスタジオ録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音。エルガーの「エニグマ変奏曲」は、当ディスク以外に1958年英デッカ(当初の発売はRCA)にLSOをスタジオ録音したほか、1950年コンセルトヘボウ管、1957年ボストン響とライブ録音していた。
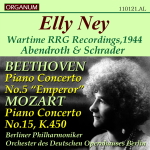
●エリー・ナイ アーベントロートほか
ベートーヴェン「皇帝」、モーツァルト ピアノ協奏曲第15番
1944年ドイツ帝国放送録音
オルガヌム110121AL
ベートーヴェン ピアノ協奏曲第5番「皇帝」
モーツァルト ピアノ協奏曲第15番
エリー・ナイ(ピアノ)
ヘルマン・アーベントロート指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
エルンスト・シュラーダー指揮ベルリン・ドイツ歌劇場管弦楽団
1944年10月13日、19日、ドイツ帝国放送ベルリン第1スタジオ
モノラル、放送ライブ
※往年の大ピアニスト、エリー・ナイの第二次世界大戦中の放送録音。ドイツ在住のロシア人コレクターによる提供音源。2曲ともオリジナルは旧ドイツ帝国放送(RRG)がスタジオで聴衆を入れずに行ったラジオ放送用録音。AEG社製マグネトフォン・テープレコーダーによる録音で、録音当時、ドイツ各地の放送局で使用するために10本程度のコピーテープが作成されたといわれ、当録音は南ドイツ放送保管の音源らしい。いずれも1944年録音とは思えない高水準の音質だが、保存状態の差によるものか、「皇帝」はやや濁りがある音質で低域過剰気味だったため、ディスク化に当たっては、音質を損ねないように配慮しながらソフトウェアで濁り成分を除去、イコライジングで周波数バランスを調整した。結果的に十分鑑賞に堪える音質となった。モーツァルトは状態が良かったため、ヒスノイズを低減したほかは、ほとんど手を加えていない。
エリー・ナイは一般的なドイツ人と同程度の反ユダヤ主義的思想を持っていたと言われるが、ナチス政権に対しても素朴な賛意を示し、第二次世界大戦中も前線への慰問演奏を行うなど、積極的に戦争協力を行った。戦後の非ナチ化審議においても、ナチスへの信奉を変えないなど、同様にナチス政権に協力した他の演奏家ほどうまく立ち回れなかったため、1952年までという異例に長い演奏禁止が下された。
エリー・ナイはシュナーベルと同じ1882年生まれ、わずか2歳年下だが新即物主義の洗礼を受けたバックハウスなどと異なり、一世代前のロマン主義的な演奏スタイルで、師のエミール・フォン・ザウアーの様式に近く、第二次世界大戦当時でもすでに旧世代に属していたと言える。その結果、1952年の演奏活動解除後は、却って「古き良きドイツの伝統を継承した演奏家」として、一種カルト的な人気を博することになる。さらに1960年代に入り、80歳を過ぎると度々「告別演奏会」と称する演奏会を行った。当時訪欧中だった評論家の吉田秀和は、技術も衰えた古い演奏様式を嫌悪感もあらわに酷評したが、これがその後長らく日本におけるエリー・ナイ評価として定着することとなる。1970年代には独コロセウム原盤によるベートーヴェンのソナタ集の国内盤LPが発売されたものの、全くの販売不振に終わった。
エリー・ナイが日本で再評価されるようになるのは、1990年代に入り、独コロセウムから、かつて販売不振に終わったベートーヴェンを含む一連の録音をCD化再発売したことが契機となったようだ。この頃から日本国内にヒストリカル系の輸入CDが大量に出回り、かつてのような「決定盤」「唯一無二の演奏スタイル」を尊重する傾向が薄れ、新旧様々な様式の演奏が許容されるようになり、エリー・ナイの演奏もようやく正しく評価されることとなった。
当ディスクに聴く「皇帝」などは、まさしく旧世代に属するロマン主義的演奏スタイルであり、アーベントロート(1歳年下)の指揮と見事に様式が一致している。興味深いのは、1944年4月にもカール・ベーム指揮ウィーン・フィルと「皇帝」を放送録音しており、こちらはエリー・ナイの自由な演奏に、新即物主義世代で形式を重視するベームが何とか追いかけていくという齟齬が見られる。いずれにしてもエリー・ナイ62歳前後の演奏であり、80歳近くになって行われたスタジオ録音よりも覇気がある。
一方のモーツァルトは、なぜかエリー・ナイが好んだ作品、1935年にスタジオ録音しており、1922年ニューヨーク・フィルハーモニックの定期演奏会や、晩年の1964年にも演奏した記録がある。第20番以降の傑作群ではなく、第15番に特別な価値を見出していたのだろう。ロマン的演奏は変わらないものの意外に素直な演奏で、さすがに作品解釈は巧みである。
エリー・ナイは、当ディスク以外に、上記のようにベートーヴェンの「皇帝」を1960年独コロセウムにスタジオ録音したほか、1944年にライブ録音していた。一方、モーツァルトのピアノ協奏曲第15番を1935年独エレクトローラ(HMV)にスタジオ録音していた。
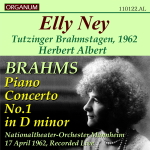
●エリー・ナイ
ブラームス ピアノ協奏曲第1番 1962年ライブ
オルガヌム110122AL
ブラームス ピアノ協奏曲第1番
エリー・ナイ(ピアノ)
ヘルベルト・アルベルト指揮マンハイム国立歌劇場管弦楽団
1963年4月17日、バイエルン州トゥッツィング
モノラル、ライブ
※往年の大ピアニスト、エリー・ナイによるトゥッツィング・ブラームス音楽祭におけるライブ録音。ドイツ在住のロシア人コレクターによる提供音源だが、残念ながらプロのエンジニアによる録音ではないらしく、オリジナル録音は良好とはとても言えない状態だった。当然テープ録音で音質自体はそれほど悪くないのだが、独奏ピアノの音が大きすぎ、オーケストラが遠くで小さく鳴り、強奏部でもピアノの音がオーケストラ伴奏を圧倒。また木管パートがほとんど聴こえず、ピアノも高音部に耳障りなピークがあった。ホール常設の天吊りマイクに加えて、ピアノのそばに補助マイクを立てたと想像されるが、いずれもマイク位置が不適切で、音楽祭関係者が後日の鑑賞を考慮せず、単なる記録用として録音を行ったのだろう。
ディスク化に当たっては、ピアノとオーケストラの音量レベル改善、聴こえない木管パートの強調と明確化、高域にピークがあるピアノの周波数バランスを調整、また、時折混入する低域ノイズの除去等々、様々な方策を施した結果、鑑賞に堪える状態まで音質を改善することが出来た。決して優秀音質と言えないが、ピアノはクリアな音質で1960年前後のライブ録音の水準にあり、この種の録音を聴き慣れたリスナーであれば、十分演奏を楽しむことが出来るだろう。
トゥッツィングは南ドイツ・バイエルン州のリゾート地で、1873年にブラームスが避暑に訪れ、「ハイドン変奏曲」などの作曲を行ったことで知られるが、1958年からエリー・ナイ自身の提唱によりブラームス音楽祭が開催されるようになったという。当録音はエリー・ナイ80歳時の演奏だが、矍鑠(かくしゃく)と言うか、年齢を感じさせない堂々たる演奏。一部ミスタッチや乱れる箇所はあるが、ライブ録音であることを考慮すれば実に充実した演奏と言える。
エリー・ナイはシュナーベルと同じ1882年生まれ、わずか2歳年下だが新即物主義の洗礼を受けたバックハウスなどと異なり、一世代前のロマン主義的な演奏スタイルで、師のエミール・フォン・ザウアーの様式に近く、第二次世界大戦後には明らかに古い演奏様式だったが、却って「古き良きドイツの伝統を継承した演奏家」として、一種カルト的な人気を博していたようだ。元々ブラームスのピアノ協奏曲第1番は、第2番に比べて録音が少なく、特に古い世代のピアニストの録音は稀少である(大家による演奏はシュナーベルの1938年録音と近年ライブ録音が発掘されたアルフレート・ヘーンによる1936年録音くらいか)。ここに録音に不備はあるが、新たにエリー・ナイの演奏が加わった意義は大きい。
エリー・ナイは、反ユダヤ主義でドイツ(ゲルマン)民族の優越性を信奉し他民族を蔑視していたと言われるが、外来の客に対しては意外にも寛大で親切だったようだ。古い音楽雑誌の記事によると、1955年音楽学者で評論家の属啓成(さっかけいせい)が訪独した際、当然事前にアポイントメントを取っていたと思われるが、エリー・ナイの自宅最寄り駅から電話連絡したところ本人が応答し、「今すぐどうぞ」とのことで自宅を訪問。するとエリー・ナイは「私がどのような演奏家かご存じないと思うのでまずは1曲演奏したい」とのことで、(曲目は不明だが)ベートーヴェンのソナタを全曲演奏して聴かせた。そして「日本人演奏家としては近衛秀麿を知っている。彼とはブラームスのピアノ協奏曲2曲を一晩で演奏したことがある」と語り、歓待してくれたという。この時のブラームスの録音が残されていればとも思うが、かつては女性ピアニストには体力的に無理と言われたこともあるブラームスのピアノ協奏曲を当時存分に弾きこなしていたことになる。
エリー・ナイは、ブラームスのピアノ協奏曲第1番のスタジオ録音を残しておらず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音と思われる。

●高音質1967年ステレオ・ライブ
バルビローリ/ウィーン・フィル
ブラームス交響曲第4番、モーツァルト「リンツ」
オルガヌム110123AL
モーツァルト交響曲第36番「リンツ」
ブラームス 交響曲第4番
サー・ジョン・バルビローリ指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
1967年12月17日、ウィーン・ムジークフェラインザール
ステレオ、ライブ
※バルビローリとウィーン・フィルによるステレオ・ライブ録音。アメリカ人コレクターによる提供。オリジナルの音源はオーストリア放送(ORF)による収録だが、アメリカのFMラジオ局との交換音源としてアメリカ国内で放送され、エアチェックされたテープが当ディスクの元となっている。ORFは1967年頃からステレオ録音を導入したが、当録音は最も早い時期のステレオ・ライブ録音の一つと思われる。
驚くべきは音の良さで、1967年とは思えない鮮烈な音質。直接音主体の録音でホールトーンはやや控えめだが、適切なステレオ用マイク・セッティングが行われているらしく、ステレオの定位に不自然さはなく左右チャンネルの分離も良好でまったく問題ない。当時エアチェックしたアメリカ人リスナーの受信環境が良く録音機器も高品質だったのだろう。ただし、メジャー・レコード会社の録音のような整理され磨き上げられた、悪く言えば化粧され演出されたサウンドではなく、やや荒削りながら、客席最前列で聴くようなむき出しの臨場感あふれるもので、ムジークフェラインで聴衆が実際に聴いたと思われるような音質。しかも、この種のライブ録音に付きもののヒスノイズやハムノイズはなく、会場ノイズも皆無に近い理想的な状態といえる。
このようなまれに見る高音質であるため、ディスク化に当たっては、FM放送の周波数上限である15khzを20khz程度まで拡張、演奏終了後の拍手をフェイドアウトさせた以外には、ほとんど手を加えていない。ブラームス演奏中のおそらく楽員による「コトン」といった小さな物音(管楽器をスタンドに置いた音か)。同じくブラームス演奏終了後、アナウンスを入れるためか、拍手が途中からモノラルに変化する箇所は、いずれも鑑賞の大きな妨げにはならないと判断し、修正は行っていない
ザルツブルク音楽祭公演やウィーン・フィル定期演奏会など、ORFが収録したライブ録音は、正規のオリジナル・マスターを元に独オルフェオなどから多数CD化されているが、いずれも生々しさが失われ、音響条件の悪い会場後方の客席で聴くような、またはライブとは思えない「飼い慣らされた」サウンドになってしまっていることが多い。スタジオ録音のような無難な音作りを目指しているのだろうが、これらはORF自身のプロデューサーやエンジニアが強く関与しているとのことで、おそらく当録音も、正規音源によるCD化が実現した場合は、そのような大人しいサウンドに変容することになると思われ、その意味ではオリジナルの音質を知る貴重なディスクでもある。
バルビローリとウィーン・フィルは、1946年と1947年、当録音を含む1967年に計12回共演したのみだったが、1966~67年、英EMIにブラームス交響曲全集をレコーディングした際には、コンサート・マスターのワルター・バリリ(またはボスコフスキーだったか?)が「バルビローリの元では、我々は全力を尽くさなければならない」と語ったように、親密で良好な関係にあった。バルビローリは温厚な人柄だが、リハーサルは要求水準が高く厳しかったと言われており、その音楽性の高さを評価したのだろう。
当ディスクの12月17日の演奏は、ウィーン・フィル定期演奏会1967~68年シーズンの第5回目に当たり、3回公演の2日目、昼12時開演のマチネー(夜は歌劇場の仕事があるため毎回この時間に始まる)、前半にモーツァルト、続いてドビュッシーの「海」、後半にブラームスという、やや長めのプログラム。注目すべきは、前記ブラームス交響曲全集録音のうち、第4番が12月6~8日に録音されており、まさにレコーディング直後の公演であること。EMIに録音したその他3曲の交響曲は、実際の公演で披露されることはなかったから、貴重な実演の機会を捉えた録音と言える。また、正規のスタジオ録音を残さなかったモーツァルトも同様に貴重な録音と言える。
バルビローリとウィーン・フィルによるブラームス交響曲全集のEMI録音は名演と言われているが、発売当初から日本の批評家の間では、その叙情性や優美さを評価する一方、ブラームス作品が持つ構築性や構成力が弱いとして「あまりにもバルビローリ的」という批判もあった。聴衆のいないムジークフェラインの豊かな残響を含んだEMI録音では、そのような印象も間違いではないように思えるが、当ディスクの演奏は残響が少ない分、またライブの勢いもあり、構築性や構成力が弱いという印象はない。一方、バルビローリらしい叙情性もよりダイレクトに伝わってくるようだ。いずれにしてもスタジオ録音とは異なる印象のライブ録音が優秀な音質で聴けることに意義がある。
バルビローリは、当ディスク以外にモーツァルトの交響曲第36番のスタジオ録音を残さず、1969年にライブ録音していた。また、ブラームスの交響曲第4番は、1959年英パイにハレ管、上記のように1967年英EMIにウィーン・フィルとスタジオ録音していた。
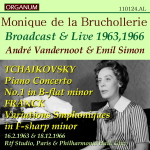
●音質良好 モニク・ドゥ・ラ・ブリュショルリ 1963・1966年ライブ
チャイコフスキー ピアノ協奏曲第1番、フランク 交響的変奏曲
オルガヌム110124AL
チャイコフスキー ピアノ協奏曲第1番
フランク 交響的変奏曲
モニク・ドゥ・ラ・ブリュショルリ(ピアノ)
アンドレ・ヴァンデルノート指揮フランス国立放送フィルハーモニー管弦楽団
エミル・シモン指揮ルーマニア・クルジュ・フィルハーモニー交響楽団
1963年2月16日、パリ・フランス国立放送スタジオ
1966年12月18日、クルジュ・フィルハーモニー・ホール
モノラル スタジオ・ライブ/コンサート・ライブ
※モニク・ドゥ・ラ・ブリュショルリによるチャイコフスキーとフランクで、いずれもブリュショルリの超絶技巧を堪能できる作品。いずれも英国人コレクターによる提供音源だが、2曲ともエアチェックではなく、放送局保管テープのコピーと思われ、基本的には音質良好でモノラルながら鑑賞上の不満はない。チャイコフスキーはスタジオで聴衆を入れずに行われたテレビ放送のための演奏で、収録時に同じマイクラインから音声のみ別録音されたものが当ディスクの元と思われる。オーディオ・テープとビデオ・テープの音声と比べると、同じマイクセッティングにもかかわらず、ビデオ音声は低域は豊かだが高域不足でクリアさに欠ける一方、音声のみの当ディスクの音源は低域は控えめだが高域が伸びて明快である。機器の特性の違いによるものと思われるが、ブリュショルリの演奏を堪能するには後者の方がよりふさわしい。
ディスク化に当たっては、低域不足を補う一方、高域が伸びているせいかピアノの音が硬めだったため、イコライジング等で若干和らげた。ただし、元来ブリュショルリのタッチは硬めであり、過度の処理は避けた。
ちなみに当録音の前年1962年にも、ブリュショルリはチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番をハイティンク指揮で録音しており、英国人コレクターからはこの音源も併せて入手した。これはラジオ・フランスによるFM放送用ステレオ録音で、音質はこちらの方が優れていた。しかし、ブリュショルリの演奏自体はほとんど変わらず、演奏時間は当ディスクの演奏より短い(テンポが速い)にかかわらず、ステレオ録音による豊かな残響によるものか、ハイティンクの堅実(微温的?)な伴奏によるものかは不明だが、「ブリュショルリの演奏としては」という前提で、良く言えばリラックスした、悪く言えば緊張感に欠けた印象があった。客観的に見れば十分に優れた演奏だが、ブリュショルリの凄さを伝えるという点では不満があり、1963年のモノラル録音をディスク化することとした。
フランクの交響的変奏曲は、後述するがブリュショルリ最後の演奏会の1曲。ルーマニア国営放送による録音だが、放送局間の交換音源として、コピー・テープがフランス国立放送に送られ保管されていたと思われる。1966年にもなると、東欧諸国でも録音技術が向上しており、モノラルではあるものの、西欧諸国の放送局の録音に遜色のない音質(イタリア国営放送などより優秀かも知れない)。バランスも良くヒスノイズも極小。ディスク化に当たっては、周波数バランスを微調整し、周波数帯域を若干拡大したのみとした。ライブだが会場ノイズもほとんど聞こえない。
モニク・ドゥ・ラ・ブリュショルリは、決まり文句として使い古された表現だが、ドイツの高名な音楽評論家ヨアヒム・カイザーが著書で「彼女はヴァルキューレとなり、グランド・ピアノは軍馬となり、いまオクターヴ征討の戦いに進発する」と言わしめたヴィルトゥオーゾ・ピアニスト。当ディスクに聴くチャイコフスキーは、1951年アメリカにおけるセンセーショナルなデビュー公演でも披露し、1952年に米ヴォックス・レーベルにフランクの交響的変奏曲とともにレコーディング、現在もブリュショルリの代表盤となっている得意のレパートリー。ヴォックス盤は現在となっては録音も古く(録音当時でも見劣りした)、ステレオによる再録音が実現しなかったのは、レコード会社の怠慢としか言いようがない。ただし、本人もレコーディングには興味がなく、パリ音楽院における教授職を優先した事情もあったようだ(有名な生徒にシプリアン・カツァリアスがいる)。
当ディスクのチャイコフスキーはヴォックス録音から11年後、ブリュショルリ47歳の時の演奏だが、年齢としては当然だが技術の衰えは全くなく、すさまじいヴィルトゥオジティの一方、表現力がより深まった感があり、貧しいヴォックス録音に代わる録音がようやく登場したことになる。また、指揮のヴァンデルノートは当時36歳、この年にはシカゴ響を指揮してアメリカ・デビューを果たすなど、レコーディングやコンサートに大活躍していた全盛期に当たる。ヴォックス録音の指揮者ルドルフ・モラルトよりもブリュショルリとの相性も良いようだ。
フランクの交響的変奏曲のライブは、特に悲劇的な意味を持つ。当演奏会終了後の帰途で交通事故に遭遇して重傷を負い、特に左手の負傷がひどく、ピアニストとしてのキャリアを絶たれてしまった。その後は教育活動に専念したが、事故の後遺症による体調不良が続き、1972年に57歳の若さで死去することとなった。当然、演奏自体は事故の予感など微塵も感じられない見事なものだが、その後の演奏家の運命を知る者には冷静・客観的な鑑賞が出来ない。敢えて演奏そのものを評価すれば、こちらも貧しいヴォックス録音に代わる存在となる価値がある。当時29歳の指揮者エミル・シモンは、日本では無名だが、パリ音楽院でナディア・ブーランジェらに師事、1964年ブザンソン指揮者コンクールで第1位を獲得するなど、ヴァンデルノートと同様、新進気鋭の指揮者として注目されており、ブリュショルリにとって申し分ない伴奏を務めている。
前述のようにブリュショルリは、当ディスク以外に、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番とフランクの交響的変奏曲を1952年米ヴォックスにスタジオ録音していた。

●優秀録音 モーラ・リンパニー
1966年ステレオ・スタジオライブ
ブラームス ピアノ協奏曲第2番
オルガヌム110125AL
ブラームス ピアノ協奏曲第2番
モーラ・リンパニー(ピアノ)
ロベルト・ベンツィ指揮ヒルヴェルスム放送管弦楽団
1966年3月21日、ヒルヴェルスム・オランダ公共放送スタジオ
ステレオ スタジオ・ライブ
※英国の名女流モーラ・リンパニーによるブラームスの協奏曲。英国人コレクターによる提供音源で、オランダの各放送団体の集積地ヒルヴェルスムにおいて、聴衆を入れずに行われたラジオ放送のためのスタジオ・ライブ録音。マイク・セッティングの自由度も大きかったためか、非常に優秀な音質のステレオ。その音質の良さからエアチェックではなく放送局保管音源のコピーと思われる。オランダの放送局では1964年頃からステレオ録音を導入しており、当初はステレオ・セパレーションの悪さなど未熟な点も見られたが、2年後の当録音ではまったく問題なく高い完成度となっている。
ただし、オリジナルの状態では、当時のヨーロッパの放送録音によく見られた例だが、家庭のラジオで聴くことを想定してダイナミック・レンジが圧縮され、ピアニシモを大きくし、フォルティシモを抑える加工が行われており、ピアノや管楽器のソロと、オーケストラのトゥッティ(強奏)が同一音量レベルで平均化されているという問題があった。
ディスク化に当たっては、曲想に沿って各セクションの音量レベルを復元する作業を行い、現代のオーディオ・システムで再生しても違和感のない状態へと改善した。元々ノイズレスで録音スタジオのアコースティックも良好であるため、鑑賞上でまったく不満のない仕上がりとなった。
モーラ・リンパニーは、英本国では若い頃から第一級のピアニストとして高い評価を得ていたが、日本では、モノラル期のレコーディングが一部評価されたものの(評論家の西条卓夫は、ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番のLPではリンパニーが最良と推した)、LPが一般に広く普及したステレオ期のレコーディングがあまり注目されず、長らく地味な存在だった。しかし晩年に3回来日したことで、その実力が広く理解されるようになり、現在では日本でも偉大なピアニストの一人と評されるようになっている。
リンパニーは、モーツァルトやベートーヴェン、ショパン、ドビュッシーのほか広大なレパートリーを持っていたが、1940年にハチャトゥリアンのピアノ協奏曲の英国初演を行うなど、特にロシア作品を好んで取り上げ(母親がロシアで英語教師をしていた影響もあろう)、特にラフマニノフについては、第4番を除くピアノ協奏曲3曲、前奏曲集の録音などを行った(前奏曲集全曲は3回録音、1回目は世界初録音)。他にもサン・サーンスの協奏曲やリトルフのスケルツォなど技巧的な作品をレコーディングしているが、日本では、リンパニーについてヴィルトゥオーゾ・ピアニストという認識はなく、ラフマニノフ本人から自作の演奏を絶賛されたという出所不明のエピソードも、技巧面ではなく叙情的な表現面について評価されたのだろう言われてきた。それは再評価が進んだ現在でも同様といえる。
今回、リンパニーの初レパートリーとなるブラームスの協奏曲は、高度な技巧を要求する割には聴き映え(弾き映え?)のしない作品と言われ、技巧に優れたピアニストが取り上げると、力業(ちからわざ)でねじ伏せたような印象となる一方、技巧の弱いピアニストが取り上げると、演奏困難な何とも弾きにくそうな作品と感じる。
その点で当ディスクのリンパニーの演奏は、表面的に際だった技巧は目立たないものの、いくつもの難所を軽やかに乗り越え、実にエレガントな演奏に聴こえる。元来、高度な演奏技術を持ちながらも、それを前面に押し出さず、抽象的な用語だが「音楽的」に表現することを目指しているのだろう。来日時にラフマニノフのピアノ協奏曲第3番を聴いた聴衆も「若いピアニストが大暴れして弾きこなす作品を、最後まで涼しい顔して淡々と演奏していた」とのこと。演奏スタイルは全く異なるが、晩年のバックハウスの演奏にも通じる点があり、当ディスクはリンパニー再評価(再々評価?)の一端となるかも知れない。
ここでもう一つ注目すべきは、ロベルト・ベンツィの伴奏。11歳で指揮者としてデビューしたが、その後は伸び悩み「大成できなかった悲劇の天才少年」という評価が一般的だが、当ディスクの指揮はそれを一変させる見事なもの。ブラームスの協奏曲は一般に器楽伴奏付き交響曲とも呼ばれるほど管弦楽の比重が大きいが、ここでのベンツィは、リンパニーを確実にサポートしつつ、スケールの大きい充実した演奏を繰り広げている。オーケストラは決して一流とは言えないが、その弱さも巧みにカバーしているようだ。録音当時ベンツィは28歳、特定のオーケストラのポストには就かず、各地の有名団体への客演を行っていた。「天才少年」の評判も残っており、引く手あまただったのだろう。後年は、ボルドー・アキテーヌ国立管やアーネム・フィルの音楽監督など、決してメジャーとは言えない団体のポストを歴任したが、おそらくペーター・マークと同じく、世界中を忙しく飛び回る「スター演奏家」としてのキャリアを拒否したのではないか。「大成できなかった」わけではないと考えられ、ボルドーやアーネムにおける仕事も再評価・再注目すべきだろう。
ちなみにオーケストラのヒルヴェルスム放送管は、一般に知られているフルネやワールトが常任だったオランダ放送フィルと別団体で、録音当時は同じくオランダ公共放送(NRU)所属の第2オーケストラに位置づけられた団体。正式名はOmroep
Orkest(放送管弦楽団)という素っ気ないもので、他にもNRU Radio Philharmonic
Orchestraなど、レコーディングでは様々な名称が使われており混乱気味だが、歌劇やバレエなどの公演も担当しており、ヒルヴェルスムの放送スタジオから出て、オランダ国立歌劇場やコンセルトヘボウなどでも演奏していたようだ。現在は他団体との合併などを経て改組・縮小され、室内管弦楽団として存続している。
上記のように、モーラ・リンパニーはブラームスのピアノ協奏曲第2番のスタジオ録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音である。
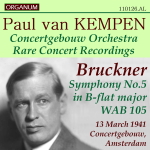
●貴重録音
ケンペン/コンセルトヘボウ 1941年ライブ
ブルックナー 交響曲第5番
オルガヌム110126AL
ブルックナー 交響曲第5番(ハース版)
パウル・ファン・ケンペン指揮コンセルトヘボウ管弦楽団
1941年3月12日、アムステルダム・コンセルトヘボウ
モノラル ライブ
※パウル・ファン・ケンペンとコンセルトヘボウ管によるブルックナー交響曲第5番の貴重なライブ録音。アメリカ人コレクターによる提供音源で、オランダ放送のアーカイブから最近発見されたもの。第二次世界大戦中の1941年、ラジオ放送と併せて78回転12インチ・アセテート・ディスク19面(18面という情報も)に録音されたという。当時のオランダ放送の録音技術は決して低くはなかったが、メンゲルベルクのライブ録音の例に見るように、アセテート・ディスクの保存状態の善し悪しにより、時にはスクラッチ・ノイズが過大で鑑賞の大きな妨げとなる場合もある。当ディスクの場合も、19面のアセテート・ディスクごとのコンディションに差があり、状態が悪いものも散見された。しかし、さらに大きな問題は、第一・第四楽章のそれぞれ後半にドロップアウトが多数存在したこと。テープ録音の場合、記録面の磁性体が剥がれると、その箇所は再生時に無音となり音切れ(ドロップアウト)が生じる。しかし、アセテート・ディスクの場合は音溝が破壊されても無音となることはなく、相応のノイズが生じるので、この点は疑問であったが、アメリカ人コレクターが音源を入手した段階で既にドロップアウトが存在しており、真の原因は不明である。おそらくアセテート・ディスクからデジタル・レコーダーにダビングした際、ディスクの傷などによる過大なノイズが入った場合にデジタル・レコーダーがミュート(無音化)するように設定されていたのではないかと想像される。
このままでは欠落が多く鑑賞の大きな妨げとなるため、ディスク化に当たっては、ドロップアウト部分と同一の楽音を他の箇所からコピーして空白部に埋める作業を行った。幸いブルックナーの作品はリピートが多く、十数カ所のドロップアウトを修復することが出来た。一方、スクラッチ・ノイズについては慎重にノイズ処理を行ったが、特にノイズが多い数カ所は、ノイズを完全に除去すると音楽部分に悪影響を及ぼすため、わずかにノイズが残った箇所もある。
結果的には、フィリップス原盤のメンゲルベルクのライブ録音と同等の音質改善を図ることができ、この種のアセテート・ディスクや78回転SP原盤から復刻したCDを聴き慣れたリスナーであれば、全く不満なく音楽を鑑賞できるレベルとなっている。
ケンペンはブルックナーについては、交響曲第4番を1950年に独テレフンケンにスタジオ録音したのみで、交響曲第5番は初登場となる貴重な録音。推進力・活力に富むケンペン本来の演奏スタイルと、ブルックナー作品の様式は完全に一致しているとは思えないが、「厳格」である一方「無愛想」とも言われる交響曲第5番を自らのスタイルとうまく融合させ、巧みにまとめ上げている。ケンペンは、レコーディングではなぜかポピュラー小品の録音が多く、レコード会社はその器用さを重宝したのだろうが、ブルックナーでも器用さがプラスに活かされていると言える。コンセルトヘボウ管は、ブルックナー演奏の長い伝統があるが、メンゲルベルクはなぜか第5番のみ演奏しておらず、ケンペンの演奏は、年史的には1918年のコルネリス、1924年のムック、1931年のシューリヒト、1934年のワルター以来の演奏となる。
1941年の演奏会は、ケンペンの記念すべきコンセルトヘボウ管デビュー・コンサートに当たり、本来は祝福されるべきものであるはずだが、様々な問題を含んだコンサートと言わざるを得なかったと思われる。当日は定期演奏会で、13日と15日の2回公演(ただし15日はハーグにおけるツアー公演)、プログラムは、プフィッツナーの付随音楽「ハイルブロンのケートヒェン」序曲、ブラームスの「アルト・ラプソディ」(ローレ・フィッシャー独唱、アムステルダム・ベルカント・アカペラ合唱団)、休憩を挟んで後半にブルックナーというもの。
実は、予告ではベイヌム指揮による異なるプログラムが発表されており、急遽ケンペン指揮の上記プログラムとなったとの記録がある。ベイヌムの急病などが理由であれば同一プログラムを引き継ぐことも多いが、アルト歌手や合唱団を新たに招いており、かなり以前からケンペンに交代させることが計画されていたと言うべきだろう。当時は第二次世界大戦中で1940年5月以降、オランダはナチス・ドイツの占領下にあった。ケンペンはオランダ出身で、1913年から4年間コンセルトヘボウ管のヴァイオリニストを務めたが、1916年からはドイツのポーゼン、ドルトムントなどのオーケストラでコンサート・マスターを務め、1932年にはドイツ国籍を取得。指揮者としてオーバーハウゼン歌劇場で音楽監督、1934年から1942年までドレスデン・フィルの首席指揮者を務めた。ということは、オランダ出身でコンセルトヘボウ管の元メンバーながら、1941年現在、オランダ人にとっては占領国ドイツ人の指揮者を定期演奏会に迎えた形になり、しかも当初予定していたベイヌムから代わったという事情がある。この交代がナチス・ドイツ占領軍の意向か、または、戦後ナチスに協力したとして追放されたメンゲルベルクの意向によるものかは不明だが、ケンペンに対するオランダ人の反感が醸成されても不思議ではない事態である。なお、ケンペン公演1年半後の1942年10~11月にも、ベイヌムが同じくブルックナー交響曲第5番を演奏しており、ケンペンへの無言の批判のようにも思える。
演奏会自体は、録音からも分かるように盛大な拍手で終了しており、トラブルはなかったようだが、その後、戦時中に限っては、ケンペンはコンセルトヘボウ管を1942年12月に2回指揮したのみで終わっており、オランダの聴衆やコンセルトヘボウ管にとってケンペンは招かれざる客だったようだ。なお、公演とは別だが、ケンペンとコンセルトヘボウ管は1943年5月、独ポリドール(グラモフォン)にシューベルトの交響曲第8(9)番「グレート」をレコーディングしている。
1945年、第二次世界大戦が終結。オランダはナチス・ドイツから解放され、1946年初頭、ケンペンはオランダに戻った。ドイツ国籍のため、戦時中の彼に非難されるような行為がなく、音楽活動を行うための労働許可証は得られたが、再帰化申請は認められなかった。ただ、オランダ国内では音楽活動は困難だったようで、フランス、スペイン、イタリアなど、主に国外で客演指揮を行った。1949年になって、オランダ放送フィルの首席指揮者に就任。オランダ国民が反感を持っていたケンペンが就任できた事情は不明だが、終戦後4年が経過し、オランダ国内の多くのナチス協力者に対する活動停止処分が解除されつつあった状況と、オランダ公共放送がケンペンの実力を認めた結果であろう。オランダ放送フィル首席指揮者就任後の騒動等ついては、当レーベルのケンペン指揮ブラームス交響曲第1番(オルガヌム110077AL)の解説を参照していただきたい。
ケンペンについて日本では、昭和30年代半ば(ということはケンペンの最晩年)に至っても、レコード専門誌などで評論家から「彼はまだ若い」などという発言が出ており、戦前にポピュラー小品をおびただしく録音した中堅指揮者というイメージが抜けていなかったようだ。当時はようやくフィリップス原盤(当時の日本では提携先の米コロンビア経由のエピック・レーベルとして発売)によるベートーヴェンの交響曲などが発売されつつあったから、ケンペンが少なくとも更に数年存命し、レコーディングが更に増えていれば、早くから日本でも巨匠として評価されたと思われる。
上記のように、パウル・ファン・ケンペンはブルックナーの交響曲第5番のスタジオ録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音である。
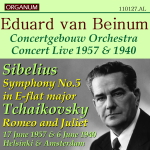
●音質良好
ベイヌム/コンセルトヘボウ 1957年・1940年ライブ
シベリウス 交響曲第5番ほか
オルガヌム110127AL
シベリウス 交響曲第5番
チャイコフスキー 幻想序曲「ロミオとジュリエット」
エドゥアルド・ファン・ベイヌム指揮コンセルトヘボウ管弦楽団
1957年6月17日、ヘルシンキ・Aエキシビション・ホール
1940年6月6日、アムステルダム・コンセルトヘボウ
モノラル ライブ
※ベイヌムとコンセルトヘボウ管によるシベリウスの交響曲第5番とチャイコフスキーの「ロミオとジュリエット」。シベリウスはアメリカ人コレクターによる提供音源。また、チャイコフスキーはドイツ在住ロシア人コレクターによる提供音源。いずれもエアチェックではなく、放送局保管音源のコピーと思われる。テープ録音のシベリウスはモノラルながら年代の水準を上回る良好な音質で、1960年代前半の録音に匹敵。チャイコフスキーは古いアセテート・ディスク録音だが、スクラッチ・ノイズは極小で当時としては異例なほど良好な音質。シベリウスと比較しても遜色ない。ディスク化に当たっては、シベリウスは、音質を損ねない範囲でヒスノイズの低減、チャイコフスキーは、わずかに残っていた大きめのスクラッチ・ノイズを除去した程度で、十分鑑賞に堪える音質とすることができた。
ベイヌムは、シベリウスについては英デッカや蘭フィリップス(独テレフンケンにも)管弦楽作品はいくつかスタジオ録音を残しているが、交響曲の録音は行わなかった。コンセルトヘボウとの演奏記録を見ても、交響曲第5番のみ1955年と1957年に計6回取り上げたのみである。他のオーケストラへの客演で第5番以外の作品を演奏した可能性は否定できないが、通常のレパートリーとしていなかったことは確かだ。そもそも第二次世界大戦前のオランダではシベリウスの交響曲への理解が進まず、コンセルトヘボウ管においては、メンゲルベルクは全く取り上げず(管弦楽作品は演奏しているが)、1939年以前に限ると、1911年コルネリス(第2番)、1913年ブゾーニ(第4番、作曲家・ピアニストしても知られるフェルルッチョ・ブゾーニだ)、1923年ムック(第1番)、1927年モントゥー(第2番)、1934年ワルター(第7番)と、わずかしか演奏されていない。
当ディスクの録音は、本拠地コンセルトヘボウではなく、1957年ヘルシンキ・フェスティバルのシベリウス・ウィークにおけるライブで、ベイヌムが第5番を演奏した最後の記録に当たり、数少ない演奏機会を捉えた貴重な録音。ベイヌムは1955年の定期演奏会でも取り上げているだけに、シベリウスの語法を深く理解し違和感なく表現していると言える。この時の演奏会は、前半にメンデルスゾーンの交響曲第4番「イタリア」、ドビュッシーの交響詩「海」、休憩を挟んで、シベリウスの交響曲第5番、アンコールとして「フィンランディア」というプログラム。おそらく他の曲目の録音も残っていると思われる。
一方のチャイコフスキーは、英デッカにスタジオ録音し、コンセルトヘボウ管と36回も取り上げた得意のレパートリー。当録音は奇しくもその第1回目の演奏に当たる。ただし、1956年の演奏が最後となっており、その後はベイヌム自身の趣向の変化があったのかも知れない。ちなみにメンゲルベルクもこの作品を好み、コンセルトヘボウ管と94回も取り上げているが、1939年11月が最後の演奏となり、翌1940年6月の当録音でベイヌムに引き継いだ形となった。当演奏は、前任者メンゲルベルクのカラーが色濃く残っており、硬いフォルティシモや濃厚な旋律表現など、新即物主義的なベイヌムらしからぬスタイルとなっている。しかし、メンゲルベルクのような恣意的なテンポの変化やアクセントなどはなく、時代が一歩進んだ感がある。この時の演奏会は、チャイコフスキー生誕100年を記念した演奏会で、前半に「ロミオとジュリエット」、続けてピアノ協奏曲第1番(ピアノ独奏:ゲオルゲ・ファン・レネッセ)、休憩を挟んで、後半が交響曲第6番「悲愴」というもの。本来はメンゲルベルクが指揮する予定だったがベイヌムに代わったという。このような記念すべき演奏会にメンゲルベルクが登場しないことは考えられず、おそらく急病などが理由と思われる。一方、ベイヌムによる「悲愴」の録音が残っていれば非常に興味深い。
エドゥアルド・ファン・ベイヌムは、上記のようにシベリウスの交響曲第5番のスタジオ録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音。一方、チャイコフスキーの「ロミオとジュリエット」は、1950年英デッカにロンドン・フィルとスタジオ録音していた。
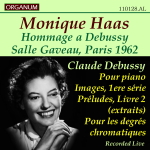
●優秀録音 モニク・アース ドビュッシー・リサイタル
1962年サル・ガヴォー・ライブ
オルガヌム110128AL
ドビュッシー
「ピアノのために」
映像第1集
前奏曲集第2巻から
「第8曲 水の精」「第11曲 交代する三度」「第12曲 花火」
練習曲集第2部から
「第7曲 半音階のための練習曲」(アンコール)
モニク・アース(ピアノ)
1962年6月3日、パリ・サル・ガヴォー
モノラル ライブ
※フランスの名女流モニク・アースによるリサイタルのライブ。英国人コレクターからの提供音源で、音質の良さからエアチェックではなく、放送局保管音源のコピーと思われる。オリジナルの音源はノイズも少なく、放送局による手慣れた感じの安定した音質。ただし、そこで鳴っていた音をとりあえず収録したという状態で高域不足のやや地味な音作り。このままではドビュッシー作品らしい輝きに乏しく、演奏の魅力を十分に伝えているとは言い難かった。ディスク化に当たっては、周波数バランスを調整、音質を損ねることを防ぎつつヒスノイズを低減、前半と後半で録音レベルが異なっていたため音量の平均化等々の作業を行った結果、モノラルながら魅力的な音質へと改善することが出来た。1950年代後半、モノラル末期のメジャー・レーベルのスタジオ録音と同等の音質と言える。会場ノイズもほぼ皆無。
コンサートは、"Hommage a Claude
DEBUSSY"(クロード・ドビュッシーを讃えて)と称するドビュッシー特集で、フランス国立放送パリ・アンテルによる公開収録。一般的な演奏会よりも短いのは放送時間の都合と思われるが、これは公開収録前半の第1部らしく、別の演奏者による第2部が開催されたらしい。モニク・アースのリサイタルについては、最後に本人の挨拶と共にアンコールを演奏しており、完結している。
放送時間の制約のためか、「ピアノのために」と映像第1集は全曲演奏、前奏曲集第2巻は3曲のみの抜粋演奏だが、様々な性格の作品を組み合わせ、しかも、練習曲集第2部から軽めの作品をアンコールとして取り上げるなど、コンサート・プログラミングとしては巧みな構成。ベテランらしい老練さを感じる。
モニク・アースは、同世代のフランスの女流ピアニストの中ではレコーディングにも恵まれ、日本でも国内盤が早期から発売され知名度が高い。1946年仏デッカへのレコーディングが初録音のようだが、1940年代後半~1960年代半ばにはドイツ・グラモフォン(DGG)でフランス系作品の録音を多く手がけ(ほかにモーツァルトやシューマン、バルトークなども)、1960年代後半以降は仏エラートでドビュッシーとラヴェルの作品全集などを録音しており、それらの多くは現在でも入手可能である。
またフランスのピアニストは、男女問わずプロ・デビューしてしばらくすると、並行してパリ音楽院やエコール・ノルマルなどで長年教育活動を行い、演奏活動を制限することが多いが、モニク・アースは例外で、パリ音楽院で教えたのは1967~1970年の3年間のみ。その他にザルツブルク・モーツァルテウム音楽院のマスタークラスを受け持った程度で、演奏活動優先だったようだ。来日こそしなかったが、海外公演も頻繁に行い、アメリカでは1960年にボストン響やデトロイト響などと共演しており、国際的な名声を確立したと言える。
知名度が高く、レコーディングが多く、身近に思えることが却って災いした訳ではないと思うが、よく例えられる、パリ音楽院を中心とするフランス流派の教育を受けた女流ピアニスト=いわゆるグラン・ダーム(grande
dame、貴婦人・名声のある女性の意)の一群(ルフェビュールやタリアフェロら)から、モニク・アースは外れているような印象もある。また、演奏スタイルについても、マルグリット・ロン以来の伝統的奏法を踏まえた上で、よりインターナショナルなスタイルを目指した傾向があり、これも伝統的でローカルなフレンチ・ピアニズムを期待する保守的なリスナーの好みとは異なるものがあったかも知れない。
経歴を見ると、夫であるルーマニア出身の作曲家マルセル・ミハロヴィチを通じて、エコール・ド・パリと呼ばれたパリ在住の外国人作曲家たち、マルティヌー、チェレプニン、タンスマンなどと交流し、バルトークやヒンデミットの作品を早くから取り上げるなど、フランスという枠に留まらない活動していたことが理解できる。DGGというフランス国外のレーベルがレコーディング契約したのも、そのようなモニク・アースの国際性に着目したからであろう(要はフランス以外でレコードの売れ行きが見込める)。
とはいうものの、当ディスクに聴くドビュッシーは、まぎれもなく洗練を極めたフレンチ・ピアニズムの典型と言える演奏であり、最良の意味でのスタンダードな演奏とも言える。フランスのピアニストと言っても様々な演奏スタイルの持ち主がおり、ピアニスト個々人の個性やくせをフレンチ・ピアニズムと錯覚・誤解していた傾向があったのかも知れない。その中にあって、モニク・アースは特別な存在だったと思われる。当ディスクは、時代的にはDGGとの契約時期と重なるが、DGG特有の「コンサート・リアリズム」とは異なる録音スタイルで、ライブ特有の自由さも加わって、演奏もより華やかな印象があり、注目すべき録音と言える。
モニク・アースは、当ディスクの全作品を1970年仏エラートにスタジオ録音したほか、「ピアノのために」第3曲トッカータを1949年、練習曲集第2部「第7曲
半音階のための練習曲」を1951年、前奏曲集第2巻「第8曲 水の精」「第11曲 交代する三度」「第12曲 花火」を1963年にそれぞれドイツ・グラモフォンにスタジオ録音していた。
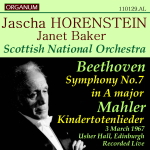
●優秀録音 ホーレンシュタイン/スコティッシュ・ナショナル管
ベートーヴェン交響曲第7番、マーラー「亡き子を偲ぶ歌」
1967年ライブ
オルガヌム110129AL
ベートーヴェン 交響曲第7番
マーラー「亡き子を偲ぶ歌」
ジャネット・ベーカー(メゾ・ソプラノ)
ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮スコティッシュ・ナショナル管弦楽団
1967年3月3日、エジンバラ・アッシャー・ホール
モノラル ライブ
※ホーレンシュタインがスコティッシュ・ナショナル管に客演した際のライブ録音。英国人コレクターからの提供音源で、オリジナルはFMモノラル放送のエアチェック。家庭用テープレコーダーが普及した時代でもあり、音質は基本的に良好だったが、受信障害によるパルスノイズ混入や、テープの経年劣化によるドロップアウト、高音域の音質劣化など、古い録音テープに起こりがちな瑕疵も散見された。また、放送局側の責任だが、ピアニシモが小さすぎて聴き取れない反面、フォルティシモが過大という問題もあった。ディスク化に当たっては、音質低下を防ぎつつノイズ除去、ドロップアウト補正、イコライジングによる周波数バランス調整等々を行った結果、モノラルながら、ステレオ録音並みの良好な音質へと改善することが出来た。一般的な鑑賞には不満のない状態と思われる。会場ノイズも少ない。
1933年、ユダヤ系のホーレンシュタインは、デュッセルドルフ歌劇場音楽監督の地位をナチスによる批判や圧力によって辞任後、特定の歌劇場やオーケストラでポストを持たないフリーランス指揮者として生涯を過ごしたが、残されているライブ録音は比較的英国の団体が多いようだ。BBCが熱心に録音し放送した結果とも思われるが、フランス国立放送管とはまとまった録音が残っており、第二次世界大戦中に国籍を取得したアメリカの団体にも、公開されていないだけである程度の録音が残されているらしい。ただし興味深いのは、1950年代に米ヴォックス・レーベルに大量の録音を行ったものの、同社の本拠地ニューヨークにはあまり縁がなく、ニューヨーク・フィルとは1943年に夏の野外コンサートを4回指揮したのみ(共演したヨーゼフ・ホフマンとナタン・ミルシテインに注目が集まってしまい、ホーレンシュタインは脇役だった)。カーネギー・ホール出演も1969年にアメリカ響2回、1964年アメリカン・オペラ・ソサエティ1回(ただしブゾーニの「ファウスト博士」という意欲的上演)で、メトロポリタン歌劇場への出演もない。ニューヨーク以外では、1950年代にセントルイスのリトル・シンフォニー管(セントルイス響とは別団体)を2シーズン指揮後、各地のオーケストラへの客演はあったものの、アメリカにおけるキャリアは大成功とは言い難かったようだ。
一方で、エーリヒ・クライバーの紹介もあって中南米では頻繁に客演を行い、英国とフランスでは客演依頼が続いた。特に英国では1959年にロンドン交響楽団(LSO)と行ったマーラー交響曲第8番公演のセンセーショナルな成功は、同国においてマーラー演奏については、ホーレンシュタインはクレンペラーと並ぶ評価を得ることとなり、1960年のマーラー生誕100周年を祝う10回のコンサートのうち、ホーレンシュタインは3回のコンサートを担当した。
当ディスクは、既に英国での評価が定まった時期のスコットランドへの客演で、ベートーヴェン・マーラー共に、特に個性的というわけではないが、手際が良いという以上の高水準の演奏。インターナショナルな傾向を持ちつつも、ドイツの巨匠指揮者の伝統的な演奏スタイルを感じさせる点で、客演にもかかわらずホーレンシュタインの老巧さを感じる。得意としたマーラーは名手ジャネット・ベーカーの歌唱も光る。コンサートは、おそらく序曲などの小品、続いてマーラー、ベートーヴェンというプログラム構成だったと想像される。
ホーレンシュタインはレコーディングについて、前記のように米ヴォックスと1952年から1959年まで、ほぼ専属的に録音を行った。しかし、最後は社主ジョージ・メンデルスゾーン(同名の作曲家の子孫)とロイヤリティを巡ってトラブルとなり、それに懲りたか、特定のレコード会社と密接な関係を避けたように思われる。その後、英EMIや米リーダーズ・ダイジェスト、英ユニコーンなどに録音を行ったが、1962年頃、リーダーズ・ダイジェストのプロデューサー、チャールズ・ゲルハルト(元米RCAのプロデューサー)がホーレンシュタイン指揮LSOによるマーラーまたはブルックナーの交響曲全集録音を計画していたという。交渉先の米RCAが資金提供を拒否したため実現しなかったが、ホーレンシュタインによるマーラーやブルックナーのライブ録音の発掘(や捜索)が行われている現在から見ると残念なことであった。
結果的にホーレンシュタインは、マーラーやブルックナーのみならず、ベートーヴェンやブラームスなどでも交響曲全曲の正規のスタジオ録音を残さなかった。こちらも今後のライブ/放送録音の発掘に期待したい。
ホーレンシュタインはベートーヴェンの交響曲第7番のスタジオ録音を残さず、当ディスク以外に1956年と1966年にライブ録音していた。また、マーラーの「亡き子を偲ぶ歌」を1928年独ポリドールにハインリッヒ・レーケンパーと、1954年米ヴォックスにノーマン・フォスターとスタジオ録音したほか、1956年マリアン・アンダーソン、1970年カルメン・ルイーザ・レテリエルとライブ録音していた。
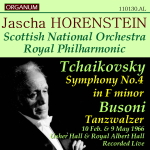
●優秀録音 ホーレンシュタイン/スコティッシュ・ナショナル管ほか
チャイコフスキー交響曲第4番、ブゾーニ「踊りのワルツ」
1966年ライブ/スタジオ放送ライブ
オルガヌム110130AL
チャイコフスキー 交響曲第4番
ブゾーニ「踊りのワルツ」
ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮
スコティッシュ・ナショナル管弦楽団、ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団
1966年2月10日、エジンバラ・アッシャー・ホール
1966年5月9日、ロンドン・BBCマイダ・ヴェイル・スタジオ
モノラル ライブ/スタジオ放送ライブ
※ホーレンシュタインによるチャイコフスキーとブゾーニのライブ/スタジオ放送ライブ。いずれも英国人コレクターからの提供音源で、オリジナルはFMモノラル放送のエアチェック。家庭用テープレコーダーが普及した時代でもあり、音質は基本的に良好だったが、チャイコフスキーについては、なぜか1・2・4楽章冒頭に歪みがあり、第2楽章に受信障害以外の金属的なノイズ(録音テープ劣化が原因か?)が時折混入、1・2楽章に対して3・4楽章の録音レベルが高く、しかも4楽章の強音にリミッターがかかりフォルティシモが弱いなど、様々な問題があり、原状のままでは鑑賞に不都合が多かった。ディスク化に当たっては、上記の問題について、音質を影響を与えないように注意深く配慮しつつ、一つずつ解消した。一方、ブゾーニは大きな問題はないものの、曲想も影響しているが、やや地味な音質でチャイコフスキーに比べて見劣りしたため、周波数帯域を拡大、イコライジング等で改善を図った。会場ノイズは極小。
ホーレンシュタインは1898年旧ロシア帝国・現ウクライナのキエフに生まれた。比較的裕福なユダヤ人の家系だったが、ポグロム(16世紀以降のドイツや東欧におけるユダヤ人迫害、ロシアでは20世紀初頭になっても頻発した)を避けるため、一家は1906年ドイツのケーヒスベルクに移住、ホーレンシュタインはヴァイオリンを習ったが、当地のギムナジウム(中等学校)でハンス・アイスラーと出会い親交を深めた。1911年ウィーンに移ると本格的に音楽修行を開始。1916年ウィーン・アカデミーに入学し、フランツ・シュレーカーに作曲、ヨーゼフ・マルクスに和声法を学んだ。同アカデミーではシュレーカーの弟子カロル・ラートハウスと知り合い、彼が亡くなるまで親しく付き合った。
アカデミー卒業後は、1920年にシュレーカーがベルリン高等音楽院に移籍したことに伴い、ホーレンシュタインもベルリンに移り住み、シュレーカーのクラスで学んだ。当時同じクラスには、アロイス・ハーバ、エルンスト・クルシェネク、ユリウス・ブルガーら、後に革新的な作品を生み出す逸材が揃っていた。ホーレンシュタインは、勉強の傍らウィーン交響楽団の第2ヴァイオリン奏者として1シーズン活動。当時は作曲家かヴァイオリニストを目指していたようだが、指の怪我によってヴァイオリニストのキャリアを断念し指揮者となることを決意。1922年古巣のウィーン交響楽団を振って指揮者デビューした。
その後、ベルリンで合唱指揮の大家ジークフリート・オックスに師事、その縁からフルトヴェングラーに認められて助手となり、彼の推薦により1928年デュッセルドルフ歌劇場のカペルマイスター(楽長)に就任、翌年には音楽総監督の地位を得た。デュッセルドルフでホーレンシュタインは、アルバン・ベルク、クルシェネク、クルト・ワイル、ヤナーチェクなど当時の現代作品を意欲的に取り上げ、クレンペラー率いるベルリン・クロル・オペラと並び称されるほどの注目を浴びた。しかし1933年、ユダヤ系のホーレンシュタインは、ナチス政権による批判や圧力によってデュッセルドルフ歌劇場音楽監督を辞任、その後はフランスやポーランド、ソ連を経て、第二次世界大戦勃発によりアメリカに亡命することとなった。
このような若い頃の経歴を見ると、ホーレンシュタインはロシア生まれながらも、ドイツの伝統的指揮者の典型的なキャリアを歩んでおり、現代作品を積極的に取り上げた点ではクレンペラーとも重なる(後に英国で評価された点も似ている)。このようなホーレンシュタインがチャイコフスキーを取り上げた場合、ロシア的な要素が薄いドイツ・ロマン派的表現となることは当然だろう。しかもフリーランスとして長く活動したため、限られた時間のリハーサルで手際よく、しかも高水準にまとめ上げる能力に秀でており(これは現代作品初演の際にも威力を発揮する)、スタイルはまったく異なるが、民族性が薄く洗練された演奏はピエール・モントゥーとも共通点がある。客演したスコティッシュ・ナショナル管は、決して超一流とは言えず、金管に一部ほころびもあるが、オーケストラの弱点を補いつつ、長所を活かす点も老巧さを感じる。
一方のブゾーニは生誕100年を記念した英BBCによるラジオ番組のために、聴衆を入れずに行われたスタジオ録音。1965年から66年にかけて、ホーレンシュタインは15作品ほどを録音している。ホーレンシュタインは1920年代、晩年のブゾーニと親交があり、1964年には彼の未完の歌劇「ファウスト博士」のアメリカ初演を行うなど、生誕100年記念の録音には適任だったろう。ブゾーニの作品は、今日(時折再評価の気運が高まりつつも)ほとんど忘れられた存在で、マックス・レーガーなどと並んで、専門家は評価するものの一般的人気は低く、演奏会にかけられる機会は極めて少ない。ブゾーニ作品は、同時代のリヒャルト・シュトラウスやマーラーの持つ大衆性や、最近再評価が著しいツェムリンスキーやシュレーカー、マルクスの耽美さ、シェーンベルクなど新ウィーン楽派ほどの前衛性もなく、理念先行で晦渋なイメージが強い。その中では「踊りのワルツ」(妙な訳だが)はヨハン・シュトラウス(父)に献呈された作品で、ブゾーニとしては比較的理解しやすい作品であり、ホーレンシュタインの解釈の巧みさが目立つ。
ホーレンシュタインは、チャイコフスキーの交響曲第4番、ブゾーニの「踊りのワルツ」ともにスタジオ録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音である。

●音質良好 ペルルミュテール ショパン・ライブ
ショパン 24の前奏曲、3つのマズルカ
1960年・1966年ライブ
オルガヌム110131AL
ショパン 24の前奏曲、マズルカ第1番、第32番、第19番
ヴラド・ペルルミュテール(ピアノ)
1960年12月5日、ロンドン・BBCマイダ・ヴェイル・スタジオ
1964年1月24日、ロンドン・ロイヤル・フェスティバル・ホール
モノラル ライブ
※フランスの名匠ペルルミュテールによるショパン・ロンドン・ライブ。英国人コレクターからの提供音源で、オリジナルは、前奏曲は英BBCが海外放送局への音源提供のために製作したLPレコード(BBCトランスクリプション・ディスクと呼ばれる)、マズルカはFMモノラル放送のエアチェックと思われる。前奏曲は、元はテープ録音だが、BBCは海外放送局向けに音源を提供する際にLPを製作して供給した。わざわざLPを製作するよりも、テープをコピーした方が手間もかからずコストも低いはずだが、放送局は意外に保守的で、輸送中の温度や湿度変化にはテープよりもLPの方が劣化トラブルが少ないという判断だったのだろう。このような例は、BBC以外にもフランスやドイツなどの放送局(さらに日本のNHK)でも見ることが出来る。基本的にプレス枚数は少なく100枚以下、放送で使用した後は廃棄処分されることになるが、一部が放送関係者を経て流出、さらに一時はBBCが余剰在庫のディスクを市販したこともあり、市場に出回ることは少なくないようだ。
当ディスクの前奏曲は、LP独特のスクラッチノイズが多く、また、録音には定評があるBBCとしては意外に冴えず鈍い音質。ディスク化に当たっては、ソフトウェアによって音質に影響を与えずにノイズを消去する一方、イコライジング等によって周波数バランスを調整し音質を改善した。一方のマズルカも、ノイズは少ないもののオリジナル録音は高域不足で中低音ばかり強調された音質、録音の問題というよりは、録音テープの経年劣化と思われる。ディスク化に当たってはイコライジング等によりピアノらしい響きの再現に努めた。
結果として、ショパンらしい繊細な音質が再現され、鑑賞に不都合がないレベルまで改善することが出来た。2会場とも会場ノイズは極小。
24の前奏曲は、BBC Thursday invitation
concertと銘打ったスタジオ・ライブ。普段は聴衆を入れないBBCマイダ・ヴェイル・スタジオに聴衆を入れた公開収録(聴衆は抽選等による無料招待だろう。拍手の様子から想像すると数百人程度か)。ペルルミュテールは当時56歳の円熟期。活発に演奏活動やレコーディングを行っていた時期に当たる。前奏曲については、同年4月にもロンドンで演奏、秋にはコンサート・ホール・ソサエティにレコーディングするなど、得意とする作品だったようだ。
3つのマズルカは、1964年にロイヤル・フェスティバル・ホールで行われたショパン・リサイタルから。当日はマズルカのほかに、バラード第4番、スケルツォ第3番、ポロネーズ第5番、そしてここでも24の前奏曲などが演奏された。
ペルルミュテールは、パリ音楽院でモシュコフスキやコルトーに学んだフランス楽派のピアニストで、ラヴェルの演奏で定評があるというのが一般的認識だが、旧ロシア・現リトアニアの生まれでユダヤ系ポーランド人の家系。3歳のとき一家でフランスに移住し、10歳でパリ音楽院に入学、21歳フランス国籍を取得している。ポーランドからフランスに移り住んだショパンとの共通点もあり、ポーランド人のペルルミュテールにとって、ショパンはフランス系作品と並んで重要なレパートリーだった。もちろん音楽教育をフランスで受けているため、いわゆるポーランド楽派(個性が強いのがマウツジンスキ、穏健なのがハラシェビッチやステファニスカか)とは異なる典型的なフレンチ・ピアニズムだが、1960年代のペルルミュテールのショパン演奏は、垢抜けた洗練さを持ちつつもどこかローカル色を感じる。
ちなみに当ディスクのライブと同年のスタジオ録音を比較すると、基本スタイルは変わらないものの、落ち着いたスタジオ録音に比べて、ライブは勢いがありダイナミックなイメージ。また晩年のニンバス・レーベル録音に聴く、穏やかで悟りを開いたような演奏とはかなり異なる(こちらも別の意味で名演だ)。
従来、ペルルミュテールは名教師で名演奏家であり、「趣味の良い」演奏をするフランスのベテラン・ピアニストの一人という位置づけだったが、今後、50歳代のペルルミュテールの録音発掘が進めば、彼がサンソン・フランソワやロベール・カザドシュなどと同格の、1960年代のフランスを代表するピアニストだったことが理解される日が来るかも知れない。
ペルルミュテールは、上記のようにショパンの前奏曲集を1960年コンサート・ホール・ソサエティ、1981年英ニンバスにスタジオ録音したほか、1972年にBBCに放送録音していた。また、マズルカ第32番を1986年英ニンバスにスタジオ録音していた。
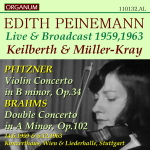
●音質良好 エディト・パイネマン
プフィッツナー ヴァイオリン協奏曲
ブラームス 二重協奏曲
1959年コンサート・ライブ、1962年スタジオ・ライブ
オルガヌム110132AL
プフィッツナー ヴァイオリン協奏曲
ブラームス 二重協奏曲
エディト・パイネマン(ヴァイオリン)
エンリコ・マイナルディ(チェロ)
ヨゼフ・カイルベルト指揮バンベルク交響楽団
ハンス・ミュラー=クライ指揮シュツットガルト放送交響楽団
1959年6月14日、ウィーン・コンツェルトハウス
1963年12月6日、シュツットガルト・リーダーハレ
モノラル コンサート・ライブ/放送スタジオ・ライブ
※近年再評価の気運が高まっているドイツの女流、エディト・パイネマンのキャリア早期のコンサート/放送スタジオ・ライブ。ドイツ在住のロシア人コレクターからの提供音源で、オリジナルは、プフィッツナーはおそらくオーストリア放送のエアチェック録音。ブラームスは(南ドイツ?)放送局保管音源のコピーと思われる。両者とも基本的には無難で良好な音質だが、プフィッツナーはややくすんだ印象でややナローレンジ、若干歪みやヒス・ノイズもあり、支障なく音楽を楽しめるレベルまでには達していなかった。一方、ブラームスはプフィッツナーに比べると年代も新しく、録音条件の良い放送スタジオ録音のため安定していたが、こちらはダイナミック・レンジが広すぎ、オーケストラに比べて独奏楽器の音が小さすぎるという問題があった。
ディスク化に当たっては、プフィッツナーは、FM放送の周波数上限15khzからCDの上限20khz程度まで周波数レンジを拡大、イコライジング等により高域(独奏ヴァイオリンの音域)を中心にバランスを調整、ソフトウェア等により音質を損ねない範囲でノイズを低減、歪みを解消した。また、ブラームスは家庭内での鑑賞に支障がないレベルまでダイナミックレンジを若干圧縮、独奏楽器を強調する操作を行った。結果として、プフィッツナーは、独奏ヴァイオリンの音に艶が出て、細部の表現も明確化、オーケストラも充実した響きとなり、演奏全体の存在感が増した。ブラームスも独奏楽器とオーケストラの音量バランスが適正となり、いずれも十分鑑賞に堪える音質へと改善された。
1959年録音のプフィッツナーは、同年のウィーン芸術週間におけるライブ。パイネマンは、カイルベルトが首席指揮者を務めていたバンベルク響演奏会のソリストとして出演、当時22歳で1956年ARD(ドイツ公共放送連盟)主催ミュンヘン国際コンクールで受賞後(当時は入賞順位はなく彼女のみが受賞)の間もない時期。プフィッツナーの熱心な紹介者だったカイルベルトのアドバイスを受け、ドイツ国内でもほとんど忘れられていたヴァイオリン協奏曲に取り組んでおり、当ディスクの演奏はその初期の例である。
とはいうものの、すでに立派な演奏で作品を十全に自らのものとしており、他の録音、例えば同じドイツの先輩格ラウテンバッハーの米ヴォックス録音よりも魅力的な作品として聴こえる(ラウテンバッハーの名誉のために付言すれば、ヴォックス録音は「知られざるヴァイオリン協奏曲」LPシリーズの一曲で、十分な準備もないまま一挙にまとめて録音された可能性が高い)。また楽器について当時はチェコ近郊クリンゲンタールにあったフィエカー製、あるいは1720年頃のロンドン・ダニエル・パーカー製ヴァイオリンを使っており、後年ジョージ・セルの尽力によって入手したグァルネリのような「凄み」のある音色ではないが、それでも十分に美しい。
パイネマンはその後も度々プフィッツナーの協奏曲を取り上げ、後述するように、1962年にロスバウトと共演した放送録音が近年ディスク化されたが、やはりカイルベルトとの共演は特別な意味を持つ。ちなみにこの時の演奏会は、前半がヒンデミットの「弦楽と金管のための協奏音楽“ボストン交響楽団”」、続けてプフィッツナー、休憩を挟んで後半がレーガーの「モーツァルトの主題による変奏曲とフーガ」という、かなり渋いドイツ・プログラム。このような中では、パイネマンのヴァイオリン独奏は、ひときわ鮮やかに聴こえたに違いない。なお、会場ノイズはほぼ皆無で静か。
一方のブラームスは、聴衆を入れずに行われた放送のための録音。チェロはベテランの名手マイナルディで、若いパイネマンはチェロを引き立てつつ、マイナルディの深い音楽性や表現を吸収しながら演奏しているように思える。指揮は長年シュツットガルト放送響の首席指揮者を務めたハンス・ミュラー=クライ。さすがに手堅くまとめているが、仮に同放送響の常連指揮者だったシューリヒトが共演していたら、即興的なとてつもない名演か、打ち合わせ不足で不完全燃焼に終わったのではなどと想像すると興味深い。
パイネマンは、その才能を見込んだジョージ・セルが後見役として、前述のように楽器の購入や有名オーケストラへの招聘など様々に関与し、レコーディングについても、レコード会社と安易に契約せず慎重に判断するようにアドバイスしたという。セルは、若い演奏家が作品への理解が足りないままポピュラー名曲を次々と録音させられ、次第に評価を下げていく有様を多く見てきたのだろう。結果としてパイネマンは、正式なレコーディングとしては、独グラモフォンにデビュー盤的意味でドヴォルザークのヴァイオリン協奏曲とラヴェルのツィガーヌ、後年マイナー・レーベルにブラームスのソナタや、スーク、バルトーク、ブロッホの小品を録音したほかは、レーガーやヨーゼフ・マルティン・クラウスなど地味な作曲家の録音を残したのみとなった。
パイネマンは、実際の演奏会ではポピュラーな作品を演奏する一方、レコーディングでは価値はあるものの埋もれた作品の録音を望んだようで、数多くの名手が名録音を残している有名作品をわざわざ録音する意味を見出せなかったのだろう。スターを目指す演奏家であれば、自らを売り込むセールス・ツールとしてレコーディングは重要である。パイネマンは、北米などへの海外ツアーを繰り返し来日公演も行っており、スター演奏家的に頻繁な演奏活動を行ったものの、単に聴衆を喜ばすだけのエンターテイナーになるにはいささか知的すぎたようだ。レコーディングについても、レコード会社を儲けさせて機嫌を取るつもりはなかったらしく、おそらく当ディスクに聴くプフィッツナーの録音も希望したと思われるが、大きなセールスが期待できないと考えるレコード会社と意見が合わず実現しなかった可能性が高い。
以上のように、エディト・パイネマンはプフィッツナーのヴァイオリン協奏曲のスタジオ録音を残さず、当ディスク以外には1962年にライブ録音していた。またブラームスの二重協奏曲もスタジオ録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音である。
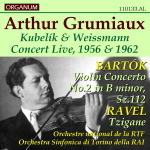
●音質良好 グリュミオー バルトーク ヴァイオリン協奏曲第2番ほか
1956年・1962年ライブ
オルガヌム110133AL
バルトーク ヴァイオリン協奏曲第2番
ラヴェル ツィガーヌ
アルテュール・グリュミオー(ヴァイオリン)
ラファエル・クーベリック指揮フランス国立放送管弦楽団
フリーダー・ワイスマン指揮トリノ・イタリア放送(RAI)交響楽団
1956年2月23日、パリ・シャンゼリゼ劇場
1962年2月2日、トリノ・イタリア放送オーディトリアム
モノラル、ライブ
※名手グリュミオーによるバルトークとラヴェルのライブ録音。バルトークは英国人コレクター、ラヴェルはアメリカ人コレクターからの提供音源で、オリジナルはいずれもエアチェックではなく、放送局保管音源のコピーと思われ、かなり良好な音質。ただし、放送局録音によく見られる傾向だが、そこで鳴っている音をとりあえず記録したというスタイルで、忠実ではあるものの、演奏を魅力的に聴かせようという良い意味での演出はなく、独奏ヴァイオリンも地味な印象だった。ディスク化に当たっては、周波数帯域を拡大、イコライジング等でバランスを調整することにより独奏ヴァイオリンを明確化、オーケストラもスケールアップして響くように処理した。結果として、それぞれの録音年代の水準を上回る音質を確保でき、鑑賞には不満のない状態とすることが出来た。2曲とも会場ノイズはほぼ皆無。
グリュミオーは、しばしばイザイ、デュボワを継ぐフランコ・ベルギー派の正統的後継者と言われ、フランス系作品はもとより、バロック期から古典派、ロマン派のスタンダード・レパートリーを得意としていたが、近・現代作品については、フランス系を除けばかなり控えめで、スタジオ録音を残したのは、ストラヴィンスキーとベルクの協奏曲、イザイ(グリュミオーの大師匠に当たる)、バルトーク、コダーイの小品などに限られ、1945年に初演を依頼されたウォルトンはもちろん、シベリウスやプロコフィエフの協奏曲すら録音を残していない。
当ディスクではバルトークのヴァイオリン協奏曲第2番を演奏しており、その意味で貴重な記録と言える。1956年の録音当時グリュミオーは34歳。14歳でデビューしており、すでに20年ほどのキャリアがあったが、まだ新しいレパートリーに意欲的に取り組んでいたようだ。残念ながら、その後、バルトークの協奏曲はグリュミオーのレパートリーからは外されたが、当ディスクで聴く限り、相性が悪いようには感じない。グリュミオー自身の演奏美学と何らかの齟齬があったのだろうか。
ちなみにこの演奏会は、クーベリック指揮フランス国立放送管の公開収録で、前半にオネゲルの交響曲第2番、続いてバルトーク、グリュミオーによるアンコールとしてイザイの無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番、後半にムソルグスキー=ラヴェル編曲の「展覧会の絵」という近・現代中心のプログラム。バルトークの協奏曲は主催者側の意向かも知れない。
一方、1962年録音のラヴェル「ツィガーヌ」は、ピアノ伴奏・管弦楽伴奏のいずれでもスタジオ録音を残しており、グリュミオー得意のレパートリー。安定した演奏を披露している。ちなみにここで注目すべきは指揮のワイスマン(1893~1984)。1920年代前半から、協奏曲伴奏やポピュラー小品など大量のレコーディング(1933年までに2000点以上と言われる)を行ったことで知られているが、日本では、第二次世界大戦後の活動についてはほとんど知られていない。資料を見ると、ユダヤ系のワイスマンはナチス政権による排斥を受け、1933年以降はオランダとアルゼンチンで活動、1938年にアメリカに拠点を移し、ニュージャージーやペンシルベニアなどのオーケストラの常任指揮者を歴任、1954年にヨーロッパに帰還、グリュミオーと共演当時はイタリア国立放送(RAI)の各オーケストラに客演を繰り返していたようだ。1974年に引退するが、1950年代後半からイタリア各地のオーケストラでマーラーの交響曲を集中的に取り上げており、当時としては非常に先進的な試みだったと言える。前記のようにレコーディングでは伴奏指揮が多かったが、ドイツ各地の歌劇場で修行を積んだこともあって合わせものは得意としており、当ディスクでも巧みなサポートを見せている。
アルテュール・グリュミオーは、バルトークのヴァイオリン協奏曲第2番のスタジオ録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音。また、ラヴェルの「ツィガーヌ」は、当ディスク以外に、1954年(管弦楽伴奏)、1962年(ピアノ伴奏)、1966年(管弦楽伴奏)それぞれオランダ・フィリップスにスタジオ録音したほか、1975年(管弦楽伴奏)ライブ録音していた。
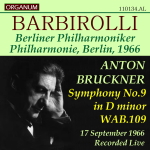
●音質良好 バルビローリ/ベルリン・フィル ブルックナー交響曲第9番
1966年ライブ
オルガヌム110134AL
ブルックナー 交響曲第9番(ノヴァーク版)
サー・ジョン・バルビローリ指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
1966年9月17日、ベルリン・フィルハーモニー・ホール
モノラル、ライブ
※バルビローリとベルリン・フィル(BPO)によるブルックナー交響曲第9番のライブ。ドイツ在住ロシア人コレクターからの提供音源で、オリジナルはいずれもエアチェックではなく、放送局保管音源のコピーと思われ、モノラルながら非常に良好な音質。ただ、出所はドイツの放送局ではなくオランダ放送らしい。放送局間の交換音源として送られたようだ。1966年に至ってもステレオではないことが惜しまれるが、当時、西ドイツの放送局は、部分的にステレオ録音を導入していたものの、本格的に普及したのは1960年代末であり、残念ながら一歩間に合わなかった。
なお、当演奏にはエアチェックと思われる既出盤があるが、欠落やドロップアウト、ノイズが多い上に、ラジオ放送を想定してフォルティシモを抑え、ピアニシモを大きくする圧縮加工が行われていたらしく、鑑賞には不都合が多かった。当ディスクの音源は既出盤とは異なり、欠落はなくノイズもわずかにヒスノイズが感じられる程度。ただし、既出盤ほどではないと思われるが、若干ダイナミックレンジが圧縮されていたため、ディスク化に当たっては、ダイナミックレンジを拡大。音質に影響を与えない範囲でヒスノイズを低減。結果的に、鑑賞には全く不満のない状態とすることが出来た。演奏のイメージも、既出盤の演奏はラフで大味な印象だったが、当ディスクでは、緻密でしかもバルビローリらしい情熱的な印象へと激変した。会場ノイズはほぼ皆無。
バルビローリはBPOと1949年にスコットランドのエジンバラで初共演、1950年にベルリンで再び共演、10年ほどのインターバルを経て、1961年に3度目の客演指揮を行った。この時の公演が大好評となり、その後バルビローリが亡くなる1970年まで毎年指揮、BPOとの共演は84回に上った。その間には、BPOの希望によりマーラー交響曲第9番のレコーディングを行うなど親密な関係を築いた。当時のBPO支配人ヴォルフガング・シュトレーゼマンによれば、マーラーの交響曲第9番については、「バルビローリの演奏を聴くまでは、(団員も含め)こんなに良い作品とは思っていなかった」とのこと。1960年代半ばになっても、ドイツでは当ディスクに聴くブルックナーに比べて、マーラー作品への評価が確立していなかったのだ。
当ディスクが録音された1966年、バルビローリは67歳を迎えていたが、ハレ管首席指揮者とヒューストン響音楽監督を務める傍ら、レコーディングや各地のオーケストラに客演する多忙な日々を送っていた。1月にはBPOに客演してマーラーの交響曲第6番などを演奏、同じく1月から2月にかけてハレ管を指揮、ブルックナーの交響曲第9番などを演奏、3月にはヒューストン響を指揮、米国内ツアーを行いニューヨークでマーラーの交響曲第5番を演奏(当演奏はプレミエ60117DFでディスク化済み)、4月から7月には再びハレ管を指揮、その間6月にはチューリヒ・トーンハレ管とジェノヴァのテアトロ・カルロ・フェリーチェ管に客演、7月にはロンドンで、ハレ管・ロンドン響・ニュー・フィルハーモニア管とともに英EMIにディーリアス、エルガー、シベリウス作品をレコーディング、8月にはモンテ・カルロ・フィルとフィレンツェ・テアトロ・コムナーレ管(別名5月音楽祭管)に客演後、ローマ国立歌劇場でプッチーニ「蝶々夫人」を英EMIにレコーディング、続けてローマ聖チェチーリア音楽院管に客演、9月には当ディスクに聴くBPOへの客演と、休むことなく活動を行っていた。
9月17日の公演は、ブルーノ・ワルターの生誕90周年を記念する演奏会で、前半にはモーツァルトの交響曲第40番、後半にブルックナーが演奏された。前記のマーラーとは異なり、モーツァルトやブルックナーは当然BPO伝統のレパートリーであり、当演奏が行われた半年前の3月16・17日にカラヤンがブルックナーの同曲を取り上げており(19日に独グラモフォンにレコーディング)、翌シーズン(1966~1967年)に当たるものの、シーズン開始早々に同じ曲を取り上げていることが異例であるとともに、記念演奏会を任せるほどにBPOがバルビローリを高く評価していたと言える。
バルビローリがブルックナーをレパートリーとしたのは、それほど古いわけではなく、1940年ニューヨーク・フィル常任指揮者時代に第7番を1回2公演取り上げているが、本格的に取り組んだのは第二次世界大戦後の1950年代からである。当時のイギリスではブルックナー作品に対する理解が遅れ、1960年代に入っても、BBCラジオはクレンペラー指揮のブルックナーを深夜の「現代音楽専門番組」で放送していたという。
このような状況下、バルビローリも交響曲第9番をかなり遅れて1961年に初めて演奏しているが(ハレ管とBBCノーザン響の合同オケ)、それから5年後の当ディスクの演奏では、既にブルックナー独特の語法を完全に自家薬籠中の物としている。またブルックナーの演奏では経験豊富なBPOの貢献も大きいと思われ、現在3種確認されているバルビローリによるブルックナー交響曲第9番の中では出色の演奏と言える。
ジョン・バルビローリは、ブルックナーの交響曲第9番のスタジオ録音を残さず、当ディスク以外に、前記のように1961年ハレ管とBBCノーザン響の合同オケ、1966年ハレ管とライブ録音していた。
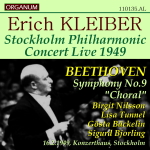
●音質良好 エーリヒ・クライバー/ストックホルム・フィル
ベートーヴェン交響曲第9番 1949年ライブ
オルガヌム110135AL
ベートーヴェン 交響曲第9番
ビルギット・ニルソン(ソプラノ)
リサ・テュネル(アルト)
イェスタ・ベッケリン(テノール)
シーグルド・ビョルリンク(バリトン)
エーリヒ・クライバー指揮ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団・合唱団
1949年2月16日、ストックホルム・コンツェルトハウス
モノラル、ライブ
※エーリヒ・クライバー指揮ストックホルム・フィルによるベートーヴェン交響曲第9番のライブ。ドイツ在住ロシア人コレクターからの提供音源で、エアチェックではなく、放送局保管音源のコピーと思われるが、オリジナルは33回転のアセテート・ディスクらしくスクラッチ・ノイズが目立った。ただ、録音年代から想像すると、元々はテープ録音されたものの、放送後、当時は高価だったテープを再利用するため、録音消去前にアセテート・ディスクにダビングして今日まで保管されてきたと思われる。元がテープ録音であるためか、音質そのものは比較的良好。独唱や合唱などのバランスも問題なかった。ただし、アセテート・ディスクの周波数帯域の狭さに起因する高域不足、経年劣化によって一部スクラッチ・ノイズが楽音を覆い隠している箇所があった。
ディスク化に当たっては、耳障りなスクラッチ・ノイズの低減、ノイズでマスキングされている楽音の修復、周波数レンジの拡張等を行った。結果的にスクラッチ・ノイズは大幅に低減され、また周波数レンジ拡張により、1950年代のテープ録音に匹敵する音質を確保することが出来た。1950年代のモノラルLPを聴き慣れているリスナーであれば、ストレスなく演奏を楽しめるレベルと言える。会場ノイズも極小。
エーリヒ・クライバーというと、現在は「あのカルロスの父」という常套句が付くが、父は1923年に33歳でドイツを代表する歌劇場であるベルリン国立歌劇場の音楽監督に就任するなど、当時はドイツを代表する名指揮者の一人だった。しかし、1934年に当時のナチス政権を嫌いベルリン国立歌劇場音楽監督を辞任してドイツを出国、ヨーロッパ各地で客演指揮を行う傍ら、1937年からはアルゼンチンのコロン歌劇場を中心に南米や北米で活動。第二次世界大戦後の1948年ヨーロッパに帰還(1947年という資料もある)、ロンドン・フィルやウィーン・フィルに客演、英デッカとレコーディング契約、1950年からは大戦で疲弊した英ロイヤル・オペラ(コヴェント・ガーデン)の再建に貢献した。その後、1951年には17年ぶりにベルリン国立歌劇場に客演、当時の東ドイツ政府から音楽監督就任を要請され1954年に就任したが、政府が歌劇場の運営に介入したため反発して翌年辞任、その後はフリーランスとして活動した。
クライバーの残したスタジオ録音には交響曲など管弦楽作品が多いが、これは制作費用の都合や営業政策によるもので、基本的には歌劇場指揮者だったと言える。当ディスクは、ヨーロッパ復帰後まもない1949年にストックホルム・フィルに客演した際の録音。前年の3月にも同フィルに客演して同一独唱陣とベートーヴェンの荘厳ミサ曲を演奏しており、2年の客演契約だったのだろう(1949年にはストックホルム王立歌劇場で「さまよえるオランダ人」も指揮している)。前述したベルリン国立歌劇場との関係が深まる前、自由に客演活動していた時代で、ロンドンやウィーンのほか1951年にはフィレンツェでヴェルディの「シチリアの夕べの祈り」(マリア・カラスと共演)という意外なレパートリーまで演奏している。
歌劇場の経験が豊富なだけに、第9の特に声楽部分の指揮は見事。独唱陣は当時のスウェーデン声楽界のトップメンバー。ソプラノのビルギット・ニルソンはまだ31歳で声が若い。スウェーデン国内の評価は高かったものの、国外では無名で、その後1951年グラインドボーン音楽祭でモーツァルト『イドメネオ』に出演して国際的な名声を獲得した。ニルソンの伝記では、クライバーとの共演について「(前年に続き)また彼の指揮で歌うことができて嬉しかった」と述べ、クライバーによる声楽の扱いが巧みだったことを示している。
1956年に発行されたオペラLPのガイドブックThe Decca Book of
Operaにはクライバーが序文を書いており、「(以前の78回転SPレコードでは)どんなに高価な機器を使っても、音楽が4分ごとに区切られていることを誤魔化すことはできなかった。(LPによって)一生に一度か二度しか歌劇場で聴くことができないような作品を、愛好家が身近に感じることができ、レコード自体の性能も格段に向上している。世界中のあらゆる町や村で、現代の優れた演奏が聴けるようになるのだから、そのメリットは明らかである。」「歴史家はいずれ1950年代を、質の高い演奏が知られていなかった多くの地域で、賢明で厳格な聴衆が形成され始めた時代だと指摘するに違いない。」としており、レコードを高く評価している。しかし一方で「歌劇は音楽の中でも最も複雑なものであり、異質な力が絡み合っているため、満足のいく演奏ができるとは言いがたいものである。」「演奏家を苦しめる危険性は、最終的にレコードから取り除かれているか、あるいは取り除かれているはずであり、演奏は可能な限り理想的なものとなる。そのため、ある有名なパッセージは、歌劇場でこれほどうまく演奏されるのを聞くことはほとんどないだろうとリスナーは確信するだろう。しかし、このような一般的な基準の引き上げには危険も潜んでいる」。「どんな録音でも、ステージアクションのニュアンスを伝えることはできない」。「また、共感や興奮の突風や反発といった親密な振動を伝えることもできない。
しかし、自宅でレコードを最も楽しんでいる人は、その結果、歌劇場の魅力が倍増していることに気づくだろうと確信している。一方は補完するものだが、他方を置き換えることはできない。」とも語り、その問題点も指摘している。
クライバーは、このように歌劇のレコーディングに意欲的だったが、レコード業界が本格的に歌劇のレコーディングに取りかかる前、1956年に65歳に急死してしまい、歌劇全曲のスタジオ録音は「ばらの騎士」と「フィガロの結婚」(これはクライバー唯一のステレオ録音)のみで終わった。指揮者としてこれから円熟期を迎えるという年齢での死去であり、英デッカは優秀な歌劇指揮者を失った。一方で、膨大な量のライブ録音が残されており(特にコロン歌劇場など)、これらは音質に問題が多いが、改善できればクライバーの歌劇指揮者としての真価が再評価されるに違いない。
エーリヒ・クライバーは当ディスク以外に、ベートーヴェンの交響曲第9番を1952年英デッカにスタジオ録音したほか、1939年ウルグアイ放送響とライブ録音していた。

●音質良好 マグダ・タリアフェロ 1963~1965年パリ・リサイタル
モーツァルト ピアノ・ソナタK.576、ベートーヴェン「熱情」ソナタほか
オルガヌム110136AL
モーツァルト ピアノ・ソナタ第18番、K.576
ベートーヴェン ピアノ・ソナタ第23番「熱情」
フランク 前奏曲、コラールとフーガ
プロコフィエフ ピアノ・ソナタ第3番
マグダ・タリアフェロ(ピアノ)
1963年5月6日(モーツァルト、プロコフィエフ)
1965年3月6日(ベートーヴェン)
パリ・サル・プレイエル
1964年3月13日(フランク)
パリ・パレ・ド・オルセー
モノラル ライブ
※往年の名女流ピアニスト、マグダ・タリアフェロによるパリにおけるリサイタルのライブ。英国人コレクターからの提供音源。すべて放送局保管テープのコピーと思われ、年代が比較的新しいこともあり音質は良好。音楽波形を分析すると、フランクとプロコフィエフは、フォルティシモが大きすぎてレベル・オーバーしている箇所があるが、実際に聴く限りでは一瞬やや音が濁るだけで歪みもなく、鑑賞上は問題を感じない。音が濁るのは録音の問題ではなく、元々そのような奏法(タッチ)によるものだろう。特筆すべきは、2つの会場と3年にわたる日付の異なる演奏にもかかわらず、録音傾向や音色が統一されていること。残響をあまり入れずにオンマイクで録音しているためでもあるが、同じエンジニア(アンドレ・シャルラン?)が、ほとんど同じマイク・セッティングで録音したと思われ、一晩のリサイタルを通して聴いている感覚になる。
ディスク化に当たっては、オンマイクが極端な箇所については、ソフトウェア等で改善し、わずかにホールトーンを増やす処理を行った。ただし、会場のサル・プレイエル、パレ・ド・オルセーともに残響が豊かなホールではないため、違和感のないレベルに抑えた。そもそもパレ・ド・オルセー(現オルセー美術館)は、元は鉄道駅舎兼ホテルで、録音当時はホテルやイベント会場として使用されており、音響条件はあまり良くない。オンマイク録音のためか会場ノイズは皆無。
録音当時マグダ・タリアフェロは70歳から72歳。ベテランの域に達していたが、技術的な衰えは全くなく若々しい演奏を行っている(その後92歳!までリサイタルを行うなど現役を続けた)。当録音は、1962年に仏エラートにフランス作品のリサイタル盤を録音後、80歳時に1972年母国のブラジル・エンジェルにヴィラ・ロボスとショパンの作品集をレコーディングするまでのスタジオ録音空白期に当たる。ピアニストとして最も円熟した時期、しかもステレオ録音技術も確立した1960年代中期の正規録音がないのは極めて残念だが、タリアフェロはこの時期にもパリ音楽院の教授職と並行して多くのコンサートを開いており、少なからぬライブ録音が残されている可能性が高い。当ディスクの録音もその種の一つで、その一部?はタリアフェロの故国ブラジルで限定発売された書籍の付録CDに収録されていたようだが、古典から近現代作品まで幅広いレパートリーを持っていたことが理解できる。
タリアフェロは、日本では第二次世界大戦前から複数のレコードが発売されて評判も良く、クラシック愛好家の間で知名度は高かった。しかし、1960~1970年代になると、前記エラート原盤のリサイタル盤とオランダ・フィリップス原盤のサン=サーンスのピアノ協奏曲ほかのLPがカタログに残るのみで次第に忘れられた存在となり、1969年に76歳で来日するものの大きな注目を集めることもなかった。タリアフェロが再び注目されるようになるのは、1980年代以降、タリアフェロを含む輸入ヒストリカルCDが市場に出回り、従来の「決定盤・名盤主義」とは異なる多様な演奏様式が受容されるようになってからと思われる。
タリアフェロは、ギオマール・ノヴァエスとは同じブラジル出身で2歳違い、同じくパリ音楽院で学んだということで共通点も多いが(仲も良かったらしい)、ノヴァエスはブラジル人の両親を持ち、地元ブラジルでブゾーニの弟子ルイージ・キアッファレッリ(同じくブゾーニの弟子にはエゴン・ペトリがいる)によって高度なレベルの音楽教育を受け、ピアニストしてほぼ完成した状態でパリ音楽院に入学したため、純粋なフランス流派とは言い難く、ヴィルトゥオーゾ的性格の強いインターナショナルなピアニズムと考えられる一方、タリアフェロはフランス人の両親の元で育ち、早期からパリ音楽院で学んだため、典型的なフランス流派のピアニストと言える。ただし、フランス系女流ピアニストの多くが師事したマルグリット・ロンではなく、アントナン・マルモンテルとコルトーに師事しており、ドライで即物主義的な傾向のあるマルグリット・ロン門下とは異なり、コルトーのロマン主義的ピアニズムの影響が感じられる。
マグダ・タリアフェロは、当ディスク以外にモーツァルトのピアノ・ソナタ第18番を1938年仏パテに、フランクの前奏曲、コラールとフーガを1973年ブラジル・ロンドンにスタジオ録音していた。その他の2作品は当ディスクが現在確認されている唯一の録音と思われる。

●ジョコンダ・デ・ヴィート 1961・1956年ライブ
メンデルスゾーン、ブラームス ヴァイオリン協奏曲
オルガヌム110137AL
メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲
ブラームス ヴァイオリン協奏曲
ジョコンダ・デ・ヴィート(ヴァイオリン)
ルドルフ・ケンペ指揮バンベルク交響楽団
オイゲン・ヨッフム指揮バイエルン放送交響楽団
1961年10月頃、ロンドン・BBCマイダ・ヴェイル・スタジオ(メンデルスゾーン)
1956年11月15日、ミュンヘン・ヘルクレスザール(ブラームス)
モノラル ライブ
※名ヴァイオリニスト、ジョコンダ・デ・ヴィートによるロンドンとミュンヘンにおけるライブ。メンデルスゾーンは英国人コレクター、ブラームスはドイツ在住ロシア人コレクターからの提供音源。メンデルスゾーンは、詳しくは後述するがテレビ放送の音声のみをエアチェックしたもの。ブラームスは放送局保管テープのコピーと思われる。
メンデルスゾーンのオリジナル音源の状態は、ヒスノイズ過多、低いピッチ、ナローレンジで低域がブーミーな反面ヴァイオリンの高音がきつく聴こえるなど、録音年代を考慮すると残念ながら貧弱な録音。おそらく放送当時のテレビには音声出力端子が付いていなかったため、イヤホンジャックからレコーダーに録音したと思われ、同じくFM音声規格ながらラジオのエアチェックよりも条件が悪かったのだろう。ちなみに30年ほど前に日本国内で同一録音と思われるプライベートLPが少量発売されていたが、音質は同様だったと思われる。
ディスク化に当たっては、ノイズの低減、周波数レンジの拡大、低域過多・ヴァイオリン高域の飛び出しなど周波数バランスの調整、ピッチの正常化等々、オリジナルを尊重しつつ手を尽くした結果、1950年代半ば頃の平均的なライブ録音程度までの音質改善を果たすことが出来た。決して優秀な音質とは言えないが、ヒストリカル音源を聴き慣れたリスナーであれば、ストレスなく演奏を鑑賞できると思われる。
一方、ブラームスは1956年という年代の水準を上回る高音質。バイエルン放送の録音技術の高さに感心する。周波数帯域がそれほど広いわけではないが、バランスも良く、適度に残響を入れた臨場感あふれるもの。ただし、独奏ヴァイオリンに比べてオーケストラの音量が大きすぎ、家庭で鑑賞する音量では、独奏ヴァイオリンが聴き取りにくいという問題があった。実際の演奏会場の音量差に近いとも言えるが(それだけ原音に忠実な録音であるともいえる)、鑑賞に支障があることは問題。当演奏は、かつて仏ターラから複数のヴァイオリニストの演奏をまとめた2枚組CDの1曲として発売され、ほかにもマイナー・レーベルの非正規盤も存在するが、正規音源によるCD化が行われていないのは、上記のようなオーケストラと独奏ヴァイオリンのバランスに問題があるためかも知れない。
ディスク化に当たっては、コンプレッサーによってオーケストラとヴァイオリンの音量差を改善、さらにヴァイオリンの重要周波数帯域を若干クローズアップさせるなどの処理を行った結果、初めてデ・ヴィートの演奏が容易に聴き取れるようになった。2曲とも会場ノイズはほぼ皆無。拍手付き。
ジョコンダ・デ・ヴィート(イタリア語の実際の発音では「ヴィトウ」に近い)は、1962年4月、54歳という円熟期に引退したが、その理由として、テレビの録画放送で自らが演奏する姿を初めて見てショックを受けたからといわれ、おそらくその放送が当ディスクのメンデルスゾーンの演奏と思われる。
放送は1962年1月2日22時25分から。BBC「International Concert
Hall」という番組名で、上記のように生中継ではなく、放送前にBBCのロンドン・マイダ・ヴェイル・スタジオに聴衆を入れて録画された。番組ではメンデルスゾーンのほかに、R・シュトラウスの「ティル・オイゲンシュピーゲル」も演奏されたので、1時間弱の放送時間だったと思われる。残念ながら現状では収録日は不明だが、ケンペとバンベルク交響楽団が前年10月に英国公演を行っており、その前後に収録されたようだ。マイダ・ヴェイル・スタジオは、複数のスタジオの集合施設だが、最も大きなスタジオは、オーケストラに加えて、数百名の聴衆を入れるスペースがあったから、ラジオの公開放送なども盛んに行われており、当レーベルのペルルミュテールのリサイタル(オルガヌム110131AL)も「Thursday
invitation concert」と銘打ったスタジオ・ライブである。
ちなみにメンデルスゾーンの録画は、1964年春にNHKでも放送された記録があり、複数以上のコピー・テープが存在したと思われる。フィルム撮影であれば現存している可能性が高いが、ビデオの場合はテープが非常に高価だった時代であり、当時の習慣として放送使用後は別の番組の録画に再利用されることも多く、ビデオ・テープが現存しているかは不明である。
一方のブラームスは、デ・ヴィートの最も得意とするレパートリー。デビュー前10年以上も研究を重ねたといわれ、2回のスタジオ録音のほかライブ録音も数種残しているが、当ディスクの演奏は、ヨッフム指揮バイエルン放送響という強力な指揮者・オーケストラが共演しており、注目すべき録音と言える。優秀な録音ながら上記のような音量バランスの問題があったが、今回の改善により、ようやく演奏の真価が理解されると思われ、録音状態を含め、総合的にはデ・ヴィートによる同曲の最良の演奏となるのではないだろうか。
ジョコンダ・デ・ヴィートは、1951年に英EMIの役員・プロデューサーであるデイヴィッド・ピックネルと結婚。デビュー当初の独ポリドールを除き英EMI(レーベルはHMV)にレコーディングを行ったが、協奏曲録音では共演者にあまり恵まれていない。国際的に評価が高い指揮者はビーチャム(モーツァルト)とクーベリック(バッハとモーツァルト)くらいで、メンデルスゾーンやブラームスの協奏曲ではサージェントとシュワルツが共演し、良くも悪くも“伴奏”に徹した演奏に終始している、夫がEMIの役員・プロデューサーであるから共演指揮者を自由に選ぶ権限を持っていたはずだが、敢えて自己主張が少なく、独奏者の希望を全面的に受け入れる(従ってトラブルも少ない)穏便な指揮者を選んだのかも知れない。結果としてデ・ヴィートの一人舞台というか、ヴァイオリン独奏のみ高く評価され、伴奏指揮は評価保留(実質は低評価)という録音が残された。
その点で当ディスクのケンペとヨッフムは、デ・ヴィートを着実にサポートしつつ、自らの解釈も明確に主張しており、EMI録音よりもはるかに優れた伴奏と言える。やはり、独奏と伴奏がともに充実していて初めて協奏曲の名演奏が成り立つことを再認識する。
ジョコンダ・デ・ヴィートは、当ディスク以外にメンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲を1951年英HMVにスタジオ録音したほか、1952年と1957年にライブ録音していた。また、ブラームスのヴァイオリン協奏曲を1941年独ポリドール、1953年英HMVにスタジオ録音したほか、1951年、1952年、1956年、1960年、1961年にライブ録音していた。

●アンリエット・フォール 1955・1951年ライブ
サン=サーンス ラヴェル ピアノ協奏曲
オルガヌム110138AL
サン=サーンス ピアノ協奏曲第4番
ラヴェル 左手のためのピアノ協奏曲
アンリエット・フォール(ピアノ)
ピエール・デルヴォー指揮フランス国立放送管弦楽団
アンドレ・クリュイタンス指揮パリ音楽院管弦楽団
1955年3月3日、パリ・シャンゼリゼ劇場(サン=サーンス)
1951年9月11日、ブザンソン・グラン・クルサール(ラヴェル)
モノラル ライブ
※ラヴェルの名解釈者として知られるピアニスト、アンリエット・フォールによるサン=サーンスとラヴェル。いずれも英国人コレクターからの提供音源で、放送局保管テープのコピーと思われる。
サン=サーンスのオリジナル音源は極めて明快な音質で、1955年とは思えない優秀録音。フランス国立放送管弦楽団のシャンゼリゼ劇場ライブ録音には、時折驚くほど優れたものがあるがこれもその一つ。名エンジニアのアンドレ・シャルランかまたはそのスタッフが協力していたのかもしれない。周波数レンジも広くピアノと管弦楽とのバランスも良好。会場は残響が乏しく、音響条件は良いとは言えないが、それを逆手にとって解像度が高く、しかもドライで貧相にはならない最良のポイントにマイク・セッティングしていると思われる。ディスク化に当たっては、音質を損ねない範囲でヒスノイズを低減、中域中心で高音がやや不足していたため周波数バランスを調整したのみで、十分鑑賞に堪える音質となった。
一方、ラヴェルはブザンソン音楽祭におけるライブで、サン=サーンスより4年ほど古いこともあり(この頃の4年の技術差は大きい)、ナローレンジでくすんだ音質。高音不足の一方低域は過剰気味。元はテープ録音だったようだが、テープを他番組に再使用するためアセテート・ディスクにダビングして保存されていたらしく、一部にスクラッチノイズが混じる状態。ディスク化に当たっては、スクラッチ・ノイズの低減、周波数レンジの拡大。イコライジング等によるバランス調整等々を行った結果、一応はピアノはピアノらしく聴こえ、オーケストラもラヴェルらしい響きが出るように改善された。決して優秀録音と言えないが、鑑賞に不都合はない音質とすることが出来た。
アンリエット・フォール(1905~1985)はフランス・アヴィニョン生まれ、父親は医師、母親はその父も医師であった。ピアノ伴奏者として知られるモーリス・フォールや作曲家ガブリエル・フォーレとの血縁関係はない。
母親はピアノに無関心だったといわれ、早期の音楽教育は受けず、父の転勤に伴いベジエ、ベルダン、ナルボンヌとフランス各地で育ったが、ベジエでは公園で偶然サン=サーンスと出会ったという。サン=サーンスは自身の孫の世話をしていたが、孫と同世代の幼いフォールはその場で音符を学ぶ機会を得た。ナルボンヌに転居後、最初のピアノ教育を受けたが、才能を認めた教師(ルイ・ディエメの弟子)がパリに行くことを勧め、パリ音楽院でディエメに学んだ。そして、1920年15歳でプルミエ・プリを獲得して音楽院を修了。翌年演奏家として活動を開始した。
演奏活動開始前からフォールはラヴェルの作品に興味を持っており、1922年ラヴェルに直接手紙を書き、教えを請うたところ、ラヴェルは快く了解。後日ラヴェルはフォールのアパートを訪問し、「高雅で感傷的なワルツ」について弾かせてリズムや抑揚、ペダルの使い方など2時間半にわたって熱心にレッスンした。
レッスン終了後、ラヴェルは「ほかの作品を習いたいのであれば、モンフォールにある自分の家に来るように」と勧めたため即答すると、自宅までの交通手段、汽車やバスの時間までていねいに教えた。ラヴェルの説明によれば、「朝8時頃に(フォールのアパートを)出発して、アンヴァリッドで汽車に乗り、9時にモンフォールに到着。そこからバスに乗り、10分後にベルヴェデーレ(私の家)の前で停車。レッスンをして、ランチを食べて、さらにレッスンをして、17時45分発のバスで18時発パリ行きの汽車に乗ればよい」とのこと(ラヴェルの几帳面な性格が出ていて興味深い)。そして「9月になっているが、1月にコンサートを開催したければ、週に2~3回は私の家に来なさい」と言ったという。こうしてフォールはラヴェルの弟子となり、週に2回、時には3回レッスンを受け、ラヴェルの家に泊まることもあった。
フォールによると「彼の作品の教え方は、簡潔で、細心の注意を払い、厳しく、同時に誰にでもわかるような明快さを持っていた。しかし、彼は細部に至るまですぐに実現したいと考えており、その細部には一つの偶然も許されない」。「彼が最初に弾いた2~3個の和音から、私がラヴェルの「タッチ」と呼ぶものを感じることができた。彼には唐突さ、秘密の暴力、痛烈なアルペジオ、首を絞めるようなクレッシェンドがあった。また、音を浮かび上がらせる方法や、大気中に影のような反響を広げて和音を奏でる方法もあった」という。
このような詳細なレッスンを受けていれば、まさしく作曲家直伝の演奏となるだろう。ラヴェルが当時17歳になったばかりのフォールに演奏法を教えたのは、まだ演奏家として個性が固まっていない(別の言い方をすれば悪い癖が付いていない)若い演奏家の方が、自らの教えを忠実に再現してくれると考えたのかも知れない。
こうしてアンリエット・フォールは1923年1月12日、パリ・シャンゼリゼ劇場でオール・ラヴェル・プログラムによるリサイタルを開催し、センセーショナルな成功を収めた。当日は、作曲家のアルベール・ルーセル、フローラン・シュミット、ルイ・オーベール、ポール・ル・フレム、楽譜出版者ジャック・デュラン、ルネ・ドマンジュ、批評家エミール・ヴュイエルモーズ、アレクシス・ロラン=マニュエルなど著名な音楽関係者が集まり、18歳の新進ピアニストのリサイタルとは思えない関心の高さだった。
その後、フォールによる同様のオール・ラヴェル・プログラム・リサイタルは開催される度に評価が高まり、1938年のシャンゼリゼ劇場におけるリサイタルは超満員で、客席に座れなかった聴衆が続出し、ステージ上に並べられた椅子で聴いたという。
ところで、ラヴェル直伝の演奏を行うと言われるピアニストとしては、ほかにヴラド・ペルルミュテールやジャック・フェヴリエ(左手のためのピアノ協奏曲の演奏指導を受けた)がいるが、同じ「直伝」演奏でも全く同一の解釈とはならず相違が出るのは、ピアニスト自身の個性もあるが、残された録音の大半が、ラヴェルによる教えを受けてから数十年後という時間を経ていることもあるだろう。
もちろんフォールはラヴェルばかり演奏していたわけではなく、幼い頃に偶然の出会いがあったサン=サーンスはもちろん、パリ音楽院の入学試験で弾いたベートーヴェンやショパン、リストなどもレパートリーとしていた。また、1962年ドビュッシー生誕100周年記念リサイタルもキャリアのハイライトとなった。ちなみに当ディスクに聴く左手のためのピアノ協奏曲は1930年に書かれており、上記レッスンの対象にはなっていないため、フォールはいわば他作品の解釈を「応用」して演奏していることになる。
フォールは晩年まで演奏活動を続けていたが、多くの同世代のフランス人ピアニストと同様、1960年代に入ると教育にも重点を置き、レコーディングから遠ざかった。正式なスタジオ録音としては、1949年仏デッカに残した10インチ78回転SP2枚組のラヴェル作品集、LP時代に入って1955年仏デッカと仏EMIパテに残したラヴェル作品集、1961年デュクレテ・トムソンに残したドビュッシー作品集のわずか4点であった。
アンリエット・フォールはサン=サーンスのピアノ協奏曲第4番とラヴェルの左手のためのピアノ協奏曲のスタジオ録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音である。なお、蛇足ながらラヴェルの(両手の)ピアノ協奏曲については放送録音が残っていると言われる。
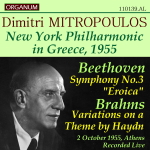
●ミトロプーロス/ニューヨーク・フィル
ベートーヴェン「英雄」ほか 1955年ライブ
オルガヌム110139AL
ベートーヴェン交響曲第3番「英雄」
ブラームス ハイドンの主題による変奏曲
ディミトリ・ミトロプーロス指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
1955年10月2日、アテネ・オルフェウス・ホール
モノラル ライブ
※ミトロプーロス/ニューヨーク・フィル(NYP)によるベートーヴェン「英雄」とブラームスのハイドン変奏曲。1955年にNYPがヨーロッパ・ツアーを行った際、ミトロプーロスの故国ギリシャにおけるライブ録音。アメリカ人コレクターからの提供音源で、エアチェックではなく放送局保管テープのコピーと思われる。
オリジナル音源の音質は、低域不足だが1950年代中期ヨーロッパの放送録音の標準レベル。特に優秀というわけではないが、情報量は豊富でヒス・ノイズを除けば致命的なノイズや欠落もない。ギリシャの放送局の技術レベルが特に高いとは言われておらず、それを考慮すれば頑張った方で、一通り手を加えれば十分良好な音質に改善できると期待された。ただし残念ながら、ベートーヴェンについては、第3楽章の途中からレコーダーの不調かテープ・スピードが不安定になり、第3・第4楽章では十数カ所ピッチが変動・低下する部分があった。全体に一定してピッチが低下したわけではなく瞬間的に急激に変動するため、修正はかなり困難だったが、ディスク化に当たっては、ピッチの変動箇所を一つずつ補正することで、完全とは言えないが改善することが出来た。ブラームスについては、ベートーヴェンより先のプログラムだったためか、ピッチ変動トラブルはなかった。その他にヒス・ノイズの低減、周波数レンジの拡大と低域・高域バランスの調整等、基本的な音質改善を行った結果、一般的な鑑賞に不都合はないレベルとすることが出来た。会場ノイズは極小。
ちなみ当音源はかつて海外で既出盤が存在したが、周波数バランスやピッチの変動などは修正せず、長大な残響を付加したのみと言う、安易なディスク化が行われていたようだ。
前記したように1955年NYPはヨーロッパ・ツアーを行い、9月5日から10月5日までに、スコットランド、オーストリア、ベルギー、ドイツ、フランス、スイス、イタリア、ギリシャ、イングランドで21公演を実施した。中でもギリシャ公演はミトロプーロスの故国ということで特別に開催されたのだろう。
10月2日の公演は午前11時開演で、前半にヴェルディの歌劇「運命の力」序曲、ブラームスのハイドン変奏曲、ギリシャ近代の作曲家スカルコッタスの「36のギリシャ舞曲」からの1曲(詳細不明)、休憩を挟んで後半がベートーヴェン「英雄」、アンコールとして、スカルコッタスの「36のギリシャ舞曲」から第4番と5番が演奏された。
興味深いのは、ハイドン変奏曲では演奏終了を待たずに拍手が入ること。聴衆が興奮して拍手するような類いの曲目ではないが、自国出身指揮者の「凱旋公演」ということで盛り上がったのかも知れない。その代わりにベートーヴェンの「英雄」では演奏が終了してから拍手が入っているのも面白い(休憩中に誰かが聴衆に注意したのだろうか)。
ミトロプーロスはNYP常任・首席指揮者時代、「現代音楽ばかり演奏する」と保守的な聴衆や理事会から批判されたが、演奏会記録を見ると、ベートーヴェンの「英雄」については1955年のヨーロッパ・ツアー以前に、1949年常任指揮者就任の年に3公演、1952年5公演、1954年2公演、1955年3公演と、頻繁と言う訳ではないが意外に多く演奏している。ミトロプーロスに対する批判は、演奏会プログラムにポピュラーな作品と併せて、現代音楽を「潜り込ませた」ことにあり、現代音楽ばかりというのは根拠のない言いがかりだったようだ。ちなみに当ディスクに聴く1955年10月の演奏は、ミトロプーロスがNYPと「英雄」を演奏した最後の機会となった。一方のブラームスのハイドン変奏曲については少なく、1954年2公演、1955年に米国内ツアーで7公演演奏したのみ。「英雄」と同様に当ディスクがNYPと演奏した最後の機会だった。
難解な現代作品を即座に把握できたミトロプーロスにとって不得意な曲目は存在しなかっただろう。ベルリン国立歌劇場でエーリヒ・クライバーの助手を務めた経験もあり、ドイツ・オペラやイタリア・オペラも守備範囲だった(ワーグナーやヴェルディ、プッチーニの名演がライブ録音で残されている)。当ディスクに聴くベートーヴェンやブラームスも演奏回数の多寡にかかわらず、模範的・理想的とも言える演奏を行っており、決して平凡な演奏には陥らない点はさすがと言える。
ディミトリ・ミトロプーロスは、ベートーヴェンの交響曲第3番とブラームスのハイドン変奏曲のスタジオ録音を残さず、当ディスク以外にベートーヴェンの交響曲第3番のみ1949年にライブ録音していた。

●パリ・サル・ガヴォー開館50周年記念コンサート
マルグリット・ロン、ランパル、ラスキーヌ、ランスロ、ベルナック、プーランク、パスキエ・トリオほか
フォーレ、ドビュッシー、ラヴェル作品集 1957年ライブ
オルガヌム110140AL
フォーレ 幻想曲
ラヴェル 序奏とアレグロ
ドビュッシー「美しい夕暮れ」「羊の群れと立ちならぶ生垣は」「2人の恋人のプロムナード」「フランソワ・ヴィヨンによる3つのバラード」
フォーレ:ピアノ四重奏曲第1番(アンコール:第2楽章)
ジャン=ピエール・ランパル(フルート)、ジャクリーヌ・ボノー(ピアノ)
リリー・ラスキーヌ(ハープ)、ジャック・ランスロ(クラリネット)
ルーベン・ヨルダノフ(ヴァイオリン)
ピエール・ベルナック(バリトン)、フランシス・プーランク(ピアノ)
マルグリット・ロン(ピアノ)、ジャン・パスキエ(ヴァイオリン)
ピエール・パスキエ(ヴィオラ)、エティエンヌ・パスキエ(チェロ)
1957年5月10日、パリ・サル・ガヴォー
モノラル ライブ
※パリの名コンサート・ホール、サル・ガヴォーの開館50周年を記念したコンサートのライブ録音。当時のフランス音楽界を代表した空前とも言える豪華なメンバーによる公演である。イギリス人コレクターからの提供音源で、エアチェックではなく放送局保管テープのコピーと思われる。オリジナル音源の音質は特別に優秀というわけではないが、ノイズレスでバランスも良く無難な状態。フランス国立放送特有のホールトーンを入れない直接音主体の録音スタイルだが、小編成の作品が多いため不満はない。残響が乏しい分、フォーレのピアノ四重奏曲がやや窮屈な響きの印象を与えるが、元々残響に乏しいホールであるため、実際に会場で響いていた音に近いと思われる。ディスク化に当たっては、わずかに楽器からマイクを離す(各楽器をブレンドさせる)処理のみ行った。一般的な鑑賞にはまず不満のないレベルと言える。会場ノイズもほぼ皆無。
1957年5月10日、フランス芸術文化省長官ジャック・ボルドヌーブの主宰により、パリを代表するコンサートホールの一つ、サル・ガヴォーの開館50周年を祝うフランス音楽の夕べが開催された。出演者の人選は絶妙で、サル・ガヴォー開館当時から活動している82歳の長老ロンから、ベテランのパスキエ・トリオ、ベルナック(と欠かせないパートナーのプーランク)、ハープ界の第一人者ラスキーヌ、当時35歳で新進気鋭のランパルまで、新旧の一流演奏家をバランス良く参加させている。なお、開催日を9日とする資料もあるが、より信頼性の高い資料に従った。
フォーレの幻想曲はランパルとボノー、ラヴェル「序奏とアレグロ」はランパル、ラスキーヌ、ランスロ、ヨルダノフ、パスキエの3兄弟(パスキエ・トリオ)、ドビュッシーの歌曲はベルナックとプーランク、フォーレのピアノ四重奏曲はロンとパスキエ・トリオが演奏している。
サル・ガヴォーは1907年、当時フランスの有力ピアノ・メーカーだったガヴォー社のオーナーの一人、エティエンヌ・ガヴォーによって建設された。収容人員は1000名ほどで、室内楽やピアノ・リサイタルなどに最適な規模だったが、時にはオーケストラ・コンサートも行われ、サン・サーンスがピアノ弾き、若き日のモントゥーがコロンヌ管弦楽団?を指揮した写真も残されている。しかし、1963年になってガヴォー社が倒産、サル・ガヴォーは保険会社に売却され、解体される危機に遭遇したが、跡地利用を巡って解体が遅延(駐車場になるとも言われた)、幸い1976年に熱心な音楽愛好家であるシャンタルとジャン=マリー・フルニエ夫妻が購入。現在もコンサート・ホールとして活用されている。1957年の記念コンサートは、ガヴォー社末期の時代に当たり、当日の使用ピアノもガヴォーだったと思われる。
出演者の中では特にマルグリット・ロンの録音が貴重。なぜかライブや放送録音がほとんど発掘されておらず、当ディスクの演奏は珍しい。ロンは高齢ながら衰えもなく十分に現役で通用する技量を保っている。ちなみに前年の1956年に同じくパスキエ・トリオとフォーレのピアノ四重奏曲第1番を仏コロンビアに録音しており、これがロンの最後のスタジオ録音となった。サル・ガヴォーでの演奏はレコーディングの再演に当たるが、スタジオ録音よりも柔軟性や自由度が増している印象がある。また、祝祭コンサートということもあり、第2楽章をアンコールしている。
また、ベルナックとプーランクの名コンビについては、1952年の米コロンビア録音以降、ドビュッシーのレコーディングを行っておらず(大半は1930年代の英HMV録音)、当ディスクの方が歌唱スタイルがより現代的で、時代と共に変化していることが分かる。また、パスキエ・トリオは、若手・中堅のランパルやランスロ、ベテランのロンとの共演のいずれにも演奏に齟齬がない点は、同トリオの柔軟な対応力もあるが、世代の違いはあっても一貫したフランス独特の演奏美学が存在することを感じさせる。
それにしてもこれだけ豪華なメンバーが揃った公演が実現し、録音が残されたことは誠に幸いだったと言わざるを得ない。
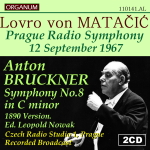
●優秀録音 マタチッチ/プラハ放送響
ブルックナー交響曲第8番 1967年放送ライブ
オルガヌム110141AL
ブルックナー交響曲第8番(ノヴァーク版)
ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮プラハ放送交響楽団
1967年9月12日、プラハ・チェコ放送第1スタジオ
モノラル 放送ライブ
※2枚組。マタチッチ/プラハ放送響によるブルックナーの交響曲第8番。1967年プラハのチェコ放送第1スタジオにおいて、ラジオ放送のため聴衆を入れずに行った演奏録音。ドイツ在住ロシア人コレクターからの提供音源で、エアチェックではなく放送局保管テープのコピーと思われる。
オリジナル音源の音質は、モノラルながら優秀。ダイナミックレンジ、周波数レンジも十分に広く、ブルックナー作品にふさわしいスケール感、適度に残響を伴った美しい録音。若干低域過剰で高域が低下気味だったため、イコライジング等で微調整したが、いずれにしても一般的な鑑賞では不満のないレベル。ステレオでないことが惜しまれるが、当時の西欧諸国では、西ドイツなどを除けばステレオ録音・放送が普及していたものの、東欧諸国でステレオ録音が試験的に導入されたのは1960年代末頃と言われ、これは致し方ないところ。
なお、当ディスクの演奏は、20年ほど前に海外レーベルでCD化されていたが、疑似ステレオ化された上、さらにステレオ的広がりを狙ったのか位相も操作するなど、却って定位が不安定で音質もバランスも悪化した「改悪盤」だった。結果的に、当ディスクで初めて演奏本来の姿が再現されたと言える。
マタチッチは、1947年から断続的に始まった英EMI(HMV/コロンビア)とのレコーディング契約が1962年に終了(例外的に1929年にクロアチアの作曲家作品を録音、1974年にリヒテルとシューマン、グリーグの協奏曲を録音している)、一方で1959年頃から、おそらくスポット契約でチェコ・スプラフォンに数点のレコーディングを行い、この中でブルックナーについては、チェコ・フィルと交響曲第5番(1970年11月)、第7番(1967年3月)。第9番(1980年12月、ライブ録音で当初からLP発売を計画したのかは不明)の録音を行ったが、残念ながら第8番が欠けていた。当ディスクに聴く当作品の録音は、第7番スタジオ録音の半年後に当たり、スプラフォン録音の欠落を補うものとして貴重な存在である。なお録音日が9月であることは間違いないが、12日は放送日であって録音日ではないという情報もあり、この点はやや不確定である。
マタチッチによるブルックナーの交響曲第8番は、後述するように現在5種類の録音の存在が確認されているが、内訳はNHK交響楽団とトリノ・イタリア放送交響楽団がそれぞれ2種(トリノ・イタリア放送響による2種の演奏は同一との説もある)、残りの1つが当ディスクの録音となる。いわゆる独墺系以外の団体との録音が大半で、純粋なドイツ系ではないものの、広い意味で独墺文化圏のプラハ放送響を指揮した当ディスクの録音はこれまた貴重である。
プラハ放送響は1926年に設立された放送オーケストラとしては歴史のある団体。チェコ国立放送局に所属しチェコ・フィルに次ぐ存在と言われる。当ディスクの演奏を聴く限り、弦も管も安定しており、ドイツの放送交響楽団のランキングに入れても中位程度以上のレベルと思われ、マタチッチの(独特の?)指揮にもブルックナーの語法にも十分対応しているようだ。この辺りは幅広いレパートリーを要求される放送オーケストラならではの柔軟性を感じる。
ここで注目すべきは演奏時間。残された5種の録音の中では最も早い時期の演奏にもかかわらず、トータルの演奏時間は最も長く、有名な1984年N響とのライブよりも11分も長い(各楽章について1~4分程度長い)。指揮者が年齢を重ねるとテンポが遅くなることはよくある傾向だが、マタチッチの場合は逆で、最後のトリノ・イタリア放送響との録音が最も演奏時間が短い。ここで想像されるのは、プラハ放送響と録音したチェコ放送第1スタジオは、放送スタジオとしては例外的に残響が豊かな一方、N響のNHKホールやトリノ放送響のトリノ・イタリア放送協会オーディトリアムは響きが豊かとまでは言えず、マタチッチは響きを考慮した上でテンポ設定をしていたのではないかということ。
有名なエピソードだが、チェリビダッケがベルリン・フィルの暫定的常任指揮者時代(チェリビダッケではなく他の指揮者という説もある)、フルトヴェングラーに対して、ある作品のテンポ設定を訪ねたところ、「それは(会場の)響きによる」と回答、チェリビダッケは「私にとって天啓だった」と感想を述べている。
譜面のテンポ(メトロノーム)指示にとらわれることなく、会場の音響も考慮してテンポ設定を行うことをマタチッチも実践していたと思われ、少なくとも1967年時点でマタチッチのブルックナー解釈は完成しており、年齢を重ねても変化がなかったと考えられる(それゆえ1967年3月、ブルックナー交響曲第7番のスタジオ録音が高い完成度を持っていたと言える)。当ディスクに聴く第8番は他の録音に比べてテンポが遅い分、更に残響が豊かな分、マタチッチ本来のスケールの大きさがより際立っているように思われる。
ロヴロ・フォン・マタチッチは、上記のようにブルックナー交響曲第8番のスタジオ録音を残さず、当ディスク以外に、1975年と1984年にNHK交響楽団と、1983年11月13日と18日にトリノ・イタリア放送交響楽団とライブ録音していた(前述のように同一演奏か)。
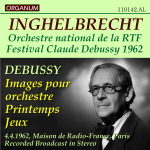
●高音質ステレオ録音 アンゲルブレシュト/フランス国立放送管
ドビュッシー生誕100年記念コンサート 1962年放送ライブ
オルガヌム110142AL
ドビュッシー
管弦楽のための「映像」、
交響詩「春」、
舞踊詩「遊戯」
デジレ・エミール・アンゲルブレシュト指揮フランス国立放送管弦楽団
1962年4月4日、パリ・ラジオ・フランス・スタジオ
ステレオ 放送ライブ
※ドビュッシーの演奏解釈で定評があるアンゲルブレシュトによるオール・ドビュッシー・プログラム。1962年、パリ・ラジオ・フランスの客席付き大型スタジオ(オーディトリアム)において、聴衆を入れて行われた公開収録である。英国人コレクターからの提供音源で、放送局保管音源のコピーと思われるが、当時としては驚異的な高音質録音。昨今の凡庸なデジタル録音よりも優れているかも知れない。フランス国立放送は1950年代末からステレオ録音を徐々に導入していったが、当録音時には既に完成期に入っており、放送スタジオのためマイク・セッティングの自由度が大きいこともあってか、左右の分離やバランスなどは全く問題なく、周波数レンジやダイナミックレンジも十分広く、当時のメジャー・レーベルのレコード会社のLP録音と勝るとも劣らない印象。会場がスタジオであるため残響は控えめだが、クリアに聴こえるためドビュッシー作品には却って好都合。古いアナログ録音に付きもののヒスノイズも皆無で、十分に満足して鑑賞できる水準と言える。会場ノイズもほぼ皆無。ごく控えめに拍手が入るのも放送のための録音ゆえか。
なお、当ディスクに収められた3作品は、1984年に仏エラートからLP発売されていたが、なぜかモノラルで音質も特に優れたものではなかった。おそらくAMラジオ放送用の音源を使用したのではないだろうか。
当演奏会は、ドビュッシー生誕100年を記念するもので、「Festival Claude
Debussy」と題され、当ディスクに収められた作品のほかに、バリトンのカミーユ・モラーヌによる「フランソワ・ヴィヨンの3つのバラード」「シャルル・ドルレアンの3つの歌」も演奏された。ちなみに実際の演奏は、「春」「フランソワ・ヴィヨン・・・・」「遊戯」「シャルル・ドルレアン・・・・」「映像」の順であった。モラーヌの歌唱も非常な名演であり、今後ディスク化する予定。
アンゲルブレシュトは、ドビュッシー本人と1910年から彼が亡くなる1918年まで文通を続け、作品の演奏について様々な助言を受けたとされるが、アンゲルブレシュトのドビュッシー演奏は、意外にもドライで即物的な傾向があり、一般に言う印象主義的で曖昧模糊な情緒を排した明快なものである。演奏家としては新即物主義の洗礼を受けた世代より一世代前に属しており、その影響よりも、作曲家本人の助言による要素が大きいのではないだろうか。
演奏家が楽譜自体から受けるイメージと、作曲家が意図するイメージの乖離はしばしば起こるようで、近年も、ある日本人指揮者が武満徹の「ノヴェンバー・ステップス」について「水墨画のようなぼんやりした作品」と思っていたところ、初演者の小澤征爾から「これは戦いの音楽だ」と注意されたという(偶然だが同作品はドビュッシーの影響があると言われる)。さらに凡庸な演奏家の場合、例えばラムルー管の指揮者カミーユ・シュヴィヤールは、リハーサルに立ち会ったドビュッシーの助言を受けてさえも、助言どおりの演奏ができなかったと言われる。ドビュッシー作品は本来、明快に演奏されるべきものかも知れない。
アンゲルブレシュトは、ドビュッシーの「映像」を1954~1957年、「遊戯」を1957年それぞれ仏コロンビアにスタジオ録音していた。「春」は当ディスクが現在確認されている唯一の録音である。

●音質良好 ミシェル・ベグネール ショパン/バルトーク ピアノ協奏曲 1965年・1967年放送ライブ
オルガヌム110143AL
ショパン ピアノ協奏曲第2番
バルトーク ピアノ協奏曲第3番
ミシェル・ベグネール(ピアノ)
ロヴロ・フォン・マタチッチ、ディミトリ・コラファス指揮フランス国立放送管弦楽団
1965年2月25日、1967年11月12日、パリ・ラジオ・フランス・スタジオ
モノラル 放送ライブ
※近年惜しくも亡くなったフランスの女流ミシェル・ベグネール(1941~2021)によるショパンとバルトークの協奏曲。2曲ともパリ・ラジオ・フランスの客席付き大型スタジオ(オーディトリアム)において、聴衆を入れずに行われたラジオ放送のための録音である。英国人コレクターからの提供音源で、放送局保管音源のコピーと思われるが、残念ながらモノラル。録音年を考慮すればフランス国立放送でステレオ録音が本格化していた時期だが、AMラジオ放送用に収録されたのかも知れない。そのためかは不明だが、オリジナル音源は高域が8kHz程度でカットされており、AM放送の高域上限が7.5kHz程度と考えると放送を前提とした措置か。音質自体はノイズレスで、厳密に聴かない限りそれほど悪くはないが、やはり高域不足・ナローレンジでクリアさに欠ける印象があった。ディスク化に当たっては、ソフトウェアによって、欠けている高域を補間・拡張する作業を行った。無理に周波数レンジを拡大するとデジタルノイズが発生する恐れがあり、ノイズを発生させない範囲で補間・拡張した結果、FM放送上限の15kHz、部分的にはCD上限の20kHz程度まで周波数レンジが広がり、モノラルながら鑑賞に不満のない水準とすることができた。元々の音質やバランスが良好だったことが幸いした。
ミシェル・ベグネール(以前はボグネール、ボーグナーなどの誤表記もあった)は、フランスのリヨン生まれ。パリ音楽院でペルルミュテールやフェヴリエなどに師事、若い時期から活動を開始し、1961年20歳で仏フィリップスからレコード・デビュー、その後、エラートやカリオペ、アデスなどにモーツァルトやショパン、シューマン、フランクほかの録音を残した。演奏活動も比較的活発に行い、レコーディングも大量というわけではないが決して少ないわけではなく、晩年には活動を再開したディスコフィル・フランセにモーツァルトのピアノ・ソナタ全集を録音するなど一部で注目されたが、少なくとも日本では、生前は最後まで「知る人ぞ知る」地味な存在だった。
おそらく、演奏活動で世界中を飛び回るスター・アーティストの道を拒否し、コンサートもレコーディングも、納得のいく仕事のみを選べるマネージメント事務所やレコード会社と契約して活動したためと思われるが、結果として、残されたレコーディングはことごとく名演・名盤と評価されており、名手であったことは間違いない。
当ディスクに聴くショパンやバルトークの協奏曲は正規のレコーディングを残さなかったが、オーケストラを伴わないソロ作品の録音にはショパンやバルトークがあり、十分にレパートリーの範疇だったと思われる。ただし協奏曲の正規録音については、エラートのモーツァルトとハイドン、カリオペのバッハのみで、古典派以降の協奏曲は皆無で貴重な存在と言える。
実演では多くの協奏曲レパートリーの演奏機会があったようだが(ベートーヴェンやダンディ作品の録音が確認されている)、おそらく演奏する作品を慎重に選び、納得できる指揮者やオーケストラのみとレコーディングを行うという姿勢は、効率を重視するメジャー・レーベルのレコード会社からは敬遠されがちで、逆にマイナー・レーベルではオーケストラを雇う予算が乏しいという事情から、仮に本人が録音を希望しても実現が難しかったのだろう。
当ディスクの演奏がベグネールの新たな評価につながることを期待したい。
指揮者について触れると、マタチッチの登場は意外に思われるが、実際には頻繁にフランス国立放送管に客演しており、以前からブルックナーなどの放送録音がCD化されている。その風貌?から細かい対応が要求される協奏曲の指揮は不得意そうに思えるが、若い頃から歌劇場で修行しただけに伴奏は巧みで、英EMIも協奏曲録音で多く起用している。一方、珍しいのはコラファス(1916~2004)。ギリシャ出身でパリ音楽院に留学し、その後、主にフランスやベルギーの歌劇場やオーケストラで活動(バレエ指揮も多かった)。晩年、故国ギリシャのアテネ国立歌劇場音楽監督に就任した以外、常任指揮者といった特定のポストを持たず客演が中心だったようだ。レコーディングも協奏曲の伴奏ばかりで、このような指揮者の場合、実演に接することができるフランスとは異なり、日本ではその実力を全く知られることがないという現象が起きる。当ディスクの伴奏を聴く限り、堅実という以上の力量を持った指揮者だったらしく、管弦楽作品の演奏を聴いてみたいところだ。
ミシェル・ベグネールは、当ディスクに聴くショパンとバルトークの協奏曲の正規録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音である。
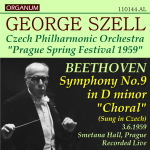
●音質良好 ジョージ・セル/チェコ・フィル ベートーヴェン交響曲第9番
1959年「プラハの春」音楽祭ライブ
オルガヌム110144AL
ベートーヴェン 交響曲第9番「合唱付き」(チェコ語歌唱)
ドラホミーラ・ティカロヴァー(ソプラノ)、ヴィエラ・クリロヴァー(アルト)、
イヴォ・ジーデク(テノール)、ラディスラフ・ムラーズ(バリトン)
ジョージ・セル指揮チェコ・フィルハーモニー管弦楽団・合唱団
1959年6月3日、プラハ・スメタナ・ホール
モノラル ライブ
※ジョージ・セルが「プラハの春」音楽祭に参加、チェコ・フィルを指揮した際の記録。音楽祭最終日の閉会コンサートではベートーヴェン第9の演奏が行われるが、当時の慣例としてチェコ語による歌唱となっている。ドイツ在住ロシア人コレクターからの提供音源で、音質の良さからエアチェックではなく放送局保管音源のコピーと思われる。チェコ(録音当時はチェコスロバキア)は、スプラフォン・レーベルを代表されるように東欧諸国の中では録音技術が優れており、放送局のライブ録音も当時の西側諸国に劣らないと言われるが、当ディスクのオリジナル音源の状態も、ヒス・ノイズも極小で各セクションのバランスも良好。当時のライブ録音としては十分に優秀な状態。ただし、放送録音らしいと言うか、良い意味での演出は皆無で、会場で鳴っている音を「とりあえず収録しました」という印象で、高域や低域を無理に伸ばさない中域主体の音作り。音楽祭ライブという祝典的雰囲気、ベートーヴェン第9のスケールの大きさなどは感じさせず、こぢんまりとまとまってしまっている感は否めなかった。
ディスク化に当たっては、周波数バランスを中域主体からフラット・バランスへ修正、併せて周波数レンジも拡張、また中・高域に若干のピークがあったため修正。第4楽章声楽部分にリミッターがかかっていたため音量の調整等、いくつかの補正を行った結果、ベートーヴェン第9らしいスケールの大きな響きを復元することができ、一般的な鑑賞には不満のない状態となった。
ジョージ・セルは母親がスロバキア人であり、第二次世界大戦前、プラハのドイツ歌劇場の音楽監督に就任するなど当時のチェコスロバキアとの縁は深く、チェコ・フィルとは、英HMVにレコーディングを行うほか(ドヴォルザークの「新世界から」、カザルス独奏によるチェロ協奏曲はよく知られている)、しばしば客演も行った。戦後は、セルが活動の拠点をアメリカに移したため、チェコ・フィルとの関係は薄れたが、それでも1959年の当公演、1963年ザルツブルク音楽祭において共演している。
当公演の演奏は、セルが音楽監督を務めていたクリーヴランド管との演奏と基本路線と同様だが、セルはチェコ・フィルに対してクリーヴランド管ほどのアンサンブルの精緻さは求めておらず、引き締まった機能美よりも、中欧の団体らしい木質的な暖かさ(チェコ・フィルの弦や管の渋さが理由か)、鄙びたローカルカラーが感じられるところが興味深い。また第4楽章のチェコ語歌唱も、当時はそれが常識だったためか違和感なく聴ける。なお、当公演では、交響曲第9番の前に「コリオラン」序曲が演奏されており、こちらは以前、海外でCD化されていた。
ちなみに当公演時のエピソードではないと思われるが、ある時、セルとチェコ・フィルのリハーサル休憩の際、楽員の一人が同僚にチェコ語の方言?で、セルのことを「仏頂面だからなあ」と言ったところ、すかさずセルが「そんなことないさ」と同じ方言で返したという。楽員は、セルをハンガリー系または独墺系と認識しており、チェコ語が理解できるとは思わなかったのだろう。セルは東欧やロシア語も含めてヨーロッパ諸国の十数カ国語が堪能だったと言われ、公開レッスンでもヨーロッパ各地から集まった学生が様々な言語で質問しても、通訳を介さずに学生の使った言語で回答していたという。第二次世界大戦前の独墺系の指揮者は、ドイツから旧オーストリア・ハンガリー帝国領内、さらにはロシアまでの広大な地域の歌劇場間で転職を繰り返しながら、より高いポストにステップアップしていくことが通常の出世ルートだったから、各地の言語を習得することは必須だったのだろう。
ジョージ・セルは当ディスク以外に、ベートーヴェンの交響曲第9番を1961年米コロンビアにクリーヴランド管とスタジオ録音したほか、1968年にニュー・フィルハーモニア管、1969年にウィーン・フィルとライブ録音していた。

●音質良好 バルビローリ/ハレ管 1965・1963年放送/ライブ
エルガー「エニグマ変奏曲」、ヴォーン・ウィリアムズ「タリス幻想曲」ほか
オルガヌム110145AL
エルガー エニグマ変奏曲
ヴォーン・ウィリアムズ トマス・タリスの主題による幻想曲
ディーリアス 幻想曲「夏の庭で」
サー・ジョン・バルビローリ指揮ハレ管弦楽団
1965年7月4日、マンチェスター・フリー・トレード・ホール
1963年6月5日、ベルゲン・グリーグ・ホール
モノラル 放送ライブ/コンサート・ライブ
※バルビローリ/ハレ管得意のブリティッシュ・ミュージック・プログラム。すべて英国人コレクターからの提供音源で、エルガーは「BBCランチ・タイム・コンサート」という番組のために、聴衆を入れずに行われた放送のための録音。後で述べるように音質の特徴からエアチェックではなく放送局保管音源のコピーと思われる。ヴォーン・ウィリアムズとディーリアスは、ベルゲン音楽祭におけるライブ録音。こちらはエア・チェックと思われる。
エルガーのオリジナル音源の状態は、マイク・セッティングの制限がないBBCの放送録音としては問題が多かった。音質自体は悪くないのだが、低域は過剰、高域も一部の周波数帯域が飛び出し、さらにダイナミック・レンジが広すぎて、強音を基準にボリューム設定すると弱音が全く聴こえないというバランスの悪いもの。ラジオ放送に使用する場合、少なくともコンプレッサーによって強音と弱音の差を縮める作業を行うから、オリジナルの音源は放送前の未編集の状態と思われる。フリー・トレード・ホールはハレ管が長年本拠地としていた会場で、BBCによる放送も数多く行われたと思われるから、このような不出来な録音は疑問であり、慣れない新人エンジニアが担当したのだろうか。
ディスク化に当たっては、イコライジング等によりバランスを補正、コンプレッサーによってダイナミック・レンジの適度な圧縮、一方で周波数帯域を拡張するなど、上記の問題を一つずつ解決した結果、不満なく鑑賞できる音質へ改善することができた。元々音質は良好だったため、1960年代中頃の放送録音としては上位の部類と言える。
一方のヴォーン・ウィリアムズとディーリアスは年代相応の音質だが、ライブという条件の悪さもあって解像度は今ひとつ。ノルウェー放送NRKの録音機材が少々古いのかも知れない。その割にダイナミック・レンジは大きめで調整が必要だった。ただし、それよりも大きな問題は、おそらくテープの経年劣化によると思われる中低域の断続的なノイズ。ヒス・ノイズやハム・ノイズ等の連続したノイズに比べて、途切れ途切れの断続的なノイズは音楽と重なりやすく、ノイズを削ると音楽も削ってしまう恐れがあった。ディスク化に当たっては、断続的なノイズのうち音楽がかぶっていない部分をサンプルとして採り、音楽を削らないように慎重にレベル調整したソフトウェアでノイズを低減。その他、周波数バランスを調整して(感覚的にだが)解像度を向上、ダイナミック・レンジを適度に圧縮した結果、ようやく鑑賞に堪える音質まで改善することができた。
BBCランチ・タイム・コンサートは、気軽にクラシック音楽を楽しむ主旨の番組らしいが、予想外にプログラムは凝っており、当ディスクに聴く1965年7月4日の収録(放送は8月25日)では、カバレフスキーの「コラ・ブルニョン」序曲、続いてエニグマ変奏曲、アラン・ロースソーンのピアノ協奏曲第2番(ジョージ・ハジニコス独奏)、最後になぜかベートーヴェンのレオノーレ序曲第3番というもの。統一性に疑問はあるが、名匠バルビローリの演奏でもあり、本格的なクラシック・リスナーも納得できる内容。英国の音楽文化レベルの高さを感じる。
ヴォーン・ウィリアムズとディーリアスは、ハレ管が1963年6月にノルウェー、スウェーデン、フィンランド、デンマーク各国をツアーした際の記録。5日の当録音はツアー初日の公演で、ベルゲン音楽祭へのゲスト出演に当たる。プログラムは、当ディスクに聴くヴォーン・ウィリアムズとディーリアスから始まり、続いてドビュッシーの交響詩「海」、おそらく休憩を挟んでシベリウスの交響曲第5番というもの。いずれもバルビローリ得意のレパートリーで、ドビュッシーとシベリウスの録音も聴きたくなる。
1963年当時、バルビローリはハレ管の首席指揮者を務める一方、ヒューストン響の常任指揮者も兼任、ベルリン・フィルやロンドンの各オーケストラにも客演、さらには英EMIに多くのレコーディングを行うなど、超多忙なスケジュールをこなしていたが、指揮者としてはまさに円熟期にあった。ちなみに同年1月のベルリン・フィルへの客演でマーラーの交響曲第9番を演奏、「こんなに良い作品だったのか」(同フィル支配人シュトレーゼマンの言)と団員も感銘を受け、翌年英EMIにレコーディングを行う契機となった。
ジョン・バルビローリは、エルガーのエニグマ変奏曲を1947年英HMVにハレ管と、1956年英パイにハレ管と、1962年英HMVにフィルハーモニア管とスタジオ録音していた。また、ヴォーン・ウィリアムズの「タリス幻想曲」を1946年英HMVにハレ管と、1962年同じく英HMVにシンフォニア・オブ・ロンドンとスタジオ録音していた。また、ディーリアスの「夏の庭で」を1968年英HMVにハレ管とスタジオ録音していた。
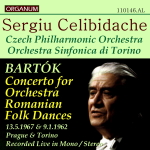
●チェリビダッケ/チェコ・フィル、トリノ・イタリア放送響
バルトーク 管弦楽のための協奏曲ほか 1967・1962年ライブ
オルガヌム110146AL
バルトーク 「管弦楽のための協奏曲」、「ルーマニア民俗舞曲」(弦楽合奏版)
セルジュ・チェリビダッケ指揮
チェコ・フィルハーモニー管弦楽団
トリノ・イタリア放送交響楽団
1967年5月13日、プラハ・スメタナ・ホール
1962年1月9日、トリノ・イタリア放送オーディトリアム
モノラル/ステレオ ライブ
※チェリビダッケによるバルトーク2作品。いずれも英国人コレクターからの提供音源。「管弦楽のための協奏曲」はプラハの春音楽祭のライブで、おそらくBBCラジオ・サード・プログラム(第3放送)のエアチェック。一方「ルーマニア民俗舞曲」はトリノ・イタリア放送の公開収録。こちらはステレオで、エアチェックではなく放送局保管音源のコピーと思われる。イタリア国営放送(RAI)は、1960年頃からステレオ録音を導入しており、ヨーロッパの放送局の中では早い方だった。
「管弦楽のための協奏曲」のオリジナル音源の状態は、ノイズこそ少ないものの、受信状態に問題があったのか、放送局側のマスターに問題があったのかは不明だが、ピアニシモがほとんど聞こえず、特に冒頭序奏部の十数秒はほとんど無音状態。また低域が強調される一方で高域が不足、全体に歪みも多くて聴きづらく、到底このまま商品化できる状態ではなかった。ピアニシモが極端に小さな点はおそらく弱音重視のチェリビダッケの特徴でもあり、音源供給元であるチェコの放送局が演奏を忠実に収録した結果とも思われるが、そうであれば、この状態のままBBCが放送したことに驚く。高域・低域のバランスの悪さや歪みはエアチェックしたリスナーの機器の問題やテープの経年劣化によるものだろう。ディスク化に当たっては、ピアニシモをわずかでも聴き取れる程度に音量を引き上げること、高域・低域のバランス補正、イコライジング等による歪みの除去に務めた。結果として、一応ストレスなく鑑賞に堪えるレベルまで音質改善を果たすことができた。
一方、「ルーマニア民俗舞曲」のオリジナル音源の状態は、ステレオということもあり、とりあえずは無難な状態。ただし、周波数ややレンジが狭く、一部の音域の凸凹による歪みも感じられた。ディスク化に当たっては、ソフトウェアによって周波数帯域を拡大、イコライジング等によりバランスを取り直した結果、こちらも不満なく鑑賞できる音質となった。
チェリビダッケは、チェコ・フィルを指揮した1967年当時54歳。スウェーデン放送響の音楽監督を務めていたが、後のミュンヘン・フィル時代のような巨匠的評価は受けておらず、中堅的な存在として、技術水準も様々なヨーロッパ各地のオーケストラに客演。プラハの春音楽祭の出演前後には3月と6月にスウェーデン放送響を指揮、7月にはナポリ・イタリア放送スカルラッティ管、8月にはシチリア交響楽団へ客演と、イタリア南部はおろか最南端まで「遠征」していた。チェリビダッケは1950年代後半からイタリア各地のオーケストラに客演を繰り返しており、その頃のコネクションが残っていたのだろう。
「プラハの春音楽祭」のプログラムは、ジョヴァンニ・カブリエリの「3つのカンツォーナ」、ショスタコーヴィチの交響曲第9番、休憩を挟んで「管弦楽のための協奏曲」という意欲的な構成。「管弦楽のための協奏曲」は、チェリビダッケがベルリン・フィル暫定首席指揮者時代から晩年まで頻繁に取り上げた作品で、1977年に初来日し読売日響を指揮した際にもプログラムに入れている。よほど自信があるか気に入った作品だったのだろう。また1967年当時のチェリビダッケにとって、チェコ・フィルは彼が指揮することができた最上位ランクの団体であり、オーケストラ・メンバーに高度な技術が要求される作品には最適と考えたのかも知れない。演奏は後年のような異常に遅いテンポ設定ではなく、やや遅めながら常識的範囲に収まっており、良い意味で違和感なく聴くことができる。一方、1962年録音の「ルーマニア民俗舞曲」はそれほど多く取り上げておらず、珍しい録音と言える。チェリビダッケは1963年から先述のようにスウェーデン放送響音楽監督に就任しており、イタリア各地のオーケストラに客演を行った時代の末期に当たる。
なお、曲想の違いもあるが、トリノ・イタリア放送響のチェコ・フィルとの技術レベルの違いは明白で、両者を比較するとアンサンブルの精度はもちろん、音楽的表現力の差を大きく感じる。トリノ・イタリア放送響は、名指揮者マリオ・ロッシが長年育成し、イタリア国営放送が運営する4つの放送響の中では屈指の存在という評価を得ていたが、国際的な一流団体はさらに高いレベルにあることが理解できる。また、当時のチェリビダッケが、オーケストラに対して後年ほどの厳格なリハーサルを行っていなかった事情もあると思われる。
セルジュ・チェリビダッケは、バルトークの「管弦楽のための協奏曲」を、1970年スウェーデン放送響、1976年南ドイツ(シュツットガルト)放送響、1995年ミュンヘン・フィル(2種)とライブ録音していた。また、「ルーマニア民俗舞曲」を、詳細は不明だが1970年代に南ドイツ(シュツットガルト)放送響とライブ録音していた。
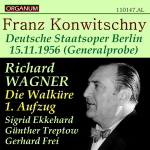
●コンヴィチュニー/ベルリン国立歌劇場管ほか
ワーグナー「ワルキューレ」第1幕 1956年ゲネラル・プローベ
オルガヌム110147AL
ワーグナー 楽劇「ニーベルングの指輪」第1夜
「ワルキューレ」第1幕
ジークリンデ:ジークリッド・エッケハルト(ソプラノ)
ジーグムント:ギュンター・トレプトウ(テノール)
フンディング:ゲルハルト・フライ(バス)
フランツ・コンヴィチュニー指揮ベルリン国立歌劇場管弦楽団(シュターツカペレ・ベルリン)
1956年11月15日、ベルリン国立歌劇場(リンデン・オーパー)
モノラル ライブ
※コンヴィチュニーによるワーグナー「ワルキューレ」第1幕全曲。ライブ録音ではあるが、本公演ではなくゲネラル・プローベ(最終リハーサル)における録音。ドイツ在住ロシア人コレクターからの提供音源。エアチェックではなく放送局保管音源のコピーと思われる。録音はラジオ放送に使用されたと言われるが、本公演ではなくゲネプロを録音したのは、マイクロフォンが聴衆の視界に入ることを演出家など劇場関係者が嫌ったためだろう。かつてNHKが招聘したイタリア歌劇公演などはステージ手前にマイクが林立していたが、これは放送局が主体で企画し、放送を前提として公演を行ったから許されたのだと思われる。
とはいうものの、当ディスクのオリジナル音源の状態は、本当に放送に使用されたとは思えないような劣悪な状態。オーケストラは比較的良く録れているが、歌唱については歌手がステージ上を移動する度に音量が変化し、マイクから遠い位置にいる場合、ほとんど蚊の鳴くような音量しか得られず、一方でマイクに近い位置での歌唱ではレベル・オーバー気味の大音量となりバランスが悪い。せっかくマイク・セッティングの制限がないゲネプロを録音したにもかかわらず、ステージ上にマイクの数が少なかったか、もしくはステージ中央の天吊りマイク1本のみで収録したのかも知れない。さらに録音テープの経年劣化の影響かヒスノイズが過剰で、一部は歌唱よりノイズの方が大きい箇所さえあった。また、気になるほどではないものの、聴衆が入っていたのかどうかは不明だが会場ノイズが若干あり、おそらく会場関係者が遠慮なく咳などをしたのかも知れない。とにかく到底このままでは一般的な鑑賞に堪える状態とはいなかった。
ディスク化に当たっては、まずは歌手の音量レベルの平均化。本来の声量の強弱を考慮(想像)しながらバランスを取り直す必要があったが、常にソプラノが弱く、バスが強すぎる傾向にあった。実際に声量差があったのだろうが、実演を聴く場合には視覚的に補えるため違和感は少ないが、ディスクとして音のみを鑑賞する場合にはバランスが悪い。また、マイクから遠い歌唱をボリュームアップするとヒス・ノイズも同様に増大するため、ピンポイントでノイズを低減。またボリュームアップのみでは高域が不足し歪みが生ずるため、周波数バランスを調整するなど、様々な対策を施し音質改善に努めた。幸い欠落や致命的に大きなノイズなどはなく、音質自体も1950年代中頃の平均レベルをクリアしていたため、優秀とは言えないまでも、何とか鑑賞に堪えるレベルまで持って行くことができた。1950年代のオペラ・ライブCDを聴き慣れているリスナーであれば、とりあえずは不満なく鑑賞できると思われる。
1956年、ベルリン国立歌劇場は第二次世界大戦後初めて、「ニーベルングの指輪」全曲の上演を企画。当時の音楽総監督コンヴィチュニー、演出エーリッヒ・ヴィッテの元、11月17日に「ワルキューレ」、翌1957年4月14日に「ラインの黄金」、5月26日に「ジークフリート」は1957年、7月21日に「神々の黄昏」が上演された。「ワルキューレ」と「ラインの黄金」の上演順が逆になっている理由はよく分からないが、出演キャストのスケジュールやリハーサル時間の確保などの都合かも知れない。
コンヴィチュニーは当時ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管の首席指揮者も兼務していたが、多くのドイツ系指揮者が西ドイツへ「脱出」した後、ヘルマン・アーベントロートとともに、東ドイツのクラシック音楽界をリードする指揮者として活動していた。しかし、アーベントロートが1956年5月に死去すると、孤軍奮闘状態となり、重要公演には必ず関与せざるを得ず多忙を極めることとなった。ベルリン国立歌劇場の上演記録を見ると、1956~1957年シーズンの288公演中、コンヴィチュニーは46公演を指揮しているが(歌劇以外にオーケストラのみの公演も数回行っている)、その他の指揮者陣は、ハンス・レーヴライン、ヨハネス・シューラー、まだ中堅クラスだったロヴロ・フォン・マタチッチ、若き日のホルスト・シュタイン、オスカー・ダノンなどであり、コンヴィチュニーと比べると明らかに格落ちの感がある。いかにコンヴィチュニーが東ドイツで唯一無二の存在だったか理解できる。結果として、この多忙がストレスとなってアルコール多飲となり、1962年にわずか60歳で世を去る遠因になったとも言える。
歌手について触れるとこちらも興味深い。ジークリンデ役のジークリッド・エッケハルト(1920~1990)は、今日ではほとんど忘れ去られたソプラノ。1946年に若くしてベルリン国立歌劇場と契約。イタリア・オペラの分類で言うリリコ~リリコ・スピント系でレナータ・テバルディに似た声質。ブリュンヒルデのような重い役柄を歌うようなワーグナー・ソプラノではなかったが、守備範囲は広かったらしく、「ドン・ジョヴァンニ」のドンナ・エルヴィーラ、「コシ・ファン・トゥッテ」のフィオルディリージ、「フィデリオ」のレオノーレ、「影のない女」の染物師の妻、「ヴォツェック」のマリー、「トラヴィアータ」のヴィオレッタ、「ボエーム」のミミから「トゥーランドット」のタイトル・ロール(抜粋のLPがある)まで歌っている。当ディスクの録音を聴く限り、優れた歌手だったことが理解でき、ウィーン国立歌劇場(1960年「エレクトラ」)やパリ、プラハ、チューリッヒ、ケルンなどの歌劇場にも出演した記録があるが、活動の中心はベルリン国立歌劇場だったようだ。しかし1961年6月に「エレクトラ」に出演後、8月に「ベルリンの壁」が建設されると、以降は同歌劇場への出演が途絶えた。当時まだ41歳だったが、今回調査した限りでは、その後の各地主要歌劇場への出演記録が見当たらず、どのような活動していたのか不明である。ステージを引退して教育活動に専念したのだろうか。
ジークムント役のギュンター・トレプトウは、ワーグナー作品に親しいリスナーであれば特に説明不要な著名人。ただし1956年当時はピークを過ぎつつあった時期かも知れない。
フンディング役のゲルハルト・フライ(1911~1989)は、日本ではあまり馴染みがないが、ベルリン国立歌劇場を中心に活動したベテラン。1939年にドイツ東部ゲルリッツの歌劇場でデビュー後、1948年にヴァルター・フェルゼンシュタイン率いるベルリン・コミッシェ・オーパーと契約。1954年にベルリン国立歌劇場に移り、1976年まで約20年にわたり在籍した。俳優としても活動したらしい。
フランツ・コンヴィチュニーは、「ワルキューレ」第1幕のスタジオ録音を残さず、1959年英ロイヤル・オペラとライブ録音していた。
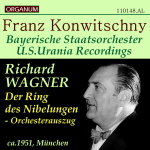
●コンヴィチュニー/バイエルン国立管
ワーグナー「ニーベルングの指輪」ハイライト 1951年頃 米ウラニア録音
オルガヌム110148AL
ワーグナー 楽劇「ニーベルングの指輪」から
「ラインの黄金」~ヴァルハラ城への神々の入城
「ワルキューレ」~ワルキューレの騎行
「ワルキューレ」~魔の炎の音楽
「ジークフリート」~第3幕間奏曲
「神々の黄昏」~ジークフリートのラインへの旅
「神々の黄昏」~ジークフリートの葬送行進曲
「神々の黄昏」~ヴァルハラ城へ崩壊と終曲
フランツ・コンヴィチュニー指揮バイエルン国立管弦楽団
1951年頃録音、ミュンヘン
モノラル 米ウラニア録音
※コンヴィチュニーによるワーグナー「リング」管弦楽抜粋。ドイツ在住ロシア人コレクターからの提供音源。オリジナルは米ウラニア・レーベルによるLP用セッション録音だが、当ディスクの音源はLPの復刻ではないらしく、音源提供者の情報では、南ドイツ放送が所有していたテープ(Reel
to reel
master)のコピーとのことで、にわかには信じがたい話。ただし当音源の音質をLPと比較すると、ウラニアのオリジナルLPは、コンヴィチュニーの演奏としては、手堅いもののスケールが小さく、緊張感に欠けた冴えない演奏という印象が強い。しかし、当ディスクのオリジナル音源は、当然同一演奏だが、LPより周波数帯域が広くダイナミック・レンジも大きく、迫力満点の充実した演奏という印象がある。LPは製作時に、再生の際のグルーブ(音溝)の振幅による針飛びを防ぐため、フィルターやリミッター等で音質を調整(低音や強音を抑える)することが多いが、当ディスクの音源はこのような「調整」前のマスターのコピーかも知れない。ただし、これがなぜ南ドイツ放送に保管されていたのか。これは飛躍した想像だが、ウラニアがレコーディングした際に、マスターのコピーをバイエルン国立管に渡し、その後マスターがバイエルン放送へ移管され、ドイツ国内各放送局間の交換音源として孫コピーが南ドイツ放送に送られたのではないだろうか。
本来のウラニアLPは、当ディスクの3曲目までとジークフリート牧歌のカップリングでURLP7063として、4曲目以降とパルシファルの第1幕への前奏曲と「聖金曜日の音楽」のカップリングでURLP7065として発売されていたが、当音源は「リング」抜粋のみとなっており、実際には「リング」抜粋をまとめて録音したのだろう。このうち「ジークフリートのラインへの旅」は「夜明け」が演奏されておらず、唐突に「ラインへの旅」から始まる。
ちなみに音源の状態は、正式なセッション録音でもあり、優れた録音機材を使用したと思われ、1950年年代初頭の録音水準を上回る優秀なもの。ただし古いテープ録音には避けられないヒス・ノイズやテープ・ノイズが混入しており、ディスク化に当たっては、音質に影響を与えないように配慮しつつノイズを低減した。結果として、全く不満なく鑑賞できる音質となった。
米ウラニア・レーベルというと、フルトヴェングラーの「エロイカ」が有名だが、確かに1951年の設立当初は、主に東ドイツの放送局所有の音源を買い取ってLP化しカタログを埋めていたが、レーベル設立と同時に自主録音も開始。ミラノ・スカラ座とイタリア・オペラ全曲録音や、東ドイツ放送局のコネクションから、アーベントロートやコンヴィチュニー、(ライブ録音だが)ケンペやヘーガーを起用、後年にはスワロフスキー、レイボヴィッツらとステレオ録音も行うなど、活発な制作活動を行った(クラシック以外にはジャズも発売している)。フルトヴェングラー「エロイカ」裁判の一件で、怪しげなマイナー・レーベルというイメージがあるが、ドイツの放送局から音源を買い取ってLP発売する手法はマーキュリー・レーベルなども行っており、少なくともAllegro、Royale、Plymouth、Varsityなど、演奏者を偽った(または演奏者非表記)、しかも盤質劣悪な廉価レーベルとは別格の存在と言える。レーベルとしては経営主体が何度か変わりながら1960年代初頭に活動を停止したようだが、音源の権利管理会社は現在でも存続しているらしく、1988~89年には所有音源から当ディスク音源以外の37点がCD化・発売されている。
コンヴィチュニーは、ウラニアに当ディスクの演奏を含むワーグナーの管弦楽曲集をLP3枚分、チャイコフスキー交響曲第5番(オルガヌム110060でディスク化済み)、R・シュトラウス「アルプス交響曲」、ほかに放送録音を元にした「トリスタンとイゾルデ」全曲などを残している。このうち「アルプス交響曲」とワーグナー管弦楽曲集は、バイエルン国立管と録音している。当時、ケンペやヘーガーが同管とレコーディングしており、ウラニアが同管と契約していたのだろう。コンヴィチュニーは、1949年からライプツィヒ・ゲヴァントハウス管の首席指揮者を務めており、すでに米ソの東西冷戦は激化していたものの、東西ドイツ間の往来は難しくなかった時代であり、コンヴィチュニーも問題なく西ドイツ入りできたと思われる。
当ディスクの正確な録音年は特定できなかったが、LPが1952年に発売されているため、ウラニア・レーベル設立年の1951年頃と思われる。録音会場も不明だが、バイエルン国立歌劇場ではオーケストラ録音に不向きで、ヘルクレスザール辺りだろうか。
フランツ・コンヴィチュニーは、「リング」全曲録音を除けば、当ディスク以外に「リング」抜粋の録音を残しておらず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音である。

●ハスキル BBCレコーディング 1946・1947年
スカルラッティ、ブランシェ、ブゾーニ
オルガヌム110149AL
ドメニコ・スカルラッティ
ソナタ ロ短調 L.33、K.87
ソナタ ニ短調 L.366、K.1
ソナタ 変ホ長調 L.142、K.193
ソナタ ヘ短調 L.171、K.386
ブランシェ ピアノ小協奏曲 変イ長調
ブゾーニ ヴァイオリン・ソナタ第2番
クララ・ハスキル(ピアノ)
ヨゼフ・シゲティ(ヴァイオリン)
サー・トマス・ビーチャム指揮ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団
1946年12月5日、9日、10日、16日(スカルラッティ)
1947年6月21日(ブランシェ)、10月14日(ブゾーニ)
ロンドン・BBCマイダ・ヴェイル・スタジオ
モノラル 放送ライブ
※クララ・ハスキルによるBBCのラジオ放送用スタジオ・ライブ。英国人コレクターからの提供音源。当然、録音当時も放送されたと思われるが、当音源は、後年(おそらく1960年代中期以降)のBBCサード・プログラム(第3放送)による再放送のエアチェックと言われる。再放送時はテープにダビングされていたらしいが、オリジナルはアセテート・ディスクによる録音で、1946年録音は12インチ78回転盤(片面4分程度)、1947年録音は16インチ33回転盤(片面10分程度)への録音と思われる。
オリジナル音源の状態は古い割には意外に良好。スクラッチ・ノイズも平均以下で、その他のノイズも少なく、周波数バランスもスカルラッティの一部に中高音の飛び出しがあった以外に問題ない。オーケストラ伴奏が付いたブランシェだけはさすがに混濁気味だったが、こちらも改善できる余地はあった。
ディスク化に当たっては、元々音質の素性が良かったため、スクラッチ・ノイズを軽く除去、スカルラッティのバランスの乱れや、混濁のあったブランシェについては、イコライジング等により「見通し」を良くし、混濁を低減するなどの調整を行った結果、古い録音ながら、ストレスなく鑑賞できる音質へと改善できた。
1946年当時、ハスキルは51歳。若い頃に脊椎側湾症を発症、その後も様々な不調に悩まされ、演奏回数は制限されたものの、既に優れたピアニストとしての評価を確立していた。同年12月22日にロンドン・ウィグモア・ホールでリサイタルを行ったが、その直前の5~21日、BBCスタジオで5回にわたってラジオ放送のための録音を行った。スカルラッティのソナタ19曲を中心に、バッハやハイドン、ベートーヴェンなどが録音されたが、当ディスクでは、BBCで再放送されたスカルラッティ4曲を紹介している。BBC録音には、バッハのイギリス組曲のようにハスキルが録音しなかった作品、ベートーヴェンのソナタ作品111のように不満足な演奏の録音しか残っていない作品など、貴重なレパートリーが含まれており、できれば全録音の公開が望まれるが、脆弱なアセテート・ディスクがすべて現存しているかは微妙なところだ。
1947年のブランシェの小協奏曲は珍しい作品。当然ハスキルの録音としても初レパートリー。エミール=ロベール・ブランシェ(1877~1943)は、スイスの作曲家・ピアニスト。4歳のとき、イグナツ・モシェレスの弟子で、ローザンヌ聖フランシスコ寺院のオルガニストだった父シャルル・ブランシェから指導を受け、18歳でケルン音楽院に入学しグスタフ・イェンセンとフリードリッヒ・ヴィルヘルム・フランケに師事。1898年ベルリンでフェルッチョ・ブゾーニに師事したという。その後、ピアニスト兼作曲家として活動。1905年からローザンヌ音楽院の院長も務めたが、1908年に院長を辞任、以降は教育・作曲・演奏活動、さらには登山に専念したという。このような経歴から、ドイツ的(ブゾーニ的?)な晦渋な作風を思い起こさせるが、1912年作曲の小協奏曲を聴く限り、フォーレのバラードをややドラマチックに仕上げたような近代フランス系作品という印象がある。この作品には、1942年、晩年の作曲者本人がアンセルメ指揮スイス・ロマンド管と共演して放送録音を残しており、同年からスイス・ジュネーヴに転居したハスキルが放送を聴いたか、アンセルメを通じて作品を紹介された可能性は高い。BBCがこの作品を録音・放送した理由は不明だが、BBCサード・プログラムは早くから現代音楽を積極的に取り上げるなど(ただしブルックナーも現代音楽扱いだったが)、画期的な番組編成を行っていたから、ハスキルとのプログラム検討で採用されたのかも知れない。
なお、ハスキルはこの録音の直後、7月1・2日に英デッカにベートーヴェンのピアノ協奏曲第4番をレコーディングしており、BBCがハスキル渡英の機会を捉えて録音依頼したと思われる。また、伴奏がビーチャム指揮ロイヤル・フィル(RPO)という点も珍しい。通常であれば自前のBBC響を起用するはずだが、スケジュールの都合かビーチャムが自分のオーケストラを売り込んだのか。RPOはオーケストラ設立(1946年)翌年の録音だが、英国中の名手を集めたと言われるだけに、若いオーケストラとは思えない手慣れた演奏を行っている。もちろんビーチャムの老練な指揮も貢献しているに違いない。
そのブランシェの師匠に当たるブゾーニのヴァイオリン・ソナタ第2番の録音は既出盤もあるが、当ディスクではイコライジング等により既出盤より歪みを低減するなど、さらに音質改善を行い、シゲティの渋いヴァイオリンも聴きやすくなった。ハスキルはこの録音を挟んで、10月12日にロンドン・フィル、21日にフィルハーモニア管とそれぞれモーツァルトのピアノ協奏曲(K.271、K.488)を演奏しており、結構多忙だったようだ。このように渡英する度にBBCが録音を依頼するなど、英国におけるハスキルの評価は、米ウェストミンスターや蘭フィリップスがレコーディングを開始する以前から高かったことが理解できる。
クララ・ハスキルはスカルラッティのソナタのうち、ロ短調とヘ短調を1950年米ウェストミンスター、1951年蘭フィリップス、変ホ長調を1950年米ウェストミンスターにスタジオ録音していたが、それ以外の作品は当ディスクが現在確認されている唯一の録音と思われる。

●音質良好 フルトヴェングラー/ウィーン・フィル
ベートーヴェン交響曲第9番 1952年「ニコライ・コンサート」ライブ
オルガヌム110150AL
ベートーヴェン 交響曲第9番「合唱付き」
ヒルデ・ギューデン(ソプラノ)、ロゼッテ・アンダイ(アルト)
ユリウス・パツァーク(テノール)、アルフレート・ペル(バス)
ウィーン・ジングアカデミー合唱団
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
1952年2月3日、ウィーン・ムジークフェライン大ホール
モノラル ライブ
※フルトヴェングラー/ウィーン・フィル(VPO)による、VPO創設者・作曲家オットー・ニコライを記念する特別演奏会のライブ。アメリカ人コレクターによる提供音源。当録音は音質劣悪な1975年発売のカナダ・ロココLP以来、LP・CDで多数の既出盤があるが、アメリカ人コレクターによると当ディスクの音源は、ヴォイス・オブ・アメリカ(VOA)関係者の遺族から入手したとのこと。ただし、アメリカのコレクター間で出回っている出所不明音源の大半は「VOA関係者提供」と称されることが多く信憑性に乏しい。ただしオリジナル音源の音質は非常に良好で周波数レンジも十分広く、ノイズも少なく明快。当音源を、既出盤で最も信頼がおける独フルトヴェングラー協会盤および米アンダンテ盤(両者ともオーストリア放送(ORF)由来の正規音源で音質は同一)と比較するとほぼ同等の音質だが、第1楽章の低域が若干過剰。第3楽章の一部が高域過剰、第4楽章の録音レベルが低いなど若干の違いもあり、両盤のコピーではないようだ。さらに異なるのは、ORF正規音源CDに特有の「漂白」されたような臨場感の不足(ORFのプロデューサー/エンジニア、クラウス/アイヒンガー両氏による過剰なノイズ・カットの悪影響だ)をあまり感じず、多少ダイレクトに響くこと。両氏が手を入れる前の世代の音源か、協会盤またはアンダンテ盤用マスターをさらにリマスター(ただし意味不明な)した音源かは不明だが、いずれにしても上記の正規音源CDは2022年現在入手困難であり、当レーベルでディスク化する価値があると判断し、発売することとした。
ディスク化に当たっては、上記の周波数バランスの悪さを解消、さらにオリジナルから存在する第4楽章終結近くの合唱の一部音量低下と歪みの改善を図った。後者は、完全には解消できなかったが、若干は違和感なく聴きやすくなっていると思われる。
オットー・ニコライを記念するVPOの特別演奏会は、戦争により中断など一部例外はあるものの毎年2月に開催されており、第1回は1887年にハンス・リヒター指揮で行われた。プログラムはベートーヴェンの管楽八重奏曲とメンデルスゾーンの弦楽八重奏曲、シューマンの「スペインの歌」(歌芝居)という、ほとんど室内楽コンサート。1891年にリヒターが初めてベートーヴェンの第9を演奏、その後、マーラー、シャルク、ワインガルトナーらが指揮を引き継ぐ間に徐々に第9の比率が高まっていったようだが、フルトヴェングラーが1928年に初めて指揮した際は、バッハのブランデンブルク協奏曲第5番とブルックナーの交響曲第7番を演奏した。ベートーヴェンの第9ばかりではなかったのだ。フルトヴェングラーは1928年以降、1932年と1947年にクレメンス・クラウス、1941年にクナッパーツブッシュが指揮した以外、死去する1954年までニコライ・コンサートほぼ独占して指揮した。
1952年のコンサートは、2月2~4日の3回公演ですべて昼12時開演(夜はオペラ公演があるウィーン・フィルならではの時間設定)。当音源は2日目の公演録音で、ORFの前身であるRAVAG(ロシア管轄のラジオ放送局)またはRWR(ロート・ヴァイス・ロート=アメリカ管轄のラジオ放送局)によるものだが、いずれにしても実際の録音はオーストリア人スタッフによって行われたと思われる。
フルトヴェングラーは録音当時66歳。死去の2年前だが、超多忙な演奏活動によって過労気味ながら、壮年期の演奏スタイルを維持していた最後の時期に当たる。1952年は1月10・14・19日にローマRAI響と3公演、23日はウィーン国立歌劇場で「ワルキューレ」(国立歌劇場は戦災による被害で再建中、会場はアン・デア・ウィーン劇場)、26~28日はVPO定期公演、その間27日夜にもシェーンブルン宮殿でVPOの特別公演、30日はウィーン国立歌劇場で「トリスタンとイゾルデ」、そして2月2~4日は当ディスクの録音を含むニコライ・コンサート、8~10日はベルリン・フィル創立70周年記念公演、29日から3月4・6・9・12・16日はミラノ・スカラ座で「マイスタージンガー」公演と、リハーサル時間などを考えるとほとんど休養なしの状態が想像される。その後も多忙な演奏活動が続き、6月に肺炎を発症して入院、11月に演奏活動に復帰するが、治療の際の抗生物質の副作用で聴力が衰え、そのためか徐々に「晩年様式」とも言える枯れた演奏スタイルへと変化していくこととなる。
当ディスクの演奏は、既によく知られているように、1951年バイロイト盤(EMI盤)の自在さと覇気を保ちつつ、より完成度の高い演奏という評価がある。EMI盤が、リハーサル録音を中心に本公演の録音をミックスした「編集盤」であることが判明した現在では、未編集のライブ録音として、今後いっそう評価が高まることが想像される。
フルトヴェングラーはベートーヴェンの交響曲第9番のスタジオ録音を残してないが、ライブ録音では、1937年、1942年(2種)、1943年、1951年(4種)、1952年(当録音)、1953年(2種)、1954年(2種)の存在が確認されている。

●音質良好 マタチッチ/シュターツカペレ・ベルリン
チャイコフスキー 交響曲第5番、R・シュトラウス「死と変容」 1957年ライブ
オルガヌム110151AL
チャイコフスキー 交響曲第5番
R・シュトラウス 交響詩「死と変容」
ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮シュターツカペレ・ベルリン(ベルリン国立歌劇場管弦楽団)
1957年1月18日、ベルリン国立歌劇場
モノラル ライブ
※マタチッチ/シュターツカペレ・ベルリン(SKB)によるチャイコフスキー交響曲第5番とR・シュトラウス「死と変容」、1957年のコンサート・ライブ。ドイツ在住ロシア人コレクターによる提供音源。音質の良さからエアチェックではなく、放送局保管音源のコピーと思われる。音質良好と記したが、オリジナル音源の音質自体は1957年という年代の水準を上回るものの、全体にバランスが悪く、演奏を安心して楽しめる状態ではなかった。交響曲の第1楽章~第3楽章と第4楽章ではレコーダーのレベル設定が異なる上、周波数特性も異なり、第1楽章~第3楽章は低域過剰の一方、ヴァイオリンの音が固くややヒステリック、放送用にダイナミック・レンジが圧縮されて迫力不足。第4楽章は逆にダイナミック・レンジが広すぎ、レベル・オーバー気味で高域過剰。終結部近くでワウ(音揺れ)が発生。「死と変容」もダイナミック・レンジが広すぎ、弱音が聴こえるようにボリューム設定すると強音が大き過ぎてうるさい等々、様々な問題があった。
ディスク化に当たっては、交響曲全4楽章と「死と変容」のレベルを揃えること、交響曲はイコライジング等により周波数バランスを改善。ダイナミック・レンジの復元、第4楽章は、ワウをソフトウェアで修正。コンプレッサーを軽くかけて弱音と強音の差を縮め、家庭内での鑑賞に適したダイナミック・レンジへの調整を行い、一般的な鑑賞で不満のない音質とすることができた。歌劇場のため残響が乏しいが違和感はない。会場ノイズは極小。拍手はオリジナルの段階からカットされている。
1957年当時マタチッチは58歳。ドレスデン国立歌劇場首席指揮者を務める傍ら、ベルリン国立歌劇場の指揮者陣の一員として(当時の音楽監督はコンヴィチュニー)、数多くのオペラ公演の指揮を行う一方、レコーディングも英コロンビアと契約。ロシア・東欧作品やオペラ諸作品、協奏曲伴奏など、録音活動も活発に行っていた。
当ディスクのライブを含むベルリン国立歌劇場1956~1957年シーズン中、マタチッチは、オペラ公演では「トスカ」、「イェヌーファ」、「コシ・ファン・トゥッテ」、「アイーダ」、「イーゴリ公」、「ポッペアの戴冠」、「トラヴィアータ」を指揮しており、あらゆるレパートリーをカバーするオペラ指揮者の典型とも言える職人的仕事をこなしている。一方、オーケストラのみのシンフォニー・コンサートにも3回出演しており、その1回が当録音となる。
1月18日のコンサートは、フレスコバルディ、ツィポーリ、ヴィヴァルディのバロック諸作品に加えて、当ディスクに聴くR・シュトラウス「死と変容」、チャイコフスキーの交響曲第5番という、意欲的というか少々風変わりな構成。おそらくR・シュトラウスまでが前半、後半がチャイコフスキーだったのだろう。
このようにベルリンとドレスデンで多忙な活動を行っていたマタチッチだが、第二次世界大戦中のナチスへの協力容疑によって、当時はその実力に対して良いポストに恵まれていたとは言えなかった。ドレスデン国立歌劇場首席指揮者の地位も、当時ベルリン国立歌劇場音楽総監督だったエーリヒ・クライバーが東独政府と対立して1955年に突如辞任、ドレスデンの首席指揮者だったコンヴィチュニーが後を継いだ結果、横滑りのような形で得たとも考えられ、その地位もわずか3シーズンで当時38歳だったスイトナーに譲ることとなる。録音契約を結んでいた英コロンビアにとってもメイン・アーティスト扱いではなく、発売アイテムのレパートリーの穴を埋める役割が中心で、おそらく専属契約ではなく、その契約も1960年代初頭には消滅する。
マタチッチがようやく安定的な国際的評価を獲得するのは、1959年にバイロイト音楽祭に出演、1961年にフランクフルト歌劇場の音楽総監督就任後といえる。その後はチェコ・フィル(レコーディングも行った)やフランス国立放送管等へ客演、N響とも関係を深めるなど活動の場を広げた。ただし旧オーストリア・ハンガリー帝国領内の出身で(貴族の家系でもあった)、ウィーン少年合唱団に入団、ウィーン音楽アカデミーを修了しているにもかかわらず、ウィーン・フィルとの縁は薄く、1944年に3回、おそらく無観客の放送録音で小品を指揮したほか、1962年ウィーン・ブルク劇場における劇作家アルトゥール・シュニッツラー生誕100年記念コンサートでシューベルト「未完成」1曲を指揮したのみで、マタチッチのウィーンにおけるコンサート活動は1928年から57回共演したウィーン響が中心だった。ウィーン・フィルを指揮することは、何らかのコネクション、強力なマネージメント事務所や大手レコード会社がバックに入らなければ容易ではないのだろう。
英コロンビアは、マタチッチがクロアチア出身のスラヴ系という理解から、ロシア・東欧系のレパートリーを多くレコーディングしており、初来日もスラヴ歌劇団と同行して「ボリス・ゴドゥノフ」などを指揮している。しかし、経歴を見れば分かるように、明らかに独墺系(特にウィーン)伝統の教育を受けており、ここに聴くチャイコフスキーもスラヴ的と言うよりもドイツ流解釈の演奏と言える。
ロヴロ・フォン・マタチッチは、当ディスク以外にチャイコフスキーの交響曲第5番を1960年チェコ・スプラフォンにチェコ・フィルとスタジオ録音したほか、1975年N響とライブ録音していた。R・シュトラウスの「死と変容」は当録音が現在確認されている唯一の録音と思われる。
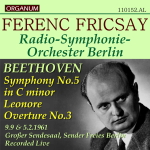
●音質良好 フリッチャイ/ベルリン放送響
ベートーヴェン 交響曲第5番、レオノーレ序曲第3番 1961年ライブ
オルガヌム110152AL
ベートーヴェン 交響曲第5番、レオノーレ序曲第3番
フェレンツ・フリッチャイ指揮ベルリン放送交響楽団
1961年9月9日、2月5日、ベルリン・自由ベルリン放送グローサー・ゼンデザール
モノラル ライブ
※フリッチャイ/ベルリン放送響によるベートーヴェン交響曲第5番とレオノーレ序曲第3番。1961年のライブ録音でドイツ在住ロシア人コレクターによる提供音源。いずれもエアチェックではなく、放送局保管音源のコピーと思われる。1961年頃になると放送局のオーケストラ録音も技術的に安定し、しかも自由ベルリン放送の本拠地ホールにおける録音でもあるため、2曲ともモノラルながら音質は良好。ノイズレスで目立った瑕疵もなく、このままの状態でも、とりあえずは大きなストレスなく聴ける状態。ただし、交響曲については、2台のレコーダーで録音したらしく、第1・第2楽章と第3・第4楽章では周波数バランスが異なり、前半2楽章は低域過剰でかぶり気味。また、これは演奏に起因することだが、フリッチャイのピアニシモが極めて小さく、第2・第3楽章などでは、フォルティシモを基準にボリューム設定するとピアニシモが全く聴き取れない状態。おそらく実際のラジオ放送では、ピアニシモが聴こえるようにボリュームを上げる一方、コンプレッサーを強くかけてフォルティシモを「つぶす」といった調整を行ったのだろう。
ディスク化に当たっては、第1・第2楽章の低域過剰を解消、第2・第3楽章の聴き取れないピアニシモについては、放送ほどの過剰なコンプレッサー使用は避けつつ、標準的なオーディオ・システムを使用して家庭で鑑賞するボリューム・レベルを想定して、コンプレッサーを軽度に使用して調整を行った。結果的に満足して鑑賞できる音質とすることができた。2曲とも会場ノイズは極小。
交響曲第5番はベルリン芸術週間演奏会における録音。9月9~11日の3回公演初日、前半にコダーイの交響曲(ベルリン初演)、続いてモーツァルトのクラリネット協奏曲(ハインリヒ・ゴイザー独奏)、休憩を挟んで後半に交響曲第5番というプログラム。レオノーレ序曲第3番は、ベルリン放送響の定期演奏会における録音。2月5、6日の2回公演初日、オール・ベートーヴェン・プログラムで、前半にレオノーレ序曲第3番、続いてピアノ協奏曲第3番(ゲーザ・アンダ独奏)、休憩を挟んで後半に交響曲第3番「英雄」というもの。コンサート・プログラムは、第2次世界大戦前から戦後1950年代中期頃までは、プログラム前半が交響曲などの大曲、後半が中小規模の協奏曲や小品の組み合わせという「前半が重く後半が軽い」構成が多かったが(フルトヴェングラーなども同様だった)、1950年代末~1960年代初頭に至って、現在と同様の形態に変化したことが分かる。
フリッチャイのレパートリーは、モーツァルトやベートーヴェンなど独墺系の有名交響曲からバルトーク、コダーイなど出身地のハンガリー人作曲家の作品、チャイコフスキーをはじめとするロシア系作品、さらにはドイツやイタリアの歌劇諸作品、現代音楽までと極めて広く、当ディスクに聴くベートーヴェンを特に中心的レパートリーとしていたわけではないが、ここで聴ける演奏は、独墺系の伝統を受け継ぐ巨匠指揮者を凌ぐほどの充実したもの。
フリッチャイは1958年頃から体調不良に悩まされ、入退院を繰り返すようになった。病名は各種情報で異なり、当初は胃潰瘍、その後は癌とも白血病とも言われ不明確だが、最終的には胆嚢穿孔で死去したとされる。一般に、このような体調の悪化がフリッチャイの演奏スタイルに変化を及ぼしたという「通説」があり、確かに、以前のような機敏な速めのテンポで、アンサンブルの正確さを重視する(縦の線を厳しく揃える)というハンガリー系指揮者に共通する楷書風の演奏から、病後は、極めて遅いテンポで、一音一音噛みしめるような重厚な演奏(例えれば晩年のチェリビダッケやジュリーニに近いか)へと変化した。もちろん体調悪化に伴い、以前のような俊敏で万全なコントロールができる指揮が困難になったことも想像されるが、それよりも作品への理解が深くなったと捉えるべきだろう。当ディスクの演奏はそのような「深化」が十分に発揮された演奏と言える。晩年には、今までレパートリーにはなかったブルックナーの研究も行っており、残念ながら演奏は実現しなかったが、この辺りはまさしく晩年のチェリビダッケやジュリーニと共通するレパートリーだ。フリッチャイがさらに数年存命していたら、さらにスケールの大きい巨匠的演奏を行っていたに違いない。
フェレンツ・フリッチャイは、当ディスク以外にベートーヴェンの交響曲第5番を1961年(当演奏会の直後)ベルリン・フィルと独グラモフォンにスタジオ録音していた。また、レオノーレ序曲第3番を1958年ベルリン・フィルと独グラモフォンにスタジオ録音したほか、1951年にライブ録音(2種)、1952年と1961年(5月)に放送録音していた。
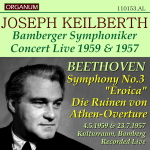
●優秀録音 カイルベルト/バンベルク響
ベートーヴェン 交響曲第3番「英雄」、劇付随音楽「アテネの廃墟」序曲 1959年・1957年ライブ
オルガヌム110153AL
ベートーヴェン 交響曲第3番「英雄」、劇付随音楽「アテネの廃墟」序曲
ヨゼフ・カイルベルト指揮バンベルク交響楽団
1959年5月4日、1957年7月23日、バンベルク・旧ドミニコ会修道院「文化の間」(クルトゥアラウム)
モノラル ライブ
※カイルベルト/バンベルク響によるベートーヴェンの交響曲第3番「英雄」と「アテネの廃墟」序曲、それぞれ1959年と1957年のコンサート・ライブ。ドイツ在住ロシア人コレクターによる提供音源。交響曲は音質の良さからエアチェックではなく放送局保管音源のコピー、序曲はエアチェックと思われる。ただし、序曲もエアチェックとはいうものの年代を考慮すればかなり良好な音質。いずれにしても1950年代末の録音の水準を上回り、特に交響曲は放送局によるモノラル録音末期、1960年代後半の音質と同等の高音質。オリジナルの録音はバイエルン放送によると思われ、同放送局の録音技術の優秀さを示している。なお、交響曲には既出CDがあり、1990年代?にバンベルク響定期会員向けに限定配布された。演奏・録音共に優れていたため実施されたのだろう。序曲は7月という異例の時期の演奏だが、夏の音楽祭などが開催されていたのかも知れない。
ディスク化に当たっては、交響曲は、ヒス・ノイズも極小で周波数レンジも十分広く、イコライジングによってバランスを微調整したのみで、まったく不満なく鑑賞できる音質となった。序曲はモノラルにもかかわらず位相ずれ(モノラル・テープをステレオ・レコーダーでダビングした際に生じたと思われる)や周波数バランスの凸凹があったためそれぞれ改善し、レンジも若干狭かったためソフトウェアにより高域を補完し、改善に努めた。結果として、特に優れた録音の交響曲には及ばないものの、こちらも鑑賞に堪える状態となった。いずれも会場ノイズは極小。
カイルベルトは1950年1月、バンベルク響の首席指揮者に就任、亡くなる1968年までその地位に留まり、同響の名声の向上に多大な貢献を行った。ちなみに同響の前身は、1940年チェコのプラハで当地在住のドイツ系音楽家によって設立されたプラハ・ドイツ・フィルであり、同フィルの初代(にして一代限りの)首席指揮者もカイルベルトだった。同フィルは1945年5月に最後の演奏会を行った後、同年の第二次世界大戦終結によるドイツ人国外追放を受け、同フィルのメンバーがドイツ・バイエルン州へ移住して新たなオーケストラを設立、当初はバンベルク・トーンキュンストラー管と称し、1946年に現行のバンベルク響へ改称、ヘルベルト・アルベルト、ゲオルグ・ルートヴィヒ・ヨッフムなどが指揮を行ったが、1949年3月にカイルベルトが4年ぶりに指揮、聴衆とオーケストラから大好評を得、前述のように改めて初代首席指揮者となった。
当ディスクに聴くベートーヴェン2作品は、カイルベルト49~51歳という、指揮者としてはまだ中堅に当たる年齢の演奏だが、すでに巨匠的風格を持った充実したもの。オーケストラの技術レベルも安定期に入っていた時期であり、余裕を持って演奏している様子がうかがえる。特筆すべきは、「英雄」第1楽章コーダで、原譜どおりにトランペットがテーマ演奏を途中でやめている点。1959年当時、レコーディングではピエール・モントゥーが実践していたが、極めて少数派だったことは間違いない。カイルベルトは独墺系の伝統的巨匠指揮者の一人と称されることが多いが、この辺りは研究熱心で決して因習にとらわれない見識があったことが理解できる。
ヨゼフ・カイルベルトは、ベートーヴェン交響曲第3番「英雄」を1956年独テレフンケンにハンブルク国立フィルとスタジオ録音したほか、1939年シュトゥットガルト帝国放送管と放送録音、1968年バンベルク響とライブ録音していた。また、劇付随音楽「アテネの廃墟」序曲を1960年独テレフンケンにハンブルク国立フィルとスタジオ録音していた。

●音質良好 シュミット=イッセルシュテット/ハンブルク北ドイツ放送響
モーツァルト 交響曲第41番「ジュピター」、ベートーヴェン 交響曲第7番
1965年放送ライブ/コンサート・ライブ
オルガヌム110154AL
モーツァルト 交響曲第41番「ジュピター」
ベートーヴェン 交響曲第7番
ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮ハンブルク北ドイツ放送交響楽団
1965年1月28日、ハンブルク北ドイツ放送スタジオ10
1965年2月1日、ハンブルク・ムジークハレ
モノラル 放送ライブ/コンサート・ライブ
※イッセルシュテット/北ドイツ放送響によるモーツァルト「ジュピター」とベートーヴェン交響曲第7番、それぞれ聴衆なしの放送スタジオ録音と聴衆を入れたライブ録音。ドイツ在住ロシア人コレクターによる提供音源。いずれもエアチェックではなく放送局保管音源のコピーと思われる。演奏はビデオ収録が行われたが、音声のみもオーディオ・レコーダーで別録音しており、当ディスクはこちらを音源としている。両者を比較すると、ビデオ音声は貧相で冴えない音質だが、オーディオ・テープ録音はさすがに良好。ただし、テープの経年劣化または会場の音響特性によるものか、2曲とも高域不足でバランスが悪く不満が残る状態。2曲の演奏会場は異なるものの、録音年月日が近接しており、同一スタッフが似たようなマイク・セッティングで収録したのかも知れないが、ビデオ収録のため、マイクの数や位置に制約があったことによる悪影響も想像される。
ディスク化に当たっては、イコライジング等により高域を補正、全体のバランスも取り直した。幸いヒス・ノイズ等の耳障りなノイズが少なく、容易に音質改善を図ることができた。結果として1960年代中期のモノラル放送録音としては水準以上の音質となり、ストレスなく鑑賞できる音質となった。
ハンス・シュミット=イッセルシュテットは、日本では、ドイツの伝統的巨匠指揮者の一人であり、北ドイツ放送響の首席指揮者を長らく務め、英デッカにベートーヴェンの交響曲全集、バックハウスと共にピアノ協奏曲全集を録音したことで知られているが、2回の来日経験があるにもかかわらず(読響と大阪フィルを指揮した)、6歳年上のベーム、2歳下のヨッフム、8歳下のカイルベルト(そしてカラヤン)などと比べると地味な存在と言える。もちろん世代の近いレオポルト・ルートヴィヒやロスバウト(両者はそれぞれハンブルク国立歌劇場、南西ドイツ放送響で偉大な業績を残した)より知名度は高いが、レコード録音のみから情報を得ていた1960年代の日本では、専属のレコーディング契約がなく、独テレフンケンや米マーキュリーなどから散発的に録音が発売される状況では、特に際だった個性的演奏を聴かせることがない堅実な芸風のイッセルシュテットは、並み居る巨匠指揮者の影に隠れてしまったと言える。最も注目されるべき英デッカへのベートーヴェン交響曲全集録音について、当時のレコード批評を見ても、ウィーン・フィルにばかり注目が集まり、指揮者に対する批評は「手堅くまとめている」という程度で大きな賛辞はあまり見かけない。
仮にメジャー・レーベルではなくても、中堅レーベルにイッセルシュテット/北ドイツ放送響としてまとまったレコーディングを行い、さらに、このコンビによる来日が実現していたら、1950年代末~1960年代前半に来日公演を行ったコンヴィチュニー/ゲヴァントハウス管、クリュイタンス/パリ音楽院管、アンチェル/チェコ・フィルなどと並ぶ人気や評価を得ていたに違いない。
先のベートーヴェン交響曲全集は1970年のベートーヴェン生誕200年を記念して、1965年から1968年にかけて録音されたが、計画当初、英デッカ契約下にはウィーン・フィルとベートーヴェンにふさわしい独墺系指揮者が存在しなかった。クナッパーツブッシュは高齢の上1964年に死去。クリップスは1960年に米エベレストにロンドン響と交響曲全集をレコーディング済み、ミュンヒンガーはベートーヴェンを万全なレパートリーとしておらず、ショルティはまだ若過ぎ(プロデューサー、ジョン・カルショウの言)、スイス=フランス系のアンセルメは元々対象外だが、1958~1963年にスイス・ロマンド管と交響曲全集をレコーディング、資本系列先の独テレフンケンにはカイルベルトがいたが、こちらも独自に全集録音が進行中(未完に終わった)という具合だった。このような状況下でカルショウは、1950年代前半英デッカにレコーディング実績があるベームを起用したかったらしい。しかし、当時ベームは独グラモフォンと専属契約を結んでおり、スポット的なレンタル契約は可能だったものの、ベートーヴェン交響曲全集のような大プロジェクトへの起用は、独グラモフォンが許可しなかった。同社では、カラヤン/ベルリン・フィルが1961~1962年にベートーヴェン交響曲全集をレコーディングしており競合を嫌ったのだろう。後年カルショウは「ベームはアメリカで人気がないので起用しなかった」と述べているが、ベームは1960~1962年にかけてニューヨーク・フィル定期演奏会などを6回にわたって指揮(それぞれ複数回公演であるため、実際には10回以上)、メトロポリタン歌劇場にも複数回登場するなどアメリカでも評価は高かった。カルショウの発言は悔し紛れの言い訳だろう。
結果として、デッカ録音チームにいたエリック・スミスがイッセルシュテットの実子であるというつながりもあり、また、1958~1959年にバックハウスとベートーヴェンのピアノ協奏曲全集をレコーディングした実績により、イッセルシュテット/ウィーン・フィルのベートーヴェン交響曲全集が実現した。ウィーン・フィルは指揮者や作品との相性が悪いと惨憺たる結果となることもあり、同オケと相性が良かったピエール・モントゥーでさえ、ベルリオーズの幻想交響曲のデッカ録音は「完全な失敗に終わった」と述べている。イッセルシュテットは実演ではウィーン・フィルと一度も共演したことがなかったが、それでも安定したレベルの演奏を残したことは、イッセルシュテットの貢献が大きいと言える。
しかし、仮にイッセルシュテット/北ドイツ放送響によるベートーヴェン交響曲全集のレコーディングが実現していたら、さらに充実した結果が期待できただろう。
当ディスクに聴くモーツァルトとベートーヴェンは、特に個性的であったり派手な演奏ではないが、単に手堅い以上に高い音楽性を持つ充実した演奏。オーケストラもイッセルシュテットの指揮と同様に、派手なヴィルトゥオジティを披露する訳ではないが、技術レベルは高く、イッセルシュテットによる長年の育成の結果と言える。
ハンス・シュミット=イッセルシュテットは、モーツァルトの交響曲第41番「ジュピター」を1958年米マーキュリーに北ドイツ放送響とスタジオ録音したほか、1961年にライブ録音、1965年9月に放送録音していた。また、ベートーヴェンの交響曲第7番を1969年英デッカにウィーン・フィルとスタジオ録音したほか、1961年にライブ録音していた。
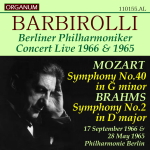
●バルビローリ/ベルリン・フィル
モーツァルト交響曲第40番、ブラームス交響曲第2番
1966年・1965年ライブ
オルガヌム110155AL
モーツァルト 交響曲第40番
ブラームス 交響曲第2番
サー・ジョン・バルビローリ指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
1966年9月17日、1965年5月28日、ベルリン・フィルハーモニー・ホール
モノラル、ライブ
※バルビローリとベルリン・フィル(BPO)によるモーツァルト交響曲第40番とブラームス交響曲第2番のライブ。ドイツ在住ロシア人コレクターからの提供音源で、オリジナルはいずれもエアチェックらしく、オランダのFMラジオ放送を受信したものという。放送局間の交換音源としてオランダに送られたようだ。エアチェックとは言うもののノイズも少なく比較的良好な音質。ただし、当時のオランダ放送の悪癖として、フォルティシモの音量を抑えるコンプレッサー処理を行っており、弱音と強音の差がほとんどない状態。ディスク化に当たっては、フォルテ、フォルティシモの音量を復元する作業を行った。また、一部周波数バランスが悪く、低域過剰・高域不足の箇所があり、こちらもイコライジング等により補正した。結果として、特に優秀な音質というわけではないが、一般的な鑑賞には十分堪えられる状態とすることができた。なお、当録音には既出のCD-Rが存在するが、音質劣悪な状態で、おそらく別のリスナーによるエアチェック音源によるものと思われる。
なお、1965・1966年当時、欧米では既にステレオLPが普及しており、当録音がステレオではないことが惜しまれるが、当時、西ドイツの放送局は、部分的にステレオ録音を導入していたものの、本格的に普及したのは1960年代末であった。
モーツァルトは1966年ベルリン芸術週間における録音、プログラム後半にはブルックナーの交響曲第9番が演奏された(オルガヌム110134ALとしてディスク化済み)。バルビローリとBPOは1949年にスコットランドのエジンバラで初共演、1950年にベルリンで再び共演、10年ほどのインターバルを経て、1961年に3度目の客演指揮を行った。この時の公演が大好評となり、その後バルビローリが亡くなる1970年まで毎年指揮、BPOとの共演は84回に上ったという。バルビローリとBPOとの共演ではマーラー演奏に注目が集まりがちだが、モーツァルトやベートーヴェン(第9も演奏している)、ブラームスなど、オーソドックスな独墺系レパートリーも数多く取り上げた。客演指揮者の場合、出身国の作曲家や得意のレパートリーにプログラムを限定されることが多いが、バルビローリは特別な存在だったのだろう。
モーツァルトの交響曲第40番は、モーツァルトの交響曲中、バルビローリにふさわしいと思える作品だが、なぜか正式なレコーディングを行わなかった。バルビローリのレパートリーが膨大で、レコード会社の営業方針も絡んでモーツァルトなど独墺系作品は優先順位が低く、初期の契約先である英HMV、後の米コロンビアや英パイにも小品などを散発的に録音しているものの、交響曲は第29番と41番(英パイ)が残されたのみ。晩年の契約先である英EMIにベートーヴェンやブラームス、マーラー、R・シュトラウスなど独墺系作品を録音し始めたのも、晩年の1960年代後半に集中しており、第40番も、録音計画はあったもののバルビローリの突然の死去によって実現しなかったのかも知れない。
一方のブラームスの交響曲第2番も、ブラームスの交響曲4曲の中では第4番と並んでバルビローリにふさわしい作風。バルビローリ自身も好んだ作品らしく、2回レコーディングを行っており、BPOとは1962年、第二次世界大戦中にドイツ軍の空襲によって破壊された英国コヴェントリー聖堂再建記念公演でも同曲を演奏している。当ディスクの演奏でも、バルビローリならではの叙情的かつ情熱的な第1、2楽章、軽妙な第3楽章に続き、第4楽章では打って変わって熱狂的な演奏を繰り広げており、特に強奏部の直前には、指揮台で一歩踏み出す足音が聞こえる。同曲のウィーン・フィルとのスタジオ録音では、落ち着いた、しかも美しい演奏が展開されているが、当ディスクではライブ演奏らしい濃厚な表情とダイナミックさが印象的。
ジョン・バルビローリは、モーツァルトの交響曲第40番のスタジオ録音を残さず、当ディスク以外に1962年ハレ管と放送録音、1964年同じくハレ管とゲネプロ録音していた。また、ブラームスの交響曲第2番を、1940年米コロンビアにニューヨーク・フィル、1966年英EMIにウィーン・フィルとスタジオ録音したほか、1962年にライブ録音(2種)していた。

●アリーヌ・ヴァン・バレンツェン 1952年放送ライブ
ベートーヴェン ピアノ・ソナタ番「熱情」、「告別」、27番
オルガヌム110156AL
ベートーヴェン ピアノ・ソナタ第23番「熱情」、第26番「告別」、第27番
アリーヌ・ヴァン・バレンツェン(ピアノ)
1952年、フランス国立放送(ラジオ・フランス)スタジオ、パリ
モノラル、放送ライブ
※現役時代は日本でほとんど知られておらず、近年急速に注目され評価が高まってきたアリーヌ・ヴァン・バレンツェンによるスタジオ・ライブ。音源は英国人コレクターからの提供で、放送局保管音源のコピーと思われる。1951年から52年にかけて、バレンツェンがラジオ放送用に聴衆を入れずにスタジオ収録したベートーヴェンのピアノ・ソナタ全曲の一部で、当ディスクの3曲は、詳しい録音日時は不明ながら1952年とされており、第23番は1952年初頭とのことで1月頃と思われる。
フランス国立放送は1940年代末頃からテープレコーダーを導入しており、当演奏もオリジナルはテープ録音だったと思われる。ただし、当時の放送局では高価だったオーディオ・テープを再利用するため、放送後はテープからアセテート盤にダビングして保存することが一般的であった。盤は16インチ33・1/3回転のセンター・スタート(外周からスタートする機器もあった)、15~20分程度の収録が可能で、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ全曲の場合、30枚(片面盤のため30面)以上の盤が必要だったと思われる。一般にアセテート盤は表面が脆弱で再生を繰り返すと早期に劣化、経年劣化も甚だしく、また保存環境が悪いとさらに劣化が進む。
当ディスク収録の3曲の場合、オリジナルの状態は第23番が比較的良好である一方、第26番と27番は問題が多かった。第23番は第3楽章を除けばスクラッチ・ノイズも少なく、高域は不足気味ながら10kHz程度まで伸びている。しかし、第26番と27番は全体に盛大なスクラッチ・ノイズが乗っており状態の悪い78回転SP盤並み。また周波数レンジも狭く高域は6000Hz止まりとナロー・レンジでこれまたSP盤程度。また3曲ともアセテート盤の特性と思われるが、中低域が過剰もしくは高域が圧倒的に不足しており鈍い音色で、そのためか演奏自体もデリカシーに欠けた、強引で力まかせの冴えないイメージがある。フォルテにも少し濁りがあるが、これはバレンツェンの打鍵が強すぎてアセテート盤の音溝に収録しきれなかったためだろう。
ディスク化に当たっては、ソフトウェアによって音質を損ねない範囲でノイズを低減、周波数帯域をFM放送並みの15kHz程度まで拡大する一方、周波数バランスを調整して中低域過剰を改善するなど、種々手を加えた結果、1950年代中期のスタジオ録音LP程度の音質まで改善することができた。一部除去しきれなかったスクラッチ・ノイズがわずかに残るものの、ストレスなく一般的な鑑賞には堪える状態と言える。
アリーヌ・ヴァン・バレンツェン(1897~1981年)はアメリカ出身の女流ピアニスト(姓から推測すると両親いずれかの先祖はオランダ系か)。4歳の時に母とともにフランスに移住し、パリ音楽院でマルグリット・ロンなどに学んだ後、ベルリンでドホナーニ、ウィーンでレシェティツキにも師事した。その後はパリを中心に活動し1927年にはヴィラ=ロボスのショーロス第8番初演に参加するなど同時代の作曲家と交流。1930年代初頭にフランス国籍を取得した後は終生パリに住んだが、北米でもツアーを行うなど広く活動した。このような経歴から、フランス音楽のみならずショパンや独墺系など様々な地域の作品も得意としたが、ベートーヴェンのピアノ・ソナタはレコーディングにおいても重要なレパートリーであり、中期のソナタは78回転SP、モノラルLP、ステレオLPとフォーマットを変えて繰り返しスタジオ録音を行っている。演奏スタイルは、パリ音楽院出身の女流ピアニストという優美なイメージとは異なる猪突猛進型で、同じレシェティツキ門下の兄弟子シュナーベルを想起させる。現代の演奏家に例えればマルタ・アルゲリッチに近いか。第23番などはバレンツェンの芸風に最もふさわしい作品で、荒々しいアグレッシブな演奏は他に例を見ない。
興味深いのは、1953年アメリカ・ニューヨーク公演時の3月26日付け「ニューヨーク・タイムズ」の記事。「フランス人ピアニストでコンサート・ステージにおけるベテラン、アリーヌ・ヴァン・バレンツェンが昨夜タウン・ホールでアメリカ・デビューを果たした。彼女の戦前のHMVレコードをご存知の方は、彼女のプロとしての地位を説明する必要はないだろう」。記者はバレンツェンがアメリカ出身であることを知らなかったようだが、確かに4歳でアメリカを離れており、戦前のHMV録音を持ち出す辺りは、バレンツェンがフランス国籍を取得する以前からフランス人と認識していたようだ。
バレンツェンは、上記のようにベートーヴェンのピアノ・ソナタ全曲をフランス国立放送ラジオ・フランスでスタジオ収録したが、現状では、全32曲のうち、内訳は不明だが22曲のアセテート盤の存在が確認されているとのこと。ただし、残り10曲が失われたわけではなく単に未発見ということだろう。ちなみに同放送録音のうち、第8番・9番・13番・14番はオルガヌム110059AL、第28番・29番は同110157AL、第30番~32番は同110158ALで発売済みである。
アリーヌ・ヴァン・バレンツェンは、当ディスク以外にベートーヴェンのピアノ・ソナタ第23番を1947年・1952年・1960年仏VSMに、第26番を1952年仏VSMにスタジオ録音していた。第27番は当ディスクが現在確認されている唯一の録音と思われる。

●アリーヌ・ヴァン・バレンツェン 1952年放送ライブ
ベートーヴェン ピアノ・ソナタ第28番、29番「ハンマークラヴィア」
オルガヌム110157AL
ベートーヴェン ピアノ・ソナタ第28番、第29番「ハンマークラヴィア」
アリーヌ・ヴァン・バレンツェン(ピアノ)
1952年、フランス国立放送(ラジオ・フランス)スタジオ、パリ
モノラル、放送ライブ
※現役時代は日本でほとんど知られておらず、近年急速に注目され評価が高まってきたアリーヌ・ヴァン・バレンツェンによるスタジオ・ライブ。音源は英国人コレクターからの提供で、放送局保管音源のコピーと思われる。1951年から52年にかけて、バレンツェンがラジオ放送用に聴衆を入れずにスタジオ収録したベートーヴェンのピアノ・ソナタ全曲の一部で、当ディスクの2曲は、詳しい録音日時は不明ながら1952年とされている。
フランス国立放送は1940年代末頃からテープレコーダーを導入しており、当演奏もオリジナルはテープ録音だったと思われる。ただし、当時の放送局では高価だったオーディオ・テープを再利用するため、放送後はテープからアセテート盤にダビングして保存することが一般的であった。盤は16インチ33・1/3回転のセンター・スタート(外周からスタートする機器もあった)、15~20分程度の収録が可能で、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ全曲の場合、30枚(片面盤のため30面)以上の盤が必要だったと思われる。一般にアセテート盤は表面が脆弱で再生を繰り返すと早期に劣化、経年劣化も甚だしく、また保存環境が悪いとさらに劣化が進む。
当ディスク収録の2曲の場合、オリジナルの状態は第28番はスクラッチ・ノイズがやや多く、第29番は若干少ないという印象。ただし、29番は一部サーフェイス・ノイズとは異なる盤面の損傷と思われる突発的ノイズがあった。また、2曲ともアセテート盤の特性と思われるが、中低域が過剰もしくは高域が圧倒的に不足しており、鈍い音色で、そのためか演奏自体もデリカシーに欠けた、強引で力まかせの冴えないイメージがある。フォルテにも少し濁りがあるが、これはバレンツェンの打鍵が強すぎてアセテート盤の音溝に収録しきれなかったためだろう。
ディスク化に当たっては、ソフトウェアによって音質を損ねない範囲でノイズを低減、周波数帯域をFM放送並みの15kHz程度まで拡大する一方、周波数バランスを調整して中低域過剰を改善するなど、種々手を加えた結果、1950年代中期のスタジオ録音LP程度の音質まで改善することができた。一部除去しきれなかったスクラッチ・ノイズがわずかに残るものの、ストレスなく一般的な鑑賞には堪える状態と言える。
アリーヌ・ヴァン・バレンツェン(1897~1981年)はアメリカ出身の女流ピアニスト(姓から推測すると両親いずれかの先祖はオランダ系か)。4歳の時に母とともにフランスに移住し、パリ音楽院でマルグリット・ロンなどに学んだ後、ベルリンでドホナーニ、ウィーンでレシェティツキにも師事した。その後はパリを中心に活動し1927年にはヴィラ=ロボスのショーロス第8番初演に参加するなど同時代の作曲家と交流。1930年代初頭にフランス国籍を取得した後は終生パリに住んだが、北米でもツアーを行うなど広く活動した。このような経歴から、フランス音楽のみならずショパンや独墺系など様々な地域の作品も得意としたが、ベートーヴェンのピアノ・ソナタはレコーディングにおいても重要なレパートリーであり、中期のソナタは78回転SP、モノラルLP、ステレオLPとフォーマットを変えて繰り返しスタジオ録音を行っている。演奏スタイルは、パリ音楽院出身の女流ピアニストという優美なイメージとは異なる猪突猛進型で、同じレシェティツキ門下の兄弟子シュナーベルを想起させる。現代の演奏家に例えればマルタ・アルゲリッチに近いか。
興味深いのは、1953年アメリカ・ニューヨーク公演時の3月26日付け「ニューヨーク・タイムズ」の記事。「フランス人ピアニストでコンサート・ステージにおけるベテラン、アリーヌ・ヴァン・バレンツェンが昨夜タウン・ホールでアメリカ・デビューを果たした。彼女の戦前のHMVレコードをご存知の方は、彼女のプロとしての地位を説明する必要はないだろう」。記者はバレンツェンがアメリカ出身であることを知らなかったようだが、確かに4歳でアメリカを離れており、戦前のHMV録音を持ち出す辺りは、バレンツェンがフランス国籍を取得する以前からフランス人と認識していたようだ。
バレンツェンは、上記のようにベートーヴェンのピアノ・ソナタ全曲をフランス国立放送ラジオ・フランスでスタジオ収録したが、現状では、全32曲のうち、内訳は不明だが22曲のアセテート盤の存在が確認されているとのこと。ただし、残り10曲が失われたわけではなく単に未発見ということだろう。ちなみに同放送録音のうち、第8番・9番・13番・14番はオルガヌム110059AL、第23番・第26番・27番は同110156AL、第30番~32番は同110158ALで発売済み。当ディスクではバレンツェンが録音を残さなかった後期ピアノ・ソナタの演奏が貴重である。
アリーヌ・ヴァン・バレンツェンは、当ディスク以外にベートーヴェンのピアノ・ソナタ第28番と第29番のスタジオ録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音と思われる。

●アリーヌ・ヴァン・バレンツェン 1952年放送ライブ
ベートーヴェン ピアノ・ソナタ第30番、31番、32番
オルガヌム110158AL
ベートーヴェン ピアノ・ソナタ第30番、第31番、第32番
アリーヌ・ヴァン・バレンツェン(ピアノ)
1952年、フランス国立放送(ラジオ・フランス)スタジオ、パリ
モノラル、放送ライブ
※現役時代は日本でほとんど知られておらず、近年急速に注目され評価が高まってきたアリーヌ・ヴァン・バレンツェンによるスタジオ・ライブ。音源は英国人コレクターからの提供で、放送局保管音源のコピーと思われる。1951年から52年にかけて、バレンツェンがラジオ放送用に聴衆を入れずにスタジオ収録したベートーヴェンのピアノ・ソナタ全曲の一部で、当ディスクの3曲は、詳しい録音日時は不明ながら1952年とされている。
フランス国立放送は1940年代末頃からテープレコーダーを導入しており、当演奏もオリジナルはテープ録音だったと思われる。ただし、当時の放送局では高価だったオーディオ・テープを再利用するため、放送後はテープからアセテート盤にダビングして保存することが一般的であった。盤は16インチ33・1/3回転のセンター・スタート(外周からスタートする機器もあった)、15~20分程度の収録が可能で、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ全曲の場合、30枚(片面盤のため30面)以上の盤が必要だったと思われる。一般にアセテート盤は表面が脆弱で再生を繰り返すと早期に劣化、経年劣化も甚だしく、また保存環境が悪いとさらに劣化が進む。
当ディスク収録の3曲の場合、オリジナルの状態は第31番はスクラッチ・ノイズがやや多く、第30番と32番は若干少ない印象。また、3曲ともアセテート盤の特性と思われるが、中低域が過剰もしくは高域が圧倒的に不足している一方、20kHz周辺にピークがあり耳障り、全体に鈍い音色で、演奏自体もデリカシーに欠けた、強引で力まかせの冴えないイメージがある。フォルテにも少し濁りがあるが、これはバレンツェンの打鍵が強すぎてアセテート盤の音溝に収録しきれなかったためだろう。
ディスク化に当たっては、ソフトウェアによって音質を損ねない範囲でノイズを低減、周波数帯域をFM放送並みの15kHz程度まで拡大する一方、周波数バランスを調整して中低域過剰を改善するなど、種々手を加えた結果、1950年代中期のスタジオ録音LP程度の音質まで改善することができた。一部除去しきれなかったスクラッチ・ノイズがわずかに残るものの、ストレスなく一般的な鑑賞には堪える状態と言える。
アリーヌ・ヴァン・バレンツェン(1897~1981年)はアメリカ出身の女流ピアニスト(姓から推測すると両親いずれかの先祖はオランダ系か)。4歳の時に母とともにフランスに移住し、パリ音楽院でマルグリット・ロンなどに学んだ後、ベルリンでドホナーニ、ウィーンでレシェティツキにも師事した。その後はパリを中心に活動し1927年にはヴィラ=ロボスのショーロス第8番初演に参加するなど同時代の作曲家と交流。1930年代初頭にフランス国籍を取得した後は終生パリに住んだが、北米でもツアーを行うなど広く活動した。このような経歴から、フランス音楽のみならずショパンや独墺系など様々な地域の作品も得意としたが、ベートーヴェンのピアノ・ソナタはレコーディングにおいても重要なレパートリーであり、中期のソナタは78回転SP、モノラルLP、ステレオLPとフォーマットを変えて繰り返しスタジオ録音を行っている。演奏スタイルは、パリ音楽院出身の女流ピアニストという優美なイメージとは異なる猪突猛進型で、同じレシェティツキ門下の兄弟子シュナーベルを想起させる。現代の演奏家に例えればマルタ・アルゲリッチに近いか。
興味深いのは、1953年アメリカ・ニューヨーク公演時の3月26日付け「ニューヨーク・タイムズ」の記事。「フランス人ピアニストでコンサート・ステージにおけるベテラン、アリーヌ・ヴァン・バレンツェンが昨夜タウン・ホールでアメリカ・デビューを果たした。彼女の戦前のHMVレコードをご存知の方は、彼女のプロとしての地位を説明する必要はないだろう」。記者はバレンツェンがアメリカ出身であることを知らなかったようだが、確かに4歳でアメリカを離れており、戦前のHMV録音を持ち出す辺りは、バレンツェンがフランス国籍を取得する以前からフランス人と認識していたようだ。
バレンツェンは、上記のようにベートーヴェンのピアノ・ソナタ全曲をフランス国立放送ラジオ・フランスでスタジオ収録したが、現状では、全32曲のうち、内訳は不明だが22曲のアセテート盤の存在が確認されているとのこと。ただし、残り10曲が失われたわけではなく単に未発見ということだろう。ちなみに同放送録音のうち、第8番・9番・13番・14番はオルガヌム110059AL、第23番・26番・27番は同110156AL、第28番・29番は同110157ALで発売済み。当ディスクではバレンツェンが録音を残さなかった後期3大ピアノ・ソナタの演奏が貴重である。
アリーヌ・ヴァン・バレンツェンは、当ディスク以外にベートーヴェンのピアノ・ソナタ第30番・31番・32番のスタジオ録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音と思われる。
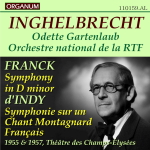
●アンゲルブレシュト/フランス国立放送管 1955年・1957年ライブ
フランク 交響曲 ダンディ フランスの山人の歌による交響曲
オルガヌム110159AL
フランク 交響曲
ダンディ フランスの山人の歌による交響曲
オデット・ガルテンローブ(ピアノ)
デジレ・エミール・アンゲルブレシュト指揮フランス国立放送管弦楽団
1955年3月17日、1957年7月4日、パリ・シャンゼリゼ劇場
モノラル、ライブ
※アンゲルブレシュト/フランス国立放送管による交響曲2作品。いずれもアンゲルブレシュトのディスコグラフィには存在しなかった作品(ダンディの第3楽章のみ海外でCD化の記録あり)。英国人コレクターからの提供音源で、エアチェックではなく放送局保管音源のコピーと思われる。2曲とも直接音主体で解像度が高く、会場のデッドな音響も相まってホールトーンをあまり入れないという、当時のフランス国立放送の典型的な録音スタイルだが、録音年を考慮すれば音質自体はかなり良好。ダンディの方が若干会場の雰囲気が感じられ、2年間の技術の進歩が感じられる。
ただしフランクは、当時の家庭用ラジオで鑑賞することを考慮したか、ダイナミック・レンジが圧縮され、フォルティシモはメゾフォルテ程度に、ピアニシモがメゾピアノ程度に調整されており、現代のオーディオシステムで聴く場合には違和感が大きかった。第1楽章冒頭導入部の音量レベルが異常に大きい一方、続く第1主題による強奏ではほとんど音量の増加がないなど、演奏解釈自体に誤解を生じる恐れもあった。ダンディについても、ダイナミック・レンジは十分に確保されているものの、独奏ピアノをクローズアップする一方、オーケストラは遠くで鳴っているような、古いスタイルのマイク・セッティングでバランスが悪く、強奏時には何とも迫力不足。また2曲とも録音テープの経年変化によるものか、高域がかなり不足していた。
ディスク化に当たっては、フランクについては周波数バランスの改善とともに、問題があるダイナミック・レンジの復元を行った。ただし単純なソフトウェア・ツールでまとめて復元を行うと、演奏者の意図と異なるおそれあったため、個々のピースについて順に、オリジナル音量レベルのわずかな差異を参考にして復元を行った。ダンディについては、根本的な改善は難しいものの、オーケストラが前に出るように周波数バランスの調整を行った。結果として、一般的な鑑賞には不満のない状態とすることができた。2曲ともライブながら会場ノイズはほとんどなく、放送を前提として聴衆には静粛にするよう要請されていたのだろう。
なお、当ディスクに聴く二つの交響曲が演奏された演奏会は、シャンゼリゼ劇場の上演記録には記載がない。フランス国立放送による公開収録という位置づけで、通常の演奏会とは見なされていないことがその理由と思われるが、形式的には、演奏会1回分のプログラムが組まれ、聴衆(おそらく抽選)もおり、通常の公演と何ら変わらない。ただし当ディスクのオリジナル音源には含まれていなかったが、当時の放送の慣習として、会場ではステージ上で司会者が進行を担当、解説者が曲目を解説していたと思われる。
1955年3月17日の演奏会は、前半にフランクの交響曲、おそらく休憩を挟んで後半にマーラーの「亡き子を偲ぶ歌」(ルクレツィア・ウェスト独唱)、最後にドビュッシーの交響詩「海」という構成で、なかなか重量級のプログラム。1957年7月4日の演奏会は、前半にバルトークの「六つのルーマニア民俗舞曲」、続いてダンディの「フランスの山人の歌による交響曲」、休憩を挟んで後半にカントルーブの「オーヴェルニュの歌」から5曲(ニコール・テヴァン独唱)、最後にアンゲルブレシュト自作の交響的招魂「ヴェズレー」というもので、通俗ではない凝った構成。オーケストラ運営を集客に頼る必要がないフランス国立放送管ならではのプログラムと言える。
アンゲルブレシュトの演奏について分かることは、いずれの作品も速めのテンポで明快な表現。ただし、フランクの交響曲の演奏時間はインターバルを含めて36分であり、ポール・パレーが33分 シャルル・ミュンシュが36分前後で演奏していることを考えるとそれほど早いわけではない。しかしシャルル・グノーが初演の際に「陰鬱」と酷評したような重苦しさがないためか、テンポが速く感じる(ちなみにモントゥーは39分 フルトヴェングラーは39分 カラヤンは42分程度で演奏しており、ドイツ寄りの演奏解釈ではテンポが遅くなるのかも知れない)。また、表現自体もパレーを思わせる。
明快な表現とは、アンゲルブレシュトの演奏に共通している点であり、ダンディ作品でピアノを演奏しているガルテンローブが、アンゲルブレシュトのドビュッシー演奏について「あえてぼやけたとか印象派的と言わず、液状的・流動的な性格の演奏を行う」と評しているように、悪い意味での低徊趣味に陥ることなく、作品を大掴みに整理・解釈することを主眼としていたと思われる。これはアンゲルブレシュト本来の演奏スタイルに加え、先のポール・パレーのテンポ設定・解釈に見られるような当時のフランスの演奏様式、さらに若い頃から新作初演など同時代の作品を多く演奏した経験から、評価の定まっていない作品の姿を正しく、しかも分かりやすい形で聴衆に提示するという目的から生まれた演奏スタイルが融合したものと言えるかも知れない。これは一般には新即物主義と言われる様式に近いが、新即物主義が、感情移入が過剰で音楽の形を崩しがちなロマン主義的・表現主義的演奏の反省から生まれたものであるのに対して、アンゲルブレシュトやパレーの演奏は、ロマン主義・表現主義が主流だった時代においても、例えばリヒャルト・シュトラウスやトスカニーニに見るような、19世紀以来途切れることなく続いていた新古典主義スタイルの延長にあるように思われる。いずれにしても、特にフランクは従来の「標準的な」演奏とは異なる、新たなアプローチを提示しているようだ。
なお、ダンディ作品でピアノ独奏を担当しているオデット・ガルテンローブ(1922~2014)は、日本では演奏家としてよりも教育者・学者として知られ、音楽教育関係者の間では著名な存在。パリ音楽院でピアノをマルグリット・ロン、ラザール・レヴィ、作曲をアンリ・ビュッセル、ミヨーらに学び、1946年にローマ大賞を受賞後、ピアニストおよび作曲家として活動を開始、1959年からは母校パリ音楽院教授として教育にも携わった。フランスの一部の演奏家の傾向として、ベテランの域に達する前に演奏活動から教育に重心を移す傾向があるが、ガルテンローブも同様らしく、演奏家として国際的に華々しく活躍するというキャリアは選ばなかった。レコーディングも少なくはないが、マイナー・レーベルを中心に自らの作品や伴奏・室内楽録音が多く、独奏はドビュッシー作品集(仏ユーロソン、プライベート・プレスと言われるが、後述する放送録音の転用か)のみ。協奏曲録音としては、非売品だがモーツァルトのピアノ協奏曲第23番のLPがあった。いずれも名演とされ、稀少盤として現在は高価に取引されている。一方、アンゲルブレシュト監修の元、フランス国立放送にドビュッシーのピアノ作品全集を録音したと言われ、その他シューマンやベートーヴェンなどの協奏曲を含む大量の放送録音が残されているとのこと。また近年になって、自作自演の放送録音がCD化されている。補足として、15歳の時に第1回ガブリエル・フォーレ国際コンクールで優勝し、賞品は仏パテ・レーベルへのレコーディングだったという記載があり、フォーレ作品の78回転盤がごく少数プレスされたかも知れない。
上記のように、デジレ・エミール・アンゲルブレシュトは、フランクの交響曲とダンディ「フランスの山人の歌による交響曲」のスタジオ録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音である。
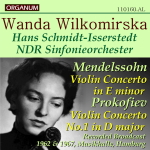
●ウィウコミルスカ 1962年・1967年放送ライブ
メンデルスゾーン、プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲
オルガヌム110160AL
メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲
プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲第1番
ワンダ・ウィウコミルスカ(ヴァイオリン)
ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮ハンブルク北ドイツ放送交響楽団
1962年3月12日・1967年、ハンブルク・ムジークハレ
モノラル/ステレオ、放送ライブ
※名女流ウィウコミルスカによるメンデルスゾーンとプロコフィエフのヴァイオリン協奏曲。ドイツ在住ロシア人コレクターからの提供音源で、聴衆を入れずに行われた放送のための録音。音質の良さからエアチェックではなく放送局保管音源のコピーと思われる。メンデルスゾーンはモノラルだが、プロコフィエフはステレオ。2曲とも録音には定評がある旧西ドイツの放送録音だけに手慣れた印象で、オリジナルの状態でもバランスが良く、とりあえず大きな不満はない音質。また、北ドイツ放送は1960年代中頃からステレオ録音を行っており、1967年のプロコフィエフでは左右の分離や定位などの点で既に完成の域に達しているようだ。とは言うものの、特にメンデルスゾーンは高域が伸びきらない印象で、これはハンブルク・ムジークハレの音響特性によるもの。当時このホールにおける北ドイツ放送響の録音の傾向でもある。残響などを付加すれば多少聴きやすくなるが、オリジナル録音に過剰に手を加えることは避け、ディスク化に当たっては、周波数帯域の拡大と周波数バランスの調整によって、高域不足を解消した。一方のプロコフィエフは、ステレオ録音というメリットもありメンデルスゾーンよりも優秀だが、こちらも若干高域が不足する印象があり、メンデルスゾーンと同様に改善作業を行った。
ワンダ・ウィウコミルスカは名手として知られておりレコーディングも多いが、当ディスクに聴く2曲はいずれもディスコグラフィには存在しなかった作品。ウィウコミルスカは1949年頃からポーランド国営レーベルのムザにレコーディングを開始したが、自国ポーランドの作品を中心に、同名のコンクールで入賞した縁からヴィエニャフスキを除けば、バルトーク、ショスタコーヴィチ、ハチャトゥリアンなど東欧・ロシア系の近現代作品が多く、なぜかドイツ・ロマン派などクラシック作品のメインストリームを外したレパートリーが大半であった。後年、米コニサー・ソサエティにまとまったレコーディングを行った際、レーベルの希望もあったのか、ようやくバッハやベートーヴェン、ブラームスなどのソナタ作品をレコーディングしているが、その後も当ディスクに聴くような有名協奏曲の録音を行うことはなかった。真摯な演奏家がしばしば言うところの「ある作品に多くのLP・CDが存在する中で、自分がさらに録音する必要を感じない」一人だったかも知れず、その点で当ディスクに聴く2曲は貴重な録音と言える。
メンデルスゾーンは、ウィウコミルスカ32~33歳頃の演奏。デッドな音響の録音のためか、冒頭は楷書体の几帳面な演奏という印象だが、演奏が進むに連れて自由度が高まっていく感があり、基本的に録り直しを行わない放送録音らしい臨場感がある。プロコフィエフは残念ながら録音月日は不明だが、メンデルスゾーンの5年後の録音。ステレオの広がりもあり、ウィウコミルスカのさらに自在な演奏を楽しめる。やはり近現代の作品の方が相性が良いのかも知れない。シュミット=イッセルシュテットは期待通りの手堅い指揮。
ウィウコミルスカは1960年代に年間平均100回以上の演奏会を行ったと言われており、自国ポーランドのみならず、西欧や北米、オーストラリアまで幅広く演奏活動を行った。今後はこれらツアー中のライブ/放送録音の発掘に期待したいところだ。
上記のようにウィウコミルスカは当ディスクに聴くメンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲とプロコフィエフのヴァイオリン協奏曲第1番のスタジオ録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音である。
![]()
●テバルディ/バスティアニーニ
マルティーニ&ロッシ・コンサート1957
オルガヌム110161AL
ヴェルディ 歌劇「仮面舞踏会」~お前こそ心を汚すもの
ヘンデル 歌劇「ジュリオ・チェーザレ」~この胸に息のある限り
ヴェルディ 歌劇「リゴレット」~悪魔め、鬼め
カタラーニ 歌劇「ワリー」~もう安らかではいられない
ヴェルディ 歌劇「オテロ」~クレド「無慈悲な神の命ずるままに」
プッチーニ 歌劇「マノン・レスコー」~この柔らかなレースの中に
ジョルダーノ 歌劇「アンドレア・シェニエ」~祖国の敵
ポンキエルリ 歌劇「ジョコンダ」~自殺
レナータ・テバルディ(ソプラノ)
エットレ・バスティアニーニ(バリトン)
オリヴィエロ・デ・ファブリティース指揮ミラノ・イタリア放送交響楽団
1957年1月7日、ミラノ芸術劇場
モノラル ライブ
※テバルディとバスティアニーニ。第二次世界大戦後1950年代のイタリア・オペラ黄金時代を代表する名歌手の共演。イタリアの洋酒メーカー・マルティーニ&ロッシ提供のラジオ番組の公開収録がオリジナル・テープで、このほど新たにコンタクトのとれたイタリア人コレクターからの提供音源。イタリア放送協会(RAI)による録音だが、放送のエアチェックではなく、現在RAIに保存されているテープからのコピーでもなく、放送当時(1950年代末頃)、RAIのテープからコピーされた個人所有の第二世代テープが当ディスクの音源となっているらしい。オリジナル音源の音質は年代相応のややナローレンジで古びた感じだがノイズも少なく、そのままの状態でも一応聴き通せる状態。ただし少々不思議な点は、番組のオープニング曲が流れ、アナウンサーが順に曲目を紹介していくという、通常の放送をそのまま収めてあるが、各曲ごとに音質が異なり、聴衆の拍手も大ホールと思えるような響きの大きい大喝采の曲目から、小ホールで少人数の聴衆が控えめに拍手しているような曲目もあり、同一会場の演奏とは思えないこと。また、テバルディの一部歌唱のみ、歌唱が終わる前にフライングで拍手が入る点は、オペラの国イタリアの聴衆にはあり得ない行為だ(しかも収録会場はスカラ座のあるミラノの中規模?ホール)。
あくまで想像だが、当初は全曲通して放送されたものの、後に個別の曲目のみを放送するため、テープを切り離して放送に使用した際、個別にイコライジング等で音質調整したり、拍手を差し替えた可能性が考えられる。放送を前提とした公開収録では、応募して招待された聴衆は「静粛にすること、風邪を引いていないこと、咳をしないこと、拍手も控えめにすること」を参加の条件とされたと言われ、例えオペラ・アリアでも控えめの拍手に終始した可能性がある。しかし、このような大人しい拍手では放送に使用した場合に盛り上がらないこと必至。拍手を加工して放送された曲目と、個別には放送されなかった(拍手の差し替えがなかった)曲目を再度結合して1本のテープとして復元。当ディスクの音源としたことから、このような差異が生じたのではないだろうか。
全体として、テバルディの歌唱の方が音質が良く、周波数レンジも広い。ホールはデッドな音響で残響が乏しいはずだが、2曲目の「ジュリオ・チェーザレ」は美しい残響が入っている。1950年代当時、デジタル・リバーブ/ディレイなどの電子的な処理は存在しなかったからエコー・ルームなどで残響を付加したのだろうか。またフライング気味の拍手はテバルディの歌唱に多い。一方、バスティアニーニの歌唱はナローレンジでやや古びたイメージ。「アンドレア・シェニエ」は人気曲で繰り返し放送に使用されたためか、ややテープ劣化がある。こちらも一部に拍手の追加があるようだが、不自然ではない形に仕上がっている。
ディスク化に当たっては、ヒスノイズの低減、周波数レンジの拡大といった基本的な処理に加え、5000Hz以上が急速に低下していたため周波数バランスの補正、バスティアニーニの歌唱部分を改善するためのイコライジング等の作業を行った結果、ストレスなく鑑賞できる音質とすることができた。拍手の復元は不可能であるためそのままとした。またテバルディの「ジュリオ・チェザーレ」の付加残響はそれなりに良くできているので、カットせずに残した。
マルティーニ&ロッシ・コンサート(正式名称「Grandi Concerti Martini & Rossi」)は1936 年 11 月 30
日放送開始。おそらく第二次世界大戦の中断を挟んで1960年代初め頃まで、毎週月曜日午後8 時 40
分に放送が行われた。当初は生放送だったようだが、後年は録音による放送が行われたと想像される。当時のイタリア・オペラ界の代表的な歌手のほぼ全員に加え、イタリアに客演した他国の歌手なども出演した。RAI所属の三つのオーケストラが伴奏(ローマ、ミラノ、トリノの各放送響。ナポリの団体が出演した記録は未発見)、会場は上記ローマ、ミラノ、トリノに限らずイタリア各地で開催されたらしい。基本的に二人ないし三人の歌手が交代で単独にアリアや歌曲を歌う構成で、重唱などはなく、複数の歌手の共演が聴けない点ではやや残念。1954年にはサンレモでマリア・カラスとベニャミーノ・ジーリが出演しており、もし二重唱が実現していれば新旧世代の代表的歌手の歴史的共演となったかも知れない。
これらの放送録音は、1980年代後半から伊フォニト・チェトラからLP・CDとして散発的に発売され、1995年からはIncontri
Memorabili(思い出に残る出会い)というシリーズでまとめてCD発売された(総数は不明だが34枚までは確認されている)。RAIに保存されていた1951年から1961年までの録音で構成されており、当時のイタリア・オペラ界の代表的歌手から、当時は注目されたものの、今日では忘れられた知られざる名歌手まで様々な歌手の貴重な歌唱を楽しむことができる。
しかし、当ディスクの演奏は同シリーズに含まれておらず、この点は疑問が残る(少なくともLP・CD発売は確認できなかった)。フォニト・チェトラもRAIの音源すべてをCD化したわけではないだろうが、テバルディとバスティアニーニという大スターの録音を発売しないという理由はない。オリジナル音源提供者の情報によると、おそらくRAIが当ディスクの元テープを紛失したか行方不明になっているとのこと。その意味ではコピー・テープがコレクターも手元に保存されていたことは誠に幸いと言うべきだろう。
プログラムは、バスティアニーニについては得意の作品を並べたという印象。特に「オテロ」の「クレド」をこれほど朗々と見事に歌いきった例はまれだが、役柄を考えるとやや英雄的すぎる。一方「アンドレア・シェニエ」の「祖国の敵」はまさしくはまり役で空前絶後の名唱。「クレド」には意外に冷静(冷淡?)な拍手がある一方「祖国の敵」には大絶賛と聴衆も役柄をよく分かっている。これに対し、テバルディは、どちらかというとリリカルで定評ある作品を敢えて外し、ドラマチック寄りのレパートリーを選んでいるようだ。テバルディは声質が1950年代中期までのソプラノ・リリコ寄りからスピント(強く)的傾向が強まりつつあった時期であり、声質の変化に伴い新たなレパートリーを試みていたか、従来のような歌としての美感よりもドラマとしての迫真性を追求していたのだろう。
なお、
ジャケット写真についてひと言。1959年11月26日、ナポリ・サン・カルロ歌劇場におけるチレーア「アドリアーナ・ルクヴルール」のドレス・リハーサル終了後の光景である。左からテバルディ、シミオナート、バスティアニーニ、コレッリという超豪華な出演者たちが揃っており、まさしくイタリア・オペラ黄金時代を象徴する写真。ちなみにこの4人を除いても、カラス、バルビエーリ、ゴッビ、デル・モナコ(またはディ・ステーファノ)の4人を揃えれば全く同レベルの豪華メンバーを揃えた公演ができるほど、当時のイタリア・オペラ界は伝説的な名歌手がひしめいていた。
ちなみに、実は写真のキャストによる公演は実現しなかった。リハーサル直後にテバルディが喉の不調を訴えて降板(写真に写っている犬が原因か?)、急遽、病気退院直後のマグダ・オリヴェロが呼び出され、28日の公演を行ったという。オリヴェロは正規のレコーディングは少ないものの、テバルディに勝るとも劣らない大歌手。特に「アドリアーナ・ルクヴルール」は当たり役であり、同公演のライブ録音は後にLP・CD化され、伝説的名演として評価されている。
いずれにしても、テバルディとバスティアニーニの知られざる録音が比較的良好な音質でディスク化された意義は大きい。
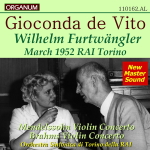
●良好新音源
ジョコンダ・デ・ヴィート、フルトヴェングラー/トリノRAI響 1952年ライブ
メンデルスゾーン、ブラームス ヴァイオリン協奏曲
オルガヌム110162AL
メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲ホ短調
ブラームス ヴァイオリン協奏曲ニ長調
ジョコンダ・デ・ヴィート(ヴァイオリン)
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー指揮トリノ・イタリア放送交響楽団
1952年3月11・7日、トリノ音楽院ホール
モノラル ライブ
※名女流ジョコンダ・デ・ヴィートとフルトヴェングラーによるメンデルスゾーンとブラームスのヴァイオリン協奏曲。このほど新たにコンタクトのとれたイタリア人コレクターからの提供音源。詳しくは後述するが、新たにオリジナル・ディスクから復刻された音源が提供されているようだ。
オリジナルの音源は、イタリア放送協会(RAI)による聴衆を入れて行われたラジオ放送のための録音で、独テレフンケン製テープ・レコーダーで収録されており、放送に使用するためにマイク・セッティングもそれなりに考慮されたと思われ、音質は優秀とは言えないものの、それほど悪くはなかったと想像される。しかし、放送終了後、当時は高価だった録音テープを他番組に再利用するため、音源の消去前に「パデローニ」と称する16インチ33・1/3回転のアセテート盤にダビングされ、今日まで保存されてきた。
パデローニ(Padelloni=フライパン、鍋、皿という意味)は、RAIがイタリア国内の電機メーカーと協力の上1940年代に開発したアセテート・ディスク・レコーダーで、センター・スタートで連続15分程度の録音が可能だった。テープ・レコーダー導入以前、15分以上録音する場合は2台のディスク・レコーダーで2分間ほど重複して録音し、放送する際には1000分の1秒単位で連結ポイントを探り出して連続再生したという。テープ・レコーダーの本格導入後は、当演奏のようにテープ音源のバックアップや保存のために活用され、1950年代末まで稼働していた。
問題はパデローニの性能の低さにあり、高域の周波数上限は6000Hz程度で78回転SP盤以下のナローレンジ。また周波数バランスの凸凹による歪みが多く聴きづらい。また、アセテート盤に共通する欠点として、盤表面のアセテート素材が脆弱なため経年劣化に弱く、再生を繰り返すとスクラッチ・ノイズが急速に増え、再生不能となるなどの問題もあった。
このような状態のパデローニからの復刻であるため、当演奏についても、1972年発売のカナダ・ロココ・レーベルによる初発LP以来、音質の悪さには「定評」があった。その後も様々なレーベルから音質改善を謳ったLP・CDが発売されたが、いずれも根本的に音質改善できた盤は存在せず、従来の評論が音質の悪さのみに終始し、演奏に言及されることがほとんどなかった。
一方、今回発売の盤は、近年パデローニから新たに復刻された音源と思われ、既出盤に比べて歪みが大幅に低減され、ノイズも皆無ではないが大幅に低減、そのままの状態でもかろうじて鑑賞に堪える水準となった。おそらくアセテート盤面を丹念にクリーニングした上、異なる形状の数種類の再生用スタイラス(針)を試し、最も音溝に適したスタイラスとイコライザー・カーブを使用して再生・ダビングしたと想像される。
とは言うものの、規格上の限界による周波数レンジの狭さ、大幅に改善されたとはいえ周波数バランスの悪さ、独奏ヴァイオリンの歪みやヒステリックな響き、不明瞭で鈍い音色のオーケストラなど、改善を要する箇所は多々あった。メンデルスゾーンとブラームスを比較すると、メンデルスゾーンはヴァイオリンの歪みが多い一方、オーケストラはナローレンジながら無難な状態。一方ブラームスはヴァイオリンは多少ましな状態を保っている一方、オーケストラは音量も小さく不明瞭だった。
発売に当たっては、スクラッチ・ノイズの低減と共に、ソフトウェアによって周波数レンジを拡大、3000Hz辺りが突出する一方、4000Hz以上が急激に低下している周波数バランスを改善(これによりヴァイオリンの歪みが解消)、オーケストラについては部分的にイコライジングを施すなど、明瞭化とボリュームの改善を行った結果、ようやく音質に不満を感じることなく音楽を鑑賞できる状態とすることができた。音響条件の悪い会場だが高域を補うことで響きも若干豊かになり、独奏ヴァイオリンをクローズ・アップし、オーケストラを背景に配した古い録音スタイルながら、オーケストラの迫力も十分に感じられ、それにより演奏の善し悪しを判断できるレベルとなった。
当演奏は以前から、ジョコンダ・デ・ヴィート(イタリア語の実際の発音では「ヴィトウ」に近い)とフルトヴェングラーという二大巨匠の共演という点で注目された演奏だったが、録音の劣悪さとオーケストラの質の低さ?から、不当に低い評価がされていたと言える。今回、音質改善された当ディスクを聴くと、両者の相乗効果を強く感じる。特にジョコンダ・デ・ヴィートにはメンデルスゾーン、ブラームスそれぞれに別録音が存在するが、集中力の高さやクライマックス部分の高揚感などは「フルトヴェングラー効果」が出ているようだ。また質が低いと評価されてきたトリノ・イタリア放送響だが、音質が改善されたことで、技術的にウィーン・フィルやベルリン・フィルには当然及ばないものの、フルトヴェングラーの意図を十全に表現しており、大きな不満を感じることはない。全体として名演奏だったことが理解できる。デ・ヴィートの演奏としては、既出のスタジオ/ライブ録音と比べて伴奏指揮が充実しているという点では特筆すべき演奏と言える。
7日は、ブラームスのヴァイオリン協奏曲と交響曲第1番というシンプルなプログラムで、放送を前提としたらしい構成。11日はシューベルト「ロザムンデ」序曲と「未完成」、メンデルスゾーンの協奏曲、ワーグナー「トリスタンとイゾルデ」から「前奏曲と愛の死」という、多少演奏会らしいプログラミング。
ジョコンダ・デ・ヴィートは録音当時45歳。演奏技術・楽曲への理解面ではまさに円熟期。メンデルスゾーンの協奏曲は前年1951年に英HMVにスタジオ録音済み、ブラームスの協奏曲は1941年に独ポリドールに録音していたが、さらに翌1953年英HMVに再録音が予定されているなど得意のレパートリー。1951年には英EMIの役員・プロデューサーであるデイヴィッド・ピックネルと結婚するなど公私ともに充実していた時期にあった。
フルトヴェングラーは録音当時66歳。死去の2年前だが、超多忙な演奏活動によって過労気味ながら、壮年期の演奏スタイルを維持していた最後の時期に当たる。1月はローマに滞在し、10・14・19日にローマ・イタリア放送響と一連のコンサートを指揮(「ワルキューレ」第1幕という大物もあった)。その後ウィーンに移動して23日には国立歌劇場で「ワルキューレ」(国立歌劇場自体は戦災で再建中。公演会場はアン・デア・ウィーン劇場)、26日から29日にかけてウィーン・フィルとのコンサート、30日には再び国立歌劇場でトリスタン。2月3日から5日かけてウィーン・フィルとベートーヴェン第9(3日の公演はオルガヌム110150ALで発売済み)、8~10日はベルリン・フィル創立70周年記念公演、ミラノに移動して、29日から3月4・6・9・12・16日はスカラ座で「マイスタージンガー」。その公演の間、3・7・11日に当ディスクに聴くトリノ・イタリア放送響を指揮している。
ちなみにフルトヴェングラーは1948年9月8日のエジンバラ音楽祭において、ローマ聖チェチーリア音楽院管を指揮、ベネデッティ=ミケランジェリ、デ・ヴィート、マイナルディという超強力なイタリア勢と共演してベートーヴェンの三重協奏曲を演奏(録音が残っていれば・・・・)。また、1953年11月16日には、バチカン市国で、ローマ教皇ピウス12世による「芸術家のためのミサ」に際して、フルトヴェングラー(ピアノ伴奏)とデ・ヴィートがブラームスのヴァイオリン・ソナタ第1番を演奏。10日後の26日にもローマ近郊カステル・ガンドルフォにおいて、ローマ教皇ピウス12世のために同じくブラームスのヴァイオリン・ソナタ第1番を演奏している。
フルトヴェングラーとデ・ヴィートは共に英HMVの専属アーティストであり、当演奏を聴く限りでは相性も悪くなかったように想像でき、両者が共演したスタジオ録音を残さなかったことは意外に思える。当時のHMVは、同じくEMI傘下の英コロンビアも含めて、契約アーティストの数が膨大であったためか、本来行われるべきだったレコーディングの多くを録り逃がしたきらいがあり、一方で、今日では(当時でも)蛇足と思えるレコーディングを行っている。逆にライバルで新興の英デッカはEMIより少ない契約アーティストを有効に活用、また優秀な録音技術を駆使して名録音・名盤を多く作り出した。英デッカに比べてLP発売やステレオ録音導入の遅れなど、新時代・新技術への対応について、名門・老舗ゆえの保守性・迷走があったのかも知れない。その意味で、音質が大幅に改善された当ディスクの価値は大きいと言える。
ジョコンダ・デ・ヴィートは、上記のように当ディスク以外にメンデルスゾーンの協奏曲を1951年英HMVにスタジオ録音したほか、1957年と1961年にライブ録音していた。また、ブラームスの協奏曲を1941年独ポリドール、1953年英HMVにスタジオ録音したほか、1951年と1956年にライブ録音していた。一方、フルトヴェングラーは、当ディスク以外にメンデルスゾーンの協奏曲を1952年英HMVにイェフディ・メニューインとスタジオ録音したほか、ブラームスの協奏曲を1949年同じく英HMVにイェフディ・メニューインとスタジオ録音していた。