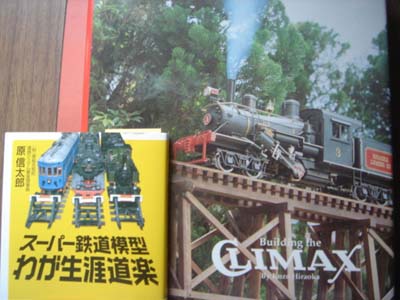MORI Hiroshi's Floating Factory
Model Railroad Workshop
<機関車製作部>
スペシャルな5月

/☆Go Back☆/
5月になっても雨が少なく、天気は良いけれど、そんなに暑くはない、という素晴らしい日が多かったようです。いつも5月になると蚊がいるので、それなりの防御をしないと駄目なのですが、今年はまだいません。池のメダカやカエルのおかげでしょうか。
5/12に、スペシャル・オープンディが開催されました。第4回です。天気も今までで一番。もの凄く楽しい一日でした。今回のレポートはほとんどこの話題です。
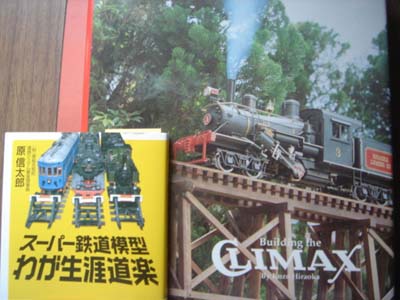
なんと、そのオープンディに平岡幸三氏がいらっしゃいました。そのときにいただいた本が、上の写真の右。クライマクスの作り方です。ギアまで自作する、という究極の工作本です。それから、左にあるのは、昨年、大阪のJAMコンベンションでお会いした原信太郎氏が出版された本です。模型人生を語った内容です。
下のバナーの欠伸軽便鉄道の広報部から、「掲示板」と「広報部ブログ」へリンクしています。「掲示板」の方は、地道な日々の活動を写真でつづる欠伸軽便鉄道社長のブログ。ほぼ毎日、数枚の写真をアップしています。一般の投稿もできますので、ご活用下さい。また、「広報部ブログ」は文字どおり広報部長のブログです。このところ、忙しいようですが、忘れた頃にこっそり更新されているかもしれません。それから、一般向けの日記「MORI LOG ACADEMY」もよろしく……。

<爽やかな季節>


とにかく、爽やかです。日向は暑いけれど、木陰はまだ涼しい。ちょうど良い季節。庭園鉄道をしないで、何をするのか、という日が続いています。写真は、AB10の列車ですが、運転していると、自分の前に客車が走るので、風景が実際に客車の窓から覗いているときみたいで面白いのです。
実は、線路が通り抜けている森の樹木を、5月中旬、庭師さんに剪定してもらったので、ずいぶん明るくなりました。木漏れ日の下を走るのがとても綺麗です。


こちらは、工事車両です。レールバスとクレーン・ワゴン。ラジコンでコントロールします。ときどき走らせて、眺めるための車両。写真を撮ると、緑に映えます。


西庭園は草花でいっぱい。ポーチ横のカーブには、緑が茂って、ときどき剪定しないと車両が通れなくなります。
その反対側には、ガレージ駅のヤードがあります。レールバスが待機しているところが、小さなターンテーブルがある場所。現在、ここに本格的なターンテーブルを建設する計画を進めています。次回か次々回にご報告できるでしょう。

この辺りは、芝が伸びると線路が見えなくなります。ナローらしくて良い雰囲気なので、そのままにしていますが……。
<コッペル試運転4>


3月末に完成後、4月に3回試運転を行いましたが、そのたびに不具合があり、まだまともに走っていません。今回が4回めのチャレンジです。まず、今まで使用してきたOSのブロアファンを使うのをやめて、コンプレッサを使ったブロアを試作しました。といっても、真鍮板を丸めて、少しテーパをつけ、そこに穴を開けて、パイプをハンダ付けしただけの簡単なものです。当鉄道は、駅にコンセントもコンプレッサもありますので、こちらの方がシステムとして簡単です。結果は良好で、ブロアの力もファンよりは強力でした。
というわけで、コッペルは走りだしました。今回の問題点は、停車中に、ブロアだけで火力が保てないことでした。走っていれば問題ないのですが。

この機関車のボイラとエンジンは、8号機のサファイアと同じMAXITRAK製です。サファイアの方が、ブロアがとてもよく効き、逆にドラフトだけでは火力が足らなくなります(走っているときもブロアを少し吹かす必要がある)。まったく症状が逆ですね。両者の煙室内のノズル位置などを比較して、改良したいと思います。しかし、少しずつまともに走るようにはなっていますね。
<小さい機関車>


アキュクラフトの入門機、エドリグです。オープンキャブの可愛らしい機関車。ガス炊きです。圧力計もちゃんとあります。アウトサイドフレームで、ゲージは45mmと32mmに対応します。コックさんの運転手が乗っていますが、走らせるときは降ろさないと、熱で溶けてしまうでしょう。
緑のタンクは、以前からある古い機関車。アルコール炊きで、快調に走ります。もともとは、星野氏がイギリスで購入されたものです。壊れないうちに引退させて、飾っておいた方が良いかもしれませんね。


アスターのシェイは、ユニバーサルを直してからは快調です。ただ、あまり長くは走りません。力も弱そうです。これも、そうとうに年代物です。
最後の機関車は、ブリキ製ですが、とても大きく、なんと3.5インチゲージです。ただ、89mmの3線式で走らせるもので、線路に電流を流して、集電をします。モータはテンダにあったようです(エンジン部だけ中古で入手)。カツミで扱っていたクマタの製品らしく、子供を機関車に乗せて、親がパワーパックでコントロールして走らせる、という遊び方をしたものだとか。
<他社からのレポート>


群馬県高崎市にお住まいのMatthew Foster氏のTakasaki Light Railwayです。16mmスケール(32mmゲージ)の庭園鉄道です。メールをいただいたとき、「あれ? どこかで見たな」と思ったのですが、Garden RAILWAYS誌に写真が載っていましたね(最後のページです)。それによると、1920年代の日本をモデルにした軽便鉄道、とのこと。人形が、確かに全部日本人です。可愛い機関車が活躍しています。


栃木のバンダイ・ミュージアムのレイアウトを走っている列車、先頭のガソ1。沼尻鉄道で走っていた車両です。これは晩年「磐梯急行」になったことから「バンダイ」を引っ掛けて作ったものだそうです。写真は星野氏からいただきました。
もう1枚は星野氏の新作の電機。ちょっとゲテモノですね。駆動部は床下にあって、タミヤのギアボックスと乾電池です。ゲージは89mm。以前に作られた貨車を再利用されたものです。人を引っ張ることもできるとか。荷台にいろいろ載っているのは、スリップしないためのウェイトですね。
<スペシャル・オープンディ>

5/12に第4回スペシャル・オープンディが開催されました。関東、中部、関西、中国地方から、約20名のモデラが我が欠伸鉄道弁天ヶ丘線に集結。毎度のことですが、刺激の多い、楽しい一日となりました。
天気は、過去3回と比べても一番。暑くもなく寒くもない、庭園鉄道にうってつけの日。森の中を、レールバイクで快走されているのは、井上昭雄氏です。昨年末、脳梗塞で入院されたのですが、あっという間に回復され、以前と変わらないお元気なご様子が拝見できました。
このレールバイク、運転させてもらいましたが、大変乗り心地が良いのです。安定しています。ステアリングも少しだけ切れます。カーブに合わせてステアリングを切ると、走行抵抗が少なくなるのが体感できるのです。年代物のヘッドライトが付いていました。


ポーチは賑やかです。青い小さな機関車を運転しているのは、星野氏。この機関車もタミヤのギアと乾電池で動いているもの。今回初参加されたのは、ギアードロコの製作本で世界的に有名な平岡幸三氏(写真で機関車に指をさしている方)。それから、NHK教育テレビに出演されていたイラストレータの諸星昭弘氏(写真左下の白い帽子の方)です。
2枚めの写真は、32mmゲージのスチームトラムを走らせる井上氏の話に聞き入る皆さん。エンドレス線もいつもなにかが走っている、という盛況。


前回のときは、未塗装でしたし、コンプレッサでの運転でしたが、関根氏のシェイが、ほぼ完成の域。今回は、石炭でスチームアップし、快調に走りました。まえにも書きましたが、この機関車はもともとは3.5インチなのですが、台車だけ5インチでもう1組作り、履き替えることができるのです。シェイならではですね。3気筒のエンジンは大変力強い感じです。本当は、この後ろにテンダが付いて、そこへもユニバーサル・ジョイントで回転を伝えてるようになります(つまり、3or4トラック)。


弁天ヶ丘線の最小カーブは(1箇所ですが)半径3mです。最初に確認をしましたが、このシェイはそのカーブをクリアしました。これも、ギアードロコ、面目躍如といったところでしょうか。
ガレージ駅のシェイの横に座っているのは、佐藤氏の愛犬エル君。そうです。弁天ヶ丘線史上、人間以外のゲストは、彼が初めてなのです。


犬のご紹介がさきになってしまいましたが、こちらがその佐藤氏のライオン号。大阪のJAMで展示されていた機関車。機関車もぴかぴかですが、黄色い客車も綺麗ですね。軸配置は、0-4-2ですが、従輪は横にスライドせず、つまりC型と同じです。これも、半径3mが大丈夫かな、と心配されましたが、なんとあっけなくクリアしました。おそらくモデルニクスの線路が少し幅広く作られているせいでは、と思います。


いつもは、シェイを持ってこられる木内氏ですが、今回はこのDLです。モデルニクスのユニットを使って、シャーシもボディも全部アルミで製作された機関車。後ろにトレーラがありますが、そのトレーラもアルミ製でした。
もう1枚は、井上氏の機関車です。ボイラがあって、2気筒の首振りエンジンで駆動するトラムです。ロボットが乗っています。それにしても、奇想天外な機関車ばかり作られますね。


バイキンマンが乗っているのは、杉浦氏の作。タミヤのチェーン駆動ユニットと乾電池で動きます。走ると、バイキンマンが忙しく動きます。下にあるモータは実はダミィで、本当はバイキンマンが動かしているらしいです。
AB20を運転しているのは佐藤氏。エル君が誇らしげな顔で乗っています。低床のトレーラを作った甲斐がありました。


AB20を運転する小池氏と諸星氏。いやあ、良い笑顔ですね。走行方向が逆になっていますが、弁天ヶ丘線はリバースがありますので、ときどきこのように、反対向きに走らせることができます。コースが2倍楽しめるのです。


45mmと32mmのデュアルゲージのエンドレス線には、古めかしい機関車がいつも集まります。Oゲージのライブスチームです。赤い機関車は、須藤氏が持ってこられたLMSミッドランド・コンパウンド。ハンダ付けで修理をしつつ、快調に走っていました。


こちらは、小池氏が製作中の回転レイアウト。洗面器の内側にレールが敷かれていて、電車が走行します(なんと、ラック式)。それに合わせて、風景がぐるぐる回転する、という、ありそうでなかったアイデアもの。
もう1つは諸星氏が製作中のレイアウト。もの凄い急カーブを機関車と貨車がぐるぐると走り回ります。人形も作られている途中で、素材は何でしょう。クレィみたいなものかな。完成したところが楽しみです。

血圧計のコンプレッサを搭載して、首振りエンジンを駆動して走る機関車。後ろにいるのが、井上氏のオリジナル。前を走るのが、我がA&Bの新作(前レポート参照)です。ときどき、追いつかれて、押されて走っていました。


なかなか見られないショットではないでしょうか。左から、井上氏、佐藤氏、平岡氏です。奥にいるのは、シェイの関根氏ですね。
本当に良いお天気でした。エル君はいつも佐藤氏と一緒です。


前回のレポートで動画をご覧に入れた佐藤氏が製作されたシェイのエンジン。コンプレッサで動かして、みんなで眺めているところ。左から横田氏、渡邊氏、井上氏。もの凄く低速で動くので、皆さんびっくりされていました。
駅長パスカルです。エル君とはお互いに意識し合って近づかず。

夕方、記念写真を撮って、お開きとなりました。事故もなく、楽しい一日でした。またの機会を楽しみに……、お疲れさまでした。
<シェイのボイラと台車>


スペシャル・オープンディのときに、これが来ました。シェイのT型ボイラです。イギリスに発注して製作されたものが、海を渡って届きました。それから、もう1枚は、木内氏が製作した、シェイのフレームと台車。フレームはアルミ製です。そうです、これに佐藤氏が製作したあのエンジンが載って……。さあ、完成はいつのことになるでしょうか。楽しみですね。
<ポイントマシン移設>


弁天ヶ丘線の車両限界のうち、足許のエリアを制限していたのは、このポイントマシンでした。これが線路の近くにあるため、たとえば、OSのトレーラに足を乗せていると、その足がぶつかることがあります。危険なので、車両の方を改造して、低い位置で横に出ないように工夫をしていました。しかし、オープンディなどで、他社の車両が入線すると、ここがいつも問題になります。
足をぶつけたり、足を乗せるペダルをぶつけたり、という事故が何度か発生していました。そこで、今回、思い切って、ポイントマシンの位置を離す改造を行うことになりました。
具体的には、ポイントマシンを据え付ける帯板を枕木に取り付け、リンケージロッドを延長するだけです。しかし、現場ではできませんので、ポイントごと、1機ずつ工作室へ運び入れて、改造しました。写真は、No.3とNo.2ポイントの改造後の様子です。No.3は延長するだけでしたが、No.2の方は樹の幹に当たるため反対側へポイントマシンを移動しました。


No.1とNo.5の改造後の写真です。プラスティックのカバーを被っていますが、これは雨避け。これまでは、使用するときにはカバーを外していましたが、離れたことで余裕ができたため、今後はカバーを付けたままで使用することになりました。
本線のポイントは全部で6機。今回、これらすべてを改造しました。

最後が、デッキ上のこのNo.6ポイントでした。ここも、ポイントマシンを反対側に移設。通路なので、引っかけないように、アルミのカバーも取り付けました。これで、もうマシンに足をぶつけることはなくなるでしょう。まだ、建物の角が迫っている部分があるので、車両限界が劇的に改善されたわけではありませんが、多少は安心して走れるようになったと思います。
<コッペル試運転5>


5/24に、コッペルの5回めの試運転をしました。今回は、煙室のブロアノズルを煙突に20mmほど近づけて臨みました。結果的にこれが功を奏し、停車中にブロアで火力がなんとか保持できるようになりました。走行も安定してきました。だんだん仕上がってきたようです。多少はゆとりをもって運転ができるようになりましたので、動画を撮影しました。
コッペルの走行中の動画がこちらとこちらにあります。
/☆Go Back☆/