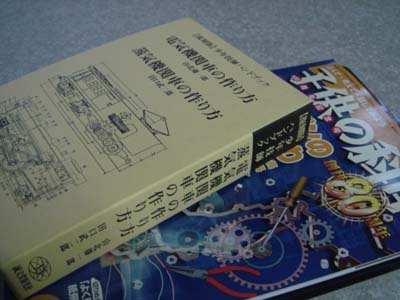MORI Hiroshi's Floating Factory
Model Railroad Workshop
<機関車製作部>
シーズン到来

/☆Go Back☆/
台風や地震がありました。幸い、弁天ヶ丘線に被害はありませんでした。台風に対する事前の対策としては、信号機をガレージ内に待避させたくらい。周囲が森林なので、風で樹木がもの凄く躍動します。近くの樹がウッドデッキに当たって、お互いに削れたりはしますが、その程度です。しかし、インターネットのための光ファイバが近所で切れました。やはり電柱の近くの樹が揺すって張られていたワイヤを切断したようです。1週間は駄目だろうと、古いモデムを出してきて電話回線でインターネットをする準備をしましたが、翌朝NTT西日本に電話をしたところ、その日の午後には復旧工事をしてくれました(といっても応急措置らしいですが)。なによりも驚いたのは、NTTに電話がつながったことです(しかもたった7回のコールで)。改善されていますね。かなり見直しました。
雨が続いていましたが、秋らしい晴天の週末も何度か訪れました。これだけは本当に神様からの授かりものでしょう(オーバな)。庭園鉄道にとって、お金や土地や時間よりももっと大切なのは、やる気と天気です。雨が降っているうちに、あれこれ思いついたことをメモしておき、晴れたらその作業を1つずつ片づけていきます。庭園鉄道以外にも、庭や家(特にガレージ)のメンテナンスもあって、忙しい日々です。
また、この時期は何故か、お客さんも多いのです。毎週末には、平均10人くらいは来客があります。もちろん、全員が鉄道を目当てにくるわけではないのですが(そういう人は珍しい)、ちょうど運行している日だと、やはり乗りたくなる、ということはあるわけで、一気に乗客が増えるシーズンです。新しい路線で、大量輸送を行っていますが、お客さんが多いと、どうしてももっと強力な機関車が欲しいな、と考えてしまいますね。自分一人だったら、そんなものはいらないのですが……。
10/16に誠文堂新光社の取材を受けました。「大人の工作読本」に記事が掲載されます。誠文堂といえば、「子供の科学」ですが、もう40年近く毎月購読している雑誌です。上の写真は、その取材の日の模様で、機関車がフル出動、そして駅長トーマも西庭園のまん中に……。
<フル稼働>


引き込み線に待機中の9号機Plymouthの貨物列車。4両のナベトロが揃っています。最後尾にオレンジのカブースが見えます。
引き込み線の横、舗装道路は、久しぶりに登場のミニクーパ。その向こうに眠そうな駅長、ずっと向こうのアーチ橋にはAB10の列車が……。天気が良く、とても暖かい午後です。


弁天ヶ丘線の主力機関車AB10は、今のところノートラブルです。こんなに長持ちするとは思いませんでした。芝は、短く刈ったあともまた緑の芽が伸びている感じです。
デキ3の小編成が手前を通過中。フリーで走らせて、カメラマン氏が流し撮りを幾度かされていました。


もう少し寒くなったら、落ち葉が一面を覆うでしょう。今はそれがないため比較的まだすっきりしています。洗い出しコンクリートで固めてしまった線路部分(踏切)もトラブルはありません。
同じ場所にいるようで、各列車が微妙に位置が変わっていますね。カメラマン氏が構図をいろいろ考えて、移動させているためです。

光も綺麗で、絶好の撮影日和になりました。自分で遊んでいるときには、こんなふうに2編成をメインラインに(しかも逆向き)置くことはまずないので、珍しいショットといえます。
<ガレージ駅オープン>


そろそろ蚊も少なくなってきました。ガレージのドアを完全に解放できる日も近そうです。この日はガレージ駅のヤードに列車を並べて、入れ替わりで走らせました。
2番線にデキ3、3番線には、グースとワークディーゼル。そして、2枚目の写真は、その奥のターンテーブル付近にいる単端。ちらっと後ろに見えていますが、錆びた焼却炉がここにあります。手前の青い変なものは、飛行機の鼻先というか、プロペラの中心にあるスピンナです(実機のもの)。


2番線のデキ3が出ていきました。3番線のワークディーゼルは、既にメインラインを何周もしたあとです。横にフォークリフトがいます。
グースも出動しました。どうも前部のキャビンが右へ傾いていることに気づきました。この日は、このまま撮影してもらいましたが、夜になって補修をしました。原因は、キャビン内の電池ボックスが外れていたため、重量バランスが崩れたせいでした。強度不足のため、よく修理をしている車両です。実は、窓ガラスのスモークが濃すぎて、「族」っぽい感じになっているので、もっとクリアにしようと常々考えるのですが、なかなかできません。
<大人の工作読本取材>


「大人の工作読本」の取材中の模様です(といっても、いつもどおりの光景ですが)。弁天ヶ丘線広報部長のN倉氏が撮影した写真なので、珍しく社長が運転中のところが写っています。ワークディーゼルを運転していますが、実はこのとき、N倉氏は同じメインラインでワークディーゼルを追って、AB10の列車を運転中だったのです。運転しながら写真を撮れるようになったらもう免許皆伝ですね。
もう1枚は、森の中。カメラマン氏の要望で、ポイント操作を無線でしているところ。それを後方から撮影しています。もう一人は、誠文堂新光社の編集の方です。


こちらもN倉氏撮影。芝はまた少し緑になった感じです。AB10がリバース線を通って西庭園に入ってきたところ。森が暗くて、手前が明るくて良いコントラスト。
もう一枚は、AB10の列車に乗って西庭園駅を発車する社長。近頃は、この低床貨車に乗車する機会が多いです。客車よりも乗り心地が良い、との指摘もあって、お客様にこちらに乗ってもらうこともしばしばです。
<子供の科学>
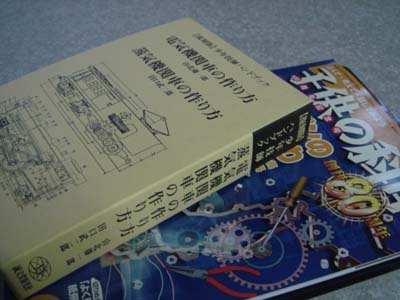
「大人の工作読本」の取材は4時間で無事に終了。そのときに、お土産にもらったのが、この復刻版の「電気機関車の作り方」「蒸気機関車の作り方」です。買おうと思っていたのですが、書店でなかなか見かけず、持っていなかったものです。ですから大喜びです。「子供の科学」も80周年なんですよね。80周年って、かなり凄いですよ。そんな雑誌、他にどれくらいあるでしょう?
「製作記事とかいかがですか?」と言われたのですが、製作記事を書くほど、立派な製作をしていませんからね、しかし、それ以外だったら、「子供の科学だったら、ノーギャラで書きますよ」とアピールしておきました(笑)。
<駅長視察>


翌日の日曜日も晴天。この日は、プライベートで運行を楽しみました。駅長も何度も試乗されました。写真は、ポーチの付近で、試乗後の駅長の様子。もともと、彼が乗りやすいように低床貨車を作ったようなものです。オレンジ色の工具箱、蓋が開いていていろいろ入っているのが見えます。だいたい、CRC(潤滑油、線路に吹き付けるため)とハサミ(雑草や邪魔な樹の枝を切るため)が常備必需品で、その他、携帯蚊取り、ペンチ、ドライバ、それから、ポイント切り換え送信機などが入っています。運転手はこれくらいのものを持って乗るわけです。
それから、西庭園駅の渡り橋は、このように脚を取り付けられました。約1時間の日曜大工でした。わりと頑丈に作りましたので、上に人が乗ることもできます。もう、ほとんど頭を下げずにくぐり抜けることができるようになりましたし、重いので先日の台風でも動きませんでした。柱や筋交いは、後日、焦茶色にペンキが塗られました。
<8両編成>


次の週末も晴れました。plymouthの貨物列車を運行。バックでガレージから出て、駅で待機中です。機関車、運材車(運転手乗用)、ナベトロ×4両、タンク車、カブースの8両編成です。過去最大かもしれません。運材車を2両と数えると9両編成です。短い9両編成ですね。
これで本線を何周か走りましたが、けっこう走行音が煩いです。一番音が大きいのは、北のウッドデッキの上を走っているとき、次が、南庭園の石畳区間です。ご近所の迷惑にならないように、なるべくゆっくりと走らなくてはなりません。
<Onのギアードロコ>


バックマンのOn30のクライマクスがついに発売になりました。それも2万円ちょっとという破格です。一昨年にシェイが3万円で発売になったときほどの感動ではありませんけれど、でも、品質も凄いし、相変わらずコストパフォーマンスは抜群の商品といえるでしょう。クライマクスというのは、写真のように斜めになったシリンダが両側にあって、それを車体中央を貫くプロペラシャフトで、前後のボギィ台車へギアで伝達する形式です(シリンダは、別のタイプもありますが)。バックマンは、これとほぼ同じクライマクスをGゲージでも出しています。
もう一枚の金色の機関車は、シェイです。こちらはOnなので、線路は19mm。重心が低くて格好が大好きなミシガン・カリフォルニア#2ですが、未塗装の工芸品(国産です)。


シェイは、車体の片側にシャフトを通して、ギアで台車へ動力を伝達します。メカニカルな部分は片方に集中しているため、こちら側の写真が多いですが、反対側は2枚目の写真のようにすっきりしています。左右がここまで非対称の機関車は、他にないでしょう。
鉄道模型の特に蒸気機関車では、このように真鍮(ブラス)製の未塗装(ニスは塗ってある)のものが、わりと流通しているのです。黒く塗らないで、金色のまま飾っておくコレクタが多い、ということですね。ちなみに、これくらいの機関車になると、名のあるペインタに塗装を依頼する、なんていうこともあります。
<Onレイアウトその後>


前回のレポートで探していたOスケールのストラクチャ・キットが見つかって、それを組み始めています。レジン製のもので、給水タンクを載せた小屋です。壁や屋根はレジンなので簡単ですが、その他は角材を切って組み立てないといけません。レイアウトに置いてみましたが、真っ白なのでまったく様になりませんね。ちなみに、2枚目の写真で黄色のワゴンの連結器が見えますが、これがこのレイアウトで採用した簡易フックです。カーブが急なので、これが一番確実です。
やっぱり、Oスケールは大きいなあ、と思います。レイアウト作りに関してはHOでもそれほど変わらない気がします(Nは小さすぎる)が、やはり一番の違いは、車両が走るときの様子です。ナローですから小さい車両が多いのですが、HOではこそこそと揺れながら走ります。それが、Oになると実にゆっくりスムースに動くわけです。やっぱり重さと大きさ、つまりは固有周期の差ですね。これがGスケールになるとさらに顕著になりますし、5インチになるともう本物に近い走りっぷりになるわけです。
<墜落?>


ガレージの2階です。書斎の前に飛行機が墜落したみたいになっています。面白いので写真を撮りました。実は、配置換えをするのと、天窓の修理をするため、飛行機を待避させています。4分の1スケールのタイガーモスが行き場所がなくて、ここで逆立ちしています。
今年は、昨年よりは飛行機を飛ばしていて、既に6,7回飛行場へ行きました。来年からは飛行機製作部の活動が活発になる予定です。鉄道の方は、たまたま庭園鉄道という珍しい分野だったので、HPで公開したり本を出したりしてきましたが、飛行機の方はスケール機が主体だし、キットを組み立てることが多いし、オリジナリティがない点が、HPや本にならない所以でしょうか。なにか自分だけの特徴を出した飛行機作りをいずれは目指したいところ。たとえば、庭園飛行場とか(引っ越すことが前提ですが)、あるいは、スチーム・プレーンとかですね(今のところ蒸気エンジンで飛ぶラジコン飛行機は見たことがないです)。
<他社からのおたより>


星野氏からのレポートです。千葉の石川邸のレイアウトの運転会の様子。近所の幼稚園の園児を招待したそうです。長閑な風景です。最近の子供は、やっぱり煙が出ない機関車や新幹線の方が喜ぶみたいですが、おじさんたちの方がずっと楽しんでいる、という姿を見てもらうことに価値があることでしょう。


岡山の稲木軽便鉄道(仮称)から可愛らしい赤い機関車の写真が届きました。モデルニクスのセットを使って自作されたものらしいですが、ナローらしい愛嬌のあるプロポーションで、「おお、これは同類だ」と感じました。貨車の方は乗用トレーラにもなるようですが、多少乗りにくいとのこと。ペットボトルは猫よけでしょうか? 投稿どうもありがとうございました。
<Gパイクのその後>

Gゲージャ(なんていう用語はあまり使いませんが)の方々から、以前の急カーブのパイクはその後どうなったのか、というお問い合わせメールをいただいています。このとおり、どうもなっておりません。基本的にこれは組み立て式レイアウトなので、固定してシーナリィを付けてしまうと、面白みが半減するような気もしますし、また、このように機関車を載せるとわかりますが、レイアウトの敷地全域が、ほとんど車両限界に入ってしまうため、シーナリィもストラクチャも作るスペースがない、というのが正直なところ。引き込み線に機関車が待機していようものなら、もう本線が通れない、みたいな事態になるのです。もう少し考えましょう。
<レトロOゲージ>


イギリスの古いおもちゃです。もちろん、いずれもStar Field経由で入荷したもの。赤い方はゼンマイのDuke of York。テンダに書かれているとおり、1931年のバセット・ローク製。
もう1つは、Oゲージにしては大きすぎるくらい立派なライブスチームのボーマン製4-4-0。大きい分、ナローみたいに車輪が内側に入っています。アルコール炊きで、ボイラ下面が少し焦げています。これが新製品だった当時には、光り輝く憧れのモデルだったことでしょう。
<コーナの鏡>


気候が良いので、ちょっとした時間を見つけて運行しています。本線を数周回ったら、車庫に戻る、という短時間運転も多いです。いつでもすぐに動き、すぐに片づけられるのが、電気機関車の利点。庭園鉄道の基本かもしれません。
北デッキの西コーナが、見通しが悪く、AB10の列車のように、運転手が後ろの方にいるときは、先頭のことが少々不安です。このため、ミラーを設置しました。たまたまガレージに1つミラーが余っていたからです。
<雨の夜のエンドレス>


今夜は大雨です。ガレージの中で、久しぶりに半径1mのエンドレスでビッグワークを運転しました。この機関車、そろそろ解体して、本線用の主力機関車に作り替えたいと考えていますが、そう言いながらかれこれ1年半ほど、ずっとこの状態。それくらい、こんな小さなエンドレスでも乗っていると面白い、という証拠かと……。
/☆Go Back☆/