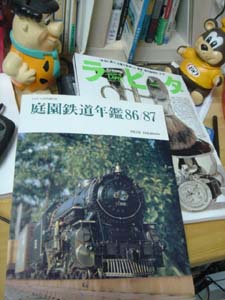MORI Hiroshi's Floating Factory
Model Railroad Workshop
<機関車製作部>
庭園大工事 part8

/☆Go Back☆/
6月はその後も晴天続き。台風の日以外は毎日が爽やかな青空でした。庭園工事の終盤も雨で中断することなく順調に進みました。そして、なんとか一応の完成に、といえると良かったのですが、実はまだ完成していません。もう一歩です。それにしても、昨年のガレージ建設といい今年の庭園工事といい、どちらも毎日毎日職人さんが来て、スバル氏は好きなときに出かけられず、不自由をしたようです。バネが充分に縮んだ状態ですから、もうすぐ凄い勢いで飛び出していくことでしょう。こうして、いろいろな人に助けられて、ものは作られるということですね。
実は今のところへ引っ越して以来、夏が涼しいのです。「今年の夏は涼しいよね」というのが口癖になっていたのですが、どうも世間はそうでもない。ようするに、この場所の朝夕が涼しい、ということのようです。そういえば、冬は雪が沢山積もるし……。最寄りの駅まで歩いて10分(下りの場合。帰りは上りで20分)なのですが、そことの高低差は100m近くあるのです。けっこうな坂道だから、鉄道だったらラック式にしないと上れないかも。朝は夏でもTシャツでは寒いと感じるくらいです。夜にクーラを使うことはまずありません。これでも市内か、という感じです。
さて、毎年、弁天ヶ丘線が夏期休業する主たる理由は暑さではなく、蚊です。刺されないように虫ペールをすれば良いのですが、ガレージを線路が通り抜けているため、ドアが開けたままになりますから、ガレージ中に蚊が入り、夜の書斎活動に支障をきたします。そこで、今回の線路工事では、この点を考慮して、ガレージのドアをすべて閉じた状態でも、エンドレスを回れるように改善しました。さらに、夏の運転に備えて、各種の防虫殺虫グッズを試すべく、ネット販売で取り寄せて、ただ今試験中です。夜間運転を、夏の風物詩にしたいものです。
上の写真。庭園に照明が灯りました。最初、庭師さんが設定したライトが明るすぎて、半分のワットにしてもらいましたが、それくらい、この近辺は暗くなります。星空が綺麗です。家の中も暗くて、そもそも暗いところが好きなのです(笑)。そして、ついに、ポイント転轍機にもライトを入れて点灯させました。毎日、暗くなると自動的に灯るように設定してあります。とっても良い雰囲気です。
<緑あおあお>


清々しい季節です。このまま固着したいくらいですね。葉は生い茂り、深い緑はとても綺麗。工事のため、長く殺風景だった南庭園ですが、ようやく生き生きとしてきました。先日の台風で、植えたばかりの樹が数本倒れましたが、すぐに起こして復旧。ちなみに、上空に見える電線、これ光ファイバなのです。これを通って、このHPがアップされているのです。切れなくて良かったですね。
ウッドチップを敷いた中州(というのかな)の部分にも、小さな植物がぽつんぽつんと植えられています。庭師さんによると、半年か1年もすれば、地面は見えなくなるくらい緑で覆われる、との予測。根をつけるために、少しずつ植えているようでした。

一方の西庭園は、まだこんな状態で、工事中です。森の中を抜ける線路は、現在取り外されています(手前に積んでありますね)。でも、緑は勢いを増していて、木陰が涼しそう(実際涼しいです)。

その木陰の端に井戸があります。井戸の横に立っている短い柱は、ポンプの電気配線のためのもの。ずっと奥にアーチ橋が見えます。手前の線路はレンガにのって浮いていますが、もちろん土を入れて高さを合わせ、バラストを敷き直します。
<小径と小川>


石屋さんは結局3日間かけて石を貼りました。線路と交わる部分は、写真のように道の方が切れています。今は線路が浮いていますが、ここも土とバラストを入れる予定。小径の両側は芝になる予定です。古い小さな焼却炉が立っていますが、これはどこへ置こうかな、と検討中。
洗い出しの小径と、同じく洗い出しの小川がクロスする地点の処理。小径の方が沈み込んでいます。石貼りの小径と洗い出しの小径が交わるところは、縁が切られています。それ以外の土の部分はすべて芝になります。

こちらは、石貼りの小径と洗い出しの小川がクロスする地点。同じように、小径が沈み込んでいますね。白い石を踏んで小川を渡ります。あとは緑を植えるだけになりました。この近くにも1本大きな樹を植えるので、木陰になるでしょう。
<ついに全貌が!>


大工さんが来て、構造物の上屋が取り付けられました。意外なものでなくてすみません(笑)。これは何だ? ときかれれば、答は「駅」です。この中を線路が通り、プラットホームになるわけです。「駅には見えないぞ」という方も多いと思いますが、もちろん、そのあたりが、スケール・マニアではない所以です。「兼ね合い」というか、「バランス」のデザインですね。微妙なところです。
将来は蔦などが茂ると良いなあ、と考えています。
<小山へ上る道>


本物の(と書かないといけないのが面倒ですが)枕木が到着しました。庭師さんがチェーンソーで切って、階段を作っています。小径が小山にぶつかる部分の処理。予想どおりだったと思います。左には線路があります。これは、どうなるのでしょう?
もうわかりましたね、そうです、トンネルになります。枕木を並べて土留めをして、上にも枕木を被せました。2枚目の写真も未完成の状態のときで、入口付近の樹を避けてのぎりぎりの処理です。
<庭園の夕べ>


電気屋さんが来て、照明が灯るようになりました。レンガサークルの中心は40Wの一番明るいライトです。これで、玄関ポーチはとても明るくなりました。一番喜んだのは、夜に配達にくる宅配便の人でしょう。
2枚目は、南庭園の東側。トロリィ路線が走る際です。もうすっかり緑が定着して、落ち着いた風情になりました。ここは20Wにしました。いずれもクリアの電球です。


これが南庭園へ移動したポイント転轍機の表示灯。オレンジとブルーのライトが光ります。すぐ奥には、石畳をカーブで通過する路線が見えます。また、ずっと遠くに小さく光っているのが、上の1枚目の写真にあるレンガサークルのライトです。


「ポイント転轍機」という言葉は、本来は分岐ポイント自体をいう言葉のようですね。最近、坂本衛氏の「鉄道施設がわかる本 」を読んで知りました。だから、転轍機のレバーといわないといけないのですね。これは北海道のJRで使われていたもので、根本が円錐になっている格好良いやつです。たしか、オークションで5万円でした。ダルマ転轍機の5倍です。
上で点灯していたライトは、2枚目の写真のように、丸太にのっています。この丸太は古い電信柱だとか。枕木もそうですが、防虫剤が染み込み、とても硬そうです。
<備品整備>


ガレージの中や、庭で工作をするとき、あるいはライブスチームの後片づけなどで、この掃除機が大活躍します。先日、中に溜まったゴミを出しました。購入して1年以上になりますが、溜め込んでいまして、今回が2回目でした。パワーも充分で性能的には満足していますが、ホームセンタで購入した安物のため、ちょっと重心が高い(そういう妥協の設計だと思われます)のが欠点。引っ張ると、ときどき引っかかって転びます。掃除機は工作室でも頻繁に使うので、あっちへいったりこっちへいったりの引っ張りだこ。もう1つ小さいものを購入しようかと考えているところ。
ダルマ転轍機ですが、白いところのペンキがほとんど剥げていたので、刷毛で塗り直しました。この写真はガレージの前に仮置きしてあるとき。庭師さんと相談して、木陰に設置することになりました。クレーンが来たときに動かします(後述)。
<機関車工場>


ガレージ内で待機中のカトー7ton。線路が不通のため、出番がありません。麦わら帽子を被っていました。なかなか似合います。すぐ左に、以前に作ったポイントマシンがあります(タミヤのギアボックスを使用したもの)。今は取り外されていて、使われていません。表示器だけは回転しますが。
前回登場したGゲージのディーゼル機関車。淡いグリーンに塗装されました。これからウェザリング(汚し)です。


亀の子はキャブの天井を修理中。下から覗くと、天井裏に白いボール紙が張って補強されているのがわかります。横に立っているのは、ミス・ペネロープ。ちょうどスケールが合っているのでは。工作室の棚にのっています。
ニイザキのコッペルですが、2回パーツ配布があって、その後はまだ来ません。発注から1年半になります。ゆっくりペースなのですね。こちらも合わせて、ゆっくりです。シリンダを仮組みしました。シリコンシーラントを使ってシリンダの蓋をするので、ホームセンタでいろいろ見て、耐熱温度が一番高いものを探したのですが、同じ商品でも白いものよりもグレィのものが50度も高かったりすることに気づきました。いつも白いのを使っていますが、今回はグレィでいきます。どうせ見えなくなりますが。
<他社からのおたより>


以前からメール交換をしている星野公男氏。ライブスチーム界ではとても有名なモデラです。1枚目の写真は3.5インチゲージのMollyという機関車で、いかにもイギリスらしいタンク。客車を牽引しているあたりがさすがですね。場所は、千葉の石川氏宅のレイアウトで、ここは「庭園鉄道年鑑86,87」にも載っていた個人庭園鉄道の草分け、でしょうか。
もう1枚は、森が「これが走っているところの写真を送って下さい」とお願いした5インチのトラム。ボギィの電車です。屋根を作ったら、子供しか乗れなくなりますが、取り外しにする手はあるかも。こちらのレイアウトは、足立区の北鹿浜交通公園というところだそうです。1周300mとか。やはりライブ人口が多いから、そういう施設も沢山あるのですね。


さて、その星野さんですが、メールが1週間くらい返ってこないので、「またイギリスへ行かれているのでは?」と思っていたら、そのとおりでした。トレビシックが蒸気機関車を走らせてから今年で200年目だそうで、いろいろ記念のイベントがあったようです。写真はトレビシックのペナダレン(Peny Darren)号のレプリカ。これが、蒸気機関車の第1号といわれています。たしか実物は、こういうちゃんとしたレールの上を走ったわけではなかったはず。蒸気の第1号ってスチーブンソンじゃないのか、と思った人多数でしょう。違うのです。これは、ヨークで開催されたイベント。あそこの鉄道博物館は、マニアは一度は行くべきところでしょう。
星野さんからは、ビデオも届きました。イベントの他に、イギリスの庭園鉄道の運転風景ばかり3時間延々という「濃さ」でした。星野さんの解説付きですから貴重ですね。大感謝。上の2枚目の写真は、ウェールズのBeddgelertという村だそうですが、「コンチネンタル・モデラ」か、「ブリティッシュ・レールウェイ」に出てきそうな、いかにもな風景(特にストラクチャが)。そうか、レンガのアーチ橋も、こんなふうに蔦を這わせる手があるな、と連想しました。
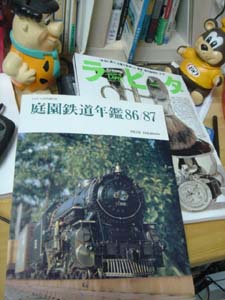

上で話題に挙がった「庭園鉄道年鑑86,87」ですが、今から20年近くもまえにプレス・アイゼンバーンが出版したもので、今でも購入できます。対談に、星野氏や技巧舎の社長さんも登場しています。出版としては、先見の明があったことは確かですが、早すぎたのか、このあとは出ていないようです。薄っぺらい(普通のTRAINの半分くらい)本ですが、5000円もしますので、ちょっと買いにくいとは思いますけれど、内容は他には例のない大変貴重なものだと思います。こういった本がまた出ると良いな、と期待。
川口市の木内さんからは、製作中のシェイの写真をお送りいただきました。これは5インチで、T型ボイラです。小型でナローで好みのタイプでしたのでご紹介します。これって、後部の水槽の上に運転者が乗れるんでしょうか? それから、T型ボイラっていうのは、小さくしてもちゃんとうまく働くものなのでしょうか。あと、どれくらいのカーブが曲がれるでしょう? 興味は尽きません。走るところが見たいし、それに、できたら自分でもいつか作ってみたい機関車です。
<アーチ橋開通!>

6月24日には線路が開通したのですが、仕事と天候のため、最初の走行試験は26日に行いました。問題なく通ることができました。実際に乗って走ると、相当スリルがあります。ゆっくりと通らないと恐いです。

ウッドデッキからアーチへ渡る部分は、写真のようにアングルで組んだフレームです。黒に塗装しました。幅は橋と同じ60cmですが、下が見えますから、余計に高さが感じられます。アーチ橋の上は、レンガに直接鉄板を敷いて、その上に線路がのっています。固定はしていません。


AB10も客車を率いてやってきました。ボギィの長い車両で走行テストです。貨車も沢山牽引しているので、走行音がとても楽しい。デッキの上、レンガ・アーチの上、鉄骨フレームの上と、音がまったく違います。
走行音は、枕木によって変わるとよく言われますが、枕木よりも、その枕木の下の構造が大きく影響するようです。たとえば、コンクリートの上なのか、土の上なのかでだいぶ違います。下が木造や鉄骨造の構造物だとさらに顕著です。よく話題になるのは、木の枕木と鉄の枕木における走行音の違いですが、これは下が固いコンクリートだと違いが出ますけれど、下が土でバラストだと、大して差はないように思えます。弁天ヶ丘線は、いろいろな路線があるので、その比較ができるわけです(木製枕木も実験をしました)。ただし、本線の場合、重量級の大型が通ることはないですから、一般的とはいえませんね。
アーチ橋の走行試験の結果は、まったく問題ありませんでした。新線の走り心地は、とても新鮮です(駄洒落か)。
<新高架線試験運転>


アーチ橋を越えると、レンガの橋脚が9本並ぶ高架線です。途中にトラス鉄橋もあります。ここは勾配もあって、けっこうデリケートな路線。何度も行き来をして、確かめました。
黒いフレームが、アングルを溶接して組んだフレームです。これは、レンガの柱に引っかかって、のっているだけで、固定はされていません。同様に、線路も固定されていません。トラス鉄橋も同様です。すべて置いてあるだけなのです。ちなみに、機関車の後ろのナベトロにのっている赤いものが、運転者用のシートです。これも置いてあるだけ。撮影のときに外すのを忘れました。


上から見るとこんなふう。下が透けて見えますからスリル満点です。カーブの部分の走行もだいたいOKでした。少しずつ高さが低くなっています。とりあえず、脱線が起こるような捻れはなく、また勾配も大丈夫そうな感じです。若干、勾配にばらつきがあるため、これはあとで(何かを線路の下に挟んで)微調整をすることになりました。
今回は、まだこの先が開通してないので、このあとは、機関車が貨車を押して、バックで勾配を上ってデッキへ戻る運転になりますが、まったく問題ありませんでした。とりあえず、人間が1人のときは、重量も勾配も大丈夫だということがわかりました。
笹は、ほとんど取り除かれました。冬がくれば地面はまた落ち葉で覆われるでしょう。
<工事は最終段階>


6月26日の夕方です。少し蒸し暑くなったでしょうか。ガレージ駅の前に、大きな樹が1本立ちました。スバル氏のミニクーパのすぐ左です。まだあと4本ほど、これくらいの大きさの樹を西庭園や玄関前に植える予定です。木陰が増えると夏は良いですね。
トンネルの手前の線路を組み立てました。本物の枕木を短く切って並べ、その上に線路をのせます。紅葉が2本とも残っていますので、以前の庭の雰囲気を残していますが、この小さい方の紅葉、実は庭を広くするために移動しています。


これが駅前に立った樹です。もしかして、ソヨゴっていうのかな。清水の舞台から飛び降りたつもりで書いてみましたが、自信はありません。駅周辺はまだ雑然としています。この近辺が最後にどんなふうになるか楽しみです。
南庭園の東端。トロリィ路線が抜けていくところです。植樹が終わり、もうほぼ完成の状態。白く見えるのは、そうです、ダルマ転轍機。木陰の良いところに設置してもらえました。


枕木の上にのっています。格好良いですね。犬釘が1本だけあるので、ドリルで穴を開けて飾りで差し込んでおく、と庭師さんが話していました。うーん、素晴らしい。それにしても、200kgもありますので、クレーンを使わないととても動かせません。たまたま庭園工事をしているときだったから、こうして良い場所に設置できたわけです。本当にラッキィでした。
ちなみに、2枚目で、下に半分写っているのは、AB10のパンタグラフ。


ということで、あとはこの西庭園なのですが、とにかく未完成です。あと1週間くらい、とのこと。一番の難所は、2枚目の写真にある橋です。木造の橋を計画していて、大工さんと最終打合せもしました。次回には開通します、きっと……。
<監督の視察>


新しい貨車は、監督も乗り降りが楽です。さっそく乗り込んで待っているトーマ。台車を支持するボルトの支持構造をいろいろ変更し、ようやく満足のいくものになりました。人が乗る車両は、ある意味で機関車よりも難しいです。なにしろ、荷重が大きいですし、乗り心地に対する文句も言われますから。
デッキへ上がってきました。トーマの前にあるのがコントローラで、延長して、機関車から4m離れても運転ができます。後ろで運転するというのも、眺めがなかなか良いものです。

トーマを載せてデッキを通過していたら、スバル氏に見つかりました。それで、写真を撮ってもらうことに。
<夏の列車>


6月最後の日曜日です。もうすっかり夏。こんな季節に運行するなんて、弁天ヶ丘線では異例ですが、線路が整備されましたので、今年は夏も頑張りましょう(まだできていませんけれど)。
南庭園の様子。だんだん緑で覆われてきました。1枚目が転轍機が置かれている後ろの小径です。木陰で、ちょっと一休みしたくなる場所になりましたね。2枚目が、その反対側のダルマ転轍機。この石畳の路線は、走行音が非常に独特で、ごろごろという感じです。

北のデッキが、やはり一番涼しい場所です。例年は、夏はここでしか活動をしていなかったくらい。先日の台風で枯れた松が何本か倒れたようで、見晴らしが良くなっていますが、また、そのうち別の樹が伸びてくることでしょう。
ウッドデッキは、僅かに緑の苔(?)が付着したくらいがグッドだと思いますが、いかがでしょうか? 実は、このデッキを近所の猫が良く通ります。スバル氏がときどき拉致して、家の中に入れていますが、トーマはこれが面白くありません。

日中はお休みして、また夕方に活動をする、というのが健康的なパターンではないでしょうか。のんびりと、コーヒーを飲みながら、そして、次の工作について考えながら……。

これが6月27日の西庭園です。土を大量に入れて、右側は盛り上がってきました。線路はほとんど外されています。手前にある大きな穴は、樹を植えるためのもの。さあ、1週間後に完成している、かな?
/☆Go Back☆/