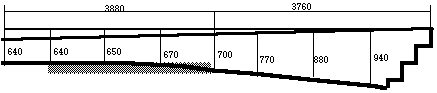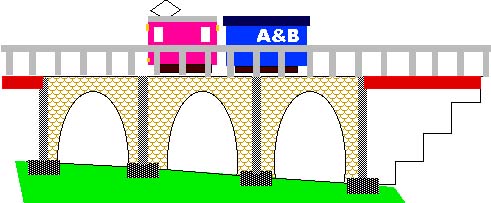MORI Hiroshi's Floating Factory
Model Railroad Workshop
<機関車製作部>
工事進まず

/☆Go Back☆/
弁天ヶ丘線のオーナは昼と夜と別々の仕事(しかも全然別の)に追われて、工作のための時間はこの頃では1日に20分になってしまいました。そういうわけで、取り立てて大躍進はありませんが、なるべく前倒しに仕事を片づけ、週末には、なんとか時間を捻出し、運転をしています。この時期はとにかく気候が良いので、頑張らないともったいない。本当にこれだけは、お金では買えませんからね(ドームでも建てれば、一年を通して良い季候が実現可能なので、めちゃくちゃお金をかければ買えないこともありませんけれど……)。
まずは、各種の問題点を潰していく作業が優先します。たとえば、ガレージのドアの鍵が少し硬いから穴を削ろうとか、まあ、そういう地道な工作。その次が、故障箇所の修理。これは、そんなに頻繁ではありませんけれど、なにしろ紙で作った車両が多いので、ちょっと足を引っかけて壊してしまったりしますから、セメダインで直します(わりと楽しい)。それから、各種のメンテナンス。などなどをしているうちに、新規の工作のための時間がなくなってしまうのです(長い言い訳)。この点については、ここ数年の間に解決したい所存です(まえにも書きましたね、これ)。
工作に関するエッセイ「工事中よ、永遠に」を『小説すばる』で連載していて、それがあと3カ月で満期(貯金か)になりますので、来年には単行本として出版されます。適度に庭園鉄道のことも話題になっています。それから、『ミニチュア庭園鉄道2』も、来年夏頃には出せることになりました。現在、中央公論社のN倉氏(超プレイモビルマニア)と内容について検討中です。多少は写真が大きくなるかも。
それから、本機関車製作部の英語ページもアップしました。これは、文章はなくて、日本語ページと同じ写真に簡単なキャプションをつけただけです(一箇所だけ、英語バージョンだけで公開しているページがありますけれど)。ミニチュア庭園鉄道(Miniature garden railway)というのは、世界的な一般認識としては、遊園地や公園で走っている可愛らしい鉄道たちのことをさします。したがって、弁天ヶ丘線くらいの大きさのものは、「超ミニチュア」になるわけですね。
上の写真は、グースの横に立つ頭でっかちのお嬢さん。フェンダにバケツがのっています。
<ペンキ塗り>


土曜日の午前中。晴れ間が覗いたので、ペンキ塗りをしました。新しいポイント2つ(未塗装のまま既に使用)と、自作ポイント2つと、それから自作クロッシングの枕木部分を茶色に塗りました。どうせ汚れますので、適当です。
玄関ポーチのカーブでAB10の混合列車が待機中。ガレージがなかったときは、いつもこの場所で工作をしていましたね。向こうの駅(自転車置き場)にグースとワークディーゼルが見えます。
<平常運転>


そのワークディーゼルとグース。ワークディーゼルは、相変わらずブースタ回路を付けず、バッテリィ1つで動かしています。スピードはOFF-1-2の3段切換(2段変速ということ)です。でも、特に不自由はありません。フォンが鳴るのですが、音が大きすぎて滅多に鳴らせません。音の大きさが変えられたら良いのに、と思います。
グースも快調。トレーラを牽引しませんので、今のところ1軸駆動でも大丈夫です。このグースとビッグワークの2両だけが、人が乗る車両に駆動輪があるタイプになります(つまり、いわゆる「電車」式ですね)。どういうわけか、このところずっと、木曽のショートカブースを牽引しています。


デキ3の錆はその後落ち着きました。良い感じです(笑)。走りも絶好調で、一人で走るならば、これが一番楽しいです(音が良い)。最近は、トレーラをガソリン機関車と共用しているため、出番が少し減ったかも。
もう1枚は、森林の中のカーブを通過する混合列車。後ろ向きに乗ったら、こういうふうに見えるわけですが、ちょっと恐くてそんなことはできません。

逆光で撮る写真が好きで、どうも機関車をシルエットにしがち。ディテールよりもアウトラインの方が大事だと無意識に考えているせいかもしれません。実物も模型も、考えずに撮ると、圧倒的に逆光が多くなるのです。
<難工事に着手か>


西のデッキまで到達している線路をさらに延長し、これを西庭園の本線に繋げる工事が、既に何ヶ月もまえから男たちの前に立ちはだかっていた(某番組ふう)。
1枚目の写真が、デッキの階段を見たところ。2枚目が、反対にデッキ側から見たところです。ついに、杭を打ちました。糸を張って、水準器でレーザを当てて、高さをチェック。
どちらにしても、地面は1m近く下にありますから、橋をかけるなり、高架にするなりの、難工事にならざるをえません。


横から見たところです。糸は水平を出して張りました。デッキの端から、最初の杭(上の1枚目の写真)までが約4mです。地面は傾斜し、奥ほど下がっています。
上の写真で、地面に角材で作った台のようなものが置いてあります。先日の雷でクーラが1つ故障し、屋根の上にあった室外機を交換しました。そのとき、古い台を廃棄して、鉄製のものに替えました。つまり、これがその室外機の台です。なんとなく、荒涼としたシーナリィに馴染んでいますので、ここに置いてあります。
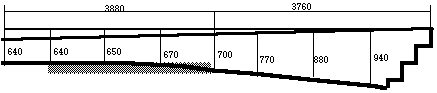
測量結果です(自分に対するメモ)。既にある本線の高架線路と西デッキの高低差は30cmほどなので、デッキから3%の傾斜で下りながら橋を渡り、10mほどさきならば、本線の高さまで下げることができます。線路をどこに引くのかはまだ検討中(といって、そんなに選択肢はありませんが)。かつて檻があった場所(上の写真で、ブルーのシートが置かれているところ)は、将来は、駅にする予定です。
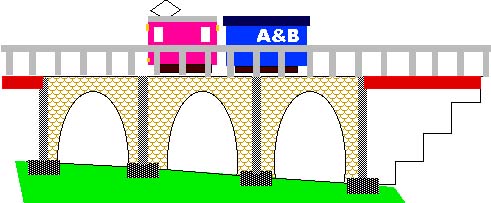
完成予想図です。こうやって絵にすると、一気にやる気がなくなるのですが、それは、ドローソフトのせいでしょうか?(笑)
<小さなライブスチーム>

ライブスチームというのは、ゾンビに対抗するために結成されたLives Team(生きものチーム)ではなくて、Live steam(生きた蒸気)のことです。ようするに、お湯を沸かして蒸気の力で走る模型機関車のこと。もう何度も本レポートに登場していますが、人が乗れない小さなライブスチームも、沢山のサイズがあって、それぞれマニアがいます。
工作室の北側のデッキに、久しぶりに32mmと45mmのエンドレスを敷きました(しばらく常設の予定)。いろいろ機関車を出してきて、走らせるつもりで準備。ポットが立っていますが、熱湯を(水のかわりに)用意して、なるべく早くスチームアップするようにしているのです。

45mmの方は、この機関車を最初に動かしました。久しぶりなので、最初調子が出ず、これで時間をとられ、今日はこの1台だけ。アスターのかなり昔のBタンクです。上の写真では赤いカウキャッチャが付いていますが、あまりにも格好が悪いので今回外しました。アルコールで走ります。本来、10分くらい走るのですが、調子が今一つで、2分ほどでストップ。


32mmの方では、マモッドのBタンクが今回は絶好調でした。4回トライして、一度は5分以上走り続けました。こんなに長く走ったのは初めてです。ライブは、そのときの天候(風の影響も受けます)や、ちょっとした調整で変化するので、難しいのですが、そこが楽しみといえば、楽しみ。今は、フリーで走らせていますが、ラジコン装備で速度コントロールをして、長いトラックを走らせると、さらに面白いでしょう。
同じ機関車を2台持っているので、重連に挑戦したいところですが、現在は片方が部品が一つ足らないため、まずそれを作らないと同時に2台は無理です。
記録的に長く走ったので、デジカメを取りにいって、撮影する時間がありました。
小型ライブスチーム一瞬の通過(70kb)(面白さ★)
駆け回る小型ライブスチーム(230kb)(面白さ★)
<インドア派>

監督は玄関の絨毯の上で昼寝中。急に起きたので、片目が小さいです。


Gゲージのデジタル化は、停滞中です。運転は既にデジタルで充分に楽しめるからです。内側の電化路線は、まだアナログで動いていて、デコーダのない車両を走らせるときは、蒸気でもこの架線のところで走らせています(笑)。デジタルとアナログとを切り換えるようにスイッチを作れば良いだけなのですが……。ストラクチャを増やしたいのですが、もう置き場所がありません(足の踏み場がなくなる)。
<小さな機関車たち>


古くからあるHOナロー(すべてHOeで9mmゲージ)の車両を幾つか撮り直しました。緑の機関車は、ホワイトメタルのキットを組んだもの。グレィの方も、ホワイトメタルですが、これは完成品を買いました。いずれも、下回りはNゲージのものです。全長5,6センチというところ。

有名なピコのホワイトメタルキットを組んだスチームトラム。色はオリジナルです。下回りは、Nゲージのパワートラックを入れました。このタイプだったら、5インチで作っても、ロッドが見えないので、簡単そうです。


乗工舎のキットを組んだフォーニィと亀の子。こうして勝手な色に塗っています。亀の子の方はCタンクですね。キャブの中にぎりぎり入っているのはモータです。

シェイです。これは、珍しくナローではなく、16.5mmゲージ。だから、なんとなく、がに股だし、シリンダも傾斜している感じで、無理っぽいです。やっぱり、シェイはナローじゃないと引き締まらないのかも。

アウトサイドフレームのCタンク。これは小さいのに、キャブにモータが見えなくて、それから、細い細いロッドが芸術的に動きます。ちょっと珍しい職人芸の作品。
<脱線防止対策検討委員会調査WG>


ガレージの前を横切る線路には、車のタイヤが踏みつけるため、写真のようにレールの間に板が置いてあります(固定せず置いてあるだけ)。ここを、列車を無人で走行させると、軽くなったトレーラが脱線します。原因は、2枚目の写真のように、板に車輪が当たって、乗り上げるためでした。2軸車両って、カーブでは、線路と車軸の垂直性が全然保たれないのです。ほんのちょっとしたことで、脱線は起こるので、その都度、原因を確かめて、それを取り除くことが必要です。
<ロングラン100m>


また逆光のデキ-3です。AB10の列車とグースが、いずれも駅の線路へ待避しましたので、本線があきました。久しぶりにデキ3でロングドライブしましょう。

電動ポイント切換機は、その後ずっと問題なく働いています。今のところ不具合は一度もなく、耐久性もまずまずです。もう少しコードを延ばして、遠くで操作をした方が良いかもしれません。
ポイントの切換システムについては、ただ今、各種の方法を検討中です。

エンドレスを除けば、本線から北のデッキへ乗り上げるラインが、現在最も長い運転が可能な区間です。同じ線路を通らず、全長で100mくらいを走ることができます。写真は、その終点の西デッキへの最後のカーブ。
では、ご好評にお応えして、動画をお楽しみ下さい。でも、メモリも食いますので、これくらいで最後にしたいと思います。
デキ3の弁天ヶ丘線一周(2.1Mb)(面白さ★★★★★)
<新たなる旅路へ>

何が新たなのか、どこへ旅路なのか、よくわかりませんね。A&Bの秋のポスタを作るとしたら、こんなピンナップかな、と……。
/☆Go Back☆/