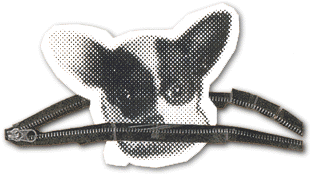

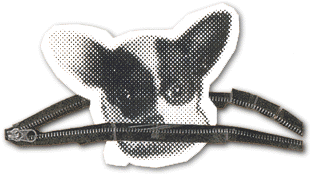
|
Wyclef Jean Presents the Carnival Wyclef Jean (Ruffhouse/Columbia)
フージーズは、なにかと、こう、ギャングスタ方面へと視野が狭くなりがちだったラップの世界に、もう一度音楽的な要素とか、ギャングスタ以外の歌詞の世界とかを思い出させるうえでとても重要な役割を果たしてくれたわけだけれど。ワイクレフ・ジーンはそこんとこをさらにもう一歩、意識的に押し進めたような音作りを聞かせている。
R&B、ゴスペル、ジャズ、アフロ・カリビアン、レゲエ、サルサ、フォーク、ヨーロッパ系ムード・オーケストラもの、そしてなんとニューヨーク・フィルまで動員したクラシックやオペラの要素までを、けっこう知的にごった煮にした仕上がり。サルサの女王、セリア・クルースをゲストに迎えてリメイクされた「グアンタナメラ」とか、ネヴィル・ブラザーズをゲストに迎えたスウィートな「モナ・リサ」とか、お見事だ。
クレオール・ランゲージでのラップや歌をフィーチャーした曲も何曲かあって。妙に新鮮。自らのルーツを強く意識した意欲作ってとこでしょうか。
|
|
Love, Peace & Nappiness Lost Boyz (Group Home/Universal)
で、登場した新作。クイーンズを本拠にする彼ららしく、もろ東系の音でわくわくさせてくれる。ぐっとコアに、ドープにきめた作品もあるし、歌詞のほうで最近のヒップホップ・シーンのどうにもならない現実に思いを馳せる曲とかもあるけれど、全体的な印象はさほどダークじゃない。
レッドマンやA+らのバックアップを受けた「Beasts From The East」がベスト・トラックだけれど、メンバーのチークスとターががっちりリードした他の曲もなかなかの出来。現実の世界がはらんでいる様々な問題に言及しながらも、とことん突き詰めることなく、まあ、なんとかなるだろう……的に解決していく曲が多いような感じで。そこがもしかしたら批判の対象になるかもしれないけれど。ポップ・ミュージックとしては、実はこっちのほうが正解なんじゃないかとも思う。まじに。
|
|
Homemade Blood Chuck Prophet (Cooking Vinyl)
たぶんこれがソロ4作目。グリーン・オン・レッド時代よりもぐっとカントリー/スワンプ色を強く打ち出した姿勢がごきげん。スティーヴ・バーリンがプロデュースした前作『Feast of Hearts』も素晴らしかったけれど、今回のほうがさらにラウドかつファンキーな仕上がりだ。CCRとか、ジョージア・サテライツ〜ダン・ベアードあたりのファンには絶対おすすめ。
ジョン・フォガティの世代でもなく、ベックの世代でもない、その中間に位置しながらルーツ・ミュージック探訪を続けるプロフェットはダン・ベアード同様ずいぶんと損をしているのかもしれないと思う。けれど、そんなある種中途半端な世代ならではの何とも言えない喪失感が漂う音像と歌詞は本当に魅力的だ。
|
|
The Mollusk Ween (Elektra)
で、この6枚目のアルバム。今回はひとつのサウンド・スタイルにこだわることなく、乱暴にジャンル横断しながら彼ら独特のイカレ感覚を全開にしているみたい。歌詞をまだよく把握していないので、もしかしたら何か大きなテーマに貫かれているのかもしれないけれど。でも、“軟体動物”なるアルバム・タイトルから見ても、今回は曲ごとにくねくねしてみた、と。そういうことじゃないかと思う。
いきなりグッド・オールド・タイム調の陽気な曲にサンプラーのピッチをいじりまくったようなヴォーカルを乗せた曲でスタートして、その後はポルカをおちょくったり、テクノをおちょくったり、最近ふうのオルタナ・ポップをおちょくったり、フォークをおちょくったり。次々と狼藉を繰り広げる。テクノ・カントリーとでも言いたくなるようなサウンドの「Waving My Dick In The Wind」とか、くっだらねーんだ。アメリカ版「たんたんたぬき」ってとこでしょうかね、こりゃ。
ただ、一瞬、ティラノザウルス・レックスを思い出してしまった「Mutilated Lips」とか、すげえいい曲だし、歌詞も美しくねじれてるし。きっちり音楽家としての才能も発揮してたりして。あなどれないねー、まったく。
|
|
Straight On Till Morning Blues Traveler (A&M)
今回の新作も、きっとああいう人たちの間で大いに人気を集めるわけだな。オールマン・ブラザーズ・バンドとかマーシャル・タッカー・バンドとかエルヴィン・ビショップとか、そういうのが当たり前に好きだった世代にとって、どうにも抗えない何かをこいつらは持っているみたいだ。だから、ぼくもそれなりに好意的に聞いてしまうのだけれど。
もちろん、この人たちはニューヨークが本拠だから。先に列挙したサザン・ロック軍団とは違う、もっと、こう、60年代グリニッチ・ヴィレッジでブルースにのめり込んでいた白人フォーク・アーティストとか、ポール・バターフィールドとか、マイケル・ブルームフィールドとか、アル・クーパーとか、そういう連中に通じる冷静なたたずまいもあったりするわけで。ある種の“理性”のもとで構築されたバーチャルなパワーハウス・ブルース・ロックって感じでしょうかね、この新作も。
どの曲でもポッパーさんのウルテク・ハーモニカ・ソロがフィーチャーされていて。これが鼻につく人には絶対ダメかも。納豆嫌いな人はいくら説得してもダメだもんね。
|
|
Pristine Smut The Murmurs (MCA)
これまではアコースティック・デュオって感じだったけれど、今回はエレクトリック・ギターに持ち替えて、やはり女の子のベースとドラムを加えたバンド編成によるレコーディング。全11曲中、4曲をk.d.ラングがプロデュースしている。そう思うと、確かに4人とも、まあ、なんというか、“そっち方面”の女の子っぽくも思えたりして。記憶が定かではないのだけれど、中心メンバーのリーシャとヘザーのうち、どっちかがk.d.ラングとデートしているところをスクープされてたような気がする。わかんないけど。深いです。
ギター・バンド編成になったとはいえ、透明感のある、抜けのいい音像が魅力的。相変わらず、女の子ならではの、夢見ているようでいながらしっかり冷静な歌詞の世界も光る。暑い日とかにぽけーっと聞くのにもいいかも。
|
|
Butch The Geraldine Fibbers (Virgin)
パンキッシュだったりスペイシーだったりするギターに、フィドルやら、ウッドベースやらが絡む音像は魅力的。ただ、様々な音楽要素をひとつのサウンド・スタイルの中に融合するのではなく、曲ごとに突如、もろカントリーになったり、もろノイジーなパンクになったり、不安定な浮遊感がみなぎるバラードになったり……と、雑多な方向性を無理に統一することなくどばっとぶちまけたような仕上がりだ。だから、ぼくは曲によって好きだったり、嫌いだったり、です。
|
|
Love Among the Ruins 10,000 Maniacs (Geffen)
ただ、マーチャントの後釜はやっぱりキツイよね。同じように淡々としたヴォーカルを聞かせてくれるメアリーさんだけど、淡々とした中での表現力となると今ひとつかも。昔からのマニアックス・ファンがその辺を攻撃対象にしてくるかもしれない。がんばってね。
すでに全米チャートにランクインしているロキシー・ミュージックのカヴァー「More Than This」と、アルバムのオープニング・チューン「Rainy Day」がベスト・トラックかな。ジュールズ・シアが共作者としてクレジットされている3曲も悪くない。
|
|
Egyptology World Party (The Enclave)
その辺に気づきながら聞くのと、そうでないのとではずいぶんと評価も変わってくるのだろうけど。気づいてはいても、カール・ウォリンジャーのなんともかよわげな歌声が放つ妙な吸引力に持ってかれちゃうところはあります。イギリスのポップスだなぁって感じか。
|
|
Little Head John Hiatt (Capitol)
今回の新作はちょっとだけ好き。『Bring The Family』ほどではないけれど、やっぱりこの人はいいなぁ……と思わせてくれる、そんな渋い底力がアルバム全体に流れている。ブルース、R&B、カントリー、ロックンロールなど、ルーツ・ミュージックをこよなく愛し、すべてを自分なりに昇華した彼ならではの深い表現がそれなりに楽しめる。
曲によってタワー・オヴ・パワー・ホーン・セクションやらベンモント・テンチやらが参加。
|
|
Get Some Snot (Geffen)
アグリー・キッド・ジョーが彼らのデモを聞いて気に入り、それをきっかけにデビューが決まったらしい。まあ、とにかくそういう音です。ポップ・ミュージックの“旬”みたいなものを気にすると、ちょっと旬を逃した音って感、なきにしもあらずだけど、カリフォルニアのティーンにはたまらないバンドなんだろうなぁ。暑い日には熱いお茶……というのが好きな人には、この夏、絶好のパートナーかも。
|
|
Copyright © 1997 Kenta Hagiwara kenta@st.rim.or.jp |