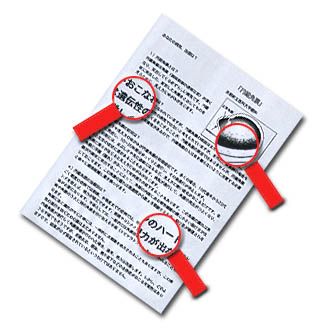本年は税理士登録30年になり、近畿税理士会12千人強の会員の中で最年少の30年表彰をこの6月20日に受けることが出来ました。 私は高校2年生頃から近視・乱視になり20歳以降は特に乱視が強くなってきたと信じておりました。実際には乱視ではなく別紙の京都府立医科大学眼科教室のパンフレットの説明の「円錐角膜」という病気でした。 昭和45年(22歳)に京大病院で円錐角膜と診断され、当時は京大病院でも年に1〜2人ぐらいの患者数であったようでしたが、角膜がどんどん突出し、最後は物が見えなくなると言われました。発病原因については不明であり、角膜移植しか対処方法はないとも、また当時の角膜移植の成功率は50%以下であり、だいいち角膜の提供自体が少ないため、その移植の夢は夢の夢であるとも言われました。 昭和44年頃より税理士試験を目指して勉強をしていました私にとって、目の状態は最悪のプレゼントになり、マッサージの勉強でもしたほうがとも言われたこともありました。然しながら幸運なことに、その頃よりコンタクトレンズが普及しだしてきました、片目分15千円程度だったと思います。給料5万円程度の書生さんにとっては高額でしたが、より見えることからすれば大変な朗報でした。何回も落として、また角膜とのカーブが合わなくなって痛くなり京都河原町三条の京都コンタクトレンズによく通ったものでした。 何度もコンタクトを落としましたが、それは不注意だけが原因でなく角膜の突出したカーブにレンズが合わせきれなかったのも原因でした。当時の特注品でもだんだん合わなくなり、税理士試験に合格し税理士登録証書伝達式に出席した日(昭和48年1月)などは、目が痛く喜びの涙のはずが痛さの涙を流して、将来への不安を覚えた記憶が未だに消えていません。 昭和48年7月のNHKのテレビで「円錐角膜の画期的な治療法の開発」というような番組が放映された旨、田舎の父より連絡を受けNHKに詳細を尋ねて早速先生の診療日に合わせて10日後ぐらいに東京:順天堂大学付属病院の糸井素一助教授の診察を受けました。(その日は金大中韓国前大統領が東京から韓国に拉致された日で記憶しているのですが) 診察の結果は、元来正常な角膜の人でも8時間ぐらいしか1日に装着できないコンタクトを痛いながらも10時間以上できる私は、助教授の角膜先端部分の切開をする手術をしても結果は同じで、装着時間がもっと短くなった時に処置しようということに成りました。 昭和52・53年頃の新聞に糸井(角膜学会会長)京都府立医科大学教授とコンタクトメーカーとの共同開発により、「円錐角膜にフィットするコンタクトの開発」が出来た旨の記事を見たため、早速京都府立医科大の糸井教授を訪ねました。 糸井先生に順天堂大学以降のお話をし、診察をして頂いた後、当時助手であられた中山千里先生をご紹介され、それ以降私の角膜により装着しやすいコンタクトの提供を受けるようになり、随分と楽に仕事が出来るようになりました。 中山先生はそのうちJR立花駅(尼崎市)近くで眼科医院を開業され、以来私は特に異常があったとき以外は年に2・3回程度中山先生の医院でコンタクトの調整検診等を受けてまいりました。 円錐角膜は年齢を重ねるごとに小康状態を保っていましたが45歳頃からは老眼になり始めたのか、めっきり字を読むことが苦しくなり始めました。 また時折しなければならない運転免許書の更新が大変なプレッシャーでした。 更新の回数を減らすためにも優良免許であり続けるよう努力していましたが、最後の2回はCの字の判読は出来ないので視野の検査でかろうじて更新して頂いていた状態でした。そんな訳で中山医院へ行く回数も増えるようになってきたのですが、平成11年の初秋に「田中さん、角膜移植しませんか」と言われたときは、これこそ正に目から鱗の気持ちでした。移植手術が出来るのであれば、何の不安も心配も無く即お願い致すのみでした。 京都府立医科大学の眼科に紹介状をもって受診しますと、佐野洋一郎先生が診察をして下さいまして、仕事等の都合を見計らって平成11年12月後半にまず右目の移植手術をすることになりました。 手術及び入院は京都バプテスト眼科クリニックということで、平成11年12月22日手術しました。当初相当の痛みがあると予測していましたが、ほとんど無く術後写真のように綺麗に縫合してあり、佐野先生の器用さに大変感銘を受けました。一部の抜糸は平成13年12月でしたが、それ以来の右目の見えようは格段に飛躍し、移植後も左目にコンタクトをして老眼鏡をかけての生活でしたが、抜糸後はこの老眼鏡は不要となりました。 正直なところ、術後の右目は細かい字があまり見えず、老眼鏡で拡大して見ていたような状態でした、「抜糸すると角膜表面に丸みが出るのでそれからは良くなりますよ」との事でしたので、期待していましたが期待以上の結果になりました。その後2年間は主に左目のみで細かい仕事をしていましたが、そのせいもあってか左のコンタクトの調子が徐々に悪くなって参りました。右目での仕事等の自信がついたので、次は左目の移植を平成14年6月25日再び行いました。 執刀医は勿論前回同様、佐野先生で経過は前回以上に良好な状態になっています。只、2回目は拒絶反応がひどいようで、それに対応すべく半年間は経口薬や目薬の種類は前回の比ではなく、時間時間の摂取に追われていました。しかし目の不自由さから比べれば、この程度は何の苦でもないことであり、しかも未だ拒絶反応も一度も現れておりません。現在、右目は近眼状態で手元がよく見え、左目は遠視状態で遠くがよく見えます。左の抜糸もやがてと思われます、左は更によく見えるようになるものとより多く期待致しております。 両眼ともドナーはアメリカ人で右目は当時59歳(私、51歳)、左目は47歳(私、53歳)の人とお聞き致しております。お二人の死があって私の目が蘇ったわけであります、知らされざるお二人のご家族には感謝の思いを表しようがありませんが、そのお気持ちに応えるためにも目を大切にし、別の形で世の中にお返しをしようと思っております。 後で佐野先生から教えて頂いたのですが、中山先生は現在も京都府立医大の円錐角膜の客員教授をされておられ、且つ円錐角膜の権威の先生であられるとのこと、その中山先生の診察・アドバイスと佐野先生の診察・執刀力がなければこれまた今日の私の幸せはないわけであり、両先生にも感謝申し上げますとともに、いろいろな素晴らしい方にお会いできていることを改めて神に感謝と御礼を申し上げます。
|
||||||||||||||