
2003年、湘フィルにも毎回多くの見学の方が見え、活気にあふれた年明けとなりました。新年を迎えるにあたり、松村先生が以前に書いて下さった文章を再び紹介したいと思います。よく味わって、新たな気持ちで練習に臨みましょう。
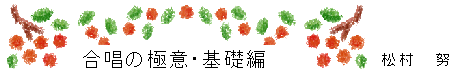
その一 声を発することは、能動的な作業と知るべし
合唱団を選ぶ。合唱団に入る。練習に参加する。すべて能動的な作業から始まった。しかし、そこにいるだけでは、何も始まらない。音を発しなければ、何もないのである。それも出させられる声ではなく、自らの内から発せられる感性の信号でなくてはならない。
その二 全ての原点は、呼吸にあり
何も難しいことではない。人間の喜怒哀楽、全ての感情表現が呼吸にある。さらに、吐き出す息に感情が乗るとするなら、その息を吸い込むときに既に感情の変化が起こっているのである。このことを考えるなら、出そうとする声の質によって、吸い込む息の表情が変わらなくてはならない。吸い込む息が大事だとすれば、それを吸い込む前の吐き終わりこそが最も大事だと言うことになる。つまり、フレーズの終わりをどう歌うかが重要だ。
その三 声に生命を与える
生きた声、死んだ声。音が聞こえているだけの声と、それに表情が乗っている声の違いのことである。表情を伝えるために、継続する息の供給が必要不可欠。響きを伝え、聴き手の心の奥底にまで届く長い息の流れが生まれた時、人の声は、『歌う』から『祈る』へとその世界を変える。昔から「『歌う』は、三度『祈る』に等しい」という。
その四 合唱とは、自らの存在を消すことに始まる
突出した声、揺れた声、硬い声など、自らの存在を確認することのできる声は、たくさんある。これらを捨て去ることができたとき、自らの存在は消え、そこには、超自然の響きが、かぎりなく生まれて来るのだ。……… 倍音
その五 声部間の対話が音楽を生み出す
演奏者は、指揮者との二次元的つながりで演奏してはいけない。自分以外の声部の動きを全て知り、その響きの中で自分の旋律を見つめなくてはならない。そして、他声部との対話が生まれたとき、指揮者との関係は、三次元、四次元へと世界を広げ、音楽を創り出していく。
その六 感動とその分析の必要性を知るべし
作品に対して大いに感動すべきである。感動なきところに音楽は生まれない。しかし、重要なのは練習の段階で、それをどう冷静に分析するかである。更に、分析したものを、どうテクニックに置き換えていくかである。この分析が為されなければ、聴き手に何一つ伝わることはない。
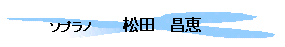
栗林先生がドイツへ留学されている間のピンチヒッターとして、湘フィルのヴォイストレーナーに。熱心でバイタリティーあふれる指導で湘フィルの声を支えて下さいました。栗林先生とは大の親友。今回も息のあったハーモニーを聞かせていただけることでしょう。北海道教育大学、東京芸術大学及び大学院終了。第3回JSGシューベルト国際歌曲コンクール女声部門第1位。第4回日本声楽コンクール第1位。第5回奏楽堂日本歌曲コンクール第1位。二期会会員。
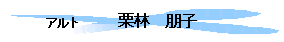
言わずと知れた湘フィル初代ヴォイストレーナー、栗林先生。東京芸術大学大学院を卒業された頃から、湘フィル創生期の声づくりに力を尽くして下さいました。1991年第3回日本声楽コンクール第1位。92年第1回藤沢オペラコンクール奨励賞、94年第63回日本音楽コンクール第1位。96年には五島記念文化賞オペラ新人賞受賞によりベルリンへ留学。帰国後は、オペラ「オルフェオとエウリディーチェ」のタイトルロールで新国立劇場デビューを飾って以来、オペラの舞台で目覚ましい活躍をされています。
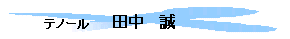
2000年『ミサ・ソレ』、01年『ヴェル・レク』の演奏会で歌って頂いて以来の登場となります。服部先生の言葉をお借りすれば、「熱いパッションと奥深い洞察力に裏づけされた音楽表現は、持ち声を振り回して歌ってしまうありがちなテノールとは比較にならない。音楽で勝負してくる本当に貴重なテノール」とのこと。国立音楽大学声楽科及び大学院オペラコース終了。1997年ミラノに留学。二期会会員。
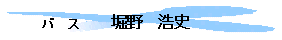
湘フィル初登場の堀野さんは、東京芸術大学卒業後、ドイツに留学し、ドイツ語、ドイツ歌曲を学ばれました。オペラでは「魔笛」「フィガロの結婚」「カルメン」「椿姫」等に出演する他、「浅茅ヶ原」「脳死を超えて」等の邦人話題作にも多数出演。スーパーバスと称された深々とした低音、叙情性豊かな歌唱と言葉の鮮明さには定評があるそうです。第2回奏楽堂日本歌曲コンクール第1位。山田耕筰賞受賞。東京室内歌劇場会員。
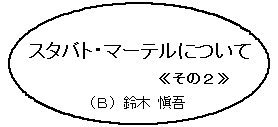
マリア信仰の始まりは2世紀頃とされています。外典福音書(教会によって公認されていない福音書)に記されたマリアの誕生から少女時代の物語は、マリア信仰が根付く大きな要因となり、3
~4世紀にキリスト教が飛躍的に発展を遂げるにつれ、その処女性を讃美する傾向が強まって、この頃の宗教会議で「処女マリア」と言う称号が承認されるまでになったのです。
4
~6世紀には宗教会議での「神の母」の称号承認から「永遠の処女」であることが公認されたころにかけてマリア信仰は次第に広まり、マリアの祝日が体系化されて、自然にそれまでの女神信仰に代わるものとなっていったのでした。 この頃になると皇帝たちは、権力が神によって与えられたものである事を示すためにマリア信仰を利用し、マリアは豪華な衣装をまとった女帝として描かれるようになります。
そして9世紀、マリアは天界と地上の最高位に君臨する女王となって玉座を与えられ天使の一団を統率するとされました。11世紀以降、教会の権威が国王を凌ぐようになると、マリアの「汚れのなさ」を教会のイメージとして利用し、幼な子イエスを膝の上にのせたマリア像は「荘厳の聖母」と呼ばれ、各地には奇跡物語が伝えられて巡礼地には人々が押し寄せるようになったのです。
やがて「荘厳の聖母」像が教会の入り口に飾られて、国家権力と結び付いた教会の権威の象徴として大聖堂が建立され、マリアの肉体が天に昇ったという「聖母被昇天」の信仰が広まるようになって、マリアは(明けの明星)(春先のバラの花)(泉のほとりの百合)などと、その美しさが讃えられました。
これらの事柄を知ると、私のようなキリスト教に疎い者は、ルカの福音書に述べられている、受胎告知を受けたマリアが「私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように」と答える「信仰篤い清純な乙女」のイメージとの隔たりに困惑してしまうのです。ただ、その結果、マリアを描いたとされる美しい絵画や優れた彫刻、また
“Ave Maria” “Salve regina” など、沢山の音楽作品が残されたことは無信仰な者にとっても感謝すべきことではありますが。
ところで同じ12世紀頃、十字架上で死んだイエスを膝のうえに抱き悲しむ「ピエタ」と呼ばれる図像が登場し、「悲しみの聖母」に対する信仰が生まれてきます。 疫病や戦争で疲弊混乱していた社会で、人々は自身の不幸をマリアの苦しみや悲しみに重ね合わせて祈ったのでしょう。先に記したような権力が作り上げたマリア像では無く、スタバト・マーテルの韻文は、庶民の祈りの中から生まれて来たようにも思われるのです。
さて、私たちの「スタバト・マーテル」の作曲者アントニン・ドヴォルザークは1841年9月、ハプスブルグ家に支配されるようになって200年余り経ち、漸く民族意識が目覚め始めたチェコの、モルダウ河畔近い肉屋と兼業の居酒屋を営む家で生まれました。少年の頃から音楽の才能を見出された彼は、教育熱心な父の勧めでカメニッツェという町でドイツ語と音楽を学んだ後、オルガニストになるならとの父の同意を得てプラハに出、オルガン学校に通いながら、オーケストラのヴィオラ奏者としても沢山の作品を学んだようです。オルガン学校を卒業した彼は相変わらず貧しく、作曲を続けながら、ヴィオラを弾き、ピアノを教え、アルバイトにオルガンを弾くと言う生活でしたが1873年、教え子のアンナ・チェルマークと結婚、間もなく、長女ヨゼファが誕生しています。それより以前彼より16歳あまり年長のスメタナは既に歌劇「売られた花嫁」で圧倒的な成功を収め、チェコ国民音楽の基礎を築いていました。ドヴォルザークはスメタナの指揮するオーケストラでヴィオラを弾きそのオペラの初演にも度々立ち会っていましたし、彼もまた、その先輩と同じようにワーグナーの影響を強く受けていたのです。
1875年にオーストリア文化省の奨学金を受けられるようになった背景には、その審査で彼の才能を見抜いたブラームスとハンスリックの(皮肉なことにワーグナー派と鋭く対立していた)強力な推薦があったことは以前紹介(通信02年5月号)したことがありましたね。
徐々に小さな成功を収め収入も安定して来た彼に、長女ヨゼファの死という不幸が襲ったのも同じ1875年のことでした。
敬虔なカトリック信者であった彼が、愛娘の死という悲劇に出会い、その悲しみを「スタバト・マーテル」の詩に託したのは、ごく自然なことだったのでしょう。多忙な日常に作曲が捗らない中、更に次女ルジェナ、長男オタカールの死という不幸に見舞われた彼の心中は、推し量ることさえ憚られるような気がします。
チェコ音楽最初の大規模な宗教音楽の傑作として作曲者の名声を確立したこの作品は、前回述べたようなセクエンツィアの範疇を超えたものと言えるでしょう。合唱と4人の独唱者に管弦楽を伴い、ドイツの伝統的な宗教音楽の形式を採りながら、そこに表れる民族的な音色(前回の練習で松村先生が「土臭い」と表現したもの)はチェコ音楽の特徴を示していますし、3行詩全60行の詩が10曲に分けられている意味、各曲の調性との関連など、これから練習を重ねるうちに学び、感じとってゆくべき事柄は実に多いと思われます。
作曲者が作品に込めた悲しみや苦しみ、慰め、祈り。楽譜から溢れ出るものを私たちの心からの音楽として表現し、聴いて下さる方々に感動を伝えたいものです。
 2003年 2 & 3月の練習日程
2003年 2 & 3月の練習日程 
1月 25日(土) ★御成小多目的ルーム 18:15 〜 20:45
2月 1日(土) 玉縄公民館 18:15 〜 21:00
8日(土) ◇茅ヶ崎市総合体育館 18:15 〜 20:45
オーケストラ室
15日(土) 明治公民館 18:15 〜 21:00
22日(土) 明治公民館 ☆13:00 〜 21:00
3月 1日(土) 玉縄公民館 18:15 〜 21:00
8日(土) 玉縄公民館 18:15
〜 21:00
15日(土) 明治公民館 18:15
〜 21:00
22日(土) 明治公民館 18:15
〜 21:00
◆30日(日) 栄区公会堂 18:15 〜 21:00
★ 御成小(鎌倉市立御成小学校)多目的ルーム (JR鎌倉駅より徒歩5分)
※ 地図の必要な方は受付までお申し出下さい。
・正門からではなく、中央図書館側の入り口よりお入り下さい。(3号館)
入り口を入って左側へお進み下さい。
・校内での駐車は出来ません。鎌倉駅周辺の駐車場をご利用下さい。
・上履きをご用意下さい。
◇ 通信1月号で未定となっていたところです。
茅ヶ崎市総合体育館の地下1F(駐車場のある階)にあります。
☆ 夕食をはさんでの一日練習です。(詳しい日程は決まり次第お知らせします)
夕食をご持参されるか、練習場近くのレストラン等をご利用下さい。
◆ 日曜日の練習です。お間違えのないように。
栄区公会堂はJR根岸線(京浜東北線)本郷台駅より徒歩10分。
地図の必要な方は受付まで。
▽▲編集後記▼△
成人式の時期になると、さすがにお正月気分も消え、‘日常’が戻ってきます。今年は私が前任校で卒業させた学年と現在務めている養護学校で初めて持った学年が揃って
成人式を迎えました。発達に遅れがあるので、高等部といってもまだまだ幼かった彼らももう‘大人’。これからのことを考えると「オメデトウ」という言葉も少々重く感じられマス。誰もが希望の持てる社会にしていかなくては、と痛切に思いました。
話は変わって、冒頭の『合唱の極意』は、この一年を新たな気持ちで歌に向かうためには絶好の文章と思います。時に読み返して、気持ちを新たにしてもらえると載せた甲斐があるというものです。先生、今度はぜひ「応用編」をお願いします= Tama


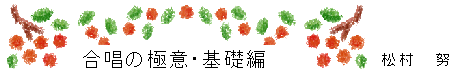
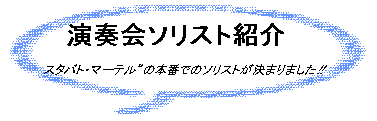
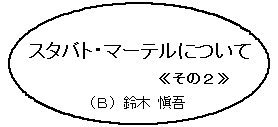 マリア信仰の始まりは2世紀頃とされています。外典福音書(教会によって公認されていない福音書)に記されたマリアの誕生から少女時代の物語は、マリア信仰が根付く大きな要因となり、3~4世紀にキリスト教が飛躍的に発展を遂げるにつれ、その処女性を讃美する傾向が強まって、この頃の宗教会議で「処女マリア」と言う称号が承認されるまでになったのです。
マリア信仰の始まりは2世紀頃とされています。外典福音書(教会によって公認されていない福音書)に記されたマリアの誕生から少女時代の物語は、マリア信仰が根付く大きな要因となり、3~4世紀にキリスト教が飛躍的に発展を遂げるにつれ、その処女性を讃美する傾向が強まって、この頃の宗教会議で「処女マリア」と言う称号が承認されるまでになったのです。