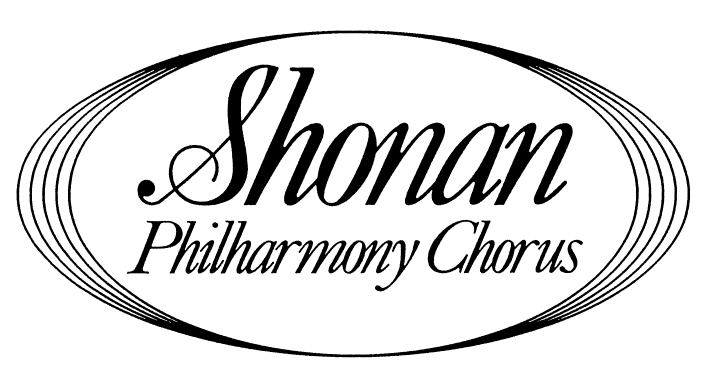 湘フィル通信
湘フィル通信
2001年3月号 Vol. 13 No. 10(Total 170 外 12)
発行日:2001.3.24 編集: 寺部
演奏会まであと一月とちょっと。チケットを買っていただく度に「いい演奏会にしなくては」と気が引き締まります。ヴェルディがこの曲に込めた祈りを表現できるかどうかは、彼が楽譜に書き込んだフォルテ、ピアノをどうとらえ、どう歌うのか、特にピアノをどこまで美しく歌えるかにかかっているように思います。それもまた、単なる技術的なことではなく、私たち一人一人の心の中にある祈りと呼応するものでなければ、到底これだけのスケールの大きな曲を表現することはできないでしょう。
例年プログラムに曲目の解説を書いて下さっている鈴木敬一神父から、原稿が届きました。プログラムに掲載するためのものですが、曲の理解に大変参考になりますので、一足お先に紹介させていただくことにします。
ヴェルディのレクィエムと
スタバト・マーテルについてのメモ
鈴木 敬一
ヴェルディは、きっかけさえあればレクィエムのテキストに作曲したいと常々思っていたに違いないと思う。その理由は、信仰心・宗教的動機からくるものである以上に、作曲家としてのヴェルディが音楽的に表現を与えてみたいテキストだったからである。
オペラに比べれば、多いとは言えないが、ヴェルディの宗教的作品は決して少なくはない。ところが、どういうテキストに作曲しているか調べてみると、かなり偏りがある。そこから分かることは、《宗教的作品においてさえも、ヴェルディの興味は神よりも、より一層人間の方にある》ということである。
典型的なのが、レクィエムを作っているのに、普通のミサ曲が見当らないということである。死と永遠のいのち、裁きとゆるし、破滅と救い・・・と真剣に取り組み、それを祈りの題材としているテキストを接して、また、それが実際に親しい者の死に際してであればなおさら、人の心(感情、思い)は大きく動くものである。これは、彼にとってとても大きな魅力だったに違いない。結局、ヴェルディは宗教的作品の中でも他のジャンルと同様に大切にしている音楽的表現は、そのテキストを前にして人の心がどのように動くか、またそのテキストを人がどういう思いを込めて歌う(聴く)のか、ということなのだと思う。これが、良くも悪くもこの曲が「オペラ的」であると評される根本的原因だと思う。
さて、作曲の経緯は次のようなことであった。
ロッシーニの死(1868年)を悼んで、ヴェルディ自身の提案でその一周忌に12人の作曲家の合作によるレクィエムを演奏する計画があり、ヴェルディは最終曲の"Libera me"を 作曲した。しかし、計画は実現せずに挫折してしまった。その後、イタリア統一運動の推進者で詩人のマンゾーニの死(1873年)にあたって、その一周忌に演奏するべく、以前に書いた"Libera me" を手直ししたうえで、これを含むレクィエムを書き上げ、翌1874年 に教会で初演された(以降は教会よりも劇場で演奏されるのが普通となっている)。
ただし、繰り返しになるが、ヴェルディはこのレクィエムを義務感から作曲したのではないと思う。また、最初から一人で全体を作るつもりでいたのではないかとさえ思えてくる。
(1) まず、最後の"Libera me"について
レクィエムの正式な名称は「死者のためのミサ」である。死者のためのミサが捧げられるケースとしては、葬儀ミサといわゆる追悼ミサがある。基本的な儀式と典礼文は、両者に共通である。
ただし、追悼ミサの場合は通常のミサと変わりなく派遣の祝福で終わるのだが、葬儀ミサの場合は、実際に遺体が安置されている状態でミサが捧げられ、ミサ後に出棺して墓地まで行くことになる。それで、ミサ後の赦祷式(故人のために罪のゆるしを願う祈り)の中で歌われる "Libera me"も含めて作曲する場合がある。
さらに、墓地で行われる埋葬式の時に歌われるのが"In paradisum"(=通常「楽園にて」と訳されるが誤訳で「楽園へと」が正しい)である。さすがに墓地までオーケストラや聖歌隊を連れて行くことはできないので、ここまで作曲することはあまりない。ヴェルディも作曲していないが、フォーレのように、演奏会用あるいは作曲者の個人的な宗教的な動機から作曲している場合もある。
☆ ヴェルディの"Libera me"(第7楽章)は、ソプラノの独唱(と合唱)で始まるが、同一音で朗唱風に歌われる部分と半音階の使用が効果的である。やがて、"Dies irae"のテーマが戻り、更に第1楽章冒頭のテーマへと回帰する。これは、全体の構成感を作り出すのに大きな効果をあげている。しかし、ここで終わらずに、曲全体のコーダともいうべき印象的なフーガに入って幕を閉じるのがいかにもヴェルディらしい。
(2) 通常のミサ曲と共通の"Kyrie",
"Sanctus","Agnus Dei"について
通常の「ミサ曲」の「楽章」は、よく知られているとおり、次の5つである。
+Kyrie(あわれみの賛歌): ミサのはじめ に、参加する自分自身の心の準備として罪 のゆるしを願った直後に歌われる賛歌
+Gloria (栄光の賛歌): Kyrieに続いて 神の栄光を讃えて歌われる賛歌
+Credo (信仰宣言〔使徒信経〕): ミサ の前半部分「ことばの典礼」の締め括りに、 信者が自分たちの信仰をあらためて宣言 する部分
+Sanctus〜Benedictus 感謝の賛歌:ミサ の後半「感謝の典礼」の中心部分で神が私 たちにどのような恵みを与えてくださったか を想起し、宣言した直後に歌われる賛歌
+Agnus Dei 平和の賛歌: 「感謝の典礼」 の中でキリストの体へと変化したパン(聖 体)を割く間に歌われる賛歌
以上の5つのうち、死者のためのミサではその性質上、GloriaとCredoは省かれている。また、Agnus Deiでは、テキストの一部が死者の安息を願う言葉に置き換えられている。
(3) 入祭唱・奉納唱・聖体拝領唱とは
「死者のためのミサ」は、冒頭、すなわち入祭唱の最初のことばが Requiem(=安息を)という言葉で始まるため、
レクィエムと呼び習わされている。
入祭唱はどのようなミサにもあり、歌われるか唱えられるのだが、毎日異なるテキストなので、通常のミサ曲では作曲されない。苦労して作っても年に一度使ってもらえるかどうか分からないのでは作り甲斐もないし、仕事としても成り立たない。ところが、人は必ず死ぬし、葬儀もするので、死者のためのミサの場合は入祭唱にも作曲するのである。
これは、奉納唱(Domine Jesu)と聖体拝領唱(Lux aeterna)についても同じことが言える。
奉納唱はミサの後半の「感謝の典礼」のはじめに、パンとぶどう酒を捧げる時に唱えられる祈り。また、そのおわりにキリストの体となったパンをいただく時に唱えられるのが聖体拝領唱である。
☆ ヴェルディは、入祭唱と"Kyrie"を続けて第1楽章として作曲しているが、当時の典礼では儀式の進行上続けて歌うことになっていたようである。ただ、それにもまして、叙情的な入祭唱と躍動感のある"Kyrie"を結び合わせることによって、人間の死と永遠の命、悲しみと希望といった対照的な心の動きを際立たせているのでもある。
☆ "Domine Jesu"(奉納唱:第3楽章)は、後述の"Dies irae"の直後であることも意識して、独唱者だけが、落ち着いた雰囲気で歌いはじめる。"Quam olim Abrahae〜" のメロディーと和声は印象に残る部分であると思う。これも叙情的な"Hostias〜"を挟んで、"Quam〜"以下が繰り返される。
☆ "Sanctus"(第4楽章)では、天使の(あるいは天上の)賛美の歌に地上の我々の声が応答するかのような2重合唱の形式がとられている。誇らしげな曲想はミサの中心部分にふさわしく、最後の"hosanna"につけられた半音階が、魂の高揚を劇的に表現している。
☆ アカペラの、しかもオクターブの単旋律で歌いはじめられる"Agnus Dei"(第5楽章)は、慎ましやかである。3回繰り返されるべき祈りのことばが、ハ長調、ハ短調、ハ長調で歌われる明快な形式であるが、ハ長調には「ふるさとに帰ったような感覚・安心感」があるのがこの曲でも感じられる。
☆ 拝領唱の"Lux aeteruna"(第6楽章)は、神秘的な響きで始まり、ソプラノ以外の3名のソリストによって歌われる。4人目を次に持ち越すことによって曲と曲との関連性がかえって増していることがおもしろい。
(4) "Dies irae" と "Stabat
Mater":
2つの「続唱」
特別な祭日や祝日等のミサには、昇階唱、アレルヤ唱(あるいは詠唱)に続いて続唱が歌われることがある。(但し、現在の典礼では昇階唱は廃止され、代わりに「答唱詩編」が配されている。そして、続唱は答唱詩編あるいは使徒書簡の朗読後に歌われ、それにアレルヤ唱、福音書の朗読が続く。)
続唱は3行ずつ韻を踏む比較的長い詩のかたちである「三行詩」によっている。本来ミサの典礼文の中には続唱はなく、中世以降信心のために作られたものがミサや正式な祈祷書に取り入れられたものである。
レクィエムの続唱(Dies irae)もやはりかなり長い詩なので多くの作曲家がテキストをいくつかの部分に分けて曲を付けているが、その区切り方は人それぞれで、作曲の構想の重要なポイントとなっている場合も多い。テキストの内容としては、最後の審判の様子を想起しつつ、主イエス・キリストにあわれみを願うものである。
ふつう「悲しみの聖母」と訳されている
"Stabat Mater"も、5つしかない続唱のうちの一つで、「聖母マリアの7つの御悲しみの記念日」に歌われていた。(現在は「悲しみの聖母」として「十字架称賛」の祝日の翌日(9/15)に記念日がある。)
☆ ヴェルディの曲の場合、この2つは非常に対照的な曲作りがされている。それが、曲の長さに表れている。一方(3行×17段落+2行×3段落+アーメン)はレクィエムの演奏時間の半分に迫る長さであり、他方は、同じ長さのテキスト(3行×20段落+アーメン)でありながら、12〜3分という短かさである。
"Dies irae"では、ヴェルディは各々の段落のテキストの内容を丹念に表現しようとして、繰り返し歌わせており、冒頭のことばを後半にもう一度繰り返すことまでもしているのである。一方、
"Stabat Mater"では、テキストを唯一度も繰り返すことなく、淡々と詞そのもののリズムを生かしながら作曲しているのが潔い。もちろん、作曲の目的のちがいにもよるだろうが、テキストの受けとめ方そのものから曲作りの構想の違いが出てきたのではないかと思うと、大変興味深いことである。
紙面の都合もあるので、個々の曲・箇所で、ヴェルディがどのような心の動きを反映させているのかを聴き取ることは、お聴きの皆さんにお譲りしたいと思うが、最後の審判の様子が描かれている部分では、荘厳さや恐れなどが大きく表現されていることが特に目立っている。また、そのような表現と、救い・ゆるし・あわれみ・希望などの表現との対照がとくに面白いと思う。
3・4・5月の練習日程
| 31日(土) 栄公会堂 18:15 〜 21:00
※ 17:30 〜 舞台づくり、 21:00 〜 後片づけ
お時間のある方はお手伝いをお願いいたします。
7日(土) リリスホール
18:15 〜 21:30 14日 (土) リリスホール
18:15 〜 21:30
15日(土) 明治公民館 13:15 〜 16:45
※ 強化練習日です。時間が変則ですのでご注意下さい
21日(土) 玉縄公民館
18:15 〜 21:30 28日 (土) 明治公民館
18:15 〜 21:30
29日(日) プラザホール 18:00 集 合
18:30
〜 19:30 発声
(コーラス&ソロ合わせ) 19:30 〜 21:30
※ いよいよコーラスとソリストとの合わせです。集合時間に遅れる
ことのないよう、準備万端整えて練習に臨みましょう!
2日(水) 鎌倉芸術館大ホール オーケストラ合わせ
18:00 集 合(リハーサル室)
18:15 〜 発 声
19:00 〜 オケ合わせ
5日(土) 鎌倉芸術館小ホール オーケストラ合わせ
13:00 集 合(リハーサル室)
13:15 〜 発 声
14:00 〜 オケ合わせ
6日(日) 横浜みなとみらいホール
ヴェルディ“スタバト・マーテル” 本 番
“レクィエム”
(スケジュール詳細は後日お知らせ致します) |
|
![]() 湘フィル通信
湘フィル通信