![]() �Ãt�B���ʐM
�Ãt�B���ʐM
�Q�O�O�O�N�P�Q�����@Vol. 1�R No. �V(Total 167 �O 12)
���s���F2000.12.24 �@�ҏW�F ����
�@�@
�N���X�}�X�E�`�����e�B�[�R���T�[�g![]() �Ãt�B���ʐM
�Ãt�B���ʐM
�Q�O�O�O�N�P�Q�����@Vol. 1�R No. �V(Total 167 �O 12)
���s���F2000.12.24 �@�ҏW�F ����
�N���X�}�X�E�`�����e�B�[�R���T�[�g| �@�F�l�����l�ł����B�P�O���N���}�������N�̃N���X�}�X�R���T�[�g�B�f�G�ȋȂɌb�܂�ĉ��������͋C�̒��A�y�����I���邱�Ƃ��ł��܂����B�搶���̍��C�����w���A�c���̓w�͂͂������ł����A����̕��X�̗����Ƌ��͂����̃R���T�[�g���x���ĉ������Ă��邱�ƂɊ��ӂ������Ǝv���܂��B �@�艉�Ƃ͂܂��ꖡ������A�V���v���Őe���݂₷�����ɂ����Ƃ��銴��������N���X�}�X�R���T�[�g�B���ɂƂ��Ă��̃N���R���́A��N�Ԃ̐g����o���K�A�h���������ƂȂǂ�����A�̂��Ă��܂��B�y���݂ɂ��ĉ������Ă��邨�q�l�������Ă��Ă���悤�ł��B�P�O�N�̊Ԃɍl�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ������������o�Ă��Ă͂��܂����A������悢�`�ő����Ă�����悤�ɂƊ���Ă��܂��B �@�F�l���肪�Ƃ��������܂����B�悢���N���悢�V���I�����}���������B�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�N���R���o�i�j�@A. �R���� |
| ����͓��������Ȃ��Ȃ�قǂ̃`�P�b�g�̔���s���i�v�S�P�W�����j�ł����B���̃`�P�b�g��ɉ����A �搶���A�F�l����̌������܂߁A���Q�R�W�C�O�O�O�������ʂ��Ĉɓ�������Вn�x������֊���鎖�ƂȂ�A�P�Q�^�P�V������\�Ƃo�i�`�[�t�ŋ���֓͂����܂����B |
|
�@�@�����ɂ悩������
���q�l�Ɉ��|�I�Ȑl�C�������̂́A
�@�֓��搶���gAve Maria�h�@�@�R�O�[ �@�i�S���ǂ��� ���Ƃ����l������A�R�V�[���̎x�����W�߂܂����B�j �@�����gHallelujah!�h�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�[ �@�@�@�@�g�L�������͗�����h�@�@�P�X�[ �@�@�@�@�gAve verum corpus�h�@�@�P�V�[ �@�@�@�@�g�c���̑I�ԃx�X�g�R�h�@ �P�V�[�@�@�@�@�@�@�Ƒ����܂��B �g�c���̑I�ԃx�X�g�R�h�̗��ɂ��g���Ȃ�s�h�Ɩ��L���ĉ����������������܂����B |
|
�@�@ �����t��̊��z
�� �Q�O���I�̍Ō������̂ɂӂ��킵�����t��ł����B
�� �ƂĂ��������đf���炵�������B�\�v���m�o�����̎��͈�l�ʼn̂��Ă���悤��
�@�@�f���炵�������B �� �S�ɂЂт��������n�[���j�[�̗��������߂���悤�ł����B
�@�@������ǂ�ł݂����ȁ@ ��܂����B �� ���͂̂��鍇���ł����B�j���p�[�g���l���̂���������Ǝv���܂����A
�@�@�キ������Ƃ��낪�������悤�ł����A�\���A�s�A�m�����炵���A�y�����N���X�}�X �@�@�R���T�[�g�ł����B �� ��������̐�������̂����藧���Ă��āA���̃n�[���j�[���ƂĂ����ꂢ�������B
�@�@�s�A�j�X�g�A�w���҂�������Ă��č��ȉ��t������B �� ���҂S�Q�C��T�ԑO�ɒ艉�ʼn̂����Ȃł����B�Ⴂ�������[����������
�@�@���������܂����B�u���Ȃ�s�v���ꂪ���邩�痈�܂��B �� �i�������Ă��Ȃ��ŁA���[���A������A����݈Ղ��Ă悩�����B���撣���ĉ������B
�� �w�Z�ʼn̂�����A�������肵�Ă���Ȃ��R�Ȃقǂ������̂Œ����Ă���
�@�@�y���������B�@ �N���X�}�X���h���[���Ƃ��Ă��悩�����B���ʂ��f���炵�������B �� �������n�[���j�[�����Ē������肪�Ƃ��������܂����B�Q�O���I�Ō��
�@�@�R���T�[�g�ƂĂ��ǂ������ł��B�A���g���ǂ������ł��B �@�@�P�Ȗڂ��ƂĂ����͂�����܂����B �� ���������̔������n�[���j�[�������ł���̂��y���݂ɂ��Ă���܂����A
�@�@���Ғʂ�ł����B �� �ƂĂ����ꂢ�ȃn�[���j�[�Ɋ�������܂����B���߂Ďf���܂����B
�@�@�A���F�}���A�ł͍��N�̎��̌����̓��X���v���܂𗬂��܂����B �@�@���y�́e���₵�f�ł��B �� ���̃n�[���j�[���f���炵���A���͂�����ƂĂ��ǂ������ł��B
�@�@����Hallelujah�͍��Z�̎��ɉ̂����v���o�[���ȂȂ̂ŁA�����Ă��� �@�@�ƂĂ��������܂����B�@ �� �����搶�̃X�s�|�`���悭����A�y�����m���������ĂƂĂ��悢�B
�@�@�֓�����̃\�v���m�A�S��ł��ꂷ�炵�������B �@�@���߂Ē����� The Lord bless you and keep you �̎��ƋȂɐS�����₳�ꂽ �@�@�v���B�ƂĂ��X�e�L�ł����B �@�@Best 3 �A���ɂ悢�n�[���j�[�������B�@ �� ��������̃t�@���ɂȂ�܂����B���N���������I�I
|
|
�@�@�@���Ãt�B���ւ̈ӌ��A�v�]
�� �w�ǂ̋Ȃ����i�Ȃ̂�����Õ��ʼn̂��ė~�����B
�� �Ãt�B���̃t���C�L���ǂ��o�����t�ł����B���x�̒艉��������ĉ������B
�@�@���ɏ������s�̒j���I�������F��܂��B�@
�� �\���X�g�A�����搶�Ƀ��C�g��������悤�ɂ��ė~�����B���炪�Â��Ďc�O�������B
�� ���i�͈Õ��������������̂ł́H
�@�@�̏��͂̂��鍇���c�Ȃ̂ňꌾ�A���������o�X���~�����ł��ˁB |
�E���t��̋Ȗڂɂ��� �@�s�����v��o�i���t
| �@�Q�O�O�P�N�P������T���{�Ԃ܂ŁA�����P��A�������K�i������K�j�� �g�ݍ��܂�܂��B�����̎c��Ȃ��{�ԁA�����Ď��̃X�e�b�v�ւ̊m���� �育�����邽�߂ɁA�C���������ė��K�Ɏ��g�݂܂��傤�I �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ƃ����ԂɁE�E�E�{�Ԃł��c�B |
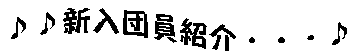 �@
�@| ��ؓo�Ύq����iA�j �@ �֓��搶�̏�M�I�ȃ{�C�g���B�S����Ƀ~�T�E�\�� �� �@�@�̂��グ���݂ȂƂ݂炢�̃X�e�[�W�B���K����{�Ԃ� �@ �ň�т������y�ŁA�F�̗͂����W���Ă��܂��}�G�X�g�� �@�@�̖��́H�E�E�E���B�Y���ꂸ�߂��ĎQ��܂����B �@�o�߂�ł�����낵�����肢���܂��B �A ����̔����̎��Ԃ͂��̂��݂̈�ł��B�{�C�g���� �@�K���������Ƃ������ɔ��f�o������Ǝv���Ă��܂��B�� �@��ɂނ��������ł����A��ꐺ�����ł��悢���ʼn̂��� �@�悤�S�|���Ă��܂��B����ȑf���炵�������̎��Ԃɒc �@�������Ȃ��̂��C�ɂȂ�܂��B |
| �����e���@�@�w�Ãt�B���Ɋāx�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ ���낢��Ȏ����12���X���̊�����J�\���b�N����ł̃N���R���ɎQ���ł��܂��A������K���x��ł���ԂɁA���y�⍇����Ãt�B���ɂ��Ċ��������Ƃ��@�C�y�Ɏv�����܂q�ׂ����Ă��炢�܂��B�����炭�����̂��Ƃ͂��ꂩ������@���ƍl���čs�����낤�Ƃ����C�����Ă���܂��B���Ԃ̂܂Ƃ߂܂łɎ���Ȃ������@�̂悤�Ȃ��̂��ƓƂ荇�_���Ă���ꕶ����e�����Ă��������܂��B �@���K���x��ł���ԂɎ莝����}���قŎ肽���낢���CD���܂����B�o�b�n�E�u���[���X�E�����f���X�]�[���E�t�H�[���E���t�}�j�m�t�E�}�[���[�E�h �{���W���[�N�E�V�����\���E�A���f�X�̉́E�X�R�ǎq������o�I�q�̉́E�X�N���[���~���[�W�b�N�E�j���������X�ł��B���̎��X�̋C���Ɉ�Ԃ҂����肷��Ȃ�I��Œ����Ă����Ǝv���܂��B�����đ����̏ꍇ�����̉��y�͎����K���ɂ��A���������Ă��ꂽ�Ƒ�G�c�ł���������Ǝv���܂��B����͂����炭���x�Ãt�B���ʼn̂��Ȃ��瑼�̃p�[�g��S�̂̉���̂Ŏ~�߂Ă��鎞�Ɠ����̂��̂Ǝv���܂��B�D�ꂽ���͉̂��ł������ł��傤���A�D�ꂽ���������y�̎����͂������K���ɂ����������Ă��ꂽ�̂��Ǝv���܂��B�����Ď��̏ꍇ�ł����A�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂́A�������������̂����肷�鉹�y�̔w��Ɋ����邠�鉽���A����͎�������܂ł����Ă��̉��y���Ă��邻�̈�����x���Ă��ꂽ�傫�ȗ͂̑��݂ł���A������ �̗͂����̊�т�K����^���Ă��ꂽ����ł���ɈႢ�Ȃ��A���y�͘e���ɉ߂��� ���̂��Ǝv���܂����B���y��̂����Ƃ͓���̔��������������Ԃ߂����� �Ƃ͌����܂ł�����܂��A�����ĉ̂����Ǝ��̂���тł��邱�Ƃ������܂ł� ����܂��A�t���I�Ȍ������ɂȂ�܂������y�͍K���Ȏ���b�܂ꂽ���̊�т� ����ɐ[�߂Ă������̂��Ƃ����o�������܂����B���y��̂����Ƃ͋ꂵ�������K ���Ȏ������������R�ɐS�̉��ꂩ�痬��o���K���̗܂ł͂Ȃ��ł��傤���B�Ԉ�� �Ă��邩������܂����y�̖{���͘Q���I�ȉ������Ǝv���܂��B�����炭�ł��� �����ł̊����̔������߂�s���ł��肻�ꂪ�K���^��������̂ƌ������痝�z�_ ���邢�͔��I�ł��傤���B �@����Ɉ�ʘ_�ł����A�����ɂ���I�[�P�X�g���ɂ��批�y�̖{���͌���Ȃ����R�ŁA ��l��l�̌X�����d�����ׂ��ŁA�e�l���t�ŁA�̂������̂͌����đ��������ׂ��ł͂Ȃ��Ɗm�M���܂��B������C�f�I���M�[���玩�R�ł���A�܂�����ɂ����Čl�̉̂�����Ɋ�Â����t��̂͏W�c�ɂ���Č����Č����������Ă͂Ȃ炸�A�@���Ȃ�ꍇ�ɂ��l�����̏W�c�ɑ�����Ɨ~�������A���̌l�̉��y�� ���鐶���i���̂��j�͑��d����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B�����܂ł��Ȃ��n��o����Ƃ��鉹�y�̎��₢�̂��̎w���͎w���҂̎蒆�ɂ���܂����A���̌l�̉̂����낪�w���҂̂���Ƀv���e�X�g����ꍇ���\���L�肤��Ǝv���܂��B���̂Ȃ特�y�͂��̖������ݍ��ޑS�l�I�ȑ傫�Ȃ��̂Ǝv������ł��B�l�ƏW�c�̊W�͐��Ă��藣���܂��A�l�����Ȃ���ΏW�c���������Ȃ��̂��܂��^�� �ł��B �@�Ƃ���ŃI�[�P�X�g���ɂ��捇���ɂ���ۉ��Ȃ��Ƀn�[���j�[�Ƃ������Ƃɓ�����܂��B�����܂ł��Ȃ��D�ꂽ�n�[���j�[�͒����ɂ���̂��ɂ���e���ɂ���ウ�@��������A���R�Nj������ׂ����̂ł��傤�B���t���钇�Ԃ�������Α����قǂ��̗D�ꂽ�n�[���j�[�̔��͂����܂��ƂƂ��ɂ��̌��_���܂��ǂ�������ƌ������炲�ᔻ���o�邩������܂��A�l���̑����ɂ������Ȃ��A�����炭�ł���Ȃ��̂̈�ƌ����C�����܂��B���邢�͍ł�������Ƃ�������܂���B�n�[���j�[�Ƃ́u�W�v�ł���A�N�ł��������炭�o�����Ă���l2�l�����ł��ŏ�̊W�����o�����Ƃ͂����ɑ�ς����l����ƁA���y�I�n�[���j�[�̑n���͐l�ԊW���l���y���_�A�����A���y���Ȃ����Ă͐��܂�Ȃ����Ǝv���܂��B����ȉ��t�ł��n�[���j�[���n���ł�����ꂪ�S�ĂƖ��n���̂��̂̎�����������٘_���o�邩������܂���̂Ńy���f�B���O�ۑ�Ƃ��Ď~�߂�ƂƂ��ɂ��ᔻ�����܂��B �@��������t�ɂ͊y�����Ȃ���Ύn�܂�܂���B���̊y�����ǂ��������A�����̂̏ꍇ�̎����ǂ��������B������\���l���Č��鉿�l��������Ǝv���܂����A�����搶�ɂ��������Ă����������Ƃɂ��y���f�B���O�̏�Ԃł��B�搶�̖w�NJ����ȃe���|���̂���K�v�ɂ��ď\���Ȃ��w����ʂ��A�܂����y�̊����̍Ő�[�ŁA�ő���̓��I�ɏ[���������̂�^���ĉ�����w������K���͏Ãt�B���̓��T�������Ǝv���܂��B�����ĕ����搶�����ƂɍT���Ă�����̂͐S��������ł��B�D�ꂽ�s�A�m�ɂ��������Q���Ă��܂��B �@������q�̐�m���J�\���b�N����ɂӂƑ��ݓ���܂����B��������l������ ���ċF���Ă��܂����B���ʂɑ傫�ȏ\���˂�����A�e�̃}���A�摜�ƂƂ��ɁA�}�� �A�l�̑O�ɐ�����ꂽ�����ȕS���̉Ԃ���ۓI�ł����B�Ãt�B���̉̂����̕S���� �������킵������̂悤�ɂ����Ɗ�����J�\���b�N����̗�q���ʼn̂��邱�� �ł��傤�B �@���A���ēV��R���Ŏ��R�ȂƂ��ĉ̂��������t�v�̎��ɑ咆��������Ȃ����u�H�̏���v�̃����f�B�[�����肻�̂��̂ł����ƂĂ���D���Ȃ̂Ō������݂Ȃ��珬�����I���܂��B �Q�O�O�O�D�P�Q�D�R�@�@�@�@�@�@�@ ���ӂ����߂ā@�@�@�O�Y�M�Y |