���s���F2000. 8. 18 �@�ҏW�F ����
![]() �Ãt�B���ʐM�Q�O�O�O�N�@�W����Vol. 1�R No.�R (Total 163 �O 12)
�Ãt�B���ʐM�Q�O�O�O�N�@�W����Vol. 1�R No.�R (Total 163 �O 12)
���s���F2000. 8. 18 �@�ҏW�F ����
�@�c�����������\���グ�܂��B�l�͊����ɂ͂��Ȃ�ς����邻���ł����A�����ɂ͎ア�̂������ŁA�̒��������Ă�����͂ǂ����������������B�ł�����ς���{�̉Ă͏����Ȃ�������I���ꂾ�������n������G�߂��y���߂���čK�����Ȃ��Ǝv���܂��B���̓N�[���[�����B�N�[���[�̌��������������̒��ɂ������Ă���ƁA�G�߂��������Ă��܂����悤�ȋC�����āA�O�̏����̒��֖߂�Ɖ����z�b�Ƃ��܂��B
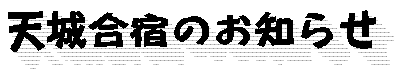 �s ���̂Q �t
�s ���̂Q �t
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||
|
|
�@ | �����e���@�@���F���f�B�I�H �@�@�@�@�@ �@�@�@ �` ���N�B�G�����̂����ƂɂȂ������f�̒����� �` �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �a�D��@�Č� �@�{���́A���̋Ȃ������ł����B���R�[�h��b�c����x�Ƃ��Ēʂ��Ē������������A���̏�y����������̂����Ƃ��Ȃ��������́A���̋Ȃ����F���f�B�I�Ɣ��\���ꂽ���ɂ͍��f�����܂����B���������̋Ȃ����Ȃƌ����鏊�Ȃ������搶�̎w���ʼn̂��A���邢�͗����o���邩���m��Ȃ��Ɩ]�݂������A���K�ɎQ�������̂ł����A�E�E�E�B�Ƃ��낪�A�y������ł��ˁA���ꂪ�I���{�l�̊��o�ł́u���N�B�G���v���y�����Ƃ����͕̂ςȂ̂ł��傤����ǁA�����h�C�c�E�I�[�X�g���A�n�̉��y���艉�t���Ă����Ãt�B���ɂƂ��Ă��A����͑傫�Ȍo���ɂȂ肻���ł��B���A�̂��Ղ��B�̂����Ƃ̊y�����A�����o�����Ƃ̉����𖡂킹�Ă����B�x�[�g�[���F���̋ꂵ��ŁA�ꂵ�ݔ����ď����Ă䂭���y�O�Ɍo���������������A���K�̉ߒ��ł��̋Ȃ����[�������Ƃ��Ă䂭���Ƃ��o����̂��Ə��X�S�z�ł͂���܂�����ǁB���ۉ̂��Ă��Ēp�����������^������܂��ˁB�����搶���x�X������Dies irae �̂R�R�U���߂̃o�X 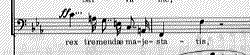 �@��A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@��A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@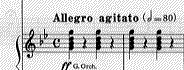 �`���́@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �`���́@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@���������p���������B �@����A�����̔������͂������ɃI�y���̃��F���f�B�B�������C�ɓ����Ă���̂́A�R�W�R���߂���� Recordare �̓�d���B������\���X�g��l���ǂ�ȉ̂����Ă���邩�ƂĂ��y���݁B�u���̊nj��y�������Ɍ��I�i�s�ƕs���̂��̂ɂȂ��Ă��邩��m�邱�Ƃ��o���邵�A�܂�������ꍇ�A���R�ɉ̎�ɉ���F��������悤�ɏ�����Ă���E�E�E�v����̓��F���f�B�̃I�y���ɂ��ď����ꂽ���͂̈ꕔ�ł����A���R���N�B�G���ɂ����Ă͂܂��āA�]�����d�˂Ă��̂����ɉ��������킹�鎖���Ȃ��̂��A�e�̂��f�e�̂킹��f��m��s�������l�̍�i������ł��傤�B�����炱�̋Ȃ̑S�̂��ǂ̂悤�ɑn��グ���Ă䂭���A���ꂩ��̗��K�̈��������҂��A�y����ł䂱���Ǝv���Ă��܂��B �@�Ƃ���ŁA���̌��e�̓��F���f�B�̂��Ƃ������ĉ������Ƃ̒ʐM�ҏW�҂̈˗��ŏ����n�߂����̂ł��B�������A���N�B�G���̉���͊y���ɔ��ɗǂ�������Ă���̂ŁA����ȊO�̎����A�Ƃ������ł����B���ƂȂ������Ă��܂������̂́A���F���f�B�̂��Ƃ��A���̃I�y���̂��Ƃ��w�ǒm��Ȃ����ɂ͖{��ǂ�ł��̎�������������Ȃ��B�ȉ��͂���ȕ��͂Ȃ̂ʼn䖝���ēǂ�ʼn������B �@Giuseppe Fortunio Francesco Verdi �͂P�W�P�R�N�k�C�^���A�̊����������R�[�����̏����ȏh���̒��j�Ƃ��Đ��܂�܂����B���e�ɓ��ɉ��y�̑f�{����������ł͂Ȃ��炵���̂ł����A���̉Ƃ��h�ɂ��Ă��������y�t�̈�l���c�����F���f�B�̑f�����������ĕ��e�ɑ��q�����y�̓��ɐi�߂�悤�������Ă���܂����B���ۂ��̏��������F���f�B�̈ꐶ���x�z���A��̐��̐l�X�ɔނ̐��X�̃I�y����i���₷���ƂɂȂ����̂ł�����A���y�������邠����l�ɂƂ��āA����͋M�d�ȏo���������ł��B �@�V�˂̎����瑺�̋���̃I���K�j�X�g�ɂ��ĕ����͂��߂P�O�˂̎����̃I���K�j�X�g���S���Ȃ����̂ŁA���e�͋ߍx�̏��s�s�u�b�Z�[�g�̖��m�o���b�c�B�ɗ��ݍ��݁A���F���f�B�͂��̒n�œ����Ȃ���n�C�X�N�[���ɒʂ����ƂɂȂ�܂����B�܂��o���b�c�B�̎�ɂ���u�b�Z�[�g�y�F����̃����o�[�ƂȂ�A�o���b�c�B�̖��}���K���[�^�Ƃ̃s�A�m��d�t�Ől�X�̂������������Ƃ�����܂����B�����ł��A���̓�l�͂��̌�[�����Ɋׂ�̂ł����A�����Ɏ���܂łɂ́A�܂����N������̂ł��B�y�F����I�[�P�X�g���̎w���҂ł������v�����F�W�̓��F���f�B�̍˔\�ɒ��ڂ��A�S�N�Ԃ��̏���Ƃ��ē������I�[�P�X�g���̌m�Â��ς����肵�ċ���܂����A���̊Ԃɂ����F���f�B�͑�R�̍�i���c�����悤�ł��B�������c�O�Ȃ��Ƃɂ��̊y���͈⌾�ɂ��S���ċp����Ă��܂����Ƃ������Ƃł��B �@�o���b�c�B�̓��F���f�B�̍˔\�������]�������w�����ă~���m�̉��y�@�Ŋw�ׂ�悤���v����Ă���܂������A���̍��������ł��������A�}���K���[�^�ƃ��F���f�B���������������C�������������̂����m��܂���B�Ƃ����ꃔ�F���f�B���~���m�ɏo�������͔̂ނ��P�X�˂ɂȂ�P�W�R�Q�N�ł����B�~���m�ł͉��y�@�̔N�ߐ����̂��ߓ��w�o���Ȃ��������̂̌l�I�Ɏw���҂Ŋnj��y�@�̑�Ƃł����������B�i����A��ȂƊnj��y�@���w�сA��b��g�ɂ��܂����B���t�v�����F�W���Ȃ��Ȃ������ƃ��F���f�B�̓u�b�Z�[�g�ɖ߂�y�F����̎w���҂ƂȂ��ĂP�W�R�U�N�T���}���K���[�^�ƔO��̌������������P�W�R�V�N�ɂ͏��̎q���A���N�ɂ͒j�̎q���Y�܂ꂽ�̂ł����A�K���͒����������A�킸���P�˂S�����Œ�����S�����Ă��܂��܂��B�y�F����̌_����������A���F���f�B�͐V��I�y���u�T���E�{�j�t�@�b�`���̔��݃I�x���g�v�������A�ȂƎq���Ƌ��ɉi�Z�̌��S�Ń~���m��K��܂��B�X�J�����̎x�z�l�������̉����ɂ���ăI�y���㉉�ɐ����������F���f�B�͒����ɃI�y����Ȃ̈Ϗ������̂ł����A���̑O��Ɏq���ƍȂ����ŖS�����Ƃ����s�K�Ɍ�����ꂽ�̂ł����B����Ȓ��ł̈Ϗ���i�̏o�����ǂ������Ȃ��A�㉉�͕s�����ɏI���A�ނ͈�w�̎��ӂ̒�ɒ��݈ꎞ�͎��E���l����قǂł����B �@����Ȓ��Ŕނ��܂��Ă��ꂽ�̂��A�������ƃv���}�E�h���i�̃W���[�b�s�[�i�������̂ł��B�ƁA�����܂ŏ��������Ŏ��́A�}���K���[�^�ƃW���[�b�s�[�i�̏ё����ǂ����Ă��������Ȃ�܂����B���F���f�B�������A�����Ďx������l���ǂ�ȏ����������̂��m�肽���̂ł��B���������A�}���قɂł��s���Ă݂܂��傤�B �ł͌��ʂƂ��̌�̂��Ƃ͖��A�����ŁB�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�Â��j �@ | �@ |