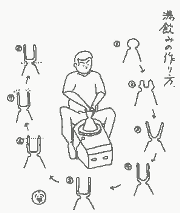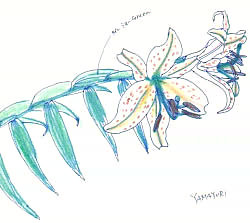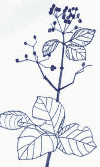ロクロの名手と言われる陶芸家の作業を見ていると、まるで舞を舞っているかのような滑らかさで、動作が続いていきます。でも、ひとつひとつの工程は、着実にこなしている。長い歳月のうちに習得した、最も無駄のない動きで、しかも要所要所で所作がぴたりと決まる。
見ていても気持ちがいいのですから、本人はさぞや楽しいことでしょう。僕もいつかはその域に達したいものです。
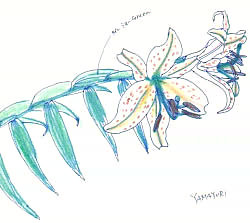
名人技と比較するのはおこがましいのですが、初心者には初心者なりに上手になったことが分かる瞬間があるものです。僕の経験でいうと、「あ、コツをつかんだ」と実感したのはロクロを始めてちょうど百時間目くらいのときです。指の動きに粘土のほうが付いてくる感じで、するすると伸びて薄い湯飲みが挽けた。それまでどう頑張ってみても肉厚でドテッとしたものにしかならなかったのに、余分な力が入らず、ほんとうに指と粘土が一体になったような快感。
K子さんも、ぜひ味わってください。教室で週に一回、二時間として、一年くらいかかる計算になりますね。ほんとうに、ある日とつぜん天使は微笑みます。粘土が薄く挽けるということは、形がキリッと締まります。それまで作ってきた器が、急にだらしなく見えてきたものです。
じつは僕の場合、「百時間目の快感」は半年ほどで訪れました。もちろん才能です、と言えればいいのですが、家にロクロを買ってしまったから。教室で初めてロクロを体験した、その週のうちにメーカーに注文しました。これは一生の趣味になるぞ、という確信があったから。
十万円は確かに趣味に使うには大金ですが、構造が単純だから十年は持つと、メーカーの人も保証しました。本気の趣味を始めるときには、「もったいない、モトを取ってやるんだ」という思いも、あんがい大切なのではないでしょうか。
さて、ロクロを置くスペースが問題でした。我が家はご存知のようにマンションです。雨のかからないベランダの、一・五平方メートルほどを使わせて頂きたいと当局に願い出た。汚くしないという条件で交渉成立。ロクロ、土練り台、粘土の保管箱などを並べて、僕のベランダ陶芸が始まりました。真冬の深夜のロクロ作業を思い出すと、いまでも胴震いがしてきそうです。ほとんど遭難寸前になるまで我慢して、風呂に飛び込んで・・・。
そんな無茶がやれたのも、やはりロクロは楽しいからですね。昨日より今日、今日より明日と、自分が上手になってゆくのを、目の前の形として見ることができる。こんな体験は、大人になるとなかなかできません。冬のしばれるベランダ陶芸はK子さんには勧めませんが、「習うより慣れろ」という言葉は、月並みではあっても真実だと思います。
ロクロの名人の話をもうひとつ。名人が手早く挽くのを見ていた人が言いました。「あんな二十秒ほどでできるものが、どうして何万円もするんだろう」それを耳ざとく聞きつけた名人は静かに言った。「二十秒で出来たのではない。五十年と二十秒じゃ」僕の大好きな話です。

○ ロクロに関するアドバイス
その1 ドロ汚れは思ったほどではありません。
ドベ受けの付いたロクロなら、ほとんど周りには飛び散りません。ちなみに、単身赴任中の僕は、マンションのフローリングの床の上に置いています。下に工事用のビニールシートを敷き、用心のために周囲の壁にビニールを貼りました。下は汚れていますが、壁の方は腰の高さ以上にはドベはとんでいません。
その2 湯飲み1000個
「湯飲みを1000個作れば、いちおう一人前と言われているよ」僕の先生はそう言いました。湯飲み作りで、ロクロ技術の基本はすべてマスターできます。
「湯のみがキチンと作れるようになれば、鉢でも皿でも徳利でも思いどおりだよ」
よーし、ということで湯飲み作りにいそしんだかというと、さにあらず。湯飲みばかり作るのは退屈だし、だいいち持って帰っても誰も喜ばない。皿や鉢なら食卓が賑やかになります。よし、こんどはサラダボールを作ろう。野菜のグリーンに合うのは黄瀬戸の釉薬だな。絵付けは真中に蕪(かぶ)を大きく描こうか・・・。
かくして、ロクロの上達はそっちのけで、いろんなものを作りました。楽しかったし、それで良かったと思っています。何年かのちに、ロクロの下手さに気がついて、集中的に湯飲みを作りました。百は勢いでできる数字ですが、千はなかなかです。その道のことには暗いのですが、「千人切り」も想像するに、おそらく苦行に近いものでしょう。
その3 自宅用を買うのなら
もしも、自宅でも練習したいなら、ロクロは教室のと同じメーカーの同じ機種を選びましょう。機械というのは自分の手の延長ですから、使いこなすためには慣れることがいちばんです。カタログを取り寄せたりして、目移りもしたのですが、同じものを選んで良かった。
その4 ロクロまわりの道具について
ロクロを挽くときに必要な道具を挙げておきましょう。
ロクロを挽くことを「水挽き」とも言うように、粘土を水で濡らしながら指との摩擦を少なくして形成します。だから、まず、水を入れる手桶。プラスチックのもので十分です。
挽いた器の縁を水平にカットするための「弓」。
縁をなめらか、そして強度を持たせるために粘土を締める「鹿のなめし皮」。
挽いた器を切り離すための「切り糸」。
このくらいのものです。
形を整えるためにコテを使うこともありますが、あえて挙げないでおきます。「手でできないものが、その先に道具をつけて出来るわけがない」。僕の教室時代の先生の名言です。
ロクロを始めると、次から次に欲しい道具が増えてきます。買おうかどうしようか迷ったときには、ぜったいに買わない。そう決めています。陶芸用品の店をのぞくと道具がささやきかけてきます。
「ラクにきれいな形が作れるよ」
「高すぎる?ウデをあげたいなら、投資しなくちゃ」
道具たちのキャッチ・セールスに陥落して買ってしまったあれやこれ。
一度も使っていない道具の山は、ああ、見るのもいまいましい。
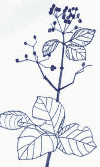
|