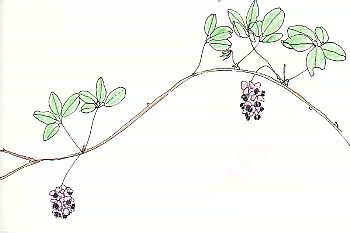| ソワサント 1999・JUNE 陶芸を始めたK子さんへの手紙 連載第二回 |
| 「手と土の出会い」 | 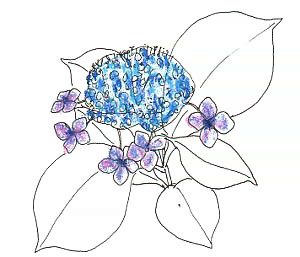 |
K子さん、処女作の湯飲みは焼きあがりましたか。 ところで、その「処女作」について、ちょっとした事件がありました。ソワサント創刊号の新聞広告に新聞社のほうからクレームが付いたのです。「処女作で乾杯」を見出しとして載せようとしたところ、「処女」は問題があるから表現を変えて欲しいと。 編集部から話を聞いて唖然としました。そのあとで大笑い。「処女」という文字を見ただけでモーソーを逞しくしてしまうなんて、なんと感性豊かな方がチェックをなさっているんだろう。 社会環境の変化によって、「処女」は絶滅のおそれがある希少種に指定されようとしている昨今ですが、「処女作」という日本語もまた絶滅の危機にさらされているのですね。保護のための運動を始めねばと本気で考えているところです。 さて、今回は粘土との出会いについて書きます。教室で初めて粘土に触ったときの感触を思い出します。手にしっくりなじんで、指に加えた力そのままに自在に形を変える。それまで味わったことのない快感がありました。あ、今回のタイトルは「土の快感」にしましょうか。「快感はちょっと問題が・・・」なんて、また言ってくるかな。今日は、どうも話がそっちに行きがちですみません。 粘土はベタッとしたものという先入観があったのにサラッとしている。指にピタリと添って、しかもスッと離れる。僕のまわりの人たちを見ていると、陶芸にハマるかどうかは、土に初めて触ったときに「快感」があったか、「不快」と感じたかで決まるようです。 手を動かしながらボーとした時間を過ごす。これが僕にはとても楽しい時。
粘土をひも状に伸ばして、円を描きながら上に上に積んでゆく、いわゆる「輪積み」で壺を作るとき。また、「掻き落とし」という僕の好きな技法があるのですが、粘土の上に掛けた白化粧を削り落としてゆくとき。これらはじつに単調な作業で、同じ動作の繰り返しです。
手の反復運動は脳のどこかの部分を開放するのでしょう。記憶の糸の結び目がスルッとほどけて、連想が脈絡もなく広がります。 とはいえ、いつも静かな気持ちでやるには、人間としての修行がまだまだ足りません。メタンガスのようなあぶくも、ブスブスと水面に浮かんできます。「荒練り」という、粘土の水分を均一にするための土練りなどは、まるで格闘技です。気分もいきおい攻撃的。「クッソー!」「バカタレガー!」などと口走りながら粘土のかたまりを思いっきり土練り台にぶつけている。仕事上のトラブルなんかを思い出しているんですね。途中で気がついて、いかんいかん、と。
☆ 粘土に関するアドバイス その1 自分の好きな土を見つけよう 僕の場合も、教室時代は信楽の粘土でしたが、今は唐津も使っています。いわゆる「さくい土」で、粘り気が少なくて腰がないので難しい。初めて使ったときには、ロクロの上の粘土を使いきっても湯飲みひとつできなかった。途中でちぎれて、つぶれたアンパンのような失敗作の山ができました。
その2 土練りの練習 粘土を手前に巻き込むように押し揉みして、両側にはみ出してくるのを内側に折り込んで、向きをかえて繰り返す。教室ではたいていこの方法を教えているようですが、僕が唐津で教わった方法を教えましょう。 まず、両手の親指の先をくっつけて粘土を上から押さえます。他の指で粘土を両側から挟んで、くっつけた親指で粘土を三、四ヵ所切ります。この段階では、まだ粘土は下の部分でつながっています。つぎに、切れ目の入った粘土を二つに分ける。一方を持ち上げて、残りの粘土に思い切りぶつけます。 このとき、「コノヤロー!」などと声を掛けると、なかなか楽しい作業になります。三十回も罵詈雑言を繰り返せば、均一な粘土の出来上がりです。教室には電動の土練機があるでしょうから、この工程は省いても構いませんが、もったいないなあ。あの、ストレス解消の妙技を機械に取られてしまうなんて。 ○ 菊練り これは、ちょっと言葉では説明しにくいので、教室で教わってください。「菊練り三年」などと言われますが、三ヶ月もすればサマになってくるから大丈夫。 パン屋さんやうどん屋さんの粉の練り方と同じだそうで、そう言えばどちらも空気を抜く必要がありますね。空気が入ったままではロクロがうまく挽けないし、窯の中で破裂することもあるので菊練りは念入りに。 知り合いの女性は味噌で練習したそうです。「でもダメ、ベッチョベチョになっちゃうから」凄まじい向上心には頭が下がりますが、やはり本物の粘土で練習しましょう。五キロほどなら教室でも分けてくれるでしょうし、陶芸材料店から宅配便で送ってもらえます。 その3 土練り台 グラグラしない、しっかりしたテーブルが必要です。上から力を加えるので、作業しやすいのはちょっと低めのもの。僕は日曜大工の店でベニヤの合板と、足になる太めの角材を買ってきて作りました。 その4 保管箱 粘土は空気に触れると乾いてしまうので、ビニール袋ごとクール便の発泡スチロールの箱に入れておきます。僕の「ベランダ陶芸」の時代は、粘土も少量で済んだのでこれで十分でした。 |