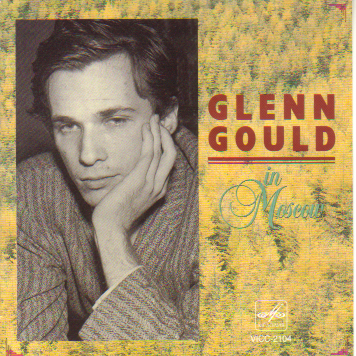モスクワ音楽院でのリサイタルの曲目は恐るべきものである。ベルグ「ソナタ」、ウェーベルン「変奏曲」、クシェネック「ソナタ3番(1、4楽章)」、当時のソビエト連邦では考えられない曲目である。今でこそベルグやウェーベルンは古典の扱いであるが当時はまだバリバリの現代音楽で、それらによる演奏会をソビエトで行うのはとんでもない行動であった。事実、演奏中音楽院の教授と思しき人物が数名会場を立ち去るということで抗議の意を表したということである。
しかし、グールドの演奏は素晴らしい。公式録音とは随分違う演奏である。特にウェーベルンの作品解説の際ピアノで弾かれる「パッサカリア作品1」、「変奏曲」を聴くと如何にグールドがこれらの作品に対する深い理解と評価を下していたかが窺える。そしてアンコール「フーガの技法(1、4、2番)」、「ゴールドベルグ変奏曲(抜粋)」バッハ作品の集中度の高い演奏は現代作品では少々ざわついていた会場の雰囲気が豹変するのが感じられる演奏である。「コントラクンプトゥス1番」末尾の休符での緊張感を聴くからに当時のモスクワの聴衆の驚きが伝わってくるようである。 |
|
|
|
|
|
一方ストックホルムの演奏も名演である。協奏曲はモーツァルトの24番とベートーヴェンの2番とグールドのお気に入りのもので、ソロのほうもハイドン「ソナタ49番」、ベートーヴェン「ソナタ31番」、ベルグ「ソナタ」と特に愛着のある作品である。ベルグはアメリカデビューリサイタルの中にも入っているし、更にはデビュー直前の1951年プライヴェート録音にも入っているからよほど好きな曲だったのだろう。ハイドンも公式録音が2種ある愛好曲であるが、軽やかな明るい演奏、このライン上でモーツァルトのソナタを録音していたならばもっと広く名盤となっていたのではなかろうか。ベートーヴェンでの繊細な音色、これも公式録音では聴くことの出来ないものである。ベルグのソナタは1小節目の和音の清澄な儚い音色、音が鳴ると同時に溶けていく氷のような演奏はやや厚ぼったい音のベルグのソナタとは思えないようである(なおストックホルムでは前半の繰り返しが守られている)。
私はこれらの録音を聴くとグールドはいわゆる正攻法の演奏、少なくとも奇矯に聴こえない演奏で恐るべき完成度に達していたのであると確信している。ライヴではグールドの素直な一面が見えるような気がする。レコーディングに於けるグールドは韜晦癖が強いのではなかろうか。 |
| さて以上がグールドのライヴについてであるが、この人はテレビでの演奏番組(ヒンデミットのフーガ、ウェーベルンの「変奏曲」が秀逸)や自作曲(「弦楽四重奏」「そんなにフーガが書きたいの?」)、ラジオドキュメンタリー(「北の理念」)、評論(「ペトラ・クラーク論」)等などいくらでも話題に事欠かない人である。それだけに多くの人を引き付けて止まないのであろう。ピアノを離れたグールドに接するのも一興であろう。 |