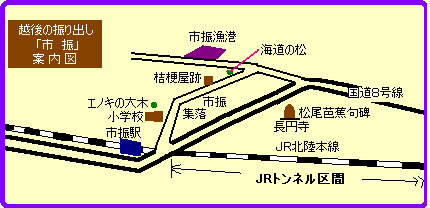
JR青海駅から車で約30分、JR北陸本線「市振駅」下車徒歩約5分
市振は、波立つ日本海と山の岩肌が迫る間の、奥行き200〜300m
延長約2kmの小さな集落で頭上を国道8号線か走っている。地理的に
青海町の中心部へ来るよりも県境の境川を越えて富山県へ出かけた方
が近いという感じです。
市振はその昔、越後と越中の国境で親不知・子不知の西の入り口であり
加賀街道で越後の重要な起点であった。
市振に関所が設けられたのは、寛永元年(1624年)頃で高田城主や幕府
代官の管理であったが、明治2年(1869年)に廃止されている。その場所は、
現在の町立市振小学校が跡地で、校庭にあるエノキの大木は、当時から
のものと云われている。このエノキは昭和49年4月、町の文化財・天然記念
物に指定されています。
・・・ 一つ家に遊女も寝たり萩と月 ・・・集落の中ほどに青海町指定文化財の
芭蕉の宿・桔梗屋跡がある。俳人松尾芭蕉は元禄2年7月、奥の細道の
旅すがら一夜の宿を桔梗屋で取り、同宿した遊女との情景を詠んだ名句を
ここで残されたと云われています。芭蕉直筆の句碑は、長円寺境内にある。
市振の東の入り口にそそり立つ老松は、樹齢200年と云われる「海道の松」
遥か遠方からも眺める事が出来る。その昔、東からの旅人が親不知の難所
を命からがら渡り、この松を見たときには。安堵に胸をなでおろした事だろう!
古来から、加賀街道の交通の目印として旅人に親しまれていた松である。
参考資料・・・・・青海町自然史博物館 発行 野紫木 洋 著
「青海町ふるさと探訪」より引用