![]()
�摜���N���b�N����ƁA�A�}�]���E�R���̍w���y�[�W�ɍs���܂��B
���̃y�[�W��ʂ��čw�����ꂽ�ꍇ�A�x���z�̈ꕔ�́A�O�A�e�}���̐��Y�Ҏx��NGO�A�u�݂�ρv�̊��������ɒ���܂��B
| ���P�s�{�F�@�m���t�B�N�V�����i�}�������֘A���܂ށj | |||
| �A�� �w�N�g, 2003, �wtextiles from guatemala �O�A�e�}���̐D ��p�����كt�@�u���b�N�E�R���N�V�����\Fabric Folios�V���[�Y�x, �ߓ� �C ��, �f�U�C���G�N�X�`�F���W | |||
 |
2003, �w�}����Z���� �����Ǝ������߂����v���W�F�N�g�x, IMADR�]MJP�O�@�e�}���v���W�F�N�g�`�[�� (�ҏW), �����ʍ��ۉ^�����{�ψ��� |
||
| 5�N�Ԃ̃v���W�F�N�g�̋O�Ղ�U��Ԃ�Ȃ���A�}���̐l�X�Ɓu�Ƃ��ɂ���v�v���W�F�N�g�Ƃ͉�����₤�B���E�̐�Z�����ɂƂ��ċ��ʂ̏d�v�ȉۑ�ł���A�����Ǝ����A�J���A�����ւ̕������ʂɂ��Ă̎�����_�l���f�ځB �i�uMARC�v�f�[�^�x�[�X���j |
|||
 |
�R�E, �}�C�P���E�c, 2003, �w��}�������x, �i ���� �� , ���J�� �x�v ��j, �n���� | ||
 |
���� ���`, 2003, �w�}������ �V���Ȃ�^���\��ǂ��ꂽ�Ñ�_�b�w�|�b�v�E���t�x�x, �u�k�� | ||
 |
�}���A �����Q�[�i, �w�}�� �}���������T�x, ���X ���m, �A�c �o�@��@�n���� | ||
 |
�ÒJ�j�M, �w�u�g�E�����R�V�̐S�v�|�}���̐l�X�ƂƂ��Ɂ|�x, 2002, ���m�V���� | ||
 |
���� ����, �}�[�e�B���A�T�C���� , �O���[�x�A�j�R���C , 2002, �w�Ñ�}������㎏�x, ���J�� �x�v, ���]���a�q, ��������, �n����, | ||
 |
�r�c����, 2001, �w���H�̈�Ðl�ފw�x, ���s�F���E�v�z�ЁD | ||
 |
���c �D�M, 2001, �w�������I�ߑ�ւ̉���\��������錠���͒N�ɂ���̂��x �p�����������q1�r�@�l�����@ | ||
 |
A�E���V�[�m�X����, 2001�i���Łj, �w�}���_�b�\�|�|���E���t�x, �щ��i�g��,�@��������BIBLIO, �������_�V�� | ||
 |
���j�I�L���̉v���W�F�N�g��, 2000, �w�O�A�e�}���@�s�E�̋L���x, �����F��g���X�D | ||
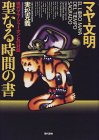 |
���� ���`, 2000, �w�}������ ���Ȃ鎞�Ԃ̏��\����}���E�V���[�}���Ƃ̑Θb�x, ���㏑�� | ||
 |
���c �`�Y, �w���ق̌Ñ��� �}���E�C���J�����̓��x �N�H�[�N�ҏW�� (�ҏW), �u�k�Ѓv���X�A���t�@���� | ||
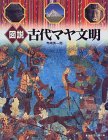 |
���� �G��Y, 1999, �w�}�� �Ñ�}������ �ӂ��낤�̖{�x, �͏o���[�V��, , | ||

|
�n�[�o���A�W�F�j�t�@�[�E�j, 1999, �w�E�C�̉˂����\�O�@�e�}������ƃ}����Z�����E�Q�����̐킢�̋L�^�x�@���� ���q, ���� ���u, ���� ����, ���� ���b�q��, ����o�Ŏ� | ||
| �O�@�e�}���R���̍��Ƒ�ʎE�C�ɑ��A�댯�Ȋv���^���ւ̎Q����I�������l�X�̌��ӂ�80�N�㏉���̓���̗l�q�A���݂̐����A�킢�����������ω��Ȃǂ��A���������̒��ɐg��u�����č��ٌ̕�m���Ԃ�B�i�uMARC�v�f�[�^�x�[�X���j | |||
 |
���� ����, 1998, �w�}�������͂Ȃ��ł�?�\��݂�����Ñ�s�s���S�̗��j�x, �j���[�g���v���X, | ||
| ���Ē����A�����J�ɑ��݂����}�������͂Ȃ��ł�ł��܂����̂�? �L�x�Ȍ��n�������т�y��ɂ��āA�}�����s�s�̐�������}�������̉�ǂ܂ŁA�Ñ㕶���~�X�e���[�̐��E���₳�����Љ��B �i�uMARC�v�f�[�^�x�[�X���j |
|||
 |
����O�}�q, 1998, �w�j�Ղ̖������@�}�����������^�x(���o�ϑ�w�����p�� ��R�R��), �i�Ёj�S�����{�w�m�� | ���̖{�͌���AMAZON�ł͈����Ă��܂���B bk1�ōw�����Ă��������B |
|
 |
�n�[�x���A�W�F�j�t�@�[�E�j�@1998�@�w�G���F�����h��{�����x�@�|�ё��@�V������ Harbury, Jennifer K.,SERCHING FOR EVERARDO,1997 http://www.personal.engin.umich.edu/~pavr/harbury/archive/ |
||
|
|
�ɏ]���q, 1997, �w�O�A�e�}����Z���̏������|���S�x���^�E�����`���E�Ɩ��剻�ւ̕����x, ���E�l�����p��17, ���Ώ��X |
||
| �O�A�e�}���̏��ɂ��Ęb�����Ƃ́A�s���ƍ��ʂɂ��Ęb�����ƁB�Љ�ʼnƒ�œ�d�̍��ʏɂ����ꂽ�ޏ��������A�ǂ�قǂ̊��ƌ��𗬂����̌o�ςɍv���������A����邱�Ƃ̂����ɏ��Ȃ������������������߂Č��B | |||
 |
�ߓ��~�q, 1996, �w�O�A�e�}������j�F��Y����}���̍��x�@�ʗ��� | ||
|
|
��q�z�q, �㑺�p��, �ύ�m��, �V��u�ێq, 1994, �w��Z�����������S�x���^�E�����`���E�̒����x, ��g�u�b�N���b�g(No.342), ��g���X | ||
| ���ې�Z�����N�̍��A�e�P��g�ł���A1992�N�x�̃m�[�x�����a��҂ł��郊�S�x���^�E�����`���E�B�u��Z�����̌����v���咣�������Â���ޏ��̊����ƈӋ`���l����B | |||
|
|
���S�x���^ �����`��, 1994, �w��n�̋��с\�O�A�e�}����Z�����̓����x, �_��C��, �؏��X | ||
|
|
��� ���m, �w���S�x���^�E�����`���E�\��Z�����̌ւ�Ɗ�]�x, �Љ�V��u�b�N���b�g,���{�Љ�}�@�֎��� |
||
|
|
���c�`�Y, 1990, �w���z�ƌ��̐_�a�@�Ñ�A�����J�����̔����x, ��������, �������_�� | ||
|
|
NHK��ޔ�, 1990�wNHK���E��|�I�s�R�i�����A�O�A�e�}���̐D���ҁj�x, ���{�����o�ŋ��� | ||
|
|
�u���S�X�A�G���U�x�X, 1987, �w���̖��̓��S�x���^�E�����`���E�i�}�����L�`�F���C���f�B�I�����̋L�^�x�@, ���������, �V���� |
||
|
|
�{���ƕv, 1985, �w�}���l�̐��_���E�ւ̗��x�@��㏑�Ё@ |
||
|
��������, 1982, �w�}�������������x, �����V��, �������_�� |
|||
| ���E�N���W�I����E��, 1981, �w�}���_�b�i�`�����E�o�����̗\���j�x, �]���F�Y��, �V���� | |||
| �f�B�G�S�E�f�E�����_, �u���J�^�������L�v, �щ��i�g��, �w��q�C����p���x��U��13, ��g���X | |||
| �R�E, �}�C�P���E�c, 1967, �w�}���x, �i���c�A������j, �w���� | |||
���w�E����
���s�K�C�h�E���s�L
| ���P�s�{�F�@���s�K�C�h�E���s�L | |||
 |
�e�n �R��, 2003, �w�X�^�X�^�������L�[�^�\�O�A�e�}���̌��L�x, �V���� |
||
| �Ҋ� ����, 2001, �w�}��/�O�A�e�}��&�x���[�Y�\�ʐ^�ł킩���ւ̗��x, ������ | |||
 |
�R�{ �T��, 2000, �w�����Ȃ��I���t���߂����ā\���L�V�R�E�O�A�e�}�����s���x, �؏��X | ||
| �@ �i��, ���� ��i, ���� ��, �u�����l�v�ҏW��, 1998, �w���J�^�������\���L�V�R�E�}�������̑��� �����l�u�b �N�X�q5�r�x, ���oBP�� | |||
| �z, 1997, �w�O�@�e�}�������؍L�x �V���� | |||
|
��� ���m, 1992, �w�|�R�E�A�E�|�R�\�O�A�e�}��/�G���E�T���o�h���̗��x, ���㏑�� |
|||
�_���i�A�C�E�G�I���j
| ���O�A�e�}���֘A�̘_�����X�g(�M���̂�) | |||
| �ѓ��݂ǂ�E�ύ�m�ȁE�V��u�ێq, 2000, �u�͂��߂Ɂ\���j�I�L���̉v, ���j�I�L���̉v���W�F�N�g�� �w�O�A�e�}���@�s�E�̋L���xPp.3-31, �����F��g���X�D |
|||
| �r�c����, 1997, �u���i�Ƃ��Ă̖����E�����E����s�\�\�O�A�e�}���������n�ɂ����閯���ό��v, �w�s��j�����x17:93-99. |
|||
| �r�c����, 1998, �u�\�͂̓����\�O�A�e�}���������n�̐�Z�������̂ƌo�ρ\�v, �w���w���_�p�x60:59-90, �F�{�F�F�{��w���w��. |
|||
| �r�c����, 2000, �u��Âƕ����v�čl�\�O�A�e�}���ɂ������Ðl�ފw�̍đz���\,
�v�z2000�N2�����iNo.908)pp.199-218, ��g���X |
|||
| �r�c����g�o�@�i��L�̘_���͂�������ǂނ��Ƃ��ł��܂��B�j |
|||
| ���c�D�M, 2000, �u�l�ފw�ƃT�o���^���̎�̓I�֗^�\�w���̖��̓��S�x���^�E�����`���E�x�ɂ�����\�ۂ̖��v, �w����v�z�x28(2):8-23. |
|||
| ����, 1990,�@�}���̕a���ƍЂ��\�O�A�e�}���̎���ƕ������͂ɂ��Ă̊o��,�@�w���������̐��E�x��, ���w�ف@ |
|||
|
����, 1994, �u���E�͂���\�O�@�e�}���̏ꍇ�v,
���c�x�q�Ғ��w�����̏o��������xpp.61-82,
�����I��516, �����V���� |
|||
| �ύ�m��, 1997, �u�O�A�e�}����Z�����^���Ɋւ���\���I�l�@�v, �g�c�G��ҁw���e���A�����J�̐����E�Љ���̐V�ǖʁxPp.45-60, �����F�A�W�A�o�ό������D |
|||
| �����p�Y, 1984, �u�O�@�e�}���̐��D�v, �w���D�̔��x��Q�W��, ���s���@ |
|||
| �����p�Y, 1997, �u���A���̓C���f�B�S�ɂ��Ă̊o�������\��ɃO�@�e�}���E���Ă𒆐S�Ɂ\�v, �w�O�@�e�}�������E�암�ɂ����閯���w������1991�`1994�x, �����Ɖ��̔����� |
|||
|
����O�}�q, 1993a, �u���ăO�@�e�}���쐼�����n�̃}�������ɂ�����R�t���f�B�A�i�M�k�W�c�j�Ɋւ����l�@�v,
�w���o��_�W�x������S�S����S���Fpp.235-294 |
|||
| ����O�}�q, 1993b, �u���J�^�������쓌���}���̏j�ՂɊւ����l�@�v, �w���o�ϑ�w���{���I�v�x������P�P���Fpp.83-139 |
|||
|
����O�}�q, 1995, �u�}�����E�̏j�ՋV��v,
�w���\�A�����J���E�x�i���ѓ��L�ҁj, ���E�v�z�� |
|||
| ����O�}�q, 1997, �u�T���e�B�A�S�E�A�e�B�g���������T�ԋV��Ɋւ��閯���w�����v, �w�O�@�e�}�������E�암�ɂ����閯���w������1991�`1994�x, �����Ɖ��̔����� |
|||
|
���㒉��, 1997, �u�O�@�e�}�����n�}���̒���s�Ƒ����v,
�w�O�@�e�}�������E�암�ɂ����閯���w������1991�`1994�x,
�����Ɖ��̔����� |
|||
![]()