![]()
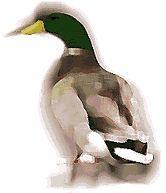
September 20, 2000
| 「すべての企てに疲れたやうな心にはまつたく雨がなつかしい。一つ/\降つて来るのを仰いでゐると、いつか心はおだやかに凪いでゆく。怠けてゐるにも安心して怠けてゐられるのをおもふ。」(『なまけ者と雨』若山牧水) 僕の住むここ、コバンの街はいつでも雨ばかり降っている。 朝方は晴れていても、決まって午後はしとしと雨が降る。 緯度は低いので見上げると太陽はほぼ真上にあって、日差しもずいぶんときついはずなのではあるが、高原地帯なので、空気はずいぶんとひんやりしている。そのうえずいぶんと雲は低く流れていくのだ。 雲の低さばかり気にしていると、雨が降り始めたときなど、どうかすると自分が街ごと雲の中に紛れこんでしなったような気分になることがある。 道を行く人々も、たとえ手ぶらであっても傘だけは持ち歩いていることも多い。もっとも大多数の人々は雨が降り始めると電気屋の軒下に身を沈めて、店先のテレビを見ながら雨のやむのをぼんやり待っているのだが。 屋根の上に山のような荷物をつんだボンネット・バスが行き来して、行き先を告げる若い車掌の声がひっきりなしに聞こえている。そしてただ木々の緑だけが生き生きとしている街である。 |
| 雲は明るく広がり 雨上がりの濡れた街路を覆わんとするが 高原の冷えた大気はまわりに満ちて 坂の上のぼくは 喧噪を取り戻した街中で ひとりとりのこされる ただひとりで こんなところまでやってきて ここまできてもただのひとりなのだ その不安が いつも次へ 次の場面へと僕をかりたてる |
| (グァテマラ・コバンにて) |
August 14, 2000
| 久しぶりに昔書いた文章を読み返してみた。ここに載せていた駄文のことである。誰に見せるともなく、ふと漏らした感慨が案外自分でもおもしろくて、人目に付きにくいところで、こっそり公開していたものである。 ほぼ1年以上ほったらかしにしていた。感慨を持つ間もなく走り続けてきたということか。気がついたらグァテマラだった。 このホームページを立ち上げた頃は、日本語教師としてカンボジアへ行くつもりだったのだ。なんだか不思議な気がする。昨日も書いたのだが、どうも実感が湧いてこない。気がついたら当たり前のようにスペイン語を話している。それだけでなんだかわくわくしてしまうのだ。 昨日と違う日が当たり前のようにやってくるというのは、考えてみれば僕の人生では珍しいことかもしれない。 昔のことを少し思い出した。研究者への道をあきらめてからこのページを作り始めたのだ。 もう少し昔のこともついでに思い出す。子供の頃の話だ。いい加減なくせに妙なところで完璧主義の僕は、自分なりに好きで調べたことをノートにまとめようとしていた。何度も同じノートを書いては気に入らず書き直していたために、はじめのところだけ妙に詳しく書かれたノートが何冊も残されている。僕が学者になりたかったのは、そんなノートを完成させたかったのかもしれない。 そこには繰り返ししか存在していない。幾度も失敗を繰り返しながら、こんどこそと思い続けてまた書き直す、そんな人生を送ってきたのかもしれない。 今の僕はもはやノートも持たず、後ろも振り返らない。そこには失敗さえも存在しないのだ。失敗は単なる分岐点にすぎない。それは新たな選択枝を作るきっかけなのだ。 良くも悪くもない。ただ繰り返すのはいやになっただけである。 |
August 13, 2000
| はるか地球の反対側までやってきて、こんな感慨を持つのもなんだが、いまだに自分がどこにいるのかがよくわかっていない。 僕宛に届くメールもどこか遠くの世界からの声のような気がして僕の中に響いてこない。 今日は日曜日で、近くの教会の礼拝の鐘の音が聞こえてくる。近所の家の犬だの鶏だのの鳴き声に混ざって市場のざわめきがここまで届く。 ここ、グァテマラに来てから一ヶ月がたった。 退屈というのは僕には存在しない。 僕の中には、いつも暗い部屋の中から外の明るい世界を眺めている自分がいて、どうかするとそうした自分と同一化してしまいそうになる。僕はそいつに追いつかれないように走り続けようとしているのだ。退屈している暇はない。 部屋から一歩踏み出した世界はそのつど姿を変えて僕の前に現れる。ある時は優しいが、ある時は冷たく感じられる。けれどもなにより僕がおそれているのは、それが怖くて部屋から出られなくなることだ。 外に出て、人と関わるのは楽しい。けれども僕にとって部屋の中で一人物思いに耽るのもまた楽しいのだ。その誘惑に打ち勝つだけ魅力ある世界を外側に作り上げなければならない。 ここグァテマラの生活は楽しい。スペイン語を話すのもさして苦にならない。できることなら日本語を使わずに済ませたいくらいなのだ。 日本人以外の仲の良い友達もできた。 それでも天気のいい日曜日の午前中にこうやって部屋の中で物思いに耽ると自分がどこにいるのかがわからなくなってしまうのだ。部屋の扉を開ければ、いったいどこに辿り着くのだろうか。 今日は天気がいい。もうしばらくしたら市場の食堂あたりでブランチを食べに行こうと思う。 |
冬, 1999
耐え難い夜だ 転げまわりたいほどの 逸る心をねじ伏せて 勢い余ってそのまま壁にでもぶちまけてしまいたいような 夜 (こんな役にも立たないものを大事に抱え込んでいるのなんて) ぼくは身をうらがえして われとわがみをけずりおとさんとする |
| (長い長い夜に) |
秋, 1999
| ひとしきり笑い転げた後、 涙を拭いながらなぜだか哀しくなってしまって ひとり夜道を帰りながら耐え難い寂寥を感じていた。 これで僕はいなくなってもいいのだ 誰かに許されればそのまま身を投げてもいいような夜だった 身の施しようも知らない悲しさよ このまま流されて 帰るところもなく 漂っていけばいい 誰かに蹴られてドブの中 石ころよ その幸せをかみしめたまえ |
| (宴の後で) |
May 13, 1999
憂鬱なる花見最近とみにパソコンに向かう時間が増えた。周期的にこうした時期がやってくるようで、どうも今はその時期のようだ。春先にはこうして部屋に籠もることも増える。春先の憂鬱と僕は勝手に呼んでいる。僕の中にある春のイメージは、およそ新緑のさわやかな季節とはほど遠い。 四月は残酷な季節だと歌った詩人のように、詩的な比喩で述べているわけではない。変化を当たり前とする価値観の中で、なんら変わらぬ自分にいらだっているのだ。 「やらなければならないことは」と、かつて愛読したフランスの作家が言っていた。「自分を完成させることだ」 パイロットでもあった彼は結局、必然性のない偵察任務のさなか、地中海上空で消息を絶った。彼を突き動かしたのは「やむにやまれぬ義務感のようなもの」だと後に誰かが語っている。高校時代からこのかた、僕を突き動かしているのも「自己の完成」とでもいうべき、そのような衝動でもあった。 しかしながら、どのような在り方が完成なのかもわからぬまま、ただひたすら自分の求めるものを追求し続けることに最近は疑問を感じている。利己的と感じてしまうのだ。その葛藤にもいいかげんつかれた。 萩原朔太郎の詩に「憂鬱なる花見」と題された詩がある。かつてこの詩を思春期に読んだ時分には、自分の押さえきれない悪癖が美しく飾り立てられて提示されたように感じた。 久しぶりに読み返す。 少しは自分が許せるような気がして、自分を見放すのも先に延ばすことにした。 |
憂鬱なる花見憂鬱なる櫻が遠くからにほひはじめた櫻の枝はいちめんにひろがっている 日光はきらきらとしてはなはだまぶしい 私は密閉した家の内部に住み 日毎に野菜をたべ 魚やあひるの卵をたべる その卵や肉はくさりはじめた 遠く櫻のはなは酢え 櫻のはなの酢えた匂ひはうつたうしい いまひとびとは帽子をかぶつて外光の下を歩きにでる さうして日光が遠くにかがやいてゐる けれども私はこの暗い室内にひとりで座つて 思いをはるかなる櫻のはなの下によせ 野山にたはむれる青春の男女によせる ああいかに幸福なる人生がそこにあるか なんといふよろこびが輝いてゐることか いちめんに枝を広げた櫻の花の下で わかい娘たちは踊をおどる 娘たちの白くみがいた踊の手足 しなやかにおよげる衣装 ああ そこにも ここにも どんなにうつくしい曲線が もつれあってゐることか 花見のうたごゑは横笛のやうにのどかで かぎりなき憂鬱のひびきをもってきこえる いま私の心は涙をもてぬぐはれ 閉ぢこめたる窓のほとりに力なくすすりなく ああこのひとつのまづしき心はなにものの生命をもとめ なにものの影をみつめて泣いてゐるのか ただいちめんに酢えくされたる美しい世界のはてで 遠く花見の憂鬱なる横笛のひびきをきく 『青猫』、新潮社、1923 |
February 15, 1999(改訂)
| 久しぶりに街に出ると、なんだか旅行者のような気分だ。見知らぬ街にくるとまず本屋を探す癖があるのだけれど、これは勝手知ったる場所に行くと安心するからだろうか。友人を待つ間に案の定また本を買い込んでしまった。雑誌と英語会話の本とペイパーバックである。 ペイパーバックのコーナーに山積みされていた"tuesday with Morrie"に目がいく。これはNHKのラジオ英会話のテキストで別宮貞徳が紹介していた本だ。大学時代の恩師が難病ALSに侵されていることを知ったコラムニストが、毎週火曜日ごとに病床を訪れ、人生について語り合うという話である。翻訳は出てるのかな。 この手の話に弱いのは、高校時代の愛読書だった『チップス先生さようなら』以来だから、けっこう昔からだ。以前に読んだ『ボディ・サイレント』もよかった。 これは骨髄癌に侵されたコロンビア大学の人類学教授が、死に向かう自らの歩みを記録した本である。身体が動かなくなるにつれ、次第に社会的な位置づけが変化し、それにつれて周囲の人間との関係も変わっていく。それを受け入れていく著者の在り方が感動的だった。自らの経験を最良のフィールドワークと呼び、死にゆく直前まで自分と周囲の世界との関わり方を考えて行こうとする姿勢は、沈みゆく豪華客船の甲板上で最後まで演奏を続けた楽士たちの姿を思わせる。授業の終わりにはいつも学生が立ち上がり拍手で見送ったという伝説的な教授だけに、文化人類学の最良の入門書としても読むことができる。彼にとって文化人類学の理論は自分の生き方を照らし出す道具でもあったのだ。 『モリー先生との火曜日』が、また違った観点から、この古くて新しいテーマを見なおす契機となってくれればうれしい。 Albom, Mitch., "tuesday with Morrie", Doubleday export edition, 1999. Murphy, Robert F./ロバート・F・マーフィー 、『ボディ・サイレント』、新宿書房 ジェイムズ・ヒルトン、『チップス先生さようなら』、新潮文庫 <追記>結構期待して読んだ『モリー先生との火曜日』だけれども、なんというか、ありがちなお話だった。モリー先生と著者との交流は確かに心温まるエピソードだけれども、モリー先生の人間像は最後までみえないままだった。 あとがきを読んで合点がいった。結局著者にとって重要だったのは、彼の人生のとある時期に死にゆく恩師と出会い、自分自身の内なる恐れを乗り越えたことであった。そこにはモリーはいない。モリーの死はきっかけにすぎないのだ。 このような言い方はあるいは、あるいは酷かもしれない。著者の意図はそこにあったのだろうし、読み手の求めるものがそこになかったからといって非難を受けるいわれはどこにもない。 ただ同じような不満をかつて感じたことをふと思い出した。村上春樹の『ノルウェーの森』を読んだときがそうだ。「100%の恋愛小説」と帯に銘打たれていたこの小説は、確かにいい話で、そのノスタルジックな文体に当時は大きく影響をうけたものだった。 しかしながら、そこに登場する精神を病んだ女性たちは美しく印象的に語られてはいたけれども、主人公(渡辺くんだ、なつかしいなぁ)にとっては、彼女たちのかかえている混乱はさして重要なものではなかったし、その内容も彼女たちを彩るエピソードでしかない。この点がこの小説に当時感じた不満である。混乱は混乱としてのみ描かれ、語られるだけだった。それは混乱を抱えた人間とうまくつきあう手段ではあっただろう。そしてその限界と破綻が同時に描かれてたが故に、この小説は優れたものであったのは確かだ。 モリー先生の話に戻る。僕が知りたいのはモリーにとって死んでゆく過程とはどういうものだったかである。周りとの人間関係のなかで何が変化し、なにが変わらなかったかである。 結局僕が知りたいのはなんだろうか。 たがいにそれぞれ相手の姿を思いこみによって自分の中につくりあげていくのはよくあることだ。またそれがどこか嘘であることもたいていの人は気づいているものだ。 けれどもそれを暴こうとする試みは、たいていおかしなものになってしまう。実際の姿などはどこにも存在していないからだ。それは関係の中だけにある。 その関係はけれども、いつも同じものではなく、ましてや死に向かう旅の途中では激しくその姿を変えるだろう。そのつど必要なものは変わり、それまでそこにあったものも姿を消していく。 僕が知りたいのはたぶん、死にゆく人間と共に過ごすことによって、死にゆくものにとって自分が必要な存在になれるかどうかなのだろう。そのケーススタディが僕の求めるものだったのかもしれない。 そうであれば、僕も少したいがいである気がする。なにかマニュアルのようなものを探しているようなものだ。「死につつある人間とうまくつきあう方法」なんていうものが僕の求める本なのかもしれないのだ。 死にゆく人との関係も僕にとってなにかの隠喩だとは思うのだが、それが何かはよくわからない。 |
February 13, 1999
| PHSが壊れて使えなくなってしまってからほぼ一週間が過ぎた。もともと電話をさほど好まぬ性質からか、そう不便をかこっているわけでもないが、なければないでものたらぬ気もする。ただ生来のものぐさ故、わざわざ手帳から番号を調べて数字を打ち込む手間を惜しんで、ここしばらくは自分から電話をかけることはなかった。 だいたい一週間もすると予定がずいぶん空くのに気がついた。 日々のルーティーンワークを除けば手帳の予定欄は白いままである。これが自分の好きに使える時間だと思うと案外楽しいものだ。 そうすると今までの休日はなにをしていたのだろう。結構なんだかんだと人に会っていたのだろうか。 かわってメールのやりとりが増えた。人との関わりとは妙なもので、やりとりの間隔が短くなると、実際に会っているわけでもないのに気安さが生まれてくる。けれども書き言葉を通じてのコミュニケーションとは少し特殊なもののようで、これに慣れると実際に顔を合わせたときに交わす言葉が少し億劫なものに思えてしまうのだ。 ホームページを立ち上げて以来、メールのやりとりはちょっと尋常ではないほどに増えた。立ち上げたのが1月23日で、今日が2月13日の深夜である。ほぼ3週間で受け取ったメールは87通。これはプライベートのみである。一日に平均4通ほどのメールが届いている計算になる。これに対して送ったメールが73通。返事が少ないのは書くのが追いついていないからだ。 メールのチェックは朝と夜の二回になった。これはしかし、必要に迫られてではない。メールが来ているのが当たり前の状態に慣れてしまうと、届いた数が少ないと物足りなく感じてしまうためである。 これに加えてホームページの更新と掲示板の書き込みである。一体どれほどの時間、パソコンに向かっているのか自分でもよくわからない。ただ文章を書くことは苦痛ではないどころか楽しくて仕方がない。読み手が常にいる状態で文章が書けるのは幸せなことなのだ。そのうえ、時間が減ったはずなのに読書量は確実に増えている。 それで手帳の空欄が増えたわけに得心がいった。PHSの故障以前に人に会わなくなったのだ。にもかかわらず人との関わりは以前より増えた気がする。おかしなものだ。 ここまで書いてきて自分自身がとまどっていることがよくわかる。急速に多様化していくコミュニケーションの手段に対して、その功罪も見えないまま巻き込まれている気がするのだ。内向的な生活を送っているのか外向的なのかもよくわからない。もはやこういった価値観を含んだ言葉は使いづらい気さえする。おかしな時代に生まれたものだというのがとりあえず今の感想である。 |
February 03, 1999
メランコリーから身を守る方法数多あるわが家の家訓のひとつに夜、手紙を書いてはいけないというのがある。 守らなければどうなるというものでもないが、時として悲観的になったり、メランコリックになりすぎたりするのを防ぐためらしい。けれども実際に僕が手紙を書くのはほとんど夜で、だからといって僕が毎晩メランコリックな想いに身もだえしながら、手紙を書きつづっているかというと、そんなことはほとんどない。 普段の僕はおよそ過ぎ去ったことに想いを馳せるといったタイプではないらしく、日々の出来事で頭の中はすぐにいっぱいになってしまうのだ。すぎてしまったことは本当におぼえていないというのが実際のところで、過去も未来も現在から離れているという意味で等価なものでしかないのである。 だから今、昔の亜細亜山荘のことを書きつづっているのも昔を懐かしむというよりは、残された文献を元に自分の過去を再構成するのが楽しいからだ。自分がどのような人間であったかが残された記憶と資料によって、わかっていくのは結構興味深いものである。案外、伝記作家にでもむいているのかもしれない。 それでも時として抗しがたい力に引きずり込まれ、あらがう術もなく、否応なしに、懐かしさのただ中に放り込まれることもあるものだ。 懐かしさというのは、あるいは、狂気に近いようなものかもしれない。あるいはまた、過去を切り捨てることによって成立させている現在の自分の在り方に対するしっぺがえしか。いずれにせよ、それはどことなく僕の居心地を悪くさせる。 居心地悪さついでというか、そういうときはさらに自虐的になるもので、昔の手紙を読み返してみたりするものだ。とくに振られたときの前後の手紙があるとなおよい。 不思議なもので、たとえその後、関係が回復し、今も仲のよい友人として続いていても、振られた自分は今も自分の中にいて、永遠に振られ続けているのだ。 手紙を遡る。この上もないしあわせさを感じている自分がそこにいる。彼は今もやはり僕の中にいて、いつまでもしあわせな気分でいるだろう。 彼女と出会った頃の僕がいる。その後の展開なんて頭にないまま、ただ興味を抱いてそこにいる。いまも彼女と出会ったその時その場にいて、そこにたたずんでいる。 過ぎ去ったことは何もなく、ただ彼らはいまも僕の中にいて、僕に何ほどかの気持ちを思い起こさせる。それが僕をたまらなくさせるのだ。 それで僕は記憶のアルバムを閉じて日々の営みへと舞い戻る。時間が適当であればその時の彼女に電話するのも良い。 こんな文章にも教訓はある。 ただ、「夜に手紙は書かない方がいい」っていうのがここから得られる教訓なのかどうかは僕にはちょっと自信がない。 |
Monday, January 27, 1999
| ホームページ作成にこんなにはまるとは思わなかった。ああでもないこうでもないとHTMLをいじりながら自分の思うようなページを作り上げていくのも楽しかったけれども、いざ、インターネット上にアップロードして、それを誰かが見ているのだと考えることが、こんなにわくわくするものだとは知らなかった。ちょっとした快感である。 読み手とすぐにでもメールでやりとりできることによって、読者の反応がすぐにわかるもの良い。読み手の顔がこんなによくわかるメディアだとは思わなかった。 作家の筒井康隆が断筆宣言のあともネット上で小説を書き続けていたのもわかるような気がする。 当時はそんなに限定された読者を相手にしているよりも、不特定多数の多くの読者を相手にしたほうがおもしろかろうにと思っていたが、とんでもない。 どんな創作活動も直接に反応を示してくれる相手がいてこそ、成り立つものだ。だからこそミュージシャンはライブを行い、画家にしても個展に来てくれるお客を大切にする。 いまのところは限定公開なので、見に来てくれるのは全て知り合いばかりである。だからこそ感じるおもしろさなのかどうか、まだ何とも言えない。不特定多数を相手にしても、読者の顔は見えるのだろうか。 |
Monday, January 25, 1999
| 久しぶりに街に出て、本屋によると面白そうな本ばかりが眼について、気がつくと紙袋いっぱいの本を両手に抱え込んでいた。それも高くて分厚い本ばかり。 今日でようやく日本語教育能力試験が終わった。といってもろくに試験勉強もしていなかったので、解放感を味わうような気分でもないのだが。 試験そのものは解いていて面白かった。普段、塾で解いている国文法の問題とは観点が随分異なっていて、けっこう楽しみながら解けた。ある意味、日本の国語教育も日本語を道具として教える観点があっても良い。 帰り道で梅田の紀伊国屋で買った本は次の4冊。 *立花隆+東京大学教養学部立花隆ゼミ、『二十歳の頃』、新潮社、1998. *ジョン・ヴァン=マーネン、『フィールドワークの物語 エスノグラフィーの文章作法』、現代書館、1999 *大橋久利編、『カンボジア 社会と文化のダイナミクス』、古今書院、1998. *ジェフリー・リーチ編著、『ネイティブ英語運用辞典』、1998. 『二十歳の頃』は立花隆の東大におけるゼミの学生達が作り上げたインタビュー集で、立花隆の名著、『青春漂流』のコンセプトを受け継いだものと言っていい。 おもしろさのあまり、帰りの電車で駅を乗り過ごしてしまったのは、いつものお約束。 このゼミは以前からインターネットでも講義録などが公開されていて、面白いことをやっているなとは思っていたが、ついに本にまでなってしまった。 アドレスは以下の通り。 東京大学教養学部立花隆ゼミ この本の詳細と後の3冊については近い内に読書ノートの形でアップロードの予定。 |
Monday, January 23, 1999
| 今は深夜12時をまわったところ。つい先ほど仕事を終えて家に帰り、簡単な夕食をとったところだ。 冷えたウォッカを軽くあおって少しほろ酔い加減。 「白玉の歯にしみとおる秋の夜の酒は静かに飲むべかりけり」なんて句がふと頭をよぎる。 でも誰の詩だっけ、これ。 実際、歯槽膿漏気味の歯茎に酒は気持ちよくしみわたるのだ。清冽、玲瓏、凜トシテ霜晨ノ若シ。酒がこんなにうまく感じられる宵には、酔いが醒める前になんとかして眠りにつかないといけないなと思いつつ、ディスプレイにむかう。酔い醒めの苦い気持ちのままに、自分のことをさらけだすような事態は避けねばならない。 この週末中にサイトを立ち上げるつもりである。自分の行動をさらけだし、自分のやっていることを傍らから眺めてみようと思う。 どうせ人目を気にせざるをえない身ならば、いっそ自分を剥きだしにして、渡世のあがき、浮き世のつらさなどはさらけだした自分にまかせ、僕自身は高みの見物としゃれこもうという趣向である。 さて、24日は日本語教育能力検定試験。 自分の全ての行為は語るべき素材としてしか存在していないと考えるのは、なかなか素敵なことである。 物語の登場人物のごとくに語ろうと思う。 「昔、男ありけり。その男、身をえうなきにおもひなして・・・」 「東下り」の主人公のように僕も「日本にはあらじ」とばかりにいずこへと旅立とうとしているのか。 ともあれ、日本語教師を目指す、さほど若くもない塾講師の試みがどんな結果に終わるのか、我ながら楽しみというところだ。 |
![]()