【 第11章 天孫降臨 】
古代氏族
アマテラスとスサノオの誓約神話は相手の所持品を受け取ってそこから生まれた子で占うといううまい構成になっています。
スサノオがアマテラスの剣をかみ砕いて生まれた五男神が天之忍穂耳、天之穂日、天津日子根、活津日子根、熊野久須毘。
アマテラスがスサノオの玉をかみ砕いて生まれた三女神が多紀理姫、市寸島姫、多岐都姫。
(古事記では剣と玉が入れ替わり、書紀1書には自分の所持品を自分でかみ砕く話もある)
誰が誰の子であるかを自由に解釈できるようになっていて内容の見えない神話ですが、剣や光などが体内に入って誕生といったタイプの神話の流れとも思えます。
下表は系図綱要/太田亮による氏族の出自の一部と歴史上の推定対応です。
祖先神 神々あるいは氏族 伊弉諾伊弉冉尊:大山津見神、大綿津見神、道俣神、上筒男神、中筒男神、底筒男神、倉稲魂命・・ 天照大神、素戔嗚尊、月読神・・→縄文系一般 高御産巣日尊 :思金命、萬幡豊秋津師姫、忌部氏祖、葛城氏祖、大伴氏祖・・→春秋〜秦文化系渡来者 神産巣日尊 :少彦名、鴨縣主祖、紀伊国造祖、度合氏祖、久米氏祖・・→海洋三苗系渡来者 津速魂尊 :中臣氏祖・・→呉越楚、東シナ海の漢文化系渡来者 振魂尊: →呉越楚、山東半島系渡来者? 萬魂尊: →その他の渡来者
アマテラスとスサノオの誓約から生まれた宗像五男神三女神はどこにいるのか。
あいまいになっています(^^;
神話的には伊弉諾伊弉冉神の子等ということで渡来者であるかどうかはあいまいで、その家臣となる人々だけが渡来系であることを示しています。
記紀の本質のひとつ、氏族融合、同根とする方針のゆえであり五男神三女神神話の本質がここにあると思います。
天津日子根(河内直祖)は九州南西岸〜太平洋岸を主とする海神族。
当初はすべての海域を範囲としたが活津日子根グループの登場以後は長崎や五島列島など九州西南岸と太平洋岸を活動領域とした五男神中の最古(BC1000〜500頃登場)とみておきます。
三苗文化の伝達者でもあります。
瓊々杵などに冠せられる天津彦の尊称は天津日子根=天津彦の祖先、が由来と推定。
活津日子根(桑名首祖)は天津日子根系から分かれたグループで、壱岐津と同意とみて朝鮮半島南岸と日本海沿岸域を活動基盤にしたとしておきます。
大己貴やアジスキタカヒコネはこのグループの一員で、弥生中期あたりから重要な位置を占め、出雲や瀬戸内の海運はこのグループが主となったと推定。
出雲熊野大社の東に那富之夜神社ナフノヤがあって現在は経津主神と武甕槌神が御祭神のようですが、地元では星神のアマノカカセオが御祭神であったという伝承があるようです。
アマノカカセオは記紀では天孫の敵役(^^;
那富之夜神社は海洋系の星神が健在だったであろう天津日子根あるいは活津日子根の時代が源だと思います。星神を退治した(^^;武甕槌神に御祭神が置き換えられたのは明治以降か。
熊野久須毘(山城直祖)は内陸系の三苗文化を伝達した最古のグループで、天津日子根に運ばれて各地に展開していたと推定。しいていうなら萬魂尊といったところか。
春秋時代までの楚の王はほぼ全員が熊の文字を使っていますが、熊になんらかの執着があったのでしょう。
出雲熊野大社、紀州熊野大社、熊本、種子島の熊毛や熊野浦、瀬戸内の熊毛、檀君神話の熊女、など各地の「クマ」の名の源ではないかと考えています。
出雲熊野大社の鑽火神事は熊野久須毘到来(初期開拓者)を源にする農耕神事だと思います。
本居宣長は御祭神の櫛御気野命クシミケヌノミコト=スサノオですが・・誤りでしょう(^^;
日御碕神社や美保神社が天津日子根など海系起源なのに対して陸系三苗起源。
英彦山の英彦山神宮ヒコサンは修験道の拠点で3羽の鳥が象徴になっており、紀州熊野の三本足のカラスとの関連がうかがえます。
紀州熊野も天津日子根がが運んだ陸系三苗文化(初期開拓者)が源だと思います。
(具体的な縁起は後述の葛城氏参照)
楚には鬼神祭祀があります。魏志倭人伝にいう卑弥呼の鬼神もこれを継承するものと推定。
(鬼神を拝するのではなく、鬼神を見ることのできる巫者が鬼神の害を防ぐ祭祀です)
古代楚文化と秦時代の斉文化のありようは日本の弥生祭祀に直結すると考えています。
中臣氏は楚の出自か、天穂日と類似文化だが微妙に違うところが後に祭祀者として忌部氏とライバルとなるゆえん(^^;
気候温暖の弥生黄金期では祭祀者は目立つ存在ではなかったと思います。しかし寒冷化と共に勢力を伸ばしていったのではなかろうか。
ある時期から祭祀者ギルド的性格をもつようになったかもしれません。
記紀編纂時代では中臣氏(藤原氏)は編纂の中枢にあって、道教の影響を受けながら縄文古来の信仰を含んだ独自性を前面に出そうとしたのではないかと考えています。神道の萌芽です。
五男神のうちの最新が呉楚七国の乱からの脱出者、天之忍穂耳と天穂日。
天之忍穂耳は呉の出自としておきます。天孫の父。
天穂日ははっきりしませんが忌部氏が高御産巣日神系ですから斉の出自とみておきます。
漢文化を持つ人々。「天之」の尊称がある名がこの系譜の表現と推定しています。
総じて書紀の人名はなんらかの背景による規則性があるとみています。
高御産巣日神系と神産巣日神系を祖とする氏族には特有の性格を感じます。
神産巣日神系からうけるイメージはずばり海賊です(^^;
東シナ海沿岸、そのうちでも越出自の可能性が濃いと推定。
度会氏が伊勢神宮を司りますが初期開拓者との関係からも納得できるところです。
(なお、鴨縣主はアジスキタカヒコネ系の迦毛とは別系と推定)
高御産巣日神系は総じて学者系。
大伴氏は軍事面で登場しますが本人が戦う武人ではなく統率者、軍師といったところでしょう。
ここには秦王族関係者が含まれている可能性少なからず(^^;
葛城氏も祭祀者だったのではないかと思います。
山東半島から天穂日(出雲臣族)あるいは出雲神族の流れに乗って奈良にはいった氏族。
出雲系譜に葛木一言主神がいます、「主」ですから斉の瑯邪八神(主)ともつながる出自と推定。
中臣氏や忌部氏とも異なる第3の渡来祭祀者。祭祀者というより原始道教のうちの「神仙求道者」で、徐福と同系と空想(^^;
後に役行者との関連がでてきますがこれも神仙求道者だったからだと思います。
縄文の山岳信仰や後の密教と結合して修験道の源になったのではなかろうか。
葛城氏は近畿ヤマト王朝に妃を少なからずいれていますが表面にはでてこない、これも氏族の持つ思想のためではないかと考えています。
西都の古墳群から盗掘された土器群(^^; が奈良の系列不明とされる葛城古墳群のそれと同系列だそうです。
西都の葛城式埴輪は天孫が奈良を制圧してから奈良葛城が祭祀者として日向へ出向いて類似埴輪が登場したと空想しておきます。
物部氏がでてきませんが多数の氏族の混合体で単一の氏族ではないから(^^;
物部とは弥生〜古墳の強力な海運者組織(ギルド)であって単一の古代氏族を祖にするのではないと考えています。
饒速日はある時代のギルドの代表者だったのではなかろうか。
AD100以降の寒冷化と共に海運者から商社的な傾向を強めていったのが物部氏の祖ではなかろうか。
軍事を含めてその活動は多岐に渡りますが、農耕には従事しなかった。
現代でも巨大商社が歴史を動かす力を持ちますが、それと同じ状況が生まれてゆくわけです。
旧事紀(先代舊事本紀)には降臨時の陪臣としてずらりと30人ほどの物部氏族が登場しますが末席とはいえこれはいささか異様。各地のオサの名を並べたのでしょう。
港を拠点に商業に転じ、「土地」に制約されない人々(手工業製品や毛皮など農作物以外を生産する人々)の頂点に立つようになったのが物部(氏)だと考えています。
(農作物を統べるのは王朝の最重要政策→租税につながってゆく)
天之忍穂耳上陸の偵察先遣隊の天之稚彦は地元の娘と良い仲となっていたが、天之忍穂耳とスサノオとの戦闘中に長弓部隊の流れ矢に当たって死亡、このあたりは記紀の記述通り(^^;
天之稚彦は鳥葬風習を持つところから少なくともその祖先は長江でも上流の山岳系の出自でしょう。
記紀にアジスキタカヒコネと容貌が似ていたとありますが、この時代では出身地の特徴がよく残っていて風貌で祖先がわかることを示しているのでしょう。
アジスキタカヒコネは「天之」ではないので呉楚七国とは無関係に渡来していた人物で、大己貴の類族といったところだろうと思っています。
倭
中国から「夷」と呼ばれた人々のうちで稲作をメインにする人々が倭(委)であると考えています。
BC2000以降に長江三苗文化の影響を受けた人々でもあります。
(殷周時代では山東半島もそうですが、ここでは稲作は定着しなかった→したがってこの一帯は夷です)
すなわち、地域でも人種でもなく稲作によって生活する夷の人々、それが倭だと考えています。
したがって時代によって倭の位置や勢力は変動します。
ある時期までの中国側のいう倭は日本や日本人とは限らないということです。
倭の文字は後漢になってから作られたもので、それ以前では「委」が使われていた。
委には曲がってたれた稲と弱々しくしなだれるといったやや見下す方向の意もあり、夷の発音(yi)との類似もあります。
夷のうちの稲作を糧にする人々、これに委の文字をあてたわけです。
「委」は呉音漢音ともに「wei」で、飛鳥の木簡ではワサビのワに委の文字をあてています。
飛鳥では「ゥエサビ」といったのかもしれません(^^;
最古の「倭」は詩経(春秋時代)での登場のようですが、現在残る完本は後漢時代に補注を加えた写本だけのようです。
山海経には蓋国が燕の南、倭の北にあり。倭は燕に属すとあります。
また後漢書には鮮卑と燕の紛争のなかで「委」をとらえています。潜水で魚を捕れるのは「委」でないとできなかったために数千人を連れ帰った、とあります。
ここでの「委」は平壌付近の沿岸の民ではなかろうか。
このころ(戦国〜秦)に認知されていた稲作と漁労で暮らす「委」は朝鮮半島西南岸の人々であって、それより南の「日本」は知らなかった。徐福も日本を「蓬莱」と認識していたわけです。
しかし前漢となり楽浪郡や帯方郡が設置されて朝鮮半島西岸は漢に所属し、その一帯の「委」は漢の一部となって委ではなくなります(真番郡もそのひとつと推定)。
そしてもっと南の「委」の存在を知り、後漢となって「委の南限の王」が朝貢してきた。
光武帝が金印を授与した時点(AD57)では倭の文字は存在せず金印には委が使われたが、国と認めたことによって格上げされ「委に人」を加えて作られた文字が「倭」、と推定。
公式の印に略字を用いることはあり得ないですから、「委」は「倭」の前身ということです。
AD100頃には辞書の説文解字が完成しこれには倭の文字が存在します。
それ以前の古書を写本する場合も、委の呼称を「新たに制定された倭」に写すことになると思います。
しかし、後漢時代には寒冷化がはじまっています。
遼東半島での稲作は消えたのではないかと思います。委の人々はいなくなった。
後漢時代では稲作地帯は半島西南岸と日本になって、「倭」もその一帯の人々を示すことになるのですが、かってはそうではなかったことが古伝書の写本での倭の解釈に問題を生じるのだと思います。
稲で暮らす人々がいるならば日本とは無関係の地域の人々でも倭と書かれうるわけで、遼東半島でも台湾でも稲作者なら、委→倭と記されうるわけです。
隋書(636)では「人+妥」の文字がでてきますが、新しい文字で混乱した古記録の誤りをそのままに写したか、台湾の人々を意味する文字なのか、どちらかでしょう。
朝鮮半島南西岸で稲作を糧にする人々ももちろん倭となります。
百済系の氏族であっても稲作民なら倭です。 後に強いて識別したい場合に倭漢といった表現が使われたのだと思います。
倭漢とは前漢時代に楽浪郡や帯方郡で漢系譜と混じり合ったその地域の委だった人々の後裔、と考えています。
後には南下してきた高句麗や百済を構成する人々の一部にもなります。
かっての箕子朝鮮とのつながりもあるはずですが300年経過ではあったとしても意識だけでしょう。
弥生中期(BC150〜AD50)頃の九州での倭(委)は天孫とアマテラス族が代表で準じて出雲族。
魏志倭人伝時代での「その他の倭」とは中国地方や近畿の出雲のこと。
後には氏族や地域を意味するような使い方も登場して混乱してきますけれど、これは国家が大きくなってその代表名に使われるようになったからだろうと思います。
長崎や五島列島など海神族の勢力地や薩摩大隅など稲作主体ではない人々は従来のままで「夷」です。
現在の鹿児島県の夷守とかえびの市といった地名は周、秦時代の「夷」の地のひとつだったことの残滓だろうと思います。夷の意味を知る外国人がその地にいたということでもあります。
なお後漢書にタン州(さんずい+亶、倉庫の意味をもつ亶タンの発音としておきます)という地名が登場しますが、これは奄美諸島や薩摩大隅の南端あたりをさす地名と思います(海辺の高倉といった印象からの地名とみる)。
弥生時代中期以降では稲作者(とその支配者)はエリートとなってゆきます。
孝霊天皇〜開化天皇には「倭根子」の名が使われていますが、「稲作を行う人々を祖先とする子」の意味でそれを誇りにしていたゆえの名だと考えています。
孝昭天皇の観松彦香植稲がそのはじまりで、孝安ないし孝霊では「天孫系譜」ではなく「委」の系譜であることを意識した命名になっているのではないかと考えています。
(書紀編纂時代ではその認識によって命名しているということです)
天孫の誕生
天之忍穂耳の妻の萬幡豊秋津師姫は高御産巣日神の娘となっています。
秦〜前漢時代の山東半島からの渡来者(春日市付近)とアマテラス族の娘(八女市付近)との間に生まれた子の可能性が高いとみています。
どのような渡来氏族かは空想のネタもありませんが、ここでは秦王族が父親としておきます(^^;
天之忍穂耳にとっても中国初の統一王朝の親族との婚姻は大喜び。朝鮮半島との関連が深まるならますますです。
まあ、このあたりは空想の楽しみといったところで、状況証拠もありませんけれど(^^;
秦王族なら混じりけなしの100%高御産巣日神の系譜でもあります。
萬幡ヨロズ・ハタとはあらゆる舶来文化の意。
機織りのハタ・オリ、畑のハタ・ケ、など舶来文化をもつ豊かな秋津の有力者の娘。
後に秦氏族をハタと発音するのはこのあたりに源があると推定。ただし、応神以降の秦氏が弥生の秦氏の後裔かどうかは別です。
母系にアマテラス系の女性がはいっているならば、母系社会からみれば天之忍穂耳の子はむろんアマテラスの孫です。
萬幡豊秋津師姫を高御産巣日神の娘と明示することで、天之忍穂耳をスサノオとの関連でアマテラスの子のごとく表現せざるを得なかった五男神三女神誕生での血縁関係の修復をしているともいえます。
萬幡豊秋津師姫18才、天之忍穂耳40才、結婚は宗像協定締結を期してのBC130年。
(天之忍穂耳には別の妃の子もいます、20才あたりか、こちらは伊都国の継承者)
秦氏族のもとにもアマテラス族の娘が嫁いでいます。記録にはまったくでてきませんが・・後に重要な人物がここから登場します(^^;
アマテラス族の娘の子であれば親父がだれであろうとみなアマテラスの孫、みな兄弟・・
記紀における天孫とは天神との間に生まれたすべての子が相当すると考えます。
父系はいろいろ、母系でさえ厳密にはひとつの氏族ではないということです。
さて、数年後の伊都国、天之忍穂耳の宮殿の書斎で。
ふたつの降臨
なにをぶつぶついってるのですか。
狭い、狭すぎるぞ。ここは。
それはしかたがないわ、大陸にくらべればもともと狭い島なんですから。
それにしても子供の家を建てる土地すらないのはまずいぞ。
3人目ももうすぐ生まれるし、なんとかならんかなあ。
アマテラスさんから聞いた話ではよい土地がないことはないらしいけど。
あなたが取り戻してあげた日向の南に太平洋に面した広い土地があるそうです。
でもアマテラスさん達が開拓した土地ですから勝手にはできないわ。
数週間後、八女のアマテラスの別邸にて。
ひとつ相談があるのだが・・これこれこうなのだがどうじゃろう。
私たちといっしょに住むのでよろしければ。
おお、それで文句のあろうはずもない。
ちょっとまって、あなたはだめよ、恩人でも外国人ですから皆が賛成はしてくれないわ。
あなたはここでこの土地を守ってくださらないと。
いっしょに住むのはここで生まれたあなたの息子だけ、それならいいわ。
乳母も用意しましょう。で、息子さんには日向を守ってほしいの。
ありがたい、兵士のことはまかせてもらおう。息子二人でもいいかな。
そうねえ、二人ではそのうち兄弟喧嘩するかもしれないわねえ。
二人が大きくなったらどちらかに海を渡らせればいいかしらん。
黒潮に乗ってうんと東に濃尾という広い土地があると冒険者から聞いてますし。
そう、もし婿養子でもよろしければ他にもよいところもありますけど・・
ま、それは後から考えますね、先に日向の用意をしておきましょ。
てなことでまずは幼子ひとりが大勢の家臣と女官に守られて阿蘇へ向かった。
アマテラスは海神族との交渉のためにしばらく八女に留まり、山越えの道案内には日向五十鈴川の猿田彦が呼び出されます。
天之忍穂耳は領土がほしかった。
アマテラスには日向の軍事力を強化して大分からの出雲南下を牽制したかった。
また、九州西岸の海神族との関係をさらに深めて海運の優位を確保しておきたかった。
アマテラスと天之忍穂耳の思惑が一致します。
九州にはアマテラス(大山津見神系)とその縁戚でもある海神族(大綿津見神系)の勢力が平行して存在し、降臨は両者の土地へ行われた。
解釈を少し動かすだけでもずいぶん違った展開もありえます。それは各自でお楽しみください(^^;
ちょい調味料も加わります。徐福が漂着し南九州にその影響を受けた勢力が存在すること(^^;
別掲の人脈図、系統図などを併せてごらんください。
アマテラスの先導を受けて日向に降臨したのが天火明。
書紀1書では他に天大耳などの名も見えますが、ここでは日向降臨は天火明のみにまとめておきます。
旧事紀(先代舊事本紀)では天火明(あるいは饒速日)を天照国照天火明櫛玉饒速日として降臨させていますが、神武紀で登場する饒速日降臨説話が天火明の紀州上陸伝承に合成されて生じた名と見ておきます。
記紀では天火明の後の系譜が消えており、ここに物部の祖とされる饒速日が挿入された。
天火明の紀州ないし濃尾上陸では多数の海運者が支援しているはずで、これとジョイントされて紀州ないし濃尾の物部氏系の伝承となったものと推定。
実際に上陸したのは天火明の子の天香語山かもしれませんが大差はないでしょう。
天火明以降の系譜は旧事紀に詳しいですが、解釈には記紀同様に注意が必要になりそうです。
ウエツフミなど記紀以外の古伝編纂者も自前の伝承群の年代を決定することができず、記紀の神武東征呪文を含めた年代設定の束縛を受けているということです。
もう一人の子、瓊々杵は九州南西岸の海神族のもとへ向かいます。
こちらの降臨地はアマテラス領土ではないので幼妻ならぬ幼婿といったところです。
瓊々杵には天津彦の尊称があるので天之忍穂耳の子ではなく、天津日子根系譜の子である可能性が50%以上かもしれません。
氏族の系譜としてはどちらであるかは重要ですが以後の歴史としてはさほど重要ではないので、記紀の系譜通り天之忍穂耳の子であり、海神族に養子にはいったために天津彦の尊称が加わったとみておきます。
瓊々杵の海路と天火明の山路の2つの降臨がひとつに合成されたために船が山へ降臨するという話ができあがります。
神々が山へ降臨という神話は他にもありますが、船で山へというのはちと珍しいのではなかろうか(^^;
ま、天の船というのはなかなか良いアイデアではありますけど。
天孫の降臨地には事勝国勝長狭という土地神がいて、「命令通り国をさしあげます」といっています。
これはアマテラスに命じられたので、という意味でしょう。
書紀1書にはこの神の別名をシオツチともいうとあるのが興味深い。
海幸山幸で彦火々出見を竜宮城へ案内する海神族の神と同名で、神武紀にも饒速日降臨情報の提供者として登場します。
事勝国勝長狭とシオツチは陸と海の土地神(長老)で、それぞれの降臨地の長老を合成したために2つの名が残ったのでしょう。
降臨を瓊々杵ひとりにしぼったのは神武への道程に複数の系譜が関与して複雑化するのを押さえるためかもしれませんが、瓊々杵の子には彦火々出見の他に9つの名が登場してだれがだれであってもおかしくない状況で、系譜の混乱もあるかもしれません。
降臨者を天火明としても内容に影響なし。彦火々出見は天火明の子かもしれません。
降臨者を瓊々杵として書いたのは、神武に至る過程で海神族の影響が大きかったからだと思います。
天照大神の孫が神武天皇の祖であることが大事、その途中は要点だけで十分・・といったところか。
鹿児島県川内市には新田神社があり祭神は瓊々杵尊でその御陵墓ともされる可愛御陵エノミササギが源とされます。(御陵墓指定にも迷いがあるように見えますけれど(^^;)
瓊々杵の上陸地は海神族とアマテラス族の接点、出水あたりだったのではなかろうか。
筑後川を有明海へでて海神族の根拠地の長崎や天草諸島に挨拶回りを兼ねた訪問をしながら南下した。
こちらの降臨は鼻歌交じりの船旅(^^; もちろん船は天の橋船。
瓊々杵の尊称にも火の文字がありますがこちらは島原雲仙の火か。
書紀には薩摩半島西端の野間の笠沙と思われる上陸地点がでてきますが、漂着でないかぎり陸の人間には条件が悪すぎると思います。
後に瓊々杵等の港整備の一環としての上陸はあったかもしれませんけれど、笠沙降臨伝承は瓊々杵よりずっと昔に「海外から漂着」した人物が重なって生まれたと見ておきます。
日向降臨ルートは筑後川を甘木市付近から遡って日田市〜小国町までは船旅。
阿蘇山麓を横断して高千穂を越えて延岡から日向へ。
五ケ瀬川の沢下りは最大の難所、現地人の道案内がなければ遭難確実(^^;
猿田彦が天孫一行を出迎えたのは阿蘇南麓あたりか。
記紀には「道をかきわけて進む」とありますが、道なき道を藪こぎで進んだのでしょう(^^;
このルートも途中までは船ですから船で降臨というのもそれほどおかしくはないです。
水行は10日程度でも陸行はたいへん、1日数キロがようやっとで1ヶ月といったところか。
後に猿田彦はその功績によって天之忍穂耳の舞姫であったアメノウズメを妻にもらうことになります。
天鈿女命、天があるのは天孫系渡来者を意味すると思います。
伊予や大隅、島根半島のサタはそれ以前の初期開拓者にちなむもので、猿田彦はその後裔と推定。
猿田彦と天鈿女の子等は天火明等と共に濃尾へ渡って伊勢に住み、そこにも故郷の五十鈴川の名をつけた。
日向五十鈴川と伊勢五十鈴川の河口が九州と近畿を結ぶ黒潮航路の海運拠点になります。
近畿の猿田彦と天鈿女の後裔(猿女君)は平安時代には神事(神楽)を司り、その一族の一人が古事記編纂にかかわった稗田阿礼です。
「天の八重多那雲押し分けて、稜威の道別き道別きて、天の浮橋に浮きじまり、そりたたして筑紫の日向の霊じふる峰に天降りましき」
青文字が瓊々杵側、赤文字が天火明側を表現しているわけです(^^;
海と山の降臨を合体させたために書紀での降臨地の記述はあいまいになります。
この海と山のルートを霧島横断で結合すると後の景行天皇巡幸の道になります。できるべくしてできた道なのだと思います。
書紀1書では「天孫」の妃は吾田鹿葦津姫アタカシツヒメまたの名を木花開耶姫コノハナサクヤヒメというとあります。二つの名がある人物が再び登場。
アタが薩摩半島の阿多(吾田)であるならこの「天孫」は九州南部の人物とみるのが自然と思います(神武の最初の妃が吾田吾平津姫)。
吾田鹿葦津姫の津はここでも海を示すと見ます。
葦と鹿と海、狩猟と漁労を行う人々、後の隼人族の娘だと思います。
これらの漢字をあてたのは書紀編纂時代でしょうけれど地域を識別できる伝承が存在していて、その意に近い漢字を使ったと考えます。
木花開耶姫は山系の神社の祭神ともなっていて、姉の木花知流姫が八島士奴美の妃であるなど付帯説話もあることから、吾田鹿葦津姫と木花開耶姫は別人とみます。
なお、木花開耶姫の名は吾田鹿葦津姫と違っていかにも伝説っぽくて理論的じゃない(^^;
なんらかの別伝承が合体されたものだろうと推察。
豊後あたりの出雲神族系伝承か・・木花開耶姫は美人だが、木花知流姫はそれなり。
だが美人薄命、木花開耶姫をめとったためにその氏族は永続しない、という書紀一書があります。
この話が天孫と対立した側の伝承であればそのような一書があることが納得できます(^^;
瓊々杵の妃が吾田鹿葦津姫で、天火明の妃が木花開耶姫。海には海の妃、山には山の妃が自然だと思います。
木花開耶姫は夫の天火明が記紀では行方不明となってしまうので瓊々杵の妻にもなってしまった(^^;
濃尾へ渡った天火明と木花開耶姫の東海での伝承が後に富士山や浅間山など中部関東の山岳に大山津見神の娘として祭られるようになったのでしょう。
ホツマツタエには「瓊々杵」と吾田鹿葦津姫の話が場所を変えて伊勢と伊豆の物語として登場しますが、吾田鹿葦津姫の名が木花開耶姫(桜)になる理由が書かれています。
桜であるならその分布から近畿が中心でしょう。この話は紀州濃尾での天火明伝承と記紀の瓊々杵伝承が合成されて生まれた話であろうと思います。
天津と天之
瓊々杵と鵜草葺不合に冠せられる天津彦という尊称は天津日子根と同じく海を意味すると思います。
天津日子根とは天津彦の先祖、の意でしょう。
彦火々出見(山幸)にも天津彦の尊称がありますが、これは海神族の妃をいれて縁戚関係になったために加わったものと推定します。
天火明は津がなく「天之火明」です。天之とは海系ではない人々、高御産巣日神系の人々ないしは農耕系文化の人々しめす尊称と推定します。
ちなみに天火明の名の由来は阿蘇の火でしょう。
「ツ」は「なになにの」を意味するという説もありますが、記紀での天津と天之の使い分けに注目します。
どちらも「なになにの」であるとしたらなぜ「津」と「之」を使い分けるのか。
「津」は九州西岸〜南岸の海で活動していた神産巣日神系の人々、海神族を意味するものだと解釈しておきます。
耳という名
「耳」という名について少々。
天之忍穂耳、布帝耳(天之葺根の母)、そして神武の子4人には全員に耳の名があります。
(魏志倭人伝の投馬国の長官も彌彌)
八岐大蛇伝承でアシナヅチに須賀之八耳の名がある記述も興味深い。
日向の耳川や五ケ瀬川流域は縄文の洞窟遺跡の多い秘境で、落ち武者の隠れ場にもなった地域。
八岐大蛇伝承は日向での事象。 耳川上流に八岐という地名があり、いくつもの谷筋が蛇のようにうねっています。
八岐大蛇とはいわゆる土蜘蛛とよばれる先住民の住む苔むし杉の生えた幾筋もの谷間の意味だろうと思います。
(ウエツフミには草薙の剣の来歴に興味深い記述があります)
地名が源か、氏族の慣習が源か・・
彦火々出見兄弟にも神武の兄弟にも耳はいません。
妃が違うにもかかわらず神武の子に耳の名があるのは神武の意志が働いたからだと思うのです。
日向出自であることを意識したのか、耳氏族の後裔であることを意識したのか・・
安寧天皇101-114の子には息石耳がいますが、息石耳の弟?の懿徳天皇92-105以降では彦あるいは日子が一般的となって耳は消え、孝霊175-204から開化225-248の名は「倭根子彦」(倭を祖先とする日子)が共通項となります。
なにを名の元にしているのか興味深いところです。
天孫の子等
九州南〜西岸は太古の南海系海洋民やBC2000以降の長江からの三苗系の子孫が多い地域で、海運者の発祥の地。
海運者の伝承の代表がウエツフミだと思います。類似伝承が太平洋岸にも散在する理由でもあります。
(ウエツフミといっても内容の異なる複数の写本があります)
これには73代目を神武とする鵜草葺不合王朝が書かれています。
ウエツフミは記紀の年代設定や伝承配列の影響を受けながら独自の記録を加えて編纂された書だと考えています。書紀が王朝の記録とすれば、ウエツフミには民との関係の記述の多いことも注目です。
記述に使われている「特殊文字」は海運者や後のサンカといった共同体の中で使われた一種の暗号文字で、仮名文字と同時代に作られたかもしれないが、少なくとも古代文字ではないと思います(ホツマ文字も同じくです)。
鵜草葺不合王朝の名称がでてきますが、記紀に登場する名称を流用して記述されたものでしょう。
2千年にわたる王朝として書かれているのは長江大洪水の三苗渡来を始祖とみなしているからだと思います。
1世代を25〜30年平均と見れば年代がぴたり一致します。
この王朝で多数の新文化登場がありますが、三苗が九州へもたらした新文化を示すものでしょう。
記紀には登場しない星神が多数登場するのも海神族の神々の伝承が残されたものだと思います。
瓊々杵はその九州南西岸の「海神族王朝」に婿養子的にやってきた。
三苗を祖先とする最新文化をもつ氏族の王子でもあり、アマテラスの紹介もあって成人後には海神族の主にもなったかもしれません。
彦火々出見は瓊々杵の実子なのか・・
彦火々出見には天津彦の尊称がありますが、山幸として書かれています。
瓊々杵の実子であるなら天津彦の尊称は当然ですが、なぜ山幸として書かれているのか。
妃の豊玉姫と彦火々出見に習慣の違いもあります。
彦火々出見は日向系の出自だが海神族の妃をとったために天津彦の尊称が加わったもの。
彦火々出見は天火明の子である・・少なくとも瓊々杵の子ではない。
記紀の彦火々出見兄弟には9種の名が登場し兄弟も2人から4人までいろいろで、系譜としてのつながりがいささか??となる部分です。
「火照、火須勢理、火遠理」、これが古事記。
以下は書紀。
「火闌降、彦火々出見、火明」
「火酢芹、火明、彦火々出見」
「火明、火進、火折彦火火出見」
「火明、火進、火折彦、彦火々出見」
「火酢芹、火折(彦火々出見)」
「火明、火夜織、彦火々出見」
「火酢芹、彦火々出見」
だれがだれにでもなりえる状況でこの時代の系譜伝承があいまいだからだと思います。
9つの名にはすべて火が含まれているのは重要な「共通項」のあることを示すものでしょう。
燃える家から脱出した子供達、火は桜島や霧島の噴火かあるいは戦の火か、どちらかだと思いますが、名に戦をイメージさせるものがないところから火山の火を表すものと思います。
瓊々杵の子、天火明の子、火山の子・・火の子供等はみな兄弟(^^;
ある時点で霧島や桜島の付近で瓊々杵系と天火明系、加えて南九州の先住者(後の隼人族)がドッキングした。
彦火々出見はそこで噴火災害にであったその子等のひとり。
ここまでの流れでは瓊々杵はBC130〜BC60頃の人物で、神武はBC5〜BC66頃の人物となります。
数世代が瓊々杵と神武の間にないと不自然です。
彦火々出見はひとりではない(^^; 彦火々出見の兄弟に多数の名があるのは複数の人物がここにいることをを示すのではないかと思います。
だれがだれの子であれ「彦火々出見兄弟」の紛争が海幸山幸伝承となります。
海幸山幸
宮崎県串間の偵察小屋。
火々出見様、昨日聞こえた雷鳴のような音は桜島の噴火の音だったようです。
被害がなければよろしいのですが。
ふむ桜島の噴火か。火須勢理はいやな奴だが村人は別だ。様子を見てこよう。
お気をつけくださいませ、船でゆかれますか。
おお、速い船を用意してくれ。
彦火々出見の名はその「火を見に出かけた」ところからの名(^^;;; 桜島の周囲30キロほどは古墳のない空白地帯です。 串間から鹿児島湾の鹿屋までおおよそ120キロ、快速船で3日ほどか。
おおごとだぞ、鹿児島は全滅したようだ。なんと海水が山の上にまで押し寄せたらしい。
海神族の船もずいぶん沈んだようだ。鹿屋でも火山灰がまだ降っていたぞ。
俺はとりあえずここにある食料を持ってもう一度ゆく。
急いで救援物資を集めてできるだけの人数と船を送ってくれ。
火々出見の手を握る火須勢理・・
貴殿の救援で何人の村人が助かったことか。礼の言葉もない。
海神族からも救援の手が届き始めた。もう大丈夫でござる。
ここでは礼もできぬゆえぜひとも指宿にお寄りくだされ。
てなわけで彦火々出見が指宿でひと風呂あびていると・・(^^;
海神族の長老がやってきた。
シオツチと申しますで。
こたびは仲間をお助けくださったそうで、わしらのところへもぜひ。
小さい船で申し訳ないの、鹿児島の救援で大きい船がではらっておるじゃけん。
沖へ出たら帆をはるじゃでの。少々波をかぶるが大きい船よりずっと早いでがまんしてござもす。
海神族の快速艇は双胴で中央に丸木が何本も渡してあり、その上に座ると水面の上を滑ってゆくような快感があった。
目の下に大きな亀が泳いでいるのが見える。
ありゃあまだまだ小さい、背中に2,3人乗れるようなでかいのもおるで。
次の港へはまだ時間がかかるで、釣り針を後ろへ流しておけば魚もかかるでやってみるけ。
釣り針はたくさんあるで、食い逃げされてもかまわんじゃけん・・
竜宮城でのお話は記紀通りとして・・
竜宮城はどこにあったのでしょうか。
豪華な宮殿だったかどうかはわかりませんが、少なくとも景勝地にある住まいだったと思います。
竜宮城は天草諸島、彦火々出見は瓊々杵叔父さんにも会ってきた。
なかなか帰らぬ彦火々出見を心配していた家臣や村人が、突然に竜宮城から戻ってきた主をあわてて出迎えるという神事が宮崎の青島神社に伝承されているそうです。
海幸山幸伝承は南海民の持っていた古伝承と彦火々出見時代の南九州進出と先住者の紛争に重ねて書かれたものだろうと考えています。
隼人舞いには海におぼれるような仕草があるようですが(あいにく見たことはありません)これは実際に海におぼれる様子かもしれません。
海で暮らす人々がおぼれるとすれば相当な災害にであった記憶があるということでしょう。
長江の大洪水の記憶を含んでいるのかもしれません。
山幸の得たもの
なぜ海神族が彦火々出見側を支援したのか記紀の話だけではよくわかりません。
海神族が同族であるはずの海幸を釣り針程度でこてんぱんにするのだろうか(^^;
海神族と薩摩大隅の先住の人々とのつきあいの方がずっと古い。古い故に紛争も生じていたのか?
しかし、瓊々杵と海神族が縁戚関係となっていたなら話は早いです。
海神族が彦火々出見に与えた支援は潮満瓊(玉)と潮涸瓊の不思議な力と相手と違うことをやれという一風変わったものです。
農耕でも武力でもなく相手を負かすものとは・・
経済という第3の力の登場を海幸山幸伝承が暗示するのではないでしょうか。
海神族と瓊々杵のドッキングによって商業の発達がはじまった。
これが記紀が瓊々杵を降臨者とする理由のひとつではないかと思います。
瓊々杵の名は海神族ゆかりの瓊ふたつが由来かもしれません。
商業の黎明期、祭祀はアマテラス族、軍事は天孫族、経済は海神族(海運者)が受け持つ連合王朝の様相が見えてきます。
祭祀と軍事だけでは王どまりです。経済力が加わってはじめて王朝が生まれる。
鏡、剣、玉(勾玉)のイメージもそれぞれ祭祀、軍事、経済に対応するように考えられたのでしょう。
長江の良渚文化における象徴、玉ソウ(祭祀)、玉鉞(軍事)、玉壁(経済)の日本版です。
三種の神器として鏡、剣、鈴とする説もあるようですが、鈴とは初期の馬鐸(銅鐸)であって古出雲王朝系の象徴が混じり込んだものではないかと考えています。
神武登場
記紀において彦火々出見の兄で喧嘩相手とされた火照(海幸)は阿多君の祖とされます。
「君」は皇族近親氏族の尊称で、阿多は薩摩南部ですから火照は瓊々杵につながる人物でしょう。薩摩隼人の祖かどうかは別にして関係深い人物かもしれません。
火須勢理は火照等と同一人物ともされますが、天孫とは縁戚関係のない地元先住の人物で彦火々出見と争って後に従属した大隅隼人の祖のひとりかもしれません。
彦火々出見は日向に降臨した天火明時代から神武時代に至る数世代にわたる複数の人物の代表名、とみなしておきます。
海神族の豊玉姫と慣習の違いがあるところから彦火々出見は山系の人物でしょう。
海神族側と婿入り、嫁入りが数世代にわたってくりかえされて縁戚関係が強化されたが、うまくゆかずに離婚することもあったわけです(^^;
BC110頃、現在の福建省、台湾の対岸付近にビン越国があります。
呉楚七国の乱に参与した長江付近の東越国は先に滅ぼされていますが、ビン越は存続して勢力を強めて栄えていた。
しかしBC110に武王の長江以南への侵攻がはじまりビン越国も滅亡します。
このとき多数のビン越と東越の住民が江蘇省付近へ強制移住させられています。
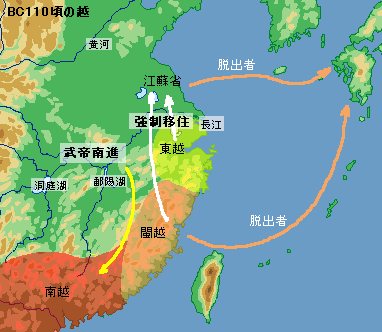
前漢に支配されて暮らすより九州へゆこう、祖先が渡っていた場所で自由に暮らそう・・
BC100頃に九州西岸へビン越や東越の人々が少なからず渡来していた。
最新の船の技もやってきた。南方系の製鉄技術をもつ者も含まれていたかもしれません。
縄文時代の三苗到来、弥生初期の戦国〜秦時代の山東半島や朝鮮半島の人々、そして弥生中期の越族の渡来。
呉楚七国の乱からの脱出者は王族だがごく少数だった、しかし50年後の脱出者は民間人で多数。
その人々が九州西岸各地で先住者と混じり合っています。
AD8には前漢が滅び、前漢から逃れていた人々の足かせも消えています。
出雲では瀬戸内〜近畿、日本海の縄文との一体化が進んでいます。
天孫では九州南部や西岸域の先住者と最新の中国系渡来者が一体化する、それが瓊々杵〜神武時代です。
鵜草葺不合は彦火々出見の実子なのか・・
豊玉姫と彦火々出見が離婚した、生まれた子はどちらが引き取るのか・・瓊々杵の親族が育てるのがよかろう・・(^^;
鵜草葺不合は彦火々出見に対応する海神族側の瓊々杵から神武時代に至る数世代の人物を代表させた名であるとみなしておきます。
その数世代間に日向天孫との縁戚関係が強化された。
ここまでは神代ですから記紀では実子でなくても「同族の子」なら子として書いていると思います。
九州の東岸と西岸の天孫の流れを彦火々出見と鵜草葺不合に代表させて合成したのが記紀の系譜。
記紀のあいまいな部分に三苗渡来から神武直前までの海神族の伝承を鵜草葺不合王朝として記述したのがウエツフミではないかと思います。
神武はだれの子なのか・・
神武の子全員につけられている「耳」の名は、神武が「日向天孫」を強く意識していたからだと思います。なぜ意識したのか。
神武の兄は彦五瀬、三毛野、稲氷、神武は末っ子とされています。
実際に4人兄弟かどうかは別にして、彦五瀬は日向の王、九州西岸では三毛野や稲氷が王となったが、神武の領土は霧島山麓の小さな野原のみ。
隼人勢力のどまんなかです。霧島山麓は薩摩隼人と大隅隼人の接点、隼人族の中心部。
なにかがなければ隼人勢力の真ん中に領土を得ることはできないと思います。
神武の最初の妃は吾田吾平津姫。吾田は南九州の一般地名で大隅半島には吾平町アイラの地名もあります。吾田吾平津姫は隼人族の娘でしょう。
おまえは隼人族の婿養子となって隼人族をまとめろ・・
隼人族の娘を妃にいれたのではない・・神武が隼人族へ婿入りした。
そこで得たのが霧島山麓の「狭い野原」。養子ならしかたなし(^^;
狭いけれど南九州では唯一の稲作可能な土地です。
神武の別名の佐野(狭野)の由来はこれだと思います。
神武は日向天孫から隼人族の土地へはいってその娘を妃として隼人族の王となった人物、としておきます。
神武は歴史を勉強した(^^;
中国ではどこでも父系じゃないか、母系を名乗る必要はないのか・・
俺は隼人の王、そして俺は日向天孫の子孫なのだ・・
神武の子に耳がつく理由はここにあり(^^;
なお、神武東征説話で神武の兄とされる三毛野や稲氷に海神を母としてという表現があるところから三毛野や稲氷側には母系を重視する感覚が残っていたのかもしれません。
神武がいつ生まれたかはちとむずかしい。
自説での神武即位はAD36となりますが、これは北九州で奴国を建国したときとみておきます。
20才くらいで南九州の奴国、10年ほど後に北九州での奴国建国とすればAD6頃の誕生か。
神武は濃尾天孫が活躍している話を聞いていたでしょう。
北九州では祖先の作った伊都国が栄えていたが、寒冷化がはじまり食糧事情が不安定となって出雲勢力との争いも再び発生しています。
AD25頃に神武は隼人族を統一し、陸海共に最強の軍隊が育ちつつあった。
養子の身の上と狭い領土、その境遇をバネにしてある考えが神武の中に芽生えはじめています。
九州の天孫と連携して出雲を九州から追い落とす、出雲領土を我がものに・・
川上しのぶ (c)2000/11原文 2001/06改訂 2001/08/28修正 woodsorrel@tcn-catv.ne.jp