公民館利用ルールの見直しが議題に 〜公運審笠懸部会 2025.9.16
随分と遅いように思われますが、8月も数日で終えようとしている8月28日(木)、ようやくみどり市公民館運営審議会(公運審)笠懸部会の今年度初会議が笠懸公民館で開かれました。
部会は笠懸公民館独自の問題やより議論を深めたい問題について審議するために開かれるものです。今年度の委員数は7人で、今回は公民館利用規則の見直しや加藤工太郎さんの急逝により空いてしまった市公運審委員長ポストについてなどの議題を中心に協議が行われました。
協議事項では、笠懸公民館の事業実施状況として今年度の講座・学級の開催状況や集会、事業の実施状況などについての説明があり、さらに、今後協議される公民館事業の点検・評価時に使われる評価シートの見方についての説明が公民館からありました。残念ながら説明内容が難しく、委員には十分に理解が行き届かなかったようすでしたが、委員からは質問もなく、議題は次の「公民館利用ルールについて」に移りました。
ここでの問題の焦点は、「公民館利用団体やサークルの構成員が7割以上、市内在住・在勤・在学者で占めなければならない」ことや、「部屋の予約は1度の申し込みでは2回まで」などのルールについてです。このルールは、合併前に笠懸公民館で施行されていたものを、市内各公民館の状況をあまり斟酌しないでそのままみどり市の公民館規則として引き継いだもので、その後の状況の変化もあり、今では違和感のあるルールです。
合併前の笠懸公民館は利用が非常に混雑していて、部屋の利用予約はたいへんでした。月初めには開館前から利用者が公民館入り口に詰めかけて、開館と同時に部屋の予約をするのが常でした。それでも人気の音楽室や交流ホールでは思うように予約のできない団体がでる状況で、「何とかしてくれ」という要望が利用者から出されていました。笠懸公民館長はこうしたことから、公運審に「利用ルールの策定」を諮問し、公運審では毎週のように協議を重ね、3年を費やして答申に漕ぎつき、今のルールの土台となりました。
しかし、合併後の状況は、新ルールが適用されたことやコロナの蔓延、地域の状況変化などによって大きく様変わりしています。東公民館では当日の申し込みでも部屋はほぼ借りられ、大間々公民館では多世代交流館のルールが適用されていて公民館規則は適用外です。笠懸公民館では、“市民7割ルール”が、「少子高齢化の影響でサークルのメンバーが少なくなる中、1人が脱会すると7割を割ってしまうなど会の存続に関わる」「高齢になり仲間が減る中で新しい仲間を得ようとしてもこのルールで輪を広げられない」「高校の同級生などで市内在住者が少なく、集まろうとしても集まれる場所がない」などといった“弊害がある”とする意見も増えているようで、時代の変化が出ていました。
こうした状況から今回の議題に上がったものですが、「合併前に20人の委員が3年かけて議論して策定したものを、数人で短期間の論議で変更すのは無謀ではないか。利用者の会や利用者懇談会、場合によってはアンケート調査などを経て慎重に取り組むべきではないか」との意見が出され、公運審笠懸部会としては継続的に事態を見つめていくことになりました。
加藤公運審委員長の逝去に伴う対応では、みどり市公運審が誕生した黎明期に委員長を務めた近藤巧さんが、今年度も残りが少ないことで、その期間だけ委員長をに着くことになりました。
次の公運審は全体会で、地域文化祭が終わる11月の開催を予定しています。これから行われる各種事業の評価や公民館大会への取り組みなど、公運審にはまだまだ盛りだくさんの協議事項が控えているようです。
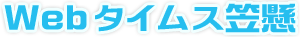
 ホームへ
ホームへ