区民の安全のため防災を学ぶ 〜みどり市7区 2025.7.8
 |
| 地域の防災について話す川端さん。 |
6月29日(日)午後2時から、みどり市笠懸町7区(区長=須藤修さん)で、区民35人が参加して同区公民館を会場にみどり市の出前講座「防災講座」が行われました。市防災危機管理課の川端均さんを講師に迎え、①笠懸町で起こりうる災害について、②地域にあった避難方法について、③避難所開設について学びました。
川端さんは、「昨年度、笠懸町6区で自主防災組織が結成され、みどり市は全地域に自主防災組織ができています」「この地域では災害の可能性少なく安全だが、太田断層による地震ではおよそ5,000世帯の断水(一日後)が想定されています」「どこに避難するか。食材等の備蓄の場所などを確認しておきしょう」などと話しました。
また、「報道されることが少ないが、一番困るのはトイレ。災害時には、飲食料や衣料の確保とともに、トイレ・衛生対策が重要。水や食料はある程度我慢ができたとしても、排泄を我慢することはできません。震災では、トイレに行く回数を減らすために水分を控えたことで慢性的な脱水状態となり、その結果、病気になってしまいます」とトイレ対策の重要性を話しました。
防災における自助・共助・公助についても触れ、地域の役割(共助)としては、「地域の人たちが知り合いに避難や安否確認などの防災訓練を行い、いざというときに共助(地域)の力が発揮できるよう備えましょう」「行政の役割(公助) は、能登半島沖地震ではほとんど機能しませんでした」などを話しました。
短い時間で急ぎ足の講演でしたが、会場の参加者からは、「私は公民館のカギを預かっていますが、災害時どうしたらよいのでしょうか」との質問に対して川端さんは、「ここは地区の公民館です。責任者は区長さんです。行政ではありません。避難所運営マニュアルを見てください」と、自主防災組織の市民参加による初期消火、救護及び避難訓練等の重要性が語られました。
その後、地区公民館長の吉田貴彦さん(現役の消防官)が中心となって、調理室から出火の想定で消防訓練が行われました。全員の前で通報者は携帯電話で消防署に通報、「火事ですか、事故ですか」との問い返しにしっかりと対応し、避難誘導も大きな声で行われました。
固定電話からの通報は、電話番号で場所がすぐにピンポイントで特定でき、携帯電話からでも30〜50mの誤差内で特定できますこと、119番は桐生消防本所につながりますが、発信場所により太田署や伊勢崎署につながることもあるということです。「いつ起こるかわからない災害から区民の安全を守るため、この講座が役に立てばよいです」との川端さんの言葉が印象に残りました。
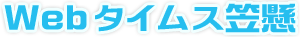
 ホームへ
ホームへ