“鹿田郷”の原型をつくった人たちの集落 ~笠西小用地の遺跡 2021.2.16
 |
| 「山田」と印された瓦を持つ藤生課長。 |
 |
| ■部分が発掘調査地点。(みどり市HPの「笠懸西小学校(仮称)建設工事の進捗状況」掲載の写真を一部加工しています (拡大する)。 |
令和4年4月の開校が予定されている(仮称)笠懸西小学校の建設用地(みどり市笠懸町鹿地内)で、工事に先立って行われた埋蔵文化財の発掘調査が終了し、その調査概要が市教育委員会文化財課から発表されました。笠懸野の古代のようすをうかがわせる重要な資料も発見されています。
建設予定地が決定したのち試掘調査を行ったところ、計画地内に遺跡があることが判明し、校舎等の建設に伴い埋蔵文化財の消滅が避けられない場所について記録保存のための発掘調査を行ったものです。期間は令和2年8月20日から12月7日まで、面積6,870㎡の調査が行われました。遺跡はこの地域の旧小字名をとって「天神遺跡」と名付けられました。
発見されたのは、縄文時代の落とし穴14か所、奈良・平安時代の竪穴式住居22か所、掘立柱建物跡1か所、井戸2か所、土坑39か所などで、縄文時代の落とし穴は、遺跡の北に広がる現在「大田んぼ」と呼ばれる湿地帯に集まったイノシシなどを獲るためのものだろうということです。奈良・平安時代の住居跡からは土師器や須恵器などの日用品のほか、カマドの補強材に獣脚(じゅうきゃく)の鋳型や瓦、製鉄炉の炉材を用いたものが多く見つかり、これらは上野国分寺の建立に関係するということです。また、天神遺跡は、「大田んぼ」を拓き、のちの「鹿田郷」(『新田義重譲状』(1168年)に出てくる新田荘19郷のひとつ)の原型をつくった人々の集落と考えられるということです。
上野国分寺の建立は8世紀の中頃で、その当時、この周辺は国分寺建設のための石材(天神山の凝灰岩採掘跡)や瓦(鹿田山や琴平山周辺の瓦窯跡)などの一大生産地だったということです。天神遺跡はそれから50年ほど下った9世紀以降のものということですが、その住居のカマドの補強材に国分寺建立に関係するものが使われていたということには興味がそそられます。「山田」という郡名がいくつも印された大きさ30cmほどの瓦はほぼ原形をとどめていますが、色が茶褐色でヒビも入っています。本来、瓦は登り窯の入り口を閉じた還元焼成で焼かれて灰色に仕上がりますが、空気が入るなどしてきれいに仕上がらなかったり、ヒビが入ったりしたものがいわば不良品として出荷されずに残されて、それらを住居に使ったのではないか、ということが想像されます。獣脚の鋳型は仏具などの脚部をつくるもので、本来の用途として使われた後には中を取り出すため鋳型は壊されるので、やはり使われずに残っていたものを住居に再利用したものかもしれません。口が少し欠けただけでみごとな形で発掘された灰色の瓶子(へいじ)をみせてもらっていると、「これは須恵器で、焼き方は瓦と同じですよ」と岩宿博物館長の萩谷さんが教えてくれました。
建設工事が急がれることやコロナ禍の影響で現地説明会は行われませんでしたが、文化財課では見つかった資料の整理をさらに進めることにしていて、藤生課長は「博物館での展示会だけでなく、地域の人たちや子どもたちが『自分たちの地域は昔はこんなところだったんだ』と身近に感じられるような活用を考えていきたい」と話していました。
→(仮称)笠懸西小学校建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査の結果について (PDF)
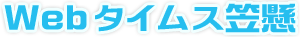
 過去の記事indexへ
過去の記事indexへ