読みやすさ、おもしろさをめざして ~新聞づくり研修会開かれる 2020.12.1
 |
| 新聞づくりについて説明する高橋さん。 |
みどり市笠懸公民館視聴覚室で11月24日(火)午後7時から、新聞づくり研修会が開かれ館報編集協力員や社会教育関係団体などの広報担当者、WEBタイムス笠懸の会員など17人が参加し、読みやすい記事の書き方などについて学びました。
この新聞づくり研修会は、笠懸公民館の主催で毎年行われています。今回講師を務めた桐生タイムス社編集局記者・高橋康之さんは20年以上の記者経験を持ち、昨年9月からはみどり市を担当しているということです。
高橋さんははじめに、「パソコンやスマートフォン、SNSの普及で情報が増えすぎて取捨選択や信ぴょう性の確認がたいへんになっている」「紙媒体はわかりやすさにも配慮され、責任感を持って出されているので地域の人に対して有効性を持っている」「全国紙などが地方に人を置かなくなってきて地域の話題が載りづらくなってきている。地域メディアの存在意義は大きい」と地域新聞や団体広報誌などの大切さを話し、そのあと具体的な記事の書き方などの説明に入りました。
新聞記事は表現や漢字の使い方で“中学生が読んで内容を理解できる”ことを前提にわかりやすさを意識していて、そのために“虎の巻”として用字用語ハンドブックを使っていると話しました。「最重要は第一段落に」「5W1H」が原則であり、「一文は短く」「句読点と改行でリズム感」が読みやすさにつながると話し、「カタカナ語やかっこによる強調の多用は避ける」「人名や連絡先の表記は特に注意」「特定商品名は言い換える」などの注意点のほか、不快語や差別語にも配慮が必要と話しました。よい取材をするためには事前の準備が大切ということ、見出しは一目で内容が理解できるものがよい、写真はなるべく1枚で伝えたいことを表現する、躍動感や感動が伝わればさらによい、など、新聞づくり全般にわたって自己の体験などを織り交ぜながらわかりやすく話しました。
講演のあと質疑応答も行われ、「行政区で新聞を出したいがどのような内容にしたらよいか」「毎年行われる行事を行われたことだけ書くのではつまらない記事になってしまう。主観や主張などの立ち位置が面白さにつながるのでは」などが出され、特に「おもしろさ」「主観を入れた記事」について活発に意見交換されました。
研修会を終了し館報編集協力員会会長の髙野富由美さんは、「今日の話を参考に見出しや写真を工夫して館報の内容を充実させていきたい。“やさしさ”を伝えられたらいいと思う。それぞれの団体がみどり市のよさを伝え、地域の活性化につながればうれしい」と話していました。身近な地域新聞や広報の大切さを改めて感じることができた研修会でした。
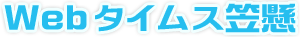
 過去の記事indexへ
過去の記事indexへ