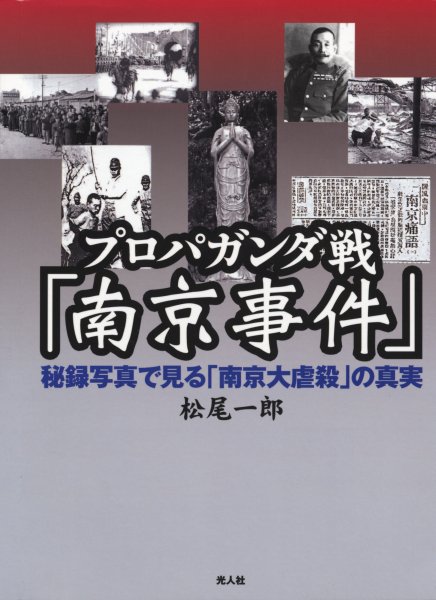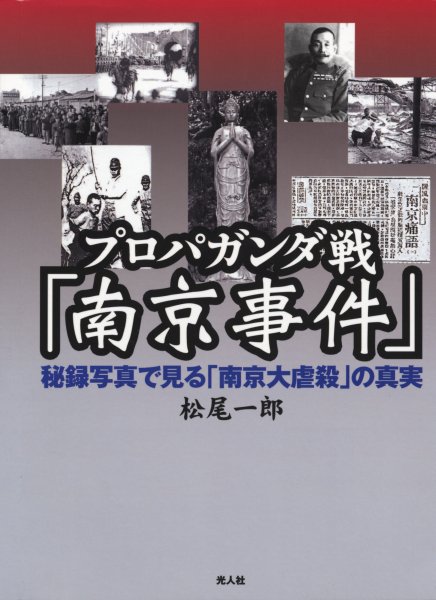郎一尾松
うろちいおつま
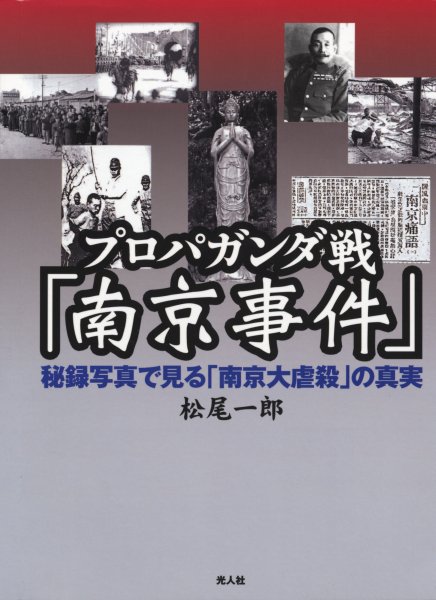
プロパガンダ戦「南京事件」
秘録写真で見る「南京大虐殺」の真実
平成十六年一月二十一日 光人社
ISBN4-7698-1163-2 C0095 税別千八百円
「南京大虐殺」は、中国の対外宣伝工作によって作られた虚構か?──「南京事件」に興味を抱き調査解析をはじめて七年余、新進気鋭の日中問題研究家が、新しい視座から事件の全容と情報思想戦の実態に迫る衝撃の歴史ノンフィクション。
序に代えて
黄 文雄
かなり前の話だが、南京「虐殺」の研究に並々ならぬ情熱を傾けていた鈴木明氏から、台湾人と中国人を見分ける新しい目安を教えてもらった。両者の顔は若干似ているが、「南京大虐殺」を信じるかと質問すると、「信じない」と答えるのは台湾人で、中国人の場合は「信じる」「鉄証如山」(確たる証拠は山のようにある)と答えると言うのだ。
もちろん中国人には例外も少なくない。私は、南京金陵大学で当時教鞭をとっていた何人かの学者に「虐殺」の見聞を徴したことがあるが、どの人も「都是騙人的」(すべて嘘だ)と言っていた。
中国社会はそもそも人間不信の社会であって、政府も民衆も嘘をつかなければ生きていけない。日本人は中国政府の主張を鵜呑みにするが、中国人は政府の言うことなど信用しない。中国民主化運動の長老である劉賓雁などは「『人民日報』紙上で、紙名以外はみな嘘だ。日付ですら嘘である」とまで指摘している。もっと強烈な批判は、朱鎔基元首相の捨てゼリフ、「只有騙子是真的」(ペテン師だけが本物だ)であろう。つまり「中国はすべてが嘘だ」と言っているのである。
このように考えると、広く真実と信じられている「南京大虐殺」という嘘は、戦後中国政府最大のヒット作と言っていいだろう。
「三光作戦」や「万人坑」「七三一部隊」もそうだが、「南京大虐殺」の嘘が、社会主義政権防衛のために行う反日、敵日の運動、教育、洗脳政策の強力なテコとなっていることは、私がずっと指摘してきたことだ。
私はかつて、「南京大虐殺」に強い関心を持つある日本の友人に、「あんな嘘を信じているのは実直な日本人だけだ。嘘を研究しても無意味だから、ほっておいたらどうか」と話したら、「いや、嘘も百回つかれたら、真実になってしまう。真実を徹底的に究明しなければならない」と言われた。さすがに日本人らしい。
たしかに「一犬日に吠え、万犬虚に吠える」といった現象は、世間ではよく見られることだ。ことに実直な日本人には、この「虚言」を素直に信じている人が少なくない。しかも「研究」の名を借りて、中国政府に呼応する反日学者も大勢いるから、やはり「虐殺」については、徹底的に研究する必要があると痛感している。
中国史から見た「南京大虐殺」は、実に凄まじいもので、東晋時代の王敦によるもの以来、南京大虐殺は王朝交代や内訌、内乱のたびに発生し、多くの城民が殺されてきた。就中、南朝時代の宋のときは、皇族間の殺し合いだったため、皇族一族は断絶した。梁の時代の候景による南京大虐殺は史上最多の死者を出し、日本軍の「百万虐殺」説は、これのコピーではないかとも思われる。南朝の中で、官軍王僧弁軍の南京への逆襲やら、隋の陳王朝攻滅の大虐殺も有名だ。隋以降、南京城は一事廃城にもなった。
その後も「南京大虐殺」は続き、十九世紀にも、太平天国の乱における曹国センの大虐殺、二十世紀に入ってからは、辛亥革命直後に張勲による大虐殺が起こった。曹国センの大虐殺当時、天京(南京)から財宝を搬出する車列は延々三ヶ月間も続いたと、趙烈文の『能静居士日記』に記録されている。
このように「南京大虐殺」は、中国で騒乱があるたびに欠かせない、いわば中国史の恒例行事のようなもので、もちろん大虐殺は、南京だけにとどまらず、長安、洛陽、開封、北京、揚州といった都市でも、歴代王朝の交替、変動のたびに行われていることは、『史記』をはじめとする「二十五史」など、この国の正史がはっきりと記録するところだ。
つまり中国の史例をモデルに創作されたのが、日本軍による「南京大虐殺」であるというのが、私が中国史研究を通じて得た結論である。
もちろんこれまで上梓された、優れた「南京大虐殺研究」からも、少なからざる教えを受けてきたが、今回私は松尾一郎氏の『プロパガンダ戦「南京事件」』のゲラを読み、これが真相の解明に対し、実に多くの示唆に富む研究成果であることを知った。またことにニセ写真の分析に精力的に取り組むなど、事件究明の上で実に核心をついている。
本書の上梓によって「南京大虐殺」の嘘の解明がさらに進むことを期待するとともに、これがより多くの人に読まれ、歴史の真実が広く伝えられることを願ってやまない。
まえがき
誰が述べたものなのか失念してしまったが、《嘘を百回繰り返すと真実になる》という言葉がある。この言葉は、まさに真実をついているのではないだろうか。事実と異なる話であっても、聞かされ続けているうちに、いつの間にか、さも事実であるように錯覚を起こしてしまうという例は意外に珍しいことではない。たとえば、毎年年末にはかならずと言ってよいほど放送される時代劇《忠臣蔵》がこれに当たるのではないかと感じてしまうからである。
この忠臣蔵は、年齢が若く実直な赤穂浅野藩の殿様であった浅野内匠頭が、京都の朝廷からの勅旨(使者)の接待役として任ぜられたものの、上役であった吉良上野介による意地悪に憤慨し、殿中である江戸城松の廊下で禁じられている抜刀をして斬り掛かったためにその責任を取り、切腹を命じられ、遂には浅野家取り潰しとなる。しかしその後、赤穂浪士四十七士は、幕府の追求を逃れつつも吉良邸へと討ち入り、主君の仇を討つといった義挙の物語である。
しかしながら、現在ではこの話が事実とずいぶん異なっている点があることが判明している。たとえば、吉良上野介は実際、浅野内匠頭に対して、朝廷からの勅旨に対する(現代風に言えば)ホスト役を指導する立場にあった。浅野内匠頭を、物語にあるように吉良が意地悪をすることで失敗されたとするならば、結果、それは吉良自身に指導役としての評価を落とさせることとなり、そもそも意地悪をして失敗させる必要性自体ないのである。
むしろ接待役としての浅野自身は、お世辞にも有能であるとはいえず、事実、失敗ばかりしていた。それに対し注意をした吉良に対して、七歳で家督を継いだ経歴を持つ浅野がカッとなり、家臣のことを顧みずに斬り掛かったのではないか。結果、《忠臣蔵》にあるように、浅野家は即切腹、お家取り潰しとなった。
ちなみに、殿中において抜刀したら、かならず切腹と思いがちだが、実際は抜刀したものの不問とされた者もいたのである。浅野切腹の本来の理由は、別の所にあったのではないかと、諸説言われている。
ところで、どうして忠臣蔵が今のような物語になったかといえば、元浅野家家臣討ち入りの話を聞いた、当時有名な芝居作家だった近松門左衛門らによって、面白おかしく現在の物語が作られたようである。有名な《忠臣蔵》には、事実とはずいぶんとかけ離れた真実が存在しているのである。
日本人は知らず知らずのうちに、物語を繰り返し見たり、聞いたりしているうちに《吉良=悪》《浅野=善》という図式が固定観念として定着し、何ら疑問を感じなくなっていったのは、先に述べた言葉通りといえよう。南京事件を忠臣蔵と同レベルで論ずるつもりはないが、固定観念にとらわれずにご一読いただけたらと願うばかりである。
平成十五年八月
自宅にて 松尾一郎
【終章──国際宣伝戦での敗北】
南京事件は、昭和十二(一九三七)年七月七日の盧溝橋事件から始まる日中間の戦争中に、中国によって対外宣伝工作、つまり情報・思想戦によって作られた可能性が高い。蒋介石率いる国民党は、盧溝橋事件当初から、ラジオ放送などを使ってデマを飛ばし、その結果、日本人が虐殺された通州事件なども起きており、中国側の宣伝の巧妙さを証明している。今ではその「通州事件」そのものが、あらかじめ計画されたものであったことが判明もしている。
この宣伝工作において、八月十三日に始まった第二次上海事変から揚子江岸一体の戦闘で、日本軍は常に勝利していたものの、米国内にあった国際宣伝(情報・思想戦)という主戦場では、気づかぬうちに敗北し続けていたのである。そして、とうとう十月には『ライフ』赤ん坊写真によって、痛恨の一撃を食らうまでにいたってしまった。
上海戦での敗退以降、蒋介石が何とか英米などの干渉を引き出そうと、あの手この手を尽くしていた様子や心理状態は、多くの関連史料の中から読み取ることができる。南京陥落の二ヶ月後の昭和十三年二月一日には、国民党は共産党と合流することで宣伝機構を統一し、軍事委員会政治部が設立されたことにより、今まで国民党の一組織によって行われていた宣伝工作(中央宣伝部)が、一気にこれら宣伝工作に数万人をも動員できるまでに増員されたことになった。これにより、さらに中国側の(主に)対米宣伝工作が活発化することとなったのである。写真集『日寇暴行実録』、ティンパーリーの著書『外国人の見た日本軍の暴行』などの対日イメージを悪化させる宣伝書がつぎつぎと発行されたのはこのためである。
昭和十三年以降、米国における対日感情が急速に悪化しはじめた。日米開戦の遠因が日中戦争にあるというのは、まんざらウソではないといえる。国際外交上において、一度、相手国に対して不信感が生まれると、なし崩し的に急速に関係悪化が起きることは、歴史上さほど珍しいことではない。中国の抗日宣伝工作によって、米国の対日感情が悪化し、時間の経過とともに雪ダルマ式に大きくなり、そのため遂に日本は昭和十六(一九四一)年十二月八日に、真珠湾攻撃をもって太平洋戦争に突入し、昭和二十(一九四五)年八月十五日を以て終戦となる。
その後の東京裁判では、プロパガンダ(宣伝)工作《南京事件》のイニシアチブ(主導権)は中国から米国へと移り、歴史的政治ショーであった東京裁判において、『南京事件』という一方的な断罪を受けることとなった。
東京裁判から二十三年後には、今度は日本国内のマスコミがイニシアチブをとって中国共産党とともに、『南京大虐殺』宣伝工作を担った。その背景には、明らかに日中国交正常化に際しての中国の宣伝戦略が存在しており、いかにして外交交渉を有利に運ぶか、という目的があったことは間違いないだろう。
そしてさらにその十年後に、再度、日本国内マスコミの大宣伝によって、遂には『南京大虐殺』という新しい呼び名が、教科書にまで掲載されるまでになり、日本国民は中国に対して民族的贖罪意識を植えつけられる洗脳書を、政府によって与えられるまでになってしまった。今では南京事件は、中国政府によって、対日恫喝カードとして使われるまでになった。
再度述べるが、南京事件は、最初は中国(蒋介石率いる国民〈中華民国〉政府)が大宣伝を行い、続いて米国、その後に中国共産党と日本国内のマスコミ宣伝によって『南京大虐殺』が作られ、つぎつぎと主導権が移りながらも、いまだもって続く国際宣伝工作事件なのである。日本政府が、このような国際宣伝(情報・思想)戦に対し、現在もなお有効な対策を打ち出せない以上、今後も悲しい敗北をつづけるのは間違いない。
あとがき
南京事件に興味を持ち、調査を始めてから約七年となる。その間、とある会にも関わったが失望し、インターネットでホームページを作成して、少しでも多くの人に入手困難な史料の閲覧ができればと考え、現在まで運用している。(http://www.history.gr.jp/) これまで多くの方々から数々の資料の提供も受け、その結果、一冊の書籍として発表することができた。この場を借りて、特に私にとってかけがえのない方々の名前とともに、その功績に感謝したいと思う。
私が一番影響を受け、ご指導を頂いた田中正明先生、阿羅健一先生、故・鈴木明先生。一九九八年二月から一年間活動を行ったプロパガンダ写真研究会では、五明祐貴氏、中田崇氏、渡辺龍二氏ら。彼らは難しい写真検証に成果を出された優秀な方々であった。特に先の二名は学生という立場でありながら優秀な才能を十分に発揮してくれ、なおかつ身を削りながらの活躍に言葉もない。心から謝意を表したい。
「興亜観音を守る会」では、倉林和男氏、半元茂氏、そして今坂芳正氏は私が運営するサーバーにおける運用を援助して下さった方であり、感謝の言葉もない。貴重な映画『南京』を販売している日本映画新社の山内隆治氏の歴史映像における熱意や、小林一博氏、大塚英治氏、Kさん(川崎在住)、石山貴英先生のおかげである。この本をまとめるにあたって、光人社の牛嶋義勝氏には、ひとかたならぬご配慮をいただき、感謝の心を表する次第です。なお、記録映画『南京』については、日本映画新社(電話番号〇三─五四〇四─七八七〇にて入手可能である。ぜひご覧頂きたい。
平成十五(二〇〇三)年十月 著 者
る還へ【書蔵蔵溜古雲】