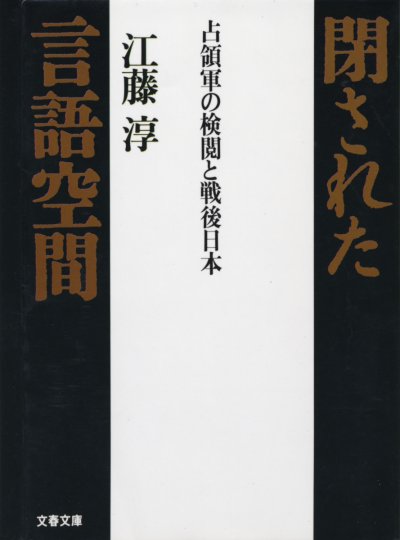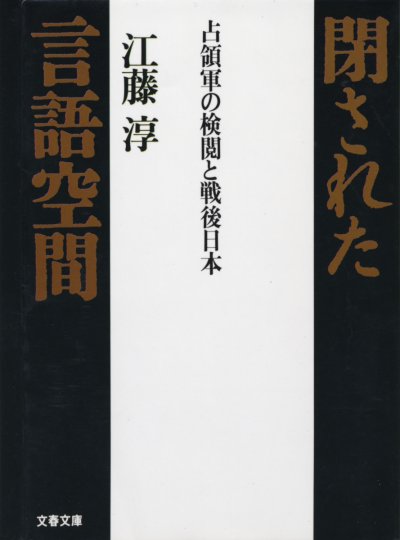淳藤江
んゅじうとえ
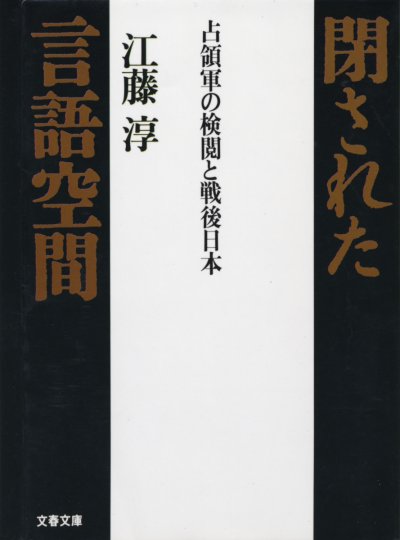
閉ざされた言語空間
占領軍の検閲と戦後日本
平成六年一月十日 文春文庫 税別五百八十三円
ISBN4-16-736608-8 C0195
さきの大戦の終結後、日本はアメリカの軍隊によって占領された。そしてアメリカは、占領下日本での検閲を周到に準備し、実行した。それは日本の思想と文化とを殱滅するためだった。検閲がもたらしたものは、日本人の自己破壊による新しいタブーの自己増殖である。膨大な一次資料によって跡づけられる、秘匿された検閲の全貌。
かたいてし備準にかいを閲検ので本日はカリメア 部一第
第一部 アメリカは日本での検閲をいかに準備していたか
-
第一章
昭和五十四年秋から昭和五十五年春にかけての約半年間、私は、ワシントンの中心部にあるウィルソン研究所(Woodrow Wilson International Center for Scholars)から、メリーランド大学付属マッケルディン図書館(Mckeldin Library, University of Maryland)と、スートランドの合衆国国立公文書館分室(The National Record Center, Suitland, Maryland)に、数日置きに交互に通うという日課を繰り返していた。
私は、九ヶ月間と限られたワシントン滞在中に、日本占領中米占領軍が行った新聞、雑誌等の検閲の実体を、できるだけ明らかにしたいと考えていた。最初に私がこの問題に逢着したのは、三年間「諸君!」に、『忘れたことと忘れさせられたこと』(文藝春秋刊)を連載していたときであった。
通説によれば、日本は敗戦・占領と同時に連合軍から「言論の自由」を与えられたことになっている。しかし、当時の状況を逐一調べてみると、実際には降伏文書調印から二週間も経たぬうちに、昭和二十年(一九四五)九月十四日午後五時二十九分を期して、まず同盟通信社が占領軍当局から二十四時間の業務停止を命じられていた。そして、翌十五日正午、業務再開を許されたときには、「同盟の通信は日本のみに限られ、同盟通信社内に駐在する米陸軍代表者によって百パーセントの検閲を受け」ることになっていた。
「朝日新聞」は同年九月十八日午後四時から九月二十日午後四時まで、四十八時間の発行停止処分を受けていた。
英字新聞「日本・タイムズ(The Nippon Times)」は、九月十九日午後三時三十分から同月二十日同時刻まで、二十四時間発行を停止されていた。十月一日には、「東洋経済新報」昭和二十年九月二十九日号が占領軍当局から回収を命じられ、断截処分に付せられていることも、のちになって知ることができた。
これを見れば、あたかも測り知れぬほどの大きな力が、占領開始後間もない時期に、外部から日本の言論機関に加えられたかのようであった。そして、この時期を境にして、占領下の日本の新聞、雑誌等の論調に一大転換が起こったことも、実際にその紙面に当たってみればまた明らかであった。
それが直接には、占領軍当局の実施した検閲の影響であることは自明だとしても、そのとき日本人の心の内と外でいったいなにが起こったのか、私はあたう限り正確に知りたいと思った。それは単に、過去に対する好奇心だけからではない。奇妙な感じ方と、人はあるいはいうかも知れない。しかし、私は、その当時起こったことが現在もなお起こりつづけている、という一種不思議な感覚を、どうしても拭い去ることができなかったからである。
それであれば、占領軍の行った検閲の実体を明らかにするというこの仕事は、過去と現在とに、つまり日本の戦後そのものの根底に対して、同時に一つの問いかけを行う試みになるはずである。私たちは、自分が信じていると信じているものを、本当に信じているのだろうか? 信じているとすれば、どういう手続きでそれを信じ、信じていないとすればその代わりにいったいなにを信じて、私たちはこれまで生きて来たのだろうか。
こう自問したとき、私は、『忘れたことと忘れさせられたこと』を書いたときよりずっと以前から、自分が何度も同じ問を繰り返して来ていることに気がついた。昭和四十四年の暮れから昭和五十三年の晩秋まで、私は毎月「毎日新聞」に文芸時評を書いていた。それは三島由紀夫の自裁にはじまり、《繁栄》の中に文学が陥没し、荒廃していった九年間だったが、来る月も来る月も、その月の雑誌に発表された文芸作品を読みながら、私は、自分たちがその中で呼吸しているはずの言語空間が、奇妙に閉ざされ、かつ奇妙に拘束されているというもどかしさを、感じないわけにはいかなかった。
いわば作家たちは、虚構の中でもう一つの虚構を作ることに専念していた。そう感じるたびに、私は、自分たちを閉じ込め、拘束しているこの虚構の正体を、知りたいと思った。現行一九四六年憲法第二十一条が、言論・表現の自由を保障しているところを思い出してみれば、おそらく憲法すらこの虚構の一部分を構成しているに違いなかった。
結果的にいえば、『忘れたことと忘れさせられたこと』は、昭和五十三年秋に本多秋五氏との間で行われた《無条件降伏》論争から発展したものであるが、実はこの論争自体が、私にとって見れば幾度となく繰り返してきたあの自問の、一つの帰結に過ぎないものであった。虚構の正体を知りたいと思うなら、占領軍が行った検閲の実体を見定めなければならない。『忘れたことと忘れさせられたこと』の連載を終えたとき、私は、ここにこそ問題を解きほぐす手がかりがあることを疑わなかった。
だが、どのようにして? 実際に検討してみると、占領期の検閲を扱った文献は、きわめて寥々としていた。
書籍として刊行されているものは、松浦総三氏『占領下の言論弾圧』(現代ジャーナリズム出版会刊)、門奈直樹氏『沖縄言論統制史』(同上)の二点、論文としては、福島鋳郎氏『占領初期における新聞検閲』(思想の科学研究会編『共同研究日本占領軍の光と影』上巻所収・徳間書店刊)一篇のみが、私の目に触れ得たもののすべてであった。
この実体を反映してか、谷井精之助氏『近代出版側面史──著作権の変遷と発売禁止』(『日本近代文学大事典』第六巻所収・講談社刊)も、慶応四年(一八六八)以来昭和五十年(一九七五)にいたる百八年間の発売禁止事例を詳しくたどりながら、占領軍の検閲については記事が乏しく、その結果発売(掲載)禁止になった事例は一つもあげられていなかった。要するにこれらの文献は、それぞれいくつかの示唆を与えてくれはしたが、さして参考にならぬことが明らかであった。
そうである以上、米占領軍が行った検閲については、一次史料に即して、自分の手で解明を試みるよりほかに手立てがない。そう思った私は、かねて招きを受けていたウィルソン研究所での研究題目を、「米占領軍の検閲とそれが戦後日本文学に及ぼした影響」と定め、そのことをジェイムズ・ビリングトン所長に通知した。
メリーランド大学付属マッケルディン図書館に在勤中の奥泉栄三郎氏から、一通の書状が寄せられたのは、あたかもその頃である。その手紙によれば、奥泉氏は慶應義塾図書館からマッケルディン図書館東亜図書部に移った人であった。そしてそこには「『諸君!』に連載された『忘れたことと忘れさせられたこと』を呼んで、あなたが占領時代に興味を持っていることを知った。
当図書館の資料がきっと役に立つと思われるので、アメリカに来たら是非立ち寄ってみてほしい」という趣旨が記されていた。なおこの書状には、二、三の資料が添付されていた。
マッケルディン図書館に占領中米軍の検閲を受けた日本の書籍、新聞、雑誌等のおびただしい資料が収められているということについては、私は、奥泉氏の手紙を受け取る前から承知していた。
しかし、この資料がゴードン・W・プランゲ文庫(the Gordon W. Prange Collection)と命名されて、同図書館東亜図書部所蔵の正式のコレクションになり、昭和五十四年(一九七九)五月六日に献呈式が行われたばかりであるということは、奥泉氏の手紙に添えられた資料によってはじめて知った事実であった。
それによれば、プランゲ文庫の内容を成しているのは、日本占領中に米軍民間検閲支隊(Civil Censorship Detachment, CCD)の検閲を受けた書籍と小冊子四万五千点、雑誌一万三千種、新聞一万一千種である。この膨大な資料がメリーランド大学の所有となったのは、戦前からこの大学の史学教官だったゴードン・W・プランゲ博士が、占領中GHQ参謀第二部(G-2)の戦史室に六年近く勤務したという因縁による。プランゲ博士は、昭和二十六年(一九五一)秋に帰国したときには戦史室長になっていたが、その際廃棄処分になりかけていた検閲資料を持ち帰ることを思い立ち、米陸軍が当時コンテナーとして使用していた五百箱の黒塗りの木箱にそれを詰めて、じぶんの本務校であるメリーランド大学に持ち帰ったのである。
しかしながら、以後昭和五十二年にいたるまで、二十六年間この資料はマッケルディン図書館の地下室に死蔵されていた。
この年になって、米国人文科学振興基金(The National Endowment for Humanities)から十一万七千ドル余の助成金が下りることが決まり、著名な書誌学者フランク・シュルマン氏と奥泉氏の下でようやく整理が開始された。しかし、一応の整理が完了したのは書籍と雑誌だけであり、児童文学関係書には全く手がつけられておらず、新聞の整理もあまりはかどってはいない。
以上のような予備知識を、私は、奥泉氏の手紙とそれに添付された数通の資料から得ることができた。プランゲ文庫は、スートランドの国立公文書館分室と並んで、ワシントンにいるあいだに足繁く通わなければならぬ場所になりそうであった。
スートランドの国立公文書館分室については、大蔵省財政史室編『昭和財政史・三・終戦から講話まで・アメリカの対日占領政策』(東洋経済新報社刊)の「文献解題」で、秦郁彦氏が簡単に紹介しているので、私はそこにダンボール箱約一万個に達するという占領軍関係の文書が収められていることを知っていた。その中に当然G-2(参謀第二部)関係の文書があり、G-2の所管下にあった民間検閲支隊の文書も含まれているはずである。いわば、検閲した方の資料はスートランドで探し、検閲された方の資料はプランゲ文書で検索する、というのがワシントンで私がしなければならぬ作業の具体的な内容になるように思われた。
だが、そのとき私は、いったいそれがなにを意味するかを、かならずしも正確に知っていたわけではなかった。
プランゲ文庫を最初に訪れたのは、ウィルソン研究所に着任してちょうど一週間目にあたる、昭和五十四年(一九七九)十月八日の午前中であった。
ウィルソン研究所から、メリーランド大学のメイン・キャンパスのあるカレッジ・パークという小さな町までは、車でおよそ四十分ほどの距離である。カレッジ・パークはワシントンの東北約十マイルの地点に位置し、国号一号線で結ばれている。なだらかに起伏する丘を一つ越えたところにひろがるこの大学の明るいキャンパスについては、ほかの場所にも書いたのでここでは繰り返さないが、プランゲ文庫のある東亜図書部は、マッケルディン図書館の三階に位置を占め、シュルマン・奥泉の両氏のほか、数名のスタッフによって運営されていた。
私はこの日、「創元」第一輯(昭和二十一年・一九四六・十二月発行)に掲載を予定され、占領軍の検閲によって掲載禁止処分に付せられた吉田満『戦艦大和ノ最後』の初出(となるはずであったもの)の校正刷りにめぐり逢う、という幸運に恵まれた。その間の事情については、『落葉の掃き寄せ』(文藝春秋刊・現行版は『落葉の掃き寄せ・一九四六年憲法──その拘束)の合本)に縷述してあるので一切省略する。いずれにしても、プランゲ文庫での第一日は、どちらかといえば幸先のよいスタートを切ったのであった。
一方、スートランドの国立公文書館分室には、それから一週間後の同年十月十五日の午後に出かけた。
この日は十月だというのに、ひとしきり雪が舞い飛ぶという肌寒い日で、午前中リサーチ・アシスタントのディヴィッドを連れて、研究者登録のために公文書館を訪れたときにも、雪は小降りになりながらもまだ降りつづいていた。
登録を済ませて研究者カードをもらい、文書係に研究目的を告げて、スートランド分室の文書係への紹介を依頼するのが、ここのシステムであった。
所定の手続きを終えるともう昼過ぎになっており、ディヴィッドと地下の小食堂に下りて、昼食用に買ったサンドイッチのビニールの包装をはがすと、パンが水気を吸ってふやけた麩のようになっていた。
しかし、私は、黙ってそのサンドイッチを味のないぬるいコーヒーと一緒に食べた。食物のまずさになど、かまっている暇はない。資料も文書も膨大な量にのぼるというのに、時間は最初から限られており、しかも刻一刻と翔び去って行く。そういう思いが、私の胸を噛みつづけていた。
その日の午後、いったん研究所に戻ると、私はスートランドの分室に電話を掛けて道順を訊いた。気の良さそうな中年の女性らしい声が、ペンシルヴェニア・アヴェニューを一路南東に向かい、アナコスシア河を渡って、ブランチ・アヴェニューを右折し、スートランド・ロードとの交叉点で左折すればよい、といった。分室のあるフェデラル・センターの入口は、スートランド・ロードに面しているというのであった。
わかり易い道筋であるにもかかわらず、私はブランチ・アヴェニューに入ってしばらくすると、スートランド・ロードへの曲がり角を見失って車をめぐらさなければならなかった。車がアメリカの友人から借りた車で、速度計の針が停まったままだというのも工合が悪かった。そのあたり一帯は黒人の居住区で、すでに雪は止み、青空が拡がりはじめているのに、寒さのせいか街路には人影がなかった。
そんなわけで、スートランドの分室にたどり着いたときには、すでに午後二時半を過ぎていた。まっすぐ行けば二十分しかかからない距離を、倍近くの時間をかけてウロウロしていたのである。
公文書館分室、つまりナショナル・レコード・センターは、いくつかの建物から成り立っているスートランド・フェデラル・センターの、一番奥まった一隅に在った。この地域は墓地の多いところで、フェデラル・センターの隣りも、斜め筋向かいも広大な墓地になっていた。人の墓地の隣りに、文書の墓場があるのか、と私は一瞬思った。しかし、人間はともかく文書なら、墓場から甦らせることも可能なはずであった。
国立公文書館の本館は、ワシントンの中心部に数多く見られるギリシア神殿風の大建築だが、分室のほうは背の低い一階建てのバラックのような建物で、少なくとも外見上は、歴史的に重要な文書を収蔵する場所とも見えなかった。入口をはいって右手に行くと、廊下の右手に小さな閲覧室があった。
この部屋は二つに区切られていて、入口に係員のデスクがある部分は事務室と休憩室の機能を兼ねており、ソファが置いてあって、ここでは喫煙が可能であった。閲覧室そのものは、休憩室とガラスの仕切で区切られた殺風景な部屋で、十ほどもある二人掛けの机に向かって、七、八人の人々が傍らに積み上げたダンボール箱から文書を取り出しては読み耽っていた。なかには、猛烈な速度でタイプライターを叩いている女性もいた。
入口の係員に来意を告げると、どういう手違いか、ワシントンの本館で紹介された文書係は、休んでいるという話であった。だが、代わりの者がいるから、今ここに呼びましょうという。ものの十分も待つうちに、姿を現したのは、実験着のような白い上っ張りを着用した小柄な人物で、口髭を生やしていた。ミスター・パーネルと名乗ったこの黒人の文書係が、以後スートランドに通っている期間を通じて、私の面倒を見てくれたのである。
パーネル氏の話では、スートランドの文書の特徴は、検索がきわめてむつかしいところにあるという。つまり、占領終了に伴い、GHQが解散され、文書類を本国に持ち帰ったときのシッピング・リストがあるだけで、そのほかにはインデックスもなければ、カードも作られていない。したがって、シッピング・リストを見ておおよその見当をつけ、あとは文書係に尋ねるよりほか方法がない、というのであった。
閲覧室の入口には、閲覧者の氏名、研究者カード番号および入室の時刻を記入するようになっている帳簿が置いてあった。パーネル氏に促されてその帳簿に所定事項を記入し、私は空席に坐ってあたりを見まわした。パーネル氏がシッピング・リストを持って来てくれるまでは、なにもすることがない。ほかの閲覧者の机には、どれも例外なくダンボール箱が積み上げられている。あれが《ボックス》なのだ、あの《ボックス》を探し当てなければならないのだ、と私はかすかな昂奮を覚えないわけにはいかなかった。
部屋の奥まった一隅には、日本人らしい二人連れがいて、一心不乱にタイプを叩きつづけていた。あとでわかったことだが、この人々は国会図書館の職員で、スートランドの文書類のうち、さしあたりGHQ民政局関係の者をマイクロフィルムに撮り、日本に持ち帰るために派遣されて来ているのであった。
パーネル氏が小脇にかかえてきたシッピング・リストを見ると、G-2関係の文書だけでも優に二百箱はあることがわかった。検閲を所管した民間検閲支隊(CCD)関係の文書は、その中に含まれているが、十箱や二十箱では到底らちがあきそうもない。私は持参したカードに、おそらく関係がありそうな《ボックス》の番号を抜き書きしはじめた。
これを全部読み通すために何ヶ月、いや何年かかかるだろう、という想いが、一瞬脳裏をかすめた。
この作業に没頭しているうちに、いつの間にか小一時間ほどの時間が経過していた。時計を見ると、間もなく午後四時である。私は席を立って、入口の係員に、パーネル氏を呼んでもらうように依頼した。
間もなく現れたパーネル氏は、私のカードを一瞥すると、ある一枚を取り上げてボールペンでマークし、
「この辺からはじめたらいいんじゃないかな」
といった。
見ると、それはRG(Record Group)番号二三一、《ボックス》番号八五六八という《ボックス》であった。どうしてこの辺からはじめるのがいいのか、もとより私にその理由がわかろうはずもない。とにかくここは文書係の言葉を信じるよりほかないと観念して、私はパーネル氏に、
「それではその《ボックス》八五六八を持って来ていただけますか?」
と、うかがいを立てた。
すると、意外にもパーネル氏は首を横に振って、腕時計を指さした。
「もう四時だよ、ミスター江藤。スートランドでは午後四時になると閲覧中の文書を回収する。午後四時十五分には閲覧室を閉めてしまう。今度はいつ来るかね。日本にはいつ帰るんだね?」
「今度は十月十八日に来ます。日本には来年の夏まで帰りません」
と、私は答えた。
「それじゃ時間はたっぷりある。十八日には、その《ボックス》を出して置いてあげよう」
と、パーネル氏はいった。
「ありがとう、ミスター・パーネル」
と、私がいった。
「フレッドだよ。フレッド・パーネル」
と、パーネル氏がいった。
「ごきげんよう、フレッド」
と、私は挨拶した。
こんなふうにして、スートランドでの第一日が終わった。
当時の研究ノートを見ると、私はそのあと、十月十八日、二十二日、二十三日、二十四日と続けてスートランドの公文書館分室に通っている。《ボックス》には玉石混淆という趣で、ファイルがぎっしりと詰まっており、その中に収められている文書から自分の目的に合うものを選び出し、コピーにまわすという手続きが、意外に時間のかかるものであることがわかって来たからである。
コピーをするためには、所定の書式に複写すべきすべての文書を特定して記入した申請書を出して、料金を前払いしなければならないが、出来上がって来るまでには平均して二、三週間、時によると一ヶ月以上も時間がかかった。料金は一頁当たり十五セントで、閲覧室の入口のデスクに控えている係員に支払うのが規定である。
係員の顔は行くたびに変わっていて、愛想のいいのに当たるときと、そうでないときとがあった。ある日、コピーを頼みに行くと、デスクに坐っていた仏頂面の若い男が、申請書と私の顔とを見くらべて、
「あんた、何を調べてるの?」
と、訊いた。
「CCDの検閲について調べています」
と、答えると、若い係員は、
「検閲?」
と、ちょっと怪訝な顔をして、
「ああ、日本を民主化するためにやったんだろう」
といった。
「だから、何のためにやったのか調べているのです」
と、私は小切手に支払うべき金額を書き入れながらつけ加えた。
もちろん、この若い係員のように単純に割り切ってしまえば苦労はない。しかし、誰が何のために占領下の日本で検閲を実施したのか、という基本的な問に答えることは、そう造作のないことではなさそうに思えた。
まず、《誰が》についていえば、CCDが検閲の実施に当たったことは、スートランドとプランゲ文庫の資料からしてあまりにも自明だとしても、それが占領軍当局の、つまり現地軍司令部としてのマッカーサー司令部独自の政策にもとづいているのか、それともワシントンの合衆国政府からの訓令または命令にもとづいて行われたことであるのかは、その段階での私には、まったく判断の材料がなかった。《誰が》が正確にわからなければ、《何のために》についても正確な解答を得られようはずはない。《ボックス》のファイルに収められた雑多な文書を一つ一つ読み進めながら、私は、早くこの《誰が》についての手がかりを得られないものかと、ひそかに願っていた。
それは、十月二十四日の午前中であった。私は、依然として《ボックス》番号八五六八に収められた文書と格闘していたが、そのうちに一通のかなり部厚いファイルに行き当たったのである。
一読してみると、この文書は、マッカーサーの参謀第二部長チャールズ・A・ウィロビー少将が、参謀長エドワード・M・アーモンド少将に宛てた長文の覚書の草案で、一九四九年(昭和二十四年)三月と記されており、日付ははいっていなかった。この覚書に「案件」として掲げられているのは、検閲要員の配置転換の問題であるが、それに続いて記されている「本件に関する基本的事実」の(A)を見たとき、私はしばしわが眼を疑った。そこには次のように記されていたからである。
《一九四四年十一月十二日付JCS八七三/三(附表A)は、合衆国の責任範囲内の地域における民間通信検閲の責任を戦域軍司令官に課し、かつこれが敵国領土占領期間中を通じて軍当局の実施すべきものであることを定めている。また、当該命令書は次のように述べている。検閲は、「その範囲と寛厳の程度については戦域軍司令官の裁量によりこれを緩和することができる。しかしながら、いかなる地域においても、あらかじめ統合参謀本部の許可なしにこれを終了させることはできない」》
つまり、検閲は、やはりワシントンの、この場合は統合参謀本部の命令にもとづいて実施された、と判断する以外になさそうであった。この覚書に出逢った結果、私の資料収集の範囲が、まず国立公文書館本館(The National Archives)へと拡大されて行ったことはつけ加えるまでもない。
JCS八七三/三、すなわち統合参謀本部命令書八七三号ノ三は、分室ではなくて公文書館本館に保管されているはずであり、それを調べれば検閲政策の立案・策定過程が、おのずから明らかになるはずだからである。
ほどなく、私は、JCS八七三/三のみならず、これに関連する一連の文書を、公文書館本館から入手することができた。それらを検討するうちに、私はさらに、合衆国検閲局(The U.S. Office of Censorship)という政府機関の存在を知るようになった。そして、合衆国検閲局を成立させた歴史的背景を探るに及んで、私の資料収集の範囲は、さらに合衆国議会図書館(The Library of Congress)、あるいはマッカーサー記念館(The MacArthur Memorial)へと拡大されざるを得なかった。もちろんその間にも、私はメリーランド大学のプランゲ文書に通い続けて、検閲された側の使用収集にもつとめていた。
思えば、昭和五十四年(一九七九)十月二十四日は、私の検閲研究にとって、一転機を劃した日だったような気がしてならない。私は、この日、同じ《ボックス》のなかから、ウィロビー覚書のみならず、「SCAPが憲法を起草したことに対する批判」「検閲制度への言及」等々、三十項目の禁止事項を列挙した民間検閲支隊の「検閲指針」をも発見することができたからである。
もとより、そのときも今も、私は米占領軍が日本で実施した検閲のすべてを知り得たなどとは、いささかも思っていない。九ヶ月を費やして調べ得たスートランドの《ボックス》は、僅々十箱に過ぎなかった。
プランゲ文庫にも、時間の制約に妨げられて参看することのできなかった資料があまた眠っている。したがって、私が以下の各章に書き記すことどもは、限りある能力と時間の制約のなかで、私が知り得たことというに過ぎない。
それを叙述の便宜上試みに二部に分かち、第一部では検閲政策の形成過程をたどり、第二部では検閲がいかに実施されたかについて、事実を紹介し、若干の所見を述べてみたいというのが、私の大体の計画である。それが、日本人の心にどのような影響を及ぼしているかについては、今後折に触れて明らかにして行きたい。そのためには、しかし、まず時計の針を、第二次大戦が最高潮に達した昭和十八年(一九四三)六月初頭まで、戻してみなければならない。
-
あとがき
これは、昭和五十四年(一九七九)十月から昭和五十五年(一九八〇)六月までの九ヶ月間、私がウィルソン研究所で行った検閲研究の集大成ともいうべき仕事である。
当時私は、国際交流基金の派遣研究員として、米国ワシントン市にあるこの研究所に赴き、日夜米占領軍が日本で実施した検閲に関わる文書の検索と通読に没頭していた。僅々九ヶ月とはいえ、この時の滞米生活から生まれた成果は少なくなく、すでに『一九四六憲法──その拘束』と、『落葉の掃き寄せ』(いずれも文藝春秋刊・原稿本は合本)の二冊の本に結実しているが、なんといっても主眼となるべきものは、検閲それ自体の実態を明らかにする研究でなければならない。私は、帰国後間もなくそのまとめに着手し、昭和五十六年(一九八一)の夏休みから執筆に取りかかった。
本書の第一部を構成しているその原稿が、「諸君!」に掲載されたのは、昭和五十七年(一九八二)二月であった。つづいて私は、同年十二月から昭和六十一年(一九八六)二月にかけて、五回に分けて本書の第二部に収められている部分を書き、同じ「諸君!」に断続的に発表した。
それを、実にそれから三年有半を経過した今日、あらためて一本にまとめて世に問うことにしたのは、著者である私が、ひたすら刊行の好機を待っていたためにほかならない。敢えていえばこの本は、この世の中に類書というものの存在しない本である。日本はもとよりアメリカにも、米占領軍が日本で実施した秘匿された検閲の全貌を、一次史料によって跡付けようと試みた研究は、知見の及ぶ限り今日まで一つも発表されていないからである。
正確にいえば、昭和五十七年(一九八二)にニューヨークのプレーガー社から刊行されたJ・L・カリー、ジョーン・R・ダッシン編の Press Control Around the World の第十章に、私自身の執筆した The Censorship Operation in Occupied Japan という論文が唯一の例外ともいうべきものだが、紙幅の制約のためにこの本の詳細さとは比べるべくもない。ダッシン女子は前掲書の序文で拙論に言及して、「合衆国内では事実上全く知られていない検閲システムについての実証的研究」と評しているけれども、私はむしろこの本を、日本の読者のみならずアメリカの知的読者にも読んでもらいたいものだと考えている。米占領軍が戦後日本で実施した隠微な検閲の苛烈さは、所謂《言論の自由》について深刻に反省する材料を、少なからず彼らに提供するに違いないからである。
日本の読者に対して私が望みたいことは、次の一事を措いてほかにない。即ち人が言葉によって考えるほかない以上、人は自らの思惟を拘束し、条件付けている言語空間の真の性質を知ることなしには、到底自由にものを考えることができない、という、至極簡明な原則がそれである。
この研究を可能にしてくれた国際交流基金とウィルソン研究所には、あらためて謝意を表したい。「諸君!」連載当時は堤堯編集長(当時)と担当の斉藤禎氏のお世話になり、出版に当たっては高橋一清氏の緻密な仕事振りに扶けられた。特に記して心から感謝したいと思う。
平成元年七月四日
鎌倉西御門の寓居にて
江藤 淳
-
文庫版へのあとがき
思いがけず歌人の岡井隆氏から長文のお便りをいただいたのは、今年も早春の頃のことであった。
それによると岡井氏は、斎藤茂吉の戦後の沈黙と作風の変化について、かねがね疑問を抱いておられたという。そして、この問題について研究をつづけられるうちに、私の『閉ざされた言語空間──占領軍の検閲と戦後日本』を一読され、ある示唆を得られたといってこの懇篤なお手紙を下さったのである。そこにはまた、
《貴書は、今、容易に手に入りませんので、図書館で借りました。因みに、ぜひ、早く文庫本化していただきたいと思ひます。わたし一個の便宜はどうであれ、この本は、今の日本人が、必ず読んで置くべき重要な文章と思ひます。多くの人が読むことができるやうに御高配下さい》
というような、身に余る言葉も書き記されていた。
これを読んだ私が、少なからず感激したことはいうまでもない。それと同時に、私は、この本が「容易に手に入り」にくくなっているという現状を知り、即刻それに対処しなければならないという必要を感じた。この本が此度文春文庫に入ることになったのは、このような事情によるものである。そのきっかけをつくって下さった岡井隆氏と、文藝春秋出版局の適切な配慮に対して、この機会に深く謝意を表したいと思う。
文庫に収めるに当たって、テクストの改変は一切行わなかった。米占領軍の検閲に端を発する日本のジャーナリズムの隠微な自己検閲システムは、不思議なことに平成改元以来再び勢いを得はじめ、次第にまた猛威を振るいつつあるように見える。
このように、《閉ざされた言語空間》が日本に存在しつづける限り、このささやかな研究も将来にわたって存在意義を主張し得るに違いない。
なお、文庫版の編集については、文藝春秋出版局の寺田英(示偏に見)氏のお世話になった。特に記してその労に感謝したい。
平成五年九月二十五日
鎌倉西御門の寓居にて
江藤 淳
還る