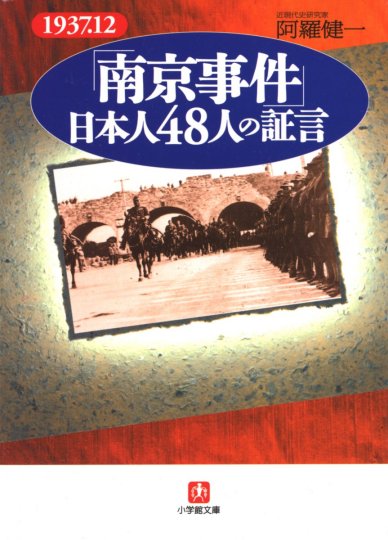一健羅阿
ちいんけらあ
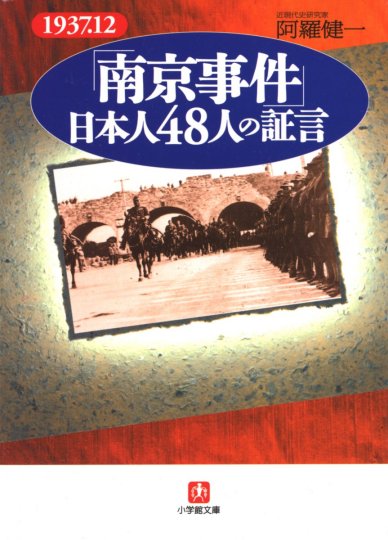
「南京事件」日本人四十八人の証言
平成十四年一月一日 小学館文庫 税別六百円
ISBN4-09-402546-4 C0193
一九三七年十二月、南京で何が起きたのか? 三十万人あるいは数千人といわれる「南京虐殺」の現場は、一体どうなっていたのか?
過去、「南京事件」の証拠、証言とされたものには多くの虚偽が含まれ、大新聞にさえ虚報が載り、真相を一層わかりにくいものにしてきた。本書は、当時南京にいた軍人・記者・写真家等、日本人生存者に直接インタビューした証言集である。
今は亡き人人も多数含む貴重な証言集から浮かび上がってくる「歴史的事件」の真相とは・・・? 昭和六二年刊行時、各界に衝撃を与えた「第一級資料」を復刊。
推薦の言葉
ジャーナリスト 櫻井よしこ
本書は、一九三七年当時の南京にいた軍人、ジャーナリスト、外交官など関係者の体験談を集めた第一級の資料である。いわゆる「南京事件」は、その呼び方すら今だ定まらないほど議論の分かれる問題だが、まずは、そのとき現地にいた人々の話を実際に聞くのが筋である。従って、本書をまとめた阿羅健一氏の手法は、ジャーナリズムという観点からみて、極めて基本に誠実なアプローチだといえる。
一体、日本人は南京で何をしたのか、しなかったのか、そして何を見たのか。虐殺と言われるようなことは本当にあったのか。
それらの結論は、本書を読めば自ずと見えてくる。
ここに、もう一つの資料がある。北村稔氏の『「南京事件」の探求』(文春新書)である。この本は、東京裁判で「南京事件」が断罪された際に提出された様々な資料をひとつひとつ見直し、冷静に検証したものだ。その中にこんな話がある。
当時、南京で中国人の遺体処理にあたったのは、現地の紅卍字会という組織と、崇善堂という慈善団体だったとされている。紅卍字会は四万三千余の遺体を埋めたといい、崇善堂は十一万余を埋めたという。それらの合計が、日本兵による何十万人という虐殺の数の大きな根拠となった。しかし、崇善堂についてはその実在性が疑われた。
その疑いに対して中国側が出した証拠は、崇善堂は車を一台所有しており、彼らがその車の部品の補給を要請したという書類だけだった。その資料から浮かびあがるのは、崇善堂という組織がたった一台の車しか持たずに、一九三八年四月のひと月間というごく短期間で十万余もの数の死体を運び、全て埋葬したという、到底信じ難い事実である。
崇善堂の主張の信憑性は、中国側が提示した証拠によって逆に疑わしいものになったという。
一方、本書にも崇善堂は登場する。当時、上海派遣軍参謀で、かつ南京特務機関長だった大西一大尉は、阿羅氏の質問に対し、紅卍字会については、知っている、遺体の埋葬をよくやっていた、と述べ、崇善堂についてはこう述べている。
「当時、全然名前を聞いたことはなかったし、知らなかった。それが、戦後、東京裁判ですごい活躍をしたと言っている。当時は全然知らない」
紅卍字会を遙かに凌ぐ埋葬活動をしたという組織を、全く知らないというのである。
上海派遣軍の大西氏は一九三七年十二月十三日に南京に入り、三八年二月からは特務機関長として一年間、南京にとどまった。南京特務機関長は中国市民への日本側窓口にあたる。大西氏は南京滞在の時期からも、その職責面からも、南京事件と南京市民の実態を最もよく知り得る立場にあった。その大西氏が崇善堂について、全く知らないというのだ。
もちろん、大西氏は崇善堂を貶めようとしている訳ではない。自分が当時実際に見たこと、知り得たことを淡々と述べているに過ぎない。しかし、こうした当事者の客観的な証言が、学者が調査した結果と見事に一致する。
真実とは、こうしたところにあるのではないだろうか。
過去、東京裁判、また朝日新聞や本多勝一氏に代表される「南京大虐殺」キャンペーンなどを経て、「南京イコール大虐殺」のイメージが定着し、我々はとにかく悪いことをした、残虐なことをしたのだという自縛意識に陥ってしまった。
しかし、私たちの親や祖父たちは、本当にそんな残虐なことをしたのだろうか。何十万もの人々を虫けらのように殺すような人たちだったのだろうか。私たちは、自分たちを信ずるに足らないような民族なのだろうか。
歴史は、人間のつながり、そして家族のつながりでもある。家族としての信頼感や民族としての愛情を全面的に否定するのでなく、私たちは歴史を冷静に正しく見つめ直すべきである。
もちろん、間違いはあっただろう。無謀な戦争に対する責任も、犯した過ちを詫びる心も大切である。しかし、戦後になって作られた情報によって、観念論のみで歴史を捉え過ぎてはいないか。日本はとにかく悪いことをしたのだと教科書で教えられ、ただひたすらそう思いこんではいないか。
反省と同時に、自分の頭で考え、実際に何があったのか、物事の真実を見極めることを忘れてはならない。また、過去に国のために戦い亡くなった人々、戦犯として裁かれた人々の犠牲に対しても、彼らの犠牲に、日本人であればこそ、思いを致し、悼み、感謝する心を忘れてはならない。
歴史には、「資料から見る歴史」、「報道から見る歴史」など様々な側面があるが、現代日本で最も省みられないものが、当事者による「語り継ぎの歴史」である。
ヨーロッパでもアジアでも、また核家族化が激しいアメリカでさえ、家族や先祖の物語がきちんと語り継がれている。しかし、日本はそれがほとんどなくなってしまった希有な国だ。 自分たちの前の世代、そのまたさらに前の世代が一体どんな暮らしをしていたのか、どんなことを思い、考えていたのかの記憶が断絶されてしまっている。さらにその傾向は年々強くなっている。多くの日本人が、教科書が教える表面的な歴史しか知らず、歴史が自分の体の一部であるという自覚がないのは、そのためだろう。
本書にはまさに、その「歴史の語り継ぎ」を補う力がある。父親や母親、また祖父母や曽祖父母に代わって歴史を語り継ぐ重要な記録である。
既に半世紀以上たって、残念ながら戦争を体験した人々の多くが亡くなっている。阿羅氏は十数年前、本書のために多くの方々を訪ねて話を聞いているが、それからさらに時が過ぎた現在、生存されている方はほんのわずかであるという。
二十一世紀に入って、世界ではテロ行為や戦争が勃発し、私たちは改めて国とは何か、民族とは何か、宗教とは何かという課題を突きつけられることになった。
折しも国内では、教科書問題や靖国神社問題など歴史認識の見直しが図られるような出来事が続いた。私たちの国、そして国際社会を築いていく基本的な価値観をどこに据えるべきか、またその価値観をどう守るべきかという岐路に立たされているのだ。
本書を読んで、物事の真実を自分の頭で判断してみてほしい。世界が揺れている時だからこそ、自分たちの国や歴史を冷静に見直すことが求められているのである。
文庫化にあたって
昭和十二年七月七日、北京郊外の蘆溝橋近辺で夜間演習を行っていた日本軍に突然弾が飛んできた。中国軍によるものだと考えた日本軍はただちに中国軍と話し合いを行った。
話し合いが行われたけれど、その一方で小競り合いは続き、そうしているうち、争いは次第に大きくなり、二十七日には、三個師団が北京方面に派遣されることになった。
そのころの中国で、最も日本人がいたのは上海である。北京の争いが続くうち、その上海が騒がしくなってきた。上海には日本の工場があり、それら工場と日本人を海軍陸戦隊が守っていた。日がたつにつれ、上海が険悪になってきた。
八月九日、海軍陸戦隊の大山勇夫中尉が射殺された。十三日には、海軍陸戦隊と中国軍が衝突した。中国の兵力は海軍陸戦隊の何倍もあり、在留日本人の生命が危険になってくる。すでに七月二十九日、北京郊外の通州で、二百二十三人の在留邦人が虐殺されるという、いわゆる通州事件が起こっていた。
そのため、上海派遣軍が編成されて上海に向かうことになった。司令官には、中国通として知られていた松井石根大将が親補された。
中国軍は、数年もかけて陣地を作っており、ドイツ式の装備をし、ドイツ軍から訓練を受けた精強な部隊が待ち受けていた。上海派遣軍は八月二十三日から上陸を始めたが、激しい戦いとなった。攻めるのは日本軍だが、一月たっても、二月たっても、上海を制圧することはできなかった。日ごとに日本軍の戦死者が増えていった。
中国軍の背後を突くため、十一月五日、新しく編成された第十軍が杭州湾に上陸した。背後から攻められた中国軍は崩れ、潰走を始めた。
上陸したての第十軍は、この際、潰走する敵を追って首都南京まで攻めのぼり、そこで和平を考えるべきだという意見を持っていた。それを意見具申するとともに、潰走する敵を追撃しはじめた。やがて、上海を制圧した上海派遣軍からも同様な意見が出された。
十二月一日、南京攻略の命令が参謀本部からくだった。上海派遣軍と第十軍を統一指揮するため中支那方面軍が設けられ、松井大将が司令官に任命された。南京を目指す日本軍は七、八万人に達した。
当初、南京攻略は一月半ばと予想されていたけれど、日本軍の追撃は速く、十二月十日には鯖江の第三十六連隊が光華門に突入、十二月十二日の昼には大分の第四十七連帯がはしごをかけて城壁にのぼりはじめた。
この日の夜、中国軍には撤退命令が出された。
しかし、ほとんどが正面から突破することを命ぜられたため、多くの将兵は軍服を脱ぎ捨て、城内にある難民区(安全区)に逃げ込んだ。
十二月十三日、城内に進んだ日本軍は中国軍を掃討していった。掃討戦は十六日まで続き、十七日には松井大将を先頭として入城式が行われ、翌日は慰霊祭が行われた。
慰霊祭が終わると、第十軍は杭州湾に向かい、南京には上海派遣軍が残った。松井大将も十二月二十二日には上海に戻った。以後、上海派遣軍の中の第十六師団が一月下旬まで南京を警備する。
上海の戦いから南京攻略戦が終わるまでの犠牲者については、日本軍の最高司令官であった松井大将の日記に、日本軍の戦病死者の総数は二万四千に達したとあり、一方、国民党軍軍政部長である何応欽上将の軍事報告には、この間の中国軍の戦死者は三万三千とある。
日本軍の戦死者のほとんどは上海戦によるもので、予想もしない膨大な数字となった。このときから八年間、日本軍は大陸で戦うことになるけれど、劈頭に最大の犠牲者を出すこととなった。
昭和十二年十二月、南京が陥落したとき、そこで何が起こったかのか。
まれにみる残虐な事件がひき起こされたと日本人が知ったのは、それから九年もして、東京裁判が開かれたときであった。
日本軍が南京に入った十二月十三日から一月下旬まで、暴行、略奪、強姦、放火が南京で繰り返されたと東京裁判で判決された。虐殺数は十万人とも二十万人とも言われた。それらを止めるために適切な手段を講じなかったとして最高司令官の松井石根大将が絞首刑になった。また、その当時外務大臣だった広田弘毅も同じ責任を問われ、ほかの理由とあわせて絞首刑となった。
しかし、そう知らされたとき、日本は占領下に置かれていて、さらにだれもが食べることに精一杯という時であった。
何十万人という大虐殺が本当におこったのか。あるいは、どの戦場にもあるような光景があっただけなのか、本当はどうだったのか。そのとき南京にいた同胞にたずねられるものなら、ぜひともたずねたい、そこに本当の答えがある。日本人ならそう思い至るのではなかろうか。
そのとき、どのような日本人が南京にいたかといえば、いうまでもなく日本軍である。日本軍といっても、南京のあちらこちらを見て歩き、南京の様子を知っていたのは、兵隊や下士官ではなく、上級将校であろう。
軍隊だけが南京にいたのではない。南京陥落を報道するため二百人を超す記者たちが南京に入った。占領したあとの行政や治安のため、外交官も入った。彼らも軍の上級将校と同じように、南京全体のことを知っていただろう。
そういった人たちが語る南京なら信用できるのではないか。
そう思ってあたってみると、六十七人が存命中で連絡がとれた。昭和五十九年から六十一年にかけてのことである。
といっても、そのときでも昭和十二年からほぼ半世紀がたっており、その六十七人のうち三十五人から話が聞け、残りの三十二人のうち十一人からは手紙で返事をもらったけれど、残りからは、主に病気という理由で、話を聞くことはできなかった。
さらに、話の聞けた人たちにしても、全員がくまなく南京を見て、南京で何が起こっていたか知っていたわけでなかった。ある場所のことは詳しいけれど、全く行ったことのない場所もある。
しかし、彼らの証言をつなぎあわせれば、ジグソーパズルを組み立てるように、南京の様子が浮かび上がってくる。
その三十五人の中には一度だけ会った人もいれば、十回ほどあった人もいる。ほとんどの方には三回会っている。話を聞くのに二度、まとめた原稿に誤りがないかどうか見てもらうのに一度である。
原稿は正確を期すために発表前に確認してもらったが、発言の「 」の部分はもちろん、地の文も発言のニュアンスをかえるといけないのでチェックしてもらった。
半分ほどの方が間違いはないということであったが、半分の方からは注文があった。このうち半分は字句の修正、一部の聞き誤りなどの訂正であったが、残り半分近くは全面的に書き直しを要望された。そのため指示に従って書き直した。
こうして、一冊の本にまとめられたものが、昭和六十二年に『聞き書 南京事件』として図書出版社から発行された。
それから十五年がたち、絶版となっていた『聞き書 南京事件』が、題名を改め、櫻井よしこ氏による文章もいただき、小学館文庫から発行されることになった。
昭和六十二年に発行されたものは、四六判で三百頁もあった。そのうえ今回は、公表をしばらくひかえてくれるようにと要請のあった南正義氏の証言と、発行の直後に話の聞けた諌山春樹氏、大槻章氏の証言も掲載したい。
しかし、これらすべてを文庫に収めると、だいぶ厚いものになる。そのため、証言者の経歴など、南京と直接関係のない部分は省くことにした。
どうやら文庫として収まることになった。四十八人の証言を収めることができた。
ここに集まったものは、ほとんどが明治生まれの日本人の証言である。われわれ日本人は、われわれの父や祖父たちの述べていることから、昭和十二年十二月に南京で何が起こったのか、何が起こらなかったのか、判断できるであろう。彼らの言葉のなかに、真実があるのではなかろうか。
補 遺
生存者のなかで、約半数の方とは会うことができなかった。ほとんどの人が病気であったからである。それでも、多くの方は手紙なり葉書なりで、南京の様子を知らせてくださった。数年間にわたって、度々手紙のやりとりをした方もいる。会えなかった人と、その人たちの見た南京の様子は、次の通りである。
中支那方面軍参謀・吉川猛少佐
中支那方面軍には六人の参謀がいたが、一番若かった吉川猛氏だけが存命中である。インタビューを申し込んだ時、入退院を繰り返しており、会って話を聞くことはできなかった。しかし、質問に対しては手紙で丁寧に答えて下さった。病気で中断することもあったが、三年ほどの間に八度の手紙のやりとりがあり、その中で次のように答えてくれた。
「一犬虚を吠ゆれば万犬実を何とやら、一度世に宣伝せられし事はこれを反論し世に正しく了解を得ることは難事中の難、第一印象の刻みは人間感情の心の奥に深く食い入るものです。
昭和十二年十二月に中支那方面軍司令部を蘇州に推進した時、庶務参謀の小生と後方主任の二宮参謀が松井大将に呼びつけられ、屍体の始末が悪い、日本軍のだけ整理し敵軍のは放置とは何事ぞと小っぴどく叱られた事があります。松井閣下はそういう御方でした」
第十軍参謀・寺田雅雄中佐
寺田雅雄中佐は第十軍で作戦主任参謀を務め、のちノモンハン事件の関東軍作戦課長として知られている。
インタビューを申し込んだ時、九十歳を超えており、お目にかかることはできなかったが、手紙で何度か答えて下さった。主な内容は次のとおりである。
「上海方面の作戦が膠着してどうにも進展しないため、大本営が第十軍の杭州湾上陸を企画した。第十軍は上海方面のようになっては大変だったので作戦本位であった。第十軍は上陸するとまっしぐらに前進するというやり方をとったため、最初から後方からの補給を受けることは不可能だとわかっていた。
これがため、糧は現地に求めることにした。事実、第十軍の作戦が猛烈果敢であったことからこそ、上海方面の敵軍が一挙に撤退したのです。
軍紀に関していわれているとすれば糧を現地に求めたため、悪いと言われたのではないでしょうか。第十軍の軍紀がそれほど悪かったとは思わない。
当時、南京事件を聞いたことはありません」
寺田氏は福井県小浜市にお住まいで、福井に行った時、思い切って電話をした。会えるものならお会いしたいと思ったからである。しかしやはり病臥中で会うことはできなかった。
第十軍参謀・仙頭俊三大尉
第十軍には国崎支隊(第五師団歩兵第九旅団基幹)がいた。国崎支隊は蕪湖付近で揚子江を渡り浦口付近に進出して南京付近の敵の退路を遮断することになった。第十軍の作戦参謀であった仙頭氏は国崎支隊と行動を共にした。
仙頭俊三氏は、病気のためお目にかかることはできなかったが、手紙での問い合わせには答えて下さり、また、当時のメモも見せてくれた。当時の様子は次のように書いて下さった。
「十二月十二日、浦口(揚子江をはさんで下関の対岸)に進出した時、浦口には味方の十五榴(十五サンチ榴弾砲)が盛んに落下していました。揚子江両岸に浮遊した敵の死体は目撃したところ数百でしょうか、中流にはあまり死体は認めませんでした。下関の岸壁が鮮血に染まっていたのを目撃し、かつ死体は手足をしばられていたようでした。
虐殺ということは当時は全く知りませんでした。軍紀に関して国崎支隊に関する限り悪かったことはありません」
侍従武官・後藤光蔵中佐
後藤光蔵中佐は侍従武官として第十軍の前線まで行き、南京にも入った。最後の近衛師団長としても知られている方である。
体が丈夫でないというのでインタビューはできなかったが、南京に入った時の様子を、「南京は人一人いない街となっており、小生はその一軒に泊まったのですが、何事もありませんでした」と書いて下さった。
昭和六十一年十二月に亡くなっている。
上海憲兵隊・岡村適三大尉
岡村適三氏は上海事変当時から上海にいて、陥落直後の南京に入った。
老人性虚血症ということで話をうかがうことはできなかったが、質問に対し、次のように書いて下さった。
「当時南京事件については聞きませんでした。
上海派遣軍憲兵隊長・横田昌隆中佐、第十軍憲兵隊長・上砂勝七少佐、副隊長・藤野鸞丈大尉などから、日本軍の軍紀について特別聞いたことはありません。
日本軍が威張っているということは聞きました」
憲兵だけに日本軍の軍紀についてよく知っていたと思われるので、是非お目にかかってもっと詳しく聞きたいと思って、何度か手紙のやりとりの後電話で申し込むと、それならと了承して下さった。
約束の日、福岡空港から電話をすると、家族の方が電話に出られて、朝言ったことを昼忘れる有様ですからお話は無理です、とのこと。仕方なく空港から引き揚げた。
同盟通信・堀川武夫記者
第十六師団に従軍した堀川武夫氏は戦後、広島の大学で教鞭をとった。
病気で寝ているということでお目にかかることはできなかったが、「お問い合わせの件格別確かなことは見聞しておりません」とのことである。
朝日新聞・藤本亀記者
藤本亀氏は十三日、光華門から南京城内に入った。
戦後、山陽新聞取締役、山陽放送社長などを務めた人である。体がよくないということで会うことはできなかったが、「従軍の間、特別に何の事件も見たり聞いたりしませんでしたことをお知らせいたします」という返事であった。
東京日々新聞・浅海一男記者
浅海一男氏は十二月十三日、中山門から南京に入城した。
昭和六十年初めインタビューを申し込むと、記憶が不鮮明なのでとお断りになった。その際、「この世紀の大虐殺事実を否定し、軍国主義への合唱、伴奏となるようなことのないよう切望します」という返事であった。
(雲古溜蔵注・浅海一男は、いわゆる「百人斬り」のでっち上げ記事を書いた記者である)
大阪毎日新聞・西野源記者
西野源氏は名古屋総局から従軍し、第九師団と共に光華門方面から南京に入城した。
「お問い合わせの件、残念ながら聞いたことがありません。戦場では幾多の流説があるのが当然のことです」とのことである。
西本願寺・大谷光照法主
大谷光照法主は十一月に上海の皇軍慰問に向かい、やがて南京に行き、十二月十七日の入場式に参列した。翌十八日、城内の飛行場で行われた慰霊祭は法主のもとに行われた。
南京の様子については、
「完全占領の翌日の十四日夕刻、南京に着き、城内に宿営しつつ四日間滞在し、城内にも数回入りましたが、もちろん虐殺を見ておりませんし、噂も聞きませんでした。もうその時は戦闘は全く終息していて、市内は平静で、市民の姿もほとんど見かけず、虐殺の起こるような環境ではありませんでした。日本軍は城内城外に適宜宿営し、のんびり休養をとっていました」
ということである。
従軍作家・石川達三氏
石川達三氏は昭和十年『蒼氓』で第一回芥川賞を受賞、昭和十二年、陥落直後の南京に中央公論社から特派された。十二月二十一日東京を発って、上海、蘇州、南京をまわり、一月下旬に東京に戻った。この時、主に第十六軍の兵士に会い、これをもとに『生きてゐる兵隊』を書き、二月十八日発売の『中央公論』に発表した。ところが『中央公論』は即日、新聞法により発売禁止になり、石川氏は起訴され、九月に禁錮四ヶ月、執行猶予三年の判決がおりた。
戦後になり、『生きてゐる兵隊』は南京事件を扱った小説と言われるようになった。
昭和五十九年十月、インタビューを申し込んだが、会うことはできなかった。理由は後でわかったが、それから三ヶ月後の昭和六十年一月に石川氏は肺炎のため亡くなった。インタビューを申し込んだ時は胃潰瘍が良くなりつつあったが、会えるような状況ではなかったのである。しかし、そのおり、次のような返事をいただいた。
「私が南京に入ったのは入城式から二週間後です。大殺戮の痕跡は一片も見ておりません。
何万の死体の処理はとても二、三週間では終わらないと思います。あの話は私は今も信じてはおりません」
連絡を取っている途中に亡くなったり、病気のため返事をいただけなかった人たちは、次の人たちである。
-
上海派遣軍参謀・松田千秋大佐
上海派遣軍報道班長・米花宇太吉少佐
上海派遣軍写真班長・一色達夫氏
南京特務機関・小島友宇氏
南京特務機関・馬淵誠剛氏
第十軍参謀・山崎正男氏
第十軍参謀・清水武男大尉
中部防衛軍参謀・宮本清一中佐
南京領事館・福田篤泰領事官補
外務省情報部・後藤光太郎氏
内務省内務事務官・池野清躬氏
同盟通信・前田雄二氏
同盟通信・不動健治写真部長
同盟通信・加藤松記者
同盟通信・祓川親茂カメラマン
同盟通信・高崎修カメラマン
同盟通信・菊地久太郎無電技師
朝日新聞・田端雅カメラマン
運輸通信朝刊部野戦高等郵便長・遠藤毅氏
あとがき
南京を歩きまわってあちこち見ていた日本人の証言から、どんなことが浮かびあがってくるであろう。
南京でいわゆる「三十万人の大虐殺」を見たという人は、四十八人の中にひとりもいない。それがひとつ。それから九年たち、南京での暴虐が東京裁判で言われたとき、ほとんどの人にとっては、それがまったくの寝耳に水だった。
つぎに、四十八人の証言から、市民や婦女子に対する虐殺などなかったことがわかる。とくに婦女子に対する暴虐は誰も見ていないし、聞いてもいない。
南京にはいたるところに死体があり、道路が血でおおわれていた、としばしば語られるけれど、そのような南京は、四十八人の証言の中にまったくない。東京裁判で語られたような悲惨なことは架空の出来事のようだ。
一般市民に対してはそうであるけれど、しかし軍隊に対してはやや違うようだ。
中国兵を処断している場面を何人かが見ている。中国兵を揚子江まで連れていって刺殺しているし、城内でも刺殺している。南京に向かう途中でも、そのような場面を見ている人がいる。揚子江岸にはのちのちまで処断された死体がたくさんあった。
これらから推察すると、南京事件と言われているものは、中国兵に対する処断だったのであろう。
といって、だからそれが虐殺として責められるべきことかといえば、必ずしもそうではない。大騒ぎすることではない、それが戦争だ、戦場だ、と大多数の証言者は見なしている。
大多数ということは、そうでない人もいた。なかには、処断の場面を見て残酷だと感じ、行き過ぎだと見なす人がいた。しかし、そういう人でも、とくに話題にすることはなかったから、特別なこととは見なしていなかった。
四十八人の証言者のなかには軍人がいた。彼らの証言をみると、中国兵をとくに虐待しようとしていた人はいなかった。中島今朝吾師団長、長勇参謀のように、中国兵にきびしく当たるような言動の人もいたけれど、軍からそのような命令が出たわけではない。反対に、最高司令官である松井石根大将は中国兵には人道的に対応するように命じている。
中国軍は、証言にもあるように、降伏を拒否していた。日本軍と最後まで戦うつもりだったし、追い詰められても、降伏は認められていなかったから、捕虜になるという考えや気持ちもなかった。最後の段階になって中国軍は軍服を脱ぎ、市民のなかに紛れこんだ。中国軍には戦時国際法が念頭になかった。
一方、中国兵を処断した日本兵は、そのことを隠すこともしないし、なかには、ジャーナリストらにわざわざ処断の場面を見せようとするものもいた。中国兵の処断は戦闘の続きだ、と日本兵は見なしていたからである。後に虐殺だと言われるとは思いもしなかっただろう。
それでは、中国兵の処断は戦時国際法からどのようにみなされるのだろうか。
現在の研究からみると、意見は分かれる。
ひとつは、司令官が逃亡し、中国兵が軍服を脱いで武器を隠し持ち市民に紛れこんだ段階で捕虜として遇されることはなくなった。日本が非難されるいわれはない、とみなす意見である。
その反対に、最後まで中国兵を人道的に遇すべきだし、処断は戦時国際法違反だ、という見方がある。
また、処断するにしても、軍律会議などを経るべきだった、そうすれば非難されることはなかっただろうという見方もある。
ともあれ、南京事件といわれるものの実態は、中国兵の処断である。戦場であったから、悲惨な場面はいくらもあった。逃げようとする中国兵のなかには城壁から落ちて死んだものもいた。しかし、それは戦場ならどこにでもある光景である。四十八人の証言はそういったことを教えてくれる。
二〇〇一年十一月二十一日
阿羅 健一
還る