赤ちゃんが生まれてから、周りの環境を理解していくのに聴覚は重要な感覚の一つです。視覚や触覚の発達より早くからスイッチが入り、乏しい情報から生きるための力を磨いています。お母さんのおなかの中から聞いていると言われています。胎教に良い音楽があるのはうなずけます。赤ちゃんが泣いていても泣きやんでしまうCMソング(中古ピアノや昆布会社)があることも不思議なことです。
子どもの聴覚の発達は、言葉の発達につながり、人とのコミュニケーションにも関係していきます。聴覚に障がいがあると、ことばが育たず、コミュニケーションがうまくいかないことで社会性も育ちません。聴覚障がいのある場合、早い時期にきちんと音を聞かせてあげる必要があります。
今は新生児スクリ−ニング検査によって早期に発見され、補聴器や人工内耳で周りの音やことばを聞かせるようになっています。私たちが聴取できる音は、20Hz〜20000Hzまで聞いています。音の大きさとしては成人が聞こえ始める音を0dBとして、0〜120dBまでの音を聞いています。30〜40dBは小声の会話、60dB前後は普通の会話、70〜80dBは大声の会話、90dBは叫び声です。100dBはガード下、110dBは車の警笛で120dBはジェット機の騒音です。聾学校の子どもは聴力障がいが80dB以上がほとんどですから、補聴器や人工内耳なしでは、聴覚の十分な発達ができません。また、補聴器や人工内耳をつけただけで、特別な配慮がないとことばが育ちません。
ことばの問題は、本人だけでなく、周りの理解と正しい接し方をしないとうまくいきません。それは一般の子どもにも言えます。子どもの聞こえや心と体の発達に従って、言葉や発音もかわっていきます。子どもの発達を考えて、遊びや接し方を考えましょう。
耳の後方約30cmの距離で、お子さんには見えないようにコピー用紙を”クシャクシャ”と揉むと30〜40dBの音圧になります。この音に気付けば、少なくとも40dB以上の難聴はないということになり、とりあえず問題はなさそうだと判断できます。
また、鈴を耳の後方1mの距離で軽く”チリンチリン”と振ると60dBの音圧になり、4kHz程度の高い周波数の音を含んでいます。コピー用紙の紙もみ音には気付かなくても鈴の音に気付いた場合、高い音は中等度以下の難聴ということになります。
家庭でできる聴力検査
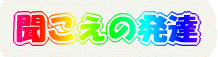
| 年(月)齢 | 音刺激に対する反応 | 聴力検査法 |
| 0から3ヶ月 | 前半 まばたき、痙攣ようの体の運動、呼吸の変化など反射性の反応{モロー反射、眼瞼反射) 後半 適応的行動が芽生える |
AABR(自動聴性脳幹反応) OAE(耳音響反射法) |
| 3〜6ヶ月 | 目を動かす、泣く、笑う、びっくりする、動作をやめるなどの 適応的行動 音に顔をむける。目覚まし時計のコチコチ音に振り向く。 |
BOA(聴性行動反応) |
| 6〜12ヶ月 | 音源を捜し求める反応(詮索反応)が起こり、自分の行動が興味ある結果と結び付くと、同じ反応を繰り返すようになる。 前半 音に興味を持ち、振り向いたり、声を出したりする。 後半 動物の鳴き声をまねると喜ぶ。音楽や言葉に応じて、行動する。 |
COR(条件詮索反射聴力検査 |
| 1〜2歳 | 新しい刺激に積極的な興味、好奇心を示す。反応の潜伏時間が短くなる。注意力の集中でできる時間の範囲で音刺激に対する行動の条件付けが可能になる。 物音を不思議がり、耳を傾けたり、合図して教える。 簡単な指示がわかる。理解できる言葉や言える言葉が ふえる。 |
COR(条件詮索反射聴力検査) |
| 2〜4歳 | 条件づけにより、短時間に音刺激に対する一定の行動様式が学習できる。 | 遊戯聴力検査 |