01A
(201A)
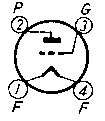
If 0.25A
Eb
Ec1
Ec2
Ⅰb
Ⅰc2
rp
gm
μ
RL
Po
201→201A(茄子型)→01A(ST)と進化。
201Aが最も多い。
201Aのトリタンフィラメントは点火すると明るい。
2A3
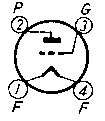
If 2.5A
Eb 250V
Ec1 -45V
Ⅰb 60mA
rp 800Ω
gm 5250
μ 4.2
RL 2500Ω
Po 3.5W
2A3が使って有るだけで高級品。
A級シングルで電磁型SPを使うと、B電圧がふらついて苦戦した記憶有り。
昭和28年のマツダの卸価格617円(散髪180円の時代で)、
当時から高価だった。
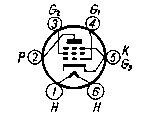
If 1.75A
Eb 250V
Ec1 (410Ω)
Ec2 250V
Ⅰb 34mA~35mA
Ⅰc2 6.3mA~9.7mA
rp
gm
μ
RL 7000Ω
Po 3.1W
戦前の高級ラジオに使われた。
戦後はまず見かけなかった。
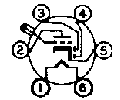
If 0.8A
Eb
Ec1
Ec2
Ⅰb
Ⅰc2
rp
gm
μ
RL
Po
日本での使用例は非常に少ないと思われる。
2B7か57を使うことが多かったようだ。
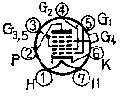
If 0.8A
Eb
Ec1
Ec2
Ⅰb
Ⅰc2
rp
gm
μ
RL
Po
短波帯は引き込み現象が強いと言うことで、発振管が別に使われることもある。
戦後は生産されず、替わりに3W-C5が使われた。
(配線が変更されている)
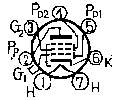
If 0.8A
Eb
Ec1
Ec2
Ⅰb
Ⅰc2
rp
gm
μ
RL
Po
この時代は5極管が使われた。
If
If
If
3Y-P1
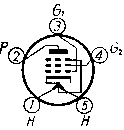
If 0.9A
Eb 180V
Ec1 -10V
Ec2 180v
Ⅰb 15~16mA
Ⅰc2 2.5~4.5mA
rp 130KΩ
gm 1750
RL 12KΩ
Po 1W
47Bに比べヒーター電流が多い、立ち上がりが遅い(ケミコンに負担)など欠点もある。
なお3YーP1のKはヒーターの中点に接続されている。
これはマツダの特許だったので、他社では1か5に接続したものが一時期売られていた。
これを持っていれば大珍品。47BKなどと言うのも有る。
経緯は無線と実験 昭和28年4月号参照。

5M-K9
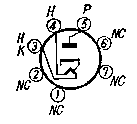
If 0.6A
5V巻線のトランスを利用するため、
他のmT管に比べ、少し遅れて発売。
80HKのmT。
日本独自の球なのに、最近何故か外国ブランドの物を見かける、逆輸入らしい。
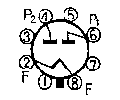
If 2A
高電圧を作るときに使います。
尖頭陽極耐逆電圧 2800V(最大整流電流150mA)
最大整流電流250mA(尖頭陽極耐逆電圧2100Vの時)
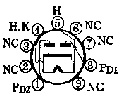
If 1.2A
mT管としては大電流が取出せる。
6CA4の5V版、ただしピン配列は異なる。
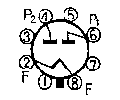
If 3A
その後TV用に改良され5U4-GBが発売された。
5Y3GT
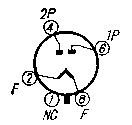
If 2A
規格が少し改良されているようだ。
最もアメリカにはチューブ型の80が有るようだが。
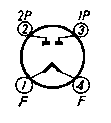
If 3A
2A3 5Z3は立派(高価)さの証明だった?。
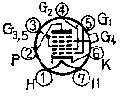
If 0.3A
引き込み現象が強く、特に短波帯では76(発振管)等と組み合わせて使った。
この為昭和23年に6W-C5が作られてから、ほとんど使われなくなった。
6AR5
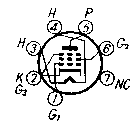
If 0.4A
Eb
Ec1
Ec2
Ⅰb
Ⅰc2
rp
gm
μ
RL
Po
日本の家庭用ラジオではSTでは42だが、
何故かmTではこちらが良く使われた。
アメリカでは6AQ5の方が多いらしい。
おかげで、現在 高価だ。
放熱注意。
6AT6
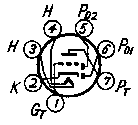
If 0.3A
Eb
Ec1
Ec2
Ⅰb
Ⅰc2
rp
gm
μ
RL
Po
6AQ5
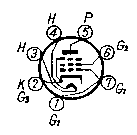
If 0.45A
Eb
Ec1
Ec2
Ⅰb
Ⅰc2
rp
gm
μ
RL
Po
放熱注意。
接続図は5極管と同じに書かれているがビーム管。
中古品を購入する時 TV用の5AQ5が紛れ込んでいる可能性があるので注意。
(5AQ5はレスTV用のヒーター4.7V 600mA)
6AU6
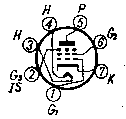
If 0.3A
Eb
Ec1
Ec2
Ⅰb
Ⅰc2
rp
gm
μ
RL
Po
カット オフの関係で、不具合になる事あり。
5球スーパーのIFに使えると思っている人が居るがこれは間違い。
マジック アイが閉じるような電界強度のところでは駄目。
高周波増幅(シャープカットオフ)、勿論低周波にも使える。
FM受信機のIFには良く使われている。
6AV6
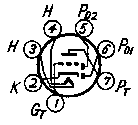
If 0.3A
3極管のμは100
6BA6
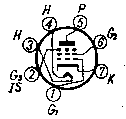
If 0.3A
発売時「gMが高いので発振する」と騒がれた。
5球スーパーで6BD6の代わりに使っても、
カソードバイアスで使う限り、充分代用可。
でも正規の100Ωにすると発振するかもしれない。
バリミュー管なので、検波にはどうも?、と言う話も有るが、グリット検波には充分使える。
6BD6
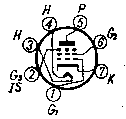
If 0.3A
6BA6に比べ使用例は意外に少ない。
6BE6
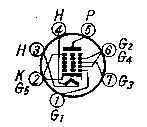
If 0.3A
ほとんどの5球スーパーに使われている。
6BM8
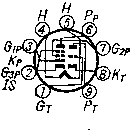
If 0.78A
Eb
Ec1
Ec2
Ⅰb
Ⅰc2
rp
gm
μ
RL
Po
低周波増幅用3極管と電力増幅5極管。
TV用に開発されたもの。
6BQ5
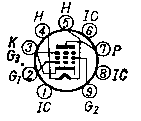
If 0.76A
Eb
Ec1
Ec2
Ⅰb
Ⅰc2
rp
gm
μ
RL
Po
7189や7189Aはこの改良型。
東芝はこの対抗に6R-P15を出した。
6C6

If 0.3A
Eb
Ec1
Ec2
Ⅰb
Ⅰc2
rp
gm
μ
RL
Po
日本では昭和11年に発売。
日本製の6C6はトップ グリットへのリード線は直線。
なお日本製は昭和20年代中頃から身長が低くなっている。
シールドケースとの相性に注意、これは6D6も同じ。
ほぼ同じ球として77がある。
6D6


If 0.3A
Eb
Ec1
Ec2
Ⅰb
Ⅰc2
rp
gm
μ
RL
Po
終戦後は作るのが難しいと言うので、標準真空管候補から外された事もある。
トップグリットへのリード線が螺旋状になっている。
これはマークが消えた時の目印でしょう。
ほぼ同じ球として78がある、これは何故か旧軍用に多い。
6E5
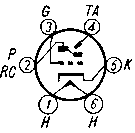
If 0.3A
新ラジオ資料館のマジックアイを参照ください。
プレート電圧により、閉じるG電圧が変わります。
シャープカットオフ特性の3極管が封入されているのでP電圧250Vの時-7Vで閉じます。
親戚に6Z-E1や2E5などが有り、また古いものはダルマ型もあります。
一般に閉じる方が下側です、誤解すると不味いので念のため。
6E5D
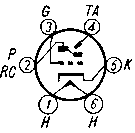
If 0.3A
中々奇麗です。
但し、アマチュアーしか使わなかったので、今となっては珍品。
学生時代に使った時の事が忘れられない。
If
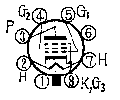
If 0.7A
Eb 250V
Ec1 (410Ω)
Ec2 250V
Ⅰb 34mA(零信号)~35mA(最大)
Ⅰc2 6.3mA(零信号)~9.7mA
rp
gm
μ
RL 7000Ω
Po 3.1W
歴史的には42→6F6(メタル)→6F6G→6F6-GT。
日本製では42とGTのみと思われる。
不思議だが、出力管はGTでは6V6-GTの方が良く使われた。
6F7
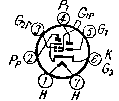
If 0.3A
終戦後もの不足の時代には憧れの球。
ラジオ雑誌にはこの球を使った1球受信機の製作記事が多かった。
軍の放出で、多数出回った。また当時としては安かった。
見かけると懐かしさのあまり、つい大量に買ってしまった。
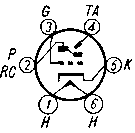
If 0.3A
これはリモートカットオフ特性(-22Vで閉じる)の3極管が使われています。
スーパー受信機には最適なのですが、実際は理論より、すぐ閉じる6E5に人気が行ったようです。
(東京など強電界では短いアンテナでAVC電圧は簡単に-7Vを越します)
6E5と6G5の両方の特性を封じ込めたのが6G-E7(上下に表示)です。
これもほとんど見かけません。
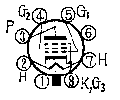
If 0.15A
自動車ラジオ用に作られたらしく、日本製は見たこと無し。
12(6)Z-P1のモデルではないかと思われる。
ヒーター電力を除いて非常によく似ている。
47Bの例に見られるように日本ではカソード材料の点で、同じヒーター電力で作るのは難しかったらしい。
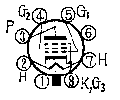
If 0.4A
日本では余り見かけない。
TENで作った可能性あり。
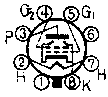
If 0.9A
送信管に改良されたのが807。
本来はメタルの6L6だが日本ではガラス管のみ。
TENなどでは6L6-GTなるものを作った。
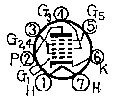
Ef 0.3A
混合管です、別に76などの発振管が必要。
Ut足のものは日本独自か?。
If
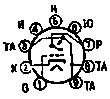
If 0.2A
ただラジオに使われているのは見たことが無い。
ヒーターカソード間の耐圧が160Vあり、TVに使う事を考慮してあるのかも?。
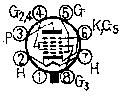
If 0.3A
6SA7(メタル)とはソケットの接続が違うので注意のこと。
これはメタルとGTで異なる珍し例です。
6W-C5のお手本になった球です。
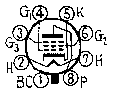
If 0.3A
RF増幅 IF増幅に使われる、バリμ管。
6SJ7と言うシャープカットオフの真空管もあり。
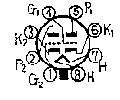
If 0.3A
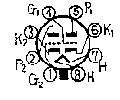
If 0.6A
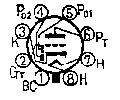
If 0.3A
双2極 高μ(100)3極管。
時代により構造が違う 2種類あり、新しい方は6AV6と同じつくり。
2極幹部がバンザイ型になっている。
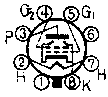
If 0.45A
高級ラジオの出力管。
6X4
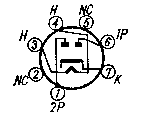
If 0.6A
5M-K9は遅れて発売。
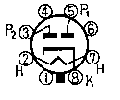
If 0.6A
6W-C5
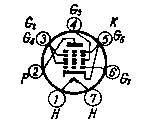

If 0.35A
当時の材料や電源事情により、ヒーター電流を増加して有る。
また当時 この球だけヒーター電圧を7Vくらいにして使えなどと推奨した例もある。
ただ0.3Aで作られた6WC5Aもあり。
昭和23年頃から大量に出回った、それ以前は6A7が使われた。
なお12W-C5のヒーターは12V 0.175Aです。
3W-C5と言う2.5V管もある、これは高1の改造用。
6Z-DH3
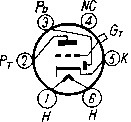
If 0.3A
ダイオード部分は1つにして、他のピン配置は同じにした、此の為トップグリットがついた。
この球を使ったラジオは昭和23年頃までに作られた可能性が高い。
(24年に作られたラジオではまず見かけない)
6Z-DH3A
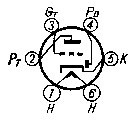
If 0.3A
NECがまず勝手に作ったらしい。
使って見ると便利なので、他社が真似した。
なお6ZDH3Aは電極の作りに2種類ある、2極管部をシールドした物と、6AV6の如くバンザイ型だ、後者が新しい。
改良と言うよりもユーザーから見れば改悪に近い、ハムを拾いやすい。
6Z-E1
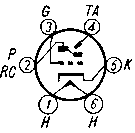
If 0.3A
6G-E7のように上下で、感度が違うわけではありません。
(上下対称に閉じます)
6Z-P1
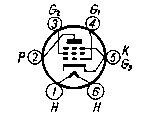

If 0.35A
Eb 180V
Ec1 -10V
Ec2 180v
Ⅰb 15~16mA
Ⅰc2 2.5~4.5mA
rp 130KΩ
gm 1750
RL 12KΩ
Po 1W
日本の家庭用ラジオに多く使われた。
愛着の多い球だ。
昔は沢山有ったが、最近は珍しい。
なお発売時の電力事情で12Z-P1に比べヒーター電力が増加されている。
また後日プレート電圧が180V→250Vに改良され、最大出力が1W→1.5Wに。
製造時期の古い物は当然昔の規格(180V)で使うべきでしょう。
12A
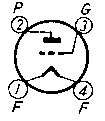
If 0.25A
古いラジオ(昭和初期 112Aの時代)には整流管として使われたものもある。
傍熱型の12AK(0.4A NECが作っていた)もある。
戦後 並四が6.3V管になった時も、6C6 76 12A 12Fで生き残った。
112Aの発売は昭和3年。
12AT6
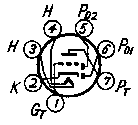
If 0.15A
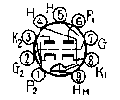
If 0.15A
Ef 6.3v
If 0.3A
ヒーターの接続方法で6.3V 12.6Vどちらでも使える。
どちらかと言うとこれは高周波で使う。
最近はHi Fi ampにも使うようだ。
12AU6
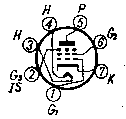
If 0.15A
勿論低周波にも使える。
間違っても、5球スーパーのIFには使わないように。
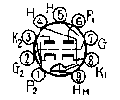
If 0.15A
Ef 6.3v
If 0.3A
ヒーターの接続方法で6.3V 12.6Vどちらでも使える。
どちらかと言うとこれは低周波で使う。
12AV6
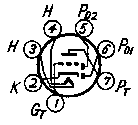
If 0.15A
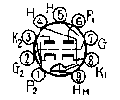
If 0.15A
Ef 6.3v
If 0.3A
ヒーターの接続方法で6.3V 12.6Vどちらでも使える。
どちらかと言うとこれは低周波で使う。
12B
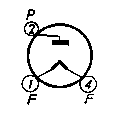
If 0.5A
maxEb 180V
maxIb 30mA
(昭和初期のラッパ付きラジオに多い、その前は電池式)
UXー112A(3極管)→KXー112A(2極管)→112B(KXは省略以下同じ)→12B→12Fと進化。
この球は4本足です。112Bが発売されたのは昭和5年です。
12Fは12年に発売されましたが、その後も12Bは売られていたようです。
(新製品のラジオにはさすがに使われなかった)
(交流入力180V 最大整流電流は30mA)
12BA6
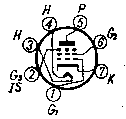
If 0.15A
12BD6
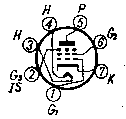
If 0.15A
何故かmTのトランスレスにはあまり使われていない。
12BE6
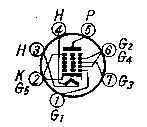
If 0.15A
12F
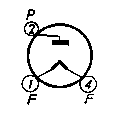

If 0.5A
Ep 300V
Io 40mA
12Bの改良型、昭和12年発売。
最初は4本脚だったが何時しか3本になった。
昭和15年7月号のマツダ通信に戦時規格として、今回3本脚になった云々と記載あり。
愛着有ります、戦後の子供時代 整流管は弱いので貴重でした。
シリコン整流器の無い時代は、B電源は大変な思いでした。
写真左は3本脚 右は4本脚の12F。
12FK
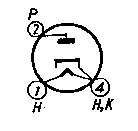
If 0.5A
Ep 300V
Io 40mA
12Fの傍熱型、他の規格は12Fと同じ。
戦後のケミコンの品質不良時代の救世主、松下が早かったと記憶する。
高1で47Bを3Y-P1に交換した場合、傍熱管の立ち上がり時間のため、
無負荷状態が十数秒続くのでケミコンが危ない。
12K
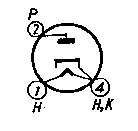
If 0.6A
Ep 350V
Io 60mA
比較的珍しい。
(交流入力350V 最大整流電流は60mA)
12Y-R1
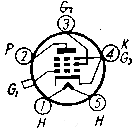
If 0.15A
昭和14年に発売、雑誌には13年末には発表済み。
資材節約の為、5ピンになっている。
高周波増幅(シャープカットオフ)。
発売初期と量産時では球の作りが微妙に違う。
放送局型122 123号受信機に使われた。
12Y-V1
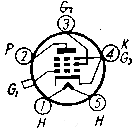
If 0.15A
放送局型123号受信機に使われた。
資材節約の為、5ピンになっている。
高周波増幅(リモート カットオフ)昭和14年に発売、雑誌には13年末には発表済み。
発売初期と量産時では球の作りが微妙に違う。
12Y-V1Aのヒーターは12V 0.175Aです。
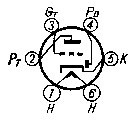
If 0.175A
75との互換性が不要なので、トップグリットを省略した。
同じピン接続にした6V球が6Z-DH3A。
歴史 6ZーDH3(75の代用可)→12Z-DH3A(代用不要)→6Z-DH3A(75代用不可)
12Z-E8
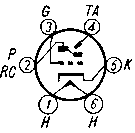
If 0.15A
但しレス用なのでP電圧が低くても動作する工夫有り。
(6E5のターゲット電圧は最低150V)
12Z-P1
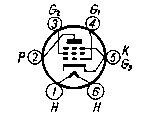
If 0.15A
Eb 180V
Ec1 -10V
Ec2 180v
Ⅰb 15~16mA
Ⅰc2 2.5~4.5mA
rp 130KΩ
gm 1750
RL 12KΩ
Po 1W
でも本当は12Z-P1が先で、6Z-P1はその後(昭和20年前後)に作られた。
アメリカの6G6Gの規格によく似ているので、
6G6Gの寸法で電極をつくり、ヒータ電力を増加させた製品と思われる。
日本製のカソード材料が悪かったので、妥協の産物か?。
放送局型122 123号受信機に使われた。
カソード ヒーター間耐圧最大150V。
12Z-P1Aのヒーターは12V 0.175Aです。
19A3
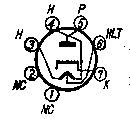
If 0.15A
Ep 127V
Io 60~70mA
Ehk 50?
電圧が低いので、パイロットランプ(3V 0.15mA)が暗いのが寂しい。
24B
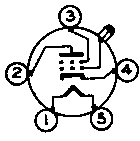

If 1.75A
アメリカでは24Aが有るが少し外形が大きい。
バリミユー管は製造が難しかったらしく高価で、58 57が発売された(昭和8年)後も安いためか、13年頃までは多量に使われた。
尤もバリミュー管を作ろうとしてうまく行かず、シャープカットオフを作るつもりが、グリット巻線が不揃いで、
擬似バリミューになったりした可能性はある?。
24Z-K2
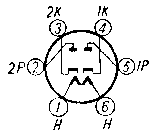
If 0.15A
Ep 125V
Io 30mA
Ehk 300V
平滑用のコンデンサーの容量は大きくしない事。
指定より大きいと、カソードをいためる。
昭和14年に発売、雑誌には13年末には発表済み。
カソード ヒーター間耐圧最大300V。
同じ接続で36Z-K12がある、いわゆるAシリーズと一緒に使われた。
このヒーターは36V 0.175A。
If 0.15A
Ep 235V
Io 70mA
Ehk 330V
26B
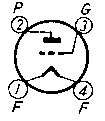
If 1.05A
26(226)の改良型、増幅率が少し大きい。
アメリカ製の26で電気的には代用できるが、外形が多少大きいので注意。
226は昭和3年に発売。
27
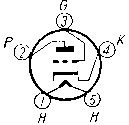
If 1.75A
227は昭和4年に発売。
なお27Bは増幅率が高い。
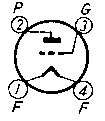
If 0.06A
国防受信機などに利用。
同じ特性で外形の異なる兄弟がある。
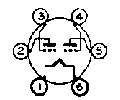
If 0.12A
軍用に使われたので、戦後大量に放出された。
マジックアイのようなストレートタイプのガラス管。
30A5
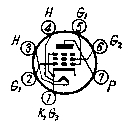
If 0.15A
35C5より、少し遅れて発売。
元々はヨーロッパ系の球、5極管
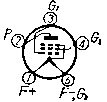
If 0.26A
日本独自の出力管47Bの原型になったと言われている。
両脚にそれぞれ1オームの抵抗を入れれば47Bの代わりに使える。
日本製はST38だがアメリカ製は一回り大きい。
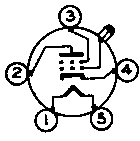
If 1.75A
もっぱら24Bの方が使われた。
35C5
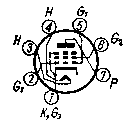
If 0.15A
30A5より発売は早い。
一般的に、この球を使ったラジオは発売時期が古い。
ビーム管(図は5極管表示で代用)
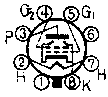
If 0.15A
35W4
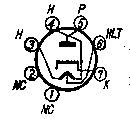
If 0.15A
Ep 235V
Io 60~100mA
Ehk 330V
「ラジオ修理メモ」を参照ください。
最大整流電流はPLへの並列抵抗値で異なる。
5球スーパー用に日本独自規格の25M-K15(25V 0.15A)もある。
これはヒーター端子⑥が出ていない。
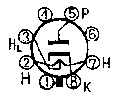
If 0.15A
Ep 235V
Io 60~100mA
Ehk 350V
B37
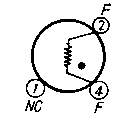
放送局型123号受信機に使われた。
他に放送局型122号受信機に使われたB49(49V用)も有る。
電灯線電圧の変動にも対応出来る。
最近の電力事情では普通の抵抗やコンデンサーで代用しても可。
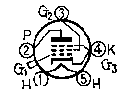
If 0.3A
6Z-P1を5本足にして、トップグリットをつけたような形。
もちろんこちらの方が時代的に古い。
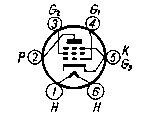
If 0.4A
Eb 250V
Ec1 -16.5
Ec2 250V
Ⅰb 34mA
Ⅰc2 7mA
rp 35K
gm 2300
μ -
RL 7000Ω
Po 3.2W
6K6、6K6GTなど兄弟がある。
日本では戦後あまりなじみが無い、軍用に使われたらしい。
42
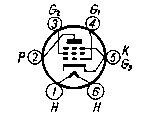
If 0.7A
Eb 250V
Ec1 (410Ω)
Ec2 250V
Ⅰb 34mA(零信号)~35mA(最大)
Ⅰc2 6.3mA(零信号)~9.7mA
rp
gm
μ -
RL 7000Ω
Po 3.1W
日本の高級ラジオの出力管として最も多く使われている。
兄弟に41(mTでは6AR5)が有るが、何故か日本では42が多い。
また他に兄弟が多数(6F6 6F6G 6F6GT)。
日本では昭和9年に発売。
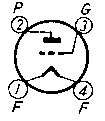
If 1.5A
超45などと言う日本製の球もある(貴重品で有名)。
戦後はマツダが作らなかったので、なじみが無い。
(最近は一般的だが)
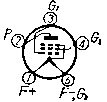
If 1.75A
音が悪いと最初 悪評だったらしい。
他に日本では47Bをはじめ47D 47Gなど47と互換性の無い紛らわしい球がある。
47B
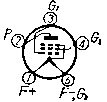
If 0.5A
2.5V管にした出力管。この時ガラスの大きさをST38にしている。
247Bは昭和7年に発売。
戦後マツダが3Y-P1を代わりに作って、生産中止にしたので、
エミ減球が多く、活きている47Bは極端に少ない。
33を使った代用真空管の作り方はラジオ修理メモ15をご覧ください。
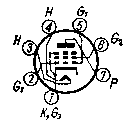
If 015A
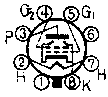
If 015A
56
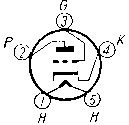
If 1A
なお56にも茄子型がまれにある(普通茄子型は3桁数値だが)。
またメッシュプレートの56もある。
(太平洋戦争当時作られた56Aは0.8A)
日本では昭和8年に発売。
57

If 1A
(太平洋戦争当時作られた57Aは0.8A)
高周波増幅(シャープカットオフ)
勿論低周波にも使える。
日本では昭和8年に発売。
57S
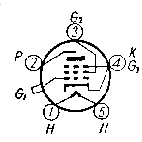
If 1A
少し性能が上がる。
「修理メモ」にも書いたが、中身は57そのもの。
58

If 1A
(太平洋戦争当時作られた58Aは0.8A)
日本では昭和8年に発売。
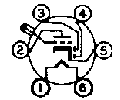
If 0.3A
当然こちらが古い。
6Z-DH3はこの75の代わりに使えるよう、ピン配置が決められた。
76
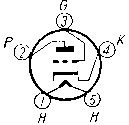

If 0.3A
昭和10年に発売。
80
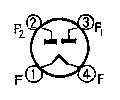
If 2A
大型のラジオや電蓄で使われた。
80は昭和9年に発売。
80BK
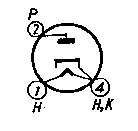
If 0.7A
(最高交流入力 350V 最大整流電流 75mA)
何故かマツダは作らず、80HKを作った。
なお戦前80Bと言うのが有ったが、これは直熱。
(ヒーター1.25A、Bは70mAの半波)
80HK
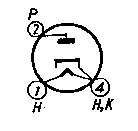
If 0.6A
(最高交流入力 350V 最大整流電流 65mA)
ヒーターがBKの0.7Aにくらべ0.6Aなので、
旧来の0.5A巻線でも無理が少ないのが12Fの補修用としてはメリット。
80BKか80HKのどちらを採用するかは、電流値の制限より、
使われる真空管メーカーによって決まると考えてよい。
保守用にはどちらを使っても実質的に問題は無い。
80K
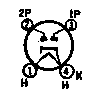
If If 2A
戦後は松下が作ったが、戦前にもあり。
戦前のはヒーターの中点にカソードが接続されていたとの事(藤室さんの「真空管半代記」参照)。
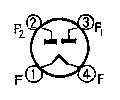
If 3A
整流時の電圧降下が15V一定と少ないので、大電流用に使われる。
TV-7などの真空管試験器に使われているのは、この15V一定と関係あり。
内部が充分温まってから高圧をかけるのが原則。
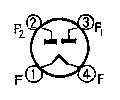
If 2A
175mAで25Vの電圧降下
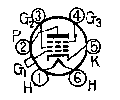
If 1A
電電公社の中継用増幅器に使われたらしく、昔は放出管が大量に入手できた。
ヒーター電圧が3.5Vなのは直列接続で電話局のバッテリーで動作させたらしく、電流が1A。
出力管の504Dも同じ理由らしい。
兄弟にCZ-501Vがあり、これは6.3V(0.55A)管。
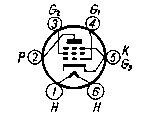
If 1A
電電公社の中継用増幅器に使われたらしく、昔は放出管が大量に入手できた。
GMは3500マイクロモー
ヒーター電圧を工夫して42の代わりに使うと便利だった。
兄弟にCZ-504Vがあり、これは6.3V(0.9A)管、これは少なかった。
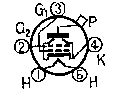
If 0.9A
アマチュア-には無くてはならぬ送信管。
大型拡声器の出力段にも使われた。